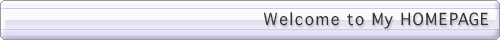Freepage List
■旅の迷路図
□北海道・東北地方

福島

岩手

山形

宮城

北海道
□関東地方

栃木

東京

千葉

神奈川

茨城
□甲信越・北陸地方

長野

福井

富山

石川

山梨

新潟
□東海地方

岐阜

静岡

愛知

三重
□近畿地方

和歌山

奈良

兵庫

大阪

滋賀

京都1

京都2

京都3
□中国地方

岡山

広島

島根

鳥取

山口
□四国地方

香川

愛媛

徳島

高知
□九州地方

大分

福岡

長崎

熊本

鹿児島

佐賀

宮崎
□海外
■映画館でみた映画

映画「あいうえお」順

映画「かきくけこ」順

映画「さしすせそ」順

映画「たちつてと」順

映画「なにぬねの」順

映画「はひふへほ」順

映画「まみむめも」順

映画「や」以降
■訪れた場所など

スポーツ観戦

競馬場観戦

訪れた城

訪れた国宝建造物

映画撮影地

登った山

訪れた八十八霊場
■些細な記載

些細な記事

桜百選

城百選

国宝建造物

国宝の塔など

W杯2002(一)

W杯2002(二)

W杯2006

W杯2010南アフリカ大会

W杯2014 ブラジル大会
全て
| カテゴリ未分類
| 映画館で見た映画
| レンタル映画
| 日本旅行記
| 香川旅行記
| 旅の迷路図
| スポーツ観戦など
| テレビで見た感想
| たわごと
| レンタル作品
| 小説や本など
テーマ: 京都。(6234)
カテゴリ: カテゴリ未分類
養源院(ようげんいん)
三十三間堂に行った後に養源院へいきました。
場所は三十三間堂の東側です。歩いてすぐの所ですので歩いていきましょう。
養源院は血天井で有名ですね。
門は小さいです。看板があり、紹介がされています。
門をくぐると、細い石畳が続いていました。独特の雰囲気がありますね。朝早かったので誰もいなかったので、入って良いのか迷いながら入ったのを覚えています。
そう思いながら、薄暗い玄関?をくぐると、おばさんが「そこで靴を脱いでください」と言われた気がします。500円の拝観料を払うと一枚の紙切れの『養源院略由緒』をいただきました。そう言っていると奥からもうひとりのおばさんが出てきて、奥へ行くように言われて「ここで待っていてください」と言われました。(正面玄関を真っ直ぐ入った所)
カセットのテープで説明が始まりました。そのテープが伸びているのかどうかは解りませんが、音がこもったり、声が聞き取りにくくなったり、声が大きくなったりして、雰囲気を出していました。その内に他の人も来ました。
奥の部屋から出ると廊下にでると、おばさんが棒を取りだして天井をさします。ん・・・・と見ると黒いシミが見えます。これが『血天井』らしいです。その説明を聞かなければ、たんなるシミに見えますが、人というのは不思議なモノで言われるとそう思いこんでしまうんですね(笑)。「ここが手、ここが胴体、ここが足」などと言っていた気がします。「これは指でもがいた後だと思います」と言われると指で引っ掻いたような後があります。人間て想像力豊ですね。
外に出ると、井戸らしきの所に人が覗いていた気もしますが、何のことか解らず「養源院」を後にしました。
☆☆☆ 養源院 うんちく ☆☆☆
文禄3年(1594)、豊臣秀吉の建立です。焼失し、元和7年(1621)、伏見城の遺構を移し再建されました。本堂の廊下の天井は血天井と伝えられます。伏見城が落ちた際、鳥居元忠らが自刃(じじん)した廊下の板が使われています。本堂の杉戸に描かれた白象や唐獅子(からじし)、キリンの絵は、俵屋宗達(たわらやそうたつ)の筆と伝えられています。狩野山楽(かのさんらく)の障壁画もあり、豊かな歴史をかいま見ることができます。
◆養源院略由緒◆
豊臣秀吉の側室淀殿が父浅井長政の追善の為、長政の二十一回忌に秀吉に願って養源院を建立し長政の従弟で叡山の僧であった成伯法印を開山とし、長政の院号を以って寺号としたのは文禄3年5月(1594)です。其後程なく火災にあい、元和7年(1621)徳川秀忠が夫人崇源院殿の願により伏見城の遺構を移建したのが今の本堂です。以来徳川家の菩堤所となり、歴代将軍の位 牌を祀って居ます。
『血天井』此の本堂の左右と正面の三方の廊下の天井は伏見城落城の時、鳥居元忠以下の将士が城を死守し、最後に自刃した廊下の板の間を天井として其の霊を弔ったもので世に血天井と称して名高い。
『宗達襖杉戸絵』此の本堂の襖(十二面)杉戸(八面)の絵は俵屋宗達の筆で、自刃した将士の英霊を懸める為に「お念仏、御回向」にちなんだ絵を画いたもので、杉戸には象や獅子や麒麟等の珍しい行動を画いて居り其の表現が奇抜で新鮮美に溢れ、又曲線美の効果 が素晴らしい。
『狩野山楽の襖絵』玄関の左の方に太閤秀吉の学問所とした牡丹の間があります。狩野山楽が牡丹の折枝の散らした図案的な襖絵を画いています。
『鶯張廊下』本堂の廊下は総て左甚五郎の造ったうぐいす張りで有名です。
『蛇が祀ってある社』門を入って右手に蛇の人形などが飾ってあります。
『井戸』門を入って左手にあります。のぞき込んでください。
伏見城と血天井についてはまた書きますね。(前にも言っていましたが・・アセアセ)
三十三間堂に訪れたら養源院も行ってみても良いと思いますが、寝ている時に思い出したら、天井が気になりますね。以外とインパクトがありますので、あまり思い詰めないでくださいね(笑)。
血天井は京都以外にも徳島にもあるみたいです。(見たことはありませんが)
三十三間堂に行った後に養源院へいきました。
場所は三十三間堂の東側です。歩いてすぐの所ですので歩いていきましょう。
養源院は血天井で有名ですね。
門は小さいです。看板があり、紹介がされています。
門をくぐると、細い石畳が続いていました。独特の雰囲気がありますね。朝早かったので誰もいなかったので、入って良いのか迷いながら入ったのを覚えています。
そう思いながら、薄暗い玄関?をくぐると、おばさんが「そこで靴を脱いでください」と言われた気がします。500円の拝観料を払うと一枚の紙切れの『養源院略由緒』をいただきました。そう言っていると奥からもうひとりのおばさんが出てきて、奥へ行くように言われて「ここで待っていてください」と言われました。(正面玄関を真っ直ぐ入った所)
カセットのテープで説明が始まりました。そのテープが伸びているのかどうかは解りませんが、音がこもったり、声が聞き取りにくくなったり、声が大きくなったりして、雰囲気を出していました。その内に他の人も来ました。
奥の部屋から出ると廊下にでると、おばさんが棒を取りだして天井をさします。ん・・・・と見ると黒いシミが見えます。これが『血天井』らしいです。その説明を聞かなければ、たんなるシミに見えますが、人というのは不思議なモノで言われるとそう思いこんでしまうんですね(笑)。「ここが手、ここが胴体、ここが足」などと言っていた気がします。「これは指でもがいた後だと思います」と言われると指で引っ掻いたような後があります。人間て想像力豊ですね。
外に出ると、井戸らしきの所に人が覗いていた気もしますが、何のことか解らず「養源院」を後にしました。
☆☆☆ 養源院 うんちく ☆☆☆
文禄3年(1594)、豊臣秀吉の建立です。焼失し、元和7年(1621)、伏見城の遺構を移し再建されました。本堂の廊下の天井は血天井と伝えられます。伏見城が落ちた際、鳥居元忠らが自刃(じじん)した廊下の板が使われています。本堂の杉戸に描かれた白象や唐獅子(からじし)、キリンの絵は、俵屋宗達(たわらやそうたつ)の筆と伝えられています。狩野山楽(かのさんらく)の障壁画もあり、豊かな歴史をかいま見ることができます。
◆養源院略由緒◆
豊臣秀吉の側室淀殿が父浅井長政の追善の為、長政の二十一回忌に秀吉に願って養源院を建立し長政の従弟で叡山の僧であった成伯法印を開山とし、長政の院号を以って寺号としたのは文禄3年5月(1594)です。其後程なく火災にあい、元和7年(1621)徳川秀忠が夫人崇源院殿の願により伏見城の遺構を移建したのが今の本堂です。以来徳川家の菩堤所となり、歴代将軍の位 牌を祀って居ます。
『血天井』此の本堂の左右と正面の三方の廊下の天井は伏見城落城の時、鳥居元忠以下の将士が城を死守し、最後に自刃した廊下の板の間を天井として其の霊を弔ったもので世に血天井と称して名高い。
『宗達襖杉戸絵』此の本堂の襖(十二面)杉戸(八面)の絵は俵屋宗達の筆で、自刃した将士の英霊を懸める為に「お念仏、御回向」にちなんだ絵を画いたもので、杉戸には象や獅子や麒麟等の珍しい行動を画いて居り其の表現が奇抜で新鮮美に溢れ、又曲線美の効果 が素晴らしい。
『狩野山楽の襖絵』玄関の左の方に太閤秀吉の学問所とした牡丹の間があります。狩野山楽が牡丹の折枝の散らした図案的な襖絵を画いています。
『鶯張廊下』本堂の廊下は総て左甚五郎の造ったうぐいす張りで有名です。
『蛇が祀ってある社』門を入って右手に蛇の人形などが飾ってあります。
『井戸』門を入って左手にあります。のぞき込んでください。
伏見城と血天井についてはまた書きますね。(前にも言っていましたが・・アセアセ)
三十三間堂に訪れたら養源院も行ってみても良いと思いますが、寝ている時に思い出したら、天井が気になりますね。以外とインパクトがありますので、あまり思い詰めないでくださいね(笑)。
血天井は京都以外にも徳島にもあるみたいです。(見たことはありませんが)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
© Rakuten Group, Inc.