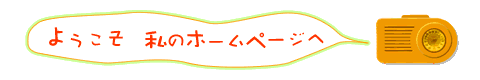「は」行の本
ひとりでも生きられる 瀬戸内寂聴評価★★★☆☆
なんだか肩に力入ったタイトルだなあ~と思った。で、実際入っていた。
昭和48年の刊行だからもうずいぶん昔の、瀬戸内晴美時代のものなのだが、いやはや、先進的(?)な考えですなあ。「妻の座」というものは空疎であり、恋愛をしないのは不幸だというメッセージ。今から30年前にこんなことを堂々というのはどんなもんだったんだろう。
その考え方がどうとかいう前に、気になったのは、情熱家独特のひとりよがりな様子。なんかさ、ときどきムキになってるような・・・。ん、でもまあ、世間の道徳に逆らって愛を貫いて、あることないこと書き立てられたんだから、こんな風な力説の仕方もありっちゃありかなっと、ちょっと冷めた分析をしてみる。
世間の道徳を良しとする人も、寂聴の姿勢を良しとする人も、これは多分に主観的な問題であって、自分に置き換えて考えてアツクなってしまいがちだ。だからこういう本は、あくまでも外側から客観的に眺めるのが賢いんではないかと思ったのでした。
蛇にピアス 金原ひとみ

題材は過激。スプリットタン(舌先を割って蛇のようにする)、背中一面の刺青、殺人・・・。もちろん、そうした過激な題材であれば、それだけ注目も集めやすいものだけど、そんな派手な道具で作品を飾り立てているのではなくて、その奥にある純愛みたいなものを強く感じさせてくれた。
主人公の女の子はいわゆるギャル系で、得体の知れない危険な男とつきあい、先のことも考えず酒とセックスの日々・・・。みたいな感じなんだけども、スプリットタンを完成させようとしたり、その男を本当に愛するようになったり、なんて、生きがいが出てきたんじゃん?ってところで、この主人公はやっぱり行き当たりばったりなので、生き急いでだんだん自滅していく感じ。
題材で面食らった人はどうも受け入れられないかもしれないしけど、この作品ではちゃんと純愛が書かれていると思う。終盤になって、いよいよ、そういうことかーって思ったとき(旬な作品なのでネタバレしないようにしとくw)、三人の主要登場人物の、それぞれの愛のかたちってもんが一気に目の前に出されて、この三人が全員いとおしく思えてしまった。やるな、金原ひとみ。第二の山田詠美って感じがしてる。
文明の憂鬱 平野啓一郎
評価★★★☆☆
平野びいきの私だけど、これはあんまり褒められないなあ。00年から02年にわたって書かれたエッセー集。とても論理的で教養を感じさせるんだけど、この発想はスゲエ!と思わせるものや面白味だとかいったものがほとんどない。さしずめ優等生クンの良くできた小論文といったところだろう。
宗教観・死生観なんかは広い視野から見ているんだなと感心したし共感もおぼえたけど、漫画やゲームについて鬱陶しい議論を展開しているところなんかは「まあ、要するに平野クンはあのテのものがキライなんでしょ」なんて一言で片付けてあげたくなっちゃう。わはは。
この一冊を読み上げて考えたのは、平野氏が小説の中でやたら難しい漢字や表現を使うのは、彼がかなりの文学オタクだからなんだろうなということ。ハメを外した才能溢れるタイプではないなあ。もうひとつは、徹底的に遊びが足りないということ。知識は膨大だし筆力もあるはずなんだからもったいないなあ。どこかで「学生の頃よく遊んだ」って言ってたけど、うそだろ。せいぜい友達とよく飲みに行ったっていうレベルなんじゃないか。悪いことなんてきっとしてないんだろうな。私と同い年だから今からやんちゃするってのも遅いな。
彼は「高瀬川」なんていう、かなり女の気持ちを掴むような傑作を書いてるからまだまだ期待してます。今回ケチばっかつけたけど、ファンです。いや、マジで。
放浪記 林芙美子
評価★★☆☆☆
自伝小説。ひとつの作品として読むと、それほど面白くないな。だって、同じことばっか繰り返してるんだもん(笑)。変な男にひっかかって、裏切られてはカフェの女給なんかをしてしのぎ、男が欲しい、ひもじい、の繰り返し(笑)。しかしすごくかわいいですよ、この人。失礼な言い方だが、よく歴史上の事件やら文豪の一節を引き合いに出してなにやら語っているけど、あんまり知性を感じないのだな(笑)。なんというか、女、というか、メス、という感じなのだ。ホンノウ、ホンノウ、生々しいまでのホンノウ。特に気に入ってるのは自分を私生児として生んだ母に対するこの一節。
-----
オッカサンに罪はない。(中略)女は子供をうむために生きている。むずかしい手つづきをふむことなんか考えてはいない。男のひとが好きだから身をまかせてしまうきりなのです。
・・・すばらしい。感動した。本気で。ここまで動物的、メスのニオイのぷんぷんする本は他にあるんだろうか。
バカの壁 養老孟司

評価★★★★☆
2003年度最大のベストセラーなどと言われている。話せばわかるなんて大嘘。客観的だとか公平だなんて自分でいうなっつーメッセージ。は~、イタイところつきますなあ。この本が売れるということは、まだまだ日本も捨てたモンじゃないね。これだけの内容をこれだけわかりやすい言葉で表現できる養老先生は、つくづく頭のいい方だと思う。
最も興味深かったのは、何らかの入力情報xに、脳の中でaという係数をかけて出てきた結果、反応がyというモデル y=ax という説明である。aという係数は本の中では「現実の重み」なんて説明されている。具体的には、aはおやじの説教をきかない子供。あんまり口うるい説教xが入力されると、子供が親の説教に対して脳内で係数0をかける。すると、説教の結果、子供は次の日も同じことをする。出力yも0になる。逆にaが無限大になると、出力に対して何でも言うことをきいてしまう。これの代表的な例は原理主義。この式にはマイナス10だとかプラス10だとかの数字を入れてアレコレ考えると面白い。私の過去の駄文に照らし合わせてみましょう・・・。エホバの証人である友人Kと、私の会話は、Kには聖書の創世記に係数100くらいかかっていて、私にも進化論に係数100くらいかかっている。互いに互いの考えには係数-100くらいかけちゃうもんだから、いつまでたっても平行線なのだ。
この本の中盤くらいまでは思わず「よくぞ言ってくれた!」なんてひざを叩きたくなる言葉がたくさんある。しかし、惜しむらくは中盤以降。なんだか養老先生がヒートアップしちゃってるように思えた。例えば、先生のいうところのバカな人のことを書くとき、少々言葉が荒くなったり、特定の人物のことを解説するのに、時々失礼になっちゃってる(長嶋さんに対してねw)。今の若者に対してほとんど明らかな勘違いをしているくだりもある。だからさあ、私の養老先生に対する係数もちょっとづつ下がってきちゃったわけよ。まあそれでもこの本は素晴らしいけどね。中盤までに養老先生に対する係数が低かった人は、ここから先、まったく頑固親父のウンチクを聞くみたいになっちゃったかもわからんね。言うべきことは大体中盤までで言い尽くしてる感があるから、後半は無くてもいいくらいの勢いだな。ちょっとだけ惜しい。
4teen 石田衣良

評価★★★★☆
14歳。4人の男子中学生の青春小説。仲良しグループ。友達。社会。エッチな話。そんな、中学生なりに考えていることを、瑞々しく描いている。しかし、石田衣良って40過ぎてるよな・・・。中学生の内面に関してどんな取材をしたんだろう。記憶に拠るところが大きいとしたら、なんて素敵な大人なんだろう。(いや、記憶に拠るところのウェートがどうであれ、この短編集を書けたことで十分素敵だ)。これ、民放でドラマ化したらすごくいいんじゃない?やってもらいたいなあ。
登場人物は上手に書き分けられている。特に感心したのは、早老症という病のナオトという少年の描き方だ。外見にもろに症状が現れる病気のナオトも、そのまわりの友達も、それからナオトに出会う人も、実に“イイカンジ”で接している。だから読み手は時々ナオトが病気なことを忘れるだろう。時にはその病気をジョークにする。こんなふうにイヤミのないジョークにできる空気、それこそが差別のない証拠だろうと思う。
この本の中では「大華火の夜に」が特に好きだ。なんて素敵な機転、思いやり。命を考えるエピソードってくさくなりがちだけどそんなことなくって、登場人物それぞれの純粋な想いがストレートに伝わってくる。
走れメロス 太宰治

評価★★★☆☆
ユウジョウって何だろうと思って、発作的に読みたくなった。中学校の教科書で出会って以来だ。まず、作品として見ると非常に無駄もなく登場人物の描き方は明快で後味の良い小説だ。メロスはとても単純で、真っ直ぐな性格を持っている。最初に親友を人質に差し出すと申し出るところでは一瞬ツッコミたくなったが、このメロスと友人は、信頼という点ということにおいての親友なのだと思ったら百%受け入れたいと思った。
私にも親友と呼んでいい友人が何人かいるが、メロスとセリヌンティウスのような一点の曇りもない信頼関係にある人はいるかどうか。多分あの人はそうだろう、と思い当たる人はいるがちょっと悩む。信頼はかなりしているが、都合で隠し事をすることもある。(疑うこと嘘をつくことはメロスが最も嫌いなことだ) だらしないところ、約束を破るところ、そんなところがある人も“親友”の中にはいる。それでもその人と一緒にいると安らぐから、得るものが大きいから“親友”と呼びたい。メロスとセリヌンティウスのようなカラッと晴れ渡った関係とまではいかなくとも(というか、晴れすぎていて怖い。もっともこれは物語なのだが)、信頼って美しくて清潔なものなのだと思った。
ぼくは勉強ができない 山田詠美

評価★★★★☆
時田秀美くんのカッコ良さといったら、なんだ。もし、彼のような高校生が目の前にあらわれたら、おねいさんは年の差なんかかまわず、もうゾッコン(死語)だろう。この本、この年齢になってから読んでヨカッタと思った。この短編集に書いてある内容は、どれもいつかどこかで一度は考えたことのあるテーマだった。それを私よりも純粋な高校生の秀美君の目を通して、もう一度考えてみた。
とりわけ面白かったのは「あなたの高尚な悩み」だ。実は空腹と虚無は象とアリくらいの隔たりがある。あ、もちろん私は間違えてはいないよ?空腹が象で、虚無がアリよ?そう、それでいいの。高尚な悩み事を抱えていても、そんなときお腹が空いていたら、そんなことかまってられないの。空腹は高尚な悩みを凌駕する。ね?びっくりした?でもコレって真実じゃない?お腹空いたり、アタマが痛いときとかに、となりで難しいコトをウンチクされたら、殺意をいだきませんか?言いすぎ?笑。その他にも色んな明言が宝石のようにちりばめられている。
ユニークな祖父と母に育てられた秀美くん。羨ましいくらいこの家庭は素敵だ。複雑な家庭事情って何なんだろう。普通とちがうって何?普通って何?そういう価値観の生まれる管理教育の功罪。あたりまえに過ごしてきたかもしれない管理教育時代で、どんな価値観が形成されてきたのか。見なおしてみたい。
ベッドタイムアイズ 山田詠美
評価★★★★☆
黒人兵スプーンと日本人少女キムの愛の物語。それもとても動物的にふたりはひかれ、愛し合う。お互いはお互いについて語り合う事はなく、まさに本能で愛し合っているのだ。キムはスプーンの本名すら知らない。ただ激しいセックスがあれば、このふたりには十分なのである。この物語のラスト、スプーンは軍の機密を売ろうとしたという罪で逮捕される。(もちろん、キムはスプーンがそんなことをしようとしてたなんて知らない。)その時になってはじめてキムはスプーンのことを知りたいと思う。逮捕の15分前、彼女は「時間がないわ!」と叫ぶのである。
山田詠美はこの作品で、「人それぞれの Crazy about you について考えた」のだそうだ。私はセックスアピールだけで男に惚れたことなんて、ない。どっちかというと、あれこれ好きになった理由を考えてしまうほうである。だから、こんな風に動物的にひかれあうことから始まる恋愛には一種の嫌悪を感じてきた。でもこの作品を読んでちょっと変わった。魂の愛がそのあとからついてくるんでも、いいんじゃない?Crazy about you ・・・それはすべてを超越するんだろうなってこと。私たちが 感じる生き物である以上は・・・。愛する人の一挙一動までもいとおしいと思うような恋をしたことがありますか?そんなとき、愛する人の色気のある仕草をみて、すべてがどうでもよくなることがありませんか?自分がナニモノであるか?どこのガッコウを出て、どこのカイシャに勤めていますか?どんな本が好きですか?音楽の趣味は?そんなことの前に Crazy about you なのである。
漂着物事典 石井忠
評価★★★★☆
これ、かーなりイケてます。一見、真面目な本なのです。いや、ある意味真面目な本であることは確かなのですが・・・。とにかくもう、吹き出さずにはいられません。筆者は海浜漂着物文化論(この時点でアヤシイ?)が御専門の学者さんです。本書では事典形式で海での漂着物について解説されています。その漂着物の例というのがですね・・・魚介類やら歴史を彷彿させる品々やらもあるんだけど・・・カボチャ、コンドーム、殺虫剤の容器、貯金箱、水中メガネ・・・ なんてのがあるんですよ(爆笑)。例えばカボチャなんかでは、漂着する理由として「農家から川に捨てられ海へ漂着したものだろう」という分析のあとに、「もったいないので持って帰ろうとするが、中は腐れている」 の一文が(笑)。そして、カボチャは何科で原産地はどこという真面目な話しに入り、また最後に カボチャに関する俳句でこの項目は終わる。う~ん素敵(笑)。 事典と言うよりも、この先生のエッセーに近いかも。一家に一冊、おすすめです。
微笑みながら消えていく 銀色夏生
評価★★★★★
衝動買いしてしまった。美しい写真と美しい詞。恋の切なさをこんなに素敵に伝える本を、私は他に知らない。いや、それは言い過ぎかな?俵万智と拮抗する・・・とでも書いておこうかな?ただ、俵万智のものは大人の女性らしく、静かにじわじわとしみわたってくるのが多いけど、この本はレイアウトに凝り、視覚に訴えるためか、言葉が突き刺さってくる。なんだかドキドキするような、微妙な緊張感に満ちている。この本をひらけば、いつでも純粋な気持ちにもどれそうな気がする。
話を聞かない男、地図が読めない女 アラン・ピーズ+バーバラ・ピーズ

評価★★★☆☆
ちょっと前の大ベストセラー。文庫が出たので読んでみました。男と女は脳が違うということを科学的データを用いてわかりやすく解説。どっちが優れている云々ではなく、男と女がただ“違う”ということ。そんなメッセージもとても好意的に受け取った。なるほどこのメッセージが頭の片隅にあれば、男女間が円滑になるだろう。私はかつて、男女は本能的に違うという考えを持っていて、それがかの田嶋陽子先生の話やら本やらで少しフェミニズムのシャワーを浴び、そしてまたこの本で考えがひっくり返った感である。(というのは言いすぎかな。田嶋先生もこの本も私にとって100%ではないのだから。)先日「結局社民党も男社会だった」と言って離党した田嶋先生だが、この本に拠れば政治などは男性の方が向いている、女性はただ関心が薄く、他にもっと向いた役割がある、そしてキャリア志向の高い女性は自然と所謂“男性的”になるのだという。つまり、客観的に男っぽくなった社民党の人ややり方の断片を見て田嶋先生は嫌気がさしたのではないかしら~とボンヤリ考えている。(人のことを勝手に憶測するのは失礼なのだけどちょっと許してね。)***さてこの本を一言で表すなら「でぶっちょ」である。同じことを何度も何度も繰り返して述べているような気がした。この本を3分の1くらいスリムにしても十分に肉付きのある良書になると思う。ただ説得力やらを上げるにはああいった手法(?)がいいのかな。ま、とにかく、多くの人に読んでもらいたい良書です。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0941 花まんま
- (2025-11-27 00:00:14)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- スタンフォードの自分を変える教室
- (2025-11-27 03:39:17)
-
© Rakuten Group, Inc.