PR
カレンダー
サイド自由欄
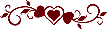

リュキア伝説・本館
☆完結しました☆
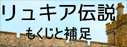

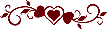

真魚子さまの絵

エメラルドeyesさんのブログ
『ねこマンサイ』
で紹介していただいた、
ふろぷしーもぷしーの過去日記
『迷い犬を保護してしまいました』2008.6.19~10.7

『いっしょに歩こう!』
2008.12~2009.1
キーワードサーチ
2024.10
2024.09
2024.07
コメント新着
さびしい赤い空の下に、ひとり呆然と立ち尽くすクロ ――― その姿は、あまりにも小さくて、哀しくて、このまま見放すことなんかとうていできないと思った。
混乱して、たまこは誰にともなく叫んだ。
「いや! こんなさびしいところにクロちゃんを一人で置いていっちゃうなんてできない!」
小さな子どものように、大声で泣き出したたまこの涙を、ミケが優しくぬぐって微笑んだ。
その笑みは、まるで、慈愛に満ちた母猫のようだ。
「珠子お嬢さま、・・・お嬢さまならきっとそうおっしゃるのではないかと思いました。 それではお嬢さまの代わりにわたくしがここに残りましょう。 思えば十二年前のあの雨の日、お嬢さまの優しいお手に拾われてから今日まで、わたくしは十分にお嬢さまに慈しんでいただきました。 猫として、本当に幸せな一生でございました。 もうこの世で望むことは何一つありません。 ですから今度はわたくしが、あの無垢な子猫に、慈悲の心を教えてあげましょう。 大丈夫、いえ、むしろわたくしのほうがお嬢さまよりうまくできるかもしれませんよ。 同じモト猫同士。 そして守り猫さまもわたくしにお力添えくださっていますからね」
振り仰げば、守り猫の示す空から、一筋の清らかな光が、地上に向かって差し込んでくる。
いや、単なる光ではない。
よく見ればそれは、光に包まれてゆっくりと地上に伸びてくる、ほそい階段なのだった。
はっとした。
「ミケ、・・・まさか、あたしをおいて、クロと一緒に天国へ行っちゃうつもりじゃないでしょうね?! だめよ! そんなの絶対許さないから!」
たまこは狼狽してミケを捕まえようとしたが、ミケは、たまこの手をするりとすり抜けて、クロのほうへと駆け出してしまった。
「行っちゃだめ! 帰ってきて! ミケ! お願い!」
泣きながら懇願したが、ミケはちょっとたまこのほうを振り向いて微笑んだだけで、立ち止まろうとはしなかった。
嬉しそうに駆け寄ってきた黒い子猫に優しく頬ずりする、その姿はまるで本当の親子のようだ。
仲睦まじげに寄り添って、ミケがクロを光の階段のほうへと導いていく。
並んでゆっくり階段を上り始めた二匹の姿が、だんだん白い光に包まれていく。
白い光が強さを増して、まぶしくてとうとう目を開けていられなくなったとき、たまこは、もう二度とミケの姿を見ることはできないと悟った。
真っ暗な悲しみのふちへとつき落されるような気がして、たまこはそのままマサキの腕の中に倒れこみ、気を失った。












