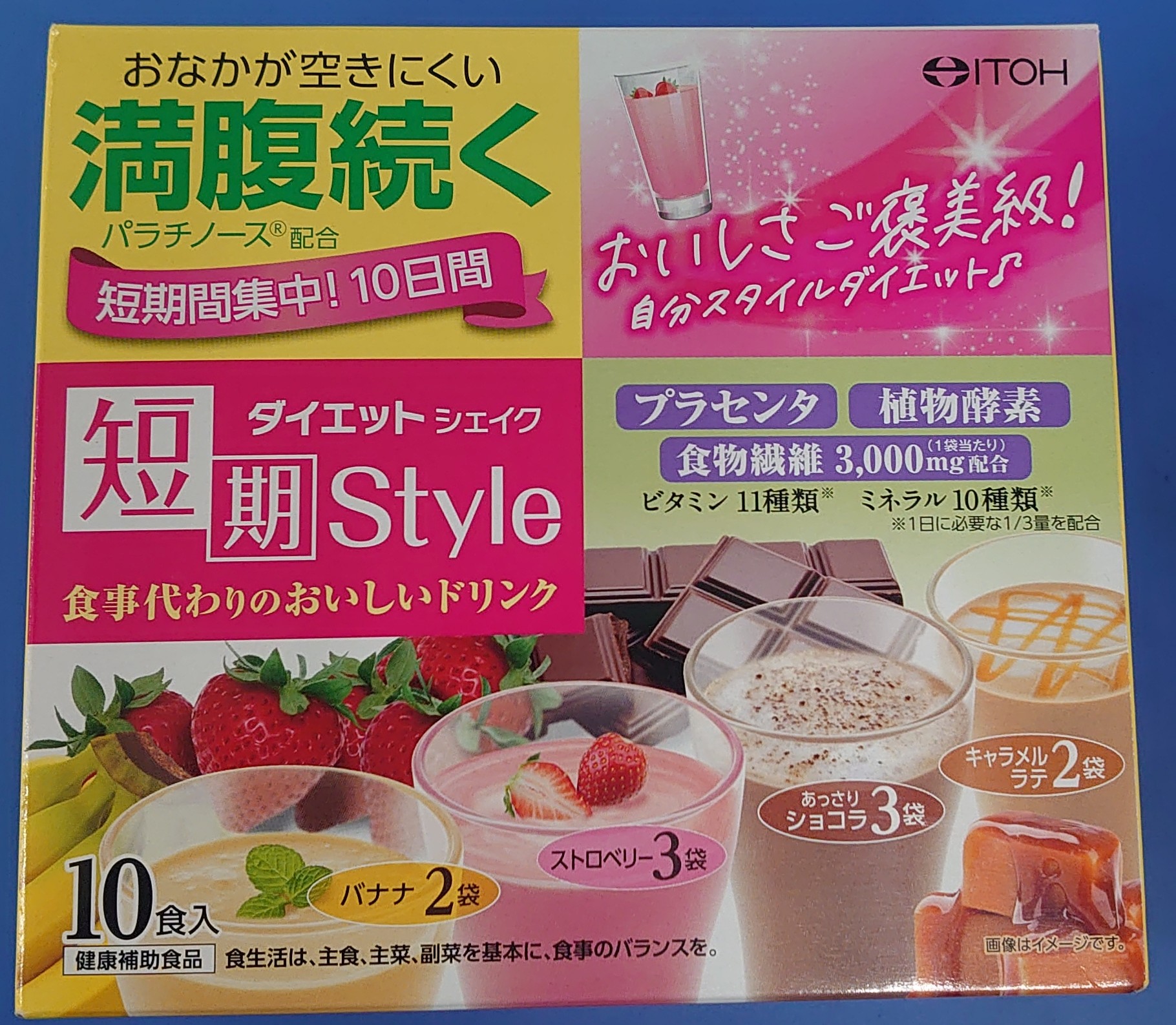戦後の日本語起源論の展開
村山七郎は、『日本語の起源』(1973)において、ポリワノフ説を援用する形で、日本語おける南方語的要素の重要性と混合語的性格を強調した。
「 私は、ウラル・アルタイ説論者の考えが根本において誤っているとは思いませんが、不十分であると思います。ウラル語族(フィン・ウグル語派とサモエード語)の言語とアルタイ系言語が同系であることは、よく主張されるのですが、証明されていません。J・ラムステットやN・ポッペ(フィン・ウグル言語の研究をしてからアルタイ言語学を始めました)のように、フィン・ウグル言語に深い理解があるアルタイ学者は、ウラル・アルタイ説に賛成しない人が多いようです。私は、日本語はアルタイ系言語と関係があり、とくにツングース・満州諸語と親縁関係がある、という結論に達しました。
他方、(中略)日本列島でも南島系の言語が、おそらく朝鮮半島をへて到来したアルタイ系の民族、とくにツングース系民族-その数は土着人に較べて問題にならないくらい少なかったでしょう-の言語によって文法的につくりかえられ、古代日本の動詞活用形式や名詞の格変化や語順がアルタイ的なものになったのでしょう。」
このように、南島系の基層言語にアルタイ・ツングース言語が流入して今日の日本語が形成されたとの説を展開した。
大野晋は、自説のタミル語説をベースに高句麗語説を取り込んだ。
参考文献
© Rakuten Group, Inc.