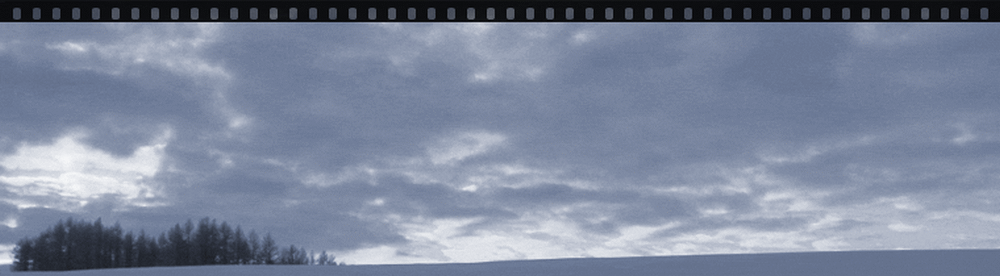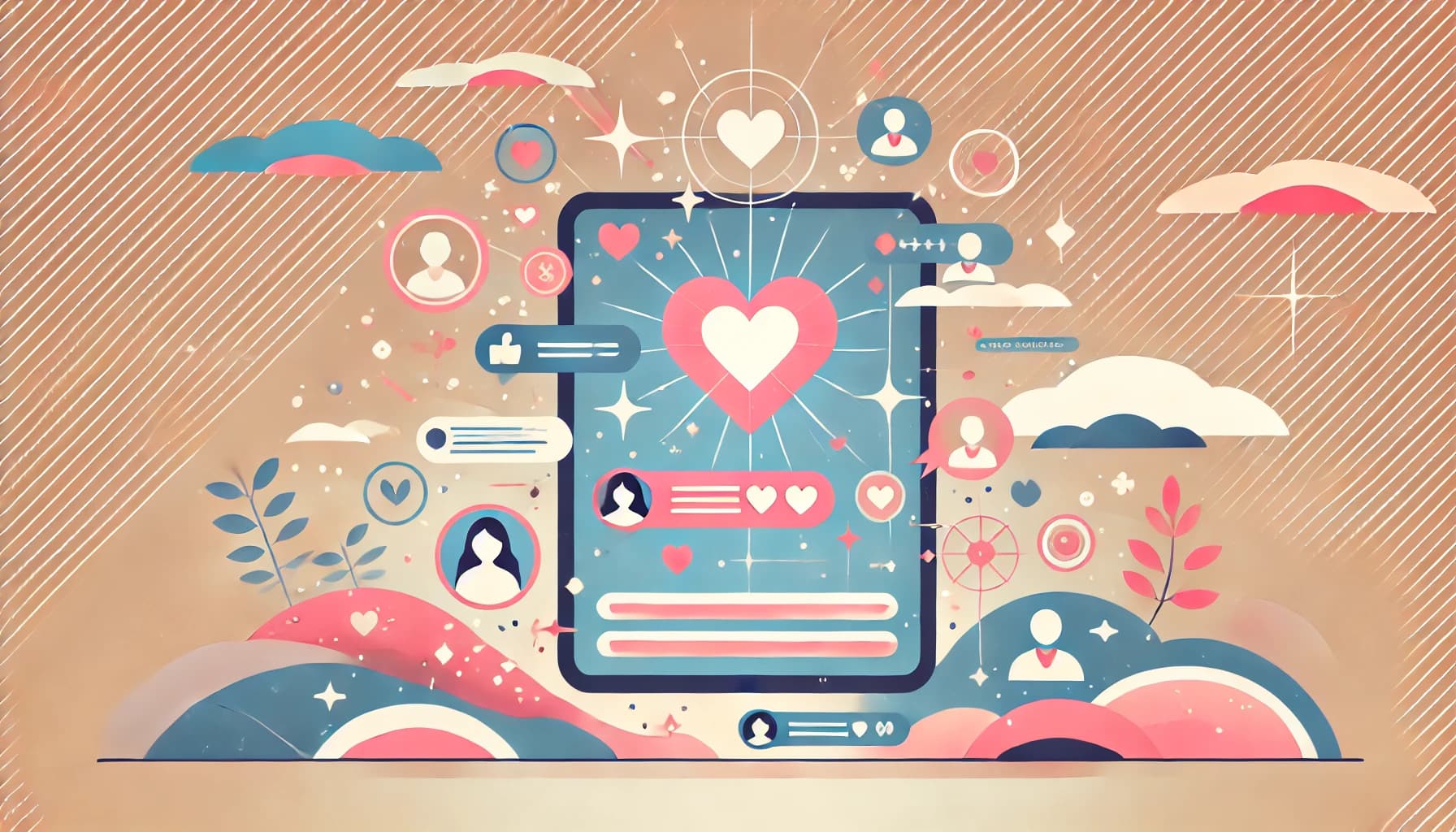全189件 (189件中 1-50件目)
-
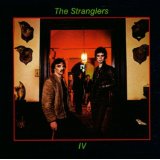
Stranglers "Rattus Norvegicus"
1970年代の半ば過ぎ、打上花火のように一瞬の煌きを放ったロンドン・パンク・ムーヴメントの中にあって、未だにしぶとく生き続ける Straglers の記念すべき 1st アルバムにして、(4th アルバム "The Raven" 以降の耽美的な作風に対する是非はともかく)初期の暴力的なイメージを決定付けた重要作。所謂「パンク」と言う概念とは相容れなさそうな、メンバー全員が奇妙なメイクを施した隠微なスリーヴ、良きにつけ悪しきにつけ Doors と比較されることになる全編で大胆にフィーチャーされたオルガン、更にそのオルガンをも圧する迫力で全体を支配する「リード・ベース」とまで評されたぶっといベース。ギターの Hugh Cornwell は大学で博士号を取得していただの、ドラマーの Jet Black に至ってはデビュー当時既に 30 代後半で起業家であった等々。「パンク」としては異色、異質。と言うより、「パンク」として語ってはいけなかったのかもしれません。一語一語を対象に叩き付けるように言葉を吐き出す、初期の代表作 "Sometimes" や "Hanging Around" 、気怠い雰囲気の Stranglers 流ブルース・ナンバー "Princess Of The Streets"、サックスをフィーチャーしシングルとしてもヒットした "(Get A) Grip (On Yourself)"、プログレ的な展開の中で「荒廃した世界で生き残る手段はラットと交わることだ」と歌われる "Down In The Sewer"。厚化粧の Sex Pistols "Never Mind The Bollocks" とも、勿論デモ・テープかと勘違いするほどにペラペラだった The Clash のデビュー作とも違う特異な音。攻撃的なありながらポップ、どこかしら捻くれたユーモア感覚も。余計なお節介は承知の上で、ベースやオルガンに比べて語られることが余りないような印象がある Hugh Cornwell のギターも、Stranglers の音を構成する重要で不可欠なピースです。【Track Listings】01. Sometimes02. Goodbye Toulouse03. London Lady04. Princess Of The Streets05. Hanging Around06. Peaches07. (Get A) Grip (On Yourself)08. Ugly09. Down In The Sewer : (a)Falling ~ (b)Down In The Sewer ~ (c)Trying To Get Out Again ~ (d)Rats Rally
2013.05.12
コメント(0)
-
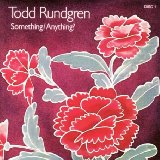
Todd Rundgren "Something/Anything?"
稀代のポップ職人 Todd Rundgren の、3 枚目のソロ・アルバムにして初めての 2 枚組アルバム。なにがしかのコンセプトやテーマがあるわけではないらしく、ヴォーカル、ギターは当然として、その他の楽器の演奏からプロデュースに至るまで全ての作業を独りでやる、と言う我々凡人には思いもつかない意図を基に制作を開始したようですが、結果的に演ってみたら良い曲が沢山出来たので 2 枚組にしてみました、とでも言った感じでしょうか。なにしろいきなりの "I Saw The Light" です。Todd の代表曲でもあり、最早ポップ・クラシックと呼んでなんの差し支えもない名曲がオープニングです。以降、およそ 90 分間に渡ってこれでもかと言う程に美しいポップ・ソングを惜しげもなく披露してくれています。"I Saw The Light" と双璧を成す Nazz 時代の "Hello It's Me" の再演あり、ユーモラスなインストゥルメンタルあり、"Torch Song" や "Dust In The Wind" と言った泣けるバラッドあり、Todd にしては珍しい比較的ヘヴィーなロック・ナンバー "Black Maria" や "Little Red Lights" があり、キラキラしたメロディーが並ぶ中で気だるい雰囲気のヴォーカルが印象的な "I Went To The Mirror" があり、、、等々ヴァラエティーも豊富で飽きさせません。こんな調子で全 25 曲、お腹一杯でもう沢山、となりそうなのに何故かそうはならない。やたらに長い楽器のソロ・パート等で無駄に(?)引き伸ばすことなく、3 ~ 4 分程度に楽曲をコンパクトに纏め上げている辺りが一因かな?。この曲もう少し聴きたかったなぁ、と思わせるぐらいの按配と言うか、匙加減がポップ職人たる所以でしょうか。【Track Listings】- Disc 1 - 01. I Saw The Light02. It Wouldn't Have Made Any Difference03. Wolfman Jack04. Cold Morning Light05. It Takes Two To Tango (This Is For The Girls)06. Sweeter Memories07. Intro08. Breathless09. The Night The Carousel Burned Down10. Saving Grace11. Marlene12. Song Of The Viking13. I Went To The Mirror- Disc 2 - 01. Black Maria02. One More Day (No Word)03. Couldn't I Just Tell You04. Torch Song05. Little Red Lights06. Overture : Money (That's What I Want) ~ Messin' With The Kid07. Dust In The Wind08. Piss Aaron09. Hello It's Me10. Some Folks Is Even Whiter Than Me11. You Left Me Sore12. Slut
2013.04.24
コメント(0)
-
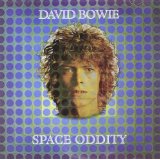
David Bowie "Space Oddity"
念願の 1st ソロ・アルバムがセールス的に惨敗を喫した David Bowie が、レコード会社を移籍して再起を賭けて放った 2nd アルバム。アポロ 11 号が成し遂げた「人類にとっての大きな飛躍」に冷水を浴びせるような内容の(勇躍地球から旅立ったトム少佐が、妻への愛の言葉を残して宇宙の孤児となってしまう)タイトル・トラック "Space Oddity" がとにかく強烈。David Bowie の初期のイメージを決定付けた楽曲であることは確かなのですが、こんな重苦しい作品をシングルに持ってくると言うのは、当時としては危険な賭けでもあったのではなかったでしょうか。なにしろ世界中が人類初の月面着陸のニュースに興奮している最中だったのですから。結果は、勿論 Bowie の思惑通り。後々までライヴでの重要なレパートリーになるだけあって、今聴いても古臭さをまったく感じさせません。しかし、そんな楽曲の完成度以上に、10 年後に自らオチ("Ashes To Ashes") をつけなくては気がすまない辺りに、David Bowie の凄さを感じてしまいます。オープニングの印象が強過ぎて、アルバムの全体像がやや見え難いのですが、サイケデリック風味のフォーク・ロックを基調に、"Letter To Hermione" や "An Occcasional Dream" のような美しいメロディーのバラッドがあり、ヒッピー・ムーヴメントへの醒めた視線を感じさせる "Cygnet Committee" や "Memory Of A Free Festival" と言った長尺の物語があり、とバラエティーに富んだ作品集。グラム・ロック期の華やかで、如何にもな「ロック」な音を期待すると肩透かしを食らうでしょうが、実質的な 1st アルバムと考えれば及第点以上の内容ではないでしょうか。【Track Listings】01. Space Oddity02. Unwashed And Somewhat Slight Dazed03. (Don't Sit Down)04. Letter To Hermione05. Cygnet Committee06. Janine07. An Occasional Dream08. Wild Eyed Boy From Freecloud09. God Knows I'm Good10. Memory Of A Free Festival
2013.04.17
コメント(0)
-

Monsoon "Third Eye"
1983 年、イギリスのニュー・ウェーヴ・シーンに忽然と姿を現した、Sheila Chandra、Steve Coe、Martin Smith の 3 人から成るエレクトリック・ポップ・ユニットの最初にして唯一のアルバム。見る者の心を射竦めるするどい視線。その意志の強さを物語っているかのような Sheila Chandra の瞳をフィーチャーした、鮮烈なデザインだけで即買いの一枚でした。肝心の中身は、と言えば、"Shakti" や "Kashmir" と言ったタイトルからお察し頂けると思いますが、(昨今では取り立てて目新しくもなくなりましたが)欧米風のダンス・ビートにエスニックな意匠を施したポップ・ミュージック。ここではインドの伝統的な楽器、シタールやタブラ、タンブーラ等が使われています。私ぐらいの年代だと(と言っても、後追い世代ですけど)、Beatles の "Within You,Without You" や Rolling Stones の "Paint It,Black" あたりが思い浮かぶんじゃないでしょうか。所謂「ラガ・ロック」ってヤツですね。サイケデリック・ミュージックとかフラワー・ムーヴメントと呼ばれたものの中でも一際「キワモノ」ぽかった性か、ひとつのジャンルとして特に根付くこともなく一過性の流行で終わってしまいました。それが 10 年以上の歳月を経て、なんの前触れもなくイギリスに現れたのです。勿論、60 年代当時の音がそのまま再現されたわけではありませんが、シタールの不思議な響きが結構気に入っていた私は、妙な懐かしさを感じつつも、すぐに夢中になっていました。1 曲目 "Wings Of The Dawn" の、正に手付かずで穢れのない夜明けの美しさを歌い上げる、Sheila Chandra の清廉な歌声でいきなりノック・アウト。続く、Beatles のカヴァーたる "Tomorrow Never Knows"。この曲のカヴァーでここまで清々しいものは聴いたことがない(笑)。Monsoon のオリジナル曲だと言い張っても通りそうなぐらい。シングルとしてもヒットした "Ever So Lonely" や本作随一の派手な作りの "Shakti" などもそうですが、シタールやタブラはあくまでスパイス。学究的に、或いは趣味にのめりこんで深く作り込むことはせず、Sheila の伸びやかな歌声を生かしたポップ・ミュージックに徹したところが良い結果を生んだのではないでしょうか。この後、Sheila Chandra は Monsoon の名を捨てて、よりトラディショナルな音へと向かうのですが、サポートするメンバーは、、、Steve Coe と Martin Smith。とすると、この作品は?【Track Listings】01. Wings Of The Dawn (Prem Kavita)02. Tomorrow Never Knows03. Third Eye And Tikka T.V.04. Eyes05. Shakti (The Meaning Of Within)06. Ever So Lonely07. You Can't Take Me With You08. And I You09. Kashmir10. Wathers Of The Night- Bonus Track -11. Ever So Lonely
2013.03.06
コメント(0)
-
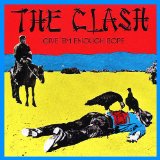
Clash "Give'em Enough Rope"
赤と黄色のコントラストも鮮やかなスリーヴが印象的な Clash の 2nd アルバム。但し、そこに描かれている構図は、ハゲタカに無残にも啄ばまれるカウ・ボーイの死体を無表情に見つめる馬上の人民解放軍兵士?と言うなにやら謎掛けめいたもの。果たして、その心は。1 曲目からエナジー全開、ハードで金属的ですらある圧倒的な音圧に驚かされました。スネア一発で始まるイントロからダブっぽい処理のエンディングまで、アッと言う間の 4 分弱。デビュー作でのスッカスカの音から突然の変化。冒頭の 3 曲のカッコ良さには抗いがたいものを感じつつも、私の周囲では結構賛否両論であったことを覚えています。なにしろ本国イギリスでは、彼らのテーマ・ソングとでも言うべき "Clash City Rockers" や、初期 Clash を語る上で外す事の出来ない "(White Man) In Hammersmith Palais" などのシングルがリリースされていたにもかかわらず、我が日本ではシングル盤の発売はなし。1st アルバムからまったく音沙汰のない状況であったわけですから、いきなりこんな作品を聴かされた日には戸惑いが先行しても仕方なかったのではないでしょうか。戸惑いの最たるものは、"Julie's Been Working For The Drug Squad" でフィーチャーされている軽快なピアノや、"Drug-Stabbing Time" におけるサクソフォンの起用等、表面的な音の変化に対するもの。つまりは、純然たるパンク・バンドからオーセンティックなロック・バンドへと「転向」しようとしているのではないか、と言うある種青臭い感情だったような気がします。私も Sex Pistols に始まり、この Clash、Damned、Jam などパンクには夢中になり、当時お決まりの「社会」がどうの「政治」がこうのと小賢しいことをしたり顔で仲間内で議論したりはしましたが、ファンダメンタリスティックな部分は何故か無縁で、本質的には純粋に音楽として楽しんでいたお気軽ファンだったのでした。その性か、後の "London Calling" は勿論のこと、"Sandinista!" も大のお気に入りで、むしろ次々に Clash から離れて行く人たちを不思議にすら思っていたほどでしたが。先に書いたように "Safe European Home" ~ "English Civil War" ~ "Tommy Gun" の 3 連発は文句なし。Topper Headon のダイナミックなドラムが光ります。その一方で、Mick Jones のちょっと情けない歌声が切なくも物悲しい "Stay Free"、これまでの外に向けて牙を剥く攻撃的な表情から一転、教え諭すような柔らかさを感じさせるラストの "All The Young Punks (New Boots And Contracts)" など、以降の更なる「変化」を予感させる作品も。当時も今も彼らの作品の中では相対的に影が薄いようにも感じるのですが、私的には1st 同様に「傑作」認定なのです。【Track Listings】01. Safe European Home02. English Civil War03. Tommy Gun04. Julie's Been Working For The Drug Squad05. Last Gang In Town06. Guns On The Roof07. Drug-Stabbing Time08. Stay Free09. Cheapskates10. All The Young Punks (New Boots And Contracts)
2013.02.27
コメント(0)
-

dip "dip"
元 Dip The Flag のヤマジカズヒデ率いるサイケデリック・ロック・トリオの 1st アルバム。ソロ・アルバムでは Neil Young の "Helpless" や "After The Gold Rush" 、或いは Canis Lupus の "天使" をカヴァー、メジャー第 1 作となる次作 "I'll slip into the inner light" では Pink Floyd の影響も窺わせるなど、音楽的な引き出しは結構広そうですが、まだまだバブル景気の残滓が見え隠れしていた時代背景もあってか(?)、マニアックに閉じこもることなくポップに纏め上げているところが良い。また、一見装丁ミスかと見間違う歌詞カードは、指定に沿って切り込みを入れて折り畳むと正常に読めるようになる。そんなちょっとした遊び心のある仕掛けも「ポップ」な印象を助長しています。次作で再演されるサイケデリックな "lilac accordion"、爆音とともに僅か 3 分弱を怒涛の勢いで駆け抜ける "稀有" 、一転、静かな波間を漂うようにゆったりとした "クロウル"、ノイジーなギターをバックに叙情的な表情を見せる "セル" と、デビュー作にして全くの捨て曲なしながら、実は本作のハイライトはシームレスに演奏される Velvet Underground の "here she comes now" と Beatles "tomorrow never knows" の 10 分に亘る(一応トラック・マーカーは分かれていますが)メドレーでしょう。絶叫調のヤマジのヴォーカル、テープの逆回転等も織り交ぜた暴走気味にも思える音の洪水が快感。更に、圧倒的なノイズの余韻に浸りつつも昂ぶった神経を慰撫するかのような、打ち込みのアンビエント・ナンバーで幕を閉じる辺りも秀逸。【Track Listings】01. lilac accordion02. 稀有03. クロウル04. セル05. here she comes now06. tomorrow never knows07. clip
2013.02.17
コメント(0)
-
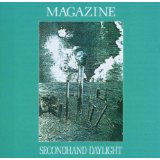
Magazine "Secondhand Daylight"
元 Buzzcocks のリード・シンガー Howard Devoto 率いるポスト・パンク・バンド、Magazine の 2nd アルバム。前作に引き続きなんとも不気味なスリーヴ(荒野の生首!?)、聴き手の不安感を煽るようなイントロに導かれて始まる、アルバムの冒頭を飾るにしてはあまりにも重過ぎる "Feed The Enemy"、或いはアルバム・タイトル「中古の陽光」とは一体何を意味しているのか。まだまだパンクの余燼がそこかしこで燻っていた 1979 年には、少し敷居が高い作品だったのかもしれません。とりわけデビュー・シングル "Shot By Both Sides" における、既製の価値観をすべてなぎ倒していくような圧倒的なまでの疾走感を期待していた向きからは、シンセサイザーを大幅にフィーチャーしたプログレ的な音作りは不評を買ったようです。ビートの利いたリズミカルな作品と、ミディアム~スローな重々しい楽曲がほぼ交互に配されるような構成なのですが、前者が逆にアルバム全体の沈鬱とも言えるイメージを助長しているかのような印象を与えさえします。なにやらネガティヴなことばかり書いていますが、私にとって本作は Magazine の最高傑作であると共に、Joy Division の "Unknown Pleasures" 、Public Image Limited "Metal Box [Second Edition]"、Pop Group "Y" 等と並んで、1970 年代後半の音楽シーンを語る上において決して外す事の出来ない最重要作のひとつでもあるのです。しかしながら世間の評価は何故かさほどでもないようで。先ほど列記したバンドと比較してもなんら遜色のない高い音楽性を有していると思うのですが、少なくともこの日本においての知名度の低さは、Radiohead 絡みで多少とも話題に上ることがあるとは言え、如何ともし難いものがあります。やっぱり Howard Devoto の粘っこい歌唱法と、特異な風貌(失礼)がネックなのでしょうかねぇ。【Track Listings】01. Feed The Enemy02. Rhythm Of Cruelty03. Cut-Out Shapes04. Talk To The Body05. I Wanted Your Heart06. The Thin Air07. Back To Nature08. Believe That I Understand09. Permafrost
2013.02.09
コメント(0)
-
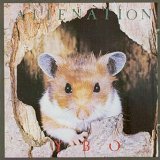
YBO2 "Alienation"
プログレッシヴ・ロックを初めとして(我が国に於いては)比較的マイナーなヨーロッパのロック・ミュージックの紹介者として登場した音楽雑誌『フールズ・メイト』の初代編集長、北村昌士率いる YBO2 の 1st アルバム。実際は Kyon2 と同じく末尾の「2」が、べき乗のように小さく表記されており、「イボイボ」、乃至は「ワイ・ビー・オー・ツー」と呼んでいましたが、正確なところは不明。まるで調和することを DNA が拒絶しているとでも言いた気な程に神経を逆撫でするヒステリックで不安定なヴォーカル、これでもかと言うぐらいに手数の多い吉田達也のドラムス、あたかも King Crimson のカヴァーを演奏する This Heat とでも言った趣のノイズとメロトロンが織り成すアグレッシヴなサウンド、或いは病的なメイクに女装といった倒錯的な北村昌士の外見などは勿論のこと、1985 年に登場するや否やわずか数年の間に 12 インチを含むシングル 5 枚、2 枚組を含むアルバム 5 枚にヴィデオ 2 本をリリースすると言う常軌を逸した過剰な露出戦略(?)など、話題には事欠きませんでした。ある意味インディーズ・シーンが生み出した稀有なトリック・スターとでも言った存在だったのかもしれません。CD をスタートさせると、小さなヴォリュームでなにやらほのぼのとしたメロディーが耳に飛び込んできます。確か、これは "Mickey Mouse Club March"。と思うまもなく突然ギター、ベース、ドラム、それにメロトロンが渾然一体となった怒号のような音の奔流に飲み込まれてしまいます。これは単に静と動を極端に対比することで我々を驚かそうとするハッタリなのか。もしくは、エンターテイメント界において今なお隠然たる影響力を持ちながら無垢な仮面で真実の姿を覆い隠すディズニーに、"Amerika" と言う「正義」の国家を表象させているのでしょうか。そして、北村昌士が口にしているのはアメリカの「良識」、Simon & Garfunkel の "Scarborough Fair"、、、などと深読みしている時点で彼らのトリックに引っ掛かっているのか。彼らの 1st シングル "ドグラ・マグラ" は、夢野久作の同名作から阿呆陀羅経の部分をそのまま引用したものでしたが、本作における 2 曲目もそれと同じく久作の『猟奇歌』からの引用。4 曲目 "To Be (帝国の逆襲)" では Steppen Wolf の "Born To Be Wild" の歌詞が切れ切れに聴き取れます。ポスト・パンク/オルタナティヴのうねりが北村昌士のプログレ趣味と奇妙に交差したその刹那、引用と剽窃の上に産み落とされたノイズの伽藍。1988 年にリリースされた 2 枚組大作 "Pale Face,Pale Skin" は YBO2 の「音楽」的ピークだったのかもしれませんが、私自身は本作に代表される、どこかしらまがい物めいた雰囲気を漂わせていた初期が一番好きです。【Track Listings】01. Amerika02. 猟奇歌03. Boys Of Bedlam04. To Be (帝国の逆襲)05. Heavy Waters06. Ural
2013.01.14
コメント(0)
-
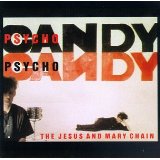
Jesus & Mary Chain "Psychocandy"
2013.01.12
コメント(0)
-
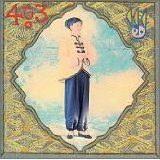
小川美潮 "4 to 3"
元チャクラのリード・シンガー小川美潮の 2nd ソロ・アルバム。なんだろうな、この安心感は。身も心も解きほぐされて、全身を何の躊躇いもなく音に委ねられる感覚。1 曲目の "デンキ" からそのたおやかな歌声に魅了されます。チャクラの頃からそうなんですが、特にテクニック的に優れているとは思えなくて、いや、実はスゴイんだけどそうは思わせないと言うか。坂田明や細野晴臣、はたまた仙波清彦に乞われたぐらいですから下手なワケはないんですが。彼女だけではなくチャクラと言うバンド自体にそう言うところがあったように思います。80 年代の初頭において少なくとも私の中では「陰」の戸川純、「陽」の小川美潮と言った構図があって、勿論戸川純も大好きだったんですが、小川美潮の「天然」なところ、まっすぐ進んでるつもりで自然に捩れ行くようなところにすごく惹かれていました。バンドとしてのチャクラも随分実験的というか奇矯な部分を持っていたのですが、それ以上にチャーミングとでも表現したくなるようなポップさがあって、難解さをそうとは気付かせずにサラリと聴かせてしまうある種の技巧(と言ってしまって良いのか)が魅力でした。そんなチャクラの良い意味での軽さと、当時小川美潮がいくつかの関西ローカルのテレビ番組にアシスタント的な役回りで出演したことと相俟って、私はかなり長い間彼女たちを関西出身だと勘違いしていたのですが。前置きが長くなりましたが、この "4 to 3" もチャクラからの良い部分を引き継いでいるように感じられるのです。時代の最先端を行こうと言う気負いも、奇を衒ったり異端を気取るような小賢しさもなく、極々自然に人間「小川美潮」が表現されています。初めて聴いた時よりも 10 年後、更には 20 年経った今の方がしっくりと馴染んで来てるような気がします。バックを支えるチャクラ時代からの朋友板倉文、Ma*To、近藤達郎、川島バナナ等腕利きのメンバーたちも目立たず出しゃばらず、それでいて随所でキラリと小技が光る好演振り。僅か 10 曲とは言え全曲お薦めの佳曲揃い。オリコン的価値観とは相容れないところがあるのかもしれませんが、これほどの作品が今現在廃盤であると言う事実はレコード会社の怠慢を物語っているとしか思えません。ストリングスを絡めて壮大に盛り上がるバラッド "窓" は、「名曲」と評してなんら問題ない作品だと未だに思いますが、更にそれで大団円にするのではなく、不審な男を追跡する少年探偵団の歌?もしくは、何の前触れも無くいきなり恋に落ちてしまった少女の歌?中味はともかく "窓" とは真逆とでも言いたいほどにほのぼのとした "おかしな午後" をフィナーレに持ってくるセンス。まいっちゃうなぁ。素敵過ぎる。【Track Listings】01. デンキ02. Four to Three03. 夜店の男04. 野ばら05. On the Road06. 記憶07. ほほえみ08. 天国と地獄09. 窓10. おかしな午後
2013.01.03
コメント(0)
-

Les Rallizes Denudes "'77 Live"
60 年代後半に活動を開始しながら単独での公式音源の発表がなかった裸のラリーズが、90 年代初頭に突然リリースした 3 枚の公式 CD の 1 枚。そのニュースを知った(確か『ミュージック・マガジン』の小さな記事であったと思います)時には、当時私が住んでいた大阪市内の、インディーズ系を扱っている主要なレコード・ショップでも既に軒並み売り切れ状態で、どこに問い合わせても在庫もないし入荷予定もない、とけんもほろろの対応。諦めきれずダメ元で発売元に問い合わせたところ "'67-'69 STUDIO et LIVE" とこのライヴ盤は何枚かある、とのことでなんとか手に入れることが出来たのでした。「公式」とは言いつつそもそも発売を目的にして録音されたものではなかったのでしょう、音質はブートレッグ並み。強烈なフィード・バックと過剰に施されたヴォーカルのディレイ効果、更にはその荒々しく毛羽立った様な劣悪な音質のお陰で(?)、輪郭が不鮮明で掴めそうで掴み切れない、常にはぐらかされているようなもどかしさは抱えつつも、聴き手である私たちのイマジネーションは自由奔放に轟音の中を飛び回れる、そんな印象を持ちます。そう言う意味合いにおいて 1 曲 1 曲を取り上げてああだこうだと評するのは野暮と言うものでしょう。一夜のライヴの全貌は 2 枚のディスクに分割され、1 曲毎のクレジットもありますが、これは「ひとつ」のものとして聴くのが一番良いのかな、と思います。最後に余談。かつてあがた森魚は 8 年もの歳月を掛けてアナログ盤 3 枚組の大作 "永遠の遠国" を産み落としました。また、PANTA は一度ならずも挫折した「水晶の夜」をテーマにした作品を構想から 10 年後に "クリスタル・ナハト" と言うアルバムに結実させました。或いは、Beatles の "Let It Be" や Rolling Stones の "Tattoo You" と言った作品は、当のアーティスト本人が匙を投げた素材を、外部のプロデューサーの手に委ねることで「アルバム」としての実体を持つに至ったものでした。意志あるところに道あり。いろいろと意見はあろうかと思いますが、ことラリーズ、水谷孝と言う人に関しては「(再生芸術としての?)作品を生み出す」と言う意志が希薄であったのだろうか、と残念に思う今日この頃。まあ(消息はわかりませんが)「引退」したと言う話は未だ聞かないので、今後なんらかの形で新しいなにかが出てくる可能性、淡い期待は持ち続けはしますが(笑)。【Track Listings】- Disque 1 -01. Enter The Mirror02. 夜、暗殺者の夜03. 氷の炎04. 記憶は遠い- Disque 2 -01. 夜より深く02. 夜の収穫者たち03. The Last One
2012.12.22
コメント(0)
-
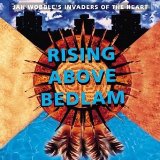
Jah Wobble's Invaders Of The Heart "Rising Above Bedlam"
元 P.I.L. のベーシスト Jah Wobble のユニット、 Invaders Of The Heart の 2 枚目にして最初のスタジオ録音アルバム。やたら(?)多作な方なので全てをフォローしている訳では到底ありませんが、Jah Wobble のソロ・ワークの中でも飛び切りポップで取っ付き易い作品であり、P.I.L. 脱退以降では、元 Can の Holgar Czukay、Jaki Liebezeit とのコラボレーション "Full Circle" に続いて彼が手に入れた大きな果実のひとつです。相変わらず上手いんだか下手なんだか判然としないダブワイズなベースを基調に、エレクトロニクス、ホーンやトライバルなパーカッションを絡ませ、時にニュー・ウェーヴ、時にエスニックなダンス・ビートといった感じで気の向くままにとりとめの無い無国籍風サウンドを展開しています。中でも印象的なのはアルバム冒頭の "Visions Of You" で透明感溢れる美声を響かせる Sinead O'Connor と、アラブ歌謡調(?)のコブシを決める Natacha Atlas のゲスト・シンガー陣の活躍振りです。とりわけ、この作品を通して初めてその存在を知った Natacha Atlas の存在感は抜群。私にとっては Peter Gabriel の "In Your Eyes" での Youssou N'Dour 以来の衝撃でした。彼女をフィーチャーした "Bomba" や "Erzulie" と言った楽曲での妖艶さはそれまで私が聴いたことのないものであり、彼女の声が私の耳に届いたその刹那、その場の空気が一気に濃密なものに変化したのではないかと思わせる程です。とぼけたと言うかのほほんとしたとでも言うのか、いつもはさして気にならない Jah Wobble の鼻歌風ヴォーカルが、この時ばかりは場違いなものに思われ耳障りで仕方ありませんでした。とまれ、Natacha Atlas と言う逸材を広く知らしめたというその一点だけでも、聴く価値のある作品だと思います。【Track Listings】01. Visions Of You02. Relight The Flame03. Bomba04. Ungodly Kingdom05. Rising Above Bedlam06. Erzulie07. Everyman's An Island08. Soledad09. Sweet Divinity10. Wonderful World
2012.12.19
コメント(0)
-
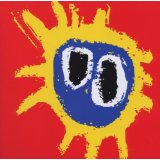
Primal Scream "Screamadelica"
Stone Roses 不在の間隙を縫って UK ロック・シーンのトップに躍り出た Primal Scream の 3rd アルバム。本作以前の Primal Scream については、フロント・マンの Bobby Gillespie が Wake や Jesus & The Mary Chain のメンバーだったと言うこともあり、John Lennon を想起させるバンド名とも相俟って興味半分で聴いてはいましたが、なんともゆるーい感じのガレージ・ロックだなぁ、と言う程度の感想しかなく、のめりこむまでには至りませんでした。それが・・・。それが一体どうしたことでしょう。前 2 作の余りの不発振りにキレてしまったのか、突然の大変貌。キーワードは Rolling Stones とハウス・ミュージックでしょうか。"Beggars Banquet" ~ "Let It Bleed" 辺りの Stones の楽曲にゴスペル・コーラスをぶち込んでハウス・リミックスしたようなオープニング "Movin' On Up" がいきなり強烈です。"Come Together" はタイトルは Beatles ですが、1 曲目同様コーラスを配して静かな出だしから徐々に高揚し圧倒的な絶頂へと向かう様は正に Primal 版 "Salt Of The Earth"、もしくは "You Can't Always Get What You Want" とでも言った趣き。普通の(?)バンドならばアルバムのフィナーレに持ってきそうな曲なのになぁ、とその捻くれ具合に妙に感心。"Loaded" はまんま "Sympathy For The Devil" だし、続くピアノの響きが印象的な、 "Exile on Main St." に入っててもおかしくなさそうなバラッド "Damaged" では、当のアルバムのプロデューサーでもあった御大 Jimmy Miller を担ぎ出してくると言う念の入り様。このように各々の楽曲も面白いのですが、オリジナル・アルバムでありながらリミックス・アルバムでもある、と言う凝った趣向がロックでありながらダンス・ミュージックでもある本作の成功の鍵なのではないでしょうか。一方で女性ヴォーカルをフィーチャーした "Don't Fight It,Feel It" やインストゥルメンタルの "Inner Flight" を聴くに及んで、プロデューサーたる Andrew Weatherall や The Orb の手腕は認めつつも、果たしてバンドとしての実体はあったのか、とやや疑問も残りますが。【Track Listings】01. Movin' On Up02. Slip Inside This House03. Don't Fight It,Feel It04. Higher Than The Sun05. Inner Flight06. Come Together07. Loaded08. Damaged09. I'm Comin' Down10. Higher Than The Sun - A Dub Symphony In Two Parts -11. Shine Like Stars
2012.12.12
コメント(0)
-
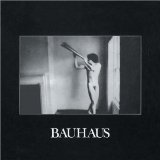
Bauhaus "In The Flat Field"
"Treasure" [Cocteau Twins] 以前の初期 4AD Records の、ダークで硬質なレーベル・イメージを決定付けると共に、後のゴシック・ロックやヴィジュアル系の源流とも評されることにもなった Bauhaus の 1st アルバム。私が所有している CD は、なにを血迷ったのか 1 曲目にボーナス・トラックの "Dark Entries" が配されると言う暴挙に等しい構成。4AD 、一体なにをやらかしてくれるんだ。このアルバムのオープニングは絶対に "Double Dare" でしょ。不吉な報せの到来を告げる鐘の音、もしくは海底深くに潜む不気味な潜水艦のソナー音をおもわせるベースで始るあの曲。それ以外の選択肢があるなどとは露ほどにも思わなかった私は、当時相当なショックを覚えました。それほどまでに、私にとっては重要で大切なアルバムなのでした。本作がシーンに登場した 1980 年代初頭のイギリスでは、Public Image Limited や Joy Division、Killing Joke、Echo & The Bunnymen 等々、ポスト・パンク/オルタナティヴと呼ばれたアーティスト達がデビュー、或いは重要作品をリリースしていた時期。次から次へと出てくる未知の音になけなしのお金をつぎ込んでいました。大袈裟に言えば私にとってのメルクマールとなった時代でした。なかでもこの Bauhaus の印象は鮮烈でした。漆黒の闇を切り裂く一閃の光のようにしなやかに跳躍する Peter Murphy と、上半身も露にノイジーなギター・サウンドを奔放に撒き散らす Daniel Ash のコンビネーションには、同時代のアーティスト達にはないスター性とでも言うのか、別格の輝きがありました。但し、肝心の音の方はそのヴィジュアルとは裏腹に(?)それほど取っ付き易いものではありません。本作の中ではボーナス・トラックとして収録されている T-Rex のカヴァーである "Telegram Sam" が一番ポップな出来かもしれませんが、それとて原曲のコアの部分だけを抽出し高濃縮したような異形のサイケデリック・ミュージックに仕上がってはいますが。【Track Listings】01. Dark Entries02. Double Dare03. In The Flat Field04. God In An Alcove05. Dive06. Spy In The Cab07. Small Talk Stinks08. St.Vitus Dance09. Stigmata Martyr10. Nerves11. Telegram Sam12. Rosegarden Funeral Of Sores13. Terror Couple Kill Colonel14. Scopes15. Untitled16. God In An Alcove17. Crowds
2012.12.08
コメント(0)
-
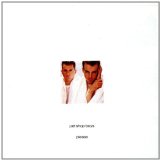
Pet Shop Boys "Please"
Neil Tennant と Chris Lowe のエレクトロニック・ポップ・デュオ Pet Shop Boys の 1st アルバム。Neil Tennant は元々音楽雑誌の編集者だったらしく、もしかするとその辺りが関係しているのでしょうか。理詰めで考えに考え抜いたのでしょう、デビュー作とは思えないほどの完成度です。アメリカやイギリスで大ヒットした "West End Girls" や "Opportunities" に顕著な、ダンサブルなディスコ・サウンドにちょっぴり哀愁や翳りを絡ませたお馴染みの音が目白押し。さすがに古臭く感じるところもありますが、それを補って余りあると思えるほど良いメロディーが満載です。テクノロジーは時間と共にどうしても陳腐化してしまいますが、メロディーは古びません。それが未だに根強い人気を誇っている大きな理由のひとつではないでしょうか。反面、そつが無さ過ぎてちょっと面白味に欠ける気もします。彼らの特徴のひとつとも言える諧謔的なところが見当たらない点も残念です。折角のデビュー作なのにわざわざ浮かない表情のポートレイトを採用する辺りに、幾分アイロニカルな部分が垣間見えはしますが。但し、こんな重箱の隅を突く様なことを言うのはあくまで私が後追いのファンだからでしょう。好きなら好きと言えば良いのにね。ひねくれ者だなぁ。って、私のことか。ちなみに、このシンガー + キーボード・プレイヤー(サウンド担当)の男性デュオと言う編成は Soft Cell や Communards、Erasure などと同じ。おまけに(?)シンガーがゲイ、と言うところも。【Track Listings】01. Two Divided By Zero02. West End Girls03. Opportunities (Let's Make Lots Of Money)04. Love Comes Quickly05. Suburbia06. Opportunities (Reprise)07. Tonight Is Forever08. Violence09. I Want A Lover10. Later Tonight11. Why Don't We Live Together?
2012.12.05
コメント(0)
-

ヴァージンVS "ヴァージンVSヴァージン"
正体不明の謎の(嘘)シンガー A児率いるブリキのロックン・ロール・バンド、ヴァージンVS の 1st アルバム。私のヴァージンVS 初体験は確かたまたま見ていたテレビの音楽番組(?)でした。やたら派手な格好のバック・バンドの面々に、負けず劣らず、どころかそれに数倍輪を掛けたような、ある意味やり過ぎ感満載のキンピカ・コスチュームの A児と名乗るシンガーが、あろうことかあの(!)あがた森魚だったのです。その頃の私は精々 "赤色エレジー" ぐらいしか聴いたことがなく、それまでの彼に対する印象は、暗い歌を歌っていた四畳半フォークの生き残り、有体に言えば「過去のヒト」、と言った今となっては赤面してしまいそうなぐらいに貧相なものでした。しかも当時は、パンク/ニュー・ウェーヴ人気を当て込んで、レコード会社やプロダクションの主導でスタジオ・ミュージシャンや地道に活動していたアーティスト達が集められて作られた即席の、所謂「業界パンク」やら「業界ニュー・ウェーヴ」などと呼ばれた(揶揄された)バンドがいくつもデビューしていた時期でもあり、私は自分勝手に A児ことあがた森魚氏の突然の変貌に、驚きと同時にある種の痛々しさをすら感じもしていたのですが。が、しかし、半分呆れつつ聴くともなく聴いていた彼らの音楽が、何故か耳から離れないのです。名前や姿形は変わっても歌声はまごうかたなきあがた森魚です。演技過剰と言うか、超ナチュラル・エフェクトで奇妙なヴァイブレーションを伴ったあの歌声です。(当時の)「最先端」たるパンクやテクノの意匠は纏ってはいても、そこから聞き取れるのはどこか古めかしい「未来」です。かつて憧憬としての幻想の大正浪漫を歌い上げたのと同じような仕方で、来るべき未来ではなく過ぎ去った懐かしい未来を描き出します。当時は飛び切りのポップ・ソングのオン・パレードに、ついつい食指が伸びて聴いていたのですが、その後あがた森魚のアルバムを幾枚も聴くにつれ(と言っても私のコレクションは未だに 10 枚程度ですが)、ヴァージンVS は突然変異でも気紛れの道草でもなんでもなく、かつてのあがた氏と今の、そしてこれからのあがた氏と地続きであったことに気付きました。陸から離れた孤島だと思っていたら、潮が引くと海の底から忽然と道が現れ陸と繋がった、とでも言うような。【Track Listings】01. 夢見るカクテルマシン~Cocktail Machine Moon Light Magic Show~02. ヌーベル・シンデレラ03. ブリキ・ロコモーション04. サントワマミイ05. やきぐりバンバン06. ロンリー・ローラー~Only Lonely Skate Roller~07. モンテクリスト・ファン・クラブ08. サブウェイ・ランナウェイ09. さらば青春のハイウェイ~Good-Bye My Friend~10. ベスパップ・スカウト11. シンデレラ・ラッキー・ロッキー12. セラヴィ- Bonus Track -13. ブリキ・ロコモーション DEMO14. 星降り時計 DEMO
2012.11.28
コメント(0)
-

Flutter "And There Is Light"
Christine Ingaldson 嬢のソロ・ユニット、Flutter の 4 枚目のアルバム。清楚な風情のポートレイトと Smiths なアルバム・タイトルに騙されて買ってしまいましたが、インダストリアルだったりゴシックだったりシンセ・ポップだったりでなかなか一筋縄ではいかないお嬢様(と呼べる年齢かどうかは知りませんが)でした。リアル・ショップならしっかり裏ジャケもチェックしたのになぁ。裏ジャケは表とは打って変わって(?)ゴス風の妖艶なメイクでバッチリ決めてます。ここ 10 年ぐらいでしょうか、インダストリアル/ゴシック界隈では Collide や Android Lust、Jakalope、Emilie Autumn に Bella Lune に、と言った具合に挙げだすとキリがないほど女性シンガーをフィーチャーしたグループやソロ・ユニットが次から次へと登場してきました。他のアーティストとの差異化を図ることはそうそう容易な状況ではないはずです。この Flutter にしても同じ事で、インダストリアル/ゴシックを前面に押し出したアルバム中盤の楽曲に関しては類型的な印象を免れません。しかし、そんな中でも "The Planning" や "Growing Pains" と言ったインダストリアルなインタールード的小曲を挟んで、しっとりとした歌声を聴かせる "And There Is Light" や "Are You There?" のようなバラッドを配したアルバムの前半、ピアノとストリングスをバックに情感たっぷりに歌い上げる "Somewhere Else"、どことなく Roxy Music の Andy Mackay を髣髴とさせるオーボエの物悲しい響きが印象的な "Angel Of Death" 等ミディアム~スローな楽曲が続く後半部はなかなか聴き応えがありました。【Track Listings】01. The Planning02. And There Is Light03. Growing Pains04. Are You There?05. Sick On Sexy06. Unlawful Assembly07. I Have No Name08. In A Fog09. Time Out10. A Daily Routine11. Somewhere Else12. Angel Of Death13. Your Gift14. When You Arrive15. Last Breath
2012.11.24
コメント(0)
-

Download "Furnace"
例えば Alain Jourgensen [Ministry] の Revolting Cocks とか、Bill Leeb [Front Line Assembly] の Delerium とか。インダストリアル方面の方々は課外活動がお盛んで、Skinny Puppy の Cevin Key もご他聞に漏れずソロ名義の他に Doubting Thomas やら Plateau やら Tear Garden と言った名前で数々のサイド・プロジェクトを展開しています。この Download もそのひとつ。さすがにサイド・プロジェクトひとつひとつを丹念にフォローするまでには至っておりませんが、本作は Cevin Key の手掛けた作品の中でも最も過激な部類に入るのじゃないかと思います。時期的には "Last Rights" リリース後数年の活動停止期間を経て "The Process" で復活する直前辺り。Skinny Puppy と言う看板を下ろした気楽さ(?)故なのか、Cevin Key の個人的趣味嗜好全開の捩れて、歪んで、屈折した(「音楽」ではなく)音響が 70 分以上に渡ってこれでもか、と言うぐらいに詰め込まれています。ノイズ塗れの "Phaedra" と言う感じが無きにしも非ず。インダストリアル界の大御所、Genesis.P-Orridge が客演されておりますが、翁のヌメっとした声が出てくる頃にはすでにお腹一杯。恐らくビジネスだとか世間的な評価というものを端から無視して作り上げたんじゃないかと思うほどに、偏執的なサンプリングや過剰なエフェクト処理を施したパーカッションやエレクトロニクスが縦横に駆け巡り、ヘッドフォーンで聴いていると気持ち悪くなってきます。疲れている時とか風邪ひいてる時とかに聴くとかなりヤバいので要注意です。CD 一枚聴き通すのにこれほど気力・体力を必要とする音楽も珍しい(笑)。Skinny Puppy が大好きな私でさえ聴いていて正直面白いとは思えないし、なんとも表現の仕様のない代物なんですが、何故か 1 年に 1 回位は聴いてしまいます。【Track Listings】01. Mallade02. Seel Hole03. Omniman04. Cannaya05. Sigesang06. Stone Grey Soil07. Mother Sonne08. Attalal09. Bebanull10. Beehatch11. Noh Mans Land12. Marred13. Hevel
2012.11.21
コメント(0)
-

After Dinner "Editions"
神戸出身の Haco を中心とした不定形でフレキシブルな編成の音楽集団 After Dinner の、80 年代前半に残されたスタジオ録音作品と 1986 年から 1990 年に掛けて行われたライヴにおける録音作品を集めたコンピレーション・アルバム。デビュー作は確か、京都のゼロ・レコードと並んで関西のサブ・カル・シーンの一翼を担ったと言っても良い、西宮市を拠点としたかげろうレコードからリリースされたシングルだったと記憶しています。多少前後するかもしれませんが、Aunt Sally の Phew や変身キリンの須山公美子、或いはチャクラの小川美潮、そして Haco さん。それぞれスタイルや音楽性は違ってもある意味百花繚乱、女性シンガー好きの私には堪えられない時代でした。なかでもこの After Dinner は、本作に収められたライヴ作品の多くが海外での公演からの選曲であることからも窺えるように、日本よりも海外での評価が高く、むしろ国内においては知る人ぞ知ると言った存在でした。なにしろ「なに」にも似ていないのですから。褒め言葉(?)にしろそうでないにせよ、とかく「ストーンズみたいなロックン・ロールだよ」とか「ギターはマイブラみたい」などとついつい表現してしまう我々凡人とってはやっかいなグループです。洋楽の安易な焼き直しでないことはわかります。だからと言って「日本的」なのか、と問われるとそれはそれでちょっと困ってしまいます。そんな彼女たちのエッセンスが詰まった作品が 1 曲目の "After Dinner" じゃないかと思います。テープ処理なのか変調された雅楽風バック・トラックの居心地の悪さと、無邪気に見えながらどこかしら不可解な部分が垣間見える大正期の童謡じみた歌詞、そしてそれらをなんなく包み込んでポップに纏めてしまうキュートなヴォーカル。深読みしようと思えばいくらでも深読み出来そうな音楽ですが、私にとってはとても中毒性の高い音楽でもあります。この CD を聴くと優に一ヶ月ぐらいは頭の中をグルグルと彼女たちの音楽が駆け巡るのです。特に、音の空間処理が印象的な "Shovel & Little Lady" や、ヒカシューの巻上公一氏と思しき男声ヴォーカルの素っ頓狂な合いの手が飛び出す "Cymbals At Dawn" 辺りはツボ中のツボ。会議中でもなんでもつい気を許すと口ずさみそうになっている自分に気付きます。【Track Listings】- After Dinner -01. After Dinner02. Sepia-ture03. An Accelerating Etude04. Soknya-doll05. Shovel & Little Lady06. Cymbals At Dawn07. Glass Tube08. Dessert09. Sepia-ture II- Live Editions(1986 - 1990)10. A Walnut11. Cymbals At Dawn12. RE13. Kitchen Life14. Glass Tube15. The Variation Of "Would You Like Some Mushrooms?"16. Ironclad Mermaid17. After Dinner18. The Room Of Hair-Mobile
2012.11.16
コメント(0)
-
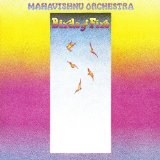
Mahavishnu Orchestra "Birds Of Fire"
John McLaughlin 率いる超絶テクニシャン集団 Mahavishnu Orchestra の 2 枚目にして、彼らの最高峰作との誉れ高きアルバム。1 曲目の "Birds Of Fire" から John McLaughlin のアグレッシヴなギター・サウンドが炸裂。ミストーン弾いてもこのまま突っ走るぜ、ぐらいの気迫を感じるプレイ。古くは 60 年代の Beatles から、グラム・ロック時代の David Bowie の黄金期を築いたロック系プロデューサーである Ken Scott が参加した性か、デビュー作よりもロック色が強いように思います。John のプレイのみならず、アルバム全体にゴツゴツした感じがあり、重戦車がバリケイド壊しながら正面突破して行くような圧倒的な凄味を感じさせます。ギター、ヴァイオリン、キーボードの三者のソロ回しとか高速ユニゾン・プレイとか、お決まりと言えばお決まりのフォーマットなのでしょうが、漲る緊張感が予定調和を小気味良いぐらいにぶち壊してくれています。ちょっと残念なのは、シンセサイザーの音色。さすがに今聴くと古臭く感じます。彼らだけではないですが、シンセサイザーの音は流行り廃りが激しいですし、その時代時代で聴き手の好みも変化して来るので、使い方がかなり難しいように思います。それとラストの "Resolution"。波乱に満ちた壮大な展開を予感させておいて前触れだけで終わる小曲。ストレスだけが残るなんとも罪作りなエピローグ(笑)。しかも一番 King Crimson っぽいし。【Track Listings】01. Birds Of Fire02. Miles Beyond03. Celestial Terrestrial Commuters04. Sapphire Bullets Of Pure Love05. Thousand Island Park06. Hope07. One Word08. Sanctuary09. Open Country Joy10. Resolution
2012.11.11
コメント(0)
-
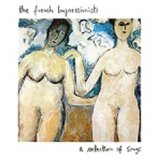
French Impressionists "A Selection Of Songs"
前回の Antena に続き Les Disques Du Crepuscule 繋がりで、(フェイク)ジャズ・バンド French Impressionists のコンピレーション・アルバムです。Antena とほぼ状況は似ていますが、コンパイルすると言ってもバンド単独でのリリースは 82 年の 4 曲入り 12 インチ・シングル "A Selection Of Songs" のみ。これでは CD としての体を成さないので、Thick Pigeon とのスプリット・シングルから "Santa Baby" を、Crepuscule のオムニバス・アルバム収録作品から数曲、どこから引っ張り出してきたのか未発表のライヴ録音、更にはバンド解散後(?)数年を経てレコーディングされた(バンド・リーダーだったと思しき) Malcom Fisher のピアノ・ソロ 2 曲(17/18 曲目)を強引に掻き集めて出来上がったのが本作。やはり Malcom のソロは余分ですね。質感も全然違うし、あまりにも真っ当過ぎる出来です。当時日本でも "A Selection Of Songs" (12 インチの方)が新星堂のレーベルから発売されていたはずで、一部の好事家から随分高評価を得ていたように記憶しています。ピアノ、ベース、それにドラムと言った如何にもジャズっぽい編成のバンドをバックに、ややロリータ気味の女性シンガーが音程も定まらぬ不安定な歌声を披露すると言う趣向。意図的なのか、一発録りっぽい鄙びた質感の音がなかなか良い雰囲気を醸し出しています。冒頭の "Pick Up The Rhythm" や、しっとりとしたバラッドの "Since You've Been Away" など結構耳に残るメロディーもあります。しかしながら、このバンドの肝はやはり決して上手いとは言い難い女性ヴォーカルに尽きるでしょう。途中で自ら脱退したのか馘首になったのかシンガーが入れ替わったり、2 人になったりしますが、基本的には下手。かの George Gershwin の名作 "Summertime" などある意味噴飯モノの出来かもしれませんが、ここまであっけらかんと歌われると逆に爽やかさすら感じます。クリスマス・ソングの "Santa Baby" は彼らの作品中最もポップな仕上がりなんですが、(きっと録音技術の性だろうけど)歌が普通に上手く聴こえて、それが逆に面白くなかったりして。【Track Listings】01. Pick Up The Rhythm02. Blue Skies03. Since You've Been Away04. Theme From Walking Home05. Santa Baby06. Castles In The Air07. Mannequin08. Rainbows Never End09. Waiting For Someone10. Boo Boo's Gone Mambo11. My Guardian Angel12. My Rainy Day (Live)13. Nothing Really Matters (Live)14. Blue Skies (Live)15. Helpless (Live)16. Summertime (Live)+17. Seven Suite18. Lantern Suite
2012.11.09
コメント(0)
-
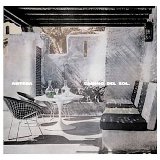
Antena "Camino Del Sol"
80 年代半ば以降 Isabelle Antena のソロ・プロジェクトとなる Antena が、トリオ編成時代に残したミニ・アルバム "Camino Del Sol" 収録曲やシングル・ナンバー等をコンパイルしたアルバム。Factory Records の Peter Saville、或いは 4AD Records の 23 Envelope 等 80 年代のポスト・パンク・シーンにおいて重要な役割を果たしたデザイナー諸氏に比べると、Les Disques Du Crepuscule で多くの(そして勿論、この "Camino Del Sol" の)デザインを手掛けた Benoit Hennebert の存在は影が薄いように感じられますが、決して忘却の彼方へ押しやられて良いものではありません。例えば 50 ~ 60 年代辺りのフランス映画のポスターだとかファッション雑誌の表紙、化粧品の広告、そんなものを想起させるちょっとレトロで、派手さは無いけれどシンプルでセンスの良いデザインが実に印象的。このスリーヴに惹かれてよく知りもしないアーティストのレコードを買ってしまったのは、私一人じゃないハズ。特に好きだったのは本作にも収録されていますが "The Boy From Ipanema" のシングル盤や本作 "Camino Del Sol" のオリジナル盤の、俗に言う「裏ジャケ」。写真のレイアウトやタイポグラフィーがなんとも絶妙でした。と、肝心の主役たる Antena を蔑ろにしてしまいました。反省。1 曲目はデビュー・シングル、ご存知ボサ・ノヴァの名曲 "The Girl From Ipanema" の改題。プロデュースは John Foxx ですが、彼の名前から想像されるようなテクノではありませんし、オリジナルのカラっとした明るい雰囲気からするとやや俯き気味。余りにも簡素なバック・トラックと、音の隙間を縫うように出入りするエフェクト過剰なヴォーカル。テクノ、ボサと言うよりはダブっぽい気もします。他の楽曲も概ねこんな調子。ボサ・ノヴァやジャスをベースにしているところは Isabelle のソロになってからも変わってはいないのでしょうけれど、"En Cavale" 以降のお洒落でソフィスティケイトされた都会的な感触はここには微塵もありません。スリーブ・デザインにこじつけるわけではありませんが、照りつける太陽の光の恩恵を全身に浴びる風ではなく、サン・シェイド越しにちょっと目を細めながら陽の光を見るともなく見ているような風情、とでも言いましょうか。勿論、私はこちらのほうが大好きです。【Track Listings】01. The Boy From Ipanema02. Camino Del Sol03. To Climb The Cliff04. Silly Things05. Sissexa06. Achilles07. Bye Bye Papaye08. Noel A Hawaii09. Les Demoiselles De Rochefort10. Spiral Staircase11. Unable
2012.11.07
コメント(0)
-
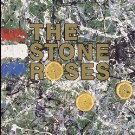
Stone Roses "The Stone Roses"
モロ Jackson Pollock 風ペインティングにレモンの輪切りをあしらったスリーヴが印象的な Stone Roses の 1st アルバム。当初日本では『石と薔薇』と言う身も蓋も無い邦題がつけられていましたが、「ロックとダンス・ミュージックの融合」と言う彼らを語る上で必ず出てくるフレーズを考え合わせると、確かに安直であることは否めませんがなんとなく納得できるかな、とも思うのです。最初にこのアルバムを聴いた時は、正直音楽メディアが絶賛するほどの作品だとは思えませんでした。むしろちょっとサイケデリックなギター・ロックと言う程度の印象でした。どことなく 60 年代ポップ・ソング風な "Bye Bye Badman" とか、Simon & Garfunkel の "Scarborough Fair" を援用した "Elizabeth My Dear" 辺りを聴くと特にそう思います。彼らと同じく、所謂 Mad-chester の一翼を担った New Order ほど無節操ではなく、Happy Mondays ほどに享楽的でもない。私の中ではそんな位置付けでした。「ロックとダンス・ミュージック云々」と派手に喧伝された割には地味と言うか。但し、出会い頭の衝撃がなかった分、後からジワジワと来たのは確かです。Ian Brown のヴォーカルは未だにどこが良いのか理解出来ないのですが(笑)、決して出しゃばるわけではないのにあちこちに印象的なフレーズを散りばめる John Squire のギターと、バンドの屋台骨を支える Mani と Reni のグルーヴィーなリズム隊。そんな彼らが生み出した最良の瞬間が "This Is One" から "I Am The Resurrection" へと繋がる本作の最後半部です。このおよそ十数分間に渡る高揚感は堪えられません。【Track Listings】01. I Wanna Be Adored02. She Bangs The Drums03. Watherfall04. Don't Stop05. Bye Bye Badman06. Elizabeth My Dear07. (Song For My) Sugar Spun Sister08. Made Of Stone09. Shoot You Down10. This Is The One11. I Am The Resurrection
2012.11.03
コメント(0)
-

Omega Lithium "Dreams In Formaline"
女声ヴォーカル Mya Mortensen を擁するクロアチア出身のゴシック・メタル/インダストリアル・ロック・バンドの 1st アルバム。Jonsi の直後に、人体破壊と言うか人体改造と言うのか、この手のバンドにはありがちとはいえこんな禍々しいスリーヴの作品を持ってくるのも如何なものかとは思ったのですが。まあ、気にしない気にしない。ちなみに、私の所有している CD はトラック・マーカーの不良なのか、1 曲目に全くの無音が 35 分間にも渡り収録(?)されています。最初、2 ~ 3 分程度気付かなくて不審に思いながらも「沈黙」のメタルを聴き続けておりました(恥)。肝心の中味ですが、ディジタルで近未来的な顔を覗かせつつも、ゴシック/インダストリアル系の宝庫たる旧東欧圏の伝統(?)を受け継いで神秘主義的とでも言うのか、重々しく荘厳な側面も持ち合わせているように思います。こんな時代になっても奥深い森の中ではなにやら妖しげな秘儀が執り行われていそうな、学生時代の歴史の時間に聞きかじった程度の知識を基にした旧東欧圏に対する私の下世話なイメージが、そう思わせているのかもしれませんが。長い曲でも 4 分程度。この手のバンドにしてはかなりコンパクトに纏まっていますが、逆に物足りなさも感じます。曲調もちょっと一本調子かなぁ。押したり引いたりが欲しいところではあります。後、男声デス・ヴォイス(と言うには中途半端)が出てくる曲があるのですが、Mya 嬢が中音域を主とした凛々しい歌声なので所謂「美醜対比」的な面白さが出ていません。つまり、余計。なにか腐してばかりな感じになってしまいました。これでも結構気に入っているんですけどね(笑)。【Track Listings】01. Infest02. Stigmata03. My Haunted Self04. Dreams In Formaline05. Andromeda06. Nebula07. Snow Red08. Hollow March09. Factor : Misery10. Angel's Holocaust11. Point Blank- Bonus Track -12. Ocean Dreams
2012.10.31
コメント(0)
-

Jonsi "Go"
アイスランド出身のポストロック・バンド Sigur Ros のシンガー Jonsi が、バンド活動休止中にリリースした 1st ソロ・アルバム。ある種近寄り難い「孤高」のイメージが強い Sigur Ros からは想像も出来ない、新しい姿を見せてくれる傑作です。初めて 1 曲目の "Go Do" を聴いた時、恥ずかしながら私は泣きそうになりました。勿論(?)涙は流れなかったけれど。Sigur Ros の特徴でもあった重く垂れ込める濃霧の様な音はそこにはなく、代わりに開放的で、躍動感があり、なによりも歓びに満ち溢れた音がありました。私には正直少しばかり眩しいけれど。正に天馬空を行くが如き伸びやかで、どこまでも響き渡りそうな Jonsi の歌声。なんの誇張もなく、私はもうこれから CD は買わなくてもいいや、とさえ思いました。残りの人生を共に過ごして行くだけの十分なコレクションは既にあるし、今更鵜の目鷹の目で革新的なサウンド、人々の口の上る話題の新人たち、そんなものを追いかける気もさらさらなくなった。ともかく、私の傍らには Jonsi のアルバムが、あると。全 9 曲、僅か 40 分余りの作品ですが、聴き応え十分、中味の濃さは保証付き。美しいメロディーと力強いリズム。流麗なストリングスと奔放に(過ぎる?)叩きまくるパーカッションが特に気になりました。そして、勿論主役たる Jonsi の、全ての桎梏から解き放たれたような自由な歌声。思わず手を叩き踊りだしそうな "Go Do" に始まり、荘厳な響きに包まれた "Hengilas" で静かに終わる構成も見事。最初から最後まで鳥肌立ちまくりの 40 分間。これ以上に、一体なにが要る?【Track Listings】01. Go Do02. Animal Arithmetic03. Tornado04. Boy Lilikoi05. Sinking Friendships06. Kolnidur07. Around Us08. Grow Till Tall09. Hengilas
2012.10.25
コメント(0)
-
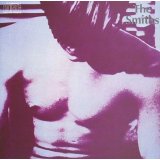
Smiths "The Smiths"
イギリス以外ではさっぱり売れなかったらしい(さもありんなん、とも思います) Smiths の 1st アルバム。このアルバムを聴くと、いや、Smiths と言うバンドを思い起こす時必ずと言って良いほど坂口安吾の文章が頭を過ぎります。「私の年齢が暗かった。私の青春が暗かったのだ。青春は暗いものだ。(省略)なべて青春は空白なものだと私は思ふ。」と言う例のヤツ。作品名はまんま『暗い青春』でしたか。そう、私の青春も暗く、不様なものでした。Morrissey が描くのは 21 世紀の日本に蔓延る「辛い思いをした分だけ他人に優しくなれる」的な青春ソングの真逆の世界。愛したい、愛されない、愛されたい、愛せない。何一つとして満たされたものは無く、なにもかもが過剰。自らのかっこ悪さをここまであからさまにかっこ悪く曝け出した表現者もそうそういないでしょう。そんななんとも惨めったらしい姿が、これまたなんとも妙なるメロディーと流麗なギター・サウンドに彩られて、我々の眼前に突きつけられたのです。リアル・タイムで彼らの音に接した時の、私(たち)の・・・あれは戸惑い、だったのか、違和感、或いは恐れ。近親憎悪。Smiths はやはり私たち自身を映し出す鏡であったのだ、と思います。2nd アルバムの "Meat Is Murder" 以降に彼らのピークがある、と言うのが一般的な評価のようですが、私はこの 1st アルバムが大好きです。物悲しく、どこか寂しげな佇まいが、私の琴線を微妙に擽るのです。とりわけアナログ盤では B 面に相当した 6 曲目 "Still Ill" からラスト "Suffer Little Children" へと至る流れは絶品。【Track Listings】01. Reel Around The Fountain02. You've Got Everything Now03. Miserable Lie04. Pretty Girls Make Graves05. The Hand That Rocks The Cradle06. Still Ill07. Hand In Glove08. What Differece Does It Make?09. I Don't Owe You Anything10. Suffer Little Children
2012.10.21
コメント(0)
-
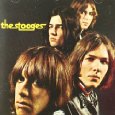
Stooges "The Stooges"
Sex Pistols がパンク・ロックの父ならば、正にゴッド・ファーザーと言う呼び名に相応しい Stooges の 1st アルバム。何処かで見たような書き出しですが・・・気にしない。ファズ・ギターが終始騒々しく鳴り響いている割に全体の雰囲気は驚くほどクール。私はお定まりの(?)ロンドン・パンク経由で Stooges に辿り着いたクチなので、「暴力的」なイメージばかりが先行し、実際にアルバムを聴いた時にはかなり拍子抜けしました。但し、ここにあるのは剣呑な素振りは露程も見せないそんな裏側で、来るべき跳躍に備えて体中の力を一点に絞っている、そんなクールさです。この辺りの感触は元 Velvet Underground の John Cale の手腕に拠るところが大きいのでしょうか。かつて Rolling Stones は「なにをやっても満足出来ないんだ」("Satisfaction") と歌い、一方で Who は「歳喰う前に死にたいぜ」("My Generation") と歌いました。それらはあくまでも個人的な感情の発露を出発点としたものではあったのでしょうが、自分達の所属する「世代」が抱える共通の認識であると偽装することで大義名分を手にし、それを梃子にして世界的なヒットに結び付けました。しかしながら、ここで Stooges が歌っているのは、「去年のオレは 21/良いことなんてなかったぜ」("1969") と言うあまりに見も蓋も無い、ある種の信仰告白とでも言ったものでした。1969 年と言えばヴェトナム戦争に倦み疲れたアメリカで、「愛と平和」のウッドストックと「血と暴力」のオルタモントと言う表裏一体のイヴェントがあった年でしたが、彼らはそんな社会状況や時代背景に触れることも無く、また主人公の心象風景を丹念になぞることもせずに「良いことなんてなかったぜ」とたった一言言い放つのです。そんな一個人の言い掛かりめいた呟きを、一切の前提条件や保留条項なしで突きつけてきた Stooges の潔さ(もしくは、間抜けさ加減)がたっぷり楽しめます。但し、John Cale の趣味が全面に出過ぎて Velvet Underground にか聴こえない読経調の不気味な楽曲 "We Will Fall" が、本作における唯一の欠点を成しています。【Track Listings】01. 196902. I Wanna Be Your Dog03. We Will Fall04. No Fun05. Real Cool Time06. Ann07. Not Right08. Little Doll
2012.10.16
コメント(0)
-

Killing Joke "Killing Joke"
Ministry がインダストリアル・メタルの父ならば、正にゴッド・ファーザーと言う呼び名に相応しい Killing Joke の 1st アルバム。ほぼ同時期に登場してきたポスト・パンクのアーティスト達、例えば Bauhaus や Echo & The Bunnymen、Gang Of Four と言った人達の中でもとりわけ硬質で原初的な音が特徴。彼らの音楽を評する際、当時の音楽雑誌は「呪縛的」だの「呪術的」だのと言ったキーワードをよく使っていたと記憶しています。昨今の所謂インダストリアル・メタルと比較すると楽曲の構成はかなりシンプルだし、音圧もかなり低めですが、一語一語を対象にぶつけるようなヴォーカルを含めてひたすらノイジーに、しかしヒート・アップすることなくクールに音の塊を叩き付ける様は、成る程「呪術的」と言いたくなる気持ちも理解出来ます。冒頭の 2 曲、"Requiem" と "Wardance" の印象が強烈ですが、改めて聴きなおすと結構ダンサブルだったことに今更ながら驚かされます。Ministry や Nine Inch Nails 等、後の世代への影響力は看過できないものがあります。その一方、セールスや一般的な(?)認知度と言う観点からはこれと言った成果は残せていないと言わざる負えません。2nd アルバム以降同じメンツが出たり入ったりの恒例とも言うべき頻繁なメンバー・チェンジ、何度も繰り返される長い沈黙期間、リーダーたる Jaz Coleman のサウンド志向の変化(と言うより端的に迷走振り)等が評価を辛くしている所以なのかもしれません。勿体ないことです。【Track Listings】01. Requiem02. Wardance03. Tomorrow's World04. Bloodsport05. The Wait06. Complications07. Change08. S.O.3609. Primitive
2012.10.14
コメント(0)
-
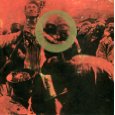
Naked City "Leng Tch'e"
アルト・サクソフォン奏者 John Zorn 率いるフリー・フォームな音楽集団 Naked City、1992 年の作品。順番としては "Naked City"、"Torture Garden" に続く 3 枚目のアルバム。何故か私の持っている CD にはメンバーのクレジットがないのですが、恐らくはいつものメンバー、John Zorn、Bill Frisell、Wayne Horvitz、Fred Frith、Joey Baron、それに山塚アイと言うお馴染みの編成ではないかと思われます。この作品、私が所有している CD の中で最もおぞましいものであると思います。以下、不快な表現が頻出するかと思いますので、この項、飛ばしていただいて結構です。・・・・・・アルバム・タイトルでもあり、唯一の収録曲たる "Leng Tch'e" とは、「凌遅刑」、もしくは「凌遅処死」と呼ばれる中国古来から清の時代まで行われてきた処刑方法のひとつであって、歴代王朝に叛旗を翻した反乱の首謀者に課せられた最も重い刑とのことです。その処刑方法とは、受刑者を柱等に縛り付けた上で、死に至らせるまで生きたまま四肢を(出来得る限りその死を遅らせ、苦痛をより長く味あわせる為に!)徐々に切り落としていくと言う残酷極まりないものだったそうです。スリーヴの写真は正にその処刑の様子を写し出したものなのです。村上春樹氏の著作『ねじまき鳥クロニクル』の中に、生きながらにして皮膚を剥ぎ取られる日本軍人のエピソードが出てきますが、あちらは戦時下で、しかも蒙古軍(?)による私刑(リンチ)的な意味合いが見て取れましたが、「凌遅刑」は合法的な刑罰であり、個人ではなく国家と言うシステムがそれを執り行うと意味において、その刑罰の持つ凄惨さと併せて二重のおぞましさを感じさせます。その「凌遅刑」にインスパイアされた John Zorn が作り上げた作品が、"Leng Tch'e" です。(わずか 30 分程度の楽曲ですが)いつ終わるとも知れない単調な演奏は正にその刑罰の長さを、15 分辺りから突如乱入してくる山塚アイの絶叫ヴォイスは受刑者の苦痛の叫びでしょうか。本当におぞましくも気が滅入る音楽です。聴くたびに総毛立つ思いが過ぎる一方で、なにかしら抗い難いもの(「魅力」とは言えないし、言いたくもないのですが)をも同時に感じるのです。怖いもの見たさ、ならぬ聴きたさ、でしょうか。【Track Listings】01. Leng Tch'e
2012.10.10
コメント(0)
-
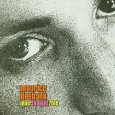
Maurice Deebank "Inner Thought Zone"
初期 Felt の繊細で透明感溢れる世界を支えたギターリスト Maurice Deebank の 1st ソロ・アルバム。プロデュースは Felt でもお馴染みの John A.Rivers。残念ながら 2 枚目が出たと言う話はまだ耳にしたことがないので、今のところ最初にして唯一の作品・・・と言いつつ、中味は 1984 年のオリジナル 6 曲に、なんと 1992 年に録音された 4 曲("Golden Hills"、"So Serene"、"Pavane"、それに"A Tale From Scriabin's Lonely Trail")が追加された編集盤的なものになっています。10 年近い時の隔たりのある楽曲が混在しているとなると相当違和感ありそうで、ついつい身構えてしまいそうになりますが、それはまったくの杞憂です。音の感触はまったく変わっていないし、むしろ 6 曲目の "So Serence" などは Felt の未発表曲だと言われれば素直に信じてしまいそうになるほど。この変化の無さはある意味驚嘆すべきものだとも思えるし、進歩していないと言われれば確かにその通りなんでしょうけれど、なんでもかんでも取り敢えず進歩すれば良いってもんじゃないでしょ、と思わず偏愛的擁護発言してしまいそうな程、私にとっては愛おしさすら感じさせる作品です。全篇インストゥルメンタルで、正に Lawrence のヴォーカル抜きの Felt と言った趣。この「青臭さ」の抜け切らないとでも表現のしようがないギター・サウンドは、好きな人(私のことですが)には堪らないと思います。間違っても万人にはお薦めできませんが、80 年代のあの「空気感」が未だに忘れられない方々は、ぜひ。【Track Listings】01. The Watery Song02. Four Corners Of The Earth03. Study No.104. Golden Hills05. Silver Fountain Of Paradise Square06. So Serene07. Dance Of Deliverance08. Pavane09. A Tale From Scriabins Lonely Trail10. Maestoso Con Anima
2012.10.06
コメント(0)
-
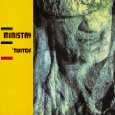
Ministry "Twitch"
インダストリアル・メタルの生みの親、Alain Jourgensen のメイン・ユニットたる Ministry の 2nd アルバム。お茶目なエレ・ポップだともっぱらの噂のデビュー・アルバム "With Sympathy" は未聴。いつかそのうち、と思いつついつの間にかどうでもよくなってしまいました。私の Ministry 初体験は 3rd アルバムの "The Land Of Rape And Honey"。遡ってこの "Twitch" を聴き、こっちの方が出来は良いのじゃないか、と思いました。こちらはインダアストリアル・メタルではなく、エレクトリック・ボディー・ミュージックの範疇に入るのでしょうか。Adrian Sherwood や Keith Leblanc と言った人選もズバリ私好み。執拗に反復するマシーナリーなビートや脅迫的なノイズ、サンプリングの挿入は、まごう方なき Ministry サウンドと言うべきものですが、次作以降に顕著な、ありったけの感情を叩きつけるような激しいヴォーカルに比べて、本作におけるクールな語り口はむしろ新鮮。"With Sympathy" の名残なのかポップなバック・コーラスがあったりもします。ハイライトはなんと言っても 7 曲目のメドレー。アルバムの前半、相当我慢でもしてたんでしょうか、とうとう箍が外れてしまったのかボディー・ミュージックとダブとインダストリアルがごちゃ混ぜになって、延々 12 分にも渡って混沌とした世界を展開します。例のスラッシュ・ギターが一切入ってないので 3rd ~ 5th 辺りのイメージのまま聴くとつまらないと思われる向きもあるでしょうが、彼らの作品の中では(敢えて 1st は除外しますが)比較的ポップで聴き易いのではないでしょうか。【Track Listings】01. Just Like You02. We Believe03. All Day Remix04. The Angel05. Over The Shoulder06. My Possession07. Where You At Now? ~ Crash And Burn ~ Twitch (Version II)08. Over The Shoulder (12" Version)09. Isle Of Man (Version II)
2012.10.03
コメント(0)
-

Mandalay "Empathy"
Saul Freeman と Nicola Hitchcock の男女 2 人組トリップ・ホップ・ユニットの 1st アルバム。21 世紀に突入して既に 10 年以上も経った今、Mandalay の音楽をどれほどの人達が覚えているのか(と言うのも、とっくの昔に解散しているので)と考えると甚だ心許ないことになるのですが、かく言う私にしても彼女たちの残した作品が私の所謂「オール・タイム・ベスト」に入っているかと問われると、必ずしもそう言うわけでもないのです。でも、なにかの拍子にふと思い出すような仕方で、まるで少年期の甘酸っぱくも苦しい記憶を呼び覚ます風に、彼女たちの音楽は私の記憶の淵にしばしば浮かび上がってくるのです。Mandalay の音楽を特徴付けているのは紛れもなく Nicola 嬢のヴォーカルです。聴き手の心を不安定に揺さぶるように細かく震える儚い歌声。強いて例えるなら Madonna の声から強さと言う強さを、アクと言うアクを全て取り払ったような声、とでも言えば良いのでしょうか。これはもうテクニックとしてのヴィブラートではありません。恐らく、レコーディング・スタジオが本当に凍えるほど寒かったのでしょう。もしくは、相方の Saul Freeman から延々とダメ出しを喰らいどうしようもなく心細かったに相違ありません。まあ、そんな与太話は置いておくにしても、これほどまでに男心をくすぐる歌声も珍しいのじゃないでしょうか。ちなみに、打込み基本のエレクトロニックなディジタル・サウンドの中にあって、Brian Eno との競演でロック・ファンにもその名を知られたトランペッター Jon Hassell と、元 Japan のドラマー Steve Jansen のクレジットが目に付きます。もしかして、David Sylvian 人脈?【Track Listings】01. This Life02. Flowers Bloom03. Insensible04. Another05. Enough Love06. All My Sins07. Opposites08. This Time Last Year09. Kissing The Day10. Beautiful11. About You
2012.09.30
コメント(0)
-
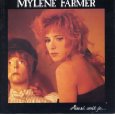
Mylene Farmer "Ainsi Soit Je..."
80 年代フランスのポップ・シーンを代表するシンガー Mylene Farmer の 2nd アルバム。視線の定かではない Mylene の傍らに佇んでいるのは、、、彼女自身を模した操り人形?結構不気味です。曲も作ればプロデュース、アレンジもこなす Laurent Boutonnat との強力コンビが作り上げた逸品。柱時計の SE が不安げな空気を醸し出すオープニング "L'Horloge" から手もなく彼女たちの術中に陥る自分が哀しい(笑)。5 曲目の "La Ronde Triste" は、タイトルはフランス語、歌詞は英語、そして何故かバックには尺八の音色と言うなにやら三題噺のような楽曲。本作中髄一の明るさを誇る(?) 9 曲目 "Deshabillez-Moi" のイントロで聞こえるのは Mylene のマジなクシャミ!? こんなの松田聖子以来ですが、聖子ちゃんほど可愛いクシャミじゃないぞ(笑)。そしてラストの "The Farmer's Conclusion" に至っては、ファミリー・ネームと英語の「農民」を引っ掛けたタイトル通り、牛やら鶏やら豚やらの鳴き声が。更にそれらの音の隙間を縫って聞こえるのは妖しげな吐息(と言うよりは、喘ぎ声)。なんとも奇妙な世界です。とりわけ初期は暗く屈折した歌詞に注目されがちな彼女ですが、重厚なストリングスやアコースティックな楽器を上手く配したエレ・ポップをバックに、時にコケティッシュに、時に消え入りそうな程に儚げな声を自在に操る Mylene の歌の力に圧倒されます。よくよく聴くと、ああ王道フレンチ・ポップだなぁ、と思ったりするのですが、色々な仕掛けが施してあって聴き手を飽きさせません。【Track Listings】01. L'Horloge02. Sans Contrefacon03. Allan04. Pourvu Qu'Elles Soient Douces05. La Ronde Triste06. Ainsi Soit Je...07. Sans Logique08. Jardin De Vienne09. Deshabillez-Moi10. The Farmer's Conclusion
2012.09.26
コメント(0)
-

Orchestral Manoeuvres In The Dark "Orchestral Manoeuvres In The Dark"
一昨年でしたか、突然 14 年振りの復活を遂げた、Paul Humphreys と Andy McCluskey の二人から成るエレクトロニック・ポップ・デュオ Orchestral Manoeuvres In The Dark (略すと何故か O.M.D. になります)の 1st アルバム。マンチェスターの伝説的インディーズ・レーベル Factory Records よりデビュー・シングル "Electricity" をリリース。あの Joy Division より(アーティスト単独での)レコード・リリースは早かったのですが、僅か 1 枚で Factory を去ります。プロデューサーの Martin Hannett (やっぱりコイツか!?)とは上手くいかなかったようですが、未だに謎の多いレーベルですから、他にもいろいろとあったのかもしれません。とにかく、その後めでたく Virgin Records 傘下の DinDisc と契約。無事(?)発売されたのが本作と言うことになります。仰々しいユニット名、Peter Saville の手による穴開きや色違い等スタイリッシュなスリーヴ・デザイン。当時はインターネットなんて影も形もなかったし、数少ない音楽雑誌の記事だけが唯一の頼り。最初見た時には敷居高そうに感じましたが、聴くと見るとじゃ大違い。人懐っこいメロディがてんこ盛りのチャーミングなエレ・ポップで御座いました。さすがに黎明期ならではの(?)チープなピコピコ具合は今となっては如何ともし難いものがありますが。彼らの場合、有名な "Enola Gay" や "Joan Of Arc" と言ったシングル・カット・ナンバー(本作においては "Electricity" 辺り)では派手目でポップな作り、一方アルバムではそれなりに実験的なこともやっていて、そんなバランス感覚も好きな理由のひとつです。【Track Listings】01. Bunker Soldiers02. Almost03. Mysterality04. Electricity05. The Messerschmitt Twins06. Messages07. Julia's Song08. Red Frame/White Light09. Dancing10. Pretending To See The Future- Bonus Tracks -11. Messages (Single Version)12. I Betray My Friends13. Taking Sides Again14. Waiting For The Man15. Electricity (Hannett/Cargo Studios Version)16. Almost (Hannett/Cargo Studios Version)
2012.09.21
コメント(0)
-
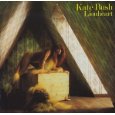
Kate Bush "Lionheart"
デビュー作 "The Kick Inside" から僅か 1 年も経たぬ間にリリースされた 2nd アルバム。屋根裏と思しき部屋で、ライオンの着ぐるみ(首から下のみ)を身にまといこちらを窺う Kate Bush のスリーヴが、今時の言葉に倣うならば「萌え死に」しそうでした。デビュー作における "Wuthering Heights" や "The Man With The Child In His Eyes" に匹敵するほどのキャッチーな曲もなく、次作 "Never For Ever" のように細部までアーティスティックに練りこまれているワケでもなく、彼女の作品の中では比較的印象が薄い部類に入るのかもしれません。が、しかし、Kate Bush に駄作なし。聴き込めば(聴き込まないと解からない私)他にひけをとらない良作であることがわかります。妖精たちが草花の陰で密やかに内緒話しているようなサビが印象的な "In Search Of Peter Pan"。続く "Wow" と "Don't Push Your Foot On The Heartbrake" は共に不安げなイントロと抑制されたメロディーに始まり、サビで感情を吐露すると言う似通った趣向の楽曲。一転して、ピアノをバックに静かに歌われる "Oh England My Lionheart" は、そのタイトル通りイングランドへの愛を歌ったものでしょうか。こうやって聴いていくと、バックの演奏は随分控え目な感じ。その分じっくりと Kate Bush のヴォーカルを堪能出来る作品ではないかと思います。勿論、例の(?)ハイ・トーン・ヴォイスですから、生理的に受け付けないと言う方は当然おられるでしょうけれど。このように決して凡庸な作品ではありません。しかし当の Kate Bush 自身は本作の出来に随分ご不満だったようで、以降セルフ・プロデュースを常とするようになります。そしてついにはレコーディング・スタジオの全てを自らの統制化に置かなくては気がすまない様になり、その天才性故、完全主義故でしょうか、あの狂気の "The Dreaming" へと突き進むことになるのですが、それはまた後々のお話です。【Track Listings】01. Symphony In Blue02. In Search Of Peter Pan03. Wow04. Don't Push Your Foot On The Heartbrake05. Oh England My Lionheart06. Full House07. In The Warm Room08. Kashka From Baghdad09. Coffee Homeground10. Hammer Horror
2012.09.19
コメント(0)
-

Echo & The Bunnymen "Heaven Up Here"
まるで未確認飛行物体から照射された光に照らし出されたかのような不気味な色合いの森の中から抜け出して、初冬の朝まだき浜辺へと歩を進めた木霊と兎男たちの 2nd アルバム。思わずコートの襟を立てそうになる寒気に満ちたスリーブのように、時折抑えきれない激情の迸りの片鱗を垣間見せながらも、決してヒート・アップしない透徹したギター・サウンドが最初から最後までたっぷり詰まっています。漠然とした不安と根拠のない自信、抱えきれない誇大な夢とその刹那に崩れ落ちてしまいそうな脆い現実。尊大でありながらナイーブ、挑発的に振舞った次の瞬間には膝を抱えて蹲っていそうな危うさ。なんとも不可解でいながらも、ああ、確かに私たちもそんな仄暗いところを通って来たのだ、と思わせる、そんな、「若さゆえ」のアンビヴァレントな感性が、奔放な 2 本のギターと、タイトなリズム隊とによって表現されています。とりわけ、オープニングの "Show Of Strength" から、"With A Hip"、"Over The Wall" へと至る部分の緊張感に満ちた構成は素晴らしく、本作における最初のクライマックスを成しています。また、焦燥感をぶちまけるようなヴォーカルが印象的な、騒々しいタイトル・トラック "Heaven Up Here" から、一転して陰鬱な "The Disease" へ、更にある種の神秘性すら感じさせる "All My Colours" と続く流れも白眉です。80 年代初頭の英国音楽が産み落とした傑作のひとつでしょう。しかし、デビューから僅か 2 枚目のアルバムでここまでの高みへと登り詰めてしまったことは、ある意味奇跡でもあり、同時に彼らにとって不幸なことであったのかもしれません。安易に言うべきことではないのでしょうが、Bunnymen のシンガーと奇しくも同じ Ian と言うファースト・ネームも持つ青年の自死により、瞬く間に「伝説」になってしまった Joy Division とついつい比べてしまうのです、(次作以降も良作をリリースし続けるのですが)以降の兎男たちの苦闘の歴史を考えると。【Track Listings】01. Show Of Strength02. With A Hip03. Over The Wall04. It Was A Preasure05. A Promise06. Heaven Up Here07. The Disease08. All My Colours09. No Dark Things10. Turquoise Days11. All I Want- Bonus Tracks -12. Borke My Neck (Long Version)13. Show Of The Strength (Live)14. The Disease (Live)15. All I Want (Live)16. Zimbo (Live)
2012.09.16
コメント(0)
-
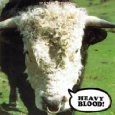
花電車 "The Golden Age Of Heavy Blood"
Boredoms のベーシストであったヒラ率いる 4 人組のヘヴィー・サイケデリック・ロック・バンドの 1st アルバム。Pink Floyd "Atom Heart Mother" を Frank Zappa がおちょくったようなスリーヴがなかなかお茶目です。1 曲目の "Future Deadlock" から尋常ならざるテンション。本体たる(?) Boredoms に比べると遥かにオーセンティックなロック・サウンドなのですが、息苦しいまでに漲る緊張感は負けず劣らずすさまじいものがあります。全身全霊でマイクにありったけの想いをぶつけるかのようなヒラのヴォーカル、暴力的にかき鳴らされるギター、全ての楽器が渾然一体となって襲いかかる様は、正にロックのダイナミズムを見事に体現していると言えるでしょう。80 年代の後半にあって、これほどまでになんの迷いも衒いもなく正面攻撃を仕掛けたロック・バンドが存在したことは、ある種奇跡と言っても良いのではないでしょうか。また、「くれくれ、オレにくれ」とか「おまえのチューブに入りたいよ」と言った直截的な歌詞の一方で、10 分以上に渡ってプログレ的展開を見せる長尺の "Blood Star" では、「動物と植物と腐っていく臭いのなか お前に会いに行こう!」と切なくも美しい絶唱を聴かせてもくれます。この辺りの暴力性と詩情の混交具合も彼らの大きな魅力のひとつです。Boredoms から派生した(?)ユニット、例えば想い出波止場や OOIOO 等に比べると余りにも真っ当なロック過ぎて、ある意味敬遠されてそうな気がしますが、「ロック」と言う定型を纏いつつ決してそれに絡めとられない自由奔放な「ロック」バンドでした(過去形なのが寂しい)。日本のインディーズ・シーンのみならず、ポピュラー音楽史を語る上において決して外すことの出来ない傑物だと確信しております。【Track Listings】01. Future Deadlock02. Bad Tube03. Hot Cake04. Blossom Body05. Blood Star06. Mary Mary Mary- Bonus Track from "West Psychedelia" -07. Headspinningdizzyblues08. Heavensucker
2012.09.11
コメント(0)
-
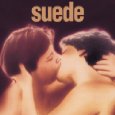
Suede "Suede"
所謂「ブリットポップ」ってヤツの発端となったともいわれる Suede の 1st アルバム。私自身は Oasis や Blur にはなんの思い入れもないので、ブリットポップ云々と言われても正直ちょっと違和感あります。まあ、それはさておき。1 曲目 "So Young" のイントロ。これだけでハマりました。イントロと言ったって Brett Anderson の歌声が聴こえてくるまで 10 秒もないんですけどね。これは個人の趣味というか感性というか、人に上手く説明出来るものではないんですが、この僅か 10 秒で Suede と言う新人バンドが、そしてこのデビュー・アルバムが私の期待を裏切らないことを確信しました。例えば Joy Division の "Disorder"、例えば Durutti Column "Sketch For Summer"、Smiths の "Reel Around The Fountain"...。これらの、正直なんの捻りもない至ってシンプルなドラム(或いはリズム・ボックス)のイントロが、私の心を震わせてきたのです。それらと同質のサムシングが、この "So Young" にはありました。期待違わず、流れてくるグラマラスな音楽は私の趣味にぴったり。淫靡なスリーヴや粘っこく時折引っ繰り返る Brett のヴォーカルは好みが分かれるところでしょうが、この Brett と艶かしい Bernard Butler のギターとの絡みは、ギター・オリエンテッドなロック・バンドの醍醐味を味あわせてくれますし、先述の "So Young" を始めとしてシングル・カットされた "Metal Mickey"、"The Drowners" など楽曲も粒揃い。Suede と言うとどうしても倒錯した歌詞が注目されがちですが、私は英語はわからないので、これ幸いと(?)純粋にポップ・ソングとして楽しんでいます。ちなみに、ほぼ同時期だと思うのですが、アメリカで Chainsaw Kittens がグランジの(ある意味)立役者 Butch Vig をプローデューサーに迎えて "Flipped Out in Singapore" と言うグラムなアルバムをリリースしています。こちらはちょっと B 級っぽいキワモノさが目立ってますが、妖しげでなかなかの良作。実のところ、ブリットポップの勃興以来ロック的なものに嫌気がさしてブラック・ミュージックにのめり込んでしまったので当時の状況がよくわからないのですが、ネオ・グラムな盛り上がりがそこかしこであったのでしょうか。そう言えば、日本の Yellow Monkey もこの辺りのデビューでしたっけ? 【Track Listings】01. So Young02. Animal Nitrate03. She's Not Dead04. Moving05. Pantomime Horse06. The Drowners07. Sleeping Pills08. Breakdown09. Metal Mickey10. Animal Lover11. The Next Life
2012.09.09
コメント(0)
-
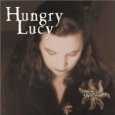
Hungry Lucy "Apparitions"
アメリカはオハイオ州シンシナティ出身、War-N Harrison と Christa Belle の男女二人のデュオによる 1st アルバム。彼女らの音楽はダーク・ウェーヴとかトリップ・ホップ、或いはダウン・テンポと紹介されることが多いようです。でも実際にはそれらの所謂ジャンルやカテゴリーが現しているものは結構曖昧です。「トリップ・ホップ」と言う言葉(随分拡大解釈されていますが)から Portishead や Massive Attack を連想する人もいるでしょうし、初期の Hooverphonic のようなポップでダンサブルなものを思い浮かべる人もいるでしょう。その曖昧さ故に私も言葉で「音」を表現する時に、ついつい便利に使ってしまうんですが。で、この Hungry Lucy、先述のトリップ・ホップ、もしくはダウン・テンポとでも表現のしようがない音楽なのです。それは、独創的だとか個性的とか言った意味合いではなく、むしろ逆。Hungry Lucy ならでは、の部分はかなり希薄。本作中の楽曲のみならず、既にリリースされている(本作を含めて) 4 枚のアルバム、どれをとっても私の印象はダンゴ状態で、正直どれがどれだか解からなくなることもあります。メロディーとか音の選び方とか、何処かで聴いたことがあるような、そんな既視感に溢れています。全然褒めてませんねぇ。でも、好きなんです。雰囲気勝負と言ってしまえばその通りなんですが、Christa Belle 嬢の、優雅にたゆたうようでいて何処か儚げ、気付いたときにはどこか空間の隙間に吸い込まれてでもいそうなヴォーカルが、私の好みにドンピシャなのです。ただ、それだけ。なので、お薦めは致しません(笑)。【Track Listings】01. Alfred02. Blue Dress03. Bound In Blood (Insomnia Mix)04. Grave05. Blame06. Stretch07. Journey08. Cover Me09. Bound In Blood (Waltz Lullaby)10. Bed Of Flames11. Stretch (Battery Mix)12. Grave (Digger Mix)13. Ode14. Goodbye
2012.09.05
コメント(0)
-
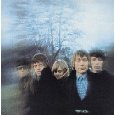
Rolling Stones "Between The Buttons"
"Aftermath" に続き全篇 Mick Jagger & Keith Richards コンビのオリジナル楽曲で固めた 5 枚目のアルバム。私が初めてこの作品を購入した頃(今からウン十年前になりますが)、当時はぼんやりとしてインパクトに欠けるスリーヴと相俟ってか、 Stones のキャリア史上最も印象の薄いアルバム、みたいな感じで評価は散々だったように記憶しています。同時代のライヴァル、Beatles や Bob Dylan、Kinks 等の影響、もしくは対抗意識があからさま過ぎて、その辺りも敬遠される理由なのかもしれません。でも、じっくり聴いてみるとこれが結構クルんです。冒頭の "Yesterday's Paper" は、60 年代はいざ知らず、現代においては噴飯モノ(?)の「昨日の女なんて要らないよ」なんて言う歌詞は置いとくとしても、Stones の楽曲の中でも指折りの美メロだし、決して上手くはないバック・コーラスもすごくポップ。その上、ザイロフォンだのハープシコードだのが入り混じってアレンジも派手。続く "My Obssesion" では、左チャンネルのピアノと右チャンネルのドラム、下の方でのたうってるベースがそれぞれ勝手気ままに鳴っていて、これまた不思議な空間を生み出しています。一転してメローな "Back Street Girl" ではアコーディオンが、"All Sold Out" ではリコーダー、Stones らしさ(?)の欠片もない "Cool,Calm & Collected" に至ってはカズーまで動員しています。"Plese Go Home" での左チャンネルでひたすらズンドコ鳴ってるドラムも相当可笑しいし、"Who's Been Sleeping Here?" における Mick Jagger の唱法は、そこまでしなくても良いだろ、って言う程にモロ Dylan。こんなやり過ぎ感が、実は本作の肝、だったりして。このアルバム、総じてアレンジが変。やはり来るべき "Their Satanic Majesties Request" の為の習作だったのでしょうか。次作のように徹底すればそれなりに評価されたのかもしれませんが、本作での未整理で拙い、まるで闇鍋のように混沌とした Stones はなかなか理解されませんでした。オープニング・ナンバーが "Yesterday's Papers" で、エンディングを飾るのが "Something Happened To Me Yesterday" と題された、この "Yesterday" 繋がりも混沌に更なる罠を仕掛ける為に意図されたものなのでしょうか。余談ですが、スリーヴの Brian Jones はちょっと、いや、かなりショボ過ぎです。よくもこんなので OK 出したなぁ。バンド内での Brian の発言力の低下がこんなところにも、と思わず涙する私でした。【Track Listings】01. Yesterday's Papers02. My Obsession03. Back Street Girl04. Connection05. She Smiled Sweetly06. Cool,Calm & Collected07. All Sold Out08. Please Go Home09. Who's Been Sleeping Here?10. Complicated11. Miss Amanda Jones12. Something Happened To Me Yesterday
2012.09.03
コメント(0)
-
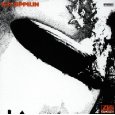
Led Zeppelin "Led Zeppelin"
既に解散後 30 年以上経つにもかかわらず、21 世紀の現在においてもなおロックの巨人として高く聳え立つ Led Zeppelin の記念すべき 1st アルバム。私がロック・ミュージックにのめり込んで 1、2 年経った辺りでしょうか。イギリスはロンドンからパンク・ロックの波が極東の島国にも押し寄せてきました。中学生だった私は他愛もなくその波に飲み込まれてしまったのですが、それまで私が聴いてきた Beatles や Rolling Stones 等のアーティストは一部のメディアから(「ニュー・ウェーヴ」に対して)オールド・ウェーヴと揶揄され、そんな風潮に(?)まんまと乗せられた私たちの小さな世界の中でも、彼らの音楽が好きで、それもかなり熱心に聴いていることを大っぴらには出来ない奇妙な雰囲気が出来ていました。そんな「オールド・ウェーヴ」の中には、勿論 Led Zeppelin も含まれていたのです。今となっては下らないジョークみたいなものです。それはさておき。Led Zeppelin のアルバムというと、冒頭を飾るオープニング・ナンバーの鮮烈さが印象的です。2nd における "Whole Lotta Love" しかり、3rd の "Immigrant Song" しかり、はたまた "Presence" での "Achilles Last Stand" しかり。本作においては "Good Times Bad Times" がきっちりとその役目を果たしています。特にイントロのもったいぶったブレイク部分が秀逸で、いやが上にも期待を増幅させます。更に、躁的な "Good Times Bad Times" の直後に、真逆の鬱的な "Babe I'm Gonna Leave You" を配するなど、デビュー作とは思えない計算された作り。視覚的ギミック(ギターの弓弾き等)を奪われたなかにあってはやや冗漫な印象が拭えないライヴ盤とは違い、起承転結がよりはっきりとした "Dazed And Confusion"、Yardbirds 時代の "White Summer" の続編とでも言うべきエキゾチックなインストゥルメンタル "Black Mountain Side"、これぞ Zep 流ハード・ロック "Communication Breakdown"。いやぁ、もう満腹です。【Track Listings】01. Good Times Bad Times02. Babe I'm Gonna Leave You03. You Shook Me04. Dazed And Confused05. Your Time Is Gonna Come06. Black Mountain Side07. Communication Breakdown08. I Can't Quit You Baby09. How Many More Times
2012.09.01
コメント(0)
-
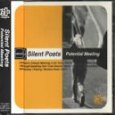
Silent Poets "Potential Meeting"
下田法晴と春野高広から成るダブ・ユニットの 2nd アルバム。前作に引き続き全曲インストゥルメンタル。一聴、サックスが大きくフィーチャーされていて、全体の音処理自体はダブ的ですが、ジャジーな印象がかなり強く感じられます。ちょっと聴く分には非常におしゃれな音楽。次作 "Words And Silence" 以降、より顕著となる、かすかに感じる透き通るような哀しさと表現すれば良いのか、聴き終えた後に引掻き傷のように残るメランコリックな感覚とでも言うべきものが、この段階ではまだ希薄に思えます。音そのものは都会的で洗練されているだけに、聞き流されてしまう危うさも一方で感じてしまうのです。勿論、私個人が勝手に、そう言った(メランコリックな)ところを彼らの美質と感じているから、と言うだけの話なのかもしれません。とりわけ、初めて聴いた Silent Poets の作品が "For Nothing" と言う、ある意味「遅れて来た」ファン故の事情も多分に影響しているでしょう。Little Creatures の青柳拓次を始めとしてゲスト・ミュージッシャンのクレジットは僅かに 4 人だけですが、トランペットやウッド・ベース等控え目ながらも要所要所で耳に残る素敵な音を発しています。個人的には終盤の "Waiting" から "Moment Scale *remix" へと続く流れが大好きです。【Track Listings】01. (There's Always) Meaning In The Tone02. Painter03. Step Out04. Bassman's Talk05. Rough Speaking Dub06. Cool Ground *remix07. Foundation (Equipment From Dubwise)08. Waiting09. Moment Scale *remix
2012.08.29
コメント(0)
-

不失者 "Live 2nd"
1 枚目のアルバムと恐らくほぼ同じ装丁のスリーヴ。黒一色の中に淡く「不失者」の名前が浮かび上がっていますが、前作と同様、それが単にユニット名を表しているだけなのか、或いはこの 2 枚組のライヴ盤の総体を称しているのか皆目不明。更に、これまた黒地に銀色(?)の読みにくい書体で短文が綴られている 20 ページばかりのブックレット。多分、歌詞なのでしょうけれど、曲名らしきものは一切なし。演奏者、プロデューサー、録音場所等の記述もなし。これほどまでに不親切な作品というのも他に類を見ないのではないでしょうか。先入観なしに取り敢えず音を聴いてくれ、話はそれからだ、と言うことなのかもしれませんが。CD 2 枚、全 13 曲で 150 分弱。不失者と言えば「轟音」と言うイメージを覆すが如く、(彼らの作品にしては)比較的静かな音が続きます。そんな中でも、さすがに「リヴァーブ・ジャンキー」を標榜するだけあって様々な「残響」を味わうことが出来ます。とりわけ、1 枚目の 3 曲目(ああ、曲名がないと不便だぁ!)の、思わず居住まいを正したくなるほどに静謐な音の繋がりと消え入りそうなヴォイス、それらを包み込む深い闇のような残響には、なにかしら「聖」的な感覚すら抱いてしまいます。2 枚目の 2 曲目(ああ、曲名がないと(以下省略))辺りから、所謂「轟音」らしきものが現れ始めます。残念ながら私は不失者のライヴを観たことがないので、本作の収録順が実際のライヴの進行と同期を一にしているのどうかは判断出来かねます。フェイド・アウトで終わる曲もありますし、灰野敬二のソロっぽく感じるところもあります。多少の編集はあるのかなぁ。でも、なかなか悪くはない流れなのじゃないか、と思います。そして、やはり圧巻はラスト、2 枚目の 7 曲目(ああ、(以下省略))。永らくロックに親しんできた私としましては正にカタルシス効果絶大です。不失者としては極めて珍しい、オーセンティックと評しても過言ではないほどに真っ当で(?)カッコ良いロック・ナンバーが堪能出来ます。歌詞も灰野氏のヴォーカルも妙に(笑)ロックっぽいです。【Track Listings】- PSFD-15 -01. [untitled]02. [untitled]03. [untitled]04. [untitled]05. [untitled]06. [untitled]- PSFD-16 -01. [untitled]02. [untitled]03. [untitled]04. [untitled]05. [untitled]06. [untitled]07. [untitled]
2012.08.27
コメント(0)
-

U2 "Boy"
今や押しも押されぬ世界的ロックン・ロール・バンドとなった U2 の 1st アルバム。邪気のない、一心にこちらを見つめる少年の瞳が、歳を経る毎にチクチクと突き刺さるスリーヴは秀逸。当初はかの Martin Hannett がプロデュースする予定だったとか。結果的に Steve Lillywhite に託して正解でしょう。Martin Hannett お得意の(?)意味あり気な SE や屈折した、輪郭の曖昧な音像では、この時点でのケレン味のない、どこまでもど真ん中の直球勝負的な U2 の魅力を生かし切れたとは思えません。思いの丈を余すところなく吐き出すかの如き感情過多な Bono のヴォーカルは、正直当時ですらキツく感じる部分はあったのですが、歌詞とは裏腹に飛び切りポップな "I Will Follow"、ミディアム・テンポの "An Cat Dubh" のエンディングを引き継いで、シームレスに繋がる "Into The Heart" の感情を押し殺したような、焦らすような長いイントロ、それに続いて前曲までの鬱屈(?)を振り払うように弾ける "Out Of Control"、これぞ The Edge の代名詞みたいなディレイを効かせたギターが聴ける "The Electric Co." 等々、こうやって改めて聴きなおすと今でも好きな曲が多いことに気付かされます。って言うか、結構空で歌えたりして(笑)。私にとっての U2 は、やっぱり "War" まで、かなぁ。【Track Listings】01. I Will Follow02. Twilight03. An Cat Dubh04. Into The Heart05. Out Of Control06. Stories For Boys07. The Ocean08. A Day Without Me09. Another Time,Another Place10. The Electric Co.11. Shadows And Tall Trees12. [untitled]
2012.08.23
コメント(0)
-
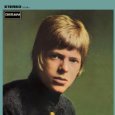
David Bowie "David Bowie"
Beatles の "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" を筆頭に、その亜流と言われ評価は散々だった Rolling Stones の "Their Satanic Majesties Request"、或いは Jimi Hendrix Experience の "Axis: Bold As Love"、Pink Floyd "The Piper At The Gates Of Dawn"、、、挙げればキリがないですが、要はサイケデリック花盛り、サイケにあらずんばロックにあらず、とまで言われたかどうかは定かではありませんが、そんなお花畑な 1967 年のイギリスでひっそりとリリースされた David Bowie の 1st アルバム。私は随分長い間 "Space Oddity" こそが David Bowie の処女作だと信じていたのですが、多分 20 歳過ぎてからでしょうか、それ以前にも実はアルバムを発表していたことを知りました。それが、本作です。ヴォードヴィル調の "Little Bombardier"、不気味な鐘の音や雷鳴轟く SE のみをバックに芝居気たっぷりに歌う "Please Mr.Gravedigger" (gravedigger は墓堀人の意)、アルバム随一のポップさを持ちながらシングル・ナンバーとしては撃沈したキャッチーな "Love You Till Tuesday" 等々。聴き込めばそれなりに面白味もありますが、正直 David Bowie の作品じゃなかったら買わなかったかも。本作に手を出すのは、取り敢えず彼の 70 年代の黄金期、2nd アルバムの "Space Oddity" から "Low"、"Heroes" 辺りまでを一通り体験してからでも良いんじゃないでしょうか。【Track Listings】01. Uncle Arthur02. Sell Me A Coat03. Rubber Band04. Love You Till Tuesday05. There Is A Happy Land06. We Are Hungry Men07. When I Live My Dream08. Little Bombardier09. Silly Boy Blue10. Come And Buy My Toys11. Join The Gang12. She's Got Medals13. Maid Of Bond Street14. Please Mr.Gravedigger
2012.08.22
コメント(0)
-
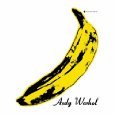
Velvet Underground "Velvet Underground & Nico"
言わずと知れた Velvet Underground (以下、V.U.)の 1st アルバム。以前、King Crimson の "In The Court Of The Crimson King" を取り上げた際に、「ポピュラー音楽史上最も語られた作品のひとつ」と評しましたが、この V.U. の 1st アルバムも負けず劣らず人の口にのぼった作品です。と同時に、語られた(今後も語られ続けるでしょうが)頻度に反比例するが如く、セールスが捗々しくないことでもこれまた人後に落ちないのではないでしょうか。私が V.U. を初めて知ったのは確か高校に入った頃でした。来日中の Lou Reed と当時新進気鋭の作家村上龍との対談が、何故か『ミュージック・ライフ』に掲載されていたのです。『ミュージック・ライフ』と言えば、『明星』、『平凡』と言ったアイドル雑誌の洋楽版のような雑誌で、(アーティストのルックスも含めて)ヴィジュアル重視の紙面作りが特徴であったように記憶しています。その雑誌になんとも奇妙な取り合わせの対談。すでに V.U. は解散していましたが、不思議なバンド名と鉄仮面のような(失礼) Lou Reed の表情は、初心な高校生の脳裏に快とも不快とも知れない引掻き傷を作ったのです。その後しばらくしてレコードは購入したのですが、地方都市の高校生の手に負える代物ではありませんでした。なにしろ恐る恐る針を落とした途端流れてくるのが、まるで聴き手の期待を嘲笑うかのような脱力感満載のフォーク・ソング "Sunday Morning" ですから。但し、この曲、左チャンネルからわずかに聞こえるコーラスがちょっと怖いです。この声は Nico かなぁ。気持ちの良い日曜の朝に散歩してたら、知らぬ間に誰かに手を取られて仄暗い世界に引き摺り込まれそうになった、そんな感じです。あっ、やっぱり書き出すとキリがなくなりそうですね。ノイジーで混沌とした "Heroin" や "European Son" と、ポップなロックン・ロール "I'm Waiting For The Man" や "There She Goes Again" が素知らぬ顔で平然と同居する面白さ。そして一部の方々からは鬼子扱いの、Nico が歌う "Femme Fatale" や "All Tomorrow's Parties" の美しさなくしてこの作品は有り得なかった、と私は思います。【Track Listings】01. Sunday Morning02. I'm Waiting For The Man03. Femme Fatale04. Venus In Furs05. Run Run Run06. All Tomorrow's Parties07. Heroin08. There She Goes Again09. I'll Be Your Mirror10. The Black Angel's Death Song11. European Son
2012.08.17
コメント(0)
-
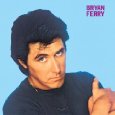
Bryan Ferry "These Foolish Things"
1973 年にリリースされた Bryan Ferry の 1st ソロ・アルバム。この年、本作の他に Roxy Music 本体のアルバム、"For Your Pleasure"、"Stranded" とを併せて実に 3 枚ものアルバムをリリース。創作意欲がピークに達していた結果と考えるか、意地悪く Brian Eno との確執が相当ストレスとなっていたが故(気分転換?)のソロ・アルバム・リリースと考えるか。真相は如何に。中味は既にご存知の通りの全曲カヴァー。しかも、Bob Dylan、Rolling Stones、Beatles に Miracles と、大ネタばかり。普通はちょっと躊躇いそうなもんです。止めるヤツは居なかったのか。しかも、楽曲のみならず Dylan を筆頭に、Mick Jagger しかり、Smokey Robinson しかり、Janis Joplin しかり、個性的なシンガーのレパートリーがずらり。ただでさえヘタウマ・ヴォーカルの元祖とまで言われる Ferry さんがカヴァーするんですから、すごいチャレンジ精神です。自爆覚悟ですか?そう言うところも一切合財込みで、私は大好きなアルバムです。派手なホーン・アレンジや女声コーラス。Roxy Music よりもリラックスして聴こえる Ferry のヴォーカル。そして、なにより彼の手によって「時代」と言うコートを脱がされて素の表情を見せる楽曲群。とりわけキューバ危機をモチーフに書かれたという "A Hard Rain's A-Gonna Fall" や、ウッドストック世代のアンセムのひとつと言えるであろう "Piece Of My Heart"、60 年代末期の混沌としたロンドンにおいて Rolling Stones の悪魔的イメージを決定付けた "Sympathy For The Devil" (この曲での Ferry さんはちょっと力入り過ぎですが)と言った作品が、時代性や社会への影響等を度外視して「ポップ・ミュージック」として素晴らしいものであると言う単純な事実を再確認させてくれる、それが意図されたものかどうかは別にしても、そう言う意味合いにおいてもこのアルバムを聴く価値は十分あると思います。【Track Listings】01. A Hard Rain's A-Gonna Fall02. River Of Salt03. Don't Ever Change04. Piece Of My Heart05. Baby I Don't Care06. It's My Party07. Don't Worry Baby08. Sympathy For The Devil09. The Track Of My Tears10. You Won't See Me11. I Love How You Love Me12. Loving You Is Sweeter Than Ever13. These Foolish Things
2012.08.14
コメント(0)
-

John Zorn "Naked City"
ジャズに留まらず多岐に渡る活動でつとに知られたアルト・サックス奏者 John Zorn の 1989 年の作品。一応ソロ名義のようですが、Fred Frith や Wayne Horvitz、或いはゲストの山塚アイなどお馴染みのメンバーが勢揃いしているので、Naked City の実質的な 1st アルバムと考えて良いのではないでしょうか。深夜の路上に打ち捨てられた射殺死体(或いは、自殺?)を写したスリーヴの殺伐とした薄ら寒さとは裏腹に、オリジナル楽曲と "James Bond Theme" や "A Shot In The Dark"(『ピンク・パンサー』シリーズ)と言った、恐らく 40 代以上の方なら、ああ、あの映画ね、と首肯出来る程に有名な映画音楽のカヴァーを交えた作品は、なかなかにポップで聴き応え十分な内容です。カヴァー物はどちらかと言えばオーソドックスでまっとうな演奏。オリジナルはこれぞ Naked City と言いたくなるほどブッ飛んでます。超多作な John Zorn の活動を把握することは私には到底不可能なのですが、彼の作品の中でも取っ付き易い部類に入るんじゃないでしょうか。特に 10 曲目~ 17 曲目辺りの山塚アイの意味不明の絶叫をフィーチャーした目まぐるしく立ち現れては一瞬で消えていく作品群は、グラインド・コアだのスラッシュ・メタルだのエクストリームなロックが好きな方ならきっと気に入ると思います。26 曲も入ってますが、一番長い曲でも 5 分弱。逆に短いものになると 20 秒程度といったものまであります。ほとんどイントロだけじゃないか、みたいな(笑)。1 曲の中でもころころと曲調が変わるので、あっと言う間に一枚聴き終わってしまいます。【Track Listings】01. Batman02. The Sicilian Clan03. You Will Be Shot04. Latin Quarter05. A Shot In The Dark06. Reanimator07. Snagglepuss08. I Want To Live09. Lonely Woman10. Igneous Ejaculation11. Blood Duster12. Hammerhead13. Demon Sanctuary14. Obeah Man15. Ujaku16. F**k The Facts17. Speedball18. Chinatown19. Punk China Doll20. N.Y.Flat Top Box21. Saigon Pickup22. The James Bond Theme23. Den Of Sins24. Contempt25. Graveyard Shift26. Inside Straight要らない注釈 : 16 曲目のタイトル、"**" の部分には "uc" が入ります(笑)
2012.08.11
コメント(0)
-
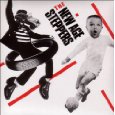
New Age Steppers "The New Age Steppers"
Slits の Ari Up や Pop Group の Bruce Smith などから成るダブ・ユニット New Age Steppers の 1st アルバム。パンク~ニュー・ウェーヴ辺りから音楽に熱中し始めた我々世代においては、New Age Steppers がダブの入口になったという方は結構いるんじゃないでしょうか。12 ~ 13 歳ぐらいだったでしょうか、従姉から教えられた Beatles で初めてロック・ミュージックを知り、それからと言うものロックばかりを聴いていました。Rolling Stones、Led Zeppelin、David Bowie・・・。そんなロック一辺倒の音楽生活から抜け出す切っ掛けは、意外にもパンク・ロックでした。Sex Pistols と並びロンドン・パンクの雄であった Clash はレゲエ/ダブにのめり込み、Jam はソウルやファンクを奏でるようになっていました。私も知らず知らずそれらの音楽に聴き馴染むようになり、いつの間にやらジャンルの垣根を飛び越えてなんでも聴くようになったのです。今更(?)パンクの CD を引っ張り出してきて聴くことも年々少なくなってきていますが、音楽の世界を格段に広げてくれたパンクには感謝多謝です。で、New Age Steppers です。ギター・パートには 3 人、ドラムスにはなんと 5 人ものミュージッシャンの名前がクレジットされており、パーマネントなグループと言うよりはもっとフレキシブルなセッション・グループとでも言った感じだったのかもしれません。そして、そんな中でも、ちょっと素っ頓狂に聴こえないこともありませんが、Ari のチャーミングなこと!ダブ・ユニットと言う性格上全面に渡ってフィーチャーされているわけでもありませんが、やはり彼女の歌声は耳に残ります。【Track Listings】01. Fade Away02. Radial Drill03. State Assembly04. Crazy Dreamsand High Ideals05. Abderhamane's Demise06. Animal Space07. Love Forever08. Private Armies- Bonus Tracks -09. Izalize10. May I11. Avante Gardening12. Singing Love
2012.08.10
コメント(0)
-
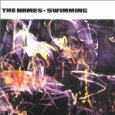
Names "Swimming + Singles"
Michel Sordinia 率いるネオ・サイケデリア、Names が唯一残したアルバム "Swimming" にシングル・ナンバーを追加収録して CD 化した作品。私はシングルやアルバムのスリーヴの美しさに惹かれてアナログ盤を買っていました。ややこしいですが、2 曲目から 6 曲目までが 1st アルバムの A 面にあたり、B 面に相当する部分が 9 曲目から 12 曲目。要するにアルバム収録曲がシングル等アルバム未収録の作品にサンドウィッチされた構成です。ちなみに、オリジナルのアナログ盤は曲間(通常は無音の部分)に、タイトルにちなんでかあたかも水中に潜っているかのような SE を挿入しているのですが、本 CD はそれをそっくり引き継いでいる為、なにがなにやらワケのわからないことになっております。80 年代当時、雨後の筍のごとく湧き出た Joy Division フォロワーのひとつ、と評して間違いはないと思いますが、初期の作品 "I Wish I Could Speak Your Language" や "Cat" などは、1st ~ 2nd 辺りの Cure に通低する青白い青春ポップ・ソングでしょうか。ベルギーでひっそりと活動していればそれはそれで彼らにとっても幸せだったような気がしますが、世に好事魔多し。何故か Factory Records の目に留まり、幸か不幸か Martin Hannett 全面プロデュースの基アルバムを製作する破目に陥ります。Martin Hannett プロデュースと言う事は要するに全部 Joy Division の劣化版にされてしまうってことです。靄のかかった森の向こう側から聴こえて来る様な、ネオ・サイケと言ってしまうにはあまりにも淡く、切ないメロディーが続きます。薄く全篇を覆うシンセサイザーの音が儚さを助長しているように思えます。同じような曲調が続く為単調な印象になるきらいはありますが、(極々一部で)名作の誉れ高き "Calcutta" を始めとして個々の作品のグレードは決して低くありません。恥ずかしながら、私の青春の一枚、と信仰告白させて頂きます。余談ですが、"Nightshift" の PV における、かなり特異な風貌な割りに薄い印象、ジャケットのポケットに両手を突っ込み猫背気味にフレームアウトしていく寂し気な姿は、どう見ても吉本新喜劇の「Mr.オクレ」です(笑)。【Track Listings】01. Music For Someone02. Discovery03. Floating World04. The Fire05. Life By The Sea06. White Shadow07. Calcutta08. Postcards09. (This Is)Harmony10. Shanghai Gesture11. Leave Her To Heaven12. Light13. Nightshift14. I Wish I Could Speak Your Language15. The Astronaut16. Cat
2012.08.08
コメント(0)
全189件 (189件中 1-50件目)