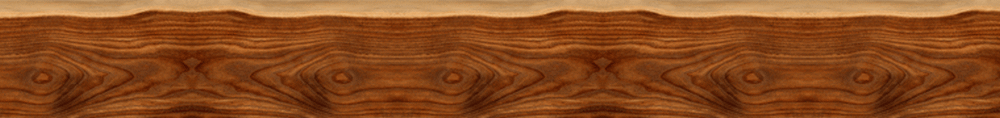#4(1) 一粒の種と欲

02年12月号(1)
新年明けましておめでとうございます!
2年ぶり・・・でしょうか。お久しぶりです。お元気ですか?どこで何をやっているのかと思っている方もいらっしゃるかもしれません。アジア学院にて4回目の冬を迎えています。2002年度のアジア学院は、アジアからミャンマー、スリランカ、パキスタン、アフリカからシラリオネやカメルーンなど14カ国から32名の研修生とデンマークや日本のボランティア12名を迎えて学びの生活がありました。共同体で生活し、いのちを支える食べものを中心に自給自足の生活。アジア・アフリカやヨーロッパ等のたくさんの国々から人々が集まる、ユニークな場所。4年目にして何を感じながら日々過ごしているのか、お知らせしたいと思います。
寮を出る

2001年の夏、2年半過ごしたアジア学院の女子寮を出、一人暮らしを始めた。アジア学院のメンバーとの共同生活は自分にとってすごく心地よい空間だった。でももっと現実的になりたかった。“共に生きるための社会作り”というアジア学院が求め、目指すこのビジョン。アジア学院の中に住み、理解のある人に囲まれ、守られて自己満足しているだけなのではないかと思うようになった。現実の社会の中でどうすればいいのか。自分で食べるものを作り、残ったら土に返し、一人暮らしの中で環境のことや自分のとる行動について考えてみたいと思った。
今、家の前の砂利がひいてあった場所を耕して少し野菜を育てている。あまり手入れをしなければそれなりのものにしか育たない。今、小さな畑を前にして、どんなに自分が頭でっかちであったのかとつくづく思い知らされている。
ひと粒の種と欲

なぜ自分が土や農から教えられる事が多いのか・・畑に立つとわかる。共に生きる姿勢の原点がそこにあるから。ありのままの姿を受け入れ、支える自然がそこにある。アジア学院では、木炭を細かくして畑に混ぜたり、豚のえさに混ぜたりしている。炭にはたくさんの穴があって(なんと、親指ぐらいの大きさの炭には1億ぐらいの穴があるんだとか!!)、それを土に混ぜる事で微生物の住む場所を提供する!土の視線、生き物の視線、人間の視線。人間は腰をまげ足をまげてもっともっと謙虚にならなくてはいけないのかもしれない。
人間の視点はともすれば自己中心的になりやすい。農業だけじゃない。なぜ差別が、なぜ経済格差が、なぜ戦争が、なぜ憎しみがうまれるのか、それはお金のせいだという人もいるかもしれないけれど、私はGreedのせいだと思う。これもあれもそれもと欲張る。自分の中にうもれている欲のせいだと思う。
豚の出産から思う事

今朝、豚が出産をした。10頭生まれたうち、5頭が死産だった。朝早くに生まれたため、寒さのために死んでしまっていた。そして、もう1頭も私の手の中で息をひきとった。震える命がすーっと息絶える瞬間。生きろと願ってもどうしようもない瞬間。悲しいを越えてやるせなさが残る。
これは、多くのアジア学院の研修生が彼らの国で直面している事でもある。栄養失調の子供が親の祈りもかなわず息をひきとるのは何故か。答えは単純ではない。社会の不公正や制度の問題であったり、個々人の無知のせいであったり、なぜ無知かというと、教育制度の不足であったり、男女の差別があったり。貧困は悪循環だ。それぞれの立場でやれる事は無数にある。今の自分にできることは現場で活動する農村のリーダーたちが力をつけてより良いリーダー・仕える人になるその過程を支える事。息をひきとった小さないのちを抱きながらそんなことを考えていた。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 我が家の春夏秋冬
- ブランチポイントのNERUS正規品スト…
- (2025-01-17 22:07:27)
-
-
-

- ラン好きです♪
- Den.アマビレ‘ベニボタン’とEria グ…
- (2025-02-17 16:26:20)
-
-
-

- みてみて♪お花の画像!!
- シクラメン数種&カランコエ3種&福寿…
- (2025-02-17 20:09:43)
-
© Rakuten Group, Inc.