全357件 (357件中 1-50件目)
-
「~すべし」という命令と「~すべからず」という命令
なんの本にあったのか忘れたので、違っているかもしれないが(したがって、実話かどうかは確認できない)、革命から間がない内戦中のある日のこと、当時、チェーカーの議長だったジェルジンスキーが会議中のレーニンに、「反革命」 分子として収監している囚人のリストを渡したという。 会議に没頭していたレーニンはメモに目を通したあと、×印のようなものをつけて、ジェルジンスキーに返した。メモを受け取った彼は、そこにある×印を見て、「処刑」 の指示だと思いこみ、リストにあった全員を即刻銃殺した。 ところが、あとで分かった話によると、実はレーニンには、日頃から目を通した書類にたんなる 「確認済み」 の意味で印をつける癖があったという。もっとも、いずれにしてもレーニンの指令で、多くの人間が 「反革命」 の罪により処刑されたことは、紛れもない事実ではある。 チェーカーとはロシア国内の反革命を取り締まる非常委員会のことだが、後にGPUに改組され、その初代長官もジェルジンスキーが務めている。なので、これはその時代のことなのかもしれない。GPUはようするにロシアの秘密警察であり、途中、いろいろと名前は変わっているが、最後は今のロシアの隠れ大統領であるプーチンが、かつて属していたKGBにまでつながっている。 ジェルジンスキーはもともと、ポーランドの貴族出身だそうだ。つまり、リトアニア出身のユダヤ人だったローザ・ルクセンブルグとは、一時は盟友関係にあったのだが、ローザはドイツに移住し、いっぽうジェルジンスキーのほうは、政治犯として収監されていたロシアでそのまま革命に参加し、やがてレーニンの重要な配下のひとりとなっていく。 レーニンがチェーカーの仕事を彼に任せたのには、当然その 「真面目」 で 「高潔」 な人柄に対する信頼もあっただろう。だが、おそらくは彼がロシア人ではなく、おまけに党にとっても新参者であったため、ロシア国内のいろいろな政治勢力をめぐる、複雑な人脈だの関係だのにわずらわされずにすむだろうという計算も、あったのかもしれない。 客観的に見るならば、ジェルジンスキーは党の新参者であるばかりに、「暴力」 の行使という、誰もがいやがる 「汚れ仕事」 を押し付けられたことになる。政治路線については、民族問題やドイツとの講和などで、レーニンと対立したこともあったが、党と革命への忠誠ということでは、ゆるぎなき 「良心」 の持ち主であり、野心や権力欲はもちろん、のちのベリヤのような暴力的な性癖とも無縁の人物であったとされている。 貴族の家に生まれた彼が革命運動に跳びこんだのは、いうまでもなく、抑圧されている貧しい民衆に対する 「愛」 であり、「良心」 によるものだっただろう。そのような彼にとって、いくら 「革命」 のためとはいえ、処刑というような行為が決して心地よかったはずはない。任務を終えたあと、彼はしばしば苦痛にゆがんだ蒼ざめた顔をしていたという。 つまるところ、彼もまた 「正義の人」 であったのであり、革命家としての 「良心」 に基づいた、「テロル」 の行使という任務の裏で、彼個人の良心もまた血を流し、うめき声をあげていたに違いない。そのせいかどうかは分からないが、彼は革命の九年後、レーニンのあとを追うように急死している。 ちなみに、やはりポーランド出身のユダヤ人で、トロツキー派のコミュニストから歴史家へと転じたアイザック・ドイッチャーは、『武力なき預言者』 の中で、「ゲ・ペ・ウにはいって仕事ができるのは、聖者か、でなければならずものだけなのだが、今では聖者は僕から逃げ出してゆき、僕はならずものだけとあとに残されているしまつだ」 という、GPU長官時代の彼の言葉を紹介している。 ところで、ナチス時代のドイツに、少数ながら残されていた、ナチへの協力に抵抗した人々について、やはりユダヤ人であるハンナ・アレントは、それはイデオロギーや思想などの問題ではなく、単に彼らには、友人を裏切ったり見捨てる、といった行為ができなかったのだというようなことを言っている。 これらの人々は、たとえ政府が合法的なものと認めた場合にも、犯罪はあくまで犯罪であることを確信していました。そしていかなる状況にあれ、自分だけはこうした犯罪に手を染めたくないと考えていたのです。 (中略) この 「私にはできない」 という考え方には、道徳的な命題が自明なように、その本人にとっては自明なものであるという分かりやすさがありました。「二足す二は五である」 と言うことが<できない>のと同じように、「私には無辜の人々を殺すことはできない」 ことは自明なことだったわけです。 「汝、なすべし」 とか 「あなたはそうすべきである」 という命令に対しては、「私はどんな理由があろうとも、そんなことはしない、またはできない」 と言い返すことができるのです。いざ決断を迫られたときに信頼することのできた唯一の人々は、「私にはそんなことはできない」 と答えた人々なのです。「できない」 という確信ハンナ・アレント 『責任と判断』 言うまでもないことだが、「良心」 はしばしば盲目であり、「善意」 はきわめてだまされやすい。「良心」 の命令には、「~~すべし」 という命令と 「~~すべからず」 という命令の二種類がある。前者が行為を促す積極的命令であるのにくらべ、後者は消極的な禁止命令にすぎない。 だが、消極的であるだけに、間違いをしでかしにくいのは、どちらかといえば後者である。しかし、それはおのれが最後に守るべき拠り所でもあり、その意味では、頑強なる抵抗や反攻のためのもっとも堅固な砦でもある。「いざ決断を迫られたときに信頼することのできた唯一の人々」 という彼女の言葉は、ようするにそういう意味だろう。 この 「できない」 という確信について、アレントは 「良心と呼ぶべきものだとして」 という留保をつけ、義務という性格は帯びていなかったと語っている。たしかにそれは、言語によって規範化された道徳というよりも、むしろ生理的な感覚といったものに近い。 関連記事:「美しい魂」を持った人
2010.05.08
コメント(5)
-
大文字の「良心」と小文字の良心
自動車事故で死んだカミュに、『正義の人々』 という戯曲がある。このもとネタは、革命前のロシアで、社会革命党の秘密組織の指導者として、要人暗殺などのテロを行っていた、サヴィンコフという名のロシア人革命家が書いた、『テロリスト群像』 という回想録の中にある。 サヴィンコフは、ロープシンという名で 『蒼ざめた馬』 などの小説も書いているが、革命後はボルシェビキ政権に対する武力闘争に加わり、最後は逮捕されて裁判にかけられた。そこで、いったんは死刑判決を受けたものの、「十年の禁固刑」 という特赦による減刑を受けたのち、なぜか刑務所で投身自殺をとげたとされている。 この話については以前書いたが、要約すれば、爆弾投擲による暗殺実行の任務を与えられた、カリャーエフという青年が、目標とする人物が乗る馬車に爆弾を投げようとしたものの、その中に幼い子供らが同乗しているのを見て、投げるのを止めたという話。 その多くが高い教育を受け、それなりの地位なども約束されていたでもあろう、ロシアの青年たちを、革命運動へと駆り立てたのは、むろん自由への憧れもあっただろう。だが、そこには、おそらくは貧しく抑圧されていた民衆に対する負い目という、「良心」 のうずきもあったに違いない。それは、たとえば有島武郎についても言えることだ。 「良心」なるものを定義するとすれば、おそらくは善と悪を判別する心の中の装置といったことになるだろう。むろん、善とはなにか、悪とはなにか、などという話になると、またややこしくなる。ただ、とりあえず、完全な善や完全な悪など存在しないし、善も悪も、それ自体として存在しているわけではないということは言える。 ようするに、世の中に存在しているのは、実体としての善や悪ではなく、せいぜいが 「善きこと」 と 「悪しきこと」 の相対的な区別であり、しかもそれは多くの場合、ややこしく入り組んだりもしている。ただ、その善と悪を区別する良心の基盤にあるのは、おそらくは、人間が持っている他者への 「共感」 能力というものだろう。 たとえば、『国富論』 の著者として有名なアダム・スミスは、最初の著書であり、彼自身、もっとも重要な主著と考えていたという 『道徳感情論』 の冒頭で、こう言っている。 人間がどんなに利己的なものと想定されるにしても、明らかに彼の本性の中には、いくつかの原理があり、そのおかげで、人間は他の人々の運不運に関心を持ち、彼らの幸福を、それを見るという快楽のほかにはなにも得られないのに、自分にとって必要なものとする。 この種類に属するものは、哀れみや同情であって、それはわれわれが他の人々の悲惨を見たり、生き生きと強く心に描き出されたりしたときに、それに対して感じる情動である。われわれがしばしば、他の人々の悲しみから、悲しみを引き出すということは、例をあげて証明する必要もないほど、明らかである。 もっとも、人間の心の中には、そのような原理と対立し、それを打ち消す原理もある。それは、スミスも認めている。「悪」 は、たしかにしばしば魅惑的であるし、人間は 「善」 や 「正義」 などという観念によって、生きているわけではない。しかし、そのことは今はおいておく。 われわれは、たしかに 「良心」 というような言葉を使うのは、あまりに気恥ずかしい時代に生きている。「良心」 という言葉は、たしかにあまりに濫用されすぎてもきた。いわく、信徒としての 「良心」、国民としての 「良心」、あるいは階級的 「良心」、革命的 「良心」 だのというように。 そこでは、「良心」 という言葉が、宗教や政治的イデオロギーによって、大文字化されている。しかし、そのような 「良心」 は、むしろ個人を拘束する共同的な規範にすぎない。そのような大文字の 「良心」 は、個人が持っている素朴な良心の預け先として、ときにはその本来の良心を解除させもする。大義の名による血なまぐさいテロルは、しばしばそうやって正当化される。 「良心」 というものは、おそらく心の中の知的な部分よりも、感情的な部分に属する。「良心」 への刺激が、しばしば怒りや悲しみをもたらすのはそのためだろう。それは感情的な部分であるがゆえに、たしかに統御が難しい。そのうえ、人間の情念は複雑であり、たがいに影響しあいもする。神ならぬ人間の 「良心」 は、そもそも完全でもなければ万能でもない。 だから、目の前の怪我人を助けるというような単純な行為ならともかく、政治的行為のような複雑な行為では、「良心」 という単純な装置だけに頼るわけにはいかない。「地獄への道は善意で敷き詰められている」 という、有名な格言はそのことを表している。しかし、それはそのような行為において、「良心」 が無用だということではない。ただ、「良心」 は万能ではないということにすぎない。 いうまでもなく、「良心」 は個人のものであり、人は他人の 「良心」 を代行できない。それは、精神が個人の精神としてしか存在しない以上、自明のことだ。とはいえ、それは、個々人の 「良心」 の間に共通性がまったく存在しないということは意味しない。「良心」 が善・悪を判別する心の中の装置だとして、それがたがいにまったく異なるのだとしたら、社会はそれこそ一瞬にして崩壊するだろう。 そもそも、人間が人間になるのは、他者との関係を通じてだ。孤立した人間は、人間の人間としての様々な能力、たとえば言語すらも身につけられない。つまるところ、人間の精神は個別にしか存在しないものの、最初から 「間主観性」 を帯びており、その意味でも一定の共通性を有している。それは、なにも 「良心」 のみに限られたことではない。 なるほど、「良心」 とか 「善」、「正義」 といった言葉は、たしかに手垢がつきやすい言葉である。そのような言葉を、政治の場で多用する者がいたなら、とりあえず疑っておいた方がよい。なぜなら、そのような場合、それらの言葉が指し示しているのは、実は規範化された大文字の 「良心」 や 「正義」 であり、その存在が暗黙のうちに前提とされているからだ。そのうえ、そのような言葉には、理性をマヒさせる魔力もたしかにある。 しかしながら、世の中、手垢の付きえない言葉などというものは存在しない。どんなに立派な言葉だって、手垢はつきうる。「権威を疑え!」 というような言葉ですら、ときにはただの無知な夜郎自大の正当化に利用されもする。しかし、だからといって、次から次へと、ただただ新しい言葉や言い回しを作り出せばよいというものでもあるまい。 「良心」 というような素朴で単純な言葉が、ときに手垢を帯びながらも、いまなお使い続けられているのには、それなりの根拠があるだろう。であるならば、その手垢の付いた言葉から、びっしりとこびりついた手垢をこそぎ落とすという作業も、ときには必要と言えるだろう。 社会の中の抑圧や不正に対して、ときにその直接の当事者でもない者らまでが立ち上がるのは、それが彼らの 「良心」 を刺激するからだ。そのような問題について考えるということは、とりあえずそのために必要な 「良心」 という場を呼び起こすことでもある。ただし、そこから先へ進むには、それだけでは足りない。 しかし、そこで呼び出された 「良心」 によって指し示された 「正義」 なるものが暴走を始めたなら、その暴走に歯止めをかけるのも、やはり同じその素朴な 「良心」 の役割と言えるだろう。カミュが言いたかったのは、おそらくはそういうことのように思える。参照先: 意図や目的より手続きを重視するということ 追記: 世界には 「完全なる善」 や 「完全なる悪」、あるいは 「善」 そのものや 「悪」 そのものは存在しないということは、言い換えるなら、世の中の物事は、「善」 と 「悪」 という言葉で考える限りにおいて、すべて多かれ少なかれ 「善なる性質」 と 「悪なる性質」 の両方を帯びているということを意味する。それは、「善」 と 「悪」 を厳しく対立させる正統的なキリスト教の倫理とは異なる、ユングの善悪観とも一致する。
2010.05.02
コメント(5)
-
「自由」についてつらつらと
いわゆる 「人権」 なるものはもちろん西欧起源であり、したがってキリスト教に由来する。中学の社会科では、ロック、ルソー、モンテスキューの三人を、代表的な啓蒙思想家として教えられるが、基本的人権といえば、ロックの 『市民政府二論』 ということになっている。 明治の自由民権運動では、「天賦人権」 なんて言葉も流行ったが、ようするに人権なるものは、神から与えられたものだから、たとえ国王でも侵すことはできないよ、という話。ロックは、たとえばこんなふうに言っている。 自然状態には、これを支配するひとつの自然法があり、何人もそれに従わねばならぬ。この法たる理性は、それに聞こうとしさえするならば、すべての人間に、いっさいは平等かつ独立であるから、何人も他人の生命、健康、自由または財産を傷つけるべきではない、ということを教えるのである。人間はすべて、唯一人の全知全能なる創造主の作品であり、すべて、唯一人の主なる神の僕であって、その命により、またその事業のため、この世に送られたものである。 ロックは17世紀後半のイギリスの人で、こういう彼の思想は、同時代の名誉革命や 「権利の章典」、さらには遠く離れた、海の向こうのアメリカの独立宣言とかにも、反映されている。 イギリスが議会の発祥国であることは誰でも知っているが、ロックより前の世代の人で、渡辺淳一でないほうの 『失楽園』 で有名なミルトンは、クロムウェルの政府を支えた一人であり、『言論・出版の自由』 などの人民の権利を擁護する政治的パンフレットも数多く残している。彼もまた、自由という権利に対して大きな貢献をした人の一人である。 しかし、人間の権利として 「自由」 なるものが与えられたからといって、それだけで人間は自由だ、ということにはならない。たとえ、奴隷のような拘束を受けていないとしても、それでもなお、本当に自分が 「自由」 かどうかは定かではない。そもそもロックやミルトンが 「人間は自由だ」 と言ったのは、人間は神の子であるという宗教的信念に基づいている。では、「自由」 とは、そもそもいったいなんのことなのか。 やはり17世紀の啓蒙思想家で、オランダに住む在野のユダヤ人哲学者であったスピノザは、「自由」 について、こんなふうに言っている。 自由といわれるものは、みずからの本性の必然性によってのみ存在し、それ自身の本性によってのみ行動しようとするものである。だがこれに反して、必然的あるいはむしろ強制されていると言われるものは、一定の仕方で存在し作用するように、他のものによって決定されるもののことである。『エティカ』 第一部より スピノザがここで言っているのは、神の自由について。少なくとも一神教においては、神とは定義上、唯一にして最高の存在であるから、他のものから、ああせい、こうせいと命令されたりはしない。神の行為は、すべて神自身の内発的意思によるものであり、だからこそ、神は絶対的に自由なのである。 だから、フォイエルバッハがいうように、人間の運命だとか幸不幸だとかを思い煩ったり、人間のお祈りだの呪文だのにほいほい呼び出されて、お願いされるままに、雨を降らせたり、風を吹かせたりするのは、人間様の下僕であって、本物の神様ではない。 したがって、自由とは結局 「意思」 の自由に帰着する。神様ほどではないが、人間も、いちおう自分の意思を持っている。暗闇の中を飛ぶ虫や、夜の海を泳ぐ魚などは、明るい光を見つけると、思わず知らず引き寄せられるが、それでは磁石に引き付けられる鉄粉と変わらない。その結果、まんまと人間様の罠にはまって、火で焼かれたり網ですくいあげられて、身の破滅を嘆くことになる。 しかし、人間ならば、たとえ少々腹が減っており、おいしそうなお菓子とかがテーブルの上にあるのを見つけても、待てよ、これは誰かの罠ではないかなとか、毒入りではないかな、腐ってないかな、黙って食べたらあとで怒られないかな、などと少しは考えるだろう。つまるところ、「意思」 の自由とは、この場合、即自的な直接の欲求に身を任せずに、抵抗する力のことを意味する。 日本国憲法では、自由権として 「思想および良心の自由」 とか 「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」 などといった権利が保障されている。そのような国民の権利を国家が侵すことは、当然ながら憲法違反である。だから、国家は国民を、その思想や信仰などで差別してはならないし、本人の自発的意思によらずに、個人の内心の告白を迫ったり、「踏絵」 を踏ませるような行為を行ってはならない。 たしかに、これによって、われわれの 「内心」 は、いちおう国家だの政治的権力だのによる、直接の介入は受けないことになっている。では、それによって、われわれの 「内心」 なるものは、本当に自由なのだろうか。 たとえば、上役の命令によって、公園に住むホームレスのテントを破壊する県や市の職員とか、上官の命令によって、非武装の市民の上に爆弾を落としたり銃弾を浴びせたりする兵士とかは(これは今のところ日本の話ではないが)、はたしていかなる 「良心の自由」 を持っているのだろうか。 「内心」 というものは、たしかに人間にとっての最後の抵抗の砦のようなものだ。たとえば、隠れキリシタンはその 「内心」 によって、「踏絵」 による詮議は受け入れながらも、250年もの間、キリストへの信仰を保つことができた(もっとも、もとの信仰からは、ずいぶんと変わってはしまったが)。 全体主義国家でも、独裁者への 「面従腹背」 を貫くことで、おのれの 「内心の自由」 を守り続けることがまったく不可能なわけではない。軍国主義時代の日本にだって、みんなと一緒に 「天皇陛下ばんざーい」 と大きな声をあげていても、心の中では 「こんな馬鹿なこと、やってらんないよ」 などと思っていた人も、おそらくはいたことだろう。 だが、それは口で言うほど簡単なことではない。街中には、独裁者のでっかい肖像や銅像が並び、扇情的な音楽が大音量で流され、みながみな独裁者を讃え、反対派を 「反革命」 だの 「非国民」 だのと罵っている中で、おのれの 「内心」 を保つことはけっして易しいことではない。そのためになにより必要なのは、おそらくは理性や良心に裏打ちされた、周囲に流されない強い意思であり、おのれの正しさに対する確信ということになるだろう。 むろん、現代ではかつてのような 「欲しがりません、勝つまでは」 とか、「贅沢は敵だ!」 みたいな国家による宣伝は行われていない。しかしながら、どんな時代にも、国家や政治家らは、国民に対していろいろな宣伝を行っている。学校だって、ある意味、子供らに対する一種の 「洗脳装置」 である。 現代社会には、その他にも様々な情報があふれている。政治的宣伝だけでなく、あれを買え、これを買え、というような情報もいっぱいある。そのすべてが無意味というわけではないが、われわれは少なくともそういう社会の中に生きている。そして、われわれの 「内心」 なるものは、そのような情報の洪水の中に曝されている。 「内心」 なるものがどこに隠されているのか、頭の中なのか、胸の奥なのかは知らないが、いずれにしてもわれわれの 「内心」 なるものは、爆弾が落ちても大丈夫なような、頑丈な金庫の中に隠されているわけではない。憲法で 「内心の自由」 なるものが保障されているからといって、われわれの 「内心」 というものは、そもそもそんなに確固としたものではない。 あれやこれやの情報に左右されて右往左往したり、空っぽの権威にすがったり、ただ大勢の意見や行動に付和雷同してくっついて行動するのは、自分の意思で動いているように見えるが、本当はそうではない。スピノザに言わせれば、そんなものは全然自由ではない、ということになるだろう。 むろん、神ならぬ人間としては、自分の内心など完全に統御できはしない。欲望や気分、感情といったものを完全に統制することは、お釈迦様でもない限り、不可能だ。誰しも、突如として 「邪悪」 な欲望を抱いたり、どうにもならない怒りや悲しみの感情に襲われることはあるだろう。 しかし、そういった欲望や感情の発生そのものは統御できぬからといって、そのようなものに支配され、その赴くままに流されてしまうかどうかは、全然別の話。人間はたしかに 「不自由」 であるが、そればかりをただ嘆いていたのでは、人間の 「自由」 などどこにも存在しないことになる。
2010.04.25
コメント(5)
-
ポーランド航空機墜落のニュースを聞いて
一昨日、ロシアのスモレンスクで行われる予定だった、第二次大戦中に起きた 「カティンの森」 事件の追悼式典に参加するために現地に向かっていた、ポーランドの大統領夫妻ら、多数の政府要人を乗せた飛行機が墜落し、全員が死亡するという事件があった。情報によれば、深い霧で視界が悪かったため、ロシア側は別の空港への着陸を要請したにもかかわらず、無理に着陸を試みたことが原因のように思われる。 「カティンの森」 事件を世界に公表したのは、第二次大戦勃発から二年後に始まった独ソ戦によって、ソビエト領内への侵攻を開始したナチスの側だが、ドイツのポーランド侵入とほとんど同時に、東からポーランドに攻め入り、ポーランドをナチとともに分割したソビエト軍の捕虜となったポーランド将校らがその犠牲となっている。 長い間、ソビエトはこの事件はナチによるものだと主張していたが、旧共産圏の崩壊によってようやく、事件がスターリンの命令を受けたものであることを認めた。ソビエトとポーランドの間には、ロシア革命後に限っても、独立を果たしたポーランドによる内戦介入と、ワルシャワまで迫った赤軍の反攻、そしてその失敗という長い歴史がある。 このときの赤軍を率いたのは、もとは帝政時代の将校だったトゥハチェフスキーだが、彼もまたのちにスターリンによって粛清される。この 「トゥハチェフスキーの陰謀」 では、大勢の赤軍の幹部や将校が粛清・追放され、そのことが結果的に、独ソ戦での初期の大敗につながったとも言われている。 航空機事故による要人の死亡というと、近年ではルワンダの大量虐殺のきっかけとなった、同国と隣国ブルンジの大統領が乗った飛行機が墜落したという事件があった。ただし、これは偶然の事故ではなく、どうやら当時の軍の一部による意図的な攻撃のようだから、純然たる事故ではない(参照)。 もっと古い話だと、日中戦争が終結した直後、「抗日民族統一戦線」 という表向きの 「国共合作」 にもかかわらず、共産党に対する警戒を崩していなかった蒋介石の軍の攻撃によって捕虜となっていた葉挺の釈放を受け、彼を迎えにいった博古ら数人の共産党幹部を乗せて、重慶から延安に向かった飛行機が墜落したという事件もある。博古はモスクワ留学の経験もあり、一時は党の最高幹部として、毛の上に立ったこともある人物である。 なお、文化大革命中に毛沢東の暗殺を企てたとして失脚した林彪も、飛行機でソ連へ逃亡する途中、モンゴルで墜落し死亡している。このときの飛行機はパキスタンから譲り受けたイギリス製のトライデントだそうで、林彪のほかに夫人の葉群、息子の林立果ら9名が乗っていたそうだ。 さて、国内のほうに目を転じると、なんとも訳のわからぬ状況になりつつある。鳩山首相の支持率が急降下しているそうだが、そのこと自体はなんら驚くべきことではない。彼に政治的な能力が欠けていることは以前から明らかだったのだし、小泉退陣後に次々誕生した安倍、福田、麻生の各政権のていたらくを見れば、そう不思議なことでもない。 しかし、奇妙なのはほんの昨日まで、ずっと政権を握っていた自民党やその系列の政治家らのほうである。なんでも、「立ち上がれ日本」 なる新党ができたそうだが、だとすると今まで日本は座っていたのか。選挙で大敗したり、政権を手放したりすると、とたんに右往左往し始めるのは、ロッキード事件のときの 「新自由クラブ」 以来のお家芸のようなものだが、なんともみっともない。 選挙というものは、負けるときもあれば勝つときもある。同じように、政党ならば、与党になるときもあれば、野党になるときもある。それは、議会制民主主義のイロハのイというものだろう。おまけに、自称竜馬があちこちにいるようだが、竜馬が暗殺されたのは31歳のとき。少なくとも、すでにその二倍の人生を無駄にすごしてきたような人らに、いまさら竜馬を名乗る資格などないのは自明のことではないか。関連記事: 今年は16年ぶりの冷夏となるか
2010.04.12
コメント(2)
-
三月は忙しかった
昨日今日と天気は回復したが、今年の春はずいぶんと気象の変化が激しかった。初夏なみの暑さになったかと思うと、いきなり冬に逆戻りして、ところによっては雪まで降った。それでも、いったん開花を迎えた桜は、誘爆式の仕掛け花火のように一気に花を咲かせた。名前は知らないが、まだ裸のままの落葉樹からも、天に向かって触手のような細い枝が無数に伸びている。 『春の嵐』 といえばむろんヘッセであるが、ヘッセはどちらかと言えば苦手なので、これは読んでいない。叙情的なのはまだよいが、「芸術」 だの 「精神性」 だのとかを持ち出されると、いよいよかなわない。かわりにといってはなんだが、藤村には 『春』 という長編と、『嵐』 という中編がある。これを二つあわせると、「春の嵐」 となる。 どちらも自伝的作品であるが、『春』 のほうは 『桜の実の熟する時』 に続く、藤村の青年時代、盟友であった北村透谷が自殺した頃の話。いっぽう 『嵐』 のほうは、それからほぼ二十年後、最初の奥さんに死なれ、手伝いに来ていた血のつながった姪を妊娠させてしまい、三年間フランスに逃げたあと、ようやく帰国して子供らと暮らしていた頃のことを描いた家庭小説である。 『嵐』 は、彼が日本を逃げ出すきっかけとなった、この事件を描いた 『新生』 の七年後に書かれているが、藤村というのは煮えきらない男で、フランスから帰国してからも、兄に内緒で、また姪との関係は復活している。なので、この題名の 『嵐』 とは、たんに気象現象のことを指すというより、そういった彼の身の回りで起きた一連の事件のことをさすと見ていいだろう。 三十年ほど前に亡くなった評論家の平野謙は、この 『新生』 執筆の動機について、姪とその父親である兄との間での 「秘密」 をめぐる関係の中で、にっちもさっちも行かなくなった藤村が、すべてを放り出してご破産にするためだったと論じている。 もはや事態は明白である。藤村が 『新生』 を書いた最大のモティーフは、姪との宿命的な関係を明るみへ持ちだすことによって、絶ちがたいそのむすびつきを一挙に絶ちきるところにあったのだ。その自由要望の声はほかならぬ恋愛からの自由を意味している。平野謙 「新生論」 より 実際、『新生』 という作品は、自分の子供を生ませた、ようやく二十歳を少しこえたばかりの姪に対する愛情も同情もほとんど感じられない、エゴイズム丸出しで自己弁護ばかりに終始している、酷い小説である。彼より二十年若い芥川が、 『或る阿呆の一生』 の中で、この主人公のことを 「老獪な偽善者」 と呼んだのも当然ではある。 『春』 の最後には、「ああ、自分のようなものでも、どうかして生きたい」 という主人公(つまりは藤村)の有名な台詞がある。この台詞は 『新生』 の中でも繰り返されているが、藤村はその後 『夜明け前』 を書き上げて、戦争が終わる二年前の1943年まで生き、71歳で亡くなったのだから、結果的には、そんなに心配することはなかったということになる。平野謙によれば、「かくて業ふかき人間島崎春樹はついに救われた」 のだそうだ。 話は変わるが、昔々、左翼系の文学理論に 「典型理論」 なるものがあった。つまり、革命的な作家は、典型的な時代の、典型的な事件と典型的な人物を描かなければならないというものだが、よくある時代の、よくある事件とよくある人物を描いたところで、それだけではちっとも面白くはなかろう。 戦後の中国では、魯迅の 『阿Q正伝』 の主人公、阿Qをめぐって、阿Qはいかなる階級の典型であったかを論じた、「典型論争」 なるものまであったという。たしかに、阿Qのような人間は、いつの時代にもいるだろう。そういう意味では、たしかに阿Qは人間のひとつの典型である。 ただし、小説の登場人物が、人間のあるタイプを代表するという意味での典型でしかなければ、それはとうてい生きた人間とは言えない。ナポレオンのような非凡な人物を描こうが、阿Qのような卑小な人物を描こうが、あるいはリアリズムで描こうが、アレゴリカルに描こうが、小説というものは、なにかの 「一般論」 のような無味乾燥な公式に還元されるものではない。 結局のところ、文学というものを支えているのは、たとえ表現形式としては 「虚構」 であろうとも、生きた人間である作者の 「実感」で あり 「感情」 ということになるだろう。世界中の物語をコンピュータにぶち込んで分析し、出てきたものにあれやこれやと脚色を付け加えたところで、それで 「はい、できあがり」 というわけにはいくまい。 むろん、個人の実感や感情が、そのままでは一般性を有しないのは言うを待たない。人によって経験は違うし、経験の積み重ねの中からうまれた、ものの考え方や感じ方がひとりひとり違うのは、当然のことだ。だから、それをそのまますべてに当てはまるかのように一般化してしまえば、ただの実感主義や感情論にしかならない。 しかし、それが人間の実感であり感情であるかぎり、そこにはなんらかの普遍性が存在するはず。であればこそ、そういった実感や感情は、たとえ完全な共感は不可能だとしても、一定の理解は可能なのであり、そこにコミュニケーションというものが成立しうる根拠もあるだろう。でなければ、個々の人間の個々の感情などを描き出した文学というものが、ときには時代や文化をもこえた普遍性を持ちうるはずがない。 ようするに、「論理」 には還元されない、人間と人間のコミュニケーションにとって必要なのは、そういった具体的な人間の 「実感」 や 「感情」 の中から、そこに含まれている 「普遍性」、言い換えるなら普遍的な意味を引き出すことであり、そういう努力をすることだ。 それは、世の中の人間のありとあらゆる 「実感」 やら 「感情」 やらを集めてデータ化したり、定量化して平均を出すようなこととは全然違う (かりにそれが可能だとして)。むろん、「実感主義」 だの 「感情論」 だのという、そのへんにいくらでも転がっているようなつまらぬ非難ともまったく関係ない。
2010.04.04
コメント(5)
-
西行法師のことなど
鳥羽院のおんとき 北面に召し使はれし人はべりき。左兵衛尉藤原義清(のりきよ)、出家ののちは西行法師といふ。かの先祖は天児屋根命(あまつこやねのみこと)、十六代の後胤、鎮守府の将軍秀郷に九代の末孫、右衛門大夫秀清には孫、康清には一男なり。 上の引用は、西行の死から五十年ほどのち、つまり鎌倉時代の中頃に成立したと推定されている 『西行物語』 の冒頭。ただし、俗名は憲清と書かれることもある。なお、藤原秀郷とはかの将門を討ち取った人物で、俵藤太の名前でも知られ、琵琶湖の近くで巨大ムカデを退治したとか、栃木のほうでは百目鬼という妖怪を退治したなんて話もある。 ただし、秀郷についてのそのような伝説が生まれたのは、西行が生きた時代よりもあとらしい。たとえば、室町に成立した 『俵藤太物語』 では、将門と秀郷の壮絶な死闘が語られており、それによれば、将門はつねに六体の分身をしたがえていて、七人いるように見えるが、分身には影がない、影のあるのは本体だけだとか、全身鉄でできているが、こめかみが弱点で、秀郷はそこを射抜いて倒したとか。 実在の人物からこれだけシュールな伝説が生じるには、さすがにかなりの時間を要するだろう。とはいえ、『今昔物語』 にもあるように、平安時代というのは鬼や妖怪、怨霊などの超自然的威力が跳梁跋扈していた時代である。であるから、ある人物に対する伝説化の欲求がありさえすれば、そこに摩訶不思議なる伝説を生じさせる素地は、いつでもあったということになる。 そのような武家の名門に生まれた西行が、二十三歳で突然出家した理由は、はっきりしない。親しかった友人が急死したからとか、高貴な年上の女性に振られたからとか、諸説あるようだが、どれもいささかできすぎている。むしろ、権謀術数うずまく宮中に嫌気がさしたというのが、平凡だがいちばんありそうな気がする。 平安に限らず、その前の奈良にしても、宮廷内の権力闘争というものはすさまじい。様々な陰謀や政敵へのデマ中傷はもちろんのこと、僧侶や祈祷師を呼んでの呪詛合戦も珍しくはなかった。なにしろ、事件や事故が相次ぐと、誰々の呪いだ、祟りだといった噂がたちまち都中を駆け巡るといった時代なのである。雅な王朝文化なんてのは、しょせんただの表の顔にすぎない。 それはなにも、非合理的な迷信とかのせいだけではない。同様のことは、権力が少数の閉じた集団に占有されている世界では、いつでも起こりうる。現代だって例外ではないのは、スターリンのような独裁者による政治の末路を見ればよく分かる。そういう世界では、自分にもっとも近い人間こそが、もっとも用心し警戒しなければならぬ相手なのだ。 いわゆる浄土信仰の流行は、末法思想の広がりに伴うものだが、藤原氏のような上級貴族にとっては、それは現世の栄華を来世でも謳歌したいという、すこぶる利己的な欲求の表れでもあった。頼通が建てた壮麗な平等院鳳凰堂は、そのことをよく表している。道長は 「この世をばわがよとぞ思う」 と詠ったが、それも生きていればの話、死んでしまってはしょうがない。 厭離穢土・欣求浄土とは、浄土信仰を一言で表したスローガンのようなものだが、信仰がしだいに下級武士や庶民へと広がるにつれて、重点はしだいに 「欣求浄土」 から 「厭離穢土」 のほうへと移動する。そこでは、阿弥陀経に謳われたような、迦陵頻伽が空に舞い、金銀財宝ざあくざくといった極楽浄土の華やかさなどは、もはや問題ではない。 ただ、戦乱や天変地異に明け暮れ、人の命など無に等しい現世をいとわしいと感じる心だけが、浄土を求める根拠となる。実際、そういった人々は、なにもこの世ではとうてい味わえぬ豪奢な暮らしがしたいというような理由で、浄土を求めたわけではないだろう。 しかし、そのような悲嘆が 「とく死なばや」 といった死の理念化へとひた走るなら、それは洋の東西を問わず、動乱期にはよくある宗教的急進化の一例にすぎない。そこへいたる心情がいかに純粋であろうと、そのような現世そのものを否定する思想は倒錯でしかない。そのような思想が無視できぬ広がりを持ったとすれば、それは時代のせいでしかあるまい。 『西行物語』 では、西行は泣いてすがる4歳の娘を縁側から蹴落とし、心を鬼にして出家したなどと、無茶苦茶なことが書かれているが、これではただのよくできた抹香臭い 「聖人伝」 でしかない。実際の西行は、すでにきな臭くなっていた時代の中、奥州藤原氏のもとを訪れたり、その途中で鎌倉の頼朝に会ったりと、世の中の動きにもなかなか敏感な様を見せている。 『吾妻鏡』 によれば、頼朝との会見を終えた西行は、土産にもらった銀の猫を屋敷の外で遊んでいた子供に与えて立ち去ったという。この話が本当かどうかはともかく、そういったことからうかがえるのは、権力などに関心はなくとも、現世そのもの、言い換えるなら、現世の中で生きる人間そのものは否定しないという思想のありようのように思える。 願はくは 花の下にて 春死なん、そのきさらぎの 望月のころ この歌は、西行が50歳のころに詠んだものらしい。表現こそ直截だが、どこかにのんびりした感が漂っている。気がつくと、もう気の早い桜があちこちで花を咲かせている。
2010.03.20
コメント(5)
-
公暁の呪いか 実朝の呪いか
すでに卒業のシーズンだというのに、列島を襲った寒気と低気圧のおかげで、このところの天気は大荒れだった。こちらでも雪が降ったが、鎌倉の鶴岡八幡宮では、樹齢千年を超える銀杏の巨木がおりからの強風で倒壊したという。 この巨樹には、鎌倉幕府の三代将軍実朝が兄頼家の子、つまり彼にとっては甥にあたる公暁に暗殺された事件で、犯人の公暁が身を隠していたという伝承があるそうだ。天下を揺るがしたこの事件について、比叡山の座主、慈円は次のように書いている。夜ニ入テ奉幣終テ、寳前ノ石橋ヲクダリテ、扈従ノ公卿列立シタル前ヲ楫シテ、下襲尻引テ笏モチテユキケルヲ、法師ノケウサウ・トキント云物シタル、馳カゝリテ下ガサネノ尻ノ上ニノボリテ、カシラヲ一ノカタナニハ切テ、タフレケレバ、頸ヲウチヲトシテ取テケリ。ヲイザマニ三四人ヲナジヤウナル者ノ出キテ、供ノ者ヲイチラシテ、コノ仲章ガ前駆シテ火フリテアリケルヲ義時ゾト思テ、同ジク切フセテコロシテウセヌ。(中略)此法師ハ、頼家ガ子ヲ其八幡ノ別当ニナシテオキタリケルガ日ゴロオモイモチテ、今日カヽル本意ヲトゲテケリ。一ノ刀ノ時、「ヲヤノ敵ハカクウツゾ」 ト云ケル。公卿ドモアザヤカニ皆聞ケリ。カクシチラシテ一ノ郎等トヲボシキ義村三浦左衛門ト云者ノモトヘ、「ワレカクシツ、今ハ我コソハ大将軍ヨ、ソレヘユカン」 ト云タリケレバ、コノ由ヲ義時ニ云テ、ヤガテ一人、コノ実朝ガ頸ヲ持タリケルニヤ。 公暁に実朝のことを親の仇と吹き込んで、暗殺をそそのかしたのは、彼の乳母の夫である三浦義村だと思われるが、頼家が将軍引退後に修善寺で暗殺されたときには、実朝はまだわずか十二歳であるから、とても事件の黒幕であったはずはない。実際の黒幕はむろん北条氏、具体的には政子の親父であり、つまり頼家にとっては母方の祖父になる北条時政だろう。 公暁は実朝よりさらに年下であるから、事件当時はほとんどなにも知らなかったはずだ。とはいえ、それから十年以上たった実朝襲撃の時点では、ある程度の真実は知っていただろう。実際、このとき公暁は、実朝に随行しているはずの北条義時の首もとるつもりで、源仲章という別人を殺害している。なお、『吾妻鏡』 によれば、このとき義時は事件現場のすぐ近くまで来ていながら、不意に気分が悪くなり、自分の役を仲章にゆずって引き返したという。 おかげで、義時は事件に巻き込まれずにすみ、かわりに源仲章なる人物が間違って殺されることとなった。実朝の首を取った公暁は、次はおれが将軍だと豪語して、信頼していたらしき三浦義村に使者を送る。報を聞いた義村は、すぐに迎えをよこすと答えながら、裏では義時にその旨を通報し、義時の命を受けて、迎えではなく公暁を討つよう配下に命じて送り出す。 結局、公暁は迎えを待たずに、実朝の首をかかえたまま義村の屋敷へ向かうが、途中で義村の討手と出会い、奮戦むなしく、中へ入ろうと義村の屋敷の塀によじ登ったところを討たれたという。慈円はことの顛末を、「頼朝は優れた将軍であったのに、その孫になるとこんなことをしでかすとは、武士の心構えもできていない愚か者よ」 というような、辛辣な言葉で締めくくっている。 唐木順三は 「実朝の首」 という文の中で、義村が公暁をそそのかして実朝と義時を討たせようとしたものの、義時生存の報を聞いて、急遽寝返ったのではと推測している。しかし、北条にとっても、実朝の殺害は以前からの既定路線であったのだし、この義村という人物、その前の和田一族が討たれた事件でも、盟を結んでいた義盛を裏切って、義時に通報している。なので、公暁は最初からただ踊らされていたに過ぎないのでは、という推測も成り立ちそうである。 翻ってみるなら、最初の武家政権である平氏政権が、清盛という卓越した個人を中心としながらも、一門としての基盤をもった権力であったのに対し、頼朝の権力は、平安以来の歴史を持つ関東武士団を軸にし、それを束ねることで成り立ったものであった。頼朝が伊豆に流されたのは十三のとき、以来二十年も関東で暮らしていた頼朝は、源氏の嫡流であり、父義朝ゆかりの縁はそこそこにあっても、ほとんどただの亡命者にすぎない。 しかし、将門以来、離合集散がたえず、しかも遠く離れた京の政治などにはさして関心もないような関東武士団を、朝廷に対抗するひとつの権力にまとめあげるには、北条だの畠山だのという個々の豪族すべての上に立つ 「象徴」 としての人物が必要であった。それはむろん 「貴種」 の血を引くものでなければならなかった。 しかしながら、いったん制度ができてしまえば、トップに立つのは本当にただの 「象徴」、つまりは 「傀儡」 でいいということになる。とりわけ、しだいに他の御家人を排除して、幕府内での独裁的地位を固めつつあった北条氏としてはそうだろう。北条氏から見れば、頼家は頼朝の息子というだけでのぼせ上がったわがまま小僧であるし、京に憧れる実朝は、独自の権力たる関東武士団の存在を危うくしかねない困り者ということになる。 結局、この事件以降、将軍は京の摂関家や皇族から次々選ばれることになるが、いずれも右も左も分からぬ幼いころに将軍に任じられ、成長するや、ことごとく罷免されて京へ送り返されるということが繰り返されている(参照)。これは、平安時代の摂関政治や院政における幼帝の擁立とほとんど同じである。 つまるところ、いったん権力が創設されると、そのトップの地位はしだいにただの 「象徴」 と化し、実権はナンバーツーに握られるというのは、どうやらこの国の政治の古きよき伝統なのらしい。そして、ナンバーツーも無能であるなら、権力はやがて下へ下へと移行し、権力装置そのものの拡散と解体にいたる。それは、戦前や戦中の政治過程でも見られたし、小泉退陣後の自民党政治にも、ある程度あてはまる。 さて、宇宙人と称し、意味不明の宇宙語をしゃべるらしき現宰相のほうはどうなのか。基地移設をめぐる発言にしても、朝鮮高校に通う生徒への学費援助をめぐる発言にしても、あっちに引っ張られ、こっちに引っ張られでくるくると変わっており、一貫性にも合理的根拠にも欠けている。だいたい、拉致問題担当相とかが、どうしてこの話に首を突っ込むんだ?
2010.03.12
コメント(2)
-
遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん
遊びをせんとや 生れけむ戯れせんとや 生れけん遊ぶ子供の声きけば我が身さえこそ ゆるがるれ 後白河天皇といえば、平安末期から鎌倉初期にかけての人で、父親は鳥羽天皇、もともとその四番目の皇子という気楽な立場だったので、若い頃は遊蕩三昧の日々を送っていたという。慈円という坊さんが鎌倉初期に書いた 『愚管抄』 にも、彼が父の鳥羽天皇から、あいつは遊んでばかりで、とても天皇になれる器ではないと思われていた、というような一節がある。 この天皇が、当時、遊女や白拍子など一般庶民の間に流行っていた、「今様」 と呼ばれていた歌謡にこっていたというのは有名な話で、天皇の位をおり出家して法皇となっていた後年、ちょうど鎌倉幕府が成立するかしないかのころに、『梁塵秘抄』 という今様を集めた書物を自ら編纂している。 Wikipediaによれば、今様とは今で言う 『現代流行歌』 といった意味だそうだ。吉本隆明は 『初期歌謡論』 の中で、「『新古今和歌集』 の歌は、とぼけた心酔者がいうほどけんらんたる和歌の世界などではない。いわゆる大衆曲謡に浸透されて俗化し崩壊寸前においこまれていた危機の詩集である」 と書いているが、そういった伝統が重んじられる上流社会にも浸透していった雑芸の代表が、後白河が熱中した今様ということになる。 若い頃のその熱中ぶりときたら、とにかく朝から晩まで一日中歌いどおしで、声が出なくなったことも三度ある。おかげで喉が腫れて湯水を飲むのもつらかったとか、一晩中歌いっぱなしで、朝になったのも気付かず、日が高くなってもまだ歌っていたなどというのだから、尋常ではない。親父殿から、「即位ノ御器量ニハアラズ」 と呆れられたのももっともな話だ。 そういう伝統や伝統的価値観の崩壊というのは、信仰の世界でも同様で、平家は清盛にはむかった奈良の東大寺や興福寺など、「南都」 の大寺院を軒並みに焼き払っている。さすがに、後に信長が比叡山でおこなった皆殺しほどではなかったろうが、これが王朝貴族らに与えた衝撃には、同じようなものがあっただろう。 堀田善衛の 『定家名月記私抄』 によれば、藤原定家はその日記 「明月記」 で、この事件について 「官軍(平氏の軍のこと)南京ニ入リ、堂塔僧坊等ヲ焼クト云々。東大興福ノ両寺、己ニ煙ト化スト云々。弾指スベシ弾指スベシ」 と書きしるしたそうだし、藤原兼実の日記 「玉葉」 には、「世ノタメ民ノタメ 仏法王法滅尽シ了ルカ、凡ソ言語ノ及ブ所ニアラズ」 とあるという。 現世の生を終えたら、次は極楽浄土に生まれたいという浄土信仰が、貴族の間に広がったのは末法思想によるものだが、やがてその教えは、とにかく 「南無阿弥陀仏」 とただ一心に唱えよという法然の教えとなり、中には 「とく死なばや」 などと、物騒なことをいう者も出てくる。一遍などは、身分の上下や男女の区別なく、大勢の信者を引き連れて、踊りながら各地で布教を行った。 こういった状況は、天台座主であった慈円のような、頭コチコチの伝統主義者の目には、きわめて由々しき事態として映っていたのだろう。法然と彼の教団について、「ただ阿弥陀仏とだけ唱えていればよい、ほかに修行などいらぬなどといって、なにも分かっていない愚か者や無知な入道や尼に喜ばれて、大いに盛んとなり広がっている」 などと憤慨している。 慈円は、安楽房という法然の弟子が 「女犯を好んでも、魚や鳥を食べても、阿弥陀仏はすこしも咎めたりはしない」 と説教していたとも書いている。実際、この安楽房という坊さんは、後鳥羽上皇が寵愛する女官との密通という嫌疑により斬首刑に処せられ、さらに法然や親鸞も京都から追放される憂き目にあった。ちなみに、後鳥羽上皇は後白河の孫にあたる。 伝統に挑戦するような新しい教えとかが広まると、正統派を自認する伝統主義者の側から 「異端」 だの 「淫祠邪教」 といったレッテルが貼られるのは、世の東西を問わず、よくあることで、この事件もまた、伝統的勢力の側による誣告が影響した可能性が高い。だが、少なくとも、彼らの眼には、新興の念仏教団が現代の怪しげな 「新興宗教」 のように、なにやらいかがわしいものと映っていたのは事実だろう。 そういったものが、最初から 「無知蒙昧」 な下々の民の間に広がるのはしかたないとしても、それが仏典なども読み、それなりに教養もあるはずの宮中にまで浸透してくるとなると、伝統や文化の守護者を自認していたであろう慈円のような人にとっては、たんに宮廷の保護を受けてきた既得権益者としての利害というだけでなく、まことに世も末というべき 「文化の乱れ」 であり、上流階級としての 「品格」 が問われる事態でもあったのだろう。 若い頃は、「即位の器量にあらず」 と父親からも見放されていたような後白河が天皇になれたのは、先に即位した異母弟の近衛天皇がはやく死んだためだが、親父様からたいして期待されていなかったのは、このときも同様で、後白河をとばして、まだ小さいその息子(のちの二条天皇)を即位させるという案もあったらしい。 しかし、それはあんまりだろうということで、とりあえず中継ぎとして即位することになったのだが、院政をしいて実権を握っていた鳥羽上皇がなくなると、とたんに宮中のいろんな対立が噴き出し、まずは兄の崇徳上皇との間で保元の乱が勃発する。その後、平治の乱から源氏の挙兵、さらに同じ源氏の義仲と頼朝の争い、次は義経と頼朝、頼朝による奥州藤原氏討伐と、次から次へと戦乱が続く。 その中での後白河の行動は、つねにその場しのぎをやっていただけの無定見と見る人もいれば、武士の台頭という大きな歴史的変動の中で、なんとか諸勢力のバランスをとって、朝廷の力を保とうとできる限りの努力をしたと評価する人もいる。ちなみに、頼朝は後白河のことを 「日本国第一の大天狗」 と評したそうだ。 とはいえ、「諸行無常」 という言葉のとおり、次々と諸勢力が勃興しては滅びていく中で、天皇退位後も、子や孫にあたる二条、六条、高倉、安徳、後鳥羽の五代に及んで院政をしき、後鳥羽をのぞく四人の夭折した天皇より永らえて、65歳まで生き続けたのは、当時としては十分に天寿をまっとうしたと言えるだろう。舞へ舞へ蝸牛(かたつぶり)舞はぬものならば馬の子や牛の子に蹴させてん踏みわらせてんまことに美しく舞うたらば華の園まで遊ばせん
2010.02.18
コメント(20)
-
「節分」ということで鬼の話など
「節分」 とは、ほんらい春・夏・秋・冬の季節の分かれ目のことであり、立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれ前日を指す。いまでも正月のことを新春と呼ぶ習慣が残っているように、もとは春が新年のはじまりであって、旧正月と暦上の冬と春の区切りである節分はほぼ同時期になる。 ただし、立春が太陽の運行に基づいているのに対し、旧暦は基本的に月の運行に基づいているから、正月と立春の関係はかならずしも一定しない。ときには、年が明ける前に立春を迎えて春になることもあり、そこから、明治に短歌革新を掲げた正岡子規により、「実に呆れ返つた無趣味の歌」 などとぼろくそにいわれた、古今和歌集巻頭のこんな歌も生まれている。としのうちに 春はきにけり ひととせをこぞとや いはむ ことしとや いはむ たしかに、この歌の意味は、年のうちに春が来てしまった、それじゃいったい今日から正月までは、去年になるのか、今年になるのか、どっちなんだ、というたわいもないものだが、「実に呆れ返った無趣味の歌」 とはいささか手厳しい。なお、この歌の作者は在原元方といって、伊勢物語の主人公でもある在原業平の孫にあたる。 「節分」 といえば当然豆まきであり、したがって鬼の話ということになるのだが、大正15年に三田史学会で行われた講演をもとにした、折口信夫の小文 「鬼の話」 は、次のように始まっている。 「おに」 という語にも、昔から諸説があって、今は外来語だとするのが最も勢力があるが、おに は正確に 「鬼」 でなければならないという用語例はないのだから、わたしは外来語ではないと思うている。さて、日本の古代の信仰の方面では、かみ (神)と、おに (鬼)と、たま (霊)と、もの との四つが、代表的なものであったから、これらについて、総括的に述べたいと思うのである。 ここで彼が言っている、おにを 「外来語だとする」 説というのが、具体的にどういうものを指すのかは知らない。ただ、すなおに考えるなら、中国から入ってきた 「鬼」 という漢字に 「おに」 という読みがあてられたということは、漢字導入より前に 「おに」 なる言葉があったということになるだろう。ただし、それは、漢字で表された中国の鬼とまったく同じというわけではあるまい。 「魏志倭人伝」 には、卑弥呼について 「鬼道を事とし能く衆を惑わす」 とある。「鬼神を敬してこれを遠ざく」 とは孔子の言葉であり、「断じて敢行すれば鬼神もこれを避く」 とは、『史記』にある趙高の言葉だが、中国での鬼とは、もともと死霊のことを指す。「怪力乱神を語らず」 と孔子は語ったが、儒教とはもともと祭祀の礼からはじまったそうだから、孔子とて、そのような存在まで否定したわけではない。 ついでにいうと、プラトンの 『ソクラテスの弁明』 によれば、彼は少年のころから 「ダイモンの声」 を聞いていたそうで、田中美知太郎はこの 「ダイモン」 を鬼神と訳している。ソクラテスの罪状は、神を認めず青年を惑わしたというものだが、ダイモンの声をつね日頃聞いている自分が神を認めぬはずがないではないかと論じて、ソクラテスは自己の無罪を主張したということだ。 さて、日本の文献で 「鬼」 という文字が最初に登場するのは、奈良時代に編纂された 「出雲国風土記」 らしい。これには、古老の話として 「昔ある人、ここに山田をつくりて守りき。そのとき目一つの鬼きたりて田作る人の男を食らひき」 という話が残されている。これ以降、鬼は人を襲い人を食らう恐ろしい存在として、様々な史書や説話に登場する。 なかでも有名なのは、源頼光が四天王の一人、渡辺綱に片腕を切り落とされ、のちに綱の養母に化けて腕を取り戻しにきたという、大江山の鬼の話だろう。もうひとつは桃太郎の鬼退治だが、こちらは、崇神天皇によって今の岡山に派遣された四道将軍のひとり、吉備津彦命(きびつひこのみこと)が、吉備の鬼ノ城を拠点とした温羅という名の鬼を退治したという伝説に基づくという説が有力のようだ。 この吉備津彦命とは、七代目の天皇である孝霊天皇の皇子ということになっており、したがって、奈良の箸墓古墳に埋葬されているとされ、一部の学者によって卑弥呼ではないかとも言われている、倭迹迹日百襲媛命(やまとととびももそひめのみこと)の弟ということになる。 こういった鬼についての、『鬼の研究』 という本での歌人の馬場あき子による分類を借りると、日本の鬼はおおよそ次のように分類できる。 (1) 最古の原像である、日本民俗学上の鬼(祝福にくる祖霊や地霊) (2) 道教や仏教を取り入れた修験道成立にともなう山伏系の鬼(天狗も) (3) 邪鬼、夜叉、羅刹、地獄の鬼などの仏教系の鬼 (4) 放逐者や賎民、盗賊などの「無用者の系譜」 から鬼となったもの (5) 怨恨・憤怒・雪辱など、さまざまな情念をエネルギーとして鬼となったもの 秋田のなまはげのように、新年の民俗行事に登場する素朴な鬼は、おそらく最も古い(1)にあたるだろう。いっぽう節分での鬼退治は平安のころ、中国伝来の宮中行事から始まったそうで、もとは新年の祝福に来ていた(1)の鬼が、その影響を受けて(2)や(3)の鬼に変化したもののようにも思える。 かりにそうだとすると、かつては新年に歓待されていた鬼が、いまや子供にすら豆を投げつけられて追い払われるようになったわけで、ずいぶんと落ちぶれたものだ。最後は、上で冒頭を引用した折口信夫の 「鬼の話」 の結語から。 まれびと なる鬼が来た時には、できる限りの歓待をして、悦んで帰って行ってもらう。この場合、神あるいは鬼の去るに対しては、なごり惜しい様子をして送り出す。すなわち、村々にとっては、良い神であるが、長く滞在されては困るからである。だから、次回に来るまで、ふたたび、戻って来ないようにするのだ。こうした神の観念、鬼の考えが、天狗にも同様に変化していったのは、田楽に見えるところである。 なお、現代で鬼を比喩に用いるとすると、「土俵の鬼」 とか 「将棋の鬼」 などとなる。「土俵の鬼」 とは初代若乃花(つまり、このたびめでたく協会理事に当選した貴乃花の叔父)であり、「将棋の鬼」 とは大山康晴のライバルだった升田幸三のことだが、このような鬼という言葉からは、ただ強いだけでなく、勝負にすべてをかけ、それ以外のことはいっさい顧みないという、いささか狂気じみたものすら感じられる。 このような表現は上の(5)の応用のようなもので、その強さとは、もちろん相手を圧倒する攻撃を主とした剛の強さであり、したがっていったん受けにまわると、あっけなく敗れてしまうというイメージも伴う。ただし、実際のところ、この二人がどうだったのかまでは、残念ながらほとんど知らない。
2010.02.02
コメント(4)
-
自民党のあきれたご都合主義
こちらのサイトによると、「三寒四温」 とは もとは中国の東北部や朝鮮半島北部で冬の気候を表すために使われていた言葉で、シベリア高気圧から吹き出す寒気がほぼ7日の周期で、強まったり弱まったりすることに由来するのだそうだ。 そこにも書いてあるように、この言葉はたしかに最近では、むしろ低気圧と高気圧が交代しながらしだいに暖かくなっていく、春先の気候変化を表すことが多くなっているが、ここ数日の気候と気温の変動は、まさにこの言葉の本来の意味にぴったりのようだ。 昨日はひじょうに暖かく、近くにある小さな橋の上から下をのぞくと、浅く透明な川の底に、まるまると太った鯉が潜水艦のようにゆったりと沈んでいるのが見えたりしたのだが、今日は一転して冷え込んだ。明日はもっと冷え込むらしい。 冬はなんとなく人が死ぬ季節というイメージがある。今年も、かつての名投手小林繁をはじめとして、様々な人の訃報があいついだ。むろん、冬でなくとも人は死ぬのだし、有名人の訃報などなくとも、あちらこちらで人が死ぬことにはかわりない。古代人ならば、冬とは太陽が最も衰える季節であるから、生き物の力もまたそれに呼応して衰えるものと考えるところだろうか。 世間は不景気のようで、こちらもほとんど仕事がない。つぶれかけた零細塾から転職して、やっとなんとか人並みに暮らせるようになったと思ったら、また前の状態に逆戻りのようだ。とりあえず、しばらくは毎日散歩でもして体力増強とダイエット、それに長年書棚の肥やし状態になっていた積読本の解消に専念しようと思うのだが、それがいつまでも続くようではちと困る。 ところで、衆議院の党首討論と代表質問で、自民党の谷垣総裁は鳩山首相と千葉法相に対して、「指揮権」 発動について三度も尋ねたという (参照)。この場合の指揮権とは、公法のひとつである検察庁法に定められた、法務大臣の次のような権限をさす。第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。 法務大臣の指揮権は、このように明確な法的根拠を持つ。であるなら、事件とその捜査をめぐる状況が、今後どのように進行するかも分からないのに、その行使そのものを最初から問題視するような谷垣総裁の質問は、きわめて筋のとおらぬおかしな話でしかない。 法的にいえば、検察庁は法務省のもとにあり、したがってその最高責任者は法務大臣である。検察庁に所属する検察官は独任官庁と呼ばれ、全体としても、またひとりひとりとしても独立性が強いが、検察庁はあくまで行政機関のひとつであり、法務大臣とひいては総理大臣に責任を負う。そして、同時に大臣はまた検察官の行為に対して、最終的な責任を負う。 そうであれば、大臣が検察に対して指揮権を持つのは当然なのであり、その行使自体を問題視して、あらかじめ法務大臣の手を縛ろうというのは、本末転倒な話と言わざるを得ない。それに、法で明確に定められた権限を行使することが、それ自体としてはなんの問題も含まないというのは、それこそ 「法治国家」 としては自明の話にすぎない。 ただし、捜査への政治権力の不当な介入を防止するために、その行使は慎重でなければならない。だから、問題なのは指揮権の行使そのものではない。ただ、そこには正当な行使と不当な行使の区別があるということであり、その正当・不当については、政治家が責任を負うということだ。反対派は、当然その行使を非難するだろう。また、場合によっては、マスコミなどによって激しく批判されたりもするだろう。 しかし、その結果は国民の声であるところの世論として現れるし、次の選挙にも反映されることになる。つまるところ、政府や政治家の行為の正当・不当について判断するのは、国民自身なのであり、それが保証されているのが民主主義というものなのだ。法定の手続きに従った合法性は、それだけでその正当性を担保するものではない。 官僚ならば、とりあえず法に従っておけば、責任を問われることはない。足利事件で菅家さんを起訴した当時の検察官が、法的な責任を問われずにすんでいるのは、そういうことだ。しかし、政治家の責任はそういうものではない。合法であっても、不当な権力行使として責任を問われることはある。それを引き受ける覚悟があるのが、ようするにウェーバー言うところの、政治屋ではない本物の政治家ということになる。 そもそも、法で認められた大臣の指揮権そのものを封じることは、たんなる行政官庁にすぎない検察を、誰に対しても責任を負わない 「聖域」 とすることである。それは、捜査権と起訴権という強大な権力を有する検察を、絶対的な権力とするにひとしい。しかしながら、誰かの言葉にもあるように、絶対的権力は絶対的に腐敗する。そこに例外はない。 憲法上の三権のうち、司法権は最高裁を頂点とする裁判所がになっている。だが、裁判所は提訴された事件を扱うだけである。とりわけ刑事事件の場合、日本では検察官のみが起訴する権限を持っている。その意味で、検察官は行政権の一部でありながらも、司法権の重要な要素をも構成している。 まして、有罪率のきわめて高い日本の司法では、検察官の実質的な権力はひじょうに強いといわねばならない。その意味において、検察を誰も手をつけられない不可侵の 「聖域」=「独立国家」 とすることは、それを 「民主主義」 の埒外、言い換えるなら主権者たる国民の手の届かぬところにおくことにほかならない。 それにしても、かつて自党の議員が検察の捜査を受け、つぎつぎと逮捕・起訴されたときには、「検察ファッショ」 だのなんだのといって非難していた自民党の諸氏が、選挙に負けて野党に回ると、今度は一転して検察を持ち上げ、政府を攻撃するとは、これはなんとも無様なご都合主義以外のなにものでもない。 政治と金の問題は、たしかに重要な問題である。しかし、その摘発と捜査が検察の恣意に任されるなら、これは政治と政局を動かす大きな武器となる。悪質な違法行為は論外だが、法と手続きの煩雑化はその完璧な順守を困難とさせるものでもあり、場合によっては、「一罰百戒」 を名目とした捜査機関による恣意的な摘発と捜査をも可能にする。それは、政治家に対する生殺与奪の権を検察に与えるに等しい。 国会がほんとうにこの事件に関心を持ち、真相を究明したいと望んでいるのなら、検察という名の虎の威を借るキツネのようなことをするのではなく、開会直前に逮捕された石川議員を釈放させ、国会の場で宣誓のうえできちんと証言させるべきだろう。それが、少なくとも 「国権の最高機関」 たる議会を構成する者らの矜持ではないだろうか。検察の捜査は、被疑者の身柄を拘束せずとも可能なはずである。 政府を攻撃するという目前の利益だけで検察の威を借るような、現在の自民党のご都合主義的な言動は、「統帥権干犯」 や 「国体明徴化」 などの名を借り、一部の軍人や民間右翼を利用して、ときの政府や対立する政党、政党人を攻撃し、自らの墓穴を掘ったかつての愚かな政治家らとそっくりである。もっとも、検察が軍のような実力部隊ではないということだけは、幸いというべきではあろうが。 たしかに、55年体制以来、長年権力を独占してきた政党としては、野党慣れしていないという点はあるだろう。しかし、鳩山政権に対する 「社会主義」 などというピントのずれた非難や、先日発表された党の新綱領原案(要旨)なるものの、選挙前とかわらないイデオロギッシュな愚かさといい、その志のあまりの低さにはあきれるほかにない。 だいたい、党の綱領というものは一時的な政治状況に左右されない、党の長期的な基本方針を定めた文書のはずだが、これを見ると、現在の自民党には、どうやら現在の対立状況しか目に入ってないようだ。ということは、ひょっとすると、このままずっと 「万年野党」 の地位に甘んじるつもりなのだろうか。
2010.01.22
コメント(1)
-
すさまじきもの
「すさまじい」 とは、現代語では 「ものすごい」 とか 「恐怖を感じさせるほどである」 といった意味だが、古語では 「興ざめだ」 とか 「殺風景」、「寒々している」 といった意味で使われる。下に引くのは、『枕草子』 の第二十三段 「すさまじきもの」 の冒頭部分。すさまじきもの 昼ほゆる犬、 春の網代。 三、四月の紅梅の衣。 牛死にたる牛飼。 乳児亡くなりたる産屋。 火おこさぬ炭櫃、地火炉。 博士のうちつづき女児生ませたる。 方違へに行きたるに あるじせぬ所。 まいて節分などは いとすさまじ。 口語訳は省くが、このほかにも 「除目(ぢもく)に官得ぬ人の家」 などというくだりがあって、これなどは現代でも、内閣の組閣や改造のときに、入閣の知らせをまだかまだかと待っていながら、とうとう連絡をもらえなかった残念な議員さんなどにあてはまりそう。 さて、報道によれば、小沢一郎民主党幹事長の政治資金をめぐる問題で、同氏の元秘書であった石川知裕議員をはじめ、昨年の西松建設献金事件で公判中の公設秘書、さらに石川議員の後任であったという元私設秘書の三名が、東京地検によって逮捕されたという。 小沢一郎は、いうまでもなくかの角栄の秘蔵っ子である。「陸山会」 なる彼の後援会の名称も、むろん 「越山会」 という角栄氏の後援会の名前にならったものだろう。とすれば、彼が角栄氏から、政治資金の調達方法や錬金術の指南を受けたことは十分に考えられる。 その点で、小沢氏に金銭面でダーティなイメージがつねにつきまとうのはしかたあるまい。実際、氏が金銭的にまったくクリーンな人だと考えている者は、おそらく一人もいないだろう。 とはいえ、現時点での石川議員の逮捕容疑は、「政治資金収支報告書」 への記入漏れによる政治資金規正法違反という、ほとんど形式的な容疑にすぎない。東京地検は、その裏に企業からの不正献金による資金調達とその隠蔽という構図を描いていると思われるが、少なくとも現時点での逮捕容疑は、どう見てもたんなる形式犯にすぎない。 このようなやりかたは、警察や検察がある事件で狙った容疑者を、通常なら逮捕を要しないような軽微な容疑で逮捕し身柄を確保したうえで、本当の狙いである別の事件について取り調べるという、いわゆる 「別件逮捕」 に限りなく近いように思われる。 「別件逮捕」 の違法性・合法性という議論については省くが、伝えられているように、もしも、検察が不正献金事件という構図を描いているのなら、その件についての捜査を進め、証言や証拠を集めて容疑が固まった時点で容疑者として逮捕するというのが、少なくとも筋の通った捜査方法であろう。 日本国憲法には、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」(第50条)という規定がある。いわゆる議員の不逮捕特権というものだ。 かつて12月に開かれていた通常国会は、国会法の改正によって、現在は1月中旬に開かれるものとなっている。今年の国会は明日18日に招集されるそうだが、その直前の逮捕は、どう見てもこの憲法による制約を免れるための 「駆け込み逮捕」 という感が強い。 たとえ、議員に不逮捕特権があったとしても、容疑に十分な裏づけがあり、また逮捕に法で定められた正当性と必要性があるのなら、議会に対して逮捕許諾請求を行い、その決議を受けて逮捕することが可能なはずだ。 実際、ロッキード事件での田中角栄をはじめ、近年では鈴木宗男議員の逮捕なども、会期中の逮捕許諾請求をへて行なわれている。したがって、これはきわめて異例な事態と言わざるを得ない。 議会の決議には、当然多数の賛成が必要ではある。しかし、十分な裏づけがあるにもかかわらず、多数党がその力で強引に許諾請求を否決したなら、それは当然に世論の批判にさらされるだろう。だから、たとえ多数党の有力議員であっても、請求が否決されることはそうそうあるものではない(参照)。 そもそも、会期中であろうとなかろうと、選挙で選ばれた国会議員が民意の代表者であることにかわりはない。だとすれば、法的にはともかく、検察は議員の逮捕については抑制的でなければならない。別件逮捕に近い軽微な容疑での議員逮捕が安易に認められるならば、それは国家の一機関にすぎない検察を、民意の上に置くことにほかならない。 健全なる民主主義を育てるのは、国民とその世論の役割なのであって、一国家機関が国民を代弁して行なうべきことではない。むろん、捜査機関の主観的な 「誠意」 まで疑おうとは思わない。しかし、東京地検特捜部といえども 「正義の味方」 などでは断じてないし(そもそも、そんなものはこの世には存在しない)、政治や政争とまったく無関係な超越的存在というわけでもないだろう。 どんな組織やシステムにも、それ自体の固有の利害というものがある。司法行政をめぐっては、ちょうど取調べの可視化などの議論も起きていることころだ。まして、組織を構成しているのは、地縁、血縁、学閥、閨閥などなど、様々な俗世のしがらみに縛られた具体的な人間である。 だからこそ、政治がらみの事件捜査では、中立公正さがとくに強く要求される。当然ながら、その中立公正さには、法によって強い権限を与えられた捜査機関が自己の固有の利害で動いてはならないということも含まれる。 どのような制度的保証があろうと、捜査機関の中立公正さとは、社会的に要請されることであり、少なくとも捜査機関自身が自らを律し、適正な手続きに従うことで守られるものであって、先験的に保証されているわけではない。もちろん当人らが 「わたしたちは中立公正です」 といえば、それがそのままとおるという話でもない。 国会開会までずいぶんと間があり、それまで待っていられないというのならともかく、開会直前の現職国会議員逮捕という東京地検の今回のやり方は、その点において、憲法と国会法の条文に反してこそいないものの、その精神には激しくもとるもののように思われる。 故事に 「瓜田に靴をいれず、李下に冠を正さず」 という言葉もあるが、このようなやり方をしているようでは、その政治的意図や背景を推測されてもしかたあるまい。なんとも 「すさまじき」 話としかいいようがない。最後につけくわえておくが、これは、民主党を支持するかしないかとか、小沢氏を支持するかしないかといったレベルの問題なのではない。
2010.01.17
コメント(1)
-
正月早々風邪をひいてしまった
ここ数日は 「西高東低」 のみごとな冬型気圧配置で、北風がびゅーびゅー吹き付けている。北陸から山陰にかけては、連日大雪が降っているとか。昔はこちらも冬には軒先につららが下がったり、路傍に霜柱が立ったりもしたものだが、最近はそういう話はとんと聞かぬ。雪が積もることも年に数回あるかないかで、雪だるまとか雪合戦などのような遊びもほとんど見られない。 清少納言は冬は早朝がよいとおっしゃったが、『枕草子』 にも年末から正月にかけて大雪が降り(旧暦だから今とはずれるが)、仕えていた中宮の命で役人や侍までかりだして、庭に雪山を作ったという話がある。それによれば、とちゅう雨が降ったりもしたけれど、一月以上、残っていたそうだ(第74段 「職の御曹司におはします頃」)。 昔の知り合いに、島根から福岡教育大に来た人がいたのだが、九州だからあったかいはずと思って冬物は置いてきたところ、寒くて寒くて往生したという。そりゃそうだ。そもそも北部九州は地勢的に山陰とつながっているうえ、福教大は宗像の山のふもとにあるのだから、玄界灘からの北風がもろに吹きつける。九州だから暖かいというのは、ただの偏見というもの。山のほうに行けば雪だって積もる。なんであれ、先入観というものはまことにやっかいなものだ。 報道によれば、奈良は桜井市にある桜井茶臼山古墳なるところで、81枚もの銅鏡が見つかったとか。桜井茶臼山古墳というのは、ひょっとして卑弥呼の墓ではないかとも言われている箸墓古墳とも近いが、箸墓のほうは宮内庁の指定により、孝霊天皇の娘である倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の墓ということになっていて、立入が禁止されているそう。 ところが、幸か不幸か、桜井茶臼山古墳のほうは昔はあまり目立たず、有名でもなかったため、誰の陵墓にも指定されることなく、放置されてきたらしい。おかげで発掘調査も可能だったということなのだろうが、これだけの副葬品が出てくれば、当然埋葬者は古代大王家につながる高貴なお方だと考えられる。規模だって、墳丘長が207mというからかなりでかいし。 しかし、宮内庁によれば、大王家の人々の墓は、すでにほとんど存在していることになっている。もし今後の調査で、茶臼山古墳の被葬者がその中の誰かということが明らかになると、いままでその人の墓ということになっていたところの指定を取り消さなければならなくなる。そもそも、古代の陵墓の指定はほとんどが江戸時代の尊皇ブームに始まるもので、当然ながら学問的な根拠などないに等しいものが非常に多い。 宮内庁が天皇やその一族の陵墓に指定しているもののなかには、怪しげなものが多いということは、以前から指摘されていることだが、そうやっていつまでも全然違う人の名前で祭祀を執り行っていたりしたら、いずれそのうちに 「おーい、おれはそこじゃないよ、ここにいるんだよ」 とか、「それは人違いだって、あたしゃその人とは違うよ」 みたいな声が、地の底から湧き出てくるのではあるまいか。 古来より、怨霊というものは恐ろしいものである。菅原道真は雷神となって恨みある藤原氏や天皇の一族に害をなしたし、保元の乱で弟の後白河天皇に負けて讃岐に流された崇徳上皇は、「日本国の大魔縁となり、皇を取って民とし民を皇となさん」 という誓いをたてて、平安末期の争乱を引き起こしたという。日本古来の信仰に忠実たらんと欲するならば、名を取り違えたままで祭祀を行なうのは、御霊(みたま)を恐れぬもっとも不敬な行為と言わざるを得ない。 さて、御年77歳の藤井財務相が健康上の不安を理由に辞任し、後任が菅直人に決まった。高齢の大臣といえば、戦前に6回も大蔵大臣を務めた高橋是清の場合、最後の蔵相を務めたのが80歳、また先の小泉内閣での塩爺こと塩川正十郎の場合が79歳であった。是清さんは2.26事件で暗殺されてしまったのだが、高齢な方にいつまでも重責を担わせるわけにはいかないだろう。いっぽう菅直人としては、鳩山首相がいつこけてもいいように準備万端といったところだろうか。 地元では、先の総選挙で落選した山崎拓前衆院議員が、夏の参院選への出馬をめざしているとか。しかし、自民党の谷垣総裁は、山崎氏がすでに70歳を越えていることを理由にそれを拒否する意向だという。これはまあ当然のことだろう。野党に転落した自民党は、ここで若返りをはかるとともに、それを世間にアピールすることが勢力回復のための第一歩なのだから。 本人としては、まだまだ心残りのこともあるのかもしれない。おまけにたたき上げの政治家である彼としては、安倍や麻生をはじめとした若い連中ときたら、どうしようもない世間知らずのお坊ちゃんばかりという心配もあるのだろう。とはいえ、参院は衆院とちがって解散もない、そのうえ任期は6年もあるわけで、どう見ても最近の山崎氏の姿は、たとえ当選したとしても任期を無事にまっとうできるようには思えない。 先日、今年初めての仕事が入ったのだが、たった2時間の仕事で2000円にもならなかった。今年も先行きは暗そう。前途多難な予感がする。景気の回復はなかなかむずかしそう。おまけに、正月早々、人混みの中に出かけたために風邪までひいてしまった。関連記事: 宮内庁もまだまだ了見が狭いと思う
2010.01.09
コメント(0)
-
正月なので暦についての話など
昨日はえらい寒く、予報ではこちらも雪といわれていたが、起きてみれば天気もよく比較的暖かだった。もっとも、一日家にこもっていてどこにも行かなかった。「初詣」 などというものには、とんと縁がない。別に「迷信」 だからというわけではなく、たんに人ごみが嫌いというだけのことだが。 正月とは新しい年の始まりだが、時間は物理的な延長のように目に見えるものでも、手で触れるものでもない。人が時間を実感するのは変化によってであり、その時間を区切ることが可能なのは、時間が円環的に進行するからである。時間が直線的にしか進行しなければ、そこに区切りを持ち込むこと、言い換えるなら時間の進行を単位によって計測し、それによって時間の経過を明確に意識することも不可能だっただろう。 つまり、われわれにとっての時間とは、生物の世代交代と同じように、死と再生を繰り返すということだ。日没とは太陽の死であり、日の出は太陽の再生である。そして、それは新たな一日の誕生でもある。同様に、大晦日とは古い年を埋葬する日であり、正月とは新しい年の誕生を祝う日のことである。これを神話的に言えば、「死」 と 「再生」 の物語ということになる。 たとえば、ルーマニア出身の宗教学者であるエリアーデは、『聖と俗』 という著書の中でこんなことを言っている。 これらのすべての事実がもつ意味を要約すれば次のようになると思われる。古代文化の宗教的人間にとって世界は年ごとに更新される。世界は新しい年がくるたびにその原初の神聖性を取り戻す。すなわち、再びかつて創造主の手を離れたときのようになるのである。... 時間が再生し、新たに始まるゆえんは、新年のたびごとに世界が新しく創造されたからである。宇宙創造の神話があらゆる種類の創造、建築の典型としていかに大きな意味を持つかはすでに前章に見たとおりである。今やわれわれはそれにつけくわえて、宇宙創造の中には時間の創造もまた含まれている。 つまるところ、正月が新たな年の再生であるとすれば、それを遡れば、宇宙の創造にまでたどりつく。だから、宇宙起源神話は同時に時間起源の神話でもある。時間を支配するものは宇宙を支配するものであり、その逆もいえる。実際、王や皇帝が人々を支配していた時代には、年はその治世をもって数えられた。洋の東西を問わず、それはどこの国をとってもかわらない。 さらにまた、新たな暦の制定とは、時間そのものの創造であり、新たな歴史の誕生を意味する。西暦がイエスの誕生した年を紀元とし(実際には少しずれているが)、イスラム暦がその開祖たるムハンマドらのメッカ退去の年を紀元としているのは、そのような事件によって、まったく新たな歴史が開かれたということを意味している。それは、それまでの時間の流れとその後の時間を切断することであり、神によって祝福された時間の開始を告げることでもある。 同様のことは、政治的な革命や建国の場合にもしばしば見られる。たとえば、フランス革命では、それまでのグレゴリオ暦にかわる革命暦が採用された。ジャコバン派の独裁が覆された事件は、「テルミドールの反動」 と呼ばれるが、テルミドールとは「熱月」という意味で、7月から8月にかけて。また、ナポレオンが権力を握ったのはブリュメール(霜月)で、10月から11月にあたる。 むろん、グレゴリオ暦が嫌われたのには、それがローマ教会に起源を持つという理由もあっただろう。また、「理性」 を崇拝するロベスピエールらにとって、時間が不均一な暦は 「理性」 に反する不合理なものに見えたのかもしれない。実際、革命暦では一月を一律に30日とするだけでなく、週=10日、一日=10時間、一時間=100分、一分=100秒というきわめて 「合理的」 な10進法まで採用されたということだ。 ところで、Wikipediaによれば、旧ソ連でも一時期ソビエト暦なる特殊な暦が使われていたらしい。恥ずかしながら、これは全然知らなかった。始まりは、レーニン死去から5年後の1929年。一月をすべて30日として、あまった五日間をすべて休日にするとか、7曜制を廃止するなど、フランス革命暦と非常に似ている。ただし、休日を年末にまとめていたフランス革命暦に対して、ソビエト暦では休日が月の合間に挟まっているのが少し違う。 その前年の28年には、トロツキーは国外追放処分を受けていた。その直後、今度は農民を擁護したブハーリンが、「右翼的偏向」 の名の下に失脚する。いわゆる 「大粛清」 はまだ先の話だが、スターリンはこの時期、すでにほとんどの政敵を追い落とし、ほぼ独裁に近い権力を握っていた。 その結果、スターリンは国家の工業化と近代化を旗印にした、強引な農業集団化と五ヵ年計画をスタートさせる。赤軍を動員して行なわれた集団化の実態がどのようなものだったかは、いまさら言うまでもないだろう。農地を採り上げられて自暴自棄になった農民は、土地の耕作を放棄し、数年後には大量の餓死者が発生することになる。 そのような状況下での、ソビエトのみに通用する暦の採用は、ソビエトを世界の他の地域とは違う、特別な時間が支配する特別な地域、つまりは 「革命の聖地」、「地上の天国」 として聖別化することにほかならない。それは、トロツキーに対抗して、「一国社会主義」 をぶちあげたスターリンの政治路線とも合致する。ちなみに、現在の階段ピラミッドのような石造のレーニン廟が作られたのは、翌年の1930年なのだそうだ。 一国での社会主義建設が可能かどうかという当時の論争には、いささかスコラ的な面もないわけではない。しかし、このような事実は、スターリンにとってこの論争がそもそもたんなる理論の問題ではなく、むしろ革命ロシアを、人類の新たな時代を切り開くという神聖なる使命を有する国として聖別化するという意味があったということを暗示している。そして、それはまた、政治的情熱と宗教的情熱とがときに持つ、強い親近性をも示している。 もっとも、この暦は不便だという声が強く、月の長さを元の戻すとか、5曜制を6曜制に変更するなど、数回の修正によってしだいにもとのグレゴリオ暦に近づけられ、最終的には第二次大戦勃発後、独ソ戦がはじまる前の年である1940年に廃止され、曜日も万国共通の七曜制に戻されたということだ。
2010.01.01
コメント(0)
-
今年もいよいよ残り少なくなってしまった
ぼおっとしていたら、あっという間にクリスマスも終わり、今年もあますところあと数日ということになってしまった。早いものだ。早いといえば、このブログも書き始めてから三年が経過した。なにごとにも飽きっぽい人間としては、なかなかよく続いたものだ。 なにしろ三年といえば、赤ん坊ならふんぎゃーと生まれてから、大人を真似した理屈を並べるようになったりするし、中学生なら入学から卒業までの期間にあたる。それはつまり英語であれば、ABCを覚えるところから関係代名詞などというものを習うまでの期間ということになる。はたして、この三年間に、子供のそういった成長に相当するだけのものが得られたのかは、残念ながらきわめて心もとない。 先日、まだ冬であるにもかかわらず、例年なら春になってから飛んでくる黄砂が観測された。これが、中国の広がり続けている砂漠化や、地球規模の気候温暖化に関係があるのかは知らない。ただ、砂漠が沿岸部まで広がって、日本までの距離が短くなれば、黄砂現象の頻度も高くなるということは言えるのではあるまいか。 黄砂の故郷としては、中国北部のゴビ砂漠、西部のタクラマカン砂漠、さらに中央部に位置する黄土高原の三ヶ所があるという。ゴビとタクラマカンの二つの砂漠はともかくとして、北から流れてきた黄河が東へと90度に屈曲しているあたり、その支流のひとつである渭水流域というのは、かつては唐の長安に代表される中国の最も栄えた地域であったし、その北には日中戦争の最中にエドガー・スノーやスメドレーが訪れた、「革命の聖地」 延安がある。 従 軍 行青 海 長 雲 暗 雪 山孤 城 遥 望 玉 門 関黄 沙 百 戦 穿 金 甲不 破 楼 蘭 終 不 還青海の長雲 雪山暗し孤城遥かに望む 玉門関黄沙百戦 金甲を穿つ楼蘭を破らずんば 終に還らじ 『唐詩選』 より 作者は王昌齢という人。よくは知らないが、杜甫や李白とほぼ同時代の人らしい。ここで言う黄沙とは、日本に飛んでくる黄砂ではなく、黄土高原の奥地からさらに西域へと向かうあたりのだだっ広い乾燥地帯のこと。 時代はかの玄宗皇帝の治世。東の唐と西のイスラムという巨大な世界帝国が、いまのキルギスにあるタラス河のほとりで激突し、唐が大敗したというころ。しかし、その結果として、中国の紙が西方に伝わったというのだから、この戦いもまったく無意味というわけではなかったということになる(のかな)。 やがて、玄宗は美人の誉れ高き楊貴妃に夢中になって政治を省みなくなり、結果、有名な安禄山の乱が起こる。「奢る平家は久しからず」 といったところか。 さて、前にふれた 「むかつく」 ことに、もうひとつつけくわえておこうかなと思う。それはなにかと言えば、誰でも知っている程度の当たり前のことを、「どうだ、おれはこんなことを知ってるんだ」 と言わんばかりに振り回す人。たとえば、「世間には危険がいっぱいだ」 とか、「差別と区別は違うよ」 とか、はたまた 「論と人は切り分けろ」 とか。 まあ、どれもそれだけ採り上げれば間違っているわけではない。「差別」 と 「区別」 はたしかに違う。なんでもかんでもごっちゃにしては、話にならない。「是々非々」 だって、その意味を正しく理解しているのなら、間違ってはいない。しかし、こういうのは、1たす1は2であるとか、水は水素と酸素からできているというような、価値判断を含まぬ単純な 「事実命題」 とは違う。 そういった 「事実命題」 なら、その人がどこまで理解しているか、ただの受け売りではないのかといったことは別として、誰が言おうとたしかに 「真理」 である。しかし、抽象的な概念で成り立っていて、「価値観」 や 「価値判断」 が含まれる命題というものはそうはいかない。 せっかくの立派な言葉であっても、胡散臭い人が言えば、胡散臭く聞こえてしまう。だから 「論」 と 「人」 とはたしかに別ではあるが、だからといってまったく関係ないというわけでもない。誰も反対できない麗々しい言葉を掲げることと、それをその人がどこまで理解しているかや、どこまで本気なのかということとは、まったく別の問題である。 「是々非々」 を掲げている人が、本当にそういう態度を貫いているかどうかは、別の話である。むろん、そういう人もいれば、そうでない人もいるだろう。自分は 「論」 と 「人」 を切り分けている、と言っている人が、本当にそうしているのかどうかも、これまた別の話である。 人は看板ではなく、言動を含めた行動で判断される。「差別反対」 でも 「戦争反対」 でもなんでもいいが、世の中、「自称」 の看板がそのまま全部認められるのなら、ぴょんぴょん靴を発明したドクター中松は、エジソンに負けぬ大発明家である。 中には、部落差別の原因は 「穢れ」 の思想にある、だから、葬儀での清めの塩は良くない、それを問題にしない者は、本気で差別と戦っているとはいえないというようなことを言う人もいる。へへぇ、清めの塩をなくしたら、現実の差別が少しでも減るのかね。 むろん、問題ありと思う人は、断ればよい。それは人の自由というものだ。しかし、現実の差別をどうするかよりも、「迷信」 撲滅のほうが大事だなんて、それじゃまるで、封建的因習の撲滅を掲げてあちこちの寺や仏像を破壊してまわった、どこかの国の 「紅衛兵」 みたいだな、などと思ってしまった。 だいたい、なんにかぎらず長い歴史を持つ社会的な制度やイデオロギーというものの場合、歴史的な起源=発生ということと、現代における存在の根拠というものは、かならずしも同じではない。歴史とは、まさに変化のことなのだから。
2009.12.28
コメント(0)
-
今日は風花が舞った
このところ急激に寒くなってきた。どうかすると一日中、鉛色の厚い雲が空をおおっており、たまに雲の合間から陽がさしても、低い位置から斜めに差し込む光には冷えた大気を暖める力はない。北風が嵐のようにびゅうびゅうと吹き、建物と建物の間で渦をまいて唸り声を上げる。 昨日と言うべきか、今日と言うべきか、どちらが正しいのかよく分からないが、とにかく今朝まで仕事をし、それから床について昼過ぎに目を覚ました。起きようとしたら、なんだか腰が痛い。曲げても伸ばしても痛い。これはまずい。なにかの祟りなのか、それとも誰かの呪いなのか。気持ちは若いつもりでも歳はごまかせぬ。 近くのスーパーまで食い物を調達しに外へ出たら、ちょうど陽がさし、少しばかり青空ものぞいているのに、白いものがひらひらと舞ってきた。おお、風花ではないか、これはまたロマンチックなと思ったが、冷たい外気は腰に良くない。腰をいたわりながら、早々に家へ戻った。 平地に風花が舞うということは、山のほうはおそらく本格的な雪なのだろう。平野を囲む山のほうに目をやっても、かすんでよく見えない。それほど高い山ではないから、クマやシカのような獣はもとからいやしまいが、イタチぐらいならまだいるかもしれない。そういえば、母さん狐から白銅貨をもらって、町へ手袋を買いにいった子狐の童話を書いたのは新美南吉であったか。 ところで、「風花」 なる言葉を知ったのは、高校時代に読んだ福永武彦の短編によってであった。「倫理社会」 のような受験にあまり関係のない授業は、多くの生徒が他の教科の宿題をやったりと、ほとんど公然たる内職の時間になっていたのだが、たまに読書の時間にもあてていた。先生方にはまことに申し訳ない。 その息の向こうに、白い細かなものが宙に舞っていた。それはあるかないか分からない程かすかで、ひらひらと飛ぶように舞い下りた。その向こうには空があった。鉛色に曇った空がところどころに裂け目を生じて、その間から真蒼な冬の空を覗かせていた。その蒼空の部分は無限に遠く見えた。かすかな粉のようなものが、次第に広がりつつあるその裂け目から、静やかに下界に降って来た。「ああ風花か。」 彼は声に出してそう呟いた。そして呟くのと同時に、何かが彼の魂の上を羽ばたいて過ぎた。福永武彦 「風花」 より 新潮文庫 『廃市・飛ぶ男』 所収 『死の島』 をはじめ、福永の長編にはさまざまな実験的手法や技巧を凝らしたものが多いが、そのような余裕のない短編では、作者の資質である感傷性が生に表出される嫌いがある。ややもすると 「少女趣味」 っぽい感じがして、辟易してしまうところもあるのだが、ぼろぼろの文庫を引っ張り出してちらちら読み直してみると、この短編には明らかに作者自身の過去が影を落としている。 年譜によれば、福永は終戦間際に急性肋膜炎にかかり、療養をかねて帯広に疎開している。その後、いったんは帯広中学の英語教師になるのだが、病気が再発してふたたび長い療養生活を余儀なくされる。その間に、離婚してまだ幼かった息子と別れることになる。その息子とは、いうまでもなくのちに芥川賞をとった作家の池澤夏樹のことである (参照)。 いまのような特効薬のなかった時代には、胸の病というのは文字どおり命にかかわる病気であった。幕末の高杉晋作や沖田総司から、石川啄木や正岡子規、さらに戦後の堀辰雄にいたるまで、多くの人が命を失っている。戦前の文学青年にとって、肺を病んで蒼白い顔をすることは一種の憧れであったらしいが、とにかく栄養と休養をとって長期の療養をする以外に処置のしようがない不治の病であった。そういえば、中学や高校の先生の中にも、結核の手術で片方の肺がほとんどないというような人もいたりした。 ところで政治的な前衛と芸術的な前衛を結びつけること、言い換えれば政治的社会的な革命と文化や芸術の革命を結びつけることは、戦後の花田清輝の活動の出発点にあったテーゼであるが、それはまたかつてのロシア・アバンギャルドの夢でもあった。 エイゼンシュテインやメイエルホリド、マヤコフスキーなどによって進められた先鋭的な芸術運動が、最後には党の指導という名の下で政治への屈服を余儀なくされたのは、もちろん花田も知っていただろう。自殺した者、粛清された者、亡命や沈黙を余儀なくされた者は数知れない。フランスにおいても、党に忠誠を誓ったアラゴンはシュルレアリスムを捨て、シュルレアリスムを守ったブルトンらはトロツキーに接近する。 そういった歴史的経緯について、花田が無知だったとはとうてい考えられない。むろん花田の活動がすべて無駄だったわけではあるまい。しかし、最後には新日本文学会を拠り所として党中央に抵抗するところにまで追い詰められた花田には、そもそもいったいいかなる計算があったのだろうか。疑問は尽きない。こんなことを考えたのは、最近、亀山郁夫の 『ロシア・アバンギャルド』 (岩波新書)なる本を読んだから。 それにしても寒い。報道によれば、元F1レーサーの片山右京と一緒に富士に登った友人らが遭難したらしい。富士の頂上は零下をはるかに下回るらしいが、寒さに震えているのは、もちろん山の獣だけではあるまい。
2009.12.18
コメント(2)
-
小泉八雲と夏目漱石、さらにアイルランドのことなど
小泉八雲ことラフカディオ・ハーンと夏目漱石の因縁浅からざる関係については、以前にちょっとだけ触れたことがある。八雲が熊本の第五高等学校(現在の熊本大学)を退職したのが1894年。漱石はその二年後に第五高等学校で、同じく英語の教師を務めている。 五高を退職した八雲は、いったん神戸のジャパンクロニクルなる英字新聞社に務めるものの、外国人居留地の雰囲気にうんざりし、二年後の1896年には東京大学の英文学講師となる。この間、漱石のほうは文部省からイギリス留学を命じられる。留学中の漱石が、その極端な言動のゆえに、友人らから狂人扱いされたのは有名な話。 漱石が帰国したのは1903年、ちょうど日露戦争の前年にあたる。その年、八雲は東大を退職し、イギリスから帰国した漱石が、すぐにそのあとを継ぐよう命じられる。八雲の東大退職は任期満了のためだそうで、大学を辞めること自体に不満はないものの、通知一本での解職というやり方にはいささか腹をたてたらしい。しかし、その翌年に狭心症を起こして亡くなっている。享年54歳である。 漱石の作家としての処女作は、いうまでもなく 『吾輩は猫である』 だが、その中には、主人公の苦沙弥先生が 「僕のも大分神秘的で、故小泉八雲先生に話したら非常に受けるのだが、惜しい事に先生は永眠されたから、」 と一ヶ所だけ、八雲について語ったところがある。八雲の奥さんだった小泉節子が書いた 『思い出の記』 によれば、八雲の家には、誰によっては分からぬが、俳誌の 「ホトトギス」 が毎号届けられていたとのこと。 このとき東大の学生の中には、やめた八雲を慕うものが多く、漱石はいささか苦しい立場にあったようだ。漱石の死後に、夏目鏡子が書いた 『漱石の思い出』 には、この辺の事情がこんなふうに書かれている。 狩野さん大塚さんなどの肝煎りで、望みどおり熊本に帰らないで、東京にいて一高で教鞭をとることになりましたが、それだけでは生活にも困ろうとあって、文科大学の講師ということになって、小泉八雲先生のちょうど後に入ることになりました。どうしてそういうことになったのか、その間の消息は私には分かりませんが、当人ははなはだ不服でして、狩野さんや大塚さんに抗議を持ち込んでいたようです。 夏目の申しますのには、小泉先生は英文学の泰斗でもあり、また文豪として世界に響いた偉い方であるのに、自分のような駆け出しの書生上がりのものがその後釜にすわったところで、とうてい立派な講義ができるわけのものでもない。また学生が満足してくれる道理もない。 八雲は漱石より17も年上で、日本とその文化について紹介した著書はすでに世界的に有名となっていたから、漱石が困惑したのは分からないでもない。『猫』 で 「僕のも大分神秘的で」 と主人公が言ったのがなにを指すのかはわからないが、たしかに漱石の 『夢十夜』 などはりっぱな怪談であるし、『倫敦塔』 や 『幻影の盾』 なども気味の悪い怪奇小説である。なお、漱石の 『こころ』 に対して、八雲には 『心』(現題は"kokoro")という随筆集がある。 年譜によれば、八雲はアイルランド人の父親とギリシア人の母親の間に生まれている。二人は父親が軍医として勤務していたイオニアの島で知り合い、そこで生まれたそうだ。思わず、ソフィア・ローレンが主演した映画 『島の女』 を連想しそうだが、こちらは土地の名士の娘なのだそう。そういえば、島尾敏雄も、戦争中に特攻隊の隊長として赴任した島の女と結ばれている。やっぱり、遠い海の向こうから来た人とかはもてるのだろうか。むろん、皆がみなそうというわけではあるまいが。 話がすこしそれた。その後、八雲は父親の家があるアイルランドのダブリンに帰国しているが、父親は今度は西インドに赴任し、残された母親は精神を病みギリシャにひとりで帰国(このへんもやや島尾と似ている)。八雲は大叔母さんに育てられたとか。ところが17歳のときに父親は死亡、おまけに保護者であった大叔母は親類にだまされて破産したとか。これでは、こんどは 「小公女セーラ」 である。 そこで仕事を探しにロンドンにで、さらに移民船で海を渡ってアメリカへ向かうことになる。ここまでは、ヨーロッパでは希望のみえぬ者がたどるよくある話。そこで20年をすごしたのち、1890年にようやく日本に来ることになる。それ以前に、ニューオーリンズで開催された万国博覧会の会場で、日本人の役人に会ったことがあり、そのつてで松江に行くことになったそうだ。 八雲がヨーロッパやアメリカを嫌い、日本の文化に憧れたのには、おそらく彼個人のそれまでの体験が大きな影響を及ぼしているだろう。たまたま文才を認められて這い上がることができたものの、彼の一生はけっして順風満帆なものだったわけではない。そのことが、奴隷として連れてこられた黒人による独特な文化が残るアメリカ南部やカリブの島々に魅せられることになり、やがては海の向こうの日本へと向かわせることになる。 それは、産業革命によってすべてが機械化され、天をも突くような高層ビルが建ち並ぶ大都会と、その中でが気ぜわしく動き回っている人々への嫌悪から来たものであり、それがおそらくはその対極にあるものへと引き付けられた理由なのだろう。そういう彼の気質が、そもそもの出自であるアイルランドと関係あるのかは、なんとも言えないのだが、まったく無関係ともいえなさそうな気はする。 アイルランド出身者といっても、もとをたどればイングランドから来た植民者であり、支配者の側につながる者もいて、十把一絡げにはいかぬのだが、この地からは古くは哲学者のバークレーや 『ガリバー旅行記』 のスウィフト、『フランス革命についての省察』 を書いたエドマンド・バークから、ワイルドやバーナード・ショー、詩人のイェーツや作家のジョイス、劇作家のベケットと多士済々の人物が出ている。 クロムウェルによる占領以来、イギリスの支配下に置かれていたアイルランドが、いかに困窮のきわみにあったかということは、そこから多数の移民(いまふうに言えば「経済難民」)が流出したことからも分かる。現在、本国に住むアイルランド人は、イギリス統治下の北アイルランドを含めても、わずか500万ほどにすぎぬのに対して、アメリカなど、海外に流出した移民の子孫はその十倍近い4,000万に上るのだそうだ。 イングランドへの隷属に長く苦しんだアイルランドがようやく独立したのは、19世紀に始まる独立運動の末、第一次大戦後の1921年のこと。ちなみに、アイルランド問題について、マルクスは1869年に友人のクーゲルマンに宛てた手紙の中で、こう書いている。 僕はますますつぎの確信をふかめるにいたったが、これをイギリスの労働者階級に徹底させることはきわめて重要である。すなわち、イギリス労働者階級がアイルランドにかんする彼らの政策を支配階級の政策からもっとも断固として分離させ、アイルランド人と共同歩調をとるばかりでなく、1801年に創設された同盟を解体して、そのかわりに自由な連合関係を樹立しないかぎり、彼らはこのイギリスではなにひとつ決定的なことはできないのだ。
2009.12.13
コメント(2)
-
小春日和またはインディアンサマーのことなど
こちらでは、ここ二三日とても暖かい日が続いている。まさに 「小春日和」 という言葉がぴったりだ。澄みきった大気は暖かい光で満たされ、樹々の葉はすでに赤や黄に色づき、風が吹くと、「金色の小さき鳥の形」 した木の葉がはらはらと舞い散る。「落ち葉が舞い散る停車場に~」 と歌ったのは、昭和の御世の奥村ちよであったか。しかし、街頭で落ち葉をはいている人たちはたいへんである。 「天高く馬肥ゆる秋」 とは、もとは北方民族の脅威にさらされていた中国の人々が、ああ、また北の方から獰猛な連中が丸々と太った馬に乗ってやってくる季節になったぞ、ということを表す言葉だったそうだが、英語のインディアンサマーについても、インディアンが襲ってくる季節という意味だという説がある。ただし、こちらのほうは異説もいろいろとあって、はっきりしたことは分からない。 最近、暇つぶしに渡辺公三という人が書いた 『闘うレヴィ=ストロース』(平凡社新書)という本を読んだが、これはこんな一節で終わっていた。 レヴィ=ストロースはインディアンたちが、多くの場合、到来した白人たちを神話に語られた祖先の礼が回帰したものとして腕を開いて迎え入れた、ということを強調している。到来すべき他者の場所をあらかじめ用意すること、他者を 「野蛮人」 とみなすばかりではなく、時には神として迎え入れる謙虚さを備えること、他者のもたらす聞きなれぬ物語をも自らの物語の中に吸収し見分けのつきにくいほどに組み入れること。 しかし、その他者が究極的には、分岐し差異を極大化してゆく存在であることを許容すること。自らの世界の中に場所を提供しつつも、対になることは放棄せざるを得ない不可能な双子、アメリカ・インディアンにとって外部から到来した 「西欧」 の存在をそこに読み取ることができる。これが 『大山猫の物語』 でレヴィ=ストロースが引き出した結論だった。 この本は今年の11月13日に出たばかり、つまりレヴィ先生が亡くなってから半月して出たことになる。まさか、レヴィ先生死去の報を聞いて急遽書き上げ、出版したわけではあるまいにと思ったら、本来は昨年の100歳のお祝いにあわせてということであったらしい。ところが、それが間に合わず、一年遅れになって、たまたま彼の死去の直後に出版されることになったということだ。これもまた、偶然のなせる業ということか。 この本では、彼が二十歳前後の学生で、フランス社会党の中心的な学生活動家だった時期の活動にも触れらていて興味深かった。彼が最初に出版した文書は、なんと18歳のときに書いた 『グラックス・バブーフと共産主義』 なる小冊子だったという。バブーフとは、フランス革命の末期、ロベスピエールらが処刑されたあとに、政府打倒の 「陰謀」 を企てたとして処刑された人だが、そこから後世のブランキや季節社にもつながる。 偉大なるナポレオンの甥っ子であるナポレオン三世は、若い頃、兄貴とともにイタリアの秘密結社カルボナリ党(「炭焼党」 と訳されることもある。関係は全然ないが、倉橋由美子の 『スミヤキストQの冒険』 はこれから名前を借りてる?)に参加していたそうだが、これもバブーフと関係がある。 レヴィ=ストロースの 『悲しき熱帯』 には、十代のころに、ある若いベルギー人の社会主義者によって、マルクスについてはじめて教えられたと書いてあって、そういやベルギーといえばアンリ・ド・マンという人がいたなあ、とか以前から思っていたのだが、渡辺によると、ド・マンがパリで講演会をしたときも、レヴィ=ストロースはその準備に当たったらしい。 アンリ・ド・マンという人は、当時ベルギー労働党で注目されていた新進理論家だが、ナチによるベルギー占領に協力したために、戦後はほとんど忘れられた。その甥っ子が、イェール学派の総帥で 「脱構築」 とかいう言葉を流行らせたポール・ド・マンであり、彼が当時、ナチを支持するような文章を書いていたことが暴露されて、一時期スキャンダルになったことは、彼の弟子(?)である柄谷行人なども触れている。 ちなみに、柄谷によれば、ポール・ド・マンと親しかったデリダに、アンリ・ド・マンのことを聞いてみたら、「だれ、それ?」 みたいな返事が返ってきたそうだ。アンリ・ド・マンには 『労働の喜び』 なる著書があり、ソレルの 『暴力論』 の新訳を残して亡くなった今村仁司が 『近代の労働観』 なる著書の中で、それについて触れているそうだが、そっちは全然知らない。 なお、ナチスの強制収容所の入口には、「Arbeit macht frei, 労働は(人間を)自由にする」 と書いてあったというのは有名な話。また、イタリアのドーポラヴォーロを真似してナチスが作った、労働者の福利や余暇についての組織の名称は、「Kraft durch Freude, 喜びをつうじて力を」(「歓喜力行団」 などとも訳される)という。 ところで、「来年のことをいうと鬼が笑う」 とよく言われるが、それはなぜなんだと思って調べてみたら、これもまた諸説あるらしかった(参照)。 仕事がない、仕事がない、とぶつぶつ言っていたら、いきなり仕事が入って忙しくなった。でも、それもあと何日かでおしまいであり、その先どうなるかはまったく分からない。鬼に笑われてもいいから、来年のことが心配である。昨年にくらべて、今年は三割近い減収になることはほぼ確定しているもので。
2009.12.03
コメント(0)
-
三島由紀夫とは何者だったのか
市谷で自決する6年前に三島由紀夫が書いた、『私の遍歴時代』 というタイトルのなかば自伝風のエッセーは、次のように始まっている。 小説家として暮らしている今になってみると、むかし少年時代の私が、何が何でも小説家になりたいと思っていたのは、実に奇態な欲望だったと思い当たる。こんな欲望は、決して美しいものでもロマンチックなものでもなく、ようするに少年の心がおぼろげに予感し、かつ怖れていた、自分自身の存在の社会的不適応によるのであろう。今とちがって、小説家になれば金持ちになるから、などという空想はありえなかった。 ここには、おそらくなんの嘘もないだろう。肉体や現実よりも先に言葉を獲得し、遅れて肉体を持ったときには、「その肉体は言うまでもなく、すでに言葉に蝕まれていた」(太陽と鉄)と回想しているような早熟の少年にとって、自分がぎこちない肉体を持ち、言葉によっては支配できない現実の中に生き、現実に拘束されていることは、たぶんとても耐え難いことであったに違いない。 だとすれば、彼が戦争末期を振り返って、「自分一個の終末観と、時代と社会全部の終末観とが、完全に適合一致した、まれに見る時代であった」 と言っているのも、じゅうぶんに理解できる。そこには、たしかに彼自身言っているように、いくらかの過去の美化が混じってはいるかもしれない。だが、なんといっても、「世界はわれとともに滅びるべし」というのは、今も昔も変わらぬ、ロマン主義者が夢見る最大の夢なのである。 しかし、「世界の破滅」 という夢が未発におわったとき、この浪漫派かぶれの早熟な少年にとって、「不幸は、終戦とともに、突然私を襲ってきた」。少年はいっときの夢から覚めて、つらい現実の中で生きていかねばならない。 幸運にも、この少年は感じやすい自我とともに、不釣合いなほどに強い意志を持っていた。だが不幸なことに、その意志にはかんじんなものが欠けていた。そのうえ、鈍重な現実によって鍛えられる前に、時代の寵児となってしまうほどの才能を持ち合わせていた。そのことも、おそらくは彼にとって不幸なことだったと言えるだろう。 売れっ子となった三島は、驚異的な努力によって肉体を鍛え上げ、隆々たる筋肉をまとうこととなったが、筋肉を鍛え上げるのは容易でも、運動神経を鍛えるのは容易ではない。三島の剣道がへたくそだったことは、当時、盾の会にいた人の証言があるが、運動音痴がへたに筋肉をまとえば、動きはかえってぎこちなくなる。「運動音痴」 とは、ようするに世界に対する肉体の違和であり、おのれの肉体に対する違和の別名なのである。 三島の葬儀で、武田泰淳は 「君はもう頑張らなくていいんだよ」 と語りかけたという。「頑張る」 とは、彼の場合、つねに他人の期待にこたえることであった。父親の期待にこたえるため勉学に頑張り、世間の期待にこたえるため 「流行作家」 として頑張り、マスコミの要求にこたえるため、「英雄」 という名の 「道化」 を演じることに頑張った。半世紀にも満たない、三島という人の一生は、そういうものであったように見える。 筋肉をまとい、健康な肉体を手に入れたことで、三島はたぶん、ひ弱で孤独だった少年時代には遠くから羨望しながら眺めていた、「男の世界」 に入る資格がようやく得られたと思ったのだろう。彼の自衛隊への体験入隊とは、そういうものだ。だが、高名な作家を迎え入れた自衛隊の側の気苦労は、はたしていかなるものであったのか。『太陽と鉄』 で体験入隊について語る、その華麗な文章はほとんど滑稽でしかない。 たかだか11メートルの高さからにすぎない落下傘の訓練程度で、「そのとき明らかに、私は、私の影、私の自意識から解き放たれていた」 などと語っていること自体が、彼が抱えていた自意識という病の深さを明るみに出している。普通の隊員は、そもそもそんなことなど考えもしまい。自意識という病は、結局のところ、彼が死ぬまで抱えていた狼疾であったのだ。 たとえば、最初に冒頭部分を引用した『私の遍歴時代』 というエッセーは、こんなふうに締めくくられている。 そこで生まれるのは、現在の、瞬時の、刻々の死の観念だ。これこそ私にとって真に生々しく、真にエロティックな唯一の観念かもしれない。その意味で、私は生来、どうしても根治しがたいところの、ロマンチックの病を病んでいるのかもしれない。26歳の私、古典主義者の私、もっとも生の近くにいると感じた私、あれはひょっとするとニセモノだったかもしれない。 官僚一族に育った三島由紀夫は、ロマン主義者としてふるまうには明晰であり、律儀でありすぎた。また古典主義者であるには懐疑的でありすぎた。人はロマン主義者であるには、自己への懐疑を禁じなければならないし、古典主義者であるには世界への懐疑を捨てねばならない。なんの情熱も持ちえない者は、唯美主義者ではありえても、ロマン主義者にはなりえない。たとえ不毛なものであろうと、情熱を欠いたロマン主義者とは、一個の背理にすぎない。 「われわれは、護るべき日本の文化・歴史・伝統の最後の保持者であり」 とか、「日本精神の清明、闊達、正直、道義的な高さはわれわれのものである」、「千万人といえども我往かん」、「民衆の罵詈讒謗、嘲弄、挑発をものともせず、かれらの蝕まれた日本精神を覚醒させるべく」(反革命宣言 『文化防衛論』 所収)などと語る彼の言葉は、ほとんど愚劣でしかない。定型文句を並べ立てたその空疎さは、とても言葉を偏愛した三島のものとも思えない。 福田和也は文庫版 『文化防衛論』 の解説で、「三島は不敵かつ不吉な扇動者となった」 と書いているが、冗談ではない。これは扇動としてはまったく馬鹿げており、同じ時期に、「前段階武装蜂起」 による首相官邸占拠を唱えて、大菩薩峠で大量逮捕された赤軍派にすら、遠く及ばない。この扇動文の空疎さは、むろん彼の現実認識の空疎さを反映したものと言えるだろう。 認識は情熱を必要とする。情熱のないところには、いかなるまともな認識も生まれない。戦争中にはどこにでも溢れていたような、空疎な決まり文句をただ羅列した扇動も、彼が作り上げたわずかな人数のおもちゃの軍隊も、結局のところ、すべて彼にとっては、自己の死を飾り立てるための道具立てに過ぎなかったように見える。 おそらく三島の悲劇は、彼が頑張りすぎる人だったことにある。社会的不適応という自覚があったのなら、無理してマスコミや文壇の寵児であり続ける必要などなかったはずだ。彼の強烈な克己心は、つねにただひ弱な自我を覆い隠し、他人の視線に応えるためにのみ充てられたように思える。それはすべて不必要な 「頑張り」 であり、ただ最後の悲劇を招きよせることに役立ったにすぎないように見える。 マスコミに出続けたのも、鎧のごとき肉体を誇ったのも、同業者らの前でわざとらしい豪傑笑いをしてみせたのも、全共闘の学生らと対談をしてみせたのも、すべては自分は本当はニセモノではないのかという猜疑につねにさいなまれ、他人の視線と評価を気にせずにはいられなかったという、少年の頃と変わらぬひ弱な自我の表れでしかなかったように見える。 彼の死は、個人としてはたしかに悲劇だったかもしれない。しかし、政治的な事件としては、まったくの喜劇でしかない。もちろん、毎年各地で行なわれている、「憂国忌」 などという事々しい名称の行事は、それ以上に愚劣な茶番でしかない。 戦後17年を経たというのに、いまだに私にとって、現実が確固たるものに見えず、仮の、一時的な姿に見えがちなのも、私の持って生まれた性向だと言えばそれまでだが、明日にも空襲で壊滅するかもしれず、事実、空襲のおかげで昨日あったものは今日はないような時代の、強烈な印象は、17年ぐらいではなかなか消えないものらしい。『私の遍歴時代』 もしも、彼があと五年、遅く生まれていたなら、大衆化した戦後の文学を象徴する、時代の先頭を切った寵児としての役割を無理に演じ続けることもなければ、戦争中に流行したような、つまらぬ 「死の美学」 に回帰的に引き寄せられるようなこともなかったかもしれない。そのような仮定は、むろん無意味なものではあるが。二年前の関連記事: 今年も 「憂国忌」 の季節がきた追記: ふっと思い出して、橋本治の著書を探し出してみたら、タイトルが同じでありました。
2009.11.24
コメント(3)
-
河合隼雄『影の現象学』は書棚にちゃんとあった
最近は不景気のせいか、めっきり仕事の量も減っている。とりわけ、夏以降は極端な低空飛行が続いており、このままでは墜落しかねない。昨年9月にアメリカで起きたリーマンショックに始まる世界的な不況は、まず輸出を主とする製造業を直撃したが、その後も立ち直る気配はなく、じわじわと社会や産業の末端のほうへと浸透しているのかもしれない(経済については疎いので断言はしない。あくまでもただの印象)。 同業者らの話を聞くと、どうやら業界全体が不景気であり、仕事の絶対量そのものが減ってきているようだ。ということは、夏をすぎて仕事が減ってきたのは、とりあえずミスや不手際といった自己の責任によるものではないということになる。とはいえ、それは言い換えると、自分の力だけではどうにもならぬということだから、これはいったい喜ぶべきことなのか、悲しむべきことなのか。 先日、ニャーニャー弁でおなじみの 地下に眠るM さんから、ユング心理学の入門書として、河合隼雄の 『影の現象学』 を薦められた。そのときは書名しか知らないと答えたのだが、二三日前に、なにげなく書棚を見たらちゃんと飾ってあった。おやおや、いったいいつの間に、これこそユングの言うシンクロニシティかな、などと思ったが、なんのことはない、自分で買っていたことを忘れていただけ。もはや自分の書棚になにがあり、なにがないのかも分からない状態なのだ。 ぺらぺらっとめくってみると、たしかに 「ドッペルゲンガー」 についても、いろいろと触れられている。事前にこの本を読んでおけば、もうちょっとましなことが書けたかもしれない。ユングと、そして河合自身も言うように、たしかに影とは誰もが持っている自分の半身であり、また分身である。それは世界各地の多くの神話や伝承、民話や習俗、さらには子供の遊びなどからさえ確認できる。 しかし、ユングの言う影とは、それだけに留まらない。同書から彼の言葉を孫引きすると、「影はその主体が自分自身について認めることを拒否しているが、それでもつねに、直接または間接に自分の上に押しつけられてくるすべてのこと ―― たとえば、性格の劣等な傾向やその他の両立しがたい傾向 ―― を人格化したもの」 であり、河合の言葉によれば、「その人によって生きられることなく無意識界に存在している」「その人によって生きられなかった半面」 というのが、その人の影ということになる。 同書では、シャミッソーの 『影をなくした男』 がとりあげられているが、この短編では、金に困っていた主人公のペーター・シュレミールが、ある金持ちの園遊会で見かけた、ドラえもんのように服のポケットから次々と物を出す不思議な 「灰色の服の男」 から、影と引き換えに、次から次にいくらでも金貨が出てくる 「幸運の金袋」 を授かる。 しかし、影をなくした男は、たちまち世間による迫害の嵐にあう。しつけのなってない悪がきどもからはからかわれたり、馬糞を投げつけられたりと、行く先々で散々な目にあうことになる。それはそうだろう、影がないとは実体がないということであり、ようするにこの世の存在ではないということだから。 結局、最初の約束どおり、一年後に再会した 「灰色の服の男」 に、シュレミールはもらった金袋と交換に自分の影を返してほしいと頼むのだが、かわりに 「灰色の服の男」 からは、影を返してほしけりゃこれにサインしろと、一枚の紙を突きつけられる。それにはこう書いてある。ワガ魂ガ肉体ヨリ自然離脱セシ後ハ、本状所有者ニ遺贈ツカマツルコト、異議ナキモノナリ。 つまり、この 「灰色の服の男」 とは、あの 『ファウスト』 にも出てくるメフィストフェレスと同じ悪魔だったのだ。あな、おそろしや。 なんか、話がそれた。ユングの言う 「影」 とは、自己の気づかぬ半身のことであり、多くの場合、それは意識的な自己とは正反対のものである。ちょうど、鏡に映った姿が左右反対であるように。 なので、厳格な禁欲的道徳を内面化した人は、それと正反対の放恣な性格を影として持っていることになるし、聖人君子のような利他愛を説く人は、その反対である利己性を影としていることになる。サドとマゾ、権威主義と反権威主義が相補的であることはフロムも指摘しているが、同性愛者をもっとも嫌悪し憎むものが、自身そのような傾向をかくしもっている者らであるということもよく言われる。 つまり、ユングによれば、人は多かれ少なかれ、二重人格者だということになる。それはたぶんそうなのだろう。「人格」 というものは、みなけっして一枚岩ではないし、人間は実際そう単純ではない。もし、本当にそんな人がいるとしたら、それは平板で深みにかけた鋳型のごとき人間であるにすぎない。ちなみに、「きれいはきたない、きたないはきれい」 とは、かの 『マクベス』 の冒頭に出てくる魔女の台詞である。 実際、明治の時代に内面的な道徳を説くキリスト教にもっとも惹かれたのは、おのれの欲望の強さに悩み苦しんだ青年らであった。それは実の姪に子を生ませた藤村の場合でも、他人の妻との 「不倫」 のすえに情死した有島武郎の場合でもそうである。もっとも、彼らのような悩みすら自覚せぬまま、たとえば聖人君子ぜんとした言動の下から、独善的な利己主義がすけて見えているような人がいれば、たしかに最悪だが。 ネット上でよく見かける、「お前が言うなー」 とか 「それはあんただろ」 などと思わず突っ込みたくなるような非難を他人にぶつけている人は、自分の影を相手に投影して、その影に向かって非難を浴びせているにすぎない。だから、その非難が他人から見れば、その人自身にもっとも合致した言葉として、そのまま本人に跳ね返っているのにまったく気づいていない。 おそらく、そのような人たちは、「自分はこうありたい」 とか 「あの人のようになりたい」 といったおのれの願望や理想を、そのまま自己の現実と取り違え、その結果、客観的な自己を見失い、無意識のうちに肥大したおのれの影を誰彼となく他人に投影して、人を非難しているのだろう。 カントは、人間の経験的認識は先験的概念である 「純粋悟性概念」 とやらに基づくと主張したが、いずれにしろ、人はみな、多かれ少なかれ自己に固有の認識の枠組みというものを無意識のうちに持っている。ありもしないところにまで 「陰謀」 の影を見る人は、その人自身がそのような枠組みで世の中を見ているからにすぎないし、他人の言葉にやたらと 「悪意」 や 「嘲笑」 を嗅ぎ取る人は、たいていの場合、おのれがそのような観念にとりつかれているからにすぎない。 なお、余談であるが、自意識過剰な 「独りよがり」 人間や、一知半解なことを知ったかした賢しら顔で言う人、あるいははったりや虚勢だけで中身のない者、物事を党派的にしか見れない者が、大きな顔で他人に大口叩いているのを見たりすると、正直言ってひじょうに 「むかつく」。その人がそういう特徴をいくつも備えていたりすると、最悪のうえに最悪である。 ネット上の論争などで、よせばいいのに余計なことに首を突っ込むのは、だいたいにおいてそういう場合である。意見や判断、解釈などについてならば、それぞれに違いがあるのは当たり前のこと。だから、あまりのトンデモぶりとかにあきれることはあっても、それほど 「むかつき」 はしない。人間、愚かなのはそもそもの仕様なのだから。 なので、それはなにも、敵だ、味方だ、というような話なのではない。ただ単純に、そういう勘違いをしている者とかを見ると、はなはだ 「むかつく」 ということなのであって、あくまで個人の好みと趣味の問題であるにすぎない。よけいな勘繰りなどはしないように。 うーん、なんだか今日もえらそう。 ひょっとすると、これは盛大なブーメランなのかもしれない(笑)関連記事: 物言えば 唇寒し 秋の空
2009.11.16
コメント(4)
-
フランクフルト学派の陰謀?
最近というわけではないが、なんでも世間には 「フランクフルト学派」 による陰謀なるものが存在しているらしい。これを暴露し、世に警鐘を鳴らしているのは、京大の中西輝政教授や、ニーチェやショーペンハウエルの訳者でもある西尾幹二氏、さらには高崎経済大の八木秀次教授など、なかなかに錚々たる学者であり研究者たちである。 これは、こんなところやこんなところで見ることができるが、これを簡単にまとめると、戦後の急速な核家族化の進行と、それによる 「家」 制度や伝統的価値観の崩壊、「行き過ぎた」 男女平等や同じく 「行き過ぎた」 性教育、ジェンダーフリー思想の蔓延や 「性道徳」 の崩壊、そして離婚の増加や少子化といった現象も、どうやら日本の社会と国家の破壊と革命をもくろんだ、恐るべき 「フランクフルト学派」 の陰謀なのらしい。 「フランクフルト学派」 とは、もとはむろんワイマール時代のドイツでフランクフルト大学に設立された社会科学研究所に集まった、アドルノとホルクハイマーを中心とした一群の研究者らのことを指す。研究所が設立されたのは1923年だが、穏健左派の初代所長にかわって、当時は 「戦闘的唯物論者」 だったホルクハイマーが二代目所長に就任したのが1930年のこと。 時代は短命に終わったワイマール共和国、シュトレーゼマンのもとで経済の安定や周辺諸国との関係正常化に成功し、国連加盟もはたした 「相対的安定期」 であった。その一方、ローザの流れをくむ急進左派の側には、いったんは共産党に参加したものの、ソビエトの内情やコミンテルンの気まぐれな指導に嫌気がさして、離党する者や、新たな党を作って分離する者らもいた。 フランクフルト学派が、マルクスの強い影響のもと、「批判的理論」 を掲げて既存の社会秩序にたいする根源的批判という立場に立ちながらも、ソビエトや国内の共産党とは一線を画した立場に一貫してこだわり続けたのには、そういう背景がある。その思想に影響を与えたのには、マルクス以外にもルカーチやフッサール、さらにはウェーバーに始まるドイツの社会学や哲学も無視できないだろう。むろん、フロイトの名前も欠かすことはできない。 一般には、この二人以外に 『一次元的人間』 を書いたマルクーゼや、『自由からの逃走』 などで知られるフロム、ナチズムを主題とする 『ビヒモス』 を書いたノイマン、さらにレーヴェンタール、ポロックなども入るようだが、別に会員制のクラブというわけではないから、人によって多少の解釈の違いがあるのはしかたがない。それに、ハーバーマス以降の世代になると、もはやアドルノらの威光も相当に薄れてきているようだし。 また、御大であるホルクハイマーとアドルノにしても、時代によってその思想は変わってきている。ジャズもハリウッドも大嫌いという 「古典的知識人」 だったアドルノと違い、マルクーゼとフロムは戦後もアメリカに留まったが、そこには 「古き良き伝統」 ともいうべきヨーロッパの中産階級文化と、アメリカの社会やその大衆文化に対する感覚の違いもあるだろう。また、ナチズムの興隆と没落という、20世紀のドイツとヨーロッパ全域を襲った最大の悲劇に対する責任の取り方の違いということもあるのかもしれない。 アメリカに留まったマルクーゼが、60年代のベトナム反戦運動にたいして、きわめて好意的だったのに対し、ドイツに帰ったアドルノらは、同時期のドイツ国内の急進的運動にたいし、むしろ嫌悪感を表明している。なので、この時代、「フランクフルト学派」 といえば、むしろマルクーゼが代表格のようであり、当時の急進主義者の間でのアドルノの評判はあまりよろしくない。 おそらく 「フランクフルト学派陰謀論」 者に対して、最も強い印象を与えているのは、「ラブ・アンド・ピース」 の神様であった、この時期のマルクーゼなのだろう。彼らとは関係のない、心理学者で性科学者であったライヒが、しばしばその仲間に間違っていれられているのはたぶんそのせいなのだろう。それに、まともな時期のライヒの著作には、彼らと重なるような部分もないわけではない。 ところで、日本の場合で有名な社会科学研究所といえば、今は法政大学に置かれている 「大原社会問題研究所」 ということになるだろうか。大原社研はもとは大阪にあり、倉敷紡績の二代目であった大原孫三郎という人によって創設されている。倉敷にある大原美術館を開館したのも彼であり、そのほかにも病院や学校を建てるなど、地元のために様々な貢献をしている。 こういう活動には、産業革命の進展とともに浮かび上がってきた、都市と農村における様々な 「社会問題」 という背景もあるだろうが、事業でえた富は私的蓄財とすべきではなく、社会に還元すべきだという明治の経済人の心意気もあったのではないだろうか。とくに彼の場合、若い頃はぼんぼんとして放蕩を重ね、その後、石井十次なる人物を知り(救世軍の山室軍平らとともに、地元では「岡山四聖人」と呼ばれているそうだ)、キリスト教の教えに触れたということもあるようだ。 当然のことながら、「資本家」 だって個人としてみるならば、ただの資本が目に見える形に顕現した 「人格」 にすぎないのではなく、具体的な特性を有した個人なのだから、その活動には個人の思想が反映されることになる。なお、前首相の麻生氏の出自である麻生一族も、地元では本業の鉱業以外にも、病院や学校など様々な社会事業の経営も行なっている。ただし、これが事業利益の社会への還元と言えるのかどうかまでは、分からない。 ここで、山口昌男の 『本の神話学』 に収められた 「ユダヤ人の知的熱情」 というエッセーの中から、オーストリア系ユダヤ人であり、伝記作家として知られているツヴァイクの 『昨日の世界』 にあるという一文を引用してみる。ユダヤ人にあっては富の追求が、家庭内部の二代、せいぜい三代で終わってしまい、まさに最も強大な代において、父祖の銀行、工場、できあがった居心地のよい商売を引き継ぐことを悦ばない弟たちを生むのである。ロスチャイルド卿が鳥類学者となり、ワールブルクが芸術史家、カッシーラーが哲学者、サスーンが詩人となったことは、偶然ではない。 上に書いた大原孫三郎もそうだが、これを読んでちょっと連想したのは、かつて三菱重工業の社長を務め、三菱自動車工業を設立するなど、三菱グループで 「天皇」 と呼ばれるほどの力を持っていたという牧田与一郎の息子である牧田吉明という人物。彼は70年代に爆弾闘争を展開した男だが、爆弾事件で起訴されていた人の裁判で真犯人として名乗り出たという経歴がある。いわゆる 「過激派有名人」 の一人であるが、最近ではむしろ右翼人とのつきあいのほうが多いらしい。 また、麻生一族には、平野謙や本多秋五らの 『近代文学』 に近い人で、大井広介という筆名で評論を書いていた人もいる。そうそう、西武グループの総帥だった堤義明の異母兄で、辻井喬の名前で詩や小説を書いてもいる、西武セゾングループの代表だった堤清二の存在も忘れてはいけない。 話を戻すが、戦後、ドイツに帰国したアドルノのもとに留学したことがある徳永恂(『啓蒙の弁証法』 の訳者でもある)は、ウェーバーやルカーチ、アドルノについて論じた 『社会哲学の復権』 の中で、問題の 「フランクフルト学派」 という名称について、1950年代末頃から使われるようになったと書いている。 ということは、「歴史哲学テーゼ」 などで知られるベンヤミンの場合、1940年にフランスからスペインへ脱出しようとして失敗し、ピレネー山中で死を選んだのだから、少なくとも本人には 「フランクフルト学派」 などという意識はなかったことになる。とはいえ、その死後に本人の意思とは関わりなく、そのように呼ばれることになったことについてどう思うかは、もはや確認のしようがない。 彼がドイツからアメリカにまるごと移転した研究所に協力したことは事実であるが、彼を 「フランクフルト学派」 に入れることは、彼をアドルノとホルクハイマーより格下とすることに等しいように思うのだが、どんなものだろうか。そうだとすると、アドルノを信用せず、ベンヤミンに対する彼らの扱いに怒っていたというアレントは、絶対に承知しないのではないだろうか。もっとも、これはまあ、絶対に認められないというような話ではないのだが。 この書では、この名称の始まりについて、「主としてドイツ社会学会を舞台につねに共同歩調をとって活動するアドルノの弟子たちの結束ぶりに辟易したダーレンドルフが、いささかの皮肉と、時代錯誤性への揶揄をこめて、「最後の学派」 と言ったのが事の起こりであり、それがやがてそういうニュアンスを拭い去って一般化していったように思われる」 と書かれている。 こういう最初の揶揄的な他称がやがて一般化し、当初の 「そういうニュアンス」 を失っていくという例は、日本で言えば 「丸山学派」 とか 「大塚史学」 などという場合でも、似たようなものだろう。だいたい、こういう呼び方は、論敵の側からつけられるほうが多いものであるから。 もうひとつ、つけくわえておくと、フランクフルト学派が陰謀論の主体としてたびたび言及されるのには、その創始者であるアドルノとホルクハイマーをはじめ、彼らにもっとも大きな影響を与えた人物や周辺の人物に、多くのユダヤ系の人がいることも無縁ではないだろう。したがって、そこには 「ユダヤ陰謀論」 との関連もあるように思われる。 なお、やはりユダヤ系ドイツ人であり、アメリカに亡命したハンナ・アレントは、ベンヤミンについて 『暗い時代の人々』 の中で、次のように書いている。それによっていちばん利益を受けるはずの人はすでに世を去っており、もはやそれは売り物ではない。こうした商業的ではなく、実利的ではない死後の名声が、今日ドイツではヴァルター・ベンヤミン自身の亡命に先行する10年たらずの間、このドイツ系ユダヤ人はそれほど有名ではなかったが、雑誌や新聞の文芸欄への寄稿者としては知られていた。その同胞と同世代人の多くにとり、戦争中で最も暗い時期とされていた1940年の初秋に彼が死を選んだとき、その名前を記憶していたものはごくわずかであった。ヴァルター・ベンヤミン 1892―1940 ところで、戦後のいわゆる 「進歩的文化人」 の代表ともいうべき丸山真男は、多くの官僚や政治家を輩出している東大法学部の教授を長年にわたって勤め、多くの官僚の卵たちの 「洗脳」 に尽力したわけだが、「丸山学派陰謀論」 というのはどこかにないのだろうか。 海の向こうに由来する荒唐無稽な 「フランクフルト学派陰謀論」 などよりは、官庁街に潜り込んだ丸山の弟子たちによる日本破壊の陰謀という 「丸山学派陰謀論」 のほうが、よっぽど信憑性もあり、世間にも受け入れられやすいように思うのだが。追記: 牧田吉明氏は楽天ブログを開いておられるようですね。 ちょっと驚きました。もっとも今は更新を停止しているようですが。 牧田吉明 こと 山猫666
2009.11.10
コメント(0)
-
レヴィ=ストロースまたは長寿の秘密
報道によると、フランスの人類学者レヴィ=ストロース大先生が10月30日に亡くなったそうだ。生まれたのが1908年の11月28日だそうだから、あと4週間頑張っていれば101歳というところだったのに、残念なことである。 彼については、以前にあんなことやこんなことを書いたが、いずれもただの雑文の域を出ない。それはそうだろう。こちらはただの手当たり次第の雑読家であって、人類学はもちろん、レヴィ=ストロースの構造人類学に大きな影響を与えた言語学についても、ちゃんとした勉強をしたことなどないのだから。 ところで、彼は1977年、もうすぐ69歳になろうかというときに日本に来て、何回か講演をしている。その中の一つ、京都で行われた、日本語で 「構造主義再考」 と題された講演では、こんなことを話している。 かりに、どこかの辞書のために、私たちが用いている意味での 「構造」 という語の定義を求められたとすれば、次のように言いたい。すなわち、「構造」 とは、要素と要素間の関係とからなる全体であって、この関係は、一連の変形過程を通じて普遍の特性を保持する。 この定義には、注目すべき三つの点というか、三つの側面があります。第一は、この定義が要素と要素間の関係とを同一平面に置いている点です。別の言い方をすると、ある観点からは形式と見えるものが、別の観点では内容として表れるし、内容と見えるものもやはり形式として表れうる。すべてはどのレベルに立つかによるわけでしょう。...... 第二は 「不変」 の概念で、これがすこぶる重要な概念なのです。というのも、わたしたちが探求しているのは、他のいっさいが変化するときに、なお変化せずにあるものだからです。 第三は 「変形(変換)」 の概念であり、これによって、「構造」 と呼ばれるものと 「体系」 と呼ばれるものの違いが理解できるように思います。というのは、体系もやはり、要素と要素間の関係とからなる全体と定義できるのですが、体系には変形が可能でない。体系に手が加わると、ばらばらになり崩壊してしまう。これに対し、構造の特性は、その均衡状態になんらかの変化が加わった場合に、変形されて別の体系になる、そのような体系であることなのです。レヴィ=ストロース日本講演集 『構造・神話・労働』 より 「構造」 という概念自体は、むろん古くからある。また、「全体」 は単なる個々の要素の集合ではなく、そのような要素には還元できないといった、「構造」 としての全体のほうをその個々の要素より重視する発想というのも古くからある。これは、アトミズムまたは還元主義とホーリズム(日本語だと全体論)の対立などと呼ばれる。 たとえば、20世紀初めにドイツで生まれたゲシュタルト心理学では、「ゲシュタルト」 の説明として、楽曲のメロディがよく引き合いに出される。メロディは個々の音の絶対的な高低ではなく、それぞれの音の高低の関係、つまりはその差異という相対的な高低によって構成されている。だから、ハ長調で歌おうとヘ長調で歌おうと、「やぎさんゆうびん」 はやっぱり 「やぎさんゆうびん」 である。 これは、平面や空間の内部をあちこち移動させても、図形の形は変わらないのと同じことだ。レヴィ先生は上記の講演で、座標平面に人間の横顔を書き込み、座標のパラメータをいろいろと変化させて、最初の横顔を様々に変形させていくという、16世紀の画家兼版画家であったデューラーの方法を例にあげて説明している。 そのような 「変形」 が可能であり、またそのような 「変形」 を通じても保持されていくのが、つまりレヴィ=ストロースのいう、たんなる 「体系」 とは異なった、特別な意味を持つ 「構造」 ということなのだろう。だから、それはしばしば批判されたような静態的なものではない(らしい)。 しかし、同時にそのことは、彼のいう構造主義なるものは、いかなる問題、いかなる分野にも適用でき、利用できるといったものではないということも意味する。それは、彼自身の言葉を借りれば、「哲学を自称するものでもなく、なんらかの主義を自称するもの」 でもない。 それは、「ひとつの認識論的態度」、「問題に注目し、接近し、これを取り扱うさいの、特定の仕方」 なのであり、それが有効であるためには、「研究する現象のタイプが、普遍的とはゆかずとも、少なくとも一般に認められる現象であって、そのほかの現象から比較的分離しやすく、そこから検出できるすべての例が均質の方法で処理できる、そのような現象でなければならない」 ということだそうだ。 たとえば、現代思想の解説書などでは、「実存主義から構造主義へ」 みたいなことがよく言われる。レヴィ=ストロースが、『野生の思考』 の最終章でサルトルを厳しく批判したのは1962年のことだが、彼自身はこの講演の中で、その前の 『構造人類学』 が刊行された1958年から、いわゆる 「五月革命」 が起きた1968年までの十年間を、本場フランスにおいて構造主義が流行した期間としている。 「五月革命」について、彼は「その時点で判然としたのは、フランスにおける青年知識層のひそかにとりつづけてきた姿勢が、20年も前、第二次大戦末期に生まれたサルトル流実存主義のそれと、ほとんどかわらぬままであったということであります」 と言っており、これが、彼によればフランスでの構造主義の短い流行の終焉なのだそうだ。 人間の自由を基調とするサルトルの哲学そのものについても、彼はおそらく批判的であったと思われるが、『野性の思考』 での批判が対象としていたのは、サルトルの 『弁証法的理性批判』 にひそかに隠されていた西欧中心主義であり、近代的な理性中心主義であって、その批判は自分の学問に関係する限りでのことと言うべきだ。 したがって、それはサルトルにかわる新たな哲学の提出などを意図したものなどではない。その意味では、「実存主義から構造主義へ」 というよくあるまとめ方は、いささか乱暴で的外れなものであり、レヴィさんにとってはむしろ心外なものであるのかもしれない。 サルトルの事実上の伴侶であったボーヴォワールはレヴィ=ストロースと同い年であり(亡くなったのはサルトルの死から6年後の1986年)、その主著である 『第二の性』 を書くに当たって、彼の最初の主著であった 『親族の基本構造』 を、出版前の原稿段階で読ませてもらったという。 朝鮮戦争を契機に決別していたとはいえ、かつては親友であり盟友でもあったメルロによる批判に続いて、今度はそのレヴィさんによって、サルトルが批判されたというのだから、ボーヴォワールの驚きははたしていかなるものであったのか。 うえに述べたように、彼はサルトルの実存主義に代わる全体的な哲学として、いわんや 「変革」 のための理論として構造主義を提唱したわけではない。だから、「五月革命」 という変革の季節に、いったんは死んだかと思われたサルトルが復活したとしても、おかしくはないということになる。 日本の場合、構造主義の流行はフランスより10年以上遅れてやってきたが、その後のサルトルの急激な凋落には、舶来の新思想をいつもありがたがってきたこの国の特殊性ももちろんだが、レヴィ=ストロースらによる批判を受けた 「思想的事件」 というより、むしろ当時の急進左翼の衰退に伴った 「政治的事件」 という側面のほうが強いのかもしれない。 レヴィ先生は、この講演でこうも言っている。 わたしたちにとって、構造主義とは、極端に慎ましい手仕事のようなものであって、おそらくや、今日的な関心とは無縁の問題を対象としています。そして、今日的な関心と無縁であればこそ、わたしたちが対象としている問題は、その他の諸問題、特定の階級なり環境なりの成員としての、歴史の特定時点に帰属する個人としての、わたしたちの関心と予断がかかわってこざるをえないような諸問題にくらべるとき、いささかなりとも、より厳密なやり方で研究されうるのであります。 なお、日本人で同様に長寿だった人ということで連想したのが荒畑寒村。寒村は1887年に生まれ、1981年に亡くなっている。享年94歳で、100歳まで生きたレヴィ=ストロースにはちょっと及ばない。彼の最初の著作は足尾銅山の鉱害と、県と政府による谷中村住民への弾圧について描いた 『谷中村滅亡史』 であり、これは天皇への直訴事件などで知られる田中正造から託されたものだという。 荒畑はそのような時代から、宇宙ロケットや核搭載も可能な長距離ミサイル、ジャンボジェットなどがびゅんびゅんと空を飛び回る時代まで行き続けたわけだ(核ミサイルはさすがにびゅんびゅんとまでは飛んでいないが)。 また、江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎は1760年に生まれ、1849年に死んでいる。享年89歳ということだが、彼の場合は、生まれたのは八代将軍吉宗が死去した9年後、亡くなったのがペリーが黒船に乗ってやってくる4年前、明治維新のほぼ20年前であり、そのときにはすでに長州の桂(のちの木戸孝允)は15歳、西郷などはなんと21歳に達していた。 ヨーロッパの歴史で100年といっても、今ひとつぴんと来ないのだが、こうやって自分の国の歴史に置き換えてみると、それがどれだけ長い期間であり、また一人の人間が100年を生きるということが、どれだけすごいことなのかがよく分かるだろう。参照: レヴィ=ストロース追悼 小田亮のブログ「とびとびの日記ときどき読書ノート」 こちらは専門的研究者による立派な記事です。
2009.11.05
コメント(1)
-
巨人ゴーレムと怒れる大魔神の関係
粘土でできた巨人ゴーレムといえば、アニメやファンタジー、ゲームなどに欠かせないキャラクターとして、いまなおあちらこちらで引っ張りだこのようだ。ざっと調べただけでも、「遊戯王」 や 「ドラゴンクエスト」、それに 「ゲゲゲの鬼太郎」 にも登場したという(もっとも、いずれもよくは知らない)。 このゴーレムについて、渋澤龍彦はつぎのように言っている。 ゴーレムは中世紀からユダヤ伝説にあらわれるようになった、呪文によって生命を吹き込まれた一種の土偶であり、フランケンシュタイン風の人造人間である。これもまた、中世魔術の生命造出に関する野望の反映であろう。 十六世紀初頭のタルムード学者ケルムのエリヤが、カバラの原典 『創造の書』 の助けを借りて、初めてこのゴーレムを作ったのも、プラーグの町のゲットーであったらしく、名高い律法教師のレーウェ・ユダ・ベン・ベザレルが、1580年、神の命により二人の助力を得てゴーレムを製作したのも、やはりプラーグのゲットーにおいてであったようだ。『夢の宇宙誌』 所収 「玩具について」 より ゴーレムの話が世界的に有名になったのは、1915年に出た、グスタフ・マイリングというオーストリアの作家による、その名も 『ゴーレム』 という小説と、これとは別に、第一次大戦をはさんでドイツで三度にわたり、パウル・ヴェゲナーという同じ監督で製作された映画 『ゴーレム』 シリーズがきっかけなのだそうだ。 額に書かれた 「真理」 という意味の "emeth" の最初の一文字を消して "meth" にすると、「われは死せり」 の意味となり、もとの土くれに戻るといった話もよく知られている(本来はどちらもヘブライ文字なのだが、ここでは表記できない)。 この映画はyoutubeにもアップされており、一部を見ることができる。映画はむろん白黒で、もとはサイレントなのだが、ゴーレムは監督自身が演じており、白黒のコントラストが、表現主義っぽい当時のいささかどぎつい演出や背景のセットにマッチしている。ゴーレムは泥人形だということで、たぶん顔にも衣装にも金粉のようなものを塗りつけているのだろう。動きもことさらのようにぎこちないが、巨人といいながら、じつは背丈は他の登場人物とそれほどかわりがないというのはご愛嬌。 マイリングの小説については、舞台であるプラハの住人であったカフカの言葉が、彼の年少の友人であったグスタフ・ヤノーホという人が第二次大戦後に出した、『カフカとの対話』 という題の回想録の中に残されている(カフカの没年は、オーストリア帝国が解体した第一次大戦後の1924年)。古いプラハのユダヤ人街の雰囲気が、見事に捉えられています。......私たちの内部には、相変わらず暗い場末が生きています。いわくありげな通路が、盲いた窓が、不潔な中庭が、騒々しい居酒屋が、陰にこもった旅亭が。私たちは新しく建設された広い市街を歩きます。しかし私たちの歩み、私たちのまなざしは定まらない。内部で、私たちは、やはり古い悲惨な小路を歩くときのようにふるえています。私たちの心臓は、衛生施設の普及についてまだなにも知らないのです。私たちの内部の不健康な旧ユダヤ街は、私たちの周囲の衛生的な新市街にくらべてはるかに現実的です。目覚めつつ私たちは夢の中を歩む。その私たち自身、過ぎ去った時代の亡霊にすぎないのです。 『創世記』 によれば、神は人間をおのれの姿に似せてつくったという。プロメテウスもまた同様である。だから、このような生命創造とは、自己の分身を作ることでもある。つまり、ここにおいて、生命創造の物語は 「ドッペルゲンガー」 の物語でもあるということになる。 事実、マイリングの小説は、外出から帰ってきた主人公のあとをつけるようにして、彼の部屋に音もなくはいってき、いつのまにか煙のように消えてしまったという謎めいた男が、じつは自分自身であったということに、主人公アタナージウス・ペルナートが気づくというところから始まっている。 いまぼくは見知らぬ訪問者がどんな格好をしていたか知っていた。それを感じようと思いさえすれば ―― いつなんどきでも ―― ぼくのからだで感ずることができただろう。しかし彼の格好を思い描くこと、つまりぼくの目のまえに面と向かってそれを見ること ―― それはあいかわらずできなかった。それはいつまでたってもできないだろう。 かれはいわば陰画として、目に見えぬ凹版としてあるのだった。その輪郭をぼくはつかむことができないし ―― その格好や表情を心の中に描こうとすると、ぼく自身がその凹版の内側に滑り込んでしまうのだ。 自己の分身を見たものは、死が近いと言われる。それは、ドッペルゲンガーという幻視が、精神の変調による自我統合の崩壊の兆しだとすれば、そう不思議なことではあるまい。芥川が死ぬ数ヶ月前に書いた 「歯車」 にもそれらしき記述があるが、近づいている死が芥川のように自殺によるか、あるいは精神の変調に続く肉体の衰弱による緩慢な死であるかは、あまり関係ない。 ポーの 『ウィリアム・ウィルソン』 の場合、主人公の分身たる同姓同名で同じ誕生日、むろん顔も同じという男は、主人公が虚栄や虚飾、放蕩といった悪行三昧にふけっているところに必ずといっていいほどあらわれて、警告を与え、友人らの前でその仮面をはがし、卑劣な男としての正体を暴き出す。つまり、この分身は彼の封印されていた 「良心」 であり、そのうずきであり、手遅れとなった 「悔恨」 の表れということになる。 つまるところ、このようなドッペルゲンガーとは、自己を見ている自己、または自己によって見られている自己のことであり、フロイトふうに言えば 「超自我」、三浦つとむふうにいえば、観念的に二重化された自己の一方が 「実体」 として外部に投影されたものということになるだろう。芥川は 『歯車』 のなかで、「僕はこの本屋の店を後ろに人ごみの中を歩いて行った。いつか曲り出した僕の背中に絶えず僕をつけ狙っている復讐の神を感じながら。……」 と書いている。 ところで、日本で人造人間をつくった話としては、鎌倉時代にかの西行に仮託して作られた 「選集抄」 の巻五第一五話に、友人と別れてさみしくなった西行自身が、野に散らばる骨を拾い集め、「反魂」 の秘術なる呪法によって、人を作ったという話がある。しかし、このときの西行の術は未熟であったため、蘇った 「人」 は姿こそ人であったものの、魂を持っておらず、言葉を話さずただ笛のような声をあげるだけだったという。ちなみに、ゴーレムもまた人語を解することはできても、自ら話すことはできない。 もっとよく似た話はないかと考えているうちに、そうだ、大魔神だ、あれは明らかにゴーレムのパクリであると、頭の中で電球が光ったのだが、Wikipediaで調べてみると、すでにそのことは触れられていた。その記述によれば、大魔神シリーズは、『大魔神』、『大魔神怒る』、『大魔神逆襲』 の三作だけで、いずれも1966年の製作だという。脚本は吉田哲郎という人が書いているそうだが、詳しいことは知らない。 小さな子供とかをのぞけば、知らない者はいまや日本中探してもほとんどいまい、というぐらいに有名なこの特撮時代劇映画が、40年以上も前のわずか一年の間に、たった三作作られただけであったというのは、いささか意外であった。しかし、よく考えれば、たしかに映画そのものを見た覚えはあまりない。 ところで、一作目の大魔神は丹波山中の岩壁に掘られた立像、二作目ではどこだかよく分からないが、湖の真中にある島に祀られた像、そして三作目では、飛騨山中にある 「地獄谷」 とかいうところに近い山の頂にある坐像という設定になっている。 つまり、この三作に登場する大魔神はすべて別々であり、大魔神様は日本各地にたくさんいらっしゃるということになる(横浜にもいたっけ?)。ちなみに、モデルとなった武人像の埴輪は、群馬県太田市の出土である。なお、来年から、角川事務所によって 「大魔神カノン」 なるものが、テレビで放送される予定となっており、現在撮影も進んでいるらしい。 関連記事: 怪奇 「砂男」 の恐怖
2009.11.01
コメント(2)
-
独学者とトンデモ説の親和性、または権威主義的性格について
以前、サルトルの 『嘔吐』 に出てくる 「独学者」 なる人物にふれて、「サルトルの 『嘔吐』 をちらちらと読み返してみた」 なる雑文を書いたことがある。そこで引用した 『嘔吐』 の箇所をもう一度ひいてみる。なお、引用文中の 「彼」 とは、この 「独学者」 を指している。彼は目で私に問いかける。私はうなづいて賛意を評するのだが、彼がいくらか失望したということ、彼が欲したのは、もっと熱狂的な賛同だったということを感じる。私に何ができようか。彼が私に言ったことのすべての中に、人からの借り物や引用をふと認めたとしても、それは私が悪いのだろうか。言葉を質問形にするのは癖なのである。じっさいには断定を下しているのだ。優しさと臆病の漆は剥げ落ちた。彼がいつもの独学者であるとは思われない。彼の顔つきは、鈍重な執拗性をあらわしている。それは自惚れの壁である。 ウェブにはこの種の人は珍しくない。なにしろ、ちょっとした手間と暇さえかければ、誰でも簡単にネット上にホームページやブログを作成して、そこになにやら 「独創的」 な研究成果を発表するぐらいのことはできるからだ。正直に言うと、昔、傾倒していた人を扱ったこの手の 「論文」 を見かけ、いささか感じたことがあったため、しばらくメールでやりとりしたこともある。 最初から、表面上はていねいな言葉の中に、なにか傲慢さを感じさせる 「慇懃無礼」 な雰囲気があって、???という気もした。なので、そこでやめとけばよかったのだが、ついつい疑問点をいくつか並べて書き送ったところ、いきなり 「あなたはまだまだ勉強が足りないようですね」 といった類の傲岸不遜な返事が返ってきた。どうやら、その人の自尊心をいたく傷つけてしまったようであった。 別に、「独学者」 一般を誹謗するつもりはないし、勉学や研究の環境が整わない中で 「独学」 を続けるということは、むろん賞賛さるべきことではある。しかし、サルトルも指摘しているように、「独学者」 にはしばしば 「夜郎自大」 という痼疾がついてまわる。いったい、それはなぜなのか。 以前の記事では、「それは 「独学」 という行為が必然的に孤独な作業であることから来るものだろう」 と書いたが、どうもそれだけではなさそうだ。じっさい、すべての 「独学者」 がそのように夜郎自大というわけではない。むしろ、それは個々の 「独学者」 が 「独学」 を続けているモチーフ、それもおそらくはその人自身も気づいていない、もっと奥の秘められたところ、一言でいえば 「自尊心」 の満足ということにあるような気がする。 「自尊心」 というものは、たしかにだれもが有するものであり、その満足は人間の本源的な欲求のひとつでもある。そして、「独学者」 にとって、もっともその 「自尊心」 を満足させることはなにかといえば、おそらく 「独創的」 であることだろう。たしかに、「独創的」 であることは 「独創的」 でないことよりも評価される。だが、いうまでもなく、「独創的」 な研究などというものは、そう簡単に生まれるものではない。 極端な例を出せば、1+1の答は誰が計算しても2である(2進法の場合は除く)。少々難しい方程式だって、それを理解できる人が正しい解法を用いて、間違いを犯さずに計算すればみな答は同じになる。たしかに、ややこしい問題とかであれば、その過程で多少の独創性が発揮される場面もないわけではあるまいが、答は一緒なのだから、その意味では「独創性」 が発揮される場面などはない。 だから、一般的に言うなら、「独創性」 が必要とされ、また 「独創性」 が発揮されるのは、「未知の領域」 ということになる。だが、「未知の領域」、すなわちいまだ解決されざる問題を見つけるには、その分野において、現時点でどこまでが既知であり、問題がどこまで解決されているかをまず知らなければならない。 「独創性」 を発揮すべき 「未知の領域」 とは、いわば雲の上に突き出ている富士山の頂上のようなものだ。だが、そこまでたどりつくには、えっちらおっちらと麓から自分の足で登っていかなければならない。ヘリコプターでいきなり頂上に降り立ったところで、それは富士を征服したことにはならない。だから、それはそう簡単なことではない。 「独学者」 の多くが、ときにはトンデモ学説ですらあるような、世間の 「常識」 から離れた説に引き付けられがちなのは、おそらくそのためだろう。それは、本当の 「独創性」 を発揮するための前提として必要な、自分が 「知らない」 ということを知るための努力を不要にしてくれるだけでなく、自分が世間の常識を超越しており、したがって世間の人々より上にいるかのごとき勘違いによって、自尊心の満足にも役立つという非常に便利なツールでもある。 たとえば、「常識を疑え」 という人たちは、コペルニクスはプトレマイオスの天動説を疑った、ガリレオはアリストテレスの運動論を疑った、ラボアジェはフロジストン説をひっくり返した、ウェゲナーは大地は動かないという常識に挑戦した、などという例を持ち出す。たしかに、それまでの常識をひっくり返したこの種の 「大発見」 は、科学の歴史にはことかかない。科学の進歩とはそういうことだ。 しかし、彼らにそれが可能だったのは、それまでの 「常識」 では説明できぬ未知の問題にぶつかったからであり、あるいは 「常識」 であり、解決済みであるとされていたことに、じつは未解決の問題が潜んでいるのに気づいたからだろう。どちらにしても、それにはそれまでの 「常識」 について、ふかく理解することがまずは前提になる。そこで必要なのは、「常識」 なるものを無批判に受け入れることでもなければ、頭ごなしに否認し、ただ投げ捨てることでもない。 さて、興味深いのは、このように 「世の常識」 や 「学界の常識」 とかに挑戦している人らの多くが、じつは彼らなりの固有の 「神」 を持っているという事実である。それはたとえば、政治・社会関係であれば副島隆彦や宮台真司であったりするのだが、同じような 「神」 は、医療や看護関係にも、物理学や宇宙論といった分野にも、また史学や思想・哲学といった分野にもいるだろう。最近では、こういった神様もじつに多様である。 むろん、それらはピンからキリまであり、十把一絡げに扱うわけにはいかない。「神様」 扱いされてるからには、それなりの力量や資格、実績を備えている人もむろんいるだろうし、馬鹿な弟子がいるからといって、それがすべて師匠の責任というわけでもない。どんなに偉いお師匠さんにも、師の教えを理解できずに誤解したり、ただの無意味な呪文にしてしまったりする不肖の弟子というのはいるものだ。それは、かの親鸞さんについてすら言える。 ただ、このことからは、そのような人の多くが、じつはフロムの言う 「権威主義的性格」 を備えているのではという印象を強く受ける。一般に 「権威主義的性格」 は、権威への服従を好むマゾヒスティックな性格と、権威を振りかざすことを好むサディスティックな性格の統合というように理解されている。これがただの小物であれば、自己の服属する権威のもとで、その権威を振りかざしたがる、いわゆる 「虎の威を借るキツネ」 ということになる。しかし、その一方で、フロムは次のようなことも指摘している。 権威主義的性格には、多くの観察者を誤らせるようなもう一つの特徴がある。権威に挑戦し、「上から」 のどのような権威にも反感をもつ傾向である。時にはこの挑戦がすみずみまでいきわたり、服従的傾向は背景に退くこともある。このタイプの人間はつねにどのような権威にも ―― じっさいにはかれの利益を助長し、抑圧の要素をもたない権威にも反逆する。ときには権威に対する態度が分裂する。すなわちある権威に ―― とくにその無力に失望した権威には抵抗するが、やがてより大きな力と約束によって、マゾヒズム的な憧憬をみたしてくれるように思われる、他の権威には服従する。...... かれらは内的な強さと統一性によって、自由と独立を妨げる力と戦う人間であるかのように見える。しかし権威主義的性格の権威に対する戦いは、本質的に一種のいどみに過ぎない。それは権威と戦うことによって、かれ自身を肯定し、かれ自身の無力感を克服しようとしている。そして他面では意識的であれ、無意識的であれ、服従へのあこがれが残っているのである。権威主義的性格は 「革命的」 ではない。私は彼を 「反逆者」 とよびたい。『自由からの逃走』 このフロムの著書はナチズムの分析を主題にしたものだが、この指摘は、たとえば反権力や反権威、超俗性などをかかげた組織や集団の中に、しばしば、彼らが挑戦しているはずの権威とそっくりの 「対抗的権威」 が形成されるのはなぜかも説明してくれる。
2009.10.25
コメント(1)
-
風と桶屋の関係、またはバタフライ効果
気象学にバタフライ効果という言葉がある。Wikipediaによると、これはエドワード・ローレンツという人が1972年にアメリカ科学振興協会でおこなった講演のタイトル、『予測可能性-ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こすか』 に由来するということだ。 これはむろん一種の比喩であり思考実験なのであって、どこかでの蝶のはばたきが、実際につねにどこかに竜巻を引き起こすというわけではあるまい。だいいち、そんなことがあちこちでしょっちゅう起きていては、たまったものではない。 難しい数学はちんぷんかんぷんだが、ようするにカオス理論なるものによれば、「カオスな系では、初期条件のわずかな差が時間とともに拡大して、結果に大きな違いをもたらす。そしてそれは予測不可能」 ということらしい。いや、そういうふうに言われても、やっぱりよく分からない。 昔の人は、「風が吹けば桶屋が儲かる」 と、なかなか洒落たことを言った。これは、「大風で土ぼこりが立つ → 土ぼこりが目に入って盲人が増える → 盲人は三味線を買う → 三味線に使う猫皮が必要になりネコが殺される → ネコが減ればネズミが増える → ネズミは桶を囓る → 桶の需要が増え桶屋が儲かる」 ということらしい(ネコさん、ごめんなさい)。 世界は様々な事象で満ちている。無から有はけっして生じないのだから、いかなる事象も、必ずどこかに原因を有する。上の命題は 「風が吹く」 で始まっているが、その風だって、吹いたのには、誰かが大きな口をあけてふーと吹いたか、吸い込んだか、あるいは台風の接近だとか、なんらかの原因によって気圧の差が生じたことによる。 そういう因果の連鎖をたどっていけば、それこそ宇宙がドカンと誕生したというビッグバンにまで遡るだろう。それに、風が吹いた結果のほうも、「桶屋が儲かる」 で終わるわけではない。たとえば、「桶屋が儲かると、近在にその噂が広まる → 噂を聞いて盗人が押し込みにくる」 などというように、その結果はさらに未来に向かって続いていくだろう。 いや、それだけではない。あるひとつの事象を決定する原因はたったひとつではない。ボールが窓に当たったとしても、それで実際に窓が割れるかどうかは、ガラスの厚さや強度、当たったボールの硬さや速度にも左右される。 それに、ひとつの事象から、枝分かれするようにいろいろな結果が同時に生まれることもあるだろう。世界の中では、いまここで風が吹いているだけでなく、その横ではカラスがカーと鳴き、ネコがニャーと鳴いているかもしれない。田中さんの家では夫婦喧嘩の真っ最中だが、公園では若いカップルがいちゃいちゃしているかもしれない。 世界の中では、つねに複数の事象がたがいに関連しながら、あるいは独立しながら、同時多発的に発生している。そして、そのような事象は、場合によってはたがいに影響を及ぼしながら、時系列にそって発生し、変化し、あるいは消滅する。これはまさに混沌とした世界である。 たとえば、17世紀にオランダにいた哲学者のスピノザはこんなことを言っている。定理28 あらゆる個物、あるいは有限でかぎられた存在を持つあらゆるものは、自分と同じように有限でかぎられた存在を持つ他の原因から、存在や作用へと決定されることによって、はじめて存在することができるし、また作用へと決定されることができる。さらにこの原因も同じように有限でかぎられた存在を持つ他の原因から、存在や作用へと決定されることなしには、存在することもできないし、また作用へと決定されることもできない。このようにして無限に進む。『エティカ』 第一部 「神について」 より だが、このようにすべての事象が因果関係の連鎖でつながっているとしても、そのことはただちに、すべての事象が必然性によってつながれた必然的に発生したものであるということは意味しない。長い因果の連鎖をへて、いまここで発生した事象のすべてが、いかなる偶然性も含まない完全な必然性によって生じたというには、すべての因果の連鎖が、最初のドカンという宇宙誕生(スピノザなら 「神」 というだろうが)の時点において、すでに決定されていたと言わなければならない。 そのような長大で、しかも相互に絡み合っている複雑な連鎖の計算は、どんなに巨大な計算機をもってしても不可能だという技術的理由はともかくとして、すべての事象の連鎖が世界が誕生した時点で決定されていたと考えるのは、どう考えても無理だろう。結果から原因を探ることは可能だとしても、因果によって生じる結果なるものは、つねに一義的とは限らない。そこにはつねにいくらかの幅や揺らぎが存在する。もっとも、全能の神様ならば、そのすべてを予見していたかもしれないが。 それに、いったん成立した個々の事象や存在は、ただ外的要因によって左右されるだけでなく、程度の差はあれ、自律的な自らの 「本性」 も持っている。煌々とともる電灯に集まってくる蛾や蚊のみなさんには、光の誘惑に抵抗するだけの自由はないのかもしれないが、彼らとて、たんなる刺激に対する反応によってのみ生きているわけではないだろう。 話はがらっと変わるが、のちにスターリンによって 「右翼的偏向」 と批判され、最後には 「裏切者」 の汚名を着せられて処刑されたブハーリンは、『過渡期経済論』 の中でこんなことを書いている。恐慌は拡大し、波のごとく伝わるが、これは、体制内の一部分における均衡破壊が、ちょうど電信線によって伝わるみたいに、その各部分へと不可避的に拡がるからである。世界経済の諸条件のもとでの戦争が ― 一か所における均衡破壊を意味したものが ― 不可避的に、体制全体の大動揺に、世界戦争に転化した。 これが書かれたのは、ニューヨークはウォール街での株暴落を原因とする世界恐慌が勃発した9年前のこと。彼がのちのような 「右派」 ではなく、レーニンの主張する屈辱的な対ドイツ講和に反対していた 「左派」 だった頃の著作である。なので、その主張には極左的な単純化傾向がいささか強い。 世界経済のネットワーク化とは、つまり世界中の地域経済の相互依存が極大に達することだ。その結果、ブハーリンが指摘した、ネットワークを通じた危機の伝播と増幅という傾向もたしかに生じはするが、それと同時に、リスクの拡散と危機の局所的爆発の回避というそれとは反対の傾向も存在する。ある時点においてどちらの傾向が強いかは、一概には言えない。 しかし、たとえば、いまここで1000円を支出してなにかを購入した場合、その1000円はどこへどのように流通し、どのように分割され、最終的にどこにどのような影響を与えるか、それは市場の専門家などでない限り、ほとんど誰にも分からない。 むろん、たとえその結果がわからぬとしても、たった一人によるたった一回きりの行為であるなら、たいした影響はないかもしれない。しかし、それと同じ行為を1000人、10000人、いや10万人の人が毎日繰り返したなら、いったいどこにどのような結果が生じるのか。 その結果、たしかに誰かは儲かるだろうが、その反対に、どこかの店が倒産し、誰かが職を失うといったことが絶対に生じないとは、たぶん誰にも断言できぬだろう。これもまた、冒頭で引用したバタフライ効果のようなものである。われわれは、まことに混沌とした世界に生きている。 それはまるで、次の一歩を右脚から踏み出すか、左脚から踏み出すかに、世界の存亡がかかっているといった妄想に突然とりつかれた結果、その場に立ち尽くし、ついに一歩も動けなくなったという狂人が住んでいる世界のようなものである。 だが、それでも人は生きていかなければならないとしたら、そのようにただ立ち尽くしているというわけにはいかない。結果がどうなるか分からないからといって、次の一歩を右脚から踏み出すのか、それとも左脚から踏み出すのかの決断を、永遠に回避し続けるわけにはいかない。できることは、せいぜい可能な限り、自己の行為が及ぼす結果について事前に考え、予測しておくといったことにすぎないだろうが。 ところで、スピノザというと、「空中に投げられた石にもし意識があれば、自分の自由意志で飛んでいると思うだろう」 と言ったとかいう話があり、これは人間の意志の自由を否定したものと解釈されている(中公版の 『エティカ』 にはたしかに石を使った比喩はあるのだが、この言葉は見つからなかった。はて?)。 しかし、彼は人間の自由というものをすべて否定したわけではない。実際、『エティカ』 には、「自由な人間はなによりも死について考えることがない。そして彼の知恵は、死についての省察ではなく、生きることについての省察である」 というような定理もある。 彼は、その第三部 「感情の起源と本性について」 の定理2の長い注解の中で、「人々が自由であると確信している根拠は、彼らは自分たちの行為を意識しているがその行為を決定する原因については無知であるという、ただそれだけのことにある」 と述べている。 それはつまり、人はなんらかの行為を行ったとき、あるいは行わないとき、それを決定した自分の意志をただ無根拠に 「自由」 と称するのではなく、それがいかなる原因によって生じたものか、いかなる根拠によって制約されたものか、それをまずは省みよ、ということだろう。彼の言う人間の自由とは、おそらくその先に見えてくるものなのだ。 「限界」 を超えるための前提は、まずその 「限界」 がどこにあるかを知ることだ。同様に、自分が抱えている 「偏見」 や 「偏向」 から自由になるために必要なのは、そのような 「偏見」 や 「偏向」 をまず自覚することだ。それは、無意識の抑圧の意識化による解消という、フロイト先生が提唱した 「精神分析」 でもたぶん同じことだろう。追記:バタフライ効果をネタにした一日違いの記事を発見 暴力も責任も地続きなので線引きしましょう
2009.10.21
コメント(0)
-
あれやこれやの雑感
鳩山内閣が誕生してはや一ヶ月である。長かった自公政権の後始末がたいへん、というのは分かるのだが、予算やら事業の見直しやらと、まだまだ前途は多難のようだ。鳩山由紀夫という人については、いまひとつよく分からないのだが、なんとなくやはり昔の細川護煕氏と同じ、育ちのよさからくる軽さが感じられる。いや、人の良さからくる能天気さのほうは、むしろ細川氏以上なのかもしれない。 たしかに、内閣のメンバーを見れば、前の内閣などにくらべて、なかなかの論客と実力者ぞろいのようだ。だが、そのことがかえって内閣のアキレス腱になるおそれというのもなくはない。つまり、はたして今の鳩山氏に、論客であり野心もあるであろう人がおおぜいそろっている内閣をまとめるだけの力があるのだろうかという疑問だ。国民新党の静香ちゃんなどは、どう見ても首相より大きな顔をしている(物理的な意味だけじゃなく)。 どこに書いてあったかは忘れたが、かつてE.H.カーは、レーニン率いるボルシェビキ政権について、「ヨーロッパで最も知的水準が高い政府」 と評したことがある。当時のボリシェビキ政府には、レーニンとトロツキーをはじめとして、多士済々の人材がそろっていた。その多くが長い外国生活の経験があり(むろん、昨今のようなのんきな留学などではなく亡命を強いられたことによる)、何ヶ国語も自由にあやつることができる国際人であり、また科学から文学や歴史まで高い教養も有していた。 そういう一言居士のようなうるさ型の船頭ばかりの政権が一つにまとめられたのは、内外からの脅威は別にすれば、むろん卓越した指導者としてのレーニンの権威によるものだが、そのレーニンですら、ドイツとの屈辱的な講和をめぐっては反対派の執拗な抵抗に悩まされ、「そんなこと言うなら、おれは辞めるぞー」 といって、党を脅さなければならないことがあったくらいだ(なんだか、小沢さんみたい)。 それは維新直後の明治政府でも同じで、薩長のほかに土佐・肥前、旧公卿などからなる政府が、かつての主君であった島津久光のような頭の固いお殿様や、随所に残る頑迷な攘夷派などの抵抗を押し切って、その後の発展の基礎をすえた改革を進められたのには、なんといっても、維新後いったん帰郷しながらも、大久保らの説得を受けて政府に戻った西郷の存在が大きいだろう。 さて、「男だったら流れ弾のひとつやふたつ 胸にいつでもささってる」 というのは、31歳で自殺した沖雅也が主演していたTVドラマの主題歌、「男たちのメロディ」 の一節であり、「男は誰もみな 無口な兵士」 とは、オーディションで合格したばかりの薬師丸ひろ子が14歳でデビューした映画、「野性の証明」 の主題歌 「戦士の休息」 の台詞である。また、沢田研二はヒット曲 「サムライ」 の中で、「男は誰でも不幸なサムライ」 と歌っている。 とはいえ、それは別に男だけにいえる話ではない。なので、そこで 「男は~」、「男は~」と連呼されると、いささか鼻白むむきもいるかもしれない。たしかに 「男のロマン」 がどうしたとか、「どうせ女には~」 などとやたらと言いたがる人というのは、たいていはただの 「自己陶酔」 型の人間か、「自己慰謝」 の好きな甘ったれた人間である。それに、そもそもそういうことは、上の歌にもあるとおり、それまでよほど運が良く、また恵まれていた人でない限り、誰にでもあてはまることである。 つまるところ、あえて口に出そうが出すまいが、何十年も生きていれば、たいていの人は脛とか背中とかに、触れるとまだ痛むような 「傷」 のひとつやふたつは負っているということだ。そして、そういう 「傷」 は良い悪いに関係なく、重ければ重いほど、その人にとっての不可欠な一部となる。それは、その人にとって肉体の一部であり、積み重ねられてきた経験の一部であり、長い間に堆積された時間の証でもある。 ただし、えてしてそういう 「傷」 は、気づかないうちに社会や他者に対する認識、そしてむろん自己についての認識にも、なんらかの 「偏向」 をもたらすことが多い。それは普段はそれほどでなくとも、そのような 「傷」 にどこかで触れるような問題にぶつかった場合に、突如として発動されたりもする。 たしかに、人間の認識に必要な意識とは、それ自体主観的な作用であり、ただの鏡やカメラの中のフィルム(古い!)ではないのだから、それもある程度はしかたない。だが、ただの借り物の言葉を振り回すような人はともかく、たとえばけっして愚かとは思えないような人とかが、自分の言葉がブーメランとなって、そのまま話者自身にはねかえっているのに気づかないのには、たぶんそういう理由があるからなのだろう。 しかし、誰を相手にしているのか知らないが、「あなたたちとは違うんです!」 みたいな 「優越感」 ゲームをネット上でやっている人とかを見ると、「おいおい」 などと思ってしまう。どんな分野であれ、専門的な知識や経験とかは 「素人」 の皆さんに分け与えるものであって(むろん、すべて無償でとまでは言わないが)、「素人」 に対してふんぞり返る 「自己正当化」 のために持ち出すものではない。 で、そういう「対立」 みたいなものをさらにややこしくしているのが、「敵の敵は味方だ!」 とか 「敵の味方は敵だ!」 というような単純かつ粗雑な論理で、勝手に 「敵」 認定や 「味方」 認定をしている人。 勝手な 「敵」 認定が迷惑なのはもちろんだが、勘違いした勝手な 「味方」 認定というのも、たぶんそれにおとらず迷惑なものである。どこをどう読んだら、その人が自分の 「味方」 だと認定できるのか、はたで見ているとさっぱり分からない場合もあるのだが、そういう人は、そもそも根本的に理解力や読解力に難があるのだろう。 なにを勘違いしたのか、自分が 「敵」 認定している人とほとんどかわらぬことを、ただし反対側からとか、ちょっとばかし異なる発想やレトリックを使って言っているにすぎないような人を、勝手に 「味方」 認定している人もいれば、どう考えても、あなたが考えているほど単純な人ではないよという人を、自分の 「味方」 だと思っているような人もいる。 たぶん、そういう人は、勝手に 「味方」 認定して、すりすりと擦り寄った相手が、実は画面の向こうでしんそこ困った顔やうんざりした顔をしていたり、ときには腹の中で 「お前が言うなー」 とか 「それはお前のことだよ」 などと思っているかもしれないなんてことは考えもしないのだろう。もっとも、「敵の敵は味方だ!」 なんて粗雑な発想をする人は、そもそも頭の中が最初から粗雑なのだろうからこれまたしかたあるまいが。 最後はまったくの余談だが、安保だの沖縄だのといった問題を全面展開したあげく、「君はどうするんだ? 許すのか、許さないのか」 みたいな論法でせまるのは、たしかに昔からよくあったオルグ作法のひとつである。このような論法が、ときとして 「詐術」 めいて聞こえるのは、たぶんある特定の問題へのコミット、つまり、そのような問題に対する責任の引き受けということが、いつの間にか○○同盟だの○○派だのといった、特定の政治的立場へのコミットということにすり替えられているからだろう。 そういうすり替えというのも、多くの場合、オルグしている本人自身が気づいていない。つまり、そういう論法を使う人自身が、頭の中で上にあげた二つの問題の違いに気づかず、無意識に等置しているということだ。しかし、この二つを等置し混同することは、その意図がどうであれ、結局は自派の勢力拡大のために個別の問題を利用するという 「政治的利用主義」 の現れにすぎない。 かりに、ある人がそのような責任を認めたとしても、それをどのような形で引き受けるかは、それぞれが自己の責任で判断すべきことである。ある問題について、自己の責任の存在を認めるか否かということと、その責任を個人がどのような形で引き受けるか、ということとはいちおう別の問題なのである。私はだれか? めずらしく諺にたよるとしたら、これは結局、私がだれと 「つきあっているか」 を知りさえすればいいということになるはずではないか?アンドレ・ブルトン 『ナジャ』 の冒頭より
2009.10.16
コメント(2)
-
「認知的不協和」またはイソップのキツネ
「認知的不協和」(cognitive dissonance)とは、人が自身の中で互いに矛盾する認知を同時に抱えた状態だとか、そのときに覚える不快感を表す社会心理学の用語で、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガー(1919-1989)という人が提唱したのだそうだ。 この人によれば、「認知的不協和」 が存在すると、その不協和を軽減し除去するための心理的圧力が生じ、その結果、どちらかといえば不都合な一方の要素が無意識のうちに修正されて、「不協和」 な状態が軽減されたり除去されるということだ。 この理論の説明でよく言及されるのが、イソップ寓話にある 「キツネとブドウ」 の物語である。これは誰でも知っているだろうが、ある日、美味しそうなブドウがなっているのを見つけたキツネが、一生懸命とびあがって獲ろうとしたものの、どうしても届かない、それで最後に 「どうせあのブドウは酸っぱいんだ」 といって諦めたという話である。 キツネとしては、一方に 「渇いたのどを潤したい」 という欲求があり、他方に 「美味しそうなブドウ」 が樹になっているぞ、という認知がある。ところが、どうしても届かないため、「美味しそうなブドウ」 という認知を 「すっぱいブドウ」 という認知に変えることで、ブドウに対する欲求を断念したというわけだ。 この場合、キツネとしてはどうしても手に入らないブドウのことでいつまでもうじうじしているよりも、さっさと諦めて、別のものを探したほうが現実的であり生産的でもある。なので、「それは現実逃避だ!」、「事実から目をそらした自己正当化だ!」 などといってことさらに非難する必要はあるまい。 そもそも人間、なんでもかんでも可能なわけではないのだから、理屈がどうであれ、そのような心理的機制によって、かなえられない欲望がおさまり、心理的な安定が得られるのであれば、それはそれでよい。これに限らないが、人間の心というものはなかなかよくできている。 しかし、問題は 「認知的不協和」 の対象がブドウのような物ではなく、「他者」 という人である場合。その場合、これはしばしば過大な 「自己評価」 の幻想による維持を意味し、その結果、「他者」 とのコミュニケーション不全をもたらすおそれも出てくる。 人間にとっては、たしかに自己の精神的安定が第一なのだから、競争や争いに負けたときに、「本気じゃなかったんだよ」 とか 「おれだってやればできるんだよ」 などといって自分を慰めるのはしかたあるまい。ただ、そういうことはあくまで内心にとどめておくべきで、公言してしまっては恥ずかしい。 吉本新喜劇の池乃めだかの 「今日はこれぐらいにしといたるわ」 というギャグが受けるのは、それがただの 「負け惜しみ」 であることが誰の目にも明白だからだが、よく考えると、たいていの人はそれと大差ないことをどこかでやっている。 自分が人から批判されるのは、彼らがわたしを妬んでいるからだ、という理屈で自分を納得させるのもそうだし、自分が誰にも相手にされないのを、自分はみなに一目置かれているのだというようにすりかえて自分を慰めるのもそうだ。こうなると、もはや病膏肓の域に近づいてくる。これは、もはやただの 「自我肥大」 か 「自意識過剰」 にすぎない。 これが意味するのは、自己と自己をめぐる状況について客観視ができないということだ。そして、そのような 「自己客観視」 の不能は、ただの自己正当化による 「認知的不協和」 の解消にますます拍車をかけることになる。その結果、ニワトリとタマゴのような関係が生じ、どっちが原因でどっちが結果なのか、もはや分からない状態になってしまう。 これはとくに自尊心の高い人ほど陥りやすいものだが、そのことはつまり、この 「病」 はかならずしもたんなる 「劣等感」 の所産とは限らないということ、言い換えると、それなりに高い才能や能力を有する人でも、このような 「病」 に罹患するおそれはあるということを意味する。実際、漱石や芥川のような才人であっても、こういう 「病」 から完全に逃れることはできなかったのだから。 漱石と並べるわけではないが、最近で言うなら、五輪招請の失敗をめぐる、石原都知事のブラジルとフランスなどとの裏取引を示唆するかのごとき発言もそうだろう。彼の過去の発言を振り返ると、招請失敗の最大の責任は彼自身にあるとしか思えないのだが、結局、彼はそういった事実や現実を認めたくないために、無意識に 「認知」 の修正をやって、責任をよそに転嫁しているにすぎないように思える。 ところで、今日10月10日は中国では双十節と呼ばれ、1911年に長江中流の都市、武昌(現在は対岸の漢口との合併によって武漢となっている)で、政府による鉄道国有化政策をきっかけとして軍隊の蜂起が起こり、全国に波及して清王朝が倒れた辛亥革命が始まった日でもある。 以下は、「日本改造法案大綱」 を書いて陸軍を中心にした青年将校らに影響を与えたため、2.26事件の首謀者として処刑された北一輝の 『支那革命外史』 序からの引用である。相抱いて淵に投じた二人の中、一人は眠りから覚めなんだ。一人は蘇生した。蘇生した一人が倒幕革命の一幕を終わってむなしく墓前に哭した時、頭をめぐらせばすでに十有余年の夢である。不肖また支那の革命にくみして十有余年、まことに一夢のごとし。ろくろく何事をもなすあたはざりし遺憾は盟友らの墓石に対するもこころよくない。清朝転覆の一幕、盟友らにとりて何程のことであらう。非命にたおれた宋教仁・范鴻仙君らの悽慘な屍を巻頭に弔らひ掲げて、ひとり暗涙をのみつつ、筆を執っていた六年前の不肖自身の心中が悲しまれる。 文中、「相抱いて淵に投じた二人」 とは、薩摩藩の開明的藩主島津斉彬が急死したのち、錦江湾にともに身を投げた西郷隆盛と僧月照のことを指しているのだろう。月照は安政の大獄で幕府から終われる身となり、西郷とともに京都から薩摩に逃亡したが、斉彬の死による藩政の変化により追放を命じられたたため、悲観して西郷とともに身を投げたということだ。 北のこの書のすぐれている点は、列強の進出に苦しむ 「後進地域」(今ふうに言えば 「第三世界」)における革命運動が、ときとして排外的でもあるナショナリズムの高揚を伴うことの必然性を理解していたところにある。それは、いうまでもなく幕末の倒幕運動が攘夷からはじまったことの意味を、彼が正確に認識していたからでもある。 彼が、アメリカかぶれの孫文を評価せず、その最大のライバルであった宋教仁を支持したのはそのためだが、その結果、上海で起きた宋教仁暗殺の黒幕を、袁世凱ではなく孫文だとしたのはいただけない。しかし、それもまた、イソップのキツネと同じ 「認知的不協和」 のもたらしたものなのかもしれない。関連記事: 「自己イメージ」 の歪み、あるいは 「認知的不協和」 について
2009.10.10
コメント(2)
-
伊勢湾台風の再来か
台風18号は、古来の南海道の鼻先をかすめて愛知県南部に上陸した。その後、本州を縦断して、東北から太平洋に抜けたとのことだ。同じようなコースをたどり、大きな被害をもたらした台風といえば、誰もが伊勢湾台風を思い起こすだろう。報道でも、伊勢湾台風との比較がさかんに行われている。 伊勢湾台風が襲来したのは1959年9月26日ということだから、その記憶はまったくない。なにしろまだ三歳にも満たぬころだから。ただ、伊勢湾台風は阪神大震災が起こるまでは、戦後最大の被害をもたらした自然災害だった。阪神大震災の死者は6,434人、行方不明者3人、負傷者43,792人ということだが、伊勢湾台風による死者は4,697人、行方不明者401人、負傷者38,921人にのぼっている。 むろん、現代では、当時にくらべ河川の改修や河口付近の防潮堤の整備、それになによりも上陸のはるか前からの正確な進路予報のおかげで、台風のためにそのような甚大な被害が出ることはないだろう。とはいえ、すでに2名の死者と59名の負傷者が出たということだ。もちろん近親に死者を出した人にとっては、その数の大小など関係のない話ではある。 ところで、洪水神話といえば当然 『創世記』 にある 「ノアの箱舟」 の話が連想される。ノアの箱舟は、トルコと旧ソ連との国境に近いカフカス山中の山、アララト山に漂着したとされているが、あんな巨大な箱舟が実際に作られたとはとうてい思えないので、これは眉唾な話だろう。おそらくは、「伝説」 を作った人々にとって、アララト山が彼らの知る最も高い山だったということにすぎまい。 この洪水説話そのものは、それよりはるかに古いメソポタミアの神話が原型だそうだが、そのひとつ、最古の文明であるシュメールの伝説的な王にして英雄ギルガメシュを歌った 「ギルガメシュ叙事詩」 では、洪水の場面がこんなふうに描かれている。六日七夜、風と洪水が大地を襲った。嵐は大地を平らにした。七日目になると、嵐は去り、洪水は苦悶する女のように自らと格闘した。大洋は静まり、悪風は治まり、洪水は退いた。私は一日中あたりを見回した。沈黙があたりを支配していた。すべての人間が粘土に戻っていた。大地は屋根のように平らだった。(中略)七日目になって、私はハトを放した。ハトは飛んでいったが、戻ってきた。休み場所が見つからなかったので、戻ってきたのだ。私はツバメを放した。ツバメは飛んでいったが、戻ってきた。休み場所が見つからなかったので、戻ってきたのだ。私はカラスを放した。カラスは飛んでゆき、水が退いたのを見た。カラスはついばみ、身繕いし、頭を動かしたが、戻ってこなかった。そこですべての鳥を四方に放ち、犠牲をささげた。「11枚目の粘土板」 より これを読むと、アメリカに多いらしいID(インテリジェント・デザイン)論者のような 「聖書」 原理主義者には悪いが、たしかに 『旧約聖書』 の物語のほうはただのパクリだとしか思えなくなってくる。 さて話は全然かわるが、ネットなどの公共の場での議論では、しばしば 「中学生にも分かる話」 と 「中学生には分からない話」 が対立することがある。言い換えると、これは基本だけを教える 「初級編」 と、それを前提にし、さらにその上のことを学ぶ「上級編」の対立ということだ。 「上級編」 では、「初級編」 で一般的に教えられたにすぎない原則がより厳密に定義されたり、原則を制限する条件や状況について教えられたりする。その結果、それまでの原則に反するかのごとき 「例外」 が教えられることもある。初級者にとって 「原則」 は唯一にして絶対だが、上級者にとっては必ずしもそうではない。 また、たいていの分野では原則はひとつではなく、互いに対立することもある。その結果、「初級編」 での教えと 「上級編」 の教えとは、しばしば対立し相反するかのように見えることになる(ただし、カルト教団などでしばしば見られる、教祖に絶対忠誠を誓った特定の信徒のみに内密で伝授される 「高度の教え」 なるものは、これとは別の話である)。 たとえば、小学生の算数では 「引く数」 は 「引かれる数」 より小さくなければならない。そうでなければ、引き算そのものが成立しない。しかし、中学生になると、この原則が簡単にひっくり返される。それは、言うまでもなく、負の数が導入されるからだが、ここで 「なんでやー」 と躓くと、その先には進めないことになる。 当然のことだが、「中学生には分からない話」 を理解できる人の数は、「中学生にも分かる話」 を理解できる人よりも少ない。ただし、そこの段差がさほど大きくなければ、「中学生には分からない話」 を理解できる人もそれなりにおり、「中学生にも分かる話」 しか理解できないという人はそれほど多くはないだろうから、さして問題とはならないだろう。 困るのは、この差がいささか大きく、そのため、「中学生には分からない話」 も理解できるという人の数があまり多くなく、結果的に 「中学生にも分かる話」 しか理解できない人のほうが多数を占めるといった場合である。 実際の中学生ならば、「自分はまだ中学生だから、これはまだ理解できないんだ。もっと勉強して理解できるようになろう!」 ですむのだが、あいにくと 「公共」 の議論に参加する人たちは、みな自分は立派な大人だと思っていて、本当はまだ中学生にすぎないということを自覚していなかったりする。 なので、そのような場では、しばしばただの 「基本編」 にすぎない 「中学生にも分かる話」 のほうが正しく、「中学生には分からない話」 は間違っているかのように見え、結果として多数を制してしまうという、へんてこりんなことが起きてしまう。 「科学」 や 「学問」 のように、それなりの知識を必要とし、参加資格が実質的に制限されていたり、暗黙のうちに序列化(それがつねに適切だとは限らないが)されているような場なら、そういうことはあまり起きない。しかし、建前上、すべての人に開かれている 「公共」 の議論では、こういうことがあちこちでけっこう起きる。 「公共」 の議論に参加する者の資格を制限するわけにはいかないので、これはしょうがないのだが、そういうところを実際に目にしたりすると、いささか脱力してしまう。勝ち誇ったような身振りで、「原則論」 をとうとうとのたまう人がいたりすると、「そんなことは分かってるよ」 とか、「いや、そういうことを最初から言ってるのだけど」 などと言いたくもなるという話である。 ところで、今日は10月8日、つまり、今から42年前に、戦争下にあった南ベトナムの首都サイゴンを訪れようとした当時の佐藤栄作首相に対し、「三派全学連」 と呼ばれたグループの学生らが空港近くでデモを行い、機動隊と衝突した結果、山崎博昭という京大の学生が死亡した日である。 彼は1948年生まれだったそうだから、生きていれば来月で61歳ということになる。評論家の橋本治や糸井重里、作家の立松和平らと同じ世代。とくに糸井とは、誕生日がわずか2日しか違わないらしい。注: 念のために、付け加えておきますが、文中で 「中学生」 という言葉を使ったのはあくまで比喩なので、もしそれが不愉快だという方がいれば、適当に 「高校生」 とか 「大学生」 などの言葉に置きかえてください。 また、だから 「公共」 の場の議論への参加には、資格制限をつけるべきだなどということを言っているわけでもありません。
2009.10.08
コメント(0)
-
我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか
ゴッホとの共同生活が破綻したゴーギャンがフランスからタヒチへと逃亡したのは、ゴッホと別れてから三年後の1891年のことである。タヒチが 「発見」 されたのは18世紀半ばで、最後にはハワイで先住民に殺された、かのキャプテン・クックことジェームズ・クックも、金星観測のため、1769年にタヒチを訪れている。 むろん、この 「発見」 とはヨーロッパ人と彼らの世界にとってのことにすぎない。タヒチは、おそらくはアジアのどこかから船出し、その後、ハワイからイースター、さらにニュージーランドにまで航海を続けた人々らによって、そのはるか以前に発見されていたのである。いうまでもなく、それはいわゆる 「新大陸」 の場合でも同じことだ。 タヒチなどの島々の 「発見」 が、当時のヨーロッパの知識人らにどのような影響を与えたかは、たとえば革命前のフランス啓蒙思想家の一人であるディドロが、航海から帰国した同国人のブーガンヴィルについて、『ブーガンヴィル航海記補遺』 という書を書いていることからもうかがえる。彼はその中で、次のように書いている。ああ!ブーガンヴィル氏よ、あなたは無邪気で仕合せなタヒチ人のすむ岸辺からあなたの船を遠ざけるがいい。彼らは幸福でいるのに、あなたはただ彼らの幸福を損なうだけであろうから。彼らは自然の本能に従うのに、あなたはこの荘厳神聖な性格を抹消しようとしている。いっさいは万人に所属するのに、あなたは我のもの、汝のものという不祥な区別を彼らの中に持ち込もうとしている。ついに、あなたはタヒチを去る。......すでに夜明けの時刻から、彼らはあなたが船に帆を上げるのを認める。彼らはあなたのもとに殺到し、あなたを抱擁して涙を流す。泣くがいい、哀れなタヒチ人よ。しかしお前たちの流す涙はこれらの野心に満ちた、腐敗した、邪悪な人間の到着を悼む涙であっても、決して出発を悼む涙であってはならない。いつか、お前たちは彼らの正体を知るに違いない。いつか、彼らは片手に十字架、片手に短剣を握って到来し、お前たちを虐殺したり、お前たちに無理やりに彼らの習俗や見解を採用させたりするに違いない。いつか、お前たちは彼らの足もとにひれ伏して、彼らとほとんど変わらない不幸な状態に陥るにちがいない。 ディドロの予言どおり、タヒチはその後、太平洋における英仏の覇権争いに巻き込まれ、1842年にはフランスの保護領、さらに1880年にはその植民地となり、現在は、共和国フランスの自治権を与えられた 「海外領土」 ということになっている。ちなみに、タヒチに近いムルロア環礁で、フランスの核実験が行われたことは、まだ記憶に新しい。 このような、いわゆる 「善良なる未開人」 の発見が近代ヨーロッパの思想に及ぼした影響については、言うをまたない。世界各地での 「未開人」 の発見は、やがて 「人類学」 なる学問の誕生に導き、ヨーロッパという 「文明諸国」 の遠い過去との比較であるとか、また人類の文化と社会の「発展段階」論といった壮大な理論もいろいろと提出された。 それはともかくとして、一般的に言うなら、自然科学であれ人文・社会科学であれ、「人間」 という生物についての科学が発達することは、人間を 「神」 の似姿という神聖な座から引きずりおろすことを意味する。 われわれ人間が、人間自身を客観的で合理的な冷たい認識の対象とするとき、人間はもはやかつての伝統的な 「キリスト教神学」 で信じられていたような、神と同じ理性を分有し、神から特別なご愛顧を受けた、他の生物とは別格の生き物ではあり続けられない。「進化論」 がもたらした衝撃とは、まさにそういうものである。 われわれは、すでに人間の 「意識」 というものが、神から授けられた、神と同じ 「理性」 などではなく、進化によって生まれた脳という器官の産物にすぎないことを知っている。だが、具体的な意識は、身体とそれを取り巻く、他者を含めた 「世界」 との関係の中で成立するのであり、したがってたんに脳の中にのみ局在しているのではない。 それは自己の身体を貫き、身体をすっぽり覆うと同時に、身体からはみ出したものとしても存在する。たとえば、熟練者が道具や機械を操作するときのように。それは、いわば 「延長された身体」であり、「二乗された身体」 でもある。そして、その結果、「身体」 の側にも、「精神」 の中に取り込まれ、「精神としての身体」 に変容するという妙な状況が生じることになる。 なんの因果かは知らないが、人間は、巨大な大脳を含む特異な身体組織を得ることで、「自己意識」 というややこしいものを持ち、言葉をしゃべるようになった。おかげで、人間はわけのわからぬさまざまな 「観念」 を生み出し、悩まされるようにもなってしまった。もっとも、それがどのようにして発生したかは、すでに遠い記憶の彼方であるから、もはや誰にも分からない。 たとえば、呪術の力を信じる 「未開人」 は、呪いをかけられたと思うと、それだけで死にいたるという。だが、それは、彼が 「愚昧」 であるがために起こるのではない。そうではなく、それは彼もまたわれわれと同じ、「観念」 という病にとりつかれているがゆえに起きるのだ。 そこに違いがあるとすれば、それはせいぜい、とりつかれる 「観念」 の違いにすぎない(どちらが高級であるかは、あえて問わない)。つまるところ、魔法や呪術を信じる 「未開人」 もまた、多少の程度の差はあれ、われわれと同じ立派な 「文化」 的存在なのである。 途中ははしょるが、結局のところ、自然史という地球の歴史への登場以来、われわれ人間はみな、究極的にはこの奇妙な 「心身」 という 「下部構造」 による規定をつねに受けている。そして、そのような 「下部」 と、その上に立つ歴史や社会、文化といった 「上部」 をつなぐ配線は、たしかに明瞭ではないが(完全に明瞭になることはありえないだろう。それはつまり人間が「自由」でもあるからだ)、なんらかのイデオロギーによってことさらにつながなくとも、すでにそこにあるものである。 したがって、そのような 「配線」 の存在を意識することは、なんらかの 「価値」、たとえば白色人種、とりわけアーリア人種の優越といった怪しげな 「理念」 や、特定の民族や社会層に対する差別を正当化するために、「遺伝学」 だとか 「生理学」 だとか、つねにひとつの暫時的な仮説でしかないなんらかの 「科学」 によって、怪しげな 「配線」 をすることとはまったく別のことだ。 それはまた、なんらかの 「下部構造」 から直接に、「価値」 だとか 「理念」 だとかを導き出そうという話なのでもない。むろん、そのような 「配線」 の存在を認識することは、人間の自由をすべて否定することでもない。ただ、その 「絶対性」 が否定されるだけのことだ。だが、絶対的に自由な人間など、地上に存在しえぬことなど、ほとんど自明のことにすぎまい。 しかし、「上部構造」 に対する否定的制約としてであれ、その成立を可能とする肯定的条件としてであれ、人間の 「本性」 や 「生活世界」 といった具体的な 「下部」 による規定を無視して、自らを 「普遍的」 と称する理念が大手を振って歩き回るなら、そこに生じるのはつまるところ 「啓蒙の暴力」 であり、せんじつめれば、現に近現代史の中でしばしば生じたような、「普遍性」 の名による 「テロル」 ということにしかなるまい。 「行動主義心理学」 を提唱したワトソンは、かつて、「もし自分に生後間もない健康な子供を預けてくれるならば、その子供をどんな性格にでも、どんな職業人にでも育て上げてみせる」 と豪語したという。むろん、これはおそらく当人も承知の、宣伝をかねた一種のハッタリにすぎないだろう。 だが、そのような人間の 「本性」、すなわち "human nature" そのものの存在をいっさい否定する論理こそが、「革命」 や 「党」、「国家」 といった大義の前には、親や家族、親しい友人らも売り渡すことが正しい行為だとして称揚された 「スターリニズム」 の論理を生んだのであり(むろん、それだけが原因ではないが)、それが最後に行き着く先はオーウェルの描いた 『1984』 ということになるだろう。 現代の社会が、いわゆるグローバル資本主義を経済としての 「下部構造」 としているとしても、われわれを規定しているのはそれだけではない。経済としてのグローバル資本主義は、自己に照応する複雑な 「上部構造」 を必要とする、それ自体が一つの巨大で複雑なシステムであり、それをもって社会を最下段で規定する 「下部構造」 であると単純にみなすことはできない。 そのような世界の変容は、むろん無視し得ない現実であるし、世界経済をかつてのような相互に孤立した国民経済へと分断することが可能なわけでもない。とはいえ、人間という存在を最終的に規定しているのは、われわれ自身の 「心身」 と 「生活世界」 とでも言うべき具体的な現実ではあるまいか。 まだ若かったマルクスが言った、「現実的な諸個人による物質的生活の生産」 とは、まずはそのような具体的な世界のことを指しているのであり、それはたんなる経済や経済学の問題なのではない。あらゆる人間歴史の最初の前提は、もちろん生きた人間的諸個人の存在である。それゆえ、最初に確認すべき事態は、これら諸個人の身体的組織、およびそれによって与えられる彼らのそれ以外への自然への関係である。『ドイツ・イデオロギー』 ついでに引用すると、マルクスの同時代人であったシュティルナーは、キリスト教の神とは、類としての人間の本質が疎外されたものであり、人間はそのような神として自ら疎外した自己の本質を取り戻さなければならないと説いたフォイエルバッハに対して、彼はただ神の代わりに、「人間」 なるものをその座につけたにすぎないと批判している。 なぜなら 「神の精神」 はキリスト教的見解によれば、また「われわれの精神」 でもある。......それは天にもわれわれのうちにも住む。哀れなるわれわれはその 「住居」 である。そしてフォイエルバッハが進んでその天上の住居を破壊し、そのすべてをわれわれのうちに移そうとするなら、そのときわれわれ ―― その地上の住居 ―― は著しく混雑をきわめるであろう。『唯一者とその所有』 人間と社会の 「基底」、いいかえれば、われわれを規定している 「心身」 を含めた人間が有する 「自然」 を承認することは、つまるところ、人間がけっして神ではないということ、そしてまた、たとえわれわれが神を殺したとしても、人間はけっして神にはなれないということを明確に承認し、自覚することでもある。 結論はしごく当然な話になってしまったが、言いたいのはようするにそういうこと。なお、タイトルはむろんゴーギャンの有名な絵からのパクリである。
2009.10.02
コメント(4)
-
連休よりも仕事がほしい
先週のことだが、なんの因果か 「結婚式」 なるものに参列するはめになってしまった。そういう類のものは正直言って苦手なのだが、諸般の事情により、どうしても出席しないわけにはいかなかったのだ。 そういうわけで、ほぼ30年ぶりに九州から本州へと遠征したのだが、いやいや世の中というものは、大きく変わっていた。まことにテレビなどで遠くから見ているのと、実際にこの目で見てみるのとではまったく違うものだ。 考えてみれば、足利尊氏などはわずか1年の間に、後醍醐政権を倒すための鎌倉から京都への進軍と、新田義貞に敗れたことによる九州への退却、さらには再度の京都いりをはたしている。それは、人の足と馬以外に交通手段のなかった700年近くも前のことだ。それどころか、江戸時代の大名たちは、一年おきに地元と江戸の間を行き来していたのだから、われながら、その腰の重たさにはあきれるほかにない。 式場は横浜にあったのだが、駅の改札を出ると、目の前に広々とした 「大地」 が広がり、遠くにはビルも建っている。あれあれ、ここは三階ではなかったのか、と一瞬困惑したが、どうやら斜面を整地して、巨大なテラス状の人工大地を何段も建設し、そこに様々な建物を建てたということらしい。 もともと、横浜は平地の少ない地域であるから、市街の膨張とともに必要に迫られて、傾斜地域を開発するために工夫された方式なのだろうが、「世界七不思議」 のひとつに数えられた、古代バビロニアの王 ネブカドネザルが建設したという 「空中庭園」 にも劣らぬその壮大さには驚いた。まことに田舎者はこれだから困ってしまう。 式場は頂上に十字架と鐘楼をおいたゴシック風の建築で、中にはいると、窓には色とりどりのステンドグラスもはめられ、列席者用の簡素な木製の座席と机が、花嫁・花婿が通る通路を中心に左右対称に並ぶなど、本物の教会を忠実に模した造りになっている。ただし、式が執り行われる空間が、まるで劇場の舞台のように一段高くしつらえてあるのには、ちょっと首をかしげた。それでは、「神聖」 なる式が、なにやら下手な役者が演じる劇のように見えてしまうではないか。 イエス様もマリア様も信じていない不信心者がこんなところに入り込んでもいいのかな、罰が当たりはしないかななどとも思ったのだが、招待されたのだからしかたがない、一日だけ 「クリスチャン」 のふりをすることにした。どうせ、花嫁・花婿も、それから列席者のほとんどもそうなのだろうから。 扉には Le Chapelle d'Evangile と書かれており、おやおや、ひょっとして使徒が襲来すると、このあたりのビルがぐあーんと動き、大地がすーっと開いて、その底からシンジ君が乗るひょろりとした 「初号機」 が登場するのかななどと思ったが、よく考えればなんのことはない、「福音教会」 という意味である。 式をとりおこなったのはヨーロッパ系の長身の男性で、その横には黒い服を着た修道女ふうの女性もならんでいる。その男性が本物の神父なのかどうかは知らないが、おかしかったのは、式の間、ずっといかにも 「外人」 ふうの妙な日本語をしゃべっていた 「神父」 様が、式典が終わったあと、壇上から降りてきてこちらに歩み寄ってき、小さな声で「おめでとうございます」 と、ごく普通のアクセントのなまりのまったくない流暢な日本語を話したことである。 たぶん、式典では 「アナタハァ、カミニィ チカイマスカァ」 というような、日本人が普通にイメージする、いかにも 「外人」 といった感じでしゃべらないと、「外人」 様というありがたみが出ないということなのだろう。「ご苦労様です」 と、思わず心の中でつぶやいたのであった。 式が終わると、建物の中をあっちこっちと引っ張りまわされたのだが、壁にどこかで見た覚えのある絵が何枚も飾ってある。青を基調にして、赤や黄色、緑で花嫁と花婿の姿や馬などの動物を描いた幻想的な画風で、覚えはあるのだが、誰の絵なのか、すぐには思い出せない。クレーでもないし、カンディンスキーでもないし、などと一生懸命頭をひねっていたのだが、何枚目かの絵に Chagall というサインがあって、ようやく思い出した。そう、ロシア出身のユダヤ人画家、シャガールであった。 シャガールの絵には、たしかに若い男女のカップルを描いた絵が多い。結婚式場に飾る絵としては、なるほどなるほど、むべなるかなというところだ。帰ってきてから、家の近くのいつものBOOKOFFで、シャガールの画集を見つけた。絵と解説(竹本忠雄という人だが、よくは知らない)のほかに、ジャン・グルニエの文章が収録されている。グルニエとは、あのカミュのアルジェリア時代の恩師だった人である。 シャガールの顔は、なにもかもが曲がっている。眉毛はアクサン・シルコンフレックスだし、唇はゆがんでいないまでもすんなりと半円形、鼻もかるく曲がって、目はまんまる、髪は半ば狂乱のていである。バルザックの時代であったなら観想家たちはこれを出発点に、さだめし人物の心的肖像画を書きあげたことであろう。 彼らはこう言ったかもしれない。精神においては繊細、芸術においてはファンテジー、生にあっては放心、心情は直感、ようするに――内的ハーモニーによってもたらされ、それによって、人間が自己のうちにその確信と憩いを見いだしうるところの全価値がそこにはある、と。そう、環境がどうあろうとも、たとえばそれが、革命、戦争、喪のごとくに人を茫然自失せしめ、あるいは辛酸をきわめたものであろうとも。『幻想と自然』 ジャン・グルニエ さて、民主党を中心に社民党、国民新党とも連立した鳩山政権がいよいよ誕生した。聞くところによると、「改正」 教育基本法によって導入された教師免許更新制度や、障害者や高齢者の負担増をもたらした障害者自立支援法、「後期」 高齢者医療制度などについて、新政権はいずれも見直しや廃止の方針を明らかにしているらしい。 こういった動きは、一見すると、法や制度の安定性と一貫性を損なう 「朝令暮改」 のように見えなくもない。しかし、そこで問われるべきなのは、むしろたった一度の選挙、それも、郵政民営化の是非のみを争点にした選挙で大量の議席を得たことをいいことに、野党や世論の反対意見にいっさい耳を貸さず、反対派の説得や妥協案の模索という民主政治における最低限の努力も放棄し、数の論理だけで押し切って、そのような問題の多い制度を次々と導入した、小泉・安倍政権の政治責任ということになるだろう。
2009.09.20
コメント(1)
-
「トリックスター」と「文化英雄」
先日ちょこっと言及した大林太良の別の著書 『神話学入門』 に、ドイツの民族学者カール・シュミッツ(政治学者のカール・シュミットと名前は似ているが、まったくの別人。1920年生まれだそうだ)による神話の分類として、次の三つがあげられている。1 だれが、どのようにして世界を創造したか(宇宙起源論)2 だれが、どのようにして人類を創造したか(人類起源論)3 だれが、どのようにして文化を創造したか? この三つの分類について、大林は下のように説明している。 天と地に関する関する神話とか、天体やその他の自然に関する神話は、私の考えではみな宇宙起源論の一部であり、洪水神話その他の大災厄神話も、宇宙起源神話の一部である。 他方では大災厄神話も、人類の起源を物語るかぎりにおいては人類起源神話の一部であり、また原古の状態に関する神話は、それが原古における文化の起源を説明するかぎりにおいては文化起源神話である。 たとえば、『旧約聖書』 であれば、神が 「光あれ!」 と叫んで光と闇とをわけ、さらに天と地をつくり、七日間で世界を創造したという 「創世記」 冒頭の説話などは、典型的な 「宇宙起源神話」 ということになる。また、土からアダムを、さらにその肋骨からエバを作ったという話は、ここでいう 「人類起源神話」 ということになるだろう。 本居宣長の死後の弟子と称した、平田篤胤による日本神話解釈は、天照大神を唯一神化するなど、当時国禁であったキリスト教の教義をひそかに取り入れることで、「神道」 教義の体系化を試みたものといわれているが、「古事記」 冒頭の 「天地の初発のとき」 の一節も、彼によって 「創世記」 同様の宇宙創造論として解釈されている。 ところで、「文化英雄」 というのは、神話の中ではあまり待遇がよろしくない。文化の起源とは、たとえば火の利用についての起源や農耕の起源、言葉や文字の起源などのことだが、ギリシア神話の場合、巨人神族のひとりであるプロメテウスは、ゼウスの目を盗んで天界から火を持ち出して人間に与えたため、報復として大きな岩に縛り付けられ、毎日毎日、鋭いくちばしを持った鷲に、生きたまま肝臓をつつかれるという目にあうことになってしまった。 原始的な宗教における神々が、冷厳な 「自然の鉄則」 や人間を取り巻く 「運命」 の象徴であるとするなら、「文化」 とはそのような自然や、あるいは自然法則であるかのように人間を訪れる 「運命」(たとえばオイディプスの物語のように)に対する反抗ということになる。「文化」 はそのような神々を出し抜き欺くことで、はじめて人間の世界に登場したということだ。 だから、神話の世界では、「文化」 が持つ意味はしばしば両義的である。そのことをいちばん象徴しているのは、これもまた 『創世記』 にある、エバをそそのかしてエデンの園の中央に立つ禁断の木の実を食べさせた、ヘビの話ということになるだろう。 『創世記』 では、ヘビは 「神が創造した野の獣の中でいちばん狡猾」 な獣と描かれているが、ヘシオドスもまたプロメテウスについて、「さまざまな策に富む」「策に長けたプロメテウス」、「知略にかけては尊大なクロノスの御子(ゼウスのこと)と、互角に張り合うほどであった」 などと描いている。 ここからは、またトロイアからの帰国途中、海神ポセイドンの怒りを買って船が難破し、あちらこちらでいろいろな苦難にあいながらも、セイレーンや一つ目の巨人だのという怪物や魔女、妖精らの裏をかいて、最後には無事故国に帰りついた 「策略巧みな」 オデュッセウスのことも連想される。 エバに対して、禁断の木の実を食べても、「君たちが死ぬことは絶対にないよ」 とささやいたヘビは、たしかに悪意を抱いて彼女を騙したのだが、それに続く、「神様は君たちがそれを食べるときは、君たちの目が開け、神のようになり、善でも悪でもいっさいが分かるようになるのをご存知なだけのことさ」 という言葉は、必ずしも嘘ではない。 実際、禁断の木の実とは 「知恵の実」 のことであり、これを食べたことで、「たちまち二人の目が開かれて、自分たちが裸であることが分かり、無花果の葉をつづり合わせて、前垂れを作ったのである」 と、『創世記』 には書かれている。人間は 「知恵の実」 を食べたことで、楽園からは追放されたのだが、そのかわりに、天にも届こうという 「バベルの塔」 を力を合わせて建てようというほどの知恵をも手に入れたということだ。 さて、掟を破って知恵の実を食べたアダムとエバは、怒った神により、次のように宣告される。君のために土地は呪われる。そこから君は一生の間、労しつつ食を得ねばならない。君は額に汗してパンを食らいついに土に帰るであろう。君はそこから取られたのだから。君は塵だから塵に帰るのだ。 「知恵」 とはつまり根源的には人間の反省意識、すなわち自意識のことだが、それと不可分のものとされている 「死」 とは、この場合、「死」 そのものというより、むしろ 「死の意識」 と言ったほうがいいだろう。つまり、人間は 「自意識」 を手に入れることで、同時に 「死」 に対する恐怖という意識にも憑りつかれるようになったということだ。 ディオゲネス・ラエルティオスによれば、古代ギリシアの哲学者であるエピクロスは 「死」 について次のように言っている。 死は、もろもろの災厄の中で最も恐ろしいものとされているが、実は、われわれにとっては何ものでもないのである。なぜなら、われわれが現に生きて存在しているときには、死はわれわれのところにはないし、死が実際にわれわれのところにやってきたときには、われわれはもはや存在していないからである。『ギリシア哲学者列伝』 なので、彼によれば、「死はわれわれにとって何ものでもないと考えることに慣れるようにしたまえ」 とのことだ。たしかに、彼の言うとおり、「死が実際にわれわれのところにやってきたときには、われわれはもはや存在していない」 のだから、悩んでもしょうがないということにはなる。だが、やはりそうはいかぬのも事実だろう。 アダムとエバに禁断の木の実を食べるようそそのかして、その目を開かせたヘビもまた、人間に対して 「知恵」 という文化の原理をもたらしたのだから、「文化英雄」 ということになる。だが、そこには神と人間に対する一定の悪意が存在していたことも明らかであるから、彼は同じく神話学で言う 「トリックスター」 としての性格も備えている。 「トリックスター」 とは、もとはネイティブ・アメリカンの神話についての研究から生まれた言葉で、「神や自然界の秩序を破り、物語を引っかき回すいたずら好き」 なのだそうだが、人類学者だけでなく、心理学者のユングなどもいろいろと論じている。「文化英雄」 と 「トリックスター」 が多くの場合、重なり合うということは、文化とは、本来そのような 「神や自然界の秩序」 を破るという性格を持つものだということを意味しているのだろう。 逆に言うならば、そのような 「神や自然界の秩序」 に対する挑戦という意味を失ってしまえば、文化は停滞してしまうということであり、文化としての意味も失われるということになる。つまるところ、「文化」 とは本来危険なものであり、だからこそほとんどつねに「文化」 は、時の権力による取り締まりや規制の対象とされてきたということでもあるだろう。
2009.09.13
コメント(4)
-
柄谷行人、小林秀雄、あるいは「自分探し」という病について
批評家の柄谷行人が、『探求II』 の中で次のようなことを書いている。 ところで、子供に死なれた親に対して、「また生めばいいじゃないか」 と慰めることはできないだろう。死んだのはこの子であって、子供一般ではないからだ。しかし、子供や妻が家畜と同じ財産と思われているような社会では、それが可能であるように見える。 たとえば、『ヨブ記』 では、神の試練に対して信仰を貫いたヨブは、最後に妻および同数の子供(男七人と女三人)とより多くの家畜を与えられる。しかし、どうしてそれで償われたといえるだろうか。死んだあの子が取り戻されたわけではないのだ。『ヨブ記』 を読んだ後に残る不条理感はそこにある。 『ヨブ記』 というのは、ヤーヴェなる全能の神と悪魔との人間の信仰心をめぐる賭けの対象に選ばれたヨブという男が、なんの咎もなしに次々と災厄を与えられるというとんでもない話である。神と賭けをした悪魔は、ヨブの命だけには手出しするなという条件で、ヨブから財産を奪い、子らを奪い、ヨブ自身にも全身がはれ上がるという病気を与えて、彼の神への信仰を試すことになる。 で、途中ははしょるが、「お前がそんな目にあったのは、なにか罪があるからだろう、きりきりと白状せい」 というようにヨブを責める友人らと、「いや、自分はいささかも罪など犯してはいない、神に背いてなどいない」 と反駁するヨブとの間で言い争いになり、腹を立てて、神に対し災厄の理由を問い質そうとするヨブの前に神が現れて、次のように言い放つ。 無知の言葉をもって、神の計りごとを暗くするこの者はだれか。あなたは腰に帯して、男らしくせよ。わたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ。わたしが地の基をすえたとき、どこにいたか。もしあなたが知っているなら言え。あなたがもし知っているなら、誰がその度量を定めたか。だれが測りなわを地の上に張ったか。その土台はなにの上に置かれたか。その隅の石はだれがすえたか。...... あなたは腰に帯して、男らしくせよ。わたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ。あなたはなお、わたしに責任を負わそうとするのか。あなたはわたしを非とし、自分を是としようとするのか。あなたは神のような腕を持っているのか、神のような声でとどろきわたることができるか。 こんなふうに言われては、ヨブとしては 「へへっ」 とかしこまるしかない。そういうわけで、最後に神は、試練に耐えたヨブを讃えて、その財産をもとの二倍にし、前と同じ数の子を与えたという。ここでの神は、キリスト教の神のような愛を説く神ではない。それは人間など足元にも届かぬ絶対的存在であり、また避けようのない不条理な運命であり災厄ですらある。 柄谷は、上に引いた文に続けて、「ヨブにとっては、妻子は家畜と同じ財産であり、したがって右のような疑念は生じないのである。」 と言っている。たしかに、前近代的な家父長制にはそのような側面があることは否定できない。しかし、全能の神にとって、人間が 「代替可能」 なただの頭数にすぎないのは当然だし、ヨブとしては、神に文句をつけるわけにいかぬのもしかたのないことだろう。 なので、この柄谷の言葉はいささか筋違いのように思える。実際、子を失ったヨブは激しく悲嘆したのだし、羊やらくだなどの家畜が二倍返しを受けたのに対し、子はなぜか前と同じ人数で返されている。家畜が二倍返しを受けたのは、それがまさに頭数でしかないからだろう。だから、家畜が二倍に増えたことは、ヨブにとって喜ばしいことである。 だが、子の数が前と同じだということは、「ヨブ記」 の作者にとっても、またヨブにとっても、子は家畜と同じ、ただ頭数だけで数えられる存在ではないということを暗示してはいないだろうか。もし、そうであるなら、神は子も家畜と同様に、前の二倍に増やして返してあげればよかったはずである。 たしかに、柄谷が言うように、新たに生まれた子は、死んでしまった前の子と同じではない。だが、「生」 と 「死」 を一種の交代とみること、すなわち、新たに生まれる者を前に死んだ者の 「生まれ変わり」 とみる観念は珍しいものではない。たとえば、大江健三郎も、『「自分の木」 の下で』 というエッセイの中で、幼い頃、熱を出していたときに、母親から 「もしあなたが死んでも、私がもう一度、産んであげるから、大丈夫。」 と言われたという話を書いている(フィクションかもしれないが)。 それはつまり、この 『ヨブ記』 の記述は、自然(あるいは神)の前には、人間は 「代替可能」 なものでしかないという 「死」 の必然性と、それにもかかわらず、固有の人間は固有の人間にとって 「代替不可能」 なものであるという人間の意識との間の微妙なバランスの上に成り立っているということだ。 さて、『ヨブ記』 についてのこの柄谷の感想は、言うまでもなく、小林秀雄の 『歴史と文学』 という講演を下敷きにしている。これは、日中戦争が長引くなかで、対米関係が悪化していった時期、ちょうど太平洋戦争が始まる半年ほど前に行われ、その後、雑誌 『改造』 に掲載されたということだ。 歴史は決して二度と繰返しはしない。だからこそ僕等は過去を惜しむのである。歴史とは、人類の巨大な恨みに似ている。歴史を貫く筋金は、僕等の愛惜の念というものであって、決して因果の鎖というようなものではないと思います。それは、たとえば、子供に死なれた母親は、子供の死という歴史的事実に対し、どういう風な態度をとるか、を考えてみれば、明らかなことでしょう。小林秀雄 「歴史と文学」 より 近代以前において、人間の 「代替不可能性」 などという問題が人々の意識に上らなかったのは、人と人が直接に交わる共同体では、おそらくそれが人々にとって自明のことであったからに過ぎまい。その逆に、そのような問題が近代において無視できぬ問題となったのは、まさに人間がただの番号や歯車になるという状況、言い換えるなら、人間の 「代替可能性」 という事実が、その前においては人間はまったくの無力に過ぎぬ神や運命の前においてではなく、人間が作るこの社会において、否定できぬ現実となったからではあるまいか。 だが、そのことは、人間の 「代替不可能性」 という問題そのものが、近代以前においては存在しなかったということは意味しない。それは、自己の胃腸の働きを知ることと、胃腸の働きそのものとは別のことであるのと同じことだ。胃腸でも脳みそでも、自分の器官が正常に働いている限り、人はだれもそのような器官の働きについて、あれこれと悩んだりはしないものだ。 だから、人間の 「代替不可能性」 という問題は、けっして近代特有の問題なのではないし、いわゆる 「近代的自我」 などというものに解消されるわけでもない。たしかに前近代では、人は 「共同体」 に包摂されており、つねに 「共同体」 とへその緒でつながっている。そこには、近代的な意味での 「個人」 だの 「個人主義」 だのといったものは存在しないだろう。 とはいえ、そのことは 「共同体」 の中に、近代とは違う意味で 「個」 というものがまったく存在しないということまでは意味しない。いつの時代であろうと、またどんな形態であろうと、人間がつくる 「共同体」 はただの牛や羊の群とはちがうし、ハチやアリが作る 「社会」 などともまったく違う。 かつて、レヴィ=ストロースは 『野生の思考』 の最終章で、サルトルを相手取って、次のような批判を加えた。 だから、わたしが民族学にあらゆる探求の原理を見出したのに対し、サルトルにとっては民族学が、乗り越えられなければならぬ障害、粉砕すべき抵抗という形で問題を作り出すものとなるのは納得できる。なるほど、人間を弁証法によって定義し、弁証法を歴史によって定義したとき、「歴史なき」 民族はどういう扱い方ができるのか? (P298) サルトルは思いがけぬ回り道をして、古臭い 「原始心性」 の理論家たちの錯覚に自らおちいっている。未開人が 「複合的認識」 をもち、分析や論証の能力を持つということは、サルトルには我慢がならぬことに思われるのである。その点ではレヴィ=ブリュールなどにさらに輪をかけている。 (P302) この批判が 「サルトルに対して」 という意味であたっているかはともかく(なにしろ、サルトルの 『弁証法的理性批判』 はむちゃ長い)、人間の「代替不可能性」 という問題を 「近代的自我」 だの 「自我肥大」 だのという問題に解消してしまうことは、結局のところ、レヴィ=ストロースが言うように、近代人と未開人の思考の間に和解不能な線を引くことであり、われわれにとって、未開人なるものをわれわれとはまったく異なった了解不能な存在とすることに等しい。 ひところ流行った 「自分探し」 という言葉は、昨今では 「中二病」 扱いされるなど、あまり評判がよろしくない。たしかに、これは言葉としてはあまりに薄っぺらだし、猫も杓子も 「自分探し」 といった流行ともなると、いささか辟易もさせられる。それに 「自分探し」 ばかりで振り回されるのは、一種の 「自我肥大」 ではあるだろう。 だが、「自我」 の病というものは、人間の固有の病ともいうべきものだ。「病」 というものはむろんよろしくないし、できるならばそんなものには罹らないほうがよい。もしも、罹ってしまったのなら、できるだけ早いうち、重くならないうちに回復したほうがよくはある。とはいえ、そのような病が、人間という存在そのもののうちに深く根ざしているのだとしたら、それはただ否定するだけですむものではない。 たとえば、2000年以上も前に王族の家に生まれながら、その地位を投げ捨て、修行と放浪の旅に出たお釈迦様もまた、やはり 「自分探し」 の旅に出たのではなかったのだろうか。つまるところ、「自分探し」 というものは、古くて新しい問題なのだから、そう簡単に馬鹿にできるものでもないということだ。むしろ 「ふんっ」 などと鼻の先で馬鹿にする者こそが、いずれそれによって報いを受けることにもなりかねないだろう。参照: 「死んだ子供」 を大切にしてください ブログ 「地下生活者の手遊び」
2009.09.06
コメント(2)
-
総選挙の結果はいかに?
報道によれば、いまや民主党は300議席を超える勢いなのだそうだ。小泉旋風が吹いた前回の選挙では自民党が三分の二を超える議席を獲得したが、ちょうどそれと反対の現象がいま起ころうとしている。 基礎票がある程度拮抗した条件下では、全体の1割にも満たぬ票が全国規模であっちからこっちへ動いただけで、まったく違った結果が生まれる。小選挙区制の導入は1994年の公職選挙法改正によるもので、実際の選挙としては1996年の第41回選挙以来五回目ということになるが、これで自民党も民主党も、どちらも小選挙区制の恐ろしさを身をもって体験したことになる。このことは、はたして今後の政局にどのような影響を及ぼすことになるだろうか。 今回、自民党に大きな逆風が吹いている最大の理由は、いうまでもなく、小泉退陣後の安倍・福田と相次いだ政権の投げ出しであり、その後の政権の、あっちに行ったりこっちに行ったりと、まるで定まらなかった舵取りにある。これを一言で言うならば、与党としての自民党の 「責任力」 に対する不信ということになる。 それにしても、前回の選挙で登場した 「小泉チルドレン」 に入れ替わるようにして、今回もまた多数の新人議員が登場することになる。これは 「鳩山チルドレン」 というべきか、それとも 「小沢チルドレン」 ということになるのか、まだよく分からないが、いささか危惧を感じるところではある。 ただ、たった1回の風で得た大量議席に胡坐をかき、勘違いして好き勝手なことをしていると、次の選挙でひどい目にあうよというのが、前回の選挙以来のひとつの教訓ではあるだろう。それは忘れてもらいたくない。とはいえ、民主党内ではおそらく大量の新人議員の囲い込みをめぐって、熾烈な党内闘争が繰り広げられることになるかもしれない。もっとも、その大半はすでにどこかのグループのひもがついてはいるのだろうが。 16年前に細川政権が誕生したときは、河野洋平が下野した党の総裁になり、その後の新進党結成をめぐる連立与党のごたごたの隙をつき、社会党の村山富市を担ぎ出すことで復権に成功した。しかし、今の自民党に、そのうち総理の座につけるという確実なあてもないままに、自分から進んで汚れ仕事を引き受けようというだけの覚悟のある人間がはたしているのだろうか。自民党がかかえている病根は、前回よりも確実に深いと言わざるを得ない。 いずれにしろ、政治家の世代交代と政界の流動化が、一気に加速することだけは間違いあるまい。それがいい方向に行くか、おかしな方向にいくかは、もちろんあらかじめどうこう言える問題ではない。だが、あちらこちらで酒に酔って醜態をさらした政治家や、ピントのずれた時代錯誤なイデオロギーを振り回してばかりというような政治家には、今回の選挙で落ちたなら、次があるなどといわず、このさいすっぱりと足を洗ってもらいたい。それがなによりもこの国のためである。 小選挙区制とは、いわば選挙区ごとに候補者が党の代表として争う選挙である。中選挙区ならば、大政党の場合、複数の候補者が立てるので、あの人よりもこの人という党内での選択も可能だが、小選挙区ではそうもいかない。だから、実際の選挙だけでなく、候補者選考の過程もひじょうに重要だということになる。したがって有権者にとっては、選挙前の党による候補者選考の過程に介入することも必要になるだろう。そうでなければ、国民はただ備え付けのメニューをあてがわれるだけのお客さんということになってしまう。 本来ならば、候補者選考の過程には、地域地域での党員や党の支持者の意見だとか、有権者の動向などが反映されることが望ましいのだが、現状は必ずしもそうなっていない。そもそも、日本の政党は、ほとんどが近代政党としての組織の体をなしていないし、逆に組織された政党のほうには、非民主的な上意下達のうえに、内側に閉じこもり外に開こうとしない傾向がある。 小泉旋風は劇薬のようなもので、その効き目におぼれたことが、その後の自民党の首をしめることになった。党の代表というものはむろん大事だが、その個人的人気という、いささかあやふやな即効性のみを期待して、これに頼ることは、法で禁止された危険な薬物に手を出すようなことであって、やっぱり誉められることではない。 そもそも、幹部や将来を期待されていた(?)中堅議員を含めて、大量の前議員の落選が予想され、いったい誰が国会に戻ってこられるか分からないという状況では、選挙後の党の体制がどうなるかもさっぱり分からない。党内の小派閥などは消滅してしまうかもしれないし、そうでなくとも幹部クラスの落選によって、実質的に派閥として機能しなくなるようなところも生まれるだろう。 言うまでもなく、麻生がこのまま党総裁の座にいすわり続けられるはずはない。だれが当選しようが、だれが落選しようが、歴史的な大敗によって、これまでの党内の幹部・中堅クラスの発言力が大きく減退し、当選回数による年功序列的な党内体制が動揺することも、間違いないだろう。 政界の勢力図が大きく様変わりすれば、民主党にとっても自民党にとっても、党内の流動化が生じるのは必至である。とりわけ逆風を受ける側にとっては、選挙後の体制がどうなるかさっぱり見当がつかないというのも、これまた小選挙区制の恐ろしさということになるだろう。むろん、いまはみな自分のことで精一杯で、そんなことを考える余裕などないだろうが。
2009.08.28
コメント(0)
-
夏の定番といえば...
夏の定番といえば、一にお祭り、二に花火、三四がなくて五に怪談ということになるだろう。古典的な怪談といえば、なんといっても夫の伊右衛門に毒を盛られて目の上を腫らしたお岩さんが登場する 「四谷怪談」 が有名だが、ほかにも、「一枚、二枚、三枚...」 と皿を数えては、最後に 「一枚足りない」 と恨めしげに語る、お菊さんの幽霊で知られる 「番町皿屋敷」 や 「牡丹燈篭」 の話も有名である。 そのほかにも、江戸時代には行灯の油が大好きという化け猫で有名な、佐賀の鍋島騒動の話もあるし、明治になれば、そのものずばり小泉八雲の 「怪談」 というのもある。「高野聖」 などを書いた泉鏡花にも様々な怪談話があるし、夏目漱石の 「夢十夜」 にも、いささか怪談じみた話が多い。ただし、Wikipediaによれば、最初にあげた三つが日本三大怪談ということになっているようだ。 「怪談」 というのを定義するとすれば、お化けや妖怪、幽霊などの超自然的な存在や超自然現象が出現して人を脅かす話ということになるだろうが、日本におけるその原型というのは、奈良・平安の頃に書かれた 『日本霊異記』 や 『今昔物語』 などに収められた、前世や現世での人間の悪行の報いを説く仏教説話ということになる。 これらの話は、ようするにこの世で悪いことをすると、あの世で閻魔様や怖い鬼たちにしばかれますよという話であり、つまりは、怖さそのものを味わう怪談話というよりも、だから悪いことをしてはいけませんよ、という話である。したがって、これはむしろ道徳の話といったほうがいい。実際、奈良・平安の時代の人々にとっては、飢えや病気、夜盗や追い剥ぎなど、てんで珍しくはなかった現世そのものが、まずは恐ろしいものであっただろう。 それだけに、人々には仏教などのありがたい教えに救いを求める気持ちも強く、したがって寺の僧侶らがとく因縁話も、おそらくは誰一人ちゃかすことなく真面目に信じられていただろう。村の古老とかが話して聞かせただろう妖怪変化などの伝説の類だって、とてもリアルなものであって、その恐ろしさを味わうなんて心の余裕は、とうていなかったに違いない。 つまり、話の怖さそのものを楽しむ 「怪談話」 というものは、そのようなお話が本当にありうるとはもはや受け取られない時代になって、はじめて成立したということになる。「恐ろしさ」 を味わうというのは、「恐ろしさ」 そのものをベタに受け取るのではなく、たとえその場では無理だとしても、「恐ろしい」 という自分の気持ちをさらにメタに見ることができるようになって初めて可能なのだ。 事実、「四谷怪談」 にしても 「番町皿屋敷」 にしても、本当にこわいのは化けて出てきたお岩さんやお菊さんではなく、仕官の話に目がくらんでお岩に毒を持った伊右衛門や、お菊に濡れ衣を着せて惨殺したお殿様などのように、生きている人間のほうである。つまり、このような怪談は、ほんとうは幽霊の恐ろしさではなく、人間の欲望の恐ろしさや、業の深さをえがいたものなのである。 だから、その 「恐ろしさ」 は、劇を見ている人間自身の恐ろしさでもあるということになる。そこでは、そのような 「怪談」 が本当にありうるかどうかは、もはや問題ではない。そこで出てくる幽霊は、人間がみな持っている恐ろしさの象徴であり、人間の業というものがひとつの実体として、目に見えるものに 「化体」 したにすぎない(哲学的に言うと、これは一種の 「疎外論」 である)。 さて、いよいよ選挙もたけなわであるが、ある政党からこんなパンフレットが出ているそうだ。 知ってドッキリ民主党 これが本性だ!! これによると、なんでも、民主党には、日本で革命を起こし、社会主義化しようという 「秘密の計画」 があるそうなのだが、結党以来、80年を超える共産党にも、戦後長らく第一野党の座を占めていた旧社会党にもできなかった 「革命」 なるものが、いったいどうやったら、多種多様な意見を有する議員で構成された民主党にできるというのだろう。 このパンフを作成した連中がこんな馬鹿話を本当に信じているとしたら、彼らはただのアホウということになる。しかし、もし自分では信じてもいない話を、こんなにでかでかと宣伝しているのだとしら、それは彼らが、この国の大衆なんて、この程度の馬鹿話で簡単に丸め込むことができると思っているということになるだろう。 「嘘をつくなら大きいほうがばれにくい」 とか、「どんな嘘でも繰り返し宣伝すれば真実になる」 などと言ったのは、たしかヒトラーであるが、いやはやなんともかんともである。 これではまるで、夏休みの子供の毎夜毎夜の夜遊びに悩まされ、万策尽きたどこかの親が、「夜遅くまで遊んでいたら、お化けに出くわすぞ!」 といった話で脅かしてなんとかしようというような話である。だが、いまどきの子供は、もはやそんな話に納得したりはしないだろう。現代っ子をなめてはいかんのだ。 「ヨーロッパにはひとつの妖怪が出没している」 というのは、有名な 「共産党宣言」 の書き出しだが、どうやら、この人たちの頭の中には、いまだに 「日教組」 とか 「共産主義」 などという冷戦時代の亡霊が、そっくりそのままの姿で徘徊しているらしい。いったい、いつの時代に生きていらっしゃるのだろう。 大衆の受容能力はひじょうに限られており、理解力は小さいが、その代わりに忘却力は大きい。この事実からすべて効果的な宣伝は、重点をうんと制限して、そしてこれをスローガンのように利用し、その言葉によって、目的としたものが最後の一人にまで思い浮かべることができるように継続的に行われなければならない。 人々がこの原則を犠牲にして、あれもこれも取り入れようとすると、すぐさま効果は散漫になる。というのは、大衆は提供された素材を消化することも、記憶しておくこともできないからである。それとともに、結果はふたたび弱められ、ついにはなくなってしまうからである。「わが闘争」 より
2009.08.23
コメント(6)
-
地震についてつらつら
大量の情報が光速でやり取りされるこの時代にあっては、ずいぶんと間の抜けた何周も遅れた感想ではあるが、先週11日に、静岡でけっこう大きな地震が起きていた。最大震度は6弱、マグニチュードは推定で6.5と報道されている。 日本が地震大国であることはだれでも知っているが、記録に残っているもっとも古い地震というのは、日本書紀に載っている允恭天皇の時代、西暦416年のことだそうだ。允恭天皇は仁徳天皇の息子であり、さらにその息子が雄略天皇ということになっている。このあたりの天皇は、多くの研究者によって、中国の史書に記載された讃・珍・済・興・武といういわゆる 「倭の五王」 に比定されているが、はっきりいって、どこまで信用できるかはなんともいえない。 二番目の記録は推古天皇、つまりは聖徳太子の時代でもある599年らしい。聖徳太子についてもあやしげな伝承が多く、実在を疑う説もあるようだが、地震については書紀に 「地動。舎屋悉破。」 と前よりも詳しく書いてある。なので、素人判断ではあるが、この記述はたぶん信用できるだろう(参照)。 時代はずっと下るが、平安末から鎌倉初期にかけて生きていた鴨長明の 『方丈記』 には、1185年に近畿を襲った大地震について、下のように記述されている。ときは、平家が滅んだ壇ノ浦の合戦から4ヶ月後。長明は触れていないが、なにしろ幼子であった安徳天皇や、その他の多くの平氏一門が海に沈んで間もないときだから、おそらくは京の都中が、「たたりじゃ、たたりじゃ」 の声で大騒ぎだったことだろう。 また、同じころかとよ、おびただしく大地震ふることはべりき。そのさま世の常ならず。山はくずれて川をうづみ、海はかたぶきて陸地をひたせり。土さけて水湧きいで、いわを割れて谷にまろび入る。渚こぐ船は浪にたゞよひ、道いく馬は足の立處をまどはす。都のほとりには在々所々、堂舎塔廟、ひとつとしてまたからず。あるは崩れ、あるはたおれぬ。塵灰たちのぼりて、さかりなる煙のごとし。 地の動き、家の破るる音、雷にことならず。家のうちにおれば、たちまちにひしげなむとす。走り出づれば、また地割れさく。羽なければ空をも飛ぶべからず、龍ならばや、雲に乗らん。恐れの中に、恐るべかりけるは、ただ地震なりけりとこそ覚えはべりしか。 平安末期から鎌倉初期といえば、源平の合戦から義仲と義経、義経と頼朝という源氏の内輪もめ、さらに北条氏によって将軍の座からむりやり降ろされた二代頼家から三代実朝と相次いだ将軍暗殺、最後は執権として実権を握った北条氏と、和田義盛など他の御家人とによる権力闘争など、幕末維新もまっさおなくらいに、血で血を洗う争いが絶えなかった時代である。 中でも、歌人としても名を知られており、北条氏の陰謀に巻き込まれるかのように、無残に殺された頼家の子公暁(実朝にとっては甥になる)によって、父の仇として惨殺された、頼朝の血をひく最後の将軍実朝は、日本史における三大悲劇人の一人といってもいいだろう(あとの二人は考え中。候補者が多すぎて困っている)。 なにしろ、実朝については、戦前には小林秀雄の 「実朝」、小説では 「平家ハ、アカルイ、...... アカルサハ、ホロビノ姿デアラウカ」 との文句で有名な太宰治の 「右大臣実朝」 があり、戦後のものでは吉本隆明の 『源実朝』 もある。史学や和歌に関する専門的な研究者による論文・研究の類ならば、それこそ山のようにあるだろう。 吉本のまとめを借りると、鎌倉時代の歴史書である 『吾妻鏡』 には、実朝が13歳で将軍についてから鶴岡八幡宮で横死するまでの16年間に、鎌倉では大小含めて35回の地震が記録されている。そのうちのひとつで、現在確認されている地震は、建暦3年5月21日(1213年6月18日)におきたもので、マグニチュード6.4と推定されているということだ。ちなみに、『吾妻鏡』 にはこのときの地震について、「音有って舎屋破壊す。山崩れ地裂く。」 と記されている。 なお、数年前に亡くなった人だが、比較神話学を専門とする大林太良は、『神話の話』(講談社学術文庫)の中で、地震の原因に関する神話について次のように分類している。一 大地を支えている動物が身動きすると地震がおきる。 a 世界牛(大地を支えている巨大な牛のこと)が動くと地震がおきる。 b 世界をとりまく、あるいは支える蛇が動くと地震がおきる。 c 世界魚が動くと地震がおきる。二 大地を支える紙あるいは巨人が身動きすると地震がおきる。この特殊な形式としては、縛られた巨人が身動きして地震をおこすという神話や信仰がある。三 世界を支える柱あるいは紐を動かすと地震がおきる。四 男女の神あるいは精霊が性交すると地震がおきる。五 地震がおきると人々は「われわれはまだ生きている」と叫んで、地震をおこす祖先や神の注意を喚起して、地震をやめさす。 と、ここまで書いていたら、ついさきほどまた地震があった。瞬間的にぐらっと揺れただけであったが、数分後に、震度3というテロップがテレビ画面に流れた。前日から続く深夜にも地震があったそうだが、こちらのほうはぜんぜん気づかなかった。福岡は地震の少ないところといわれていたのだが、どうやら4年前の西方沖地震以来、平野の中央から玄界灘の沖まで伸びている断層が活動期にはいっているようだ。 4年前の地震が起きたのは朝の11時頃であった。日頃の習慣でまだ寝ていたのだが、がばっと跳び起き、部屋をすべてまわり、大事がないことを確認してからまた寝たのだった。昼頃になって、同じ市内に一人で住んでいる父親から 「手伝いに来てくれ」 との電話を受けた。 こっちはたいしたことなかったから、向こうもそうだろう、たぶん歳をとってるし、日頃地震などなかったから動転してんだろうなどとのんきに出かけたら驚いた。部屋に入ると本棚も食器棚も倒れ、部屋中に書籍やノート、食器類が散乱し、おまけにテレビまで床の上で胡坐をかいていた。 すぐ近くにあった寺の塀は全壊していたし、マンションの壁にもあちこちひびが入っていた。父親の住んでいたマンションはちょうど断層の真上にあったため、局所的に揺れが大きかったらしい。数日後、海岸沿いの埋立地にある図書館に行ってみたら、こっちもあちこち敷石やタイル、レンガが浮いていた。地震の揺れというのは震源からの距離だけでなく、地盤によってもずいぶんと違うものだなと痛感したのであった。 さいわいにして、父親は別の部屋で寝ていたので、落下した書籍に埋もれるということはなかったのだが、今回の静岡地震では、部屋の中に天井まで平積みにしていた大量の雑誌や書籍が崩れて、女性がひとりなくなっている。わが家にも大量の本があって、壁にスチールの本棚を3つ並べた横で毎日恐怖に怯えながら寝ている。 というのは嘘だが、4年前の地震でさっさと二度寝して以来、すっかり同居人の信頼を失い、「今度なにかあったら、あんたは一人でさっさと逃げるんでしょ」 などと、毎日のように責められているのは本当である。
2009.08.18
コメント(2)
-
「反日」なる言葉について
最近というわけでもないが、一部の 「右派」 勢力や団体、政治家らによって 「反日」 なる言葉がしきりと使われている。いわく、「反日国家」、「反日サヨク」、「反日マスコミ」、「反日外国人」 などなど、その使用例は、まことに枚挙に暇がない。 たとえば、西尾幹二や渡部昇一のような 「学者」 や、彼らを信奉する者らに言わせると、中国や韓国、北朝鮮は 「反日」 国家であり、在日韓国人・朝鮮人らは 「反日」 外国人なのだそうだ。また、日教組や朝日新聞は「反日サヨク」であり、男女平等やDVについての啓蒙活動、性教育、差別の禁止や人権の保護などを訴えている人らもみな、「反日」 勢力なのらしい。 彼らによれば、戦後のGHQによる占領と東京裁判、さらには日本国憲法制定によって、神武天皇の即位以来、2600年の歴史を持つ日本の古きよき伝統は破壊されたということだ。戦後の占領政策は、なにより日本と日本人を無力化することを目的としており、そのために様々な陰謀が企まれ、実行されてきたのだそうだ。それは、たとえば連合軍内に潜んでいたコミンテルンのスパイと、戦後解放された日本の左翼勢力の協力によって進められたということのようだ。 戦後の日本社会に、ハリウッド映画やアメリカ製のドラマが氾濫し、さまざまなスポーツが盛んになり、また 「性の解放」 が進んだのも、「スクリーン、スポーツ、セックス」(3S政策というらしい)の三つを与えることで、日本人を愚昧化させようという連合国の陰謀なのだそうだ。また、学校給食にパンが導入され、それまでのコメにかわってパン食が普及するようになったのも、一部の 「識者」 によると、日本人の食生活の破壊をつうじて、家庭の破壊と日本人の弱体化をもくろんだ 「反日」 勢力の陰謀なのらしい。 ようするに、そのような人らに言わせると、核家族化と少子化が進行して伝統的な家族制度が崩壊したのも、街中にポルノが氾濫しているのも、「反日」 勢力のせいということになる。オタクや 「引きこもり」 が増えているのも、「メイド喫茶」 とかが流行っているのも、教員や公務員のモラル低下が指摘されるているのも、つまりは戦後60年にわたって続けられてきた、そのような 「反日」 勢力の陰謀のせいであり、その成果ということになるのだろう。 いまや、彼らはいたるところに 「反日」 勢力の陰謀をかぎつけている。「反日」 なのはなにもサヨクや一部アジア諸国だけではない。創価学会と公明党もまた、自民党に取り入って日本の国家と社会の破壊を企む 「反日」 カルト集団なのだし、「日の丸」 をおったてて、大音量で軍艦マーチなどを流している 「街宣右翼」 もまた、実は 「在日朝鮮人」 らに操られ、真正右翼のイメージダウンを狙って活動している 「反日」 勢力なのらしい。 最近ではすっかり凋落したとはいえ、近隣諸国との協調を主張する自民党内のリベラル派も、隠れ 「反日サヨク」 なのであるし、「夫婦別姓」 や 「外国人参政権」 に積極的な社民党や民主党については、言わずもがなだろう。日本の社会には、いまやありとあらゆるところ、毛穴のすみずみにまで 「反日」 勢力は潜んでいるのである。これは、まことにたいへんな由々しき事態なのである。 世界も日本の国内も 「反日」 勢力だらけである。われわれはついに目覚めた。新聞もテレビも、「マスコミ」 はすべて 「反日」 勢力によって牛耳られている。大学などの教育機関もそうである。したがって、そのようなものを信じてはならない。「真実」 はなによりもネットの中にある。というわけで、いまや連日連夜、彼らはネット上のあちこちの掲示板で情報を交換し、ブログや掲示板を使って 「真理」 の普及に日夜励んでいるというわけだ。 これは、カフカもびっくりするような、ほとんど不条理な世界である。しかし、いたるところに 「反日」 勢力の暗躍を見出している彼らが守ろうとしている 「日本」 とは、いったいなんなのか。それがさっぱり分からない。それは、白砂青松の自然豊かな日本なのか。それとも、能楽や狂言などの伝統芸能や、和歌や俳句、「源氏物語」 のような、「もののあはれ」 や 「わびさび」 にあふれた世界なのだろうか。 近代史をひもとけば、「反○○」 運動というのはあちこちにある。ガンディーが指導したのは 「反英」 独立運動であったし、中国や朝鮮では日本の侵略に対する 「反日」 運動も行われた。戦後のインドシナの抵抗は 「反仏」 から 「反米」 にかわったし、インドネシアの場合は 「反蘭」 運動ということになる。日本でも、戦後の米軍による占領や基地に対する抗議活動などが、「反米」 闘争と呼ばれたことがある。 これらの運動は、すべて具体的な内容と目標を持った、具体的な運動ばかりである。したがって、そこで使われている 「反○○」 なる言葉も、当然ながら具体的な意味、言い換えると明確に限定された意味を持っている。しかし、現在使われている 「反日」 なる言葉は、これとまったく異なっている。それはただの恣意的なレッテルにすぎす、具体的に限定された意味内容を持っていない。 むしろ、それはすでに見てきたように、現在の日本がかかえる様々な問題の 「根源」 であり、現代における 「根本悪」 として一括して名指しされた、想像上の 「敵」 の名称でしかないように見える。しかし、現代社会の複雑な問題が、すべてある特定の勢力や、ただひとつの原因によって生じていると考えるのは、きわめて粗雑な問題の単純化でしかない。そこからうかがえるのは、社会全体を見通すと同時に、個別の問題をひとつひとつ整理するという能力の完全な欠如であり、おのれの知的無力と無能の告白ということになるだろう。 結局のところ、彼らはおのれが敵視した相手に 「反日」 なるレッテルを貼ることで、自分たちが抱いている 「日本」 または 「日本人」 なるものとその価値を確認しているにすぎぬように見える。つまり、これは論理が逆なのであり、他者に対して 「反日」 なる本来は対抗的でしかないレッテルを貼ることによって、はじめて 「日本」 と 「日本人」 なるものを確認するという、逆転した自己確認の言葉にすぎぬように思える。 言うまでもないことだが、日本人を親とする、生まれながらの日本人が日本人であることには、なんの対価も努力もいらない。だから、「日本」 や 「日本人」 なるものを価値とするならば、これまた本人にとって、なんの努力も代償もいらないきわめて手軽な価値だということになる。なにしろ、それにはただ 「自分は日本人だ!」 と叫びさえすればよいのだから。 しかし、それでは、どの日本人も等価ということになる。それでは、あまりに虚しかろう。そもそも価値とは差異の体系であるから、自己と他者を差別化できなければ意味がない。それに事実はそれだけでは価値とはならない。たんなる事実を価値とするものはやはり基準であり規範であるから、なんらかの価値基準が必要である。そこで引っ張り出されるのが、「真の日本」 であり 「真の日本人」 ということになる。だが、それはいったいなんなのか。やはり、わけがわからない。 しかし、空疎な価値といえども、走り続ける自転車のように、たえずそこに差異を持ち込むことによって維持することは可能かもしれない。だから、彼らは自己が敵とみなしたものに対して、次々と 「反日」 なるレッテルを貼っていかねばならない。つまり、彼らが自らの価値観の基準としているであろう 「日本」 と 「日本人」 なる価値は、国家や社会の外部だけでなく、内部においても「反日」 的なものを見つけ出し、次々にそういうレッテルをはることによってしか維持できないということになる。 彼らにとっては、「日本」 と 「日本人」 なるものは、なによりも相対化できない絶対的価値でなければならない。だが、そのためには、「日本」 や 「日本人」 なるものを具体的に措定することは禁止されねばならない。なぜなら、具体化とは限定化と同義であり、限定化されたものはいずれは相対化をまぬがれないからだ。 彼らのいう 「反日」 なるものが、つねに恣意的なレッテルでしかないのは、おそらくそのためでもあるだろう。彼らにとっての 「日本」 と 「日本人」 なるものが、いつになっても具体的で明確なものではありえぬのは、まさに理の必然なのである。 むろん、いうまでもなく、自己認識は他者を鏡とすることによって得られるものである。だが、最初に空疎な 「日本」 なるものを価値基準とすることで得られる彼らの他者認識は、当然ながら虚偽の認識でしかない。したがって、「反日」 なるレッテルによる反照として得られた彼らの自己認識は、結局のところ当初の空疎な自己認識をただ再確認するものでしかないということになる。つまりは、自分の尻尾に噛み付いているヘビのような話である。
2009.08.10
コメント(10)
-
今年は16年ぶりの冷夏となるか
八月にはいっても天候はすぐれぬ。熱帯夜にはならぬから、寝苦しさに悩まされぬのはよいが、強い日差しや高温を必要とする作物を育てている農家や、海岸での 「海の家」 を経営しているような方々にとっては、いささか頭の痛い夏となりそうだ。 冷夏といえば、今から16年前にもあったことで、その年には米が著しい不作となり、タイ米や米国のカリフォルニア米などが大量に輸入される騒ぎとなった(参照)。タイ米は日本の米と種類が違ってねばりがないため、世間ではあまり人気がなかったようだが、わが家のような貧乏家庭にとっては、ただ安いというだけでありがたかったものである。 さて、夏といえば花火である。こちらでも先週末に恒例の花火大会があった。子供が小さかったときは、自転車の後ろに乗せて連れて行ったものだが、もはやそのような元気もない。というわけで、テレビ中継で我慢したのだが、テレビの画面でドンとなると、それから10数秒ほどおくれて同じドンという音が窓の外から聞こえてくる。ドドドン、パラパラパラという連発花火がテレビ画面であがると、同じドドドン、パラパラパラという音が、やはり少しおくれて窓外から聞こえてくる。 先日、アポロが月に残してきた、着陸船の土台らしき姿を写した月面の画像が公表された。それでも、まだアポロは月に行っていないとか、あの映像は偽造だとか言い張る人も一部にはいるようだが、今回の花火大会に関しては、画面からの音と寸分たがわぬ同じ音が10秒遅れで外から聞こえてきたので、これが偽装や合成でないことは十分に明らかである。 ところで花火というものは洋の東西を問わず、おめでたいときに打ち上げられるものらしい。花火の場面を写した映画にもいろいろあるだろうが、有名なのは半世紀も前にポーランドの映画監督アンジェイ・ワイダが撮った 「灰とダイヤモンド」 の一場面であろう。 ときは、1945年5月、すでにポーランドはソビエトの手によってナチスの占領から解放されていたのだが、ナチと入れ替わるようにして進軍してきたソビエト軍による実質的な占領下で、共産党による支配が着々と強化され、それに対し、大戦中にロンドンに避難していた亡命政府を支持するグループによって、共産党支持派へのテロが頻発していた時期である。 原作であるアンジェイエフスキという人の小説とは少し違うのだが(ただし、映画の脚本には原作者も参加している)、映画での主人公であるマーチェクという青年は、自分の息子が反革命グループのメンバーとして逮捕されたという報を聞いて警察署へ向かうシュツーカという党地区委員長の先回りをし、後ろから足早に近づいてくる男に対して、振り向きざまにピストルを数発発射する。 撃たれた男はよろめきながらマーチェク(youtubeで久しぶりに見たのだが、この俳優はなんだか若い頃の加藤茶に似ている)のほうへ歩み寄り、そのまま彼によりかかる。よりかかられたマーチェクは、思わず両手を出して彼を抱きとめてしまう。そこへちょうど、連合国に対するドイツの全面降伏を祝った祝勝花火が打ち上げられるという場面である。ただし、向こうの花火は日本と違って、空で丸く破裂はしない。地上から火花が宙へ打ち上げられ、そのまま柳の枝のようにゆっくりとたれ落ちてくる。 さて、ずいぶんと昔のことだが、この映画について、30年以上前に亡くなった評論家の花田清輝はこんなことを書いている。 本来、わたしは、ワイダの熱っぽく描いているような青春に特有のナルシズムに対しては、きっぱりと対立しなければならないと、とうの昔からおもいこんでいるのである。にもかかわらず、わたしは、事、志に反して、昨年度の 『キネマ旬報』 のベスト・テンの第一位に、つい、うっかり、ワイダの監督した 『地下水道』 をえらんでしまったのだ。... 政治は、燃え上がり、燃え朽ち、すでにひとにぎりの灰と化しさっているにもかかわらず、なお、自分を一個のダイヤモンドと思い込まないではいられないような人間の手にかかると、すこぶるメロドラマチックな様相をおびてくる。しかし、現実の政治は、革命や抵抗の場合であってもひどく散文的なものではなかろうか。「無邪気な絶望者たちへ」 より 上に引用した文からもわかるとおり、花田という人は、深刻ぶった顔つきやナルシズム、センチメンタリズムが大嫌いだった人である。花田もいうとおり、たしかに 「現実の政治は、革命や抵抗の場合であってもひどく散文的なもの」 であろう。にもかかわらず、ついつい同じワイダのワルシャワ蜂起を描いた 『地下水道』 を第一位に選んでしまったというのは、そういう花田の奥底にあった心情というものが、思わずぽろりと出てしまったということなのかもしれない。 花田といえば、吉本との論争でも有名である。どちらの肩を持つかは、とりあえず人それぞれである。花田の肩を持つ人の中には、同郷のよしみで中野正剛率いる東方会と関係のあった花田を、吉本が 「転向ファシスト」 と呼んだことを問題視する人もいるようだが、花田だって戦中世代である吉本をファシスト呼ばわりしたのだから、それはお互い様というものだ。 ただ、すでに 「前衛党」 神話や、世界を 「社会主義」 圏と資本主義圏による東西対立として捉える認識から抜け出ていた吉本のほうが、いまだそのような認識を軸としていた花田よりも、一日の長があったということは言えるだろう。もっとも、頭のいい花田であるから、ひょっとするとそういう認識も、本人としてはただの戦略のつもりだったのかもしれない。 たとえば、「わたしは、スターリン批判を、スターリン流の一国社会主義に終止符を打ち、ソ連における世界戦争に対する抵抗態勢を、世界革命に対する推進態勢にきりかえるためにおこなわれたものとして受け取った」 などという花田の言葉は、どうみても、当時の党の路線とはまったくちがう、当時はまだ悪魔扱いされていたトロツキストの言葉である。 また、「前近代的なものを否定的媒介にして近代的なものをこえる」 という彼の有名なテーゼも、読みようによっては、「後進国」 における二段階革命論を否定した、トロツキーの永続革命論の密輸入のように読めないこともない。 しかし、スターリン批判後に党を批判して、党から除名された若者らが主導する全学連を公然と支援した吉本と、どこか歯切れの悪かった花田との姿勢の差が、その後の二人の人気を分けたということは言えるだろう。60年代に吉本が多くの学生らに読まれ、「教祖」 とまで呼ばれるようになったのは、なによりもそういう吉本のどことも妥協せぬ姿勢が支持されたからであり、論争でどっちが勝ったとか負けたとかいうこととは、たぶんあまり関係ない。 花田という人が頭のいい人であったことは言うまでもない。ただ、その頭の良さのために、彼にはしばしば、自分だけ大所高所に立ったがごとき、机上の戦略を語りたがるという癖があったようだ。なにかといえば、「前近代的なものを否定的媒介にして近代的なものをこえる」 とか、「大衆的芸術を否定的媒介にした芸術の総合化」 といったスローガンをぶち上げたがるのもそうだろう。 戦中世代である吉本をもっとも怒らせたのは、「戦争中、戦争の革命へ転化する決定的瞬間を、心ひそかに持ち続けてきたわたしは、あまりにも早過ぎた平和の到来に、すっかり、暗澹たる気持ちにならないわけにはいかなかった」 という、「戦後文学大批判」 の中での言葉だろうが、花田にすればこれもただのイロニーに過ぎなかったのかもしれない。 しかし、沖縄の壊滅から特攻隊の召集、二発の原爆投下からソビエトの参戦にまで至り、日ごとに膨大な死者が出ていた当時の状況を考えてみれば、これはやはり無責任な放言といわざるを得まい。同世代に多くの死者をもつ吉本が怒ったのは、当然すぎるほど当然な話である。 党に対して面従腹背の気味もあった花田が、60年安保闘争を全力で戦った当時の全学連を指導した共産主義者同盟の解体をまるで待っていたかのように、構造改革派(小泉の構造改革とは全然関係ない)と呼ばれた、社会主義革命を主張する当時の共産党内の左派グループとともに集団で除名されたのには、なにやら 「策士、策におぼれる」 とか 「巧兎死して走狗煮らる」 といった感がしないわけでもない。 つまるところ、頭の良すぎた花田に欠けていたのは、良くも悪くも鈍牛のようにしつこい吉本の粘り強さということになるだろう。福岡生まれの花田はいかにも九州人らしい旗振りが好きないっぽうで、典型的な都会的モダニストでもあったが、天草生まれの船大工だったという祖父をもつ吉本のほうは、東京生まれでありながら、いくつになってもどこか田舎臭さの抜けない人でもある。
2009.08.05
コメント(2)
-
雨降って地は固まるか
先週、天上で行われた太陽と月との戦いは、一時間足らずでぶじに太陽の勝利に終わった。といっても、事前にきちんと時間を調べていたわけでもなく、たまたま入っていた大型スーパーから出たところ、なんとなくあたりが暗くなっており、おまけに外に立っている老若男女のみなさんが、そろいもそろって天の一ヵ所を見上げているのをみて、そういえば今日は日食の日であったなあ、と気づいた始末ではあったが。 しかし、せっかくの日食もずっと観察できたわけではなく、ごく短時間だけ、あつい雲の合間から、ネズミにかじられたようなご尊顔が垣間見えるという程度にすぎなかった。そういうわけで、そのときからすでに予兆はあったわけだが、それから数日もたたぬうちに大雨となった。県内では数ヶ所で山崩れもおきていて、たいへんなことになっていた。 雨がやんでから、近くの川まで行ってみたところ、すでに水かさこそ引いてはいたが、まだ濁った水がとうとうと流れていた。雨の激しかった時刻には、おそらく川に沿った遊歩道にまで水があふれていたのだろう。川原に繁茂する草の類もすっかり流れになぎたおされ、粘土のように細かな泥が一面にべっとりとこびりついていた。しばらく眺めていたが、残念ながら大きな桃は流れてこなかった。 「司馬遷は生き恥さらした男である」 と書いたのは武田泰淳だが、その司馬遷が書いた『史記』 の西南夷列伝に、夜郎という名前の国の話がでてくる。場所はミャンマーやラオス、ベトナムと国境を接し、ミャオ族やイ族など多くの少数民族が住む、今の中国の貴州省や雲南省のあたり。時代は紀元前2世紀から1世紀、司馬遷を宮刑に処した当人である漢の武帝が統治していたころのこと。 西南夷の酋長の数は十をもって数え、そのうち夜郎国が最大である。その西方の夷族はびばくの類で、その数も十ほどあり、そのうちてん国が最大である。てんから北にも、酋長の国は十ほどあり、そのうち、きょう都が最大である。これらはみな頭髪を椎の形に結び、田を耕し、村落をつくっている。...以上はすべて巴・蜀の西南の外辺に居住する蛮夷である。 で、この夜郎国に漢の使いがはじめて到来したとき、夜郎国の王は 「漢とわが国とでは、どちらが大きいか」 と問うたという。司馬遷によれば、「道が通じていないので、てん王も夜郎候も、おのおのみずから一州の君主だと思いこみ、漢の広大さを知らなかったのである」 ということだ。ここから、広い世間のことをしらずに、自分がいちばん偉いと慢心している者の態度をさす、「夜郎自大」 という言葉が生まれたという。 さて選挙が近くなってくると、ネット上もいろいろと大騒ぎである。あるブログでは、現在の自公政権を批判するついでに、「ソン・テジャクこと大作大先生率いる朝鮮カルト『創価学会』」 などというあきれたキャンペーンをやっている。 公明党を批判するのなら、その政策と政治手法を問題にすべきである。創価学会を批判するのなら、その教義や社会的集団としての振る舞いを批判すればよい。「池田大作は在日朝鮮人出身だ」 などというネット上のあやしげな風説にのっかって、「創価=朝鮮カルトだ」 などと言い出すのは、おのれの排外的な差別思想をダダ漏れにしているにすぎまい。 かのブログの主は、日頃から 「マスコミの嘘にはだまされないぞ!」 とか 「政治家や官僚にはだまされないぞ!」 などと、さかんに力みかえっているようだが、そのかわりに、9.11陰謀論からユダヤやフリーメーソンの陰謀論まで、ありとあらゆる陰謀論にどっぷりとはまり込んでいる。彼によれば、明治維新はフリーメーソンの陰謀であり、孝明天皇も皇女和宮の婿さんだった徳川家茂も、その陰謀によって殺された疑いがあるということらしい。 それなりに長いはずの人生の中で、彼がどういう経験をし、その結果、今なにに腹をたて、なにに怒っているのかは知らぬ。だが、そうやって、世の中の様々な 「悪」 を体験し、その原因について考えているうちに、どうやら、あれやこれやの 「陰謀組織」 の存在に思い至ったらしい。だが、それでは、テレビで悪の組織 ショッカーと戦う、正義の味方 仮面ライダーや、黄色いマントをひるがえした月光仮面の姿に興奮していただろう、小学生の頃からぜんぜん進歩していないではないか。 世の中に、邪悪な意思によって統率された、ただ悪意だけにみちた組織が存在しており、その隠れた意思によって、社会や世間の人々が操作されていると考えるのは、典型的なカルトの思考である。総選挙に出馬して、あえなく 「惨敗」 したオウムもまた、そのように考え、見えない強大な敵と戦うために、サリンだのVXだのという 「毒ガス兵器」 を開発し、銃の製造に手を出したのではなかったか。 おのれを無垢で純粋な 「善」 とみなし、おのれの外部に純粋な 「悪」 が存在するというマニ教的二元論にもとづいた 「陰謀論」 的思考は、差別的で排外的な思考とも、きわめて親和的である。おのれがカルト的思考にどっぷりつかっておきながら、他人を 「カルト」 呼ばわりするとは、片腹どころか両方の腹が痛くなってくる(「片腹痛し」 の語源は、もちろん、「そばにいたくない」 という意味だが)。 詐欺でも催眠術でも、自分は絶対に騙されないなどと思っている人間ほど、いざとなるところりと騙されるという。オレオレ詐欺にだまされるのが、世の中の動きに遅れた高齢者や、世間知らずの 「田舎者」 だけだなどと思っていたら大間違いだ。そんなにだまされたくないのならば、だまされないようにいろいろと学べばよろしい。「おれは絶対に騙されないぞ!」 などと力みかえったあげくに、最低最悪のがせねた(参照)にだまされ、踊らされていたのでは笑い話にもならない。 「ものを知らぬ」 ことは恥ではない。ものを知らなければ、知るための努力をすればよい。恥ずかしいのは、「ものを知らぬこと」 を言訳として、「ものを知らぬこと」 に居直り、「ものを知る」 努力をしようともしないことだ。「論語」 には 「思いて学ばざればすなわちあやうし」 という言葉があるが、そこからただの 「夜郎自大」 までは一直線である。 ヘロドトスの 『歴史』 には、現在のトルコ東部からイラン一帯を支配していたメディアと、トルコ西部にあったリディアの二つの王国の長年の争いが、日食をきっかけに和平に向かったという話がある。岩波文庫の注によれば、このときの日食は紀元前585年5月28日のものではないかということだ。 「リュディア、メディア両軍とも、昼が夜にかわったのを見ると戦いをやめ、双方ともいやがうえに和平を急ぐ気持ちになった」 とヘロドトスは書いているが、それが事実であるならまことに喜ばしいことだ。 先日の日食では、ガンジス川のほとりに集まった老若男女、善男善女のみなさんが、天を見上げて祈りを捧げている姿が映っていた。その姿は真剣そのものだったが、彼らとて、もはや日食ごときで、「世界の終わりだ!」 とまで思い込み、泣き叫びはすまい。 暦もなく、天文学も発達していない時代であれば、いきなり太陽が暗くなり、昼が夜に変わったりすれば、それこそこの世の終わりかというような騒ぎになっても不思議はない。神の怒りを解くために、いけにえを捧げたりした時代もあったかもしれない。 さいわいにして、日食は1時間もすれば元に戻るものではあるが、そのような不安が解消されたのも、いうまでもなく科学の発達と普及のおかげである。世の中には、「科学教」 などというものと戦っているらしき人もいるようだが、そういう勝手につくりあげた妄想に駆られて、風車に突っ込む前に、すこしはおのれの姿を省みてはどうだろうか。だまされないために必要なことは学ぶことであって、ただ力みかえることではない。
2009.07.28
コメント(3)
-
恐妻家と愛妻家のはざまで
世界の三大恐妻家といえば、一番はなんといってもクサンチッペを妻としていたかのソクラテスだろう。ディオゲネス・ラエルティオネスの 『ギリシア哲学者列伝』 によれば、家業をほったらかしては、人を集めて分けの分からぬ議論ばかりやっていたために、彼は腹を立てたクサンチッペから街頭で水をぶっかけられたり、着ているものをむりやり剥ぎ取られたりしたという。 二番目はというと、ロシアの文豪トルストイということになるだろう。人道主義者として知られるトルストイは、全財産を慈善のために放棄しようとして妻と争いになり、家出の途中に汽車の中で熱を出し、おりた駅でそのまま亡くなったという。もっとも、享年は82歳というのだから、すでに十分に生きたといっていいだろう。彼が亡くなった駅は、その後その名前をとってレフ・トルストイ駅と改名されたそうだ。 クサンチッペもトルストイの奥さんも、世間では夫の仕事や才能を理解できなかった 「悪妻」 の典型のようにいわれている。しかし、富士だって優美なのは遠くから眺めている限りのことであり、近くによってみればごみや石ころが散乱したただの山である。夏目漱石も、小宮豊隆などの弟子からは 「則天去私」 を絵に描いた偉人のように言われているが、一緒に暮らしていた奥さんに言わせれば、ただの癇癪もちである。 こういうことには、キリスト様も頭を痛めたらしく、マルコの福音書によれば、故郷のナザレに帰って説教をしたさい、昔からの知り合いとかに 「あいつは大工ではないか、マリヤの息子ではないか」 と嘲られたあげく、いつものような奇跡をおこなうこともできず、結局 「預言者が敬われないのは、自分の故郷、親戚や家族の間だけである」 というすて台詞をはいて立ち去ったという。 トルストイの家出をめぐっては、戦前に当時まだ気鋭の評論家であった小林秀雄と、彼より20歳以上年長の明治の小説家 正宗白鳥との間で有名な論争がおきている。ことの発端は、正宗白鳥が 「トルストイについて」(岩波文庫 『作家論』 に所収)という短文の末尾で、次のように書いたことにある。 二十五年前、トルストイが家出して、田舎の停車場で病死した報道が日本に伝わったとき、人生に対する抽象的煩悶に堪えず、救済を求めるために旅に上がったという表面的事実を、日本の文壇人はそのままに信じて、甘ったれた感動を起こしたりしたのだが、実際は細君を怖がって逃げたのであった。 人生救済の本家のように世界の識者に信頼されていたトルストイが、山の神を恐れ、世を恐れ、おどおどと家を抜け出て、孤往独遇の旅に出て、ついに野垂れ死にした径路を日記で熟読すると、悲愴でもあり滑稽でもあり、人生の真相を鏡にかけてみるごとくである。ああ、我らが敬愛するトルストイ翁! これに対し、小林は 「作家の顔」 の中で、「偉人英雄に、われら月並みなる人間の顔をみつけて喜ぶ趣味が僕にはわからない。リアリズムの仮面をかぶった感傷癖に過ぎないのである」 と書いて、激しく噛み付いた。 「あらゆる思想は実生活から生まれる。しかし生まれて育った思想がついに実生活に決別するときが来なかったならば、およそ思想というものになんの力があるか」 と書いた、若き小林の啖呵はなかなかのものである。小林がいうとおり、生活から生まれぬ思想はただの空疎な借り物にすぎぬが、生活べったりの思想には意味がない。 思想は生活から生まれるものだが、それが思想となったとき、必然的に生活からは乖離せざるをえない。そのような乖離に気づいてない者がいるとすれば、それはその人の思想がただの借り物にすぎないからだ。乖離自体が問題なのではない。乖離しているからこそ、そこに現実との緊張感も生まれる。問題なのは、そのような生活からの乖離という自覚もなしに借り物の思想を振り回すことだ。今も昔も、あっちからこっちへと、ただ軸を変えただけで、なかみの変わっていない 「転向」 は、そこから生まれる。 ただし、白鳥の言いたかったことはそういうことではない。白鳥の文章を読めば分かるが、白鳥が嘲笑したのは、偉人の行いとあれば、たとえ屁をここうが、立小便をしようが、どんなことでもありがたがる者らの俗物性なのである。なので、この論争はまったくかみ合っていない。白鳥は小林が言うように、なにもトルストイを 「月並みなる」 俗物のレベルに落とし込んで喜んでいるわけではない。 ただ、それはそれとして、小林の書いていることには、まったく意味がないわけでもない。論争というものの評価が難しいのは、今も昔も変わらない。当事者の一方のみが後世に伝えられたりした場合などは、とくにそうだ。この論争でも、小林がのちに 「批評の神様」 と偶像化されるようになり、その文章が今も読まれているのにくらべると、白鳥のほうは分が悪い。白鳥に言わせれば、大見得をきった小林の啖呵など、「当たり前じゃないか」、「意味のない空言になるのではあるまいか」 ということになる。 さて、三番目の恐妻家はだれかというと、いくつか説があるようだ。ぜいたくで有名なジョゼフィーヌを妻とするナポレオンだという説もあるし、ねねを正室とした秀吉だという説も一部にはあるようだ。ただし、秀吉の場合、日本の恐妻家としては文句ないが、やはり世界的にはさほど有名でないというのが難点だろう。 むしろ、ここではマルクスを有力な候補としてあげたい。マルクスの妻はイェニー・フォン・ヴェストファーレンといって、彼より4歳年上の貴族の家の娘である。ドイツ人で名前に 「フォン」 がつくのはそれだけで偉いのだが、イェニーの兄はドイツ統一前のプロイセンで大臣を務めてもいるのだから、なかなかの 「家柄」 である。 マルクスは、イェニーが嫁入りのときについてきたお手伝いさんに、フレデリックという息子を生ませている。これはむろん妻であるイェニーの目を盗んだ行為であろうが、生まれた子はエンゲルスの子ということにされ、エンゲルスは死ぬ間際になって、ようやく周囲に真相を打ち明けたという。これなどは、まさにマルクスの恐妻家ぶりをあらわすエピソードといっていいだろう。白鳥がこれを知ったならば、なんと言っただろうか。 さて、先週の都議選をうけて、いよいよ麻生首相が解散を決断したらしい。あの結果では、地盤の弱い議員らが浮き足立つのも無理はない。とりわけ、都を地盤にする議員としては顔面蒼白・驚天動地の思い、まさしく生きた心地もしないといったところだろう。 その意向をうけて、自民党内では大騒ぎのようだったが、結局不発に終わったようだ。実際、衆院の任期切れはもう目の前に迫っているのだから、解散をいつにしようがたいして違いはあるまい。その直前に党の顔を変えたところで、みっともないだけである。だいいち、それで総裁を選びなおし、国会でむりやり首班指名をやったところで、総選挙で負けたのでは目も当てられぬ。 史上最短の内閣は、ポツダム宣言受諾後の敗戦処理にあたり、54日間続いた東久邇宮内閣だそうだが、たとえいま麻生にかわって総理になったとしても、選挙で負ければそれでおわりである。そうなれば、2ヶ月続いた宇野内閣や羽田内閣どころか、「宮様内閣」 をも上回る、史上最短記録ということになる。いくら総理・総裁のいすが魅力あるものだとしても、そのような後世に恥を残すことになりかねない危険な賭けを、今この時期にあえてしようという酔狂者もいないだろう。 ようするに、中川・武部の両元幹事長や、そのしたにいる有象無象の議員らも、あえて自分で火中の栗をひろおうという度胸も覚悟もないままに、だれかをあてにした策謀ばかりやっているように見える。そもそも大将のいない戦など、戦にすらならない。これでは、へなへなの麻生や細田・河村といった面々にすら勝てるはずがあるまい。 巷間に伝わる予定では、21日解散で8月31日投票ということらしいが、とするとまさに夏休みの最中、夏のいちばん暑い盛りの中での選挙運動ということになる。こちらでは山崎拓などがそうだが、現職議員を含めて、立候補を予定している方々の中には高齢の人も多いようだから、ここはけっして無理をせず、くれぐれも自分の体調を考えて選挙戦に臨んでもらいたい。 実生活とはなれて飛行しようとするのが思想本来の性格であり、力であるからだ。こういう力の所有者であることが、人間を他の生き物から区別する一番大事な理由なのである。抽象の作業がもっとも不完全となり、その計量的性質がもっとも曖昧になると、思想は実生活の中に解消され、これに屈従するよりほかになすところを知らないようになる。これをぼくらは通常思想とは呼ばず、風俗習慣と呼んでいる。小林秀雄 「文学者の思想と実生活」
2009.07.18
コメント(5)
-
総選挙はいつになる?
6月は雨が少なくて、このままではどうなるかと思っていたら、7月に入ってからようやく雨が降り出した。やや季節遅れの梅雨というところだろうか。われわれの住む猥雑なる下界は、空一面に低く広がった落し蓋のような厚い雲で閉じ込められ、自ら放出した熱で自家中毒を起こしている。 雨の合間に外に出てみると、こないだまで輸入家具を扱っていた近くの倉庫のような建物が、いつのまにか、数年前に 「元気があっていい」 発言でいちやく全国に名をとどろかせた某議員の事務所に様変わりをしていた。きたるべき選挙に備えてということなのだろうが、アップになどしなくても十分にでかい顔だというのに、さらにその下に麻生首相の顔まで並べているのだから、暑苦しくてたまらない。9月に個人演説会を予定しているということだが、それはちょっとのんきすぎやしないかなと思ってしまった。 自民党内の内紛は、いよいよ末期的な様相を呈している。このままでは総選挙は戦えないとかで、一部からは総裁選前倒しという声も出ているようだが、その連中はようするに自分の首が心配なだけだろう。そもそも、小泉チルドレンなどと呼ばれる、前回の選挙で大量に当選した新人議員など、ほとんどが自分の力ではなく、小泉元首相の人気のおかげで当選したにすぎないのだから、一期だけでも議員を務められたことを天に感謝すべきである。 次も当選したけりゃ、人に頼らず自分の力で正々堂々と戦えばよろしかろう。この連中は、いったいなんのために、4年も議員を務めてきたのだろう。4年の間に自分がやってきたことに自信があるのなら、選挙も間近な今頃になって右往左往するのはあまりに恥ずかしいことだろう。首相ってのは、日本国の政治全体に責任を負っているのであって、君らの選挙のためにだけ存在しているわけではない。 しかし、そういう声を抑えなければならないはずの内閣官房長官まで、「表紙をかえても」 とか言い出す始末。おいおい、天下の首相をただの本の表紙扱いとは、さすがに失礼ではあるまいか。麻生おろしについて記者団に尋ねられた野田聖子消費者相は、「麻生さん以上に総裁にふさわしい人がいますか」 と答えていたが、まことにそのとおりである。 野田消費者相が反問したとおり、今の自民党には、もはや麻生さん以上に総裁にふさわしい人間がいないのであり、それこそがまさに今の自民党がかかえる最大の悩みなのだ。思わず、この人、にこやかな顔をして、なかなかこわいことを言う人だなと感心した。「笑って人を斬る」 とは、まさにこういう言葉のことをいう。 さて、話は変わるが、人はだれでも自分の立場を持ち、自分の考えというものを持っている。「知識社会学」の祖であるマンハイムは、「インテリゲンチャ」 というものを、「社会のために世界の解釈を準備することを専門の仕事している社会集団」 と規定し、近代においては 「従来の完全に組織化された閉鎖的な知識人階層にかわって、自由なインテリゲンチャが台頭してきている」 と述べている。 彼によれば、この 「自由なインテリゲンチャ」 は、社会において比較的階級色がうすく、「社会的に浮動する」 階層であるがゆえに、政治という舞台においてあい争う、階級的利害によって拘束された政治党派のもつイデオロギー的で部分的な 「党派的見方」 をこえた、社会に対する全体的総合という見方を可能にするのだそうだ。 しかし、そうはいっても、どんなに偉大な知識人であろうと、個人としてみるなら、みなそれぞれに固有の歴史と背景をもち、その中で意識的無意識的に形成された、固有の立場と固有の主義主張というものを持っている。だから、「党派的見方」 からまったく自由ということはありえない。客観的な証明が可能な科学ならざる人間の思想とは、ようするに選択された一定の立場のことであり、それはその良し悪しは別として、「偏向」 や 「バイアス」 ということと同義なのである。 たとえば、なにかの問題をめぐってどこかで論争がおきたりすると、人はだいたいにおいて、その相対立する二つの主張のうち、自分が共感するほうの意見を実際以上に自分にひきつけて読み、その逆に、違和の残る、なんとなく共感できない意見に対しては、自己がもつ日頃の 「敵意」 や 「反感」 を投影して、実際以上に敵対的なものとして読んでしまいがちなものである。 ネット上で公開で行われる議論というものは、基本的にだれでも参加できる 「バリアフリー」 なものであるから、そのような無用な 「対立」 が持ち込まれ、話がややこしくなってしまうのはどうしても避けられない。結局のところ、お互いとも、妙な 「押しかけ応援団」 などは無視して、対立しているかに見えるさまざまな意見の中から、ただの石ころと、そうではないダイヤとをふるいわけるという努力が必要なのではないだろうか。 社会的 「弱者」 や 「少数者」 などの他者支援運動というのは、「当事者」 である他者の総体をまるごと支援するものであって、自分の好みでもってふるいわけてはならない。しかし、人はどうしても、自分につごうのいい 「当事者」 の声のほうに耳を傾けがちなものであり、しかもそれを実際以上に自分に引き付けて読んでしまう。 だが、「当事者」 といっても、けっして一枚岩ではないのだから、そういうときは自分にとって違和の残る 「当事者」 の声にこそ、注意して耳を傾けるべきだろう。まかりまちがっても、頭の中で自分が作り上げた 「期待される当事者」 像に基づいて、「当事者」 を勝手に選別するようなことはしてはならない。 それまでの 「反ファシズム」 運動から180度転換した、スターリンとヒトラーによる独ソ不可侵条約締結の報を受けて、「欧州情勢は複雑怪奇なり」 という名文句を吐いたのは、平沼赳夫の血縁上の祖父にあたる平沼騏一郎だが、現実というものはいつだって 「複雑怪奇」 なものである。なかなか両立しがたい矛盾や対立などは、いくらでもある。頭の中でこしらえておいた 「公式」 だけで、いつもいつも正解が出るのなら、だれも苦労はしない。 吉田拓郎が体調不良を訴えて、予定していた全国ツアーを中止したそうだが、拓郎君のことしの夏休みはいったいどうなるのだろうか。拓郎君が元気になって、また 「きれいな先生」 に会えるようになることをぜひとも望みたいものだ。
2009.07.11
コメント(0)
-
マイケルが死んだ
一昨日のマイケル・ジャクソン死去のニュースには驚いた。まだ50歳、死因は心臓麻痺ということだが、これは前の世代のもう一人のスーパースター、エルヴィス・プレスリーの場合と同じである。プレスリーが死去したのは1977年、42歳だったそうだから、マイケルよりもまだ若い。プレスリーのデビューは50年代中頃であり、若い頃の画像をYoutueで探すと、ほとんどがまだ白黒であるというのには、時代を感じさせる。 プレスリーが生まれたのはミシシッピ、育ったのはテネシーで、いずれも南部に属する。おそらくは、そのことが、彼の歌に大きな影響を与えたのだろう。家族と写っているプレスリーの少年時代の写真を見ると、戦後すぐの頃のアメリカ南部の白人の暮らしが、けっして豊かではなかったことがよく分かる。今はそうでもないかもしれないが、南部での黒人差別の厳しさは、たぶんそのこととも無関係ではないだろう。 いっぽう、こちらでは、東国原宮崎県知事の例の発言をめぐって、なにやら大騒ぎのようだ。最初は出馬要請を断るための口実かと思っていたが、そうでもなく、結局、自分が自民党総裁選に出馬することを認めろという話らしい。現在の規約では、出馬には20人の推薦人が必要ということだが、そうすると、出馬に必要な推薦人を党の側で用意してくれということなのだろうか。これもまた、ずいぶんと筋の違うわけのわからぬ話である。 そもそも、一政党が県民の頭越しに、現職の知事に出馬要請をするというのがおかしな話なのだ。そうであるなら、まずは宮崎県民の皆様に、お伺いを立てるというのが筋だろう。ようするに、この話でいちばんなめられているのは、あいもかわらず地方の住民だということになる。東国原知事がどうするかは知らないが、自民党の支持率が下がっている中、県民を足蹴にするようなことをすれば、選挙がどうなるかはわかったことではない。 今頃になって、解散権がどうの改造がどうのと言っている、麻生首相や細田幹事長にしろ、なにがしたいのかさっぱり理解できない鳩山弟にしろ、自分の党の都合しか考えず、地方をなめきった古賀選対委員長にしろ、この国の政治家は、自分がとうに裸であることを知らぬ 「裸の王様」 ばかりである。こうも 「裸の王様」 が多くては、目のやり場にも困ってしまうではないか。 前の記事に続けて、昔の話をもうひとつすると、学生時代の先輩にYという人がいた。神戸の灘高の出身で、話によれば、高校生のときの69年に大阪で行われ、糟谷孝幸という岡山大の学生が死亡した、70年安保の11月決戦デモが人生最初のデモだったというとんでもない人で、亡くなった作家の中島らもと、たぶん同学年ぐらいになるはずだ。 その人は、おもに在日韓国人支援の運動に関わっており、小倉の大韓基督教会の牧師だった崔昌華さんを招いた講演会などを学内でやっていた。崔昌華という人は、かの金嬉老事件で、彼を説得するために現地静岡の旅館に駆けつけたという人でもあるが、当時はNHKを相手に、自分の名前はサイ・ショウカではない、チョエ・チャンファである、勝手に日本語読みをするな、という訴訟を起こしていた。その後、外国人登録証への指紋押捺拒否の運動なども展開していた。 当時の日本では、韓国の朴正煕政権は、左派やリベラル派によって軍事独裁とかファシズムなどと呼ばれて強く批判されており、投獄されていた詩人の金芝河に対する支援などの運動もさかんだったのだが、彼は自分が行っている運動に対して、そのようなスローガンが持ち込まれることをいっさい認めなかった。それは、在日韓国人支援の運動にそのような政治的スローガンが持ち込まれ、運動が特定の政治性を帯びてしまうことが、支援していた人たちとその運動に対して不利益となることを、じゅうぶんに理解していたからだろう。 とはいえ、自分が左翼であることを隠していたわけではない。それは、彼が付き合っていた向こうの人たちも、十分に知っていたことである。彼の下宿に行くと、トロツキーからローザや毛沢東まで、ありとあらゆる著作が壁一面に並んでいるという、とてもただの学生とは思えない人でもあった。とにかく、この人にはとてもかなわないと思わされた人でもある。 彼には、大学を出たばかりの 「できちゃった婚」 で途方にくれていたところに、自分が勤めていた塾に紹介してもらったりと大恩があるのだが、その後、そこがつぶれてそれぞれ別のところに移り、付き合いが途切れてしまった。風の噂では、その後、弁護士となり、在韓被爆者や在日コリアンの年金などの問題でも活躍しているらしいから、その筋の人なら、誰のことだかたぶん分かるだろう。 関係ない話だが、70年代には、サルトルもファノンも、左翼学生にとっては必読文献のひとつであった。なにしろ、三上寛はあの野太い声で、「サルトル、マルクス並べても 明日の天気はわからねえ」(参照)と歌い、サングラスをかけた野坂昭如は、ウィスキーのテレビCMで、「ニ、ニ、ニーチェか、サルトルか、みーんな悩んで大きくなった」(参照) と下手な歌を歌っていた時代でもある。若い人がサルトルを復権させようというのはかまわないが、そのくらいのことは常識として踏まえておくべきだろう。 もうひとつ、宗教団体(?)である幸福の科学が、選挙に参加するために幸福実現党なる組織をつくり、あちらこちらで運動している。こちらでも青いTシャツを着て、のぼりを掲げた運動員を街頭で見かけたのだが、幸福を実現するという言葉を掲げれば、幸福が実現できるのなら誰も苦労しない。運動にとって、スローガンというのはたしかに重要だが、看板だけの中身のないスローガンや、理解しがたいスローガンでは意味がない。
2009.06.27
コメント(16)
-
昔のことなどあれこれ
イラン情勢がたいへんのようだ。先週に行われた大統領選挙では、保守派とされる現職のアフマディネジャド大統領が約65%、改革派と言われるムサビ元首相が約32%というほぼ2対1の大差で、現職大統領の再選ということになったのだが、敗れたムサビ支持派が選挙の不正を訴えて各地で抗議行動を広げている。 首都テヘランでは、ムサビ支持派による数万規模の無許可デモが行われている。すでに死者も出ているらしいが、これは、ちょうど30年前に起きた、パーレビ王朝が倒された革命以来、最大の反政府運動ということになる。30年というのは、出生率の高い国なら、国民の半分以上が入れ替わるぐらいの長さになるだろう。フランス革命後の混乱が、ナポレオンの敗北で終息したのも、蜂起からほぼ30年後のことである。 振り返ってみると、イラン革命が起きた1979年というのは、国際的な大事件の相次いだ年であった。1月には、カンボジアのポルポトを支援する中国が、ベトナムに対し懲罰と称して戦争をしかけ、7月には中米のニカラグアで独裁者のソモサ政権が倒れた。10月には韓国の朴正煕大統領が側近の部下に射殺され、12月にはソビエトによるアフガニスタン侵攻が始まった。 朴正煕暗殺事件のときは、たしかある障害者団体がやっていた街頭カンパの支援に引っ張り出されていたような記憶がある(違うかもしれない)。ただし、その知らせを聞いたのがどういう経緯だったのか、詳しいことは思い出せない。ひょっとすると、号外でも出たのかもしれない。 その年というのは、本来なら大学を卒業する予定だったのだが、諸般の事情により翌年までお預けになってしまった。早い話、ろくに講義に出ていなかったから、卒業のための単位が足りなかったというだけのことなのだが。 前年に、京都大学の同学会が主催した集会があって、そこでの集会後のデモでお巡りさんになぐられて、気がついたらどこかの病院に寝かされていた。そのときは一週間で退院したのだが、帰ってきてもどうも目の調子がおかしい。左右の視線がきちんとあわない。それで、地元の病院で見てもらったところ、右目の眼球の下の骨が折れているという話だった。 結局、手術をして、まあよくはなったのだが、病院から出てきてみると、今度はまわりの連中と話があわない。中越戦争で、中国を支持しベトナムを非難するビラを出したり、ソ連を「白くま」と呼んで非難するビラを出したりと、まるでいっぱしの政治党派のような活動を始めていて、およよと思ってしまった。 そのへんのことには、いろいろと裏があったのだが、こんなバカな連中と一緒にやれるか、ということで足を洗った。ぼこりあいにこそならなかったけれど、気まずい別れであった。当時すでに、カンボジアの虐殺のニュースもちらほらと流れていたのだが、そういった現地の事情も知らずに、ようもまあそんなことが気軽に言えるよな、と感心したのを覚えている。 その連中が、今どこでなにをしているのかは、ほとんど知らない。学生時代には、青やら赤やら、あちこちにいろいろと知り合いもいたのだけれど、その連中ともほとんど付き合いはない。ただ、一度だけ、地元のニュースで、行政相手のつまらぬ事件の容疑者として、ちょっと知っていた者の名前が出てきたことがあって、おいおい、お前、まだそんなことをやっているのかよ、と呆れてしまった。 その当時、それから10年後にソビエトが解体し、鉄のカーテンで仕切られた 「社会主義圏」 なるものがいっせいに崩壊してしまうとは、いったい誰が予想していただろうか。まことに、十年先は闇である。今から考えれば、当時のアフガンやアンゴラでの無理な膨張政策と、アメリカとの軍拡競争が、彼ら自身の首を絞めたということなのだろうが。 話は変わるが、社会において不利な立場にある少数者や、いろいろな理由で自らは声をあげにくい人らを支援し擁護することは、むろん否定されるべきことではない。しかし、その場合に真っ先に考えられねばならないのは、なによりも当事者であるその人たちの立場であり、利益でなければならない。 「日の丸」 反対だの、天皇制反対、ファシズムがどうのという主張がしたければ、そういう運動とは切り離して、自らの責任ですればよい。たとえ、その主張に一定の正当性があろうと、それとこれとは別の問題だ。それを混同するのは、少数者の権利擁護という社会運動に、政治的な主張を持ち込むことであり、そういう人たちを、自らの政治的主張のために利用していることにすぎない。それが分からぬというのであれば、君らは、自分らが支援しているつもりの人たちの利益を本当に考えているのか、という話になる。 ベスト電器の不正ダイレクトメール事件から始まった、自称 「障害者団体」 の認可をめぐる問題は、郵便会社職員の逮捕から、とうとう厚労省の官僚逮捕というところにまで発展した。事件の背後には、政治家の関与もささやかれているが、この事件というのもよく分からない。そもそも、地検の特捜がわざわざ出張るほどの問題なのだろうか。 問題の 「第三種郵便物」 というのは、障害者団体向けの郵便物割引制度のことだが、連れ合いが持っている古いパンフ類を内緒で引っ掻き回していたら、「社会福祉事業団体 日本脳性マヒ者協会 全国青い芝の会総連合会」 という団体が発行していた、ぺらぺらの機関誌がでてきた。これには、ちゃんと裏側に 「第三種郵便物認可」 と印刷してあるから、不正ではない。 くしくも、これも1979年の発行で、「故横塚晃一会長追悼号」 と題されていた。横塚さんというのは、青い芝の会の指導者で、その世界では伝説的人物といってもいい人だが、生前に会ったことはない。ただし、副会長だった横田弘という人は、全国大会で一度だけ顔を見たことがある。当時、福岡の会長を務めていたN氏に、お前ついて来いと言われて、しかたなくついていったのだが、そのときの大会がどこで行われたのかは、とんと思い出せぬ。なにしろ、30年も前のことであるから。 そういえば、先日、地元のニュースでこのN氏の姿が流れたのだが、顔は変わらぬが、頭のほうはすっかり悲惨なことになっていた。やっぱり、昔の仲間だとか友人などというものには、あまり会わないほうがよさそうである。お前、誰だよ、とかいう話になりそうだし。紅顔の美少年もいまいずこ、というのでは、笑い話にもならない。 若いということは、多かれ少なかれ、愚かさや未熟さと同義である。思い返すなら、自分も、いろいろと愚かなことをしたものである。とても人様のことをあれこれと言えた義理ではない。ただ、自分の愚かさが自分に返ってくるのはしかたないとしても、関係のない人様の足を引っ張ったり、迷惑をかけぬぐらいの注意は必要だろう。
2009.06.19
コメント(4)
-
「分かる議論」と「分からない議論」
世の中には、自分にとって 「分かる議論」 をする人と、「分からない議論」 をする人がいる。「分かる議論」 とは、ようするにその人がなにを言っているかが分かるということである。厳密に言うと、それは正しいということが 「分かる議論」 と、間違っているということが 「分かる議論」 の二つに分かれるが、ここではとりあえず、その 「正しさ」 が分かる議論のほうを主に指すとする。 いっぽう、「分からない議論」 とは、そもそもその人がなにを言っているのかも、なにを言いたいのかも分からない議論のことである。であるから、この場合、それが正しいのか間違っているのかも、分からないということになる。 ネット上の論争とかを見ていると、いっぽうの人の言うことはよく分かり、もういっぽうの人の言うことは全然分からないということがよくある。そういう場合、人はだいたいにおいて、自分が理解できる人のほうを支持しがちである。なにしろ、いっぽうはいちおうなにを言っているか理解できるのだが、相手の方はなにを言っているのかが全然分からないというのだから、これはまあ無理からぬことである。 しかし、よく考えると、これにはおかしなところがある。なぜなら、事実についてであれ、観念についてであれ、「論争」 とはある主題をめぐって行われるものであり、自分にとって理解できるいっぽうの議論は、それ自体としては正しいとしても、その 「正しさ」 というのが、じつは論争の主題や相手の主張とは全然関係のない、たんなる一般的な 「正しさ」 であったり、まったく頓珍漢な明後日のほうを向いた 「正しさ」 にすぎないという可能性もあるからだ。 当たり前のことだが、一般に自分にとってよく 「分かる議論」 とは、それが今の自分の知識とか理解力とかにぴったり一致しているか、またはその範囲内にあるから、よく分かるわけだ。それは、たとえば、高校レベルの数学を十分に理解した者にとって、中学レベルの数学の問題など、ちょちょいのちょいで解けるのと同じである。 人は、「分からないもの」 と 「分かるもの」 とが並んでいると、どうしても 「分かるもの」 の方を選びがちなものだ。しかし、「分かるもの」 ばかり選び、好んでいたのでは、「進歩」 も 「向上」 もない。足し算でも掛け算でもなんでもよいが、人間誰しも 「公式」 のようなものを覚えると、それをどこでもここでも振り回したくなる。 「公式」 というのは便利なもので、使い方さえ間違えなければ、誰がやろうと必ず正解が出る。なので、世の中には、間違えてバツをもらうのが嫌なばかりに、間違える心配のない同じような問題ばかりいつまでも解いている小学生のような人もいる。なるほど、新しい問題などには挑戦せず、自分の能力の範囲内の問題ばかりしていれば、間違える心配は永遠にない。いつもいつも百点がもらえる。それはたしかに気持ちのいいことではある。 とはいえ、それでは、カゴの中の輪の中で、輪をぐるぐる回しているハムスターと同じだ。一生懸命手足を動かしていて、自分では走っているつもりなのかもしれないが、じつは一歩も前には進んでいない。というわけで、論争において 「分かる議論」 をする人と 「分からない議論」 をする人がいたならば、「分かる議論」 をする人よりも、「分からない議論」 をする人の言い分のほうをよく考えてみたほうがいい。 なにより一番駄目なのは、「分からない議論」 をする人に対して、適当に選んだ自分の手持ちのレッテルを貼っておしまいにし、「分かる議論」 をする人の肩をそそくさと持ってしまうことだ。「教科書」 に書いてないことを言う人の中にも、「教科書」 についてまったく無知な人間もいれば、「教科書」 に書かれていることなど、言わずもがなの前提にしている人もいる。 「教科書にはそんなことは書いてない」 と指摘するのは簡単だが、とりあえず、そういう違いぐらいは考えておいたほうがよい。たしかに、1+1 は誰が計算しようと2になる。だが、それだって、2進法ということになれば違ってくる。そもそも、世の中、教科書に書かれてあることしか言わぬ人ばかりでは、ちっとも面白くもない。 ただし、残念ながら 「分からない議論」 がすべて意味のあるものとは限らない。それが分かったことで、必ずなにかが得られるとも保証できない。とはいえ、それでも頭の体操ぐらいにはなるだろうから、まったく無駄というわけでもあるまい。むろん、それも時間があれば、の話ではあるのだが。 さて、政局のほうは、鳩山総務大臣の辞任で、麻生内閣の支持率がまたがくんと下がったそうだ。安倍内閣以来、あれやこれやの迷言でおなじみの、あの鳩山邦夫氏がそんなに人気があったのだとはちっとも知らなかった。これもまた、よく 「分からない」 ことである。 関が原の合戦のとき、信濃の山奥の真田家は、兄の信之が東の家康につき、弟の幸村は西の三成についた。これには、東軍・西軍のどちらが勝っても、真田家が生き残れるようにという父、昌幸の深謀遠慮が隠されていたという説がある(真偽のほどは知らない)。 民主党結成時には手を組んだ鳩山兄弟が、その後、路線の違いとかで二手に分かれたのには、ひょっとすると同じような思惑があったのかもしれない。ただし、これは根拠などなにもない、ただの思いつきである。
2009.06.15
コメント(2)
-
「レッテル」の正しい貼り方と使い方
19年前に栃木で起きた 「足利事件」 の犯人として無期懲役の刑を受けていた、元幼稚園バス運転手の菅家利和さんが、再審前であるにもかかわらず釈放された。菅家さんは、当時いくつも起きていた同様の他の事件についても 「自白」 していたが、検察は奇妙にも他の事件については不起訴とし、一件のみについて起訴している(参照)。 連続した幼児の行方不明と殺害という重大事件であり、しかも本人がせっかく 「自白」 までしたというのに、検察はなぜか他の二件については起訴を見送った。むろん、それは、「自白」 以外の物証の不足が主たる理由だったのだろう。だが、おそらくは検察も、他の二件に関する 「自白」 の任意性と内容の真偽については、当初から疑問を持っていたのではないだろうか。 むろん、事件はそれぞれ別である。理屈を言うなら、他の件に関する 「自白」 の疑わしさと、起訴された本件の 「自白」 の問題とは別だと言えなくもない。しかし、そのことは、少なくとも当時の取調べには、容疑者に対して、本人がやってもいない事件についての 「自白」 を迫る雰囲気があったということを示唆している。であるなら、裁判所は本件に関する 「自白」 の任意性と捜査の適正さについても、当初から疑いを持つべきではなかったろうか。 もし、菅家さんが一件ではなく、他の件も含めて起訴され、そのすべてで有罪となっていれば、死刑となっていた可能性は非常に高い。実際、飯塚で起きた同様の事件では、二件の殺害容疑によって、被疑者は死刑判決を受け、すでに刑も執行されている(参照)。 問題は、DNA鑑定の技術的精度だけではない。鑑定や科学的技術そのものの精度がいくら上がったとしても、結局は人間がやることである以上、故意か故意でないかに関わらず、その過程において、なんらかのミスが生じる可能性はつねにある。そのことも忘れてはならない。 さて、前置きならぬ前置きが長くなった。ここから本題にはいることにしよう。ただし、前置きと本題といっても、全然関係がないわけではない。お題は、「レッテル」 の正しい貼り方と使い方ということ。 よく、議論の場などで、「レッテル貼りはよくない!」 と言い出す人がいる。そういうときの 「レッテル」 とは、つまりカテゴリ的な概念のことだ。たしかに、印象操作や思考停止を伴う 「レッテル貼り」 はよくない。だが、だからといって、分類のためのカテゴリ使用をすべて禁止するわけにはいかない。 それでは、世界について思考するには、世界に存在する事物と同じ数の概念が必要ということになる。それは、見知らぬ町へ行くのに、その町と同じ大きさの地図を持って行け、というようなものである。 概念は、具体的な事物や関係の抽象によって得られる。個々の具体的な事物は、様々な側面を持ち、様々な関係の中にある。だから、同じものでも、見方や視点、関係付けの違いによって、様々に定義することができる。つまり、カテゴリ的概念とは、すべて事物の一面を捉えたものにすぎないということだ。イルカとマグロは生物学的にはまったく別だが、海洋生物としては一緒である。なので、海洋汚染に対しては、イルカもマグロも利害が一致するのであり、ともに団結してたたかおう! ということになる。 巨人ファンの中にだって、仏教徒もいればキリスト教徒もいるだろう。その場合、球場では仲がよくとも、宗教の話になったとたんに喧嘩を始めるかもしれない。逆に、同じ信者どうしであっても、一方は巨人ファン、他方は阪神ファンであり、野球の話については犬猿の仲という人もいるだろう。「好きな球団」 というカテゴリも、「宗教」 というカテゴリも、具体的な個人の全体を包摂することはできない。どんなカテゴリだろうと、あるカテゴリに包摂されるのは、そのカテゴリと関連したその人の一部であり、全体ではない。 カテゴリは、事物についての特定の視点で構成されたものである以上、しょせん一面的な概念でしかない。一面的なカテゴリによって構成された 「全体」 とは、それ自体一面的な 「全体」 にすぎぬのだから、どんなカテゴリも、個の全体、個が有する関係の全体を包摂できはしない。具体的な場面において、どのカテゴリを適用し、優先させるかは、そこでの問題に依存するのであり、カテゴリそのものから引き出すことはできない。 「やつは○○だ。追い払え!」 といった差別や集団的憎悪は、個と全体を同一視し、個を全体に解消するところから生じる。彼らにとっては、AやBという個人、つまり個人としての人間などはどうでもよいのであり、AやBという個人が○○というカテゴリに属するかどうかが、すべてなのである。ようするに、彼らは、たった一枚の 「レッテル」 が生きた個人のすべてを包摂しうるかのように考えているのであり、これもまた、悪しき 「レッテル貼り」 思考のひとつということになる。 「毒物」 というレッテルは、とりあえず注意を喚起するという点では役に立つ。しかし、毒にもいろいろあるのであり、具体的な場面では、それでは役に立たない。同じ毒でも、青酸カリと砒素ではまったく違うし、対処の方法だって違う。だから、目的と必要に応じて、レッテルはさらに細かく分類し、正確に貼らなければならない。レッテルを正しく使うということは、どんなレッテルも万能ではないということをふまえ、使用しているレッテルの意味、すなわち、その効用と限界を正しく認識しておくということだ。 悪しき 「レッテル貼り」 とは、まずは不正確で曖昧なレッテルを使用することであり、また、その誤りを指摘されても、がんとして認めようとしない頑迷さのことである。そして、「毒物は毒物だ」 という一見正しそうに思える、ただしよく考えれば、ただの同語反復に過ぎない論理を振り回して、毒物Aと毒物Bの違いを認めようとしない 「レッテル全体主義」 のことでもある。 なので、レッテルの正しい使い方と間違った使い方を区別できず、たまたま悪しき 「レッテル」 として使われることのある言葉を見つけただけで、パブロフの犬のように、「それはレッテル貼りだ!」 と叫び出す人も、実は同じ 「レッテル貼り」 思考に陥っているということになる。つまり、「レッテル貼り」 とは、個々の場合に応じた具体的な思考と判断を放棄した、怠慢かつ怠惰な思考のことなのだ。 裁判で言うなら、「有罪」 と 「無罪」 というのもひとつのレッテルである。「容疑者」 とか 「被告人」、「受刑者」 というのも、同じようにレッテルである。警察に逮捕されたのだから、検察に起訴されたのだから、すでに有罪判決を受けているのだから、とそこで思考を停止して、「彼が犯人に違いない」 と決め付けてしまうのは、まさに悪しき 「レッテル貼り」 思考の典型である。 たしかに、証拠もなしに警察が逮捕状を請求するはずがないとか、有罪の見通しもないのに検事が起訴するはずがない、根拠もなしに裁判官が有罪というはずがない、などというのも、全体としてならば、そこそこの推論としてなりたつかもしれない。しかし、個別の事例について判断するときには、そのような前提は、ただのよけいな先入観でしかない。全体としての蓋然的な正しさは、個々の事例における正しさとはまったく関係ない。 「司法の独立」 という原則によって、裁判官の身分が保証され、その判決に対して責任が問われないのは、ときの政治権力や有力者の意思、あるいは法的判断以外の利害によって、裁判官の判断が左右されることを防ぐためであって、どんな判決を下そうがおれたちの勝手だよ、とあぐらをかくためではない。 われわれは一生懸命やった、あの当時はあれでしかたなかった、という警察や検察、裁判所の弁明が、いまだにまかりとおるようでは、「国家無答責」 なる法理がまかりとおっていた 「大日本帝国憲法」 の時代とまったく違わない。国家とその機関は国民に対してなにをしても責任を負わないというのでは、「国民主権」 など絵に描いたもちですらない。 冤罪を生み出さないために必要なことは、自白や証拠に疑問があるなら、徹底してその不明な点を追究するという態度だけである。当時のDNA鑑定の不正確さについては、最初から疑問が出されていたのに、なんだかんだといって10年以上も再鑑定を退け続けたのには、面倒くさい、という以外に、いったいいかなる理由があるのだろうか。 この国の司法では、「疑わしきは被告人の利益に」 という近代司法の大原則があまりに無視されすぎてはいないだろうか。警察・検察や裁判所などの関係者もまた、個々の被疑者や被告人、受刑者を、それぞれ名前を持ち、家族を持ち、また未来を持っている生きた人間としてではなく、「レッテル」 が貼られた書類の上の記号としてしか見ていないということなのだろう。警察・検察の主張を鵜呑みにし、せいぜい検事の求刑をいくらか割り引いた刑を言い渡すというだけなら、サルでもロボットでもできることだ。
2009.06.05
コメント(4)
-
「王様は裸だ!」と叫んだ少年はいかなる資格を有していたのか
新型インフルエンザの感染者は、まだまだ増えつつあるが、弱毒性ということもはっきりし、一頃の騒動はどうやら山を越えたようだ。しかし、テレビをつけていると、1日に何度も、「冷静な対応をお願いします」 という首相のあのだみ声を聞かされるのはたまらない。「冷静な対応」 だなんて、今頃になってなにを言ってんだとしか言いようがない。 かつてエンゲルスは、『イギリスにおける労働者階級の状態』 の中で、世界でもっとも豊かな国の労働者らがいかに悲惨で惨めな暮らしを強いられているかを、克明に描いた。国家が豊かであるということと、国民の貧しさとは必ずしも矛盾しない。それが、当時まだわずか25歳だったエンゲルスの指摘したことだ(それは、むろん今でも多かれ少なかれあてはまる)。 それと同様に、国家とその軍隊の装備や戦力は、国民の貧しさとも必ずしも矛盾しない。世界には、スラム街でその日暮らしの生活をしている多くの貧困者がいる一方で、核兵器や遠くまで飛ばせるミサイル、高速で空を飛びまわる戦闘機をそろえて得意になっている国もある。インドもパキスタンも、またもちろん先日、晴れて 「核保有国」 の仲間入りをしたかの国でも、それは同じことだ。 しかし、言うまでもなく、そのようなものは煮ても焼いても食えはしない。人間にとって必要なものは、まずは食べるものであり、次に雨露と暑さ寒さをしのぐ場所である。先日、インドでは、アカデミー賞を取った映画に出演した子供らの住んでいた家が 「不法建築」 ということで取り壊され、路上生活を余儀なくされたというニュースがあったが、ようやくその二人の子役には、州から約束のアパートが 「ご褒美」 として与えられたそうだ。むろんそれは二人にとっては喜ばしいことだが、家を失った子供はその二人だけではあるまい。 当該の問題に直接の関係を持たない者が 「安全地帯」 から声を上げることは、非難されることではない。声を上げることが 「安全地帯」 からでしか可能でないのであれば、まずは 「安全地帯」 にいる者が声をあげればいい。それは、今はまだ声を上げられない当事者らに対する励ましとなることもある。また、そのような 「われわれは見ているぞ!」 という声には、現状を今すぐ変えることは不可能だとしても、少なくとも現状のこれ以上の悪化を防ぐぐらいの力はあるかもしれない。 誰も声を上げられないならば、誰かがまず、「王様は裸だ!」 と叫ばなければならない。チャウシェスクの独裁も、誰かがあの広場で、「お前は裸だ!」 と叫んだことをきっかけにして崩壊したのではなかったのか。誰かの声がきっかけとなって、それまでのタブーが破られるのなら、誰が口火を切ろうとそんなことはどうでもよい。王様の行列を前にして、「王様は裸だ!」 と叫んだ少年に対して、いったい誰がその資格や権利を問うただろうか。 たしかに、日本にはかつて朝鮮を植民地として支配した責任がある。だが、相対立するかに見える二つの問題があるときに、一方の問題を持ち出して、他方の問題に対する批判を封じようとするのは、ただの相殺論法に過ぎない。「王様は裸だ!」 と叫んだものが、自分もまた裸であることに気付いてなかったとしたら、笑いものにはなるだろう。しかし、だからといって、実際に王様が裸であるのなら、それを指摘した言葉の正しさまでが損なわれるわけではない。他者への批判が倫理的な非難に値するのは、それが自己の責任を隠蔽し、自己への批判をかわすことを目的にしている場合のみである。 他国への侵略や、自国内の少数民族への抑圧が 「悪」 であるなら、自民族である自国の民衆に対する抑圧もまた 「悪」 である。そこに違いなどありはしない。たしかに、それはその国の 「国内問題」 ではある。だが、どんな国の支配者にも、自国の民衆をほしいままに支配し抑圧する権利などないのは、いまさら言うまでもないことだろう。 北朝鮮が行った実験は、マグニチュード4.5から4.7程度の地震を引き起こしたそうだ。実験は、日本海に面した咸鏡北道というところで行われたそうだが、実験場から200 km離れた中国では、そのために学校が休校になったという(参照)。その地域が、もともとどのようなところであったのかは知らない。当然のことながら、実験場の周辺の住民は、とうに立ち退かされているだろう。だが、いかに地下実験とはいえ、砂漠の真中とかではないのだから、周辺に対して被害がまったく発生しないとは考えにくい。 北の 「指導部」 にしてみれば、核を持つことで、世界とりわけアメリカに対する発言権を高めると同時に、現在の 「体制」 への保証を取り付けたいという思惑があるのだろう。しかしながら、国家の体制なるものを保証するのは、ほかのどこの国でもなく、なによりその国の国民自身である。国民の支持を失った 「体制」 など、他国によっていかに保証されようが、いずれ崩壊せざるをえない。 豊かとはとうていいえない国において、そのような実験を繰り返し行うことは、その国の国民にとってなにを意味するのか。それは、不作と借金に苦しみ、白い飯も食えず、娘も売り飛ばさざるを得ないというような貧しい農民らがいた一方で、大和だ、武蔵だなどという、「世界に冠たる」 無敵の巨大戦艦を建造して悦にいっていた国と、いったいどこが違うのか。 理想を掲げたソビエトはなぜ崩壊したのか。東欧における優等生とまで言われた東ドイツは、なぜライバルであった西ドイツに完全に後れを取り、吸収合併されるという憂き目に会ったのか。かの国の人々のことが心配だという人がいるのなら、まずはそのような過重な軍備や、あのような狭小な国土で核実験を繰り返すことが、彼らの生活とその行く末になにをもたらすかをこそ、心配すべきではないか。 仏領赤道アフリカを旅行したとき、誰かに 「案内されて」 いる間は、すべてがほとんど素晴らしく目に映った、といったことを私はすでに書いたことがある。私がはっきり事物の姿を見はじめたのは、総督が回してくれる自動車におさらばして、単身徒歩で、この国を歩き回り、半年の時日をかけて、原住民たちに直接接触しようと思ったそのときからである。...... なぜか? プロレタリアは、すでに侵害された彼らの権益を防いでくれる代表者を、たとえ一人でも選出する可能性すらもっていない。人民投票は、公開で行われるにせよ秘密裡に行われるにせよ、これは人を馬鹿にしたものであり、見せかけであることは間違いない。すべての任命は、上から下に対して決定される。人民は前もって選ばれたものしか選挙する権利はない。プロレタリアはなぶりものにされている。猿轡をかまされ、がんじがらめに縛られ、抵抗などほとんど思いもよらなくなっている。じつに競技はうまくはこばれ、スターリンは見事に勝った。 これは、今から70年近く前、スターリンによる粛清開始のきっかけとなった 「キーロフ暗殺事件」 の直後にソビエトを訪問した、フランスの作家 アンドレ・ジッドが帰国後に書いた 『ソヴェト旅行記修正』 の一節である。その前に 『ソヴェト旅行記』 を書いて、革命への共感と同時に、しだいに官僚化を強めていくソビエト社会への不満と懸念をも表明したジッドは、スターリンを支持するロマン・ロランに非難されたそうだが、ジッドはロランに対してこの 「修正」 の中で、こう反論している。 私は今日まで、彼の作品に対して感心したことはないが、それでも、彼の精神的人格だけは少なくとも高く評価してきた。私の悲しみは、そこからきている。つまり、世には、彼らの偉大さをすっかり出し切らないうちに、人生を終わってゆく人たちがあまりにも少なくないと言うことをあらためて考えさせられるからである。おそらく 「争いの上にあれ」 を書いたロランは、今日の老ロランを手厳しく裁いているのではないか、と私には思われる。かつての日の鷲も、巣づくりを終えて、そこで憩いをとっている。
2009.06.01
コメント(0)
-
物事は正しい言葉で呼ばなければならない
仕事のせいで(本音を言えばネタがなかったからでもあるが)更新を怠っていたうちに、いろんなことが起きていた。国内では鳩山氏が小沢氏に代わって民主党の代表になり、海の向こうでは、盧武鉉 前韓国大統領が在職時代の「献金問題」をめぐって自殺した。 さて、21日にはいよいよ裁判員制度が始まったわけだが、この制度を定めた 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」 なる長ったらしい名前の法律では、まずこんなふうに規定されている。第一章 総則第一条この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和22年法律第59号)及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。第二条 1. 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件(法2条1項1号) 2. 裁判所法第26条第二項第二号に掲げる事件(法定合議事件)(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(同項2号) というわけで、この制度は、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強かん致死傷罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死罪といった、いわゆる重大事件を対象としているということだ(参照)。 しかし、「死刑または無期の懲役・禁錮」 という、現在の刑法においてもっとも重い刑が課せられる可能性のある事件、言い換えれば被告人にとっては、その命を左右される可能性もあるような事例に、法律の素人である 「一般大衆」 をいきなり参加させるという発想は、どう考えても解せない。 裁判というものは人間がやる以上、誤判の可能性を完全に除去することは、不可能である。であるなら、死刑という最も重い刑が課せられる可能性のある重大な事件こそ、専門家による慎重で精確な審理をもっとも必要とするのは自明なことだろう。言うまでもないことだが、そのような被告人の立場に立たされる可能性は、誰にだって皆無というわけではない。近代の裁判において、被告人の権利と利益が法で守られているのは、そのためでもある。 法務省によれば、この制度が発案された背景には、「凶悪事件」 の裁判がしばしば長期化したり、「社会的常識」 とかけ離れた判決が下されることに対して、被害者を含めた社会の一部に、現在の裁判に対する不満がくすぶっているということがあるらしい。 しかし、そうは言っても、すべての「凶悪事件」 裁判が長期化しているわけではない。長期化する裁判には、物的証拠の少なさや、自白の任意性や証言の信頼性、被告人の責任能力など、それぞれにいろいろな理由があるのであり、その結果として一部の公判が長期化したからといって、被害者感情などをとりあげて、それを問題視するのは筋が違う。 この制度導入を進めた司法制度改革審議会での議論を読む限り、裁判員の参加が重大事件に限定された背景には、最初から 「社会的関心」 が高い事件を対象にするという意向があったようだ。それには、むろん、対象事件の範囲をしぼることで、国民の負担を軽くしようという意味もあっただろう。たしかに、重大事件の件数は年間ほぼ2,000件ほどであり、刑事事件全体に占める割合はきわめて小さい(参照)。 だが、同時にそのことは、この制度の目的が、そこで謳われた 「統治主体・権利主体」 である国民の裁判参加などということよりも、むしろ光市母子殺害事件だとか、和歌山砒素カレー事件などのような、世間の耳目を集める裁判のたびに、あれやこれやと吹き上がる、マスコミを含めた世論対策の一環でしかないことを示しているようにも思われる。 つまるところ、この制度の趣旨は、国民の裁判参加を促すことでも、国民に裁判を身近なものとさせることでもなく、いわゆる 「凶悪事件」 をめぐる裁判の長期化や、理解しがたい事件を起こした被告人の責任能力の問題、あるいは刑の軽重や死刑制度の存否をめぐって、しばしば論議の的になる現在の司法制度に対して、「国民の参加」 という、それ自体としてはほとんど現実的な意味を持たない制度を導入することで、司法制度全般の正当性を象徴的に高めることにすぎないように思われる。 むろん、司法制度に対する国民の信頼は、高いほうがいいに決まっている。だが、そのためになすべきことは、そのような小手先の改革ではなく、警察の捜査や取調べの可視化、虚偽の自白強要につながる拘留の長期化や代用監獄の問題などを含めた、制度全体の信頼性を高めることであり、それによって、なによりも冤罪や誤判の発生を可能な限り抑え、万が一の場合の救済についても、より納得のいく制度を完備することのはずだろう。 一般に、民主主義とは国民の側から言えば、政治や行政への国民の積極的参加という意味を持つ。だが、国家の側から言えば、それは国民を政治過程へ動員することによってその一体感を高め、権力の正当性を担保するという意味も持つ。「国民」 の創出と並行する国家の 「民主化」 は、同時に国民の政治過程への動員によって、「国民国家」 を完成させるという役割も持っていた。 歴史的に言うなら、フランス革命とナポレオン戦争によって始まった、国家と国民のすべてを動員した 「総力戦」 の登場は、身分制度の廃止による市民の平等という 「国家」 の民主化という過程と並行している。超大国ペルシアと戦ったアテネも、自腹で武器を揃えることのできない貧しい民衆らも市民として認め、彼らを戦いに動員することで、二度の戦いに勝つことができた。 ナポレオンからの解放戦争を戦ったプロシアも、農民や中産階級らの一般国民に民主化を約束することで、民衆のナショナリズムを鼓吹し、ナポレオンを追放することができた。もっとも、アテネと違って、プロシアの場合にはナポレオンの没落とともに、その約束はあっさりと反古にされてしまったのだが。 戊辰戦争で 「会津征伐」 の指揮を執った板垣退助は、後年の回想で 「会津の藩士と領民とが一致団結せず領民たちは会津の興亡に無関心じゃった」 ために、会津は滅亡したと語り、そのときの体験から、「自由民権」 の大切さを痛感したという。つまり、彼にとって、民主主義とは、なによりもまず外敵に対して、国民が一致団結できる国家を作り上げるための重要な手段として注目されたということだ。 そもそも、「参加」 とは、当該者からの参加の希望と要求があることを前提とする。国民からの 「参加」 の希望や要望があったわけでもなく、国民に対して明確な意思が問われたわけでもないのに、政府や司法関係者、議会の意思でのみ、国民の裁判への参加を決めるというのでは、「参加」 ではなくむしろ 「動員」 というべきだろう。 なお、とくに強かん致死傷罪のような性犯罪事件での裁判員制度導入が含む問題については、下を含めていくつかのブログで指摘されている。 【性暴力事件】裁判員裁判に持ち込まれる「お茶の間裁判」の危険性 「裁判員制度における被害者のプライバシー確保を求める要請」その後
2009.05.24
コメント(8)
-
5月15日だけど5.15事件の話はやめておく
気がつくと、すでに五月半ばである。五月は古来 「さつき」 といい、五月晴れと書いて 「さつきばれ」、五月雨と書いて 「さみだれ」 と読む。もっとも、これはもともと旧暦での呼称であるから、現在の暦ではむしろ六月にあたる。なので、五月雨とは今の六月のだらだらとした長雨のことであり、五月晴れも、本来は今の五月のからりとした青空ではなく、梅雨の合間にたまに見られる晴天のことをさしたということだ。 デモのあとの集会などで、「それじゃまた」、「また今度」 などと言いながら、一人減り二人減りして、いつの間にか誰もいなくなった、というような解散のしかたを 「さみだれ式解散」 と言ったりもするが、ようするにだらだらとしていて、はっきりした区切りがついていないところが、梅雨の降りかたに似ているということなのだろう。 もう過ぎてしまったが、5月11日は関東軍指揮下にある満州国軍とモンゴル軍の衝突により、ノモンハン事件が始まった日であった。このときも、関東軍は明確な戦略を欠いたまま、ときの内閣や大本営の方針すらも無視した独走によって、戦力の逐次投入を繰り返し、あげくの果てに多大の損害を出すことになった。これなどは、いわば 「五月雨式」 戦力投入といえなくもない。 ベトナムにおける、かのホー・チ・ミンと並ぶ 「建国の英雄」 であるボー・グエン・ザップ将軍は、第二次大戦後のフランスとの独立戦争におけるディエンビエンフーの戦いで、それまでのゲリラ戦術から一転した大量の武器・弾薬と兵員を集中させた包囲戦により、フランス軍に壊滅的な打撃を与えて独立を達成した。むろん、広々としたモンゴルの草原での戦いと、ベトナムの山奥の要害地での戦いを同列に並べるわけにはいかないが。 戦力におとる側は、つね日頃は無謀な正面戦は避けながらも、ここぞというとき、ここぞという場面で、戦力を集中させて決定的な勝利を勝ち取ることを尻込みしてはならない。でなければ、ただ展望のないだらだらした消耗戦のみが、いつまでも続くことになるだろう。これは、毛沢東の人民戦争戦略についても言えることである。 もっとも、ノモンハンの場合は、革命からすでに20年を経過し、公開されたラッパロ条約の裏で結ばれた、ソ連とドイツというベルサイユ体制からつまはじきされていた国家どうしによるお互いの協力を約束した秘密協定によって、ドイツ国防軍から援助を受けていた結果、近代化され訓練も行き届いていたソビエト軍の戦力を侮るという致命的なミスを最初から犯していたのだが。 なお、クラウゼヴィッツはかの 「戦争論」 の中で、次のようなことを言っている。 これに較べれば兵力の相対的優勢、すなわち決定的な地点に優勢な戦闘力を巧みに投入することは、もっと頻繁に用いられた手段である。そして兵力のかかる相対的優勢を可能ならしめる根拠は、将帥がかかる決定的地点を正しく判定すること、またこれによって軍に最初から与えられているところの適切な方向を選ぶこと、さらにまた重要なものと重要でないものとを取捨選択するために、換言すれば彼の指揮する兵力を集結してつねに優勢を保持するために必要な決断等である。とりわけフリードリヒ大王とナポレオンは、この点できわめて傑出した将帥であった。 兵器の進歩が著しく、しかも国力や科学技術の水準によるその差も無視できないほど広がっている現代では、こういうクラウゼヴィッツの思想は、彼が意図した本来の戦争よりも、むしろ政治や企業経営といった非戦争分野のほうによくあてはまるようだ。それが、たぶん現代のビジネスマンによって、この本の縮刷版とか解説書の類が好んで読まれる理由でもあるのだろう。 報道によると、民主党の小沢代表がついに党代表の辞職を決意したとのことである。後任は、鳩山由紀夫幹事長と岡田克也副代表という、いずれも代表経験者による決戦により、16日の投票で決まるということだ。 漢字が読めないという学力不足や、傲慢不遜な物言いなどで、一時は支持率2割台にまで落ち込みながらも、脅威の粘り腰で政権を維持し続けた麻生首相は、小沢氏の献金問題で一定の支持率回復の兆しを見せて、一息ついていたところだろうが、すでに衆院任期切れまであと数ヶ月という時点で、民主党の党代表交代という局面を迎えることは予想していたのか、していなかったのか。 「災い転じて福となす」 という諺もあり、また 「人間万事、塞翁が馬」 という故事成語もあって、なにごとも最終的な結果が出るまでは、なにが禍であり、なにが福であるかなど、簡単には分からぬことである。長い人生、誰しも 「失敗」 はあるものだが、展望がなければ、今の道から 「撤退」 して別の道を探すのも悪いことではない。 「撤退」 を 「転進」 と言い換えて、大陸奥地や太平洋の島々での敗北を隠蔽・糊塗したのは旧日本軍のお家芸であったが、人生において本当に別の道を探すのなら、そのような言い換えも許されないわけではないだろう。もっとも、無計画、無展望、無方針という 「三無主義」 を信条にしているような人間が言っても、まったく説得力のない話ではあるのだが。
2009.05.15
コメント(4)
-
岡倉天心からアジア主義まで
明治期の日本人による英文の著作というと、新渡戸稲造の 『武士道』 のほかに、内村鑑三の 『余は如何にして基督教徒となりし乎』 とか、岡倉天心の 『茶の本』 なども有名である。岡倉は 『東洋の理想』 にある 「アジアはひとつである」 という言葉でも知られているが、それより前に書かれ、死後に公開された 『東洋の目覚め』 という文書では、次のようなことを書いている。十八世紀の後半、東方の略奪からうまれた信用と資本によって、ヨーロッパ産業主義の発明的エネルギーが活動をはじめる。木材のかわりに、石炭が精錬につかわれるようなった。今や、飛梭、紡績機、ミュール精紡機、動力織機、蒸気機関等のおそるべき装置が完成された。農業と協力することも、人類の産業計画を十分に解決することもなしに商業主義の時代に入ったために、西洋は、商品販売市場の発見に依存する巨大な機械になった。 驚くのは、ここで披瀝されている天心の近代観が、かの 『共産党宣言』 での著述にきわめて酷似しているということだ。『共産党宣言』 の日本語訳は、堺利彦と幸徳秋水により日露戦争中に 「平民新聞」 に掲載されたのが最初で、天心の文章はそれよりもわずかに早い。博学で、むろん外国語に堪能な天心のことだから、それ以前に 『宣言』 を読んでいた可能性はあるし、また同様の認識を他の著作から得たという可能性もなくはないだろう。 ノートに書かれたままで公開されなかった、天心のこの文書は、インド滞在中にその地の独立運動家らのために書かれたものらしい。その意味では、同じ英語で書かれたものでも、欧米人の目を意識した新渡戸の 『武士道』 とは性格がまったく異なる。新渡戸もまた博学な人であり、彼の 『武士道』 には、ソクラテスやアリストテレス、ヘーゲルやカーライル、さらにはニーチェやヴェブレンなど、実に多くの欧米の著作や著作家の名前が登場する。 ギリシア神話や聖書からはじまって、当時の最新の著作家にまでおよぶ、新渡戸の猛勉ぶりには敬服する。しかし、新渡戸によるそれらの名前の引用には、脈絡も必然性もない、やたらめったらなものという印象が強い。失礼を承知であえて言うならば、それはまるで、いかめしい顔をした厳格な教師に対して、「先生、見て見て、ぼくってこんなことも知っているんだよ」 と、しきりに取り入り、その関心を引こうとしている、早熟で自意識の強い 「良くできる生徒」 であるかのように見える。 お札にもなったほどの新渡戸には悪いが、この書で彼がやっていることは、武士道をはじめとする日本の文化が、騎士道だとかの西洋の歴史や文化といかに共通性があり、同じものであるかを強調することにすぎない。それは酷評すれば、「名誉白人」 としての処遇と承認を求める、どこにでもいる植民地エリートふうのものにすぎないように思える。 そこには、天心のような、西洋に対抗して、アジアのアジアとしての独自性を主張する強い姿勢はいささかも見られない。もっとも、その逆に、天心の場合には、アジアがあまりに理念化されていて、中国やインドの華麗で巨大な帝国と文明が、いわゆる 「アジア的悲惨」 と裏表であったという事実がまったく無視されている。まあ、だからこそ、天心はアジア主義者の祖の一人ということになったわけだが。 話はころっと変わるが、柄谷行人は、『ヒューモアとしての唯物論』 の最後に収められた、「日本植民地主義の起源」 という短文の中で、こう書いている。日本の植民地政策の特徴の一つは、被支配者を支配者である日本人と同一的なものとして見ることである。それは、「日朝同祖論」 のように実体的な血の同一性に向かう場合もあれば、「八紘一宇」 というような精神的な同一性に向かう場合もある。このことは、イギリスやフランスの植民地政策が、それぞれ違いながらも、あくまで支配者と被支配者の区別を保存したのとは対照的である。 ここで柄谷が指摘していることは、特段に新しいことではない。柄谷が言うように、日本による 「韓国併合」 は、建前上は 「日韓合邦」 という韓国側の 「要望」 を受け入れるという形で推進され、また 「内鮮一体」 などのスローガンも併合後には掲げられた。日清戦争で獲得した台湾についても、同様のことが言える。 しかし、その内実がいかなるものであったかは、いまさら言うまでもあるまい。実際、黒龍会の内田良平によれば、日清戦争のきっかけを作った東学党の流れをくみ、韓国の側で、日韓の 「対等合併」 を目指して 「合邦運動」 を推進した一進会の指導者であった李容九は、日本に病気治療に来たさい、見舞いに訪れた内田の手を握って、「われわれは馬鹿でしたなあ」 ともらしたという。 維新によってアジアの中で唯一近代化に成功し、大国ロシアにも勝利した明治の日本が、西欧の圧迫下で近代化を模索するアジア各地の国を憂える知識人やエリートらにとって、手本であり模範であったのは、想像に難くない。近代トルコの 「建国の父」 であるケマルにとっても、また頭山や犬養と親交が深かった、一時期の孫文にとっても、日本はまさにそのような 「希望の星」 であったことだろう。 死の直前になって 「われわれは馬鹿でしたなあ」 と語った李にしても、内田に吹き込まれた 「日韓合邦」 は、ロシアと清という大国の圧力にさらされながら、旧態依然とした王朝のもとで、もはや時代に適合する能力を失っているかに見えていた自国の状況を打破し、日本と同様の 「改革」 を断行するための決定的な 「秘策」 であるかのように思えたのだろう。 しかし、李に理解できていなかったのは、多民族で構成されながらも、民族なるものの存在を知らずにいた近代以前の 「帝国」 とはまったく異なった、近代に生まれた 「民族」 と、「民族」 を統合した 「国民国家」 なるものの意味である。その無理解を責めるわけにはいかないだろうが、李がやったことは、結局のところ、「前門の虎」 のかわりに 「後門の狼」 を引き入れたにすぎない。 柄谷は、前掲の短文の中で、「日本の植民地経営の原点は北海道開拓にある」 と言っている。それはたぶんそのとおりだ。だが、それは、言うまでもなく、江戸時代の幕府による 「蝦夷地開発」 にまで遡る。歴代の幕閣の中で、最も蝦夷地開発に積極的だったのは、「賄賂政治」 で有名な田沼意次であり、彼は最上徳内に樺太探検を命じたりもしている。 明治政府による北海道開発が、それ以前とは異なって 「何よりもアメリカがモデルにされた」 のは、おそらく柄谷の言うとおりだろう。札幌農学校にかのクラーク博士が招聘されたのは、そのことを象徴しているし、政府主導による近代的で国家的な規模の 「開発」 には、当然のことながら、近代的なモデルを必要とする。だが、それはそれだけの話に過ぎない。 しかし、そのことを根拠として、柄谷が日本による植民地経営のモデルまで、アメリカに求めているのはたぶん間違っている。そもそも柄谷が言うように、アメリカの植民地経営が、「被統治者を 『潜在的なアメリカ人』 とみなすもの」 だとしても、それが 「英仏のような植民地政策とは異質である」 とまでは言えないだろう。実際、植民地の現地人や先住民を文化的に劣ったものとみなし、彼らを 「文明人」 へと教育するという啓蒙的・教化的な植民地政策は、なにもアメリカ特有のものではない。 それは、スペインやポルトガルが 「発見」 し支配した植民地においても、イエズス会などの宣教師らによって早くから試みられている。そもそも、ただの金銀財宝の略奪に留まらない、前世紀における近代的なまるごとの植民地支配は、多かれ少なかれ、現地人の協力を必要とするものであり、その意味では現地人への教育などによる 「教化」と「同化」 という政策は、絶対に欠かせないものでもある。 柄谷が言うのとは異なり、戦前の日本による植民地拡張と統治の特徴は、むしろ天皇制という、ほんらいどう考えても日本固有の制度でしかないものに、たとえば 「西洋の覇道」 に対する 「東洋の王道」 などという、ナショナルな性格を脱色した衣を着せて、天皇制があたかも日本というナショナルな枠を超えて、アジア全体に普遍的な価値として通用するかのごとくに偽装したところにある。 そのような無意識の偽装が可能だったのは、おそらくは欧米による外圧のもと、急遽、突貫工事で建設された 「明治国家」 が持っていた、実態としてのナショナルな国家という性格にもかかわらず、近代的な意味での 「国民」 とその意識がいまだ成立していなかったという 「二重性」 と関係するだろう。 柄谷が言うように、「八紘為宇という肇国の理念」 が、「明治以後の植民地主義イデオロギーにもとづいて、古代の文献を新解釈したものにすぎない」 としても、そのことと彼が指摘する、「アメリカの植民地政策」 とは、おそらくなんの関係もない。「理念」 というものは、たしかに遡行的に解釈され、しばしば捏造されるものでもある。しかし、そこで呼び出された理念が、たとえ欺瞞的にではあれ、必然的に帯びざるを得ない固有の 「歴史性」 とその意味を、柄谷は逆に無視し抹消してしまっているように思える(コメント欄に追記)。 明治国家における 「国民意識」 は、対外意識、とりわけ欧米に対する意識としては成立していた。しかし、内部的な意味、すなわち国家を構成する 「国民意識」 としては成立していなかった。自由民権運動の挫折が意味するものは、そういうことであり、憲法解釈として一時は定着していたかに見えた美濃部の 「天皇機関説」 が、昭和にはいるとともに、「天皇が国家の機関などとはけしからん」 と息巻いた国粋主義者らの攻撃の前に、あっさり敗退したのもそのためである。そこには、「臣民」 はいても 「国民」 は存在していなかった。 その結果、天皇制という制度が、西欧と同じ資本主義を動力とする事実としての 「国民国家」 を統合する、ナショナルな原理にすぎないことが自他ともに明確に認識されず、天皇制が世界に冠たる 「万邦無比」 の原理として、そのままずるずるべったりと、対外的にどこまでも拡張可能であるかのごとき錯誤が生まれた。 内田良平の 「日韓合邦論」 や石原莞爾の 「五族協和論」 から、近衛のブレーンや種々の 「近代の超克」 論者らが掲げた「東亜共同体論」 や 「八紘一宇」 にいたるまで、アジア主義者が掲げた理念は、すべてそのような錯誤に基づいている。そして、そのような錯誤は、事実としての植民地支配とその拡大を正当化し、現実を隠蔽する論理として役立てられることになった。 彼らがいかに、東亜の平和や共存共栄を掲げたところで、それが万邦無比の天皇制の主導を前提とする以上、そこでの 「東亜新秩序」 は、実質的には日本による支配とその拡大を意味するものでしかない。「五族協和」 や 「王道楽土」 うんぬんという民族の楽園も、現実には他の民族の 「皇民化」 を前提とし、それを強制するものでしかありえない。 東条によって予備役へと引退させられた、その後の石原のように、たとえ、いかに現実と当初の自己の理念との乖離を嘆いたところで、そうならざるを得なかったのは、当初の理念に含まれていた錯誤からくる必然にすぎないと言うべきである。
2009.05.03
コメント(8)
-
阿弥陀様と弥勒様はどこが違うか
阿弥陀様と弥勒様がどう違うかというと、まずは阿弥陀様は如来であり、弥勒様は菩薩であるということになる。如来とはすでに悟りを開いた仏のことであり、お釈迦様のほかにも、大日如来や薬師如来などがいる。ようするに、数ある仏様の中でも最高に偉い仏様のことである。 いっぽう、菩薩のほうは、本来まだ悟りに達していない修行中の行者を指す言葉であったのが、やがてすでに悟りの境地に達しているにもかかわらず、われわれ悩める大衆を救済するために、仏陀となることを自らの意思で停止し、この世に留まることを選んだ仏をも意味するようになった。 つまり、菩薩とはおのれ一人の成仏よりも、現世の中で悩み苦しむ多くの庶民を救済することを優先させたという、たいへんに責任感が強く、また慈愛に満ちた方々なのである。なので、まだ成仏していない菩薩様は、すでに成仏した如来様よりほんらい一ランク下であるにもかかわらず、昔から下々の民にたいへん親しまれてきた。 道端に立つ、かわいらしい姿の地蔵様もそうである。なにしろ地蔵様ときたら、子供たちに縄で縛られて引きずりまわされても、けっして怒らない。それどころか、地蔵様になにをするかと子供を叱った人の夢枕に立って、「せっかく遊んでいたのに、なんで邪魔をした」 と叱り飛ばしたという話もあるくらいだ。 阿弥陀様は、念仏で 「南無阿弥陀仏」 と唱えるくらいだから、浄土真宗などの浄土系仏教では、最もありがたい仏ということになっている。ようするに、「一切の衆生救済」 という願いをたてた、無限の慈悲を持つ阿弥陀様のお力にすがることで、われわれ愚かなる人間も救われるということだろう。「無量寿経」 や 「観無量寿経」 とともに、「浄土三部経」 と呼ばれている 「阿弥陀経」 では、お釈迦様が大勢の弟子を集めて、こう説いたとされている。そのとき、仏、長老舎利弗に告げたまはく。「これより西方に、十万億の仏土を過ぎて世界あり、名づけて極楽といふ。その土に仏まします、阿弥陀と号す。いま現にましまして法を説きたまふ。舎利弗、かの土をなんがゆゑぞ名づけて極楽とする。その国の衆生、もろもろの苦あることなく、ただもろもろの楽を受く。ゆゑに極楽と名づく。」 いっぽう、弥勒様は、なんと56億7000万年後にこの世に現れて、大衆を救済するのだそうだ。もっとも、このとてつもない数字というのは、弥勒様は 「兜率天」 で4000年を過ごし、しかもそこの一日は地上での400年にあたるなどという、いろいろとややこしい計算によるもので、経典自体にそう書いてあるわけではないらしい。 社会が乱れ 「末法思想」 が流行した平安末頃には、この遠い未来に現れて大衆を救済するという、弥勒菩薩に対する信仰も盛んだったが、やがて 「西方浄土」 に現におわしますライバルの阿弥陀様に押されて、正規の仏教信仰としては衰退してゆく。 たしかに、56億7000万年は待つにはちと長すぎる。とはいえ、それ以降も、弥勒信仰は民間宗教化しながら、いろいろな形で生きながらえ、ときには 「世直し一揆」 などにも影響を与えたりもしたという。実際に、中国では、弥勒を信仰した白蓮教徒による大規模な反乱も、元の末期や清の時代などに起きている。 ただし、いずれも、いわゆる 「大乗仏教」 に属する経典にでてくる話であり、実際にシャカが説いた教えとは直接の関係はない。阿弥陀様も弥勒様も、広大無限なる 「慈悲」 によって、悩み苦しむ現世の大衆を救済するという点ではよく似ており、どちらについても、イランで生まれたゾロアスター教やミトラ教などの、「一神教」 的性格の強い 「救済宗教」 の影響が指摘されている。 いつの時代でも、貧病苦などの現実の苦しみから逃れられない人間が求める 「救済」 とは、なによりもこの世における 「救済」 なのであって、ただの 「魂の平安」 やわけの分からぬ 「来世の救済」 などではない。ユダヤの神ヤーヴェがノアに約束したのは、地上を彼の子孫で満たすことだし、アブラハムに約束したのは、カナンという 「乳と蜜の流れる約束の地」 であって、いずれも 「来世」 や 「天上」 における救済などという空手形ではない。 池田信夫という人は、「古代ユダヤ教が故郷をもたないユダヤ人に信じられたのも、ウェーバーが指摘したように「救いは地上ではなく天上にある」という徹底した現世否定的な性格のゆえだった」 と書いているが、世界の終末を経て現れる 「神の国」 とは、「天上」 ではなくこの 「地上」 に現れるものとされたからこそ、信者に対して強烈な力を及ぼしたのではあるまいか。 たしかに、その救いは天上の神によってもたらされるものだが、それがもたらされるのは、つねに 「現世」 であるこの 「地上」 においてであって、どこにあるやともしれぬ 「来世」 や 「天上」 においてではない。 むろん、それは原始キリスト教でも同じであり、「ヨハネ黙示録」 に描かれた 「世界の終末」 とは、地上の帝国たるローマが滅びて、彼らの待ち望む 「神の国」 がまもなく現実のものとなることへの期待を託したものである。そのような、遠くない未来への期待があったればこそ、彼らは様々な弾圧を耐え忍ぶこともできたのだろう。 だが、キリスト教が世俗的な権力と一体化し、あるいは自ら世俗的権力となったとき、そのような 「ユートピア」 的思想は異端視され、救済は 「現世」 ではなく、「来世」 におけるものとされることとなった。「世界の終わり」 によって現れるとされた 「神の国」 もまた、すでに教会という形で地上に存在しているものとされ、原始キリスト教が帯びていた 「終末論」 的色彩は危険なものとして否定され、拭い去られることとなった。 洋の東西を問わず、宗教的な 「終末論」 に含まれた 「現世否定」 とは、いまこの地上に存在する現実に対する徹底的な否定のことであり、それは 「天上」 における救済と同じではない。たしかに、しばしばそこには不老不死などのような、現実離れした空想が含まれることもあるが、それもまた始皇帝らがとりつかれたような、昔からある世俗的な人間の夢のひとつにすぎない。 「ユートピア」 とは、いうまでもなくトマス・モアの同名の著書に発する、「どこにもない場所」 という意味の造語である。しかし、歴史においてしばしば 「ユートピア」 思想が大きな影響力を持ったのは、それが、たんなる暇人の空想ではなく、そのような今はまだ 「どこにもない場所」 がすぐそこに迫っていると夢想され、あるいは、ときには神の意思など待たずに、自らの力で 「今・ここ」 において現実化させようという強烈な希求力を人々に与えたからでもある。 モアの 『ユートピア』 と並ぶユートピアの書である 『太陽の都』 を書いたイタリアの人カンパネッラは、地動説を説いて破門されかけたガリレオや、宇宙の無限を説いて焼き殺されたブルーノと同時代の人だが、70年の生涯のうち半分に近い30年近くを獄中で過ごしたという。それは、かの 「陰謀の人」 ブランキに優るとも劣らぬ大記録である。 彼もまた、そのような 「ユートピア」 がすぐそこに迫っており、現実化が可能だと考えたからこそ、激しい拷問と長い幽閉に耐え、ときには狂人のふりをするといった手練手管をも使いながら、ソクラテスのように従容として死を受け入れるのではなく、恥も外聞も気にせずに、ただひたすら生き延びるということを優先させたのだろう。 最後は、またまた出だしとはえらくかけ離れた話になってしまったが、タイトルはそのままにしておく。そうそう、草なぎ君の例の 「事件」 については、何人かが非難めいたことを言っていたが、そのほとんどは 「お前が言うなー」 という類のものであった。鳩山大臣もテリー伊藤も、いったいどの口で言うとしか言いようがない。
2009.04.27
コメント(6)
-
「解説する者」と「解説される者」との関係
昨日は一日曇っていたのに、今日は抜けるような青空だった。一日空を覆っていた灰色の天幕は一夜明けただけで魔法のように消え、足に力を入れて跳びあがればそのまま大気圏外にまで飛んでいけそうな青空になった。春はまことに天気の移り変わりが大きく、それに応じて、人の気分もころころと猫の目のように変わる季節である。 誰が言い出したのか、世界の 「三大哲人」 というと、インドの釈迦にギリシャのソクラテス、それに中国の孔子様ということになっている。これに、さらに中東で生まれたキリストを加えて 「四大聖人」 という呼び方もあるらしい(ソクラテスのかわりに、イスラムの開祖ムハンマドを入れる場合もあるようだ)。 鎌田東二という人(よくは知らないが宗教学者だそうだ)によれば、この 「四大聖人」 という呼び方を考案したのは、『武士道』 で知られる新渡戸稲造と講談社なのだそうだ(参照)。鎌田が言う、明治から大正にかけての 「修養」 ブームの時代とは、たとえば一高生の藤村操が 「不可解」 なる言葉を残して華厳の滝に身を投げた時代であり、夫人によれば 「狂人」 のごとき怒れる人であった漱石が、その死後には弟子らの手で 「則天去私」 の偉人へと神格化された時代でもある。 また、西田幾多郎の 『善の研究』 が多くの青年に読まれ、倉田百三が 『出家とその弟子』 を書き、人道主義を掲げた白樺派が登場し、その一方で西田天香の一燈園 注1や山室軍平の救世軍、その他、仏教系や教派神道系の様々な宗教団体の活動が活発化し、多くの悩める青年がそういった団体に身を投じた時代でもある 注2。亡き父の回想によれば、草生す田舎の神官の家から都会へと出てきたわが祖父もまた、そのような青年の一人であり、若い時期には天理教から大本教まで、いろんな宗派を渡り歩いていたのだそうだ。 鎌田の言うとおり、東洋と西洋を含む世界の文明圏から、それぞれ無難なる代表者を選んで並べあげるという発想には、いかにも昔からなんでも折衷させることが得意だった日本人らしさがにじみ出ている。それは、後発文明国の知識人特有の劣等感と、その裏返しである肥大した意識、すなわち東西の文明という二人の巨人の肩の上に乗っているだけで、その両者を乗り越えたかのように思い込む小人的高慢さとの奇妙な混合物でもあり、小は思い付き的な 「東西文明融合論」 から、大は 「八紘一宇」 などという夜郎自大な妄想にまで共通している。 「世界に冠たるドイツ」 とは、三月革命前のいわゆる 「メッテルニヒの反動時代」、いまだドイツの統一ならざる時代に、国を追われて放浪していた詩人が統一の悲願を込めて作った詩がもとになっているそうで、もともとは別に 「世界征服」 などという恐ろしい野望が込められていたわけではなかったらしいが、やがてドイツ・ナショナリズムを鼓吹する歌として熱狂的に唱和されるようになる。 また、話がそれてしまった。さて、上にあげた四人に共通する点と言えば、いずれも自己の著作を残さなかったことだ。釈迦の言葉はその死後に 「仏典」 として結集され、孔子の言葉は 『論語』 として、ソクラテスの言葉はプラトンやクセノフォンによって、そしてキリストの言行は、言うまでもなくルカやマタイによる 「福音書」 として、現代にまで伝えられている。 で、彼ら弟子たちが師の言葉をなぜ書に残したかというと(中には、すでに伝承された言葉でしか、師のことを知らない者すらいた)、それは言うまでもなく、身近に聞き、または伝承によって知った祖師の言葉に深く感銘したからだろう。「述べて作らず」 とは孔子様の言葉だが、彼らの弟子もまたそのような態度に徹した。それは、おのれが決して師の足元にも届かぬという自覚があったからに違いない(ただしプラトンは除く)。 もっとも、孔子自身は 「後生畏るべし」 とも言っていて、若い人が秘めている可能性についても素直に認めている。このへんは、なにかというと「いまどきの若い者は」などと言いたがる、われわれ愚昧なる大衆とは、さすがにできが違う。この言葉は、さらに 「四十、五十にして聞こゆることなくんば、これまた畏るるに足らざるのみ」 と続いていて、これもまたそのとおりである。諺には 「亀の甲より年の功」 というが、いつもいつも年の功が亀の甲よりも優るとは限らないということだ。 さて、三度話は変わるが、イチローが日本のプロ野球とメジャーの試合で放った通算安打数が、ついにあの張本の記録を抜いたそうである。これは、まさに孔子様の言う 「後生畏るべし」 の好例と言うべきだろう。 スポーツの世界では、どんな名選手も年齢には勝てない。体力の衰えとともに、いつかは引退を余儀なくされ、指導者や解説者としての二度目の生を送らざるを得ない。テレビなどでの彼らの解説が的を得ており、思わず、うんうんと頷いてしまうのは、言うまでもなく、彼ら自身がかつては好選手であり名選手であったからである。 ところが、世の中には奇妙な解説者というのもいる。「批評家」 と称される解説者がそれである。作家と批評家とは一般にコブラとマングースのごとき 「不倶戴天」 の関係にあり、作家の中には 「批評家」 なんて者は、実作者に憧れながらその才能がなかった連中にすぎないなどという酷評をする人までいる。たしかに、それはそれで一理ないわけでもない。 一般に、誰かについて 「解説する者」 は、その対象が優れていると思っているからこそ解説をする。これは当たり前のことで、なにか特別な必要性などがない限り、しょうもないものやつまらないものについてまで、わざわざ自分の限られた時間を費やし、手間暇かけて解説しようなんて酔狂な人間はいない。 ということは、だいたいにおいて 「解説する者」 と 「解説される者」 とでは、一般に 「解説される者」 の方が優れているということだ。そして、そのことは 「解説する者」 は往々にして 「解説される者」 のすべてを理解する能力を持っておらず、ただ自分の理解力に応じた、自分が理解したと思ったところだけを(それは、しばしばただの勘違いだったりもする)解説したり、ときにはしたり顔で批判して見せたりすることもあるということだ。 つまり、なにが言いたいかというと、世上にはマルクスだ、ニーチェだ、フロイトだのと、いろんな歴史上の偉い人の思想とやらを分かりやすく解説してくれる人がいるそうだが、たいていの場合、それはその人が理解したと思っているマルクスであり、ニーチェであり、フロイトであるに過ぎず、したがって、そんなもので分かったと思ってはいかんだろうということだ。 ましてや、まともに原著者の著作に当たらずに、そのへんの二流・三流思想家の 「批判」 なるものを読んだだけで、原著者の思想について批判めいたことを語るのは、まったく馬鹿げたこととしか言いようがない。「学びて思わざればすなわちくらし。思いて学ばざればすなわちあやうし」 とは、これまた孔子様のありがたいお言葉である。 そもそも百年・二百年を経て今なお名前が残り、その著作が多くの人に読み継がれてきたような人、言い換えるなら、百年に一人、現れるか現れないかのような偉い人の思想について、簡単にまとめた解説ができる人など、おいそれといるわけはないのである。注1. 馳浩衆院議員や、ヤンキー先生こと義家弘介参院議員などらで、「国会掃除に学ぶ会」 というものが作られ、国会内での素手でのトイレ掃除が率先して行われているらしいが、その発祥はどうやらこの団体ではないかと思われる。注2. それは大雑把に言えば、明治以来の急速な近代化に伴う社会的変動によってもたらされた 「故郷喪失による不安」 の時代であり、昭和初期の左翼運動が盛んだった時期をはさんで、そのほとんどは超国家主義運動へと合流することになる。
2009.04.17
コメント(4)
-
「スターリン言語論」の怪
前々回、スターリンの民族論に触れたが、民族に関する彼の定義は、「言語、地域、経済生活、および文化の共通性のうちにあらわれる心理状態の共通性を特徴として生じたところの、歴史的に構成された人々の堅固な共同体」 というものだった。 つまり、彼にとって 「民族」 の問題と 「言語」 の問題は、最初から切っても切れない関係があったということだ。その彼が晩年の1950年(当時すでに71歳!)、脳卒中で死亡する3年前に発表したのが、当時ソビエト言語学界を支配していたマール理論を批判した 「言語学におけるマルクス主義について」 という論文である(参照)。 この論文は、前々回にも触れた典型的な 「カテキズム」 形式で書かれている。たとえば、次のように。問 言語は土台のうえに立つ上部構造であるというのはただしいか? 答 いや、ただしくない。問 言語はいつでも階級的なものであったし、いまもそうであるということ、社会にとって共通かつ単一な、階級的でない、全人民的な言語は存在しないということは、ただしいか? 答 いや、ただしくない。 つまり、ここでは彼は、自分より格下の弟子からの 「問い」 に対して、けっして疑ってはならないご託宣のごとき 「真理」 を与える教祖様として振舞っているわけだ。むろん、それは 「偉大なる指導者」 である 「偉大なる同志」 スターリンとしては、当然の振る舞いではあるだろう。 この論文の意味は、上の二つの問いに対する回答に表れているように、言語の 「上部構造性」 と 「階級性」 の否定ということにつきる。田中克彦などの紹介(参照)によれば、彼が批判したマール理論というものには、たしかに荒唐無稽なところもあったようだが、この二つの否定が、マルクス主義の基本的な常識にまったく反したものであることは言うまでもない。 もし、これが他の者の言葉であるなら、おそらく一顧だにされていなかっただろうが、なにしろ 「偉大なる同志」 のお言葉である。あだやおろそかにするわけにはいかない。そこで、この 「論文」 を読んだ当時の共産党系の学者や理論家らは、びっくり仰天しながら、それまでの 「定説」 の書き換えや、後付けでのもっともらしい説明に苦心し、阿諛追従に走り回らざるを得なかった。ご苦労なことである。 さて、この論文での彼の言語観は、「言語は......生産用具、たとえば機械とはちがわない」 とか、「言語は手段であり用具であって、人々はこれによって、たがいに交通し、思想を交換し、相互の理解にたっするのである」 といった、その目的や効用のみに着目した典型的な 「言語=道具説」 である。 しかし、どう考えても、言語は機械のように手で触れるものでも、目に見えるものでもなければ、人間の意識の外部に、人間の意識と無関係に存在するものでもない。発話し解釈する主体としての人間と切り離してしまえば、音声としての言語は、オシログラフ上で一定の波を描く、ただの空気の振動にすぎない。 たしかに個々の人間にとっては、言語は規範としての 「外在性」 を有している。言語は、それを知らぬ人間にとっては、そこにあるものとしてまず学ばなければならないものである。だが、言語を学ぶということは、最初は自己の外部にわけの分からぬものとして存在していたものを、自己の内部へと取り込み 「主体化」 する過程にほかならない。 その一点だけでも、言語は、人間の外部にあって、目的に応じ好き勝手に利用できるただの道具などとはまったく異なるはるかに複雑なものである。そもそも、言語が人間の意識や主観と不可分な 「観念的存在」 である以上、その 「上部構造性」 を否定することはとうていできない。 スターリン時代には、しばしば科学や学問の 「階級性」 や、「ブルジョア科学」 に対する 「プロレタリア科学」 の優位ということが強調された。相対性理論や量子力学などの現代物理学が、唯物論に反する 「ブルジョア科学」 として否定された時期もあった。とりわけ、メンデルの遺伝法則を否定して獲得形質の遺伝を主張したルイセンコ学説の話などは、今も有名な語り草である。 西欧言語学の定説と鋭く対立したマール理論が、一時期ソビエト内で支配的位置を占めたのも、おそらくそれと同様の理由によるものだろう。しかし、そういったきわめて政治的な 「国威発揚」 のためのプロパガンダに過ぎない 「プロレタリア科学」 なるものは、どれも結局は現実の前に敗北した。ルイセンコ学説の 「ニセ科学性」 は、農業の不作による飢饉の発生という現実によって明らかにならざるを得なかった。 第二次大戦が終結し、ソビエトがアメリカと並ぶ 「大国」 としての地位を確立したこの時期に、スターリンがマール学説の批判に乗り出したのは、そのような旧来の独善的な 「プロレタリア科学」 なるものが、大国として世界の表舞台に登場することとなった、ソビエトの科学や学問の発展の足かせになっているという判断も、おそらくはあったのだろう。 しかし、そのような悪弊の是正は、「偉大なる指導者」 スターリンの個人的権威の行使という、これまたきわめて政治的な方法によって行われた。これは、「粛清」 や 「弾圧」 の責任を、直接の担当者であったヤゴーダやエジョフといった部下に押し付けて、自分の無謬性を守りながら、かえってその神格性を高めたやりかたと同じ、ただのトカゲの尻尾切りにすぎない。 ところで、このスターリン論文については、国語学者である時枝誠記が次のような疑問を呈している(参照)。言語は、たといスターリン氏が単一説を主張しても、歴史的事実として、そこに差異が現れ、対立が生じるのは、如何ともし難い。もしそれを階級といふならば、言語の階級性は言語の必然であつて、これを否定して単一説を主張するのは、希望と事実とを混同した一種の観念論にすぎない。「スターリン『言語学におけるマルクス主義』に関して」 言語の 「階級性」 という、本来ならマルクス主義者こそが強みを発揮しなければならない問題について、マルクス主義者ではない時枝のほうが正しく認識していたというのは、なんとも皮肉な話である。 最近刊行された伝記によると、彼は国家の最高指導者という激務をこなしながら、なんと1日500ページもの読書をこなしていたそうだ。彼はたしかに、レーニンのような緻密な思考や、トロツキーのような輝かしい才気こそ持っていなかったが、人並みはずれた強靭な意思と能力を持った人物ではあった(参照)。 なにしろ、ブハーリンのように、若い頃からの付き合いがあって、彼を正面きって批判したことなど一度もない長年の 「友人」 ですら、でっちあげの罪を着せて 「銃殺」 することをためらわなかったような人物なのだから。 いったい、彼はなぜ、あれほど多くの、それもすでにほとんどが政治的にはまったく無害であり無力であった、かつての 「同志」 や 「友人」 、有能な党幹部や赤軍将校らの血を欲したのか、それもナチによる脅威が目前に迫っている中で。これこそまさに20世紀における最大の謎というべきだろう。 たしかに、この30年代末期の 「大粛清」 には、ナチとの衝突という予想される危機の中で、自己のライバルとなりかねない可能性を持った人材をあらかじめ一掃しておくという意味もあったのかもしれない。また、革命第一世代のほとんどを抹殺することで、その歴史と記憶を書き換えることにも成功した。その結果、彼は神のごとき全能の 「独裁者」 へと、また一歩近づいたわけではあるが。 歌舞伎に出てくる河内山宗俊には、かどわかされた町娘を取り戻しに大名屋敷に乗り込んで言い放った、「悪に強きは善にもと」 という名台詞があるが、古今東西の歴史には、巨大な悪をなしとげた巨大な人物というのも、たしかに存在している。彼もまたその一例ということなのだろう。
2009.04.13
コメント(4)
全357件 (357件中 1-50件目)
-
-
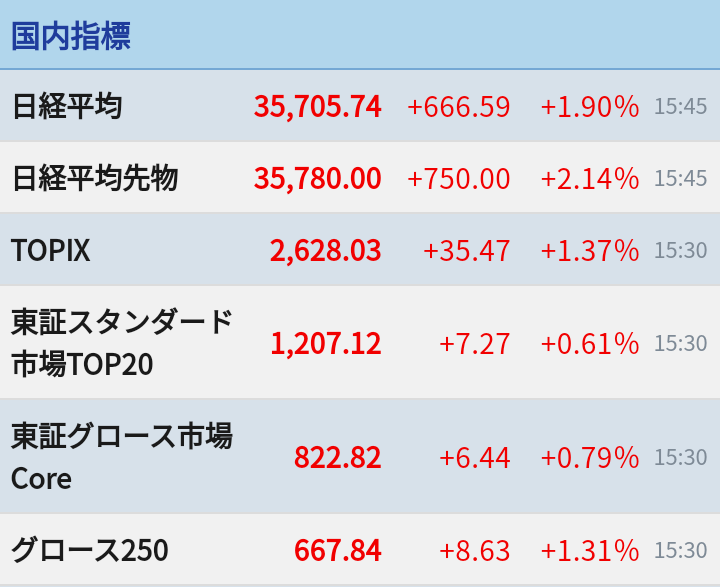
- 株式投資日記
- 株式資産も暗号資産も回復中!中長期…
- (2025-04-25 17:33:11)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-04-25 18:40:02)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 金星と土星がコンジャンクション
- (2025-04-25 19:50:56)
-







