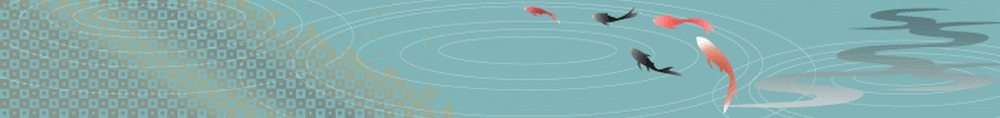唐草と防水膜の設置が完了したので、 一文字葺の本体部を設置した。軒先から設置する。本体は右山(右はぜ)なので、軒の左から右に葺いていく。

本体の固定は、「吊子(つりこ)」と呼ばれる折り返しのある短冊状の金具を介して行う。本体自体に穴を開ない工夫のようだ。吊子の固定には、ステンレス製のスクリュー釘を使用した。

本体は、 各本体の「はぜ」同士をかぎ手のように引っ掛けて設置していく。配置は列ごとに2分の1幅ずらした千鳥配置とした。この配置も、浸入した雨水を速やかに下流側の本体上面に排水するための工夫だ。
軒からはみ出た本体は切断し、下面に既設の唐草を巻くように折り曲げて端部の固定を行う。この時、水平方向のはぜは、折り曲げ部分に含まれないよう切り取る。

軒と壁面の接合部は、旧トタン板を残し、これを上から覆うように新しい鋼板を設置した。残した旧トタン板部は、モルタル壁面の裏側まで続いており、雨水の浸入から壁面本体を護っている。このため、この旧トタン部を交換するためには、モルタル壁面を部分破壊しする作業を伴う。幸いこの旧トタン部に錆等の問題はなかったため、大事を避けた次第だ。

この部分は吊子で固定できないため、軒側と壁面側に対して直接釘を打って固定した。最後にかみ合わせた「はぜ」部分を潰さない(カシメない)程度に一様に叩き慣らす。
以上で完成。
鋼板部材の現場合わせに時間が掛かったものの、その設置自体は短時間の作業だった。

軒の下側から見た様子。周囲(軒先とけらば)は、本体を折り曲げて唐草に引っ掛けてあるだけだ。この部分もカシメてしまうと排水性が損なわれる。顕著な毛細管現象が発生しない程度の折り曲げに留意した。

今回のDIY、特にガルバリウム鋼板の加工作業は、私が行ったDIYの中で最も大変な作業となった。良い経験になったが、次は既製品を使いたいところだ。
(おわり)
-
【DIY】トラックボールの右ボタンのスイッ… 2024年06月03日
-
【DIY】自宅の鉄部の再塗装 2023年06月21日
-
【DIY】キッチン水栓の交換(2023) 2023年06月03日
PR
キーワードサーチ
コメント新着
サイド自由欄