「パリスの壺」(一)~
「おっはよう」誰かが追い越しざまに私のお尻を触りました。
「きゃっ」と叫んだ私に振り向き、犯人の男性はこう言いました。
「しまった、歩美女史のおケツであったか。後ろ姿にしてやられた。広報の有香ちゃんで口直ししてこよう」
ぺろんと舌を出し、彼はエレベーターに駆け込んでいきました。
私は三十一才、独身です。社内では『鋼鉄の処女』というあだ名を頂戴しています。過去、男性とお付き合いしたことはおろか、片思いさえ経験したことがありません。
理由は簡単、私はブスなんです。父も母も、姉も弟も美男美女の中で、私だけが醜いんです。物心ついた時から様々な場で、自分だけが「つんぼ桟敷」に置かれた悲哀を何度も味わいました。私だけが「可愛い」と言われない。私だけが愛されない。幼稚園に通い始めたばかりの子供がそんなことに気付く・・・・・・悲し過ぎると思いませんか。
どう生きたらいいんだろう。一人、砂場遊びを装い真剣に考えました。考えた末、ある結論に達しました。それは「人を愛さない」こと。団子虫みたいに固い殻をかむり、丸まって小さくなって、出来るだけ人様の目に触れないこと。私みたいなブスが傷つかず生きるためには、そうするしか無いと考えたのです。
仕事を終えた後、私はよく街をうろつきます。といっても、別に遊び廻っているわけではありません。きらびやかなショウ・ウインドウの奥に、もう一つの世界が在り、誰からも愛される自分がいる、そんな夢をみるために。
その日も私は、あるアンティ-ク・ショップの店先にいました。のどかな田園風景を描いた絵皿と、揺り椅子に腰かけたお人形。「あなたはわたし。わたしはあなた」と呼びかければ、温かな木漏れ日と異国のそよ風が私を包んでくれます。
ぽんと誰かに肩を叩かれ、すぐに私の夢想は途切れました。
「そんな所に立っていないで、お店の中に入りなさい」
声をかけてきたのは、鎖付きの銀縁眼鏡をかけたご婦人でした。淡いグレーのセーターに茶色いスカート。橙色のカシミア製ショールで肩を被い、胸にはアネモネを描いたエマーユのペンダントをさげています。髪は柔らかそうな銀髪で、頬や額に刻まれた皺さえも、その上品な面立ちを一層引き立てていました。
「ひやかしで構わないわ。さあさ、早く」という言葉を信じ、彼女の後に従いました。部屋の中央には小さなアクセサリー類を乗せた円卓があり、それをコの字に囲んで背の高いキャビネットが置かれています。中には、ブロンズ製の燭台やエナメルがけのガラス壺、浮き彫り模様の銀製時計や、象牙細工の宝石箱にマイセン・セーブルなどと思われる陶磁器類、述べればきりがありません。ようするに、私のような女には一生縁がない、高価な品々がひしめいていたのです。
緊張のあまり窒息寸前の私に、彼女は椅子をすすめました。
「店先に立つあなたを見てピンときたの。これが役に立つ時がきたって」と、テーブルの上に乗せたのは、頸の長い古代ギリシャ風の壺でした。
「レキュトスと言ってね、紀元前四世紀頃に焼かれた赤絵の香油壺なの。手に取ってごらんなさい」
私は、それを恐るおそる手のひらで抱き上げました。まず目を惹いたのは、胴に描かれた不思議な人物達です。向かって左手には、房飾りのついた日傘を持ち、薄い襞付の衣をまとう貴婦人がいます。中央二人のキューピット(正しくはエロスと呼ぶんでしょうか?)を挟んだ右手には、性器も露な全裸の男性が相対しています。彼は手の上で黒猫を遊ばせながら上目遣いの視線を投げ、女性もそれにこたえて左手で月桂樹の冠を差し出しています。
「もちろんこれは後代のコピーで大きさもオリジナルの半分以下。けれど、本物にも負けない神秘な力を秘めているの。私はこれを『パリスの壺』と呼んでいるわ。ギリシャ神話やホメロスの『イリアス』は御存じ?」
「いえ、まったく」
「だったら、なおさら好都合だわ。あなたは『この壺を持つ人には至上の愛が訪れる』とだけ憶えていればいいの。御代はいくらでもいいわ。あなたが妥当と思う金額を置いてちょうだい。いえ、いっそ無代で差し上げても構わないわ」
「あの・・・・・・」
「なに、遠慮せずに言って」
「失礼ですが、お話の意味が解りません。商談のお積もりでしたら、私は何もいりませんせんから、これで失礼したいんです」
「じゃあ率直に言わせてもらうわ。あなた、一度も恋愛の経験が無いでしょう。私、あなたに初めての恋をプレゼントしたいの」
今出会ったばかりの人にそんなことを言われ、きゅんとこめかみが疼きました。そして今朝の出来事を始めとする屈辱の記憶が、果皮を食い破る虫のように頭から這い出してきました。羞恥に赤らむ顔を、私は無理矢理な憤りで隠さざるを得ませんでした。
「放っておいてください。あなたには関係ないことでしょう」
バッグを肩に掛け立ち上がる私に、彼女は臆することなく言いました。
「やっぱり怒ると思った。でも、これだけは確実よ。あなたは必ずこの壺が欲しくなる。そしてもう一度、私の許を訪れる」
きっ、とその顔を睨みつけたあと、私は早足で出口に向かいました。
それから二日後のことです。上司から書類探しを命じられ、私は資料室に出向きました。誰か先客がいるらしく蛍光灯が点っています。書架の陰から男女の話し声が聴こえました。
「絶対そうだよ。××さんだって、そう思わない」
「やだあ、××君たら、私が先輩の悪口言える訳ないじゃない」
二人とも同じ課の後輩です。思わず息を潜め聞き耳をたてました。
「悪口じゃなくて本当のことだよ。歩美女子、絶対にまだ処女だ」
この一言で私は完全に凍ってしまいました。書架の向こうで足音が動き出しても、その場を動くことが出来ません。
「分かんないわよお、案外ブリブリに遊んでたりして。あの猫背だって水子の重みが原因かもね」
「よしてくれ。あんなかび臭いオバン、金もらったって御免だ」
「あっ、ひどいこと言う。本人に聴かれたら呪い殺されるわよ」
目の前に二つの影が流れ出てきました。つづいて革靴の爪先が・・・・・・
「だけどさあ、あのひと何が楽しみで生きてるんだろう。痛っ、なんだよ。なんでつねるんだ。あっ」
もう勘弁して下さい。私は、この後を語れるほど、強い心の持ち主ではありません。
けれど、もう限界。パンクした心の押入からぎゅうぎゅう詰めの自我が飛び出して、怒れ、怒れ、と騒ぎ立てます。あの人達を見かえしてやりたい。私への嫉妬や羨望で身もだえさせてやりたい。自分にその力が無いのなら、だれか他人の手を借りてでも。
こぶしを震わせ、唇を噛む私の頭を、二日前に見たあの壺がよぎりました。
「いらっしゃい。やっぱり来たわね」
声をかけられた途端にまぶたが熱くなりました。急いで顔を覆いましたが、もう涙は止まりません。
「よほど辛いことがあったのね。いいわよ、思いきりお泣きなさい」
泣きじゃくる私の背中を、彼女は優しく摩ってくれました。その温かい掌のおかげで私は少しずつ落ち着きを取り戻しました。
「さ、涙を拭いて。幸せは、すぐそこまで来てるんだから」と言いながら、彼女はパリスの壺を私に抱かせました。
「あなたにあげるわ。午前零時になったら、この壺を鏡の前に置きなさい。神にも似た美しい男性が、あなただけのものになるから。ただし、あなたは『彼』に何も求めてはいけない。物やお金はもちろん、自分への優しささえも。彼と一緒にいる、ただそれだけに幸福を見いだしなさい。この注意を守らなければ、彼はおろか今後いっさいの恋も、あなたは失うはめになる。それだけの覚悟はおあり」
「はい」
「本当にいいの。後戻りはきかないんだから、返事は良く考えてからでいいのよ」
もう一度「はい」を繰り返す私は、正直言って上の空でした。とにかくパリスの壺を手に入れて帰りたい。その思いだけで頭はいっぱいだったのです。
まもなく午前零時です。壺を鏡台の上に置き、時が満ちるのを待ちました。
思い切りおめかしした私は、まるで逆立ちしたシンデレラ。ばかばかしいとお思いでしょう。私だって普段の心理状態ならあんな話は信じません。けれどその時の私は、なにか夢みたいなものにすがらなければ、死神の手招きに抗うことは出来なかったのです。
あと一分、それまでゆっくりだった秒針が、急に速く廻り出しました。いざその瞬間が近付くと、期待は見知らぬものへの恐怖に変わりました。三本の針が重なる直前、私は思わず顔を伏せました。
「カチリ」ついに来た。
ふたたび小さく、秒針の歩む「コッコッコッ」と言う音。
そっと頭を上げました。壺はそのまま鏡台の上、魔法のように煙を吐いた気配すらありません。私は? と鏡を覗けば、厚塗りの油絵みたいな顔が醜く歪みます。我ながら見られたもんじゃありません。泣きたい衝動にかられベッドに駆け寄りました。するとそこに、信じられない光景があったのです。
青い掛け布団の上、真っ裸の男性が横たわっているではありませんか。
尻餅をつき、そのまま衣装ダンスの陰まで後ずさると、私は小さく身を丸めました。
一大事です。けれど言葉の記憶が消え失せてしまい、助けを呼ぶことが出来ません。逃げ出そうにも、膝の関節ががくがくと揺れ、立つことすら覚束ない有様です。
なす術も無いままに時間が過ぎました。彼はまったく動きません。こちらに背を向けたまま、ベッドを占領し続けています。まさか、死んでる? 幸い震えは徐々に収まり、手足に力が入るようになりました。今なら部屋を逃げ出し、助けを呼ぶことも可能です。でも、この状態を他人にどう説明すればよいのでしょう。少なくとも生死の確認はしなければ。低く身構え枕元に近づくと、腰を引きながら首だけを長く伸ばしました。
「きゃっ」慌ててタンスの陰に引き籠もりました。彼の目が開いていたからです。起きてた、そう思いましたが、すこし間をおいてもまだ動かないので、もう一度たしかめてみる気になりました。
私は再び彼に近づきました。大きな瞳にどきりとさせられましたが、今度は飛び退きません。「もしもし生きてますか」小声で呼びかけてみましたが返事はありません。そっと腕に触れてみると、温もりを感じます。勢いを得た私の手は、彼の左胸に移動しました。鼓動が手のひらに伝わります。
「よかった、生きてる」と安堵の息をついた時、恐怖はすっかり消え失せていました。代わりに思い出したのは、鏡台に置かれた壺のこと。ひょっとしたらこの人が。
夜が明けました。状況は何ひとつ変わりません。このまま部屋を空ける訳にいかないから、会社を休むことにしました。けれど私がすることと言えば、ベッドの側に座り、動かない彼を見守るだけ。
それにしても、美しい人です。栗色の髪は光の渦を巻き、肌はひたすら白く、ひとつの染みもありません。眉間から真直ぐ勾配を描いた鼻筋は大人の利発さで、頬の間ちょこんと朱い橋を渡す唇は少年の愛らしさで、私の女心を惹きつけるけれど、それ以上に素晴らしいのは、昼も夜も遠い星に焦がれているような鳶色の瞳です。その奥に吸い込まれたら、どこかの星座にたどり着けるかも。じっと見つめれば、我知らず詩的な夢想にひたってしまいます。
間違いなく世界一の美青年です。いえ、女性でも彼を凌ぐ人はいないから、世界一美しい人間です。その人がどうして私の部屋に来たのでしょう。やはりパリスの壺が起こした奇跡、としか説明しようがありません。
近所の工場で昼休憩を告げるチャイムが鳴りました。私は、彼に何か食べさせてあげようと思い立ちました。あり合わせの材料で作ったオムライスとサラダ。貧相ですが、唯一自信のある手料理です。
「はい、お口をあけて」スプーンを口元まで運びました。反応はありません。
「おなか空いてないの? 何か食べないと死んじゃうわよ」何度か試したけれどやっぱりだめです。諦めた私は、自分の分も口にせず、また彼を見つめることにしました。
その後ふと我に返った時には、すでに夕陽が彼の肌を薔薇色に染めていました。時の速さに驚く私は、恋人達の時間が存在することを、これまで知るよしもなかったのです。
彼をひとり部屋に残すのは不安だけれど、昨日のように会社を休む訳にはいきません。今日が伝票の締日なのです。
身支度をして玄関を出ようとした時、彼の横顔がどこか寂しそうに見えました。私はベッドの傍まで引き返し、「いい子にしててね」と囁いて彼の頬にキスをしました。そのあと駅への道すがらや満員電車の中で、ほころぶ顔を隠すのに苦労しました。
朝礼が済んで、皆が席につきました。向かいにはあの二人、陰口の主達が並びます。女性の方は髪で顔をかくすようにうつむき、男性は脚を組み、ふんぞり返って業界新聞を眺めています。気にならない、と言えば嘘になりますが、じっさい私には仕事を片づけるほうが大事でした。
残業はしたくない、一刻も早く彼のいる部屋に帰りたい。針先のように集中する精神、こまねずみのように動く手。左手にある伝票の山が、びゅんびゅん右手に移動します。
勤続十二年はだてじゃありません。たかが紙束に負けるもんですか。腕まくりをしました。気合いが入りました。昼御飯も食べずつっ走りました。疲れなんか感じません。伝票が片づくにつれ、机に彼の顔が浮かぶようでした。
「終わりました。明日の朝までに印鑑お願いします」最後の一束を課長の机に置いた時、定時の鐘が鳴りました。
「馬鹿に早いじゃないか。手抜きしてないか」
「いいえ、全部見直ししてあります」
「そうか。じゃ、ワープロでも頼むかな」
「だめです。予定があるので、定時で失礼します」
一礼するやいなや、私は、まだ電話のベルや話し声が飛びかうオフィスを飛び出しました。
帰りの電車の中で考えました。部屋に帰ったら、最初に何て言おうか? 「ただいま、いい子にしてた」「寂しくさせてごめんね」どの文句も期待を膨らませてくれるけど、今一つ物足りない気がします。何だろう。そう、私はまだ彼の名前を知らないのです。どうせ訊いても答えてくれないから、私が勝手に決めてしまいましょう。
ヒロシ、ヨシオ、カズヤ・・・・・・どうもしっくりきません。どう見ても彼は西洋人だから、クロード、ジュリアン、ピエール・・・・・・だめだめ、キザっぽくていけません。もっと神秘的な名前はないものかしら。アキレス、アポロン、ヘラクレス・・・・・・なんとなく大げさでイヤ。いっそ単純に壺の名前をとってパリスではどうかしら。うん、すっきりしていい感じ。あの人のイメージにぴったりだわ。これに決めた。
「ただいま、パリス」部屋に帰ったとたん、私は彼の名を呼び、その胸に頬を擦りつけました。
「いい子だった? 一人で寂しくなかった? 私、あなたのために頑張ったのよ。すごく沢山のお仕事を残業なしでやり切ったのよ。ほめてちょうだい」
彼の顔から首筋・肩まで、私は猫のような頬ずりで埋め尽くしました。
「うちの課長ったらひどいのよ。定時過ぎなのにワープロ打たせようとするの。もちろん断ったわ。でなきゃ、こんなに早く帰れないもの。さっ、他の人なんて忘れて、二人の夜を過ごしましょ」
けれど、物事は思うように運びません。パリスと違って、私は普通の人間なのです。まず食事を摂ったり、お風呂に入らなければいけません。さらにやっかいなことに、湯上がりの身体が急に疲れを思い出しました。パリスが現れた一昨日の夜から二・三時間しか眠っていないし、そこへもってきて今日の仕事のハイペース。洗い物やアイロンがけ、あれこれ済ましてみれば、もう十時前です。恋人を見つめる時をとるか、身体を休める眠りをとるか。意地悪な天使の時計が、私の心を揺さぶりました。
私がそれを決心したのは、けっして情欲からではありません。女らしさと呼ばれる専制君主から純粋な私自身を取り戻して彼に捧げたい、そんな熱望に促された結果だったのです。謙虚さ、慎ましさなど、本来、女性としてより良く生きるため身につけたはずの性質がいつの間にか自分になり代わり、横暴な主のように振る舞っている実態に、私は逆らおうとしたのです。
「パリス、いいよね。こんなことしても」
私は一糸まとわぬ姿となり、ゆっくりとベッドに身を置きました。そして飼い猫のように、彼の懐に身を寄せました。
温かい! そのぬくもりは、まるで春の日だまりみたいに心地よいものでした。こうして見上げると、彼の顔つきは頼もしく、私を守っていてくれるようにさえ見えます。
もう目を閉じていいのです。私達は一晩中、肌と肌で語り合える。夢の中でも離れない。おやすみなさい。
ぼんやりと霞みがかった晴れ間を、銀色の飛行機が横切ります。ねこやなぎ、たんぽぽ、しろつめくさ、川の中で吹き流しのように光る魚たち。河原を離れ、ふき畑に添った小道を歩くと、茅葺屋根の家が見えてきました。庭に咲く火花のようなハナズオウを見て、自分がどこにいるか分かりました。
おばあちゃんの家、つまり母の実家です。
ただ一人、私を可愛がってくれたおばあちゃん。気がつくと私はおばあちゃんと並び、陽のあたる縁側に座っています。唄に合わせて、くるくるお手玉が回りました。最初は二つだったお手玉が、手のひらから生まれるように数を増して、とうとう数え切れなくなりました。それをじっと見てるうち、私は睡くなりました。薄らぐ意識の中、「これは夢なんだ」という自分の声を聴きました。
大好きだったおばあちゃん。「またおいで」って言ったのに、いつの間にか会えなくなったおばあちゃん。「さよなら」もしてないのに、あなたも、あの家も、きれいだった田舎の春も、私から遠のいてしまった。
涙が頬を伝いました。でもそれは、私に欠けていた何かを補ってくれる不思議な涙でした。
(五)へ続く
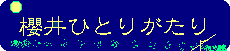
© Rakuten Group, Inc.






