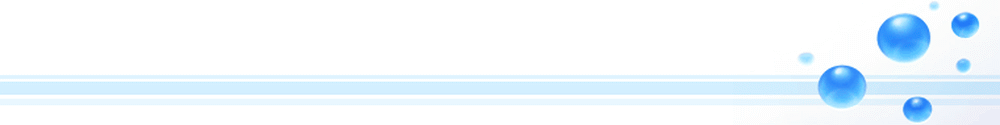第十七幕~第二十一幕
本作品は、 「るろうに剣心小説(連載1)設定」 をご覧になってからお読みいただくことをおすすめいたします。面倒とは思いますが、多少オリジナル要素が入りますので、目を通していただきますと話が分かりやすくなります。
『きみの未来』目次
『きみの未来』
第十七幕「なくした笑顔」
飛天御剣流の修業を開始してから、早二週間が立とうとしている。その日弥彦は、修業開始からまだ一時間もたたぬというのに、力尽きて立ち上がることが出来なくなってしまった。必死に息を吸うあおむけの弥彦を、剣心は厳しい目で見下ろす。
「立て」
冷酷な言葉をあびせる剣心。弥彦はせいいっぱいの精神力でなんとか立ち上がりかけたが、再びどさりと床に倒れる。剣心は弥彦の胸ぐらをつかみ無理矢理立たせる。
「午後の時間、何をして過ごしている」
弥彦の襟首をつかんだまま、剣心は先程と同じ調子でたずねる。
「……」
弥彦はつるし上げられた体勢で呼吸もままならぬまま、質問の内容にどきりとする。
「答えろ」
絶対的な師匠の言葉に、もはや逆らうことは許されない。
「……ちゃんばら」
とたんに剣心の平手打ちを食らい、弥彦はまた床に崩れた。
「今日の修業は止めだ」
それきり、剣心は道場を出ていった。
弥彦はぜいぜいと肩で息をしていたが、やがて落ち着くと、体を起こしてしばらくのあいだじっと座っていた。そうして、立ち上がり道場を出ていく。
「午後は遊ぶ時間と約束したでござろう?」
弥彦が道場を出るなり、外の壁に寄りかかっていた剣心から声がかかる。修業時のような冷徹さはないが、少し怒っているのが弥彦にも分かった。実際、めずらしく剣心は腕を組み、笑ってもいない。
「ちゃんばらだって遊びだ」
弥彦は、一応そう答えてみる。
「ただの自主稽古の言い訳でござろう?」
うっと弥彦はうなる。口でも剣心には勝てるわけがなかった。実際弥彦は、ちゃんばらという遊びを口実に、由太郎や栄次相手に稽古をしていた。さすがに御剣流を安易に見せるということはせず、振るったのは神谷活心流の剣だったが。だが、その結果がこれだった。剣心が言ったように、修業時間外に稽古をした故に体がついていかず、今日の修業をやりとげることが出来なかった。初めて修業についていけなかった。それについてはとてもくやしく、至極反省もしていたのだ。だが……。
「それに、遊ぶことの大切さも教えたはずでござるよ」
「……」
少し不機嫌そうな弥彦に、剣心はふぅとため息をつく。
「そんなに、遊ぶのが嫌でござるか?」
「……嫌とか、嫌じゃねぇっていうより……」
弥彦は少し困った顔で考え、そして剣心を見上げる。
「遊び方が、分からないんだ」
弥彦は、たんたんと続ける。
「生まれてから、俺、一度も遊んだことねぇし」
剣心は驚く。
「仕方ねぇだろ? 物心ついたころから母上は仕事で、俺は家事に忙しかったし。母上が死んでから剣心たちに会う前までも、当然無理だったし。それからは暇さえあれば日雇いと稽古してたし。ちゃんばらだって、本当のちゃんばら遊びは知らないんだ」
「そうでござったか……」
剣心は、しばらく考えたあと口を開く。
「弥彦。ちゃんばらという名の自主稽古をしたことについては、反省しているでござるか?」
「ああ」
「二度としないか?」
「ああ。しない」
「では、昼飯食べたら拙者と遊びに行くでござるよ」
剣心は、ようやくにっこり笑う。
「……」
「嫌か?」
「いや……」
弥彦のほおが、かすかに赤くなる。大人に遊んでもらう子供の自分。そういうのは、初めてだ。子供扱いはきらいなはずなのに、なんだか、くすぐったくて――。よく分からない気持ちを、弥彦はのみこむ。
「と言っても、何をして遊ぶでござるか」
昼飯後、剣心と弥彦は近所の山道を登る。
「剣心が教えてくれるんだろ? 子供の頃なにして遊んでたんだよ」
「ええと、それは……」
「……まさかちゃんばらじゃねーだろーな」
「ははは。当たりでござるよ」
困ったように笑う剣心に、弥彦はむかっときた。
「あっ、けど他にもたくさんあるでござるよ。セミの抜け殻を探したり……」
「そんなもん探して何がおもしれーんだよ」
そう言われると、身も蓋もない。
「では、かごめかごめ。一人がかがんで、まわりをみんなで輪になって回り、だれが後ろに止まったか輪の中にいるものが当てる遊びでござるよ」
「二人しかいないぜ」
「そうでござったな」
剣心はまたも苦笑する。
「それに、そんなことして何が楽しいんだ?」
「……」
剣心は、弥彦を見つめる。少し悲しい目で。自分は十からは御剣流の修業に明け暮れたけれど、それまでは家の手伝いをしながらでも遊ぶことは出来た。けれどこの子は、今までそれを経験しないまま、成長してきてしまった。それを今実感して、子供が本来喜ぶべきことを喜ぶことができない弥彦を、剣心は悲しく思ったのだ。
「……」
剣心は、そのまま黙り込んでしまった。弥彦も、何も言わず山道を登る。
ふいに、ひらけた場所へ出た。広い地面がひろがり、木々のしげる暗い道から出てきた弥彦たちは、まぶしさに目を細める。
「弥彦」
「なんだ?」
「お主は本当になにも知らないから、初めからでいいでござるか?」
弥彦は、不思議そうに剣心を見上げる。
「お主のお父上に叱られなければよいのだが……」
そうして剣心は弥彦に手を伸ばし、そして躊躇する。
「弥彦はやっぱり嫌がるでござるかな」
「なんなんだよ」
剣心は弥彦に近づくと、そっと手を弥彦の脇に差し入れ、そのまま弥彦を抱き上げた。
「な、なんの遊びなんだ? これ」
「……高い高いでござるよ」
弥彦は一瞬唖然とする。が、それがあの赤ん坊にやるものだということは、さすがの弥彦も知っていた。呆然とする弥彦。
「子供が一番初めにしてもらう遊びでござる。弥彦は、初めてでござろう?」
こくん、と、うなずく弥彦。
「ほぉら。たかいたかーい、でござるよ」
弥彦の軽い体は空に放り投げられ、また剣心の手に抱かれる。それを、剣心は繰り返す。
不思議な気分だった。あたたかくて大きな手に支えられ、空高く放り投げられ、けれど必ず受けとめてくれる手が待っている。一歩手元がくるえば落ちてしまうのに、その心配を感じないのは、そこに確かなものがあるから――
剣心も、親にそうしてもらったのだろうか。左之助も薫も。由太郎も栄次も。自分は、本当なら父にしてもらうはずだった――
「剣心……。もう、いいって……」
六回目で、弥彦は剣心にそう告げた。剣心は、そうか、と弥彦をおろした。
「やっぱり、恥ずかしかったでござるか?」
「決まってんだろ!」
弥彦は怒鳴ったあと、あわてて剣心から顔を背ける。一瞬、ほんの一瞬だけど、涙がでそうになったからだ。何故だろう。分からない。
結局その日は、木の実を拾っただけで山を下りた。下りながら、弥彦が思ったこと。それは、楽しむことに、いちいち理由など必要ないということ。十にもなって高い高いをされて恥ずかしかったけれど、赤ん坊のときだったなら、きっと純粋に笑った。そんな風に。ただ楽しく遊べばいいのだと、剣心は伝えたかったのではないだろうか。高い高いは、楽しくなかったわけではなかった。
そして――剣心は決して父上ではないけれど。父上の代わりとも思わないけれど。放られて受けとめてくれる手が剣心でよかったと思った。
体が空に浮いたとき山上から見えた町並みが、かすかな記憶となり、あたたかい手とともに弥彦の中に残る――
次の日の夕方、剣心が河原を歩いていると、弥彦が由太郎たちと遊ぶ姿が見えた。走り回りながら、くったくなく笑う顔。あんな風に子供らしく笑う弥彦は、初めてだ。
「やっぱり、子供は子供同士で遊ぶのが一番でござるな」
そうつぶやき、剣心は笑った。
その夜、剣心が弥彦にこっそり、何をして遊んでいたのか聞いてみると。
「……鬼ごっこ」
ほおをみるみる赤くして、弥彦は答えたのだった。
くったくのない笑顔。それを見せるのは、どうやら夢中で遊ぶ一時だけらしい。この子が失ってしまった十年分の笑顔を全て取り戻すのは、もはや手遅れなのだろう。けれど、ほんの少しでも……。
「弥彦。今度葵屋へ行ったときには、みんなで京都見物に行こうな」
剣心は、弥彦の頭に手を置き、優しく笑った。
☆あとがき☆
かごめかごめがこの時代に遊びとしてあったかは良く分かりませんでした(スミマセン…;;) 初めは遊びとしてではなく、「神寄せ」の儀式がルーツとされている説が有力らしいです。ところで、こんな風に時代考証をしないでストーリーを作ってしまうこともあります;; ホント、スミマセン・汗
第十八幕「母が残した悲しみ」
※この編のストーリーには「春画」「遊郭」などという言葉が出てきます。本編は、それに対して健全で真面目に語っています。尚、不特定多数の読者様(いろいろな読者様…というような意味です)がいらっしゃることを考慮して、作中上記言葉の具体的な説明はありませんのでご了承ください。
その日弥彦は、午後の時間をもてあましていた。自主稽古の代わりに新たな日課とさせられたのは遊ぶこと。けれどいつも由太郎や栄次がいるとは限らない。由太郎は学校の用事で帰りが遅くなることもあるし、栄次だってたまには養母と出かけたりもする。
誰も河原に来ないからと言って、わざわざ家まで呼びに行くようなことはしなかった。河原沿いを、弥彦は独り歩いていく。
ふいに視界に入ってきたのは、左之助だった。河原に寝っ転がり、なにか紙切れを眺めているようだ。
「何見てんだ? 左之助」
弥彦は左之助に近づき、紙をのぞきこもうとした。けれども左之助は、ガバリと起きあがり、紙を地面にバンとふせる。弥彦をじっと見つめる左之助。まるで品定めでもするかのように。
「おめぇ、いくつだ?」
「なんだよ」
不審がる弥彦。
「十か……。まだちぃと早いか……。いや、けど俺はその頃には確か見て……」
左之助がブツブツつぶやく様子を見ながら、弥彦はかすかに感づいた表情を見せる。おもむろに、左之助の手の下から紙を引き抜く。
「あ……」
「春画か」
左之助がわずかにうろたえた声を無視し、弥彦は一見平然と、それの名前を口にする。
「なんだお前……見たことあったのか」
「前のところでは、そこらじゅうに散らばってたからな」
前のところというのは、元いた極道の住処のことだ。
「なんだ。もう知ってんなら、俺が教えたって嬢ちゃんに怒られることもねぇな」
左之助は、弥彦の肩をぐいとひきよせ隣りに座らせる。
「ダチが貸してくれたんだけどよぉ、なかなかいいのがあるんだぜ?」
左之助は、何枚かの春画を見比べ、一枚を弥彦に渡す。
「どうでぇ、なかなか……ってオイ!」
弥彦は、無言で紙を真ん中から破いていた。
「なにすんでェ! 借りたダチに何て言やいいんだよ!」
「なんで左之助がこんなもん見んだよっ!」
弥彦は立ち上がり、ツバでも吹きかけん勢いで左之助に怒鳴る。
「ハァ? 見ちゃ悪ぃのかよ? 俺は大人の男だぜ? ってか何そんなに怒ってんだよ」
「大人の男はみんなそーいうの見んのかよっ!」
左之助の質問を無視し、弥彦は荒だった感情をめいっぱい左之助にぶつける。
「そりゃ……見るだろ」
「ふざけんなっ!」
困惑する左之助を、弥彦はギッと睨む。左之助の顔も次第に険しくなる。
「なんなんだお前はさっきから! いきなり意味不明に怒ったって訳分かんねーだろ?」
「……っるせぇ! ちくしょうこんなもんヘラヘラ見やがって!」
弥彦はさらに他の春画も破いていく。
「いーかげんにしろっ!」
左之助は弥彦の手首を締め上げるようにつかんだ。弥彦の手から、破れかけた春画がはらりと落ちる。
弥彦は、少しの沈黙の後左之助を見上げる。静かに、睨んだまま。
「昼間っからへーきでこんなもん見てるサイテー男を」
言った。
「育てた赤報隊の隊長は」
左之助の顔色がさっと変わる。
「最低だ」
言葉を吐いた瞬間。弥彦は頬に左之助の強烈な一撃をくらい、地面に叩きつけられた。そのまま、気を失う弥彦。
「……」
左之助はこぶしを握りしめ、肩をふるわせていた。
神谷道場の、門ではなく家屋の玄関が叩かれ、剣心と薫はそろって玄関口に出た。
「左之」
そこにいたのは、気絶した弥彦を片腕で抱えた左之助だった。
「弥彦!」
剣心はあわてて弥彦の様子を見たが、特に命に別状はないということはすぐに分かった。薫もそれを確認した後、左之助に問う。
「いったい何があったの?」
「ケンカして……俺が殴った」
「喧嘩って……お前やりすぎ……」
左之助は、ひどく不機嫌そうな顔をしたまま、弥彦を剣心に放るように押しつけた。
「……悪ぃ。帰るわ」
短い言葉を残し、左之助は去っていった。
剣心の腕で眠る弥彦を、残された二人はのぞきこむ。頬が真っ赤に腫れていた。
その晩、弥彦は熱を出した。あれから一度も目を覚まさないままふとんに寝かされ、弥彦は浅く息をする。額にぬれた布をのせられていても、顔は赤く、少し苦しそうな表情でたまにつぶやく。
「さの……すけ……」
うわごとのように。何度か繰り返す。そばで看病を続ける薫は、隣で額の布を取り替えてやっていた剣心につぶやく。
「いくら弥彦が生意気だからって、まだ十の子供をこんなになるまでぶつなんて」
「……ただの喧嘩で、左之がそこまでするとは思えぬのだが……」
剣心と薫は顔を見合わせ、弥彦の看病を続けた。
次の日の朝、左之助は剣心と並んで縁側に座っていた。弥彦は、皆が朝食をすませた今も、相変わらず眠り続けている。今日が平日であったなら、目を覚ましたとき修業のことを気にして大慌てするであろうが、その心配はなかった。
一部始終を聞いた剣心は、なるほど、と、うなずく。
「左之、弥彦のお母上は、遊郭で働いていたでござるよ」
左之助はハッとした。弥彦の母が遊郭で働いていたことにではない。それは、知っていた。そうではなく、弥彦が過剰反応したことの意味を。
「まだ小さかったアイツにとって、母親に触る男は、そりゃ汚らわしいと感じただろーな……。以来アイツは、そーいう世界や男たちを毛嫌いしてたってワケか」
「極道の連中はどうでもよくても、左之だったから嫌だったのでござろうな」
ふと、左之助の脳裏によぎる。
『なんで左之助がこんなもん見んだよっ!』
左之助が、と、そう言った。
左之助は、ふぅと一つため息をつく。
「悪ぃことしちまったな。アイツに……あとであやまんねぇと」
左之助は立ち上がり、二、三歩前へ出る。
「左之は悪くないでござるよ」
さらりと言う剣心に、左之助は驚いて振り返った。
「春画を見ること自体は悪いことではないし、左之が弥彦のお母上のことを悪く言ったわけでもない。それを弥彦は自分が傷ついたからと勝手にひとりで怒り、挙げ句の果てに相楽隊長を侮辱するような発言をした」
左之助は、剣心を見つめる。剣心が、弥彦に対して少し厳しくなったと感じるのは、気のせいだろうか。
「悪いのは弥彦でござる」
そう言いきり。剣心は微笑した。
「あとでよく言って聞かす故……。今回の件、すまなかったでござるな、左之」
弥彦の代わりにあやまりさえする、剣心は。家族として、少しずつ神谷道場に溶けこみ、やがては居候という肩書きもなくしてしまうのだろうと。
左之助は、フッと笑った。
☆あとがき☆
相楽隊長と左之助ファンのみなさま、弥彦が酷いこと言ってごめんなさい>< 弥彦、なんてこというのさっ。
弥彦大好きーな管理人が何故こんな弥彦を書くのか、不思議に思ってる方もいらっしゃるのでしょうね^^;
時代考証はほんのちょっとしかしてません(^-^;;) あまり信じないでください(^-^;;) 詳しくはこの一件話後のあとがきで……。
第十九幕「人は大人になるにつれ」
※第十八幕冒頭の注意書きをまだお読みでない方は、ご一読ください。
「さの……すけ……は?」
昼近くにやっと目を覚ました弥彦は、ふとんに横たわったまま、そばで看病していた剣心にたずねた。
「朝飯食べて帰ったでござるよ」
剣心は微笑する。弥彦は、むくりと起きあがる。
「……ってぇ」
思い出したように感じた痛みに、弥彦は思わずうめき声をもらし、確かめるように頬に触れる。指に触れたものは肌ではなく、テープで固定された薬が塗られた布きれ……いわゆる湿布だった。恐らく、剣心が貼ってくれたのだろう。御剣流の修業では幾度となく殴られ、けれどその後師匠から家族に戻った剣心は、よく手当てをしてくれた。それと同じだったから。
「だいじょうぶでござるか?」
「だいじょうぶくねぇ。けどいーんだ。痛くても……」
あまり抑揚もなく、言葉を吐く弥彦。剣心は微笑を解いて、弥彦をそっと見つめる。
「剣心、俺、左之助が尊敬してる隊長のこと、最低だって言った」
少し重い声で。ボソリとつぶやく弥彦。前を見ているようで、どこも見ていないようなそんな瞳で。
「本気で言った訳じゃなかったんだ。本気でなくても、言うつもりなんかなかった。だけど俺は、確かにそう言ったんだ」
その瞳が、かすかに揺らいでいるのに剣心は気付いた。伝わってくるのは、不安と恐怖と、いっぱいの罪悪感。それと、とまどい……。
「剣心も、あーいうのが好きなのか?」
分かっていて、聞いているのだと思った。剣心が、昨日の一件を一部始終知っていることも。好きなのか、の答えも。分かっていて聞いている。剣心も、それが分かっていて答える。
「好きでないと言えば、嘘になるでござるよ」
予想通り、弥彦が剣心の答えに驚くことはなく。けれどほんの少しだけ、目に悲しみの色をにじませた。
「母上のお仕事を、見たことがあるんだ」
唐突に、弥彦は言った。
「内緒で、こっそり影から見た、母上は……すごく辛そうな顔してた」
弥彦の小さな手は、ふとんのはしをそっとにぎる。
「極道にいたとき、オトナの男はみんなそーいうのが好きなんだって知った。俺はまだ子供で……そーいうのは分かんねぇ。けどいつかは……」
弥彦の目の、揺らぎが、強くなり……不安な気持ちが同じように強くなったのを、剣心は感じる。
「大人になるのが怖い……」
ひどくかすれた声で。つぶやく弥彦。純粋に怖いと、口にするような子ではない。その「怖い」は、恐らく、拒絶の意味なのだろう。
「大人になって……、遊郭で働く母上に、触れる……男たちが……、必ず、するような……、そんな目をするようになるのが……」
「弥彦……」
剣心は弥彦を見つめ、考える。弥彦は、ある程度分かっている。まず、左之助への一言は衝動的に出てしまったことだけれど、非は明らかに自分にあるということ。大人の男は、誰もがそれを好むこと。多分、それの本来の意味は、子供を作る手段だということも。知っているのだろう。
けれど、弥彦の知識は、少し足りない。
「弥彦」
剣心は、弥彦の両肩にそっと手を置き、自分に体を向けさせる。
「人は大人になるにつれ、子供を作る準備を始めるでござる。体も、心も」
弥彦は、剣心の前で、じっとしている。身構えるような、けれど反対に体をゆるめるような、どっちつかずの……そんな様子で。
「それは次第に、本能になっていくでござる」
「本能?」
「ああ。それ故、本当の目的以外であっても、女の人の前では反応してしまう。けれどそれはごく自然のことで、悪いことでもなんでもないことでござるよ」
弥彦は少しうつむき、考え、そして問う。
「……なら、母上のお仕事相手の男たちは? 悪く……ないのか?」
剣心は返答につまる。その答えはとても倫理的で、様々で。幼い弥彦には早すぎるし、理解出来るはずもない。剣心はふぅと息をつき。
「その話は、子供の弥彦にはまだ難しいでござるよ」
正直に、剣心は答えた。それは一つには、弥彦が、自分はまだ未熟な子供なのだという現実を、認めることが出来るほどに成長していたからだ。それは、自分は子供だからという甘えを持ったということではなく。正直に、未熟さを認める心の成長であり。それに、大人になることと、立派になること強くなることが、別なのだということも知っている。だからか弥彦は、早く大人になりたいとは言わない。それでも、子供扱いされることに何の抵抗も持たないわけでもなかったが……。
とにもかくにも、弥彦は、分かったと、剣心に無言の返事をした。剣心も、微笑でうなずく。
「俺、左之助のところへ行ってくる」
弥彦は立ち上がるがふらりと倒れ、あわてて剣心が支える。
「せめて飯を食べてから出かけるでござるよ」
「いい。左之助と会ってから食う」
弥彦は再び立とうとしたが、剣心が離さなかった。
「食べてからでござるよ、弥彦」
言い方は穏やかだったが、それは絶対的な命令であり、逆らうことは弥彦には出来ない。剣心の、外見とは違う強情さは、親しく関わる者ならみな知っていた。
結局弥彦はご飯を食べさせられ、遅くとも夕方には帰ると約束をさせられて出かけた。
☆あとがき☆
母上の仕事が弥彦にどう影響しているのかを書いてみたかったのが一つにあります。辛い幼少時代を過ごしてきた、今なお幼い弥彦。心の中には、たくさんの悲しみが揺らいでいるのだと思います。それでもいつもは普通にふるまう弥彦は、健気だなぁと、思います。
時代考証はほんのちょっとしかしてません(^-^;;) あまり信じないでください(^-^;;) 詳しくはこの一件話後のあとがきで……。
第二十幕「左之助がくれた答え」
ごろつき長屋の戸を何度も叩いたが、反応はない。弥彦が手をかけると、戸は簡単に開いた。
「……不用心なヤツ」
そうして、左之助の家に入っていく。目的のものは簡単に見つかり、弥彦はその前に腰を下ろす。持参した風呂敷包みをほどき、先程作ってきたものを取り出す。
ガラリ、と、戸を開ける音が、静かな部屋にやけに大きく響いた。入ってきたのは、夕陽の光と、左之助の気配。弥彦はほんの一瞬ビクッとするが、振り向かず、黙って作業を続ける。
「なんだ。ここにいたのか。探しちまったぜ」
左之助は、弥彦の横に腰を下ろす。
「……なんでだ?」
低い声で、問う弥彦。
「なんでって、そりゃあおめぇによぉー」
左之助は、おもむろに弥彦の腫れた頬をつまむ。
「ってぇな! 何すんだよ!」
左之助にとって弥彦の頬など、二本の指で簡単につまめるくらい小さいけれど。逆に弥彦にとって左之助の手は大きすぎて、しかも加減を知らないからたまったものではない。
「いやぁな、やっぱおめぇみてぇなガキんちょの頬を、餅みてぇにぷっくり膨らましちまったのは、大人げなかったと思ってよ」
「ガキんちょって言うな!」
顔を上げ、左之助を睨む。「子供」は受け入れられても「ガキんちょ」はダメらしい。お子様弥彦の心理は、なかなか複雑だ。
「悪かったな……」
急に真面目な目をして言う左之助に、弥彦はハッと思い出し目をそらした。
「俺はお前にあやまってもらうようなコトはされてねぇ……」
「だからガキんちょのおめぇを餅みてぇに……」
左之助はけらけらと言いかけたが、途中で口をつぐんだ。いつもの調子で絡んでくることを想定し、またそれを望んでのことなのに、弥彦はうつむいたまま作業を再開していたからだ。何をしているのかは、左之助はとっくに気付いていた。
「無理すんな」
左之助は、弥彦の手から一枚の紙を取り上げる。
「春画ってぇのは、そんな風に青ざめて吐きそうな顔しながら見るもんじゃねぇんだ……」
左之助の言葉はもちろん聞こえていたであろうが、弥彦は別の春画に手をつける。鍋で作った、器に入れたデンプン糊に刷毛を突っ込み、破れたところをペタペタと塗っていく。
「オトナのコトはよく分かんねぇけど、左之助は……」
弥彦は青白い顔で、けれどかろうじて言葉を紡ぐ。
「左之助は、きっと悪くねぇって、分かってた……。分かってたけど止めらんなくて、俺、左之助にひどいこと言ったっ、左之助がソンケーしてる隊長のこと、俺は、悪く言――」
「けど本気じゃなかった。だろ?」
それは、もういいよと優しく言えない、弥彦に対して素直でない左之助の、せいいっぱいの言葉。真っ直ぐでなくとも、弥彦には届く。それは、お互い多少の自覚がある、兄弟同然の絆があるから。
弥彦は、気がゆるんだのだろうか。急に手を口に当てると、裏庭へ続く扉をバンと開けげほげほと吐いた。左之助はあわてて弥彦の背中をさすり、水を汲んできて口をゆすがせる。はぁはぁと息をしながら、目に涙を浮かべる弥彦。それは別に、泣いて出た涙ではなかったのだけれど。
吐いた勢いで浮かぶ涙は、感情的な涙に似ていると、左之助はふと思う。吐くほど強い拒絶反応を起こしていた弥彦。
「だから言ったろ? 無理するなって。今のお前には、こーいうのは受け付けねぇんだ。……母ちゃんのことが、あるから……」
ビクッと、弥彦の体が揺れた。その反応があまりに大きかったので、左之助は驚いて弥彦を見つめてしまったほどだ。
「まだ貼り終わってねぇ……」
弥彦は、元の場所に戻り、再びペタペタと作業を始める。辛そうな、表情で。
「バカ。何意地張ってやがんだ! 吐くほど辛ぇんだろっ!?」
「……」
返事の代わりに、涙がぽとりと春画に落ちた。
「弥彦……」
「だっ……、母上が……かわいそうで……」
そのまま、勢いで泣く……そう左之助は思ったのだが、弥彦は声をもらすこともなく、涙をぬぐった。くちびるを、ぎっと噛んで。まだ、泣いてもいい年頃なのに、少年はいつも我慢する。耐えて耐えて、限界まで頑張ってどうしようもなくて泣いたときでさえ、必死で泣きやもうとしながら泣く。それは男として、とても立派で強く、頼もしいことではあるのだけれど。同時に、極道時代に甘えることは一切許されず、今では甘えるということさえ忘れてしまったこの子に、不安を覚える。だいじょうぶなのだろうか。抱え込みすぎて、壊れてしまうことはないのだろうか。そういえば、たまに感じる。剣心は、弥彦に厳しくなったが、同時に今まで以上に優しく接している、と。時には、やっと言葉を覚えたばかりの幼児にでも接するかのように。師匠として、教育係として厳しくしている分を、いっぱいいっぱいの子供をさらに追いつめている分を、必死で補おうと、そんな風であるのか――甘やかしているのとは少し違うけれど、剣心は弥彦にこれでもかと言うほど優しいときがある。
そんな剣心を思い出して、今なお辛そうな弥彦を見て、左之助はそっと手を伸ばす。弥彦の頭に置かれたその手は、頭をすっぽり包んでしまうほど大きくて。左之助には、バシバシ叩かれることはあっても、優しく手を置かれたのは初めてだったから。慣れない弥彦は、かすかに頬を赤く染めながらも、ホッとした表情を見せる。けれどそれもつかの間で、また辛そうな目をする。しかも今度は、無理をして一見平気そうな顔で頑張る。見かねた左之助は、一つ息を吐くと、頭にのせた手で弥彦の顔を自分に向けさせる。
「ほら。最後まで言えって。ちゃんと聞いてやるからよ」
弥彦は、驚いたのだろう。少し見開いた目を、左之助に真っ直ぐ向ける。
「どーした? なんでも言えって」
驚いて。けれど弥彦は疑うことはしなかった。左之助の優しさが決して嘘ではないということを、言葉なくして感じたからだ。
「剣心は……本能だから、悪いコトじゃないんだって……けど遊郭に来る男たちはって聞いたら、子供の俺にはその話はまだ難しいって……言った」
ぼそりぼそりと、言葉を紡ぐ弥彦。左之助は、いかにも剣心らしい答えだと思った。
「剣心を責めてる訳じゃないんだ。剣心の言うことは、大抵のことは合ってるし。ただ……話をお預けにされたから……。母上に触った男たちや同じようなことをしてるヤツらを、憎いと思ってきた気持ちは……どこへ向ければ、いいのかとか……。それとも、憎んだ事自体が……間違いだったのか……とか……、でも春画見たらやっぱり嫌でたまんなくて……でも俺が破いたんだから元通りにしなくちゃと思って……左之助を責めた自分は、相楽隊長のことを抜きにしても、悪いのか、とか……」
弥彦の言葉は、少々支離滅裂になっていく。左之助の手に伝わる弥彦の体温は熱い。息づかいも少し早く……また熱が上がってきたのだろうか。
左之助は弥彦を見つめたまま、左之助にしては丁寧に答えを返す。
「そーだな。剣心の言うことは大抵正しい。アイツはまっとうだし真面目だ。だが俺から見れば、真面目すぎるな。なんでかっつーと、俺が不真面目すぎるからだ」
左之助は、ニッと笑う。弥彦は、不思議そうな顔をする。
「だから、正しいことしか選べなくて答えをやれねぇ剣心の代わりに、俺が答えを教えてやる。ただしこれは俺なりの答えで、合ってるかなんて知ったこっちゃねーけどな」
「……なんだそれ」
怪訝そうな顔をする弥彦は、少しだけいつもの様子に戻っているようだ。
「結果から言えば、完璧悪いコトだな。遊郭だけじゃねぇぜ? 春画見んのもだ。ついでに言やぁ賭博だって喧嘩だって赤べこへのツケ払いだって道場へのたかりだってみんな悪いことだな」
「……全部お前がやってるコトじゃねーか」
弥彦は呆れる。
「そーだぜ? 誰かに迷惑かける。泣かせる。そーいうのは悪いコトだ」
笑いながら、自分の悪行をすらすらと述べる左之助に、弥彦はとまどう。
「わっ、悪いと思うなら、直せよっ」
「齢十九にもなると、なかなかそーもいかねぇのよ」
そうして左之助は、畳にガバッと寝転がり、天井を見上げる。
「俺だって、修正きかねぇ自分を、俺は俺だからと満足できるほど好きな訳じゃねぇさ……」
弥彦が驚いて左之助の顔を覗き込む前に、左之助はガバリと起きあがる。そうして再び、弥彦の頭に手を置く。今度は、いつものようにバシンと乱暴に。
「だからお前は、そんな風にはなるな」
左之助の目は、真剣だ。弥彦は反射的に、しっかり受けとめようと、左之助の目を真っ直ぐに受けとめる。
「賭博ツケうんぬんは、お前なら言われなくてもやらないだろーが……。大きくなって、女に興味を持つようになっても、遊郭には行くな」
本当に真剣に、左之助は弥彦に語る。
「春画は……まぁどうしてもってときなら見てもいい。けど遊郭には行くな。お前は、そのことで泣かせる女が他人よりも多いから。お前を想う女。遊郭で働かなけりゃならねぇ女。それに、お前の母上だ。だろ? 分かるか?」
「ん……。むずかしーところもあったけど、分かったとこもある。特に、母上が泣くから遊郭に行くなってところは」
「へっ。今のお前にそれだけ分かりゃあ上出来だ。んじゃ、もう春画貼りは終いにしろ」
「それとこれとは別だっ! ……うっ」
弥彦はまたも庭へ駆け込み吐いた。今度のは、春画のせいより熱のせいが大きいらしい。
「……ったく。強情っぱりめ」
左之助はやれやれとため息をつき、仕方なさそうに笑った。
星空の下を、左之助は弥彦をおぶり、道場への道を歩く。
「ゆーがたまでに帰るって、約束したのに……」
熱い息をもらす弥彦。熱はかなり上がっているようだ。頭をくらくらさせながら、弥彦は思う。約束を破ってしまった。剣心と薫を心配させてしまった。最近の剣心は手が早いから、またぶたれるかもしれない、と……。
「今日は俺がかばってやるから心配すんな」
「え? なんで俺が思ってること分かっ……」
「バーカ。お前全部口に出して言ってんだろーがよ」
熱のせいで、弥彦は思ったことを、うわごとのようにぶつぶつとつぶやいていたのだ。自覚がないままに。
「いーんだ。ぶたれても。俺が悪いから」
恐ろしく素直な発言もまた、熱のせいなのだろうか。
「この湿布だって、痛みをやわらげちまうから……。いたいままで……よかった……んだ……」
熱に浮かされ、弥彦の意識は途切れていく。そんな中で。
「さのす……け……。ごめ……」
弥彦が今日、左之助に一番伝えたかったことを、やっと口にすることができた。弱々しい口調とはうらはらに、その言葉に込められた気持ちはとても、とても強く切なく、左之助に届く。途中で途切れた言葉だが、ごめん、で終わりなのだと思った。弥彦は、誇り高い子で、それは良いことなのだが時に悪く働いたりもする。人に謝ることがなかなか出来ないことなどはいい例だ。それでも、あやまるときにはあやまる。けれど弥彦は、決してその次に「許してほしい」とは言わない。そんな子だ。
「そーだな。他のことはともかく、相楽隊長のことはホントおめぇが悪いぜ。けどいいさ。許してやるから、もう泣くな」
泣いている訳ではなかった。弥彦はすでに眠り込んでいて、左之助の声など耳に入ってはいない。ただ、左之助にはそんな気がしたのだ。弥彦が今、泣いている、と。
結局、弥彦は全ての答えを得た訳ではなかった。ただ弥彦が、今回の件で、少なからず心が楽になったのもまた事実だ。
そして皆は「大人になったら」などと一様に言ったが、弥彦が女の子に興味を持つようになるのは、ごく近い将来であり。
硬派なくせに今どきのお子様なのである。
☆あとがき☆
毎度のことですが……まず時代考証がしっかりしてなくてすみません;; デンプン糊(障子貼りとかに使う小麦粉を水で煮てつくった糊のことです…) でせいいっぱいでした^^; (しかもたったそれだけのことに一時間も時間を費やし、さらには明治時代に主流だったかは謎…春画がくっつくかものっそ不明かつ春画の紙の材質って何? ん、和紙かな? …な状態…酷すぎ・大汗) でもあんまり難しいこと書こうとすると楽しんで書けないですし、読む方も歴史好きさん以外は難しいと思うので……ものすごい言い訳ですが許してやってください><
男女平等について。「男として」という表記を出しましたが、こちらは明治時代には主流の考え方だったはずなので、現在では不適切ですがご了承ください。
さて今回は、左之助と弥彦のお話でした。昔っから頭にあった妄想話です。思い出すのって大変ですね;; いろいろ脚色されています^^; ……が、とにかく、この二人の兄弟みたいな関係が大好きです。
幼い頃から不幸続きで育った弥彦。彼が抱えるにはあまりにも大きすぎる辛さを、剣心や薫、左之助が少しずつ、あたたかい愛情で、和らげてあげてほしいなと……そんな風に思います。
(原稿執筆日(完成日):H18.11.29)
第二十一幕「武士の誇り」
白いもやの向こうに、父がいる……そんな気がする。
けれど、一歩も動くことが出来ないのは何故だろう。
そして、父は、どんな風であるのだろう。
ハッと布団から体を起こした弥彦。その目にまぶしい朝日がいっぱいに入り込む。
静かな、朝。
父の顔を、声を、ぬくもりを知らずして育った幼き子は。
「父上……」
そう小さくつぶやいた。いまだ、幼き子。
数日後の午後。ある立派な屋敷内の一室に、弥彦は正座して座っていた。その後ろに、剣心、薫、左之助が座る。弥彦の正面にいるのは、がっしりとした体つきで威厳を漂わせながらも悪びれていない、中年の男。屋敷の主である。
「おお弥彦殿。その方たちが先日話していた……」
この状況は、弥彦が父の夢を見た日から始まる。その日の午後、弥彦は父の墓参りに行った。正確には、父が参加した障義隊の火葬場の跡がある寺へと赴いた。弥彦は年に数度、寺を訪れる。そうして、見たこともない父に思いをはせる。弥彦にとって父は、障義隊に加わり義に殉じた、誇り高き人。母からそう聞かされて育った弥彦は、父に憧れと尊敬の念を、あふれんばかりに抱いている。
その日もまた弥彦は、そんな父の誇りを守って生きていくのだと、誓っていた。この場所で、何度も何度もそうしてきた。
そんなところへ、意外な人物と出会ったのだ。それは、母が生きていたまだ幼き頃付き合いのあった、父の友人。障義隊に直接加わらなかったものの、立派な人格と富で父を支えた元士族だ。懐かしい人と久方ぶりに出会った弥彦は、その者――佐元妙高の家へと招かれたが、話が進むうちに剣心や薫、左之助と共に、という話になったのである。
「左様でございます。妙高殿。今は神谷道場で、こちらの方たちにお世話になっております。俺は居候の身ではありますが、皆とても……」
弥彦があまりにすらすらと敬語を話すので、剣心たちは口をあんぐりと開けている。だが、すぐに三人とも理解した。これが弥彦が幼かった頃の、士族の世界なのだろうと。弥彦の家は貧乏でひどい生活ではあったけれど、それでも確かに士族であり、そんな世界で生きてきたのだろうと。
「そして神谷道場は……妙高殿、どうかなされましたか?」
さりげなく剣心に目を向ける妙高に、弥彦はすぐに気付く。
「いや……そちらのお方、緋村殿でしたかな?」
「おろ?」
「その刀……この廃刀令の時代にそのように堂々と腰に差すのは、あなたは凄腕の剣客であるのかと……」
妙高の言葉に、嫌みの意味はなかった。ただ、なにか探るような、どこかうろたえるような、そんな風であった。
弥彦は、何も話してないぞと剣心に目でうったえる。剣心はそれを見て微笑し、ほんの少しだけ刀を抜いてみせる。
「妙高殿。これは逆刃刀と言って、峰と刃が逆についている剣でござる。拙者がこれを携えているのは目に映る身近な人を守るため故……拙者はそんな……」
謙遜する剣心だが、それはいつものことであり、今更誰も何とも思わない。
「そうですか……。いや、しかし、ご立派ですな」
本心のようだがどこかたどたどしい妙高を、剣心は一瞬見定めるように見つめる。それを、弥彦は見逃さなかった。不思議に思い、妙高を見る。妙高の神妙な瞳は、弥彦に向けられた。
「弥彦殿。剣術を習い始めたのなら、是非ともお手並み拝見致したい。ちょうど今日は屋敷に剣術仲間も集まっている。一つ、共にどうかね」
「お誘い、ありがたくお受け致します」
そう答え、弥彦は何か考え、剣心たちの方に振り向く。
「俺、一汗流して帰るから……先に帰っててくれ」
そうして弥彦は思いだし、剣心を見る。
「いいか? 剣心……」
これは稽古になるかもしれないと思い。ほんの少しためらいがちにたずねる。修業時間外に稽古をしてはならない。それは師匠と弟子の約束事だ。
「今日は特別でござるよ」
付き合いだから仕方ないと、剣心も割り切ったようだ。微笑する剣心に、弥彦はとりあえずほっとする。
剣心たちが帰ったのを見届けると、弥彦は妙高に向き直った。弥彦はなんとなく勘づいていた。妙高が、自分だけを残したかったのではないかと。それが士族としてだからのようにも感じられ、かつての付き合いによるものとも感じられた。
弥彦の勘は、少なからず当たっている。妙高は弥彦をじっと見つめ、そして奥へと案内する。
妙高と同じ世代の、十数名の剣術仲間たち。弥彦が見知った者も数名あった。無論、妙高と同じく幼い頃に付き合っていた者たちである。ただ、その者どもが集団を組んで剣術をやっていたなどという過去はなかったはずだ。
屋敷の奥にひっそりと立てられた小さな道場。いつの間に出来たのだろう。昔はなかったはずだ。そして道場は、看板もなく、ただの稽古場として使われているようだった。
弥彦は次々と一本を決めていく。竹刀を振るうのは久しぶりだったが、真剣も竹刀も基本は一緒だ。それに今は、御剣流の修業でさらに腕を上げている。もちろん、御剣流の技は一切使わなかった。緊急時以外は誰にもそれを見せない。それもまた、剣心との約束である。
全ての者に鮮やかな一本を決めた弥彦を、当然まわりは驚愕の目で見つめる。それは妙高も例外ではなく。しばし呆然と弥彦を眺めていたが、ふいに武者震いを起こす。
「……妙高殿?」
弥彦がそばへ近づくと、妙高は弥彦の肩をがっしとつかむ。
「この時に、弥彦殿に再び巡り会えたのは、お父上のお導きだろう……」
「妙高……殿……?」
突然ふってきた、父上、という言葉。弥彦は、体内の血がどくりどくりと流れるのを感じる。
「弥彦殿。実は――」
妙高の家を後にし、神谷道場へ戻る道は、夕空へなりはじめる前の優しい光に包まれている。
『反新政府軍決起……つまり、散っていった障義隊の敵討ちを今夜決行する』
人員は妙高と先程の剣術仲間たち。剣心のことを聞かれたので、日本一強いこととこの計画をきっと止めに来るだろうと答えた。それでも――
『弥彦殿。どうか共に戦ってくれないか?』
間はほんの一瞬で。
『――ええ』
「だって俺は父上の子供なんだ」
うす紫色に染まりはじめた夕焼け空の下、弥彦は独りつぶやいた。
「俺、今夜出かけるから……」
縁側に座る剣心の正面に立ち、弥彦は告げる。夕焼け色は濃さを増していた。
たったそれだけで、剣心には解る。弥彦も、それを知っての発言である。昼間の妙高の、剣心への様子。先日の障義隊への墓参り。それになにより、弥彦の目が語っている。父上を誇りに思っている。否定するなんて出来ない。だから戦うのだと。けれど……心の奥底にひそむ思いをも、剣心は感じ取る。止めてほしい。決行を止めに来てほしい。戦ってほしい――。たまにするみたいに、怒って正しいことを諭してほしい。それでも……火を見るより明らかな結果に抗いたい。父上を否定したくない。否定したくないんだ――。そんな、必死な思いが、伝わる。二つの気持ちが、強く交差しあう。
☆あとがき☆
剣心(抜刀斎・維新志士)と弥彦の父上(障義隊・幕府側)は、立場でいうと敵同士なんですよね……。今回は、そういう事情は出していませんが、話を考えたきっかけはそれだったと思います。剣心と父上との間で揺れる弥彦。弥彦にとって、この問題を突きつけられたらかなり辛いと思います。
前ページへ 次ページへ
ご感想、 日記 のコメント欄・ 掲示板 ・ 拍手 コメント等に書き込みしていただきますと、とても励みになります。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 白い沈黙
- (2024-11-29 21:00:11)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(リチャード・C・ホーグラン…
- (2024-11-20 20:31:59)
-
© Rakuten Group, Inc.