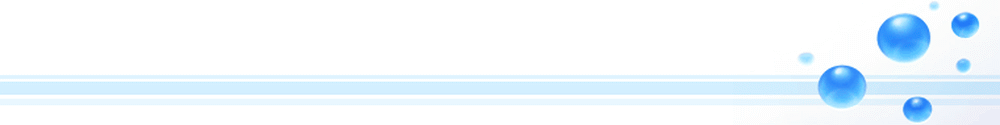第二十四話~第三十四話
本作品は、 「るろうに剣心小説(連載2)設定」 をご覧になってからお読みいただくことをおすすめいたします。面倒とは思いますが、オリジナル要素が強いので、キャラ人間関係・年齢等目を通していただきますと話が分かりやすくなります。
『剣と心』目次
『剣と心』
第二十四話「三年後」(第二部)
明治二十五年、夏。あの日から、三年あまりの日々が過ぎた。剣路は十三歳、心弥は七歳になっていた。
「もう東京に骨のあるヤツは残ってねぇか……」
剣路は木戸を開け、ぎらぎら輝く太陽の光に消えていく。薄暗い名門道場に残されたのは、倒れた門下生数百名と、おびただしい血の跡。
今日も神谷道場は、太陽の強烈な光を浴びていた。だが、その光も部屋の奥までは届かない。その場所で、剣心一家は昼食をとっていた。
囲まれた四つのお膳。座るのは剣心、薫、剣路、和。食べながら、にこにこ両親に話をするのは和。笑って聞くのは剣心。答えるのは薫。黙ったままの剣路。
それが今の、神谷家の日常――
伏し目がちに黙々と食す剣路を、和はちらりとうかがった。最近、道場荒らしもやめてしまった剣路。昼間剣路が家にいることはなく、どこでなにをしているのかといえば、ただ辺りをふらつくばかりの日々だった。そんな剣路に声をかける者は、誰もいない――
同じく昼食をとる弥彦一家。ちゃぶ台を囲む弥彦、燕、心弥。にこにこ両親に話をするのは心弥。笑って聞くのは弥彦。答えるのは燕。
それが今の、明神家の日常――
話の合間にいつも何か考え込んでいる様子の父を、心弥はちらりとうかがった。父の弥彦は、昔より口数が減った。そんな弥彦を燕は心配しながらも黙って見守った。事情を知っていたから故である。心弥にはよく分からなかったが、幼いながら父の心の痛みを無意識に感じ取っていたのだろう。父を見ては、たびたび心が痛んだ。
心弥が学校へ行き、弥彦が家を出ると、門の横に剣路がよりかかっていた。
「久しぶりだね」
三年ぶりにまともに聞いた剣路の声は、低かった。背もぐんと高くなり、弥彦と頭一つ分も違わない。顔つきはさすが剣心と薫の子供だけあり美形だが、その表情は剣心とは似ても似つかぬするどさだった。
弥彦は、無言のまま剣路を見つめていた。
「あのさぁ、街の道場はほとんど俺がこわしちゃったし、この木刀も用済みだし、そろそろ時が来たと思ってさ。俺の言ってる意味、分かるよね」
黙ったままの弥彦を、剣路は歪んだ顔で笑い見上げる。
「心の準備が必要? いいよ。三日待ってあげる。三日後夜の零時に、神谷道場で勝負だ。逆刃刀、忘れないでよね」
去っていく剣路を、ただ黙って弥彦は見つめていた。苦痛の表情を浮かべながら……。
弥彦が神谷道場へ行くと、思いがけない人物の姿があった。その男は、今来たばかりなのだろう。荷物を背負ったまま、央太と話をしていた。
第二十五話「逆刃刀が泣いている」
「よぉ央太。立派になったな」
「……左之助兄さん!」
央太は左之助の手を握った。
「僕、ずっと兄さんを待ってたんだよ!」
「そっか……。長いこと待たせちまったな」
ニッと笑い央太の頭をくしゃくしゃなでる左之助。央太も嬉しそうだった。
門下生たちは、兄弟の再会を温かく見守っていた。ただ、少しだけ違っていたのは二人。和は穏やかな笑顔で見ていたが、瞳の奥に秘めた妙な光があった。弥彦はといえば……それはもちろん兄弟の再会は嬉しかったが、それ以上の感情があった。弥彦にとって左之助は特別な存在だ。
ふと、左之助が弥彦に気付いた。
「お前……弥彦か?」
「ああ。やっと帰ってきやがったのか」
弥彦は昔のまま相変わらず素直になれず、そっけなく言った。
「帰ってきたわけじゃねぇって。またすぐ発つさ。世界のどっかへな」
左之助は弥彦に近づいたが、途中でいぶかしげな顔をした。
「お前、変わったな……」
「弥彦さんはここの師範なんだよ。腕だって日本一――」
「そうでなくって……」
央太の言葉を左之助はさえぎった。
その日の深夜、縁側にひとり座っていた弥彦の隣りに、部屋から出てきた左之助は並んで座った。
「剣心との積もる話は終わったのか?」
「まぁな。つーか別にアイツと俺自身の話は特に何もねぇんだ」
弥彦は、そうかと思った。剣心と左之助の友情に、言葉など必要ない。
「ここは、死んじまってる。墓場みてぇだ」
左之助は、鋭い目にやりきれない寂しさを宿した。剣心や薫から、左之助が去った後の現状を聞いたらしい。
「お前には、ガッカリしたぜ。期待してたのによ……」
左之助の言葉は、弥彦の心に重くのしかかった。
「期待させてたなら……悪かったな。けど、もう遅いんだ。俺は、剣路を傷つけちまった……」
弥彦は、絞り出すような声で、辛そうに言葉を吐いた。
「傷ついた? 剣路が? お前に睨まれた、たったそれだけで? けっ! 甘ったれたガキだぜ。そんでもっておめぇも甘やかしすぎだ」
「……左之助には分かんねぇよ。話聞きかじっただけだろ? あいつは今、強くなることでしか、自分の存在価値を見いだせないでいる。剣路はさ、薫似で、人一倍寂しがり屋で、けど男だからって強がって、泣けなくて、心ん中にみんなためて……そーいうやつなんだ。そんでもって、俺にとっては、兄弟同然な存在なんだ……」
「兄弟同然……ねぇ」
左之助は、ふっと月を見上げた。
「ま、そーいうのは分かんなくもねぇけどな……」
左之助は、少しのあいだ弥彦を見つめ、また月に目を移す。
「けど弥彦。昔のおめぇはそんな風じゃなかったぜ。もっと真っ直ぐで、信じた道は必ず貫き通した」
「ガキの頃の話だろ? あの頃は何も知らなかっただけだ。知らないから、純粋だった。ただバカみてぇに剣心の背中追っかけて、そうすれば夢は叶うと……人を守る剣客になれると信じて疑わなかった……」
弥彦は、組んだ両手に少し力をこめた。
「するってぇとおめぇは、昔の自分を否定してるってわけだ」
弥彦の両手はぴくりとした。左之助は立ち上がり、二、三歩前へ出ると、弥彦の方に振り向いた。
「いいか弥彦。俺はあんときのおめぇを否定したことなんざ一度もねーんだよ。おめぇははっきり言って俺なんかよりずっと立派だった。赤べこで働いて、バカみてぇに稽古熱心で、誇りをもってて……てめぇが思い描いた理想の未来に真っ直ぐ突き進んでた」
弥彦は、いままでにない左之助の様子にただ驚いていた。
「逆に俺が傷つけたことはあったな。剣心が落人群に行ったとき、俺もお前を置いて去っちまった。あれは悪かったと思ってるぜ。けど俺はお前に謝ったか? お前は剣路みてぇに荒れちまったか?」
左之助は、力強い口調で弥彦にせまった。
「……左之助は俺に謝ってねーし、俺は剣路みてぇにはならなかった。けど、だから何だよ」
「分かんねーか? つまり、兄貴と弟ってぇのはそーいうもんなんだ」
「はぁ?」
左之助の無茶苦茶な発言は、弥彦には到底理解出来なかった。
「逆刃刀が泣いてるぜ。弥彦」
弥彦ははっとした。
「剣心がお前に逆刃刀を託したのは何のためか、お前が逆刃刀を持つ意味はなんなのか、もう一度良く考えろ」
左之助は、弥彦に背中を向けた。
「今度日本に戻ったときには、もっと楽しい未来を見せてくれ。分かったな」
左之助は去っていく。
「待てよ左之助!」
弥彦は思わず呼び止めていた。呼び止めてから、その理由を考える。
「明日発つのか? 今度いつ戻るんだよ」
出てきた言葉は、それだった。
「さぁな。別にいつでもいーだろ?」
弥彦はカチンときた。
「なんだその言い草は! お前が行っちまってから、みんなお前の帰りを待ってたんだぞ! 剣心も、薫も、央太もみんな……!」
左之助は、振り向いてニッと笑った。
「弥彦。さてはおめぇ、昔俺と別れたときさみしくて泣きじゃくったんだろ」
「んなわけねーだろ!」
弥彦は間髪いれずに返したが……ふと忘れていた十歳の記憶がよみがえった。
『少しさみしいけれど、我慢しなくてはな』
左之助をのせた舟が遠くなっていくのを見送りながら、剣心の言葉を背中で聞いた。言われるまでもない。確かに少しはさみしいけれど、当然我慢できる。そう思っていたし、実際その後普通に道場へ戻り、日々を過ごしていった。
けれど、ある日風邪をひき熱を出したとき、たまたま薫ははずせない出稽古があり、剣心は氷を買いに出かけ、独り寝ている部屋はあまりにも静かだった。いつもなら、必ず左之助がそばにいて、憎まれ口を叩いていた。もうろうとした頭で、ふらふらと神社へ向かった。高いところなら、海が見えるかもしれないと思った。けれど見えなかった。そのとたん、涙がぼろぼろ出てきた。左之助、左之助……と何度も呼びかけて、返ってこない返事が悲しくて、また泣いた。
そんな記憶を、弥彦は思いだしていた。左之助はふっと優しい目で、弥彦の頭をくしゃくしゃなでた。先程央太へやったのと同じように。
「また戻ってくるさ。別に今生の別れじゃねぇ。前にもそう言ったろ?」
「……ああ」
弥彦が笑うと、左之助は満足そうに笑って去っていった。
独りになった弥彦は、ボソリと言った。
「そっか。左之助はやっぱ、俺にとって唯一の……」
弥彦は微笑した。
「一回くらい、左之助兄ちゃんって呼んでやればよかったかな。あの頃……」
自分の唯一の兄貴分である左之助。その左之助は、遠く離れたことはあっても、完全に自分を見捨てたことは一度もなかった。間違っている、いないを抜きにして、左之助はいつも強引に、けれど真剣に、自分と向き合ってくれた。
その形のみが「兄弟」であるとは思わない。けれど、罪の意識があるからと剣路から目をそらすのは、ただ逃げているだけだ。そう思った。
あのとき、まだ十だった剣路も、神社で泣いた自分と同じように泣いたのかもしれないと思った。
剣路を傷つけたのが罪なら、償わなければならない。そして、兄として、弟を救ってやらなければならない。いや、救ってやりたい。そう思った。
弥彦は、自分と左之助の過去を思い出し、左之助と央太を思い出し、そして自分と剣路のことを考え、逆刃刀の柄を握りしめた。
第二十六話「月夜の勝負」
三日後の深夜。そっと自宅を抜け出したつもりの弥彦だったが、門の影に息子の気配を感じた。
「父上。どこへ行くんですか?」
目をこすりこすり、寝間着姿の心弥はたずねる。
「稽古だ」
弥彦は、とっさにでまかせを言った。
「稽古!? それならおれも行きますっ!」
心弥は、急にぱっちりと目を開けた。
「ダメだ! 子供は寝る時間だろ?」
「……はい」
しぶしぶ戻ろうとする心弥を、弥彦は引き止めた。
「燕には内緒だぞ。心配するといけないから。いいな」
「……おれだって心配だよ」
心弥は、独り言みたいにボソリと言った。
「子供が父親の心配するなんて生意気だぞ!」
「ごっごめんなさいっ!」
弥彦に睨まれて、心弥はあわててあやまった。
「お前は燕の心配だけしてりゃあいいんだ。分かったらさっさと寝ろ」
「はい。おやすみなさい父上」
心弥は、今度は素直に聞き分けた。その目には、相変わらず燕譲りの優しさが宿っている。稽古の時には、弥彦のような強い意志があわせてあらわれる。
戻っていく息子の後ろ姿を、弥彦はながめる。我が子ながら、なかなか立派に育っていると感じる。背格好は普通の子と変わらない七歳児。けれど心は大きく成長している。優しい性格で一見頼りなさそうだが、実はしっかりしている。特に、ゆずれないことに関しては、芯が強い。相変わらず泣き虫は治らないものの、たいがいはこらえようと務めるし、泣いても泣きやもうと必死に涙をぬぐう。
息子を見送った弥彦はふぅとひとつ息を吐くと、この三年間見せなかった意を決した目をして、神谷道場へと向かった。
弥彦が神谷道場へ入ろうと木戸を少し開けると、既に剣路が月明かりの中立っていた。弥彦は思わず手を止めて、木戸の隙間から剣路を眺めた。三日前に会ったときとは違う、思い詰めた表情。ときおり苦渋に満ちた表情で目をつむり、木刀をぎゅっと握りしめている。
弥彦はそんな剣路をしばらく眺めていたが、やがて静かに木戸を開け中へ入った。剣路は弥彦に一瞬びくっとしたが、すぐにいつもの歪んだ笑みを作る。
「早かったね」
剣路は対峙した弥彦に木刀を投げる。弥彦はパシッと受け取った。そして弥彦は腰に差していた逆刃刀を抜くと、剣路に差し出した。
「……何の真似だよ」
「貸してやる。お前はそれを使って勝負しろ」
剣路は、弥彦を睨み付けた。
「何……たくらんでやがる」
「別に何もたくらんでなんかねぇよ。ただお前、これ欲しいんだろ。けどお前はまだ俺に勝てないから、せめて貸してやるって言ってんだ」
弥彦は、逆刃刀を強引に剣路の手に押しつけた。逆刃刀を握った剣路は、思わず声にならない声を漏らす。
「重いだろ」
剣路は答えず、木刀をからんと後ろに放り投げた。そして逆刃刀を構えた。
「俺には慣れない逆刃刀を渡して勝機をつかむ計算か?」
「そう思うなら、俺は竹刀でやってもいいんだぜ」
「……ふざけやがって」
剣路は、ギリ……と唇をかむ。
「俺をみくびるのもいい加減にしろよ。俺は街の道場いくつもぶっ潰してきたんだよっ。何度も修羅場をくぐってきた! たった独りでな……」
剣路は弥彦をにらみ据える。
「ここでちんたら平和に稽古してるお前とは訳が違うんだよ!」
「そうか。なら、どう違うのか見せてみろ。だが一つ忠告しておく。俺は稽古のときのように、お前の実力に合わせたりはしねぇ。だから本気でかかってこい。過信すると大怪我するぞ」
「その言葉そっくり返すぜ!」
言いながら剣路は弥彦に突進し、その懐に入った。
第二十七話「何も変わらない」
「飛天御剣流・龍翔閃!!」
剣路は下段から鋭く剣を突き上げた。その技は正に完璧だった。弥彦は剣路の天才振りに改めて驚愕する。
だが弥彦はすっと身を反らしてかわすと、一瞬で剣路の後ろに飛び上がり、その背中に強烈な一打を与えた。ダンッと床に叩きつけられる剣路。その音が道場に響き渡った。
「勝負ありだな。逆刃刀返してもらうぜ」
弥彦は、うつぶせでうめいている剣路の手から、逆刃刀を取り上げた。剣路はよほど強烈な一撃をくらったのだろう。体を動かすことはおろか、声を出すことすら困難な様子だ。
弥彦は逆刃刀を腰の鞘に収めると、剣路の前に腰を下ろした。
「三日前、央太の兄ちゃんがここに来たの知ってるか? 前に話しただろ。剣心の友達で、俺にとっては兄貴分の左之助だ。央太と左之助は十年以上も会ってなかったってのに、まるで毎日共に過ごしてきたような、そんな風だった。左之助が央太の頭くしゃってなでてさ。俺は、ああ、あれが血のつながりってやつかって思ったぜ」
聞いているのかいないのか、うつぶせのままの剣路に、弥彦は続ける。
「けどさ、左之助は俺にも同じようにしてくれたんだぜ。頭クシャって、なでてくれたんだぜ」
弥彦は、剣路の頭に手を伸ばした。一瞬その手は止まったが、弥彦はそっと剣路の頭をなでた。
「変わんねぇよ。何にも……」
弥彦は、剣路と共に自分にも言い聞かせるように、静かにつぶやいた。
「剣路……」
弥彦は、剣路の頭を優しくなで続ける。
「この三年間、お前に会うどころか、お前の名前を呼ぶことさえためらった。俺は、十歳だったお前の心に大きな傷を負わせた。それは、紛れもない事実だ」
弥彦は、優しさと苦しみをたたえた目で剣路を見つめる。
「俺は知っていたはずだった。お前の孤独な心を……。剣心と薫は分かっていても、親として、どうしても病気の和を優先せざるをえねぇ。だから、お前を救ってやれるのは俺しかいなかったし……弟だと思ってるお前を救ってやりたかった。けど……」
弥彦は、逆刃刀の柄に手を当てる。剣心から受け継いだ逆刃刀。この剣で、この目に映る弱い人や泣いている人たちを守りたいと誓った昔の自分。
弥彦は、静かに目を閉じ、そしてまた開けた。
「お前の言ったとおりだ。確かに俺は家族が大事だし、心弥はたった一人の大事な息子だ。心弥のためなら、命だってかけられる。けど、俺は……」
弥彦は、ふたたび剣路の頭に手を置く。
「俺は、お前にだって命かけられる」
その時、弥彦の手は剣路に思い切り振り払われた。剣路は、ハァハァと身を起こす。うずくまり、片方の手を床に立て、もう片方の手で弥彦の逆刃刀を抜く。
「きれいごと……言ってんじゃねぇよ! だったら、たった今ここで……俺におとなしく殺されろよ!」
剣路は逆刃刀の刃を逆にして、弥彦の喉元につきつけた。
第二十八話「それぞれの思い」
弥彦は黙って剣路を見ていたが、やがて剣路の手首をつかんで止めた。
「悪ぃな。それは出来ねぇ。お前に殺人剣を振るわせる訳にいかねぇし、俺もまだ死ねねぇ。家族のこともあるが、お前をこのままにしたまま死ぬわけにはいかねぇんだ。けど、お前を救うことが出来るまで……俺はそれまで罪を背負って生きていくから」
弥彦はそっと逆刃刀を剣路の手から離すと、鞘に収め、立ち上がった。
「剣路。大きくなったな……。けど、そう感じるほど長い間お前のそばにいてやれなくて……悪かったな」
弥彦は、道場を去っていった。
剣路は、弥彦が去った木戸を見ていた。とても、うつろな目で……。
一週間後。その日の午後も、神谷道場はいつも通り稽古が行われていた。
弥彦は、門下生たちが師範代の央太を相手に、一人ずつ由太郎に指導してもらっているのを真剣に見つめていた。
今や総勢五十人は越える道場でいちばんやる気のある門下生は、心弥と和だった。それは、誰の目から見ても明らかだった。それも二人とも、剣路が道場を去ったあの日からだ。
それにしても……と、弥彦は思う。息子の心弥はよく頑張っている。努力を惜しまず、今や大人の門下生とも互角に張り合えるほどに腕を上げた。だが、やはり天才を努力でこえるのは並大抵のことではないのだろう。剣路は七つですでに門下生一だった。当時剣路に勝てたのは、自分と由太郎、央太の三人だけだった。
そして和。この子も頑張っている。病弱な体が持つ限り、以前とは打って変わった真剣な態度で稽古に励む。最近は病気も落ち着いているようで、途中で倒れたりすることはなくなった。
けれど、弥彦は和に対して不審な点をいくつか感じていた。まず、和は剣術自体が好きなのであり、強さを求める子供ではなかったはずだ。それなのに、渇望するようにどん欲に強さを欲する目をしている。まるで、何かに追いつめられているかのように。それなのに、勝負ではぎりぎりまで相手を追いつめておいて、いつも負ける。一番最初は、病気故の稽古不足によるものだと思っていた。だが、次第に病気の症状を見せなくなっても、それは変わらなかった。和の優しい性格のせいかとも思った。だが、それならばぎりぎりまで相手を追いつめずとも、適当なところで負けてもよいはずだし、和にはそれが分かる利口な子であるはずだ。負け方も上手い。腕が未熟なふりをして、実はわざと隙を作っている。
最近それを確信した弥彦は、対処に困った。練習試合とはいえ、勝負は勝負。わざと負けるなど武士道に反することであるし、本来なら厳しく叱るべきなのだろうが……。どうも和は、分かっているようなのだ。負けたあと、いつもすまなそうにする。あからさまに表情に出さないから誰にも気付かれないけれど、弥彦にはそれが分かる。だが、それまでだ。理由までは分からない。和はいつも、何を考えているのか分からない。さらに和はかわすのも上手い。聞き出しても、上手に嘘をつく。それも、ごく自然に、しかも相手を傷つけないようにだ。本当に和は頭がよい。
結局その問題は、後回しになった。稽古後、弥彦は和から剣路の様子を聞き出した。あれからずっと自室にこもりきりだという。時が必要だと思い、弥彦は剣路を信じようと心に決め、道場を後にした。
木戸を出ると、横の壁によりかかっていたのは心弥だった。めずらしく、落ち込んだ表情をしている。父に気付くと、心弥ははっと顔をあげ、姿勢を正しくした。
「父上。今日は一緒に帰ってもいいですか?」
「ああ」
弥彦が歩き出すと、心弥は小走りにかけより弥彦の横に並んだ。普段稽古が終わると別の道から帰る心弥が父と帰るのは、久しぶりのことである。
第二十九話「あの時と同じ夕焼け色」
「和が、わざとおれに負けている気がするんです」
心弥の言葉に、弥彦はどきりとした。まさか心弥が気付いているとは夢にも思っていなかったからだ。
「どうして、そう思うんだ」
とりあえず、平静を装いそう聞いてみた。
「なんとなく……和はおれの友達だから……」
心弥はうつむいて続ける。
「父上……。どうしておれは、ちっとも強くなれないのかなぁ……。一生懸命稽古してるのに……」
「……まだまだ努力がたりないからだ。甘えたことを言うな」
本当は、言ってやりたかった。お前は限界なまでに努力している。頑張ってる。えらいな、いい子だな、と。けれど、まだそれを言うには年齢が幼すぎる。少なくとも心弥は、本当に強くなるために大切なことをまだ知らない。それを自分の力で理解することが出来るまでは、心弥はまだ剣士としては半人前なのだ。一人前になるまで、甘やかして成長を止めるわけにはいかない。
「前にこの河原で、剣路兄ちゃんとの年齢の差を乗り越えろって、父上はそう言いましたよね……。だけどおれは、おれと同じ七つのときの剣路兄ちゃんにさえ勝つことが出来ないし……同い年の和にさえ……」
いつの間にか、河原へ来ていた。そう、確かに昔、弥彦が心弥に怒鳴った場所だ。年の差のせいで剣路に勝てないと言って泣いた心弥を叱った場所だ。そうして心弥は弥彦に言われたとおり、ひたすら稽古してきた。道場での稽古はもちろん、父弥彦が知らないところで、毎日この河原で朝日に、夕日に包まれながら、三年間ひたすら剣を振り続けてきたのだ。
天才の剣路や和に全然追いつかない心弥の辛さは、弥彦には本当は痛いほど伝わってくる。
「これ以上、どう努力すればいいの? それならおれ、もう和とは遊ばない。夏祭りにもいかない。桜とも会わない。ご飯も食べないし眠らない! ずっとずっと一日中稽古するっ!」
「なにガキみたいなこと言ってんだっ」
弥彦はそう言ってから、心弥がまだ七つの子供だということに改めて気がついた。ただ、急に駄々っ子のような態度を取り始めた息子に驚いた。
「おれ、おれ……、父上の跡を継ぐことが出来ないなら死んだ方がましだぁっ!」
心弥はそう叫ぶと、声をあげて思い切り泣き始めた。まるで、すべてがどうしようもなくなってしまったかのように……。心弥がこんな風に泣くのをみたのは、初めてだ。だが弥彦は、どうしていいか分からなかった。抱きしめてやるべきか、叱るべきか。確かに、こんなにも跡を継ぎたいなどと言われて嬉しい限りである。けれど、こんな風に泣きじゃくり駄々をこねる子供を甘やかしてもいいのだろうか。結局どちらも適切ではないと思い、弥彦はただ息子が泣きやむまでそばで見守った。
やがて少し落ち着いてきた心弥は、目をこすりながら涙声で言った。
「ごめんなさい父上……。おれ、もう七つなのに……。父上の子供なのに、恥ずかしいです……」
心弥は涙をぬぐうと、キッと前を見据えた。
「これからは、素振りの一本一本に魂込めて稽古します。強くなるためなら、どんな辛い稽古でも耐えて見せます。血を吐いても、骨が折れてもいいです。絶対耐えて、そして絶対強くなります。父上の跡を継ぐために」
心弥は、弥彦を見上げた。挑むような、意志の強い目にまだ残る涙をうかべて。
「そうか。なら明日からもっと稽古厳しくしてやる」
弥彦は、ようやく息子の頭をなでた。
「はいっ!」
心弥も、ようやく笑顔を取り戻した。その拍子に、心弥の目から涙がこぼれて頬に伝った。
三年前、心弥が父の跡を継ぐとはっきり誓ったのもこの場所だった。そして辺りは今も、あの時と同じ夕焼け色に染まっていた。
数日後の日曜日。夕方森で独り稽古していた弥彦は、ふと人の気配に気付いた。何気なく草木をかき分け近寄ってみると、小さな人影が一人。
第三十話「兄弟の絆」
和だった。ふらふらになりながら、稽古をしている。それも、飛天御剣流の数々の技を完璧にこなしている。その技の切れは、剣路の比ではない。それどころか、剣心よりも上なのではないだろうか。
弥彦は信じられない光景をしばらく呆然と見ていたが、やがて和が倒れるとはっと我にかえり、あわてて和を抱きかかえた。
「……や…ひこ…さん?」
和は弱々しい声をもらした。顔が赤い。熱があるようだ。
「お前、熱があるって分かってて稽古してたのか?」
「……はい」
「ばかっ!」
弥彦は、思わず和の頬をひっぱたいた。思ったよりも力が入ってしまい、和の白い頬はみるみる赤く腫れ上がる。
「なにやってるんだ! 無茶な稽古して……何かあったらどうするんだっ!」
普段優等生な和が怒られるのは、非常にめずらしいことだった。
「ごめんなさい……」
和は、素直にあやまった。弥彦は懐から白い布きれを出し、和のくちびるからにじんでいる血をぬぐってやると、和をおんぶする。
「あっ、剣玉……」
弥彦は地面に置いてあった剣玉を取り、和に渡す。和はお礼をいい、剣玉をぎゅっと握る。和はいつでも、この剣玉をそばに置いている。
「すぐ帰るぞ。帰って薬飲まねーと」
弥彦は早足で歩き始めたが、和の体にさわるといけないと思い直し、歩をゆるめた。
「ぼく……ぶたれたのって、生まれて初めてです」
和は、熱い息とともに声を漏らした。
「痛かったか?」
「はい」
「なら、もう二度とこんな無茶するんじゃねぇぞ」
言葉とは裏腹に、弥彦の口調は優しかった。和は、返事の代わりに弥彦にまわす腕の力を少し強めた。弥彦は驚いた。自分に甘えているのだろうか。和がそんなそぶりを見せたことは、今までに一度もない。
「ごめんなさい……」
和は、辛そうに、本当にすまなそうに言った。弥彦にぎゅっとしがみつきながら……。
「もうしなければ、それでいいって」
「そうじゃ……なくって……」
「えっ?」
和の蚊の鳴くようにつぶやいた声は、弥彦には届かなかった。
「ぼくは……悪い子だから……」
今度は、かろうじて聞き取ることが出来た。
「そうだな。自分の体大事にしねーでみんなに心配かけるお前は悪い子だ。けど、ぶったからって、お前の全部が悪いって言ってる訳じゃねーんだぜ。いつものお前はいい子だよ」
和は、目をつむって辛そうに首を振った。
「ねぇ弥彦さん。この間、央太さんのお兄さんがきたでしょう? 十年以上も離れていたのに、すごく仲良しでしたね」
和は、唐突にそんなことを言い出した。
「でも、央太さんのお兄さんって、弥彦さんにとってもお兄さんみたいな人なんでしょう? 弥彦さんとそのお兄さんは、やっぱりとても仲良しなんですか?」
弥彦は、和の真意が分からなかった。子供故の単純な興味で聞いているわけではないような気がした。頭のいい和のことだ。いろいろ考えすぎてしまうところがあるのかもしれない。
「どーかな。俺と左之助はいつもケンカばっかだし。けどやっぱり左之助は、俺にとって唯一の兄ちゃんだ」
「血がつながってなくても?」
和の質問には、どこか真剣さがこもっていた。
「ああ。そうだな」
「だから兄ちゃんと弥彦さんも仲良しだったんですか?」
なんだかせっぱ詰まったようにも聞こえる和の言葉。だが弥彦にとっても、その話題は胸が痛い。答えを考えているうちに、ようやく和の真意が分かった気がした。和は剣心に似て、自分の中に抱え込んでしまう傾向が強い。その和が遠回しに、けれど必死ですがってくるのが、弥彦には伝わってきた。
「お前……要するに剣路と自分の話を聞いてもらいたいんだろ」
和の体がびくっとするのが、弥彦に伝わってきた。
「ぼくは……何のために生まれてきたのかなぁ」
ふいに和がもらした言葉は、弥彦にはとても重く感じられた。
「ずっと、考えてたんです。ぼくは病気だから、いつも父さんと母さんは大変だし、道場でも弥彦さんやみんなに迷惑かけてます。心弥だってぼくを気遣って思い切り遊べないし……。だから兄ちゃんに……」
「和。お前年いくつだ」
「……七つです」
弥彦は、ふうと息をもらした。
「まだたった七年しか生きてねぇだろ。子供はそんなに難しいこと考えるもんじゃねぇ。まだまだ先は長いんだ。そんなこと考える暇があったら、もっと未来を見据えろ」
「……ごめんなさい」
和はあやまった。いろいろな意味を込めて。
けれど、今の弥彦には、それは伝わらなかった。それが本当の意味で伝わるのは、ずっと後のことになる。けれど少なくとも、そのきっかけは数日後……。それは真夏の、特別な一日。
第三十一話「河原に響く剣玉の音」
二日後。いつもと変わらぬ暑い夏日。心弥が稽古帰りにいつもの河原へ行くと、めずらしく和が土手に座っていた。
「和! めずらしいね。今日はどうしたの?」
心弥は自主稽古をすべく竹刀を取り出しながら、笑ってたずねた。
「うん。たまには夕焼けのお空が見たくって」
和は剣玉をしながら、にっこり答えた。カン、コン、カン……と、リズムよく赤い玉がはねる。和が剣玉をする様子やその腕前を、心弥はいつも見てきたが、飽きることはない。今日も少しの間、それをながめていた。心弥は、自分でも何故か分からなかったが、和が剣玉をするのを見るのが好きだった。
けれど心弥は、はっと思い出して言った。
「だめだよ和。夏は夕方になるのが遅いんだから。こんな暑いところにずっといたら、体壊しちゃうよ」
心弥は必死になって言った。
「だいじょうぶだよ。最近ぼく稽古でも倒れなくなったでしょ」
「でも、昨日は熱出して寝てたじゃないか。和のほっぺた腫れてたから、薫さんに聞いたら、父上にぶたれたって……」
なんだか泣きそうな心弥とはうらはらに、和は頬にそっと手を当てすまなそうに笑う。その表情は、時折見せる剣心の表情と、とてもよく似ていた。
「痛かったでしょ。だいじょうぶだった? おれ、父上に、熱がある和をぶったなんてかわいそうって言ったんだよ。そうしたら父上は、そーだな、でも思わずぶっちまってたって、そう言ってたよ」
「心弥は、弥彦さんによくぶたれるの?」
和は、穏やかな笑みをたたえ、たずねた。
「えっ? そんなことないけど……。でもすごく悪いことをしたときはぶたれるよ」
「そう。いいね……」
「へっ?」
心弥は、思わず間の抜けた声を漏らした。和の言うことが、あまりにも分からなかったからだ。
「ねぇ心弥。ぶたれたとき、どんな気持ちする?」
「どんなって……いろいろだよ。辛くって悲しくって……おれ、ぶたれたらいっつも涙でちゃうよ……」
心弥は、自分が情けなくてたまらないという風だった。
「あのね心弥。ぼく、どうしてそんな気持ちになるのか知ってるよ。それは弥彦さんが、心弥のこと大切だって強く思いながらぶつからだよ。その気持ちはすっごく強いから、心弥の心に強く響いて、痛くって……。だから辛かったり悲しくなったり、涙が出たりするんだよ」
「和は、本当に頭がいいんだね」
心弥は、いつものように感心して言った。
「でも、それなら和も、父上にぶたれてよかったね。だってそれって、父上が和を大切だって思ってるからだもんね」
「うん」
和は笑ってうなずいたが、どこかさみしげだった。その様子に何となく気付いた心弥は、竹刀を袋にしまう。
「和、遊ぼう?」
「心弥……いいの?」
「うん」
心弥が優しく笑うと、和はうれしそうに笑った。
「ねぇ、何して遊ぶ?」
「じゃあ、雲の形当てっこ」
和はそう言って、草むらに寝ころんだ。心弥も横に並んで、仰向けになった。
「じゃあ、おれから問題出すよ。あのおっきな、もこもこの雲は?」
「兄ちゃん。優しい兄ちゃん……」
和は静かに答えた。心弥は、思わず和の顔を見つめた。この三年間、和が心弥に剣路の名を口にすることはほとんどなかったからだ。うれしそうな、悲しそうな、夢を見ているかのような、和の顔はそんな風に心弥には見えた。
「当たりだよ。和」
心弥は、そう言ってあげた。和は笑ったまま、目に涙を浮かべていた。
第三十二話「いつか迎えに来てくれたら」
「和……泣いてるの? どうしたの? 体が辛いの?」
「ううん。だいじょうぶだよ、心弥」
和はそのまましばらく、泣きそうな顔で笑っていた。
やがて、空は夕焼け色に染まった。
「あっ、兄ちゃんが迎えに来た」
ふいに和が言った。心弥は驚いて土手の上を見上げる。だが、誰もいない。
「なご――」
「空想ごっこだよ。心弥も一緒にしよ」
「……うん」
和の様子がどうもいつもと違うのを感じながらも、心弥は和の言うとおりにしようと思った。
「目、つむって」
「うん」
和と心弥はあおむけに寝たまま、同時に目をつむる。
「兄ちゃん、怒ってる。ぼくが、こんなに遅くまで外にいたから。兄ちゃん、言ってる。和、こんな時間まで何やってたんだ、バカって……。それで、ぼくの襟首つかんで……。ねぇ心弥。兄ちゃんの役やってくれる? ぼくのこと殴って。思い切りだよ」
和は目をつむったまま、心弥に頼んだ。
「えーっ!? やだよおれ。和のことぶつなんて」
「お願いだから……。おもいきりだよ」
言い方は静かだが、和が切実にそれを望んでいるのが心弥には伝わってきた。心弥は目を開けがばっと起きあがると、目をつむったままの和の襟首をつかみ――思い切り和の頬を殴った。
和ははっとして目を開ける。襟首をつかんだままはぁはぁしている心弥を、和はしばらく呆然とながめる。少しの間、沈黙が続いた。やがて、和が口を開く。
「ごめんね……。心弥は心弥なのにね……」
「……まだ空想ごっこ終わってないよ。続けるよ……」
すまなそうな和に、心弥は低く押し殺した声で答える。そして和の襟首をつかんだまま、心弥は和に怒った顔を見せる。
「おれ……俺が、どれだけお前のこと心配したと思ってるんだっ! あやまれ和! ごめんなさいしろっ!」
「ご……ごめんなさい」
「本当にそう思ってるのかっ!? もっと反省しろバカやろぉっ!!」
心弥は和を殴り飛ばした。和の唇が切れて、血が吹き飛ぶ。
「……ごめんなさい。ごめんなさいっ。ごめんなさい兄ちゃんっ!!」
和は必死にあやまる。心弥は、和をぎゅっと抱きしめた。
「本当に、本当に本当に心配したんだぞ! だって和は俺の、俺のたった一人の大切な弟なんだから……!!」
和は、そっと心弥にしがみついた。が、やがて手を離した。心弥は汗だくで、息を乱していた。
「ごめんね和。剣路兄ちゃんの真似、上手く出来なかったよ。すっごく頑張ったんだけど……。剣路兄ちゃんは意地悪になっちゃったけど……、でもおれね、いつか剣路兄ちゃんは優しい人に戻ってくれるって、そう思ってるんだ。ねぇ和、そうしたら剣路兄ちゃん、きっと今みたいに和を怒ってくれるよ。和のこと大切だって、そう言ってくれるよ。あっ、おれ布を川の水で濡らしてくるね。ほっぺた冷やさないとねっ」
心弥は一気にまくしたてると、川縁へ走っていった。
心弥が戻ると、和は泣いていた。肩を震わせ、ただ静かに、手のひらであふれる涙をぬぐっていた。
「和……」
心弥は、もうそれ以上は何も言わず、和の頬に濡らした布を当ててやった。
「心弥は、ぼくのこといっぱい分かってくれてるんだね」
「だって、友達だもん」
ふいにもらした和の言葉に、心弥は笑顔で答えた。和は微笑して、手にしていた剣玉をしばらくじっとながめていたが、急に心弥に差し出した。
「これ、もらってくれる? 心弥」
「えっ? いいのっ!?」
心弥は胸が躍った。剣路がまだ優しかった頃、使い古しのおもちゃはよくもらっていたが、唯一剣玉だけは和の手に渡された。その時、とてもうらやましかったのを覚えているし、優しい和が唯一自分からは貸してあげると言わなかった玩具だ。
けれど、心弥は思い直した。
「ダメだよ和。それは和の大切な、剣路兄ちゃんからもらった大切な剣玉じゃないか。いつもいつも大事に持ってたのに。宝物なんでしょ?」
「だからだよ」
和は、心弥の手に剣玉をにぎらせた。
「心弥は一番の友達だもん。だからだよ」
「でも……」
「心弥に持っていてほしいんだ」
和はにっこりと笑った。心弥はうなずいた。
「ありがとう和。大切にするね。おれにとっても、和は一番の友達だよ」
心弥と和はお互い向き合い、そして笑った。
その日の夕日は、いつもよりいっそう赤かった。
それから心弥は出稽古帰りの弥彦に声をかけられ、ともに帰っていった。剣心が近くで探してたから伝えておいてやると弥彦に言われた和はお礼を言い、けれど心弥たちが帰ると、和はあわてて木の下へ走っていった。
心弥は、父の背中を見ながら、改めて思う。剣路のことを思っていたのは、自分だけではないのだと。少し前を歩く父も、ずっとそうだった。食事の席で、たびたび箸が止まる父。なんでもないと父は言うけれど、剣路のことを考えているのだと、心弥は知っていた。剣路が神谷道場を出たあの日から、ずっと……。そして和もまた三年間、一日だって剣路を思わなかった日はなかったのだろう。
和が川で手を洗っていると、うしろから父の声が降ってきた。
「和」
和はふりむいた。予想したとおりの、少し困ったように笑う父がそこにいた。
「こんな遅くまで遊んでいたらダメでござろう? さっ、帰るでござるよ」
「ごめんなさい」
あやまる和に、剣心は手をさしのべた。
「父さん……」
ぼくのこと、怒ってもいいんだよ。ぶってもいいんだよ。そう言いかけて、和は言葉をのんだ。父さんは、そういう人じゃない。どこまでも深く優しい人だ。
和は、大きくあたたかい父の手をとり、にっこり笑った。
注:ここより先はストーリー展開がかなり過酷になります。苦手な方はご遠慮ください。
第三十三話「ある夏の一日」
注:この回よりストーリー展開がかなり過酷になります。苦手な方はご遠慮ください。
翌日。いつもと変わらぬ、空から真夏の強烈な太陽が射す一日だった。
午前十一時。剣心と薫はそろって出稽古へ出かけようとしていた。今日は少し遠くの道場へ行くことになっている。最近では剣路のことですっかり気を落としている薫を心配し、剣心はよく出稽古に行く薫につきそう。それは、和が健康になってきたから出来ることでもあった。
父と母が出かけるのを、和は玄関先で見送った。
「父さん、母さん、いってらっしゃい」
にっこり笑う和に、剣心と薫は一瞬の間をおく。
「ああ。留守番頼むでござるよ」
「おみやげ買ってくるからね」
二人は和に優しく声をかけると、門を出た。
「剣心。さっきの間はいったい何?」
「いやぁ。なんだかあまりにも和が愛おしく見えた故」
「私もよ」
二人はお互い微笑した。剣路のことがなければ、もっと手放しで喜んだことだろう。
和は、剣路の部屋の前に立った。障子の向こうには、相変わらず自室にこもりきりの剣路。和は、黙ったまま障子をにらんでいた。そして、障子をすぱんと開けた。
剣路は、奥の柱に寄りかかったまま座っていた。生気のない目。和の方を見ようともしない。
和はずかずかと部屋へ入っていくと、剣路を見下ろした。そしておもむろに剣路の懐をさぐり、小刀を取り出す。
「ふうん。これで死のうとしてたの」
和は、静かに語りかけた。
「けど死ねなかったんだ。死ぬ勇気もなかったんだね。弱いね兄ちゃんは」
和は、剣路から目を反らさなかった。その目は、和が見せたことのない、冷淡な目だった。
「逆刃刀をうばって心弥を殺すんだって? でも自分から弥彦さんに挑発しておいて、こてんぱんにやられてたね。バカだね兄ちゃんは。ぼくにさえ勝てないのに」
和はくすりと笑った。剣路の肩がぴくりと動く。その一瞬を、和は見逃さなかった。
「くやしい? だったらぼくと勝負してみる? まぁ兄ちゃんはぼくに勝てないよ絶対。剣でも勝てないし、愛情だってぼくはたくさんの人からもらってる。こないだだってぼくが無理な稽古してたら、弥彦さんがすっごく心配してくれたんだよ。兄ちゃんが本当は大好きでたまらない『弥彦兄』にね」
剣路の息づかいが乱れる。
「勝負しないならそれでもいいよ。ぼくに負けたまま、死んじゃえば?」
和は、おもいきり小刀を剣路の胸にぶつけた。
その瞬間。剣路は和の首を締め付けていた。
「殺されんのはお前だ……。和……」
剣路は押し殺した声でうめいた。憎しみをあらわにした顔で。
「お前のせいだ……。何もかも……。お前なんか生まれてこなければよかったんだ」
その瞬間、和は息をのんだ。剣路も一瞬だけ手をゆるめる。だが和はすぐに剣路を睨み付け、剣路は首を締め付ける手に力をいっそう強く込めた。が……やがて離した。
「来い和っ。道場で勝負だっ!」
剣路は部屋を出ていく。和もついていった。
第三十四話「剣路と和」
神谷道場内。剣路と和はお互い向かい合って竹刀を握る。ピンと張った空気が道場内に漂っていた。
「木刀にしなかっただけありがたく思ってよね。木刀じゃあ兄ちゃん死んじゃうからね」
「なめたこと言ってんじゃねぇっ!!」
剣路は真っ向から和に打ってくる。だが和はなんなくかわすと、兄の体に銅を打ち据えた。
「一本だよ兄ちゃん。試合ならぼくの勝ちだ」
「……るせえっ! これは殺し合いだ!!」
剣路は抜刀の構えを取った。和もそれにならう。
「神速勝負? 飛天御剣流の基本だね。でもぼくは負けない」
和は真剣に兄を見据えた。そのまましばらく、どちらも動かない。
「……はぁっ!!!」
「……やぁっ!!!」
二人が剣を振ったのは同時だった。そして……和は剣路の剣をかわし肩に一撃入れた。
「ほらね」
和は笑う。だが、その息は少し上がっている。剣路は片膝をつき、苦しげに肩を押さえる。わなわなと体を震わせていた。
「まだ負けを認めないの? いい加減みとめなよ。ぼくのほうが剣才が上なんだ。今の兄ちゃんには絶対ぼくに勝つことは出来ないよ」
「……いい気になるなよ。俺にはとっておきの技が残ってんだ」
「じゃあ、次で本当に最後の勝負だよ」
剣路は立ち上がる。お互い向かい合い、それぞれ相手の目をにらむ。ことさら和は、剣路を睨み付ける。息を乱しながら。
「いつまでそうしている気だ。さっさと構えろ」
「……」
和は、剣路から目を反らさぬまま、構えた。
「いくぞ……」
「うん……」
それからしばらく沈黙が続き……そして二人は剣を繰り出した。
「飛天御剣流・九頭龍閃!!!」
剣路が九つの斬撃を繰り出す。
「飛天御剣流・天翔龍閃!!!」
和は、なんと飛天御剣流奥義の超神速抜刀で立ち向かった。
「うわぁっ!!!」
剣路は、道場の壁までふっとび、ダアンと壁に背中を叩きつけられた。
「ぼくの……勝ちだよ……。兄ちゃ……」
勝ったはずの和が、何故かふらりとその場に倒れた。
「おい……。和?」
剣路はふらふらと、和に近づく。和の体を見たが、九頭龍閃の傷はついていない。当然だ。九頭龍閃は本当は未完成の技だったし、和に届いていなかったのも剣路は知っていた。にもかかわらず、和は苦しげにうずくまっている。剣路がよく見ると、和は胸を押さえて息苦しそうだった。
「よかったね……。ぼくの奥義が……完成してたら……兄ちゃん死んじゃってたよ……」
肩で呼吸しながらも、和は笑って言葉を紡ぐ。
「でもね……。兄ちゃんはちゃんと稽古すれば……ぼくより強いよ……。絶対だよ……。だ…って、兄ちゃ…は、日本一に…なれる…て、ぼく…分かってる……か……ら……」
和は弱々しい声で、必死に兄と話す。目が、半分閉じかけている。
「和お前まさか病気が……」
和は、かすかにうなずいた。
「も……、隠さなくても……いい…ね……」
「隠さなくてもって……お前三年間も病気隠してきたのかっ!?」
和は、目だけでうなずく。
「兄ちゃん……ぼく……生まれてきて…ごめんね……」
和は、辛そうに笑う。
「でも……も…死ぬから……だいじょぶ…だよ……」
言葉を紡ぎ出すたび、和は苦しげに息を吸う。
「ぼくね……兄ちゃんが今日……ぼくのこと真剣に見て…くれて……うれしかった……」
和は、ほとんど目を閉じる。和は最期の力をふりしぼり、懐から折りたたんだ和紙を出す。
「遺言状だよ……。もし…今日のことがばれても……だいじょ…ぶ……。ぼくが自分の意思で…死ぬことを選んだって……ちゃんと書いてあるから……」
和から差し出された遺言状を、剣路は無意識に手にする。
「兄ちゃ…は……生きて。そして……弥彦さんの跡を…継ぐ夢……かなえて…ね……」
和は、じっと兄を見つめると、力尽きて目を閉じた。
前ページへ 次ページへ
ご感想、 日記 のコメント欄・ 掲示板 ・ 拍手 コメント等に書き込みしていただきますと、とても励みになります。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月18日分)
- (2024-12-02 00:00:48)
-
-
-

- 楽天ブックス
- 百華後宮鬼譚・リブート! 1 目立た…
- (2024-12-02 12:05:28)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 細野真宏の数学嫌いでも「数学的思考…
- (2024-12-02 07:22:24)
-
© Rakuten Group, Inc.