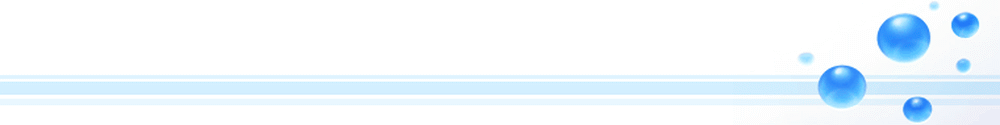小説 5~
オリジナル小説目次『巡る季節と最後の約束』(『13歳の夏』シリーズ その5)
『13歳の夏』シリーズその5。中三の春を迎えた隆介と皐月。恋も夢も順調で、幸せいっぱいの二人。そんな矢先、突然皐月は意識不明となり……。シリーズ最終話です。
それは、あまりに突然のことだった。隆介と並んで歩いていた皐月は、突然ふらりと倒れたのだ。顔面蒼白。嘔吐。隆介が触れた皐月の体は、冷たかった。
救急車で運ばれた総合病院。そのまま手術室にいれられた皐月。皐月の両親が、あわててかけつける。それから、学校の先生や皐月の友人や――。
隆介は、手術室の前の椅子に、ぼんやり座る。手を組み、口を結び、ただ一点を見るとも無しに見る。
その間隆介が理解出来たことといえば、皐月がこのままいなくなってしまうかもしれないこと――ただそれだけだった。
七歳の時に死んだ両親。重い病に倒れた今の父。同じクラスになった親友が亡くした母。
いつか皐月も――。隆介の、小さな、けれど常に胸にあった不安は、こんな形で的中した。
別れがどんなものであるかを、隆介は知っている。
手術室に、皐月の両親が呼ばれた。先生から二、三言何か告げられたあと、二人は泣きながら部屋へと入っていく。
季節は夏になっていた。隆介は、花束を抱え、太陽に解かされそうなアスファルトの道を歩く。
「病院にいるとね、季節があまり感じられないの」
皐月は、白いベッドに横たわり、隆介に微笑する。病室のカーテンが、風でひらひらと舞う。隆介は窓辺に、花を挿した花瓶を置いた。二人部屋だが、入り口側のベッドには誰も入っていない。とても静かだった。隆介は、皐月の傍らに椅子を置いて座る。
「だって、いっつも冷房が一定の温度に保たれているでしょ。それに、薬の匂いが充満してるから……」
「じゃあ今度、そこらへんに咲いてる花摘んできてやる」
「うん」
皐月は、小さな声で答えた。小さな声しか出なかった。たくさん管をつけられ、ろくな食事もとれず点滴ばかりで、やせ細ったその体では。
「ちゃんと、受験勉強してる?」
「ああ……」
本当は、それどころであるはずがなかった。勉強どころか、剣道の稽古さえ、集中できない毎日。
皐月はもう、長くはないと聞いた。告知はしないと決めたのは、皐月の両親だ。
「あのね、私、保母さんになるの」
ふいに、皐月はそう告げた。隆介は、黙ってうなずく。
「でもね、その前にね、隆介と同じ春校へ行くの」
微笑したまま話を続ける皐月に、隆介はただうなずく。皐月は白い手を、そっと差し出す。細い腕には、点滴の跡がたくさんついている。隆介が握ろうとした皐月の手は、するりと隆介の頬にのばされた。
「不安なんだね、隆介……」
「なんでだよ……」
「不安になると体が冷たくなるんだって。小説で読んだの」
隆介は、頬にふれる皐月の手を、自分の手で包み込む。
「そんな顔しないで。私、病気治すから……」
隆介の体が、ビクッと反応した。
「幸せになるって、約束したよ。去年のクリスマスイブに……」
隆介は、必死で涙を呑み込んだ。
隆介と入れ違いに、春子が病室を訪れた。
「幸せになるって、隆介と約束したの。隆介が、私のことを自分のせいだと思わないように……」
「うん。そうだね……」
春子は皐月の傍らに座り、優しく皐月を見つめる。
「だけど、本当に私の体、治るのかなぁ……」
春子はそっと皐月の手を握る。
「私、やっぱり、死ぬのかなぁ……」
言ったとたん、皐月は堰を切ったように泣き出した。
「怖いよ……。死にたくないよ……。生きていたいよぉ……」
春子は、皐月をぎゅっと抱きしめる。
「まだたった中三なんだよ……。これから先、いっぱい楽しいこと……あるはずなのに……」
皐月は春子にすがりつく。
「ずっとずっと……隆介のそばにいたいよ……」
そのまま、病室は静かになった。皐月のすすり泣く声も、だんだん途切れた。
「ハル……ありがとう……」
春子に抱き付いたまま、皐月はつぶやいた。
「隆介が……言ってたの……。親友は……大事だって……。今なら分かる……。私、隆介の前じゃこんな風に泣けないから……」
「うん……。いつでも泣いていいよ」
春子は、皐月の背中を何度もさすった。
やがて空は高くなり、木々の葉は色づいた。
皐月と隆介、二人きりの病室。窓の外からは、黄色い銀杏の葉が舞っているのが見える。
「私ね……もうダメみたいなの……。がんばったんだけど……ごめんね……」
皐月は、微笑した。手足はますます細くなり、頬はこけている。
「……あやまること、ねーって」
ぼそりと、隆介は低くつぶやいた。
「ねぇ隆介……。頑張っても……どうにもならないことって……世の中にはたくさんあるよ……」
皐月は、隆介の手をそっと両手で包み込む。
「それでも……私は幸せだった……。お父さんがいて……お母さんがいて……ハルがいて……。そして……隆介がいて……」
隆介は、黙って皐月を見つめる。
「病気になってからはね……青い空を見ることが出来る……それさえ幸せに感じるの……」
皐月は、弱々しく息を吐き、続ける。
「隆介といる時間もね……大事でたまらなく思えるの……」
隆介は、皐月の手をにぎる力を強める。
「そう……思えるように……なったから……、長く生きられる人より……幸せかもしれない……」
皐月は、にっこり笑った。
「だから……隆介も……幸せになって……。約束……した……でしょ……。一緒に……幸せに……なるって……」
隆介は、皐月を抱きしめた。
「ごめん皐月……。おれは……皐月がいないと……。剣道も……勉強も……全然ダメで……。だっ……剣道でいくら強くなっても……皐月が喜んでくれないと……おれ……」
泣いているのだろうか。ベッド上の皐月を抱きしめた隆介の表情は分からない。小さな声で隆介は、情けねぇ、とつぶやいた。
「隆介……」
皐月はとまどう。隆介は顔を上げ、こぶしで目をこする。目が真っ赤だった。ずいぶん泣いたようだ。
「皐月……」
隆介は、皐月の両肩に手を置いた。
「おれも、皐月が病気になって分かったことがある……」
隆介は、皐月を見つめる。
「皐月がいたから、いつだって幸せだったこと。おれの幸せは、皐月がそばにいることなんだってこと」
「隆介……」
「おれは、皐月といっしょに生きていきたいんだ」
真っ直ぐ見つめたその目は。皐月の心を射抜いた。
その年の暮れ、皐月は危篤状態に陥った。クリスマスイブの夜だった。隆介は、病院へむかい街を駆ける。
皐月はもうろうとした意識で。隆介は息を切らしながら。
ベルの音を聞いた。
去年のクリスマスイブ。
『皐月には……幸せになってほしいんだ』
皐月は隆介の言葉を。
隆介は口づけた皐月のいとおしさを。
それぞれ思い出していた。
翌年。桜舞い散る季節がふたたび巡る。
隆介は独り、桜並木の道を歩く。去年は、皐月と一緒だった。
隆介は、墓へむかう。
墓前に花を添え、隆介は優しくささやいた。
「ありがとう……。おれ、幸せになるよ……。だから安心しろよな……」
そうして、隆介はその場を後にした。
桜舞う道を再び歩く隆介。空を仰げば、青い空からいっぱいの花びらが降る幻想的な光景で。隆介は思わず息を呑んだ。
「春高の制服、似合ってるね!」
振り向くと、にっこり笑って立っていたのは皐月だった。
幻――そう思った一瞬。けれどこれは確かに現実。
「ばか! まだ外歩ける体じゃないだろお前は!」
「だって隆介、一回も春高の制服着てるとこ見せてくれないんだもん。だからこっそり病院抜けてきちゃった」
えへへと、皐月ははにかみ笑いをする。
「そりゃあ私は、結局退院したら中三のやり直しだけどさぁ。だからって気を遣わなくてもいいんだよ」
皐月はにっこり笑いながら、隆介のまわりをくるりと一周して姿を眺める。
「それに、今日は隆介の死んだお父さんとお母さんのお墓参りに行くって言ってたし。私が良くなるように、何度もお願いしてくれたんでしょ。だったら私も一緒にお礼を言いたかったな」
「おれがお前の分も礼言っといたから。すぐ病院に戻るぞ」
隆介は、皐月の手をぐいとひっぱる。
「待って! お願い! ちょっとだけ……!」
「なんだよ……」
「毎年必ず隆介と桜見るって決めてるんだもん。今までも、これからもずっと……!」
皐月は、幸せそうに隆介の腕に抱き付いた。
「クリスマスイブの日にね、鐘の音が聞こえたの」
ふいに皐月は言った。隆介はドキッとした。隆介にもその時、確かに鐘の音が聞こえた。
「幸せになってほしいって、前に隆介が言ってくれた言葉を思い出したの……」
あの日、危篤状態にまで陥った皐月は一命をとりとめ、以来急速に回復していった。
「おれもあの時思い出した……」
皐月はきょとんとする。
「何を?」
「キスしたこと」
「うそぉ信じられない! やらしい!」
隆介は、照れたようにそっぽを向く。
「うそだよ。すっごくうれしい!」
皐月は、そんな隆介の顔を覗き込んで笑った。隆介は照れたまま、横目でちらりと皐月を見る。
「ねぇ隆介。約束しよ」
皐月は、桜を見上げて静かに言う。
「お前は約束が多すぎるからなあ……」
「じゃあ最後の約束でいいよ」
皐月は、舞い散る桜を体に受けとめながら、語り出す。
「夏には花火を見に行こうね。秋には銀杏の葉っぱでしおりを作ろうね。冬にはクリスマスの街を歩こうね」
「なんか多くねーか? それにしおりってなんだよ……」
ぶつぶつ言う隆介におかまいなく、皐月は続ける。
「そして、春にはこうして一緒に桜を見ようね。毎年だよ!」
振り向いて。にっこり笑う皐月は。桜吹雪の中に、そのままとけてしまうのではないかと思った。隆介は思わず、皐月の手を取る。あたたかくて、ほっとした。
「約束だよ。隆介」
「ああ」
「ありがとう……」
皐月の頬から、静かに涙が伝った。隆介にとっては、服に染みこむ涙さえ愛おしかった。
大人でも子供でもない中学の三年間。二人は出会い、恋をして。ささいなことで、たくさん悩み。大きな苦しみに、たくさんのことを覚えた。
そうして育まれた二人の愛情は。もう戻らない尊い三年間は。これから遠い思い出となっていく――
大人になった二人が、肩を寄せ合い思い出の箱を開ければ。そこにいるのは、変わらぬままの中学生が二人。あの頃の隆介と皐月は、今も、色あせぬままそこにいる。
☆あとがき☆
大人でも子供でもない中学生。その等身大の恋愛を書いてみたいと思ったのが始まりです。ちょうど第一作目はキリ番リクエスト小説(内容はお任せ)ということで、リクエスト者様の年齢と合わせて書き始めました。中学生の未熟な恋愛を中心に、進路や友情等日常的なことから、病気という大きな試練までを書きました。中学生といえば一番多感な時期で、一生懸命考え、傷つきながら、それでも一番成長する時期だと思います。そんな皐月と隆介が育んだ愛を、感じ取って頂けたなら幸いです。
前ページへ
ご感想、 日記 のコメント欄・ 掲示板 ・ 拍手 コメント等に書き込みしていただきますと、とても励みになります。
オリジナル小説目次
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- D様の両親(AI画像)
- (2024-11-29 10:22:38)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- 経済
- 2024.9.3.財界オンライン:2024-09-03 元…
- (2024-11-12 00:09:27)
-
© Rakuten Group, Inc.