全て
| カテゴリ未分類
雑記・覚書
| その他
| 心霊について
| 戦争・近現代史
| 魂の不思議さ
| 人権
| 憲法・政治
| 追憶
| 創作
| 憲法・社会変革
| 論考
| エッセイ
| 小説
カテゴリ: 小説
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
この時代に釈迦がいるとすれば、仏教思想が観念の世界へ帰って行くのは、まだずっと後の事だから、神山たち一行はシヴァ神に頼んでわざわざ、この時代へとやって来たのだ。仏教はまだその原初の形態にあり、極めて簡素な理論を唱える集団に過ぎないからだ。
釈迦が本当は何と名乗っている人なのかさえ、まだ神山も知らない事なのだ。文献の通りに釈迦と名乗っている確率は低そうに思えた。この場合、神山は調査対象の名前には、拘らないことを心に決めて、皆にもそう語った。釈迦であるべき人物は、この時代この時空で、その青年期を過している。然しその人物がこの時代、釈迦と名乗っている確率は五十パーセント以下だと思った方が良い。後世に釈迦なる名前で記述されただけなのだと考えた方が良い。否寧ろ、そう考えた方がすっきりする。釈迦と言う呼称に拘らなくて良いのだ。探すべき相手の手掛かりは、「仏陀」を称する人物で、存在論やその相対化を中心に、独特の思想や法則を組み立てつつある若き思想家だと言う事だけだ。今の所、その人物の手掛かりは少ないかも知れないが、それならば、出来るだけシンプルに、「的」を絞った捜索を展開する方が良いと、神山は考えているのだった。
この時代も思想家は、確実に大都市部にいると考えられる。サバンナや洞窟などには、通常はいないと考えられる。その様な所に行くのは、旅の都合でやむを得ず行かなければならない様な場合に限られる。ベンガルトラや、オオカミに食べられても良ければ別だが、仏教徒はその様な無茶をしないと考える方が妥当だ。神山たちもこの時代にやって来てから初めて、サバンナや洞窟の如何に危険かと言う事を、身を以て学んだ。文献に描かれている事は飽くまでも参考に留めて、現実の環境に合わせて判断した方が良いのだ。

神山たちが宿屋へ帰る前に少し息抜きにと、木陰の喫茶店を思わせる茶店で甘いものと冷たい飲み物を楽しみながら午後も遅い、涼しい会話時間帯の会話を楽しんでいる時、神山たちは、何か聞き慣れた音が響いて来るのに奇妙な心持になり、蒼い天空を見上げた。
遠くから、地上にいては、国籍が判別できない程度に高い高度を飛んで来る、レシプロエンジンの航空機の群れが見えた。その内の一機が、その群れから離れて、神山たちが美味しい飲み物やお菓子を楽しむ、茶店の方角へと、高度を下げながら飛んでくる姿に、神山ら一行は何とも場違いで、「いやあな」気持ちになった。
海野ならこういう時にこそ「とんちき」という表現でこれを語るはずだが、余りに「とんちき」が過ぎて、呆れかえっていた。
旧式の戦闘機か攻撃機らしいその一機は、幸いにも、古代の市街地に攻撃を加えることなく、様子を探るだけで飛び去って行った。
一行には、この事象の訳が分からず、思考が暫く止まっていた。
暫くして、皆の沈黙を破ったのは海野であった。
ほかの皆も、何とも表現しがたい気分に襲われていた。
一群の航空機を目撃した古代のインド人は、更に驚きだった。聞いた事も無い轟音を立てながら、空に沢山の空飛ぶ塊みたいなものが現れて、頭上を飛び去って行ったのだ。神の乗り物か何かに相違ない、異常な事が起きたのだと、彼らもその心を傷つけた。
紀元前五世紀の、マドラの街で軍用機の群れを見たり、それが立てる轟音を耳にすれば誰もが、心を深く傷付けられるだろう。思いもしない時に思いもしないものが現れると、人は理解の限度を超えたその出来事を消化出来なくなって、心を深く傷付けられてしまうのだ。
然し、それらの航空機に搭乗しているパイロットやクルーは、もっと心が傷付けられていた。
つい、先刻まで十九世紀の始め頃のロンドン上空にいたホッジ中佐の率いる二個飛行大隊は、今また見た事の無い風景を下に見て、混乱していた。
ホッジ飛行大隊はそもそも、ハルゼイ提督率いる航空母艦群に所属していた。それが飛行中にタイムスリップして、十九世紀初め頃のロンドン上空へ飛ばされたのだ。それだけでもホッジ中佐を始めとした搭乗員たちには、うんざりするほどの出来事であったのに、漸くロンドンの皆にも親しみを持ってもらえるようになった矢先、今度はまた何処か知らない国の上空にいたのだ。少なくとも上空から見える風景は、欧州のものでは無い。見慣れぬ形と色をした建物、そして見知らぬ街。航空燃料も心配だ。ホッジは二個飛行大隊が無事に着陸できそうな場所を、早急に探さねばならなかった。然し、眼下に見えるのは、建物が密集した何処かの国の大都会らしい。多くの航空機が安全に降りられる、広くて平らかな場を探すのは至難の業だ。ホッジは河べりを探した。大きな河の端には、比較的平らな地面があるものだ。ホッジは懸命に、それを探した。上空から見ると、この都会は海に近い事がわかった。だが、海の方まで飛んでしまえば、都市まで帰るのに難儀かも知れなかった。ホッジ中佐は街のはずれに、大きな緑地らしき土地を発見した。彼は迷わず飛行大隊をその緑地の上空まで導いた。
まだ日暮れには早過ぎる遅い午後、そよ風にも漸く涼しさを感じられる頃。
その広場には、早い夕涼みや散策に訪れた人たちや、その広場に住まう人たちが天空を仰いで、奇妙な得体の知れないものが、轟音と共にその数を増していくのを眺めていた。
見た事も、聞いた事もないその何かは、古代の人々には空を蔽えるほどの数に感じられ、その轟音に、耳は聞こえなくなりそうだった。
この広場にも、修行者は住んでいた。神山ら一行が探している、「仏陀」を称するほどの思想家も、幾人か含まれていた。彼ら修行者は天空を仰ぎ見ると、飛んでいるのは、神の乗り物であると決めてしまった。神々が天空を飛ぶ乗り物でやって来た。間もなく災厄が訪れるだろう、と言うものもあり一方で、地面のインド人たちは、天空を見上げながらも、身構えた。この広場は、旧式の軍用プロペラ機の離発着には、まったく支障の無いほどに平らかで広く、適度に草も茂って安全でもあった。滑走路に使うには、ちょうど良い按配の土地だったのである。
とにかく地面に降下しなければ、何も分からないでは無いか。ここが何処の国なのか?ホッジもしっかりと確かめたかった。如何に「般若事象」と言われるようになった一連の怪異事変の数々あれど、まさか自分たちが今度は、紀元前五世紀のインドに移動させられたなどとはまだ、ホッジ飛行大隊の誰一人として知る由も無いのだった。
いかな「般若事象」とは言え、という思いは神山たちにも共通していた。
「まさか古代のインドですよ、ここはあ!先刻のあの、軍用機の群れと言うかなんと言おうか、ありゃあ、一体なんです?」こう聞いているのは海野である。
「日本の軍用機じゃあ無いみたいだが、般若の奴は全く!何んという!!」ここまで言って海野はもう、言うのを止めた。時空間の捻じれや時空同士の一体化などの全ては、少年としてその姿を現した「般若」の仕業である。一度その、少年としての姿を見た者にはどうしても、「般若」が、憎めない子供なのであった。
「般若」のそこが、確かに気の毒な所だ。誰もまともに付き合ってくれる友も無く、家族もいない。仏教思想の中では特殊な扱いを受け、人格を得た「般若少年」にとって人類はまったく無責任なものであった。「自分のため」だけに祈られた、身勝手な願望だけを押しつけられて、思えば般若は苦労させられてきたはずだ、少年の人格であったら「グレ」たくもなっただろう。
そのいわばグレた少年が今、時空間を破壊して、この世界そのものを無くしてしまおうと捻じり上げているのは、人類に対する怒りから来たものであった。
海野にも、「般若少年」に同感するところはあった。無論神山にもあった。
神山などは「般若少年」のいわば、保護者同然であったのだ。同感や同調を超えて、心から「少年」を案じていた。それは同行する手力男も同じだろう。
「早くほんとの親御さんとも言える、釈迦に対面できれば良いのですが。そうしたら、その『仏陀』がきっと、般若を用いて「般若少年」に光を与えて呉れる事でしょう。歪められる前の自然な「般若」の光を浴びて、自分を大事にする心を持ってくれたらそれで良いのですがねえ」
神山に言わせれば「般若少年」は「グレ」ている。偽りの「般若」と、心無い人類の、身勝手な願望によって自分を見失った少年と同じなのだ。自分自身がその身勝手な「祈り」に利用され、都合のいい願望欲望に振り回された。自分で自分を粗末にしてしまった事を「少年般若」は悔いているだろうと、神山は語った事があったのだ。
「いわば、存在観察から永遠の願望へと姿を変えた、般若という概念に「般若少年」は苦しめられたのでしょう。結果はそう言う事なのだから」と、苦しそうに神山は言うのであった。だから、一刻も早く「般若少年」を釈迦と対面させたいと言う、神山のこれは「親心」なのだった。シヴァ神や手力男も、海野も、こんな神山の心を知って何とかこれを手伝いたかった。
また、麻衣や青年はむしろ「少年の姿をした不思議な存在」に、兄弟感覚で付き合う内、いつしか大切な存在として感じる様になっていた。
そしてコロは唯一「少年般若」が、心を許せた友であったのだ。
「そうなのじゃ。皆のその気持ちを信じてわしは、お前達に与力して来たのじゃぞ。そうして何よりも、お前達には、きっとあの哀れな『少年般若』を支えて、行くべき所へと送り届けてくれるだけの力が備わっておる。コロの神性は最高の力を発揮しておるしのう」シヴァ神は、こう言いながらコロに、インド風揚げパンを、ほんの少しだけ食べさせると、その残り半分を自分で食べた。インドの大地を撃起きまわるので、ダイエットなど要らないのだが、コロに上げるお菓子には気を遣うのである。
「ころ~お。ふとっちゃうじょ~お」海野も気を遣っていた。そんな皆を、麻衣は微笑みながら見ていた。
この時、神山たち一行は未だ、明日会いに行く予定の、二人目と三人目の、二人の「仏陀」を称する人物の住むこの街の第二公園とでも言うべき広場で、ひと騒ぎが起きている事を知らない。
そこでは、「神々が降臨して来た」と、大騒ぎになっていた。
古代インド人は天空を駆け回り、天空から地上に降臨して来る神々を信じていた。その神々は、神々と人類に害をなす者をうち滅ぼす空飛ぶ乗り物と、天空で使う各種の武器について記録し、後世に伝えた。
紀元前五世紀のインドの、更に古代から、こうした記録が神々について、その乗り物や武器の特徴とともに伝えられている古代インド人は、先刻、轟音と共に天空から地上に降臨した神々を恭しく迎え、敬礼しまた礼拝して手厚く供養した。この場合の供養とは、神々に対する「もてなし」の事である。
だ、ここで神々とされ、「もてなされ」ていたのは神々では無く、先刻、米海軍の軍用機から地上に降り立った、ホッジ中佐とその大隊の将兵たちなのであった。
明日、シヴァ神や神山たちがその広場へ行くまで、ホッジ中佐たちが無事でいる事が出来たらシヴァ神や、神山博士の力で、神や地元民と意志の疎通は無論スムースに出来るようになるだろう。
厳かさや敬意さえきちんと伝えられていれば、インド人は古代からかなり文化人だったので、問題は無いのだが・・・。
(続く)
にほんブログ村
にほんブログ村
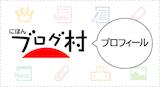
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024/05/12 04:26:16 PM
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









