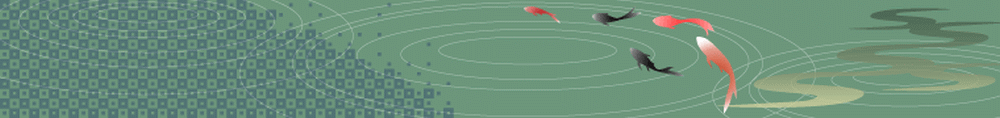考古学・歴史日記02年中頃
今日は夕方講演会があった。講師は今マールブルクに研究のため留学しているユーゴスラヴィアの人である。テーマはバルカン半島中央部の初期中世、すなわち5世紀・6世紀くらいの話である。
ところが残念なことに、講師の人はドイツ語ネイティヴでないうえに、ものすごく早口で発表したので、かなり理解できなかった。要するに、今のユーゴスラヴィア地域におけるゲルマン人の痕跡というのが発表の眼目だったと理解した。
もっとも、特定の考古遺物から民族帰属を同定するという研究方法はやや安直ではないかという疑問がぬぐえなかったが。日本では最近は弥生時代の開始(紀元前3世紀頃)というのは大陸からの農耕民の渡来という単純な図式ではなく、在来の縄文人からも積極的な参加があったというのが通説化している。民族同定というのは実にナイーヴな問題である。だいたい、当時の人がそんなに「民族」にこだわりをもっていたのだろうか。こだわったとしたら言葉くらいだろうが、それは考古学の範疇ではない。
今日の発表にあったのだが、僕は「バルカン半島」というとハンガリーとかも入れて考えていたのだが、大体ドナウ河以南というのがバルカン半島の境界であるらしい。今の国名で言うとクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ユーゴスラヴィア(セルビア+モンテネグロ)、マケドニア、ブルガリア、ルーマニア南部、ギリシャ、アルバニア、トルコのヨーロッパ部分である。
バルカン半島というのは、西ヨーロッパと西アジア(中近東)を結ぶ陸橋のようなものと理解することが出来る。農耕・牧畜や冶金は先進地帯だった西アジアからバルカン半島を通って西ヨーロッパに及んだと考えられている。一方で、中央ユーラシアの大草原が終わるところ、という見方も出来る。そのため、遊牧民世界とも密接なつながりがある。
地中海世界を制覇したローマ帝国(紀元前1世紀~後4世紀)は、大体ドナウ河の線で拡張をやめた(例外はルーマニア。「ルーマニア」という国名時代が「ローマ人の国」という意味である)。それより北は占領しても労多くして得るものが少ない、ローマから見て「野蛮の地」だったからだろうか。
さて今日の講演の時代の話になる。4世紀の末、ローマ帝国が東西に分裂するのとほぼ時を同じくして、東方からさまざまな民族がローマ帝国目指してなだれ込んでくる(世界史の授業で習ういわゆる「ゲルマン民族の大移動」である)。もともとは中央アジアでの遊牧騎馬民族間でのパワー・バランスの崩壊がきっかけで、それに玉突きされるように西へ西へという動きが起こる。ゲルマン、アラン、フン、スラヴなど様々な民族が豊かなローマ帝国目指して移動してきた。
今でこそユーゴスラヴィア、すなわち「南スラヴ人の地」というが、今日の発表によれば、今のユーゴスラヴィアにも、ウクライナあたりにいたゴート族、北ドイツあたりにいたランゴバルド族、ポーランドあたりに居たゲピド族といったゲルマン人がかなり入りこんで来たらしい。他にはもともとコーカサス地方にいたアランという系統不明の騎馬民族も来た。しめくくりは、中国の北辺に居た匈奴の末裔という説もある騎馬民族・フン族である。
僕は東西ローマの分裂(395年)というのは、先進地帯である中近東を含んでいる東ローマ(ビザンツ)帝国による、後進地帯であるローマ帝国西部(今の西ヨーロッパ)切り捨てというのが実態ではないかと思っている。実際、ゲルマン人やフン族は東ローマ帝国への侵入をあきらめ、弱体な西ローマ帝国のほうに矛先を変えている。
バルカン半島というのは、西ヨーロッパに比べ、森の豊富さにひけをとらず、鉱物資源も豊富、しかも牧畜に向いた草原もあり、実に魅力的な土地だった。そのために上記の時代ののちも、民族移動が続いている。北方からスラヴ人がどんどん入ってきてスラヴ化が進む一方、東方の草原からはアヴァール(中国の史料に見える「柔然(もしくは蠕蠕)」といわれる)、マジャール(今のハンガリー人の直接の先祖)といった騎馬民族が牧地を求めてやって来た。例えば、ブルガリアというのはスラヴ人にトルコ系のブルガル族がのっかって出来た国家である。さらには逆に西方から食い詰めたドイツ人が移住してくるという現象も起きている。
15世紀にはバルカン半島全体がオスマン帝国(1299~1923年)の支配下に入る。このアジア・ヨーロッパ・アフリカの三大陸にまたがる大帝国は、よく「オスマン・トルコ帝国」と呼ばれ、トルコ人帝国のように思われているが、皇帝がトルコ系の出身というだけで、実態は「バルカン半島多民族帝国」といっていいものだった(実際、中近東征服よりも先にバルカン征服が行われている)。軍隊の中核となったイェニチェリはバルカン半島のキリスト教徒の子弟から徴集され、セルビア人が宰相になった時代には行政府ではセルビア語が官僚の共通語になっていた(行政文書はトルコ語だったが)。
19世紀になると、かつて東ローマ帝国に切り捨てられ、ゲルマン人の跳梁に任されていた「不毛の地」西ヨーロッパは、単一民族による国民国家という共同幻想を作り上げ、強力な中央集権軍事国家の建設に成功していた。一方東方では、ロシアが、いささか時代錯誤ながら、モンゴル流の征服王朝の建設に成功していた。
これらの国々は、自分の勢力範囲を広げるという野心のため、民族主義というイデオロギーをオスマン帝国内の諸民族に吹きこんだ。度重なる戦争の結果、19世紀末にはバルカン諸国は独立し、オスマン帝国はバルカン半島を失う。これは「バルカン帝国」であるオスマン帝国そのものの解体と同じ事であった(実際には1923年まで生き延びるが)。多民族共存の地だったバルカンは「ヨーロッパの火薬庫」になってしまった。ヨーロッパの20世紀は、サライェヴォでの一発の銃声に始まり(第1次世界大戦)、90年代のボスニア内戦、99年のユーゴ空爆で幕を閉じた。
ナショナリズム戦争に疲れ果てた西ヨーロッパは、EUという多民族共存の「擬似帝国」を発明し、21世紀の今やそれはバルカンにも及ぼうとしている。
実は東西ローマ帝国の境界線というのは今も生きていて、ローマ・カトリック教会とギリシャ正教の境界になり、15世紀にはかつてのオスマン帝国の国境になり、今はクロアチアとユーゴスラヴィア(セルビア)の国境になっている。近い将来、EUの東方国境になることだろう。
ヨーロッパの初期中世考古学というのは、浮世離れしているようで実は生々しいテーマである。
2002/11/24(日) ドイツに関する本
今日は僕が日本から持ってきた、ドイツに関する本を紹介する。
といっても、僕はドイツのことを専門に研究しに来ているわけでもないし、取りたてて読書家というほどでもないと思うので(本はたくさん持っているが)、どうしても僕の好みに偏っていることを断っておく。あと、こっちに持ってくる以上、文庫本のようなかさばらない本に限定された。偶然というべきか、以下に挙げる本は全部岩波文庫になってしまった。
I「ゲルマーニア」(タキトゥス、泉井久之助訳註)
古代ローマの歴史家タキトゥス(紀元後55?~120?)による民族誌。ドイツというより、そのご先祖である古代のゲルマン人についてである。最盛期のローマ帝国を徐々に脅かす存在になりつつあったゲルマン人の質朴勇健な姿を活写している(文章自体は淡々としていてさほど面白くないが)。筆者タキトゥス自身の狙いはローマ人への警世にあったものと思われ、アメリカ人にとってみれば、かつての「菊と刀」(R・ベネディクト著)や、最近では中国に関する諸々の本(「文明の衝突」も入るのか)と同様のものといってもいいかもしれない。
面白いのはなんといってもゲルマン人の体格や風習についてである。
「・・・鋭い空色の目、黄赤色の頭髪、長大にしてただ強襲にのみ剛強な体躯。-というのは、労働、作務に対して、彼らには相応する忍耐が無く、渇きと暑熱とには少しも耐える事が出来ないからである。ただ寒気と飢餓とには、その気候、風土の為に彼らはよく馴化されている」
「飲料には、大麦または小麦よりつくられ、いくらか葡萄酒に似て品位の下がる液がある(ビールのこと)。・・・彼らは調理に手をかけず、調味料も添えずに飢えをいやす。しかし彼らは渇き(飲酒)に対してこの節制が無い・・・」
もちろんこんにちのドイツ人と二千年前のゲルマン人を単純に比較は出来ないが(それじゃあヒトラーのやることと同じである)、ドイツ人の原点を見るようである。
それと今日カエサルの「ガリア戦記」(近山金次訳・岩波文庫)を読んでいて、ゲルマン人に関する妙な記述を見た。
「・・・幼い頃から労働と困苦を求める。いちばん長く童貞を守っていたものが絶賛される。その童貞を守ることによって身長も伸び体力や神経が強くなるものと思っている。二十歳前に女を知るのは恥としている。このことについては隠し立てもしない・・・」云々。本当かなあ?そういや似たようなことをドクター中松(発明家・元東京都知事選候補)も言っていたな。女たらしで有名だったカエサルには信じられなかっただろう。
II「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(阿部謹也訳)
16世紀初頭に書かれた滑稽話である。主人公ティルはドイツ各地を放浪し、あるいは小姓になったり、あるいは徒弟奉公したり、もぐりの職人になったり、道化師になったりして教皇・国王から農民・親方たちまであらゆる身分の者たちをからかう話である。自身は阿呆を装ってその実、とりすました連中を物笑いのたねにする。一休さんの頓知話に似ていなくも無い。訳者の阿部氏はドイツ中世の社会史研究で知られるが、この物語にも当時の社会を背景とした社会情勢・習慣・法律などが登場する。
この物語にはマールブルクも登場する。絵師に化けたオイレンシュピーゲルが、ヘッセン方伯に歴代の肖像画をお城の壁に描くことを依頼され(注・実際のマールブルク城にはそういう壁画は無い)、大金をせしめる。しかし彼はもちろん絵師でもないので何も描かず、「由緒正しい生まれで無い私生児には、この絵は見えないのです」といって方伯や奥方、騎士たちを煙に巻く。最後に「阿呆女」が「これは何も描いていない」と指摘して、おかしいと思っていた皆が真実に気付き、オイレンシュピーゲルはとんずらするという話である。
オイレンシュピーゲルの話にはやたらと糞が登場する。彼自身、いつでもどこでも糞や屁を出すことの出来る異能の人物である。ドイツらしいギャグというか、ドイツ人は糞というものに常々特別の愛着をもっているらしい。
III「ドイツとドイツ人」(トーマス・マン著、青木順三訳)
様々な近現代ドイツの転機に際して、ノーベル賞受賞作家であるトーマス・マン(1875~1955年)が行った講演など6編を収録。
表題の講演は、第2次世界大戦のドイツ無条件降伏直後にマンがアメリカで行った講演のタイトルである(ナチスに反対したマンは戦前にアメリカに亡命していた)。ドイツ人(ドイツ・ロマン主義)のもつ世界市民という天性、そしてあい矛盾する、世界に対する臆病さ、内気さへの考察を、ルターから説き起こし、ナチスにまで及んでいる。ドイツには悪しき面と良き面両方があり、悪しき面(ナチスのような)が出てきたのは悪魔の策略にかかったようなものであるが、それもドイツ的なものであったと指摘する。
ワイマール共和国成立後の1922年の「ドイツ共和国について」という講演では、共和国を擁護する内容の話をした。第1次世界大戦中はドイツ・ロマン主義への共感から帝政や戦争を支持していたマンが、民主主義や共和国がドイツにふさわしいものであることを、文学を例にひいて力説している(これは「裏切り」ととられ、聴衆からブーイングを浴びた)。
その他、ナチスの台頭に警告を発し、社会民主主義こそドイツを救うと訴えた「理性に訴える」(1930年)、ナチスによるマンのドイツ国籍の剥奪(1936年)に伴う、名誉博士号剥奪に対してナチス・ドイツとの絶縁を公式に宣言した「ボン大学との往復書簡」、ドイツ最大の文豪・ゲーテ生誕200年周年の「ゲーテと民主主義」(1949年。ゲーテはふつう貴族主義的・非民主主義的といわれている)、「芸術家と社会」(1952年)を収録。
現在のドイツが取っている道、すなわちヨーロッパとの一体化(EU)、社会民主主義は、既にマンが上記のの講演などで主張していた。激変した20世紀のドイツの政治思想を理解する上でも、この講演録は重要だろう。
2002/11/12(火) マインツの毘沙門天?
夜は講演会があった。マインツで発見されたローマ時代のミトラ神殿についての講演である。もっともこの遺跡、マインツ市街地のど真ん中にあって、工事中に発見されてショベル・カーで壊された上、地元のアマチュア考古学愛好家に「盗掘」されて発見状況が分からなくなってしまっていた。
今日の講演者(女性)は破片になった遺物を丹念に観察して類例を探して復元し、また「盗掘者」から発見状況を聞き取りして、2世紀頃のものと見られるミトラ神殿の復元を試みている。その執念に脱帽である。考古学というと金とかミイラとか大発見ばかりに目が行くが、こうした地道なパズルの積み重ねが大きな成果を生むこともある。
ミトラ神というのはもともとイラン(ペルシア)の神様だった。太陽神とされることもある。紀元前5世紀のペルシア帝国の碑文にはもうミトラ神の名前が言及されているから、かなり古い。しかしペルシアではゾロアスター教の主神はあくまで光の神アフラ・マズダであり、ミトラは添え物のようだった。
ところが1世紀頃(イエス・キリストよりちょっと後の時代)からこのミトラ神信仰が西隣のローマ帝国の領内で爆発的に流行り始めた。ローマ帝国というのは軍事的・政治的にはギリシャや中近東といった地域を支配したが、所詮はこれらの地域の「ものまね」文明に過ぎなかったので、中近東・ギリシャの文物(特に形而上的なもの)がどんどんローマ帝国に入りこんで行った。
ミトラ神信仰というのは地下室みたいなところに牛を殺すミトラ神の像をまつり、秘儀的な教団を組織した。この民間信仰は特に軍人の間に広まった(中近東と接する機会が多かったからだろう)。ローマ帝国最前線のマインツにはローマの軍団が駐屯していたから(当時のマインツはモゴニタクムという名前だった)、やはり軍人・兵士が持ちこんだのだろう。ミトラ神信仰には中近東の天文学知識も加味されており、今の12星座はもともとミトラ信仰と密接な関係があった(牛を殺すというモチーフも、牡牛座の運行と何らかの関係があるものとみられている)。
一時はローマ帝国内でキリスト教を凌ぐ勢いのあったミトラ神信仰だが(キリスト教も、ローマ帝国にとってはもともと中近東から来た「外来宗教」である)、4世紀以降、キリスト教の国教化などに伴って衰退していった。もとより秘儀的であり、普遍性を欠いたのも、廃れていった原因だろう。
昭和16年、京都大学の宮崎市定助教授は「毘沙門天信仰の東漸について」という論文を発表した。詳しくは紹介しないが、仏教の毘沙門天は、仏教が東伝するうちに中央アジアあたりでイラン系民族の信仰から取りこまれた、ミトラ神の変わった姿であろう、と結論している。僕はその辺専門で無いのでこの説が今どう扱われているのか知らないが、状況から見てありえないことではないと思う。
ミトラ神はイランではさほど重視されず、ヨーロッパで大流行したように、仏教はインドでは流行らずむしろ東アジアで栄えた。ミトラ神信仰(とそれを取りこんだ仏教)がユーラシアの東西両端で栄えたというのは、中近東の文明からみれば辺境にすぎないそれらの地域では必然だったのかもしれない。
そういや「男はつらいよ」の寅さんが産湯をつかったのは、葛飾柴又の毘沙門天(帝釈天)である。同じ神様がドイツはマインツの地下から発見されたと考えると、少しは世界は狭いと思えてくる。
2002/11/15(金) 追悼・江上波夫氏
今朝、K君から電話がかかってきた。「ニュース見ましたか」と聞くので(ここでいう「ニュース」とはインターネットのことである。さもなくば日本のニュースなど普段は入ってこない)、「いいや」と答えると、「江上波夫死去」とK君は言った。
江上波夫・東大名誉教授は1906年生まれだから、96歳である。まあこの歳ならいつ亡くなられてもおかしくはないとは思っていたが、やはりショックはあった。僕は学会などで何度もご本人を見かけたし、僕の参加したシリアでの発掘隊の隊長でもあったので(名目上のことで、高齢のため現場に来たことは何度もなかったが)、僕らから見れば雲の上というか学史上の人物と言ったほうが近いとは言え、僕とまったく縁がないともいえない人だった。
江上氏はとても小柄で顔が丸く、穏やかな人のように見受けられた。あの膨大な著作や調査のエネルギーがこの人のどこに隠れているのかと思ったものだ。僕が見かけたのは最晩年だったので、たいてい車椅子とか介添えがついていたが、5年くらいまえまでは声もしっかりしていた。数年前からは出歩くことも無くなったと聞いていた。
江上波夫氏は1906年東京生まれ。1930年、東京帝国大学東洋史学科卒。その後、当時日本が勢力をのばしていた満州(中国東北部)や内蒙古に考古学・民族学調査に従事している。1945年の日本の敗戦と共に、氏の専攻であった中国北方民族学及び考古学は調査の道を断たれることになる。1948年、東京大学教授に就任。
同年に発表した「騎馬民族征服王朝説」は、「皇国史観」から解放されたばかりの日本の歴史・考古学界に大きな衝撃を与えた。去年12月の日記で紹介したことがあるが、「大和朝廷は朝鮮半島から渡ってきた騎馬民族によってうちたてられた征服王朝であった」という説である。日本の古墳時代(4~7世紀)の出土品の変化や習俗に着目し、豊富な古今東西の騎馬民族に関する知識を背景とした氏ならではの独創的・革新的な説であった。この説は賛否両論を呼び(左翼右翼の両方から攻撃されたが)、また現在の日本考古学界では氏の説をそのまま受け入れる人はもはや皆無といっていい。しかし、日本古代史を日本列島に閉じ込めることなく、中国や朝鮮半島といった地域との比較研究を促した点だけでも、この説にはおおきな意義があった。氏は「ユーラシア考古学」という大きな視点に立っていた。
1956年には戦後初めての海外調査隊を率いてイラク・イランに赴く。今や海外調査に従事する日本の発掘隊は両手の指に余るほどであるが、この調査はそのさきがけとなったものだった。それまで人類史の解明にかかわるこの地域の調査は、欧米列強の独占物であったのだが、そこに日本も加わることになったのである(もちろん、海外調査に国威発揚・「先進国」としての矜持という一面があることは否定できない。日本は驚異的な経済成長の真っ只中にあった)。
1967年に東京大学教授を停年退官。翌年長年の持論を「騎馬民族国家」(中公新書)にまとめ、毎日出版文化賞を受賞。1979年には新たに開館した古代オリエント博物館(東京都池袋)の館長に就任。海外調査の実現に尽力した。1991年、考古学者として初めて文化勲章を受賞した(他は今のところ末永雅雄氏だけである)。
今年7月に70歳で亡くなった佐原真氏(元京都大学教授・前国立歴史民俗学博物館館長)は「大和朝廷征服王朝説」に反対する急先鋒だった。1987年、江上氏と佐原氏は「騎馬民族は来た・来ない?」というテーマで対談している。もっとも、対談の後半は佐原氏が江上氏の研究の半生を聞くといった体裁で、前半の議論も佐原氏が突っ込めば(日本の習俗に、家畜の去勢や肉食といった騎馬民族的な習慣がほとんど見られないことなどを挙げた)、江上氏がのらりくらりとかわすといった感じだった。僕自身は佐原氏にお目にかかった記憶はないが、この佐原氏は1997年にドイツに研修留学し、マールブルクにも来ている。佐原氏を知る人も研究室にいる。
江上氏と佐原氏は、考古学の面白味を社会に広め、ポピュラーにしたという点では人後に落ちない人たちだった。僕も多少の縁があったこれらの偉大な先達に、少しでもあやかれればと思う。
2002/11/22(金) カラ・コルム 草原のメトロポリス
今日は夕方講演会があったので聞きに行った。今回のテーマはモンゴル帝国(1206年~14世紀)の首都カラ・コルムの発掘調査である。講師はボンにあるドイツ考古学研究所のヘルムート・ロート氏。
講演の副題は「ジンギス・カンのメトロポール」となっているが、講師自らが言っていたように、史上最大の帝国・モンゴル帝国の礎を築いたジンギス・カン(テムジン、1162~1227年)は連年の遠征に忙しく、モンゴルに戻ってくる暇さえなかったので、カラ・コルムの建設そのものにはほとんど関係が無い。2代目のオゴタイ(在位1227~1242年)の時にもっとも建設が進んだ。
現在のカラ・コルムには16世紀後半に立てられたエルデネ・ズウというラマ教寺院がその威容を誇っているが、この寺院そのものはカラ・コルムとは関係が無い。モンゴル帝国当時の建物は何も残っておらず、あたりは見渡す限りの草原である。
カラ・コルムはそれまでの北アジアの歴史に無い、中国ふうの計画的な都市だった(それ以前にも北アジアの草原地帯に都市がなかったわけではない、念の為)。王の宮殿の他に工人地区もあり、城壁に囲まれ、東西南北に街路が巡らされていた。南北1.2km、東西600mである。周囲には中国人屯田兵の耕す畑もあった。
この当時のカラ・コルムの様子を記録したヨーロッパ人がいる。1253年にフランスのルイ9世によってモンゴルに派遣された宣教師ギヨ―ム・ド・ルブルクである。彼は、
「カラコルムはカン(王)の宮殿を除けば、サン・ドニの村程の大きさも無い。(中略)カラコルムには二つの区域があり、その1つはサラセン(ペルシア・アラブ)人の区域で市場があり、この都の付近に在る宮廷と多くの使節等のゆえに、常に多くのタルタル(モンゴル)人の集まる所である。他は全て工匠であるキタイ(中国)人の区域である」
と記している。また彼の本の挿絵によると、モンゴル人は城内に住まず、城外にテント(パオ、またはユルト)を張って野営していた。
1260年に5代目のカアン(同時に中華王朝「元」の初代皇帝・成祖でもある)であるクビライが都を大都(現在の北京)に移してからはモンゴル帝国の都でなくなり、徐々に衰退していき、上記のラマ教寺院が建てられた16世紀には完全に忘れ去られていたものと思われる。
ドイツ隊の調査は大規模な地底レーダーによる地底探査と、小規模な発掘であった。レーダー探査ではカンの宮殿がはっきりと捉えられ(19世紀にロシア人によって既に場所は特定されていたが)、計画的な街路や城壁も明らかになった。サン・ドニの村というのがどのくらいの大きさなのか知らないが、結構大きいように思える。
発掘では金細工師の工房にあたり、見事な金銀の製品や中国の青磁などが出土している。ルブルクの記述の通りであり、出土品だけみると中国の遺跡と見まがうようである。とりわけ金製帯金具は切断されており、クビライによる交鈔(紙幣)導入との関連で注目される。
また1371年の銘をもつ、中国語で刻まれた元の大蔵省の印鑑が出土している。元王朝そのものは最後の皇帝・順帝が1368年に中国を去っているので(いわゆる元の北帰)、モンゴルに戻った元朝の残したものであろうと推定される。きわめて珍しい発見といっていい。
モンゴル帝国というと、どうしても「破壊者・殺戮者」というイメージで語られがちである(井上靖の「蒼き狼」などが典型である)。中央アジアには各地に「モンゴルに破壊された都市の遺跡」というものが存在する。また日本(鎌倉幕府)は1274年と1282年の二度に渡って元(とその隷属下にあった高麗)の侵攻を受けている。ヨーロッパはより深刻で、1241年にドイツ・ポーランド連合軍がバトゥ(ジンギス・カンの孫)率いるモンゴル軍に大敗を喫したリーグニッツの戦いが有名である。この時は折良く皇帝のオゴタイが死んだためにモンゴル軍はハンガリーから撤収したが、もしモンゴルの遠征が続いていれば、ヨーロッパ史の様相も大きく変わっていたに違いない(その恐怖から、ルブルクはじめ多くの使節がモンゴルに派遣された)。
ところが実際はモンゴル帝国というのは異質なものをどんどん取りこんで膨張していったのであり(そのノウハウは先行するイスラーム教徒やウイグル商人から学んだのは明らかであるが)、決して野蛮な遊牧民による旋風などではなかった。クビライは雄大な構想のもとにユーラシア規模の交易網を整備し、それまで東西交渉の主役だったウイグル人、アラブ人、ペルシア人を重用した。中央アジアの廃墟の多くは、モンゴルに破壊されたのではなく、ヨーロッパによる「近代世界システム」の確立によって交易が衰退してさびれていった都市の遺跡に他ならない。また北京を建設したのはまぎれもないクビライであり、その見識の正しさは、今も北京が中国のゆるぎない首都であることに裏付けられている。(この辺については杉山正明・京都大学教授の一連の著作に詳しい)
岡田英弘氏は、ほんとうの「世界史」はモンゴル帝国に始まる、と喝破したが、実にそのとおりだと思う。それまでゆっくりと1つになりつつあったユーラシアが、モンゴルの支配のもとで初めて政治的にも1つになり、東西交渉を活発化させた。史上に名高いマルコ・ポーロはモンゴルの保護あってこそ中国にまで行けたのであり、またマルコ・ポーロの著作に感銘して、コロンブスはインド発見の航海に出た(結果はアメリカ大陸の発見だったが)。ヨーロッパによる無残極まりない世界支配と彼らの言う「世界史」の始まりは、実はモンゴルの残した遺産を独り占めしたに過ぎなかったのである。
かつて「世界の中心」だったカラ・コルムは今は見渡す限りの平原である、と上に記した。あたりは今でも遊牧民の天地であり、世界の流れからもっとも遠い場所、もしくは取り残された場所のように思える。「諸行無常」という言葉がこれほど似合うところも無いのではないだろうか。
(追記:翌2003年9月、元マールブルク大学教授でもある講演者のロート氏はガンで急逝した)
2002/10/08(火) 久々のプール
今日はうってかわって素晴らしい晴れの日。晴れるとドイツの太陽は意外に日差しが強い。紅葉の始まりかけている周辺の山の緑も美しく見える。天気が違うだけでドイツの印象はこうも変わるものか。
今日は週一回のプールの日であった。実に三ヶ月ぶりである。この三ヶ月はデンマークとトルコでせいぜい膝まで水に漬かったくらいだった。ブランクが長かった割には結構泳げた。やはり発掘現場は体力が必要だから、いい運動になっていたのかな(あと村人としょっちゅうサッカーをしていた)?
水泳のあと皆で食べに行くのも同じ。今日は一緒に行ったM君がかつて住んでいたミュンヒハウゼンというところへいった(マールブルクの北20kmくらいのところ)。大きめの村といったところだろうか。ここのレストランへ行く。そこは実は鱒料理がメインなんだが、トルコで2ヶ月豚肉を食べられなかった僕は(ほんとはそれほど豚肉が好きというわけでもないが、習慣というのは強い)、何がなんでもシュニッツェルが食べたかったので、シュニッツェルを注文。これがまた美味しかった。「猟師風ソース」というどろりとしたソースがかかっているやつだった。腹いっぱいになった。
この店はサイドで出るふかし芋が絶品だった。ちょうど良い硬さ、そして塩加減。こんな簡単なものなのに、実に美味い。
この店に入ったときから気になって居たんだが、店のカウンタ-の前に英語を話す集団がいて、結構やかましい(何人かは明らかに英語を話すドイツ人)。イギリスのパブみたいにカウンターの前で立ったまま飲んでいるし、英語のアクセントなんかを聞いているとイギリス人と思っていた。
ところが食事をしていると、向こうからその中の一人のおばさんが僕らのテーブルに寄って来て、挨拶したのでびっくりした。さっき「ヤキウ」(野球?)と連発していたので日本の話でもしていて、こっちが気になっていたのだろうか?(ミュンヒハウゼンには東洋人は他にいないようである)。「どこから来たの?」と聞くので(英語)、「日本」と答える。英語を話すのなんて久しぶりだ。デンマークではドイツ語が通じたし、トルコではトルコ語で話していた。
このおばさんはオーストラリアの人で、おじいさんのおじいさんのおじいさんが1853年(日本に黒船が来た年だ)にミュンヒハウゼンからオーストラリアに移住したんだという。あとは「マールブルクで勉強しているのか?」「ドイツの暮らしは楽しいか」といった月並みな会話をして、むこうへ行った。「何を勉強しているんだ?」と聞かれたときに、「アーケオロジ―」(考古学)と答えると、「へえ」と驚いたような感じだった。どこの国に行っても、「考古学やってます」というと驚かれる。そんなに浮世離れした学問かな。
19世紀のドイツは遅れ馳せながら産業革命が始まり、急速に成長を遂げた。しかし爆発する人口をドイツ国内の農業生産や経済成長は支えきれず(19世紀の100年間でドイツの人口は3倍になった)、あるものはロシアに、そしてあるものはアメリカやオーストラリアといった新天地に移住していった(意外だが、アメリカ合衆国のヨーロッパ系市民でもっとも多いのはドイツ系の子孫である)。このおばさんの祖先もそういう中の一人だったんだろう。1853年から55年の三年間だけで祖国を去ったドイツ人は110万人に達したという。1848年のドイツ革命が失敗に終わり、祖国での希望を失った人が多かったことも関係している。
もともとドイツは人口のわりに農業生産の乏しい国で、16世紀以降は傭兵になって外国に出稼ぎに出るものも多かった(貧乏領主が領民を連れて外国の戦争に加わることもあった)。アメリカ独立戦争(1775年~)の際にはイギリス軍に多数のドイツ人傭兵がおり、その出身地から彼らは「ヘッセン」(マールブルクのあるあたりですな)と呼ばれ、アメリカ市民軍に恐れられていたというエピソードもある(ジョニー・デップ主演の映画「スリーピー・ホロウ」の物語の背景にもなっている)。これは余談。
さっきちょっと触れたジャガイモは、そんなドイツにとっては救世主だった。土地の痩せたドイツでも育ち、栄養価も結構ある。南米原産のこの作物は南米を征服したスペイン人がヨーロッパにもたらし、19世紀には、もはやジャガイモなしの農業は考えられないほどになっていた。
ドイツ料理というとジャガイモがすぐ思い浮かぶが、これはたかだか200年のことなのである。もっとも、韓国料理の唐辛子、イタリア料理のトマト、そして日本料理の白菜だって、実はせいぜいここ数百年の人間の交通の結果なのだが。
「伝統」というのも実は移ろいやすいものである。
2002/10/10(木) トロイアとボアズキョイ
今日はまあまあの天気だった。
夜、研究室の仲間たちと飲みに行く。結構長く飲んで、最終バスを乗り過ごしてしまったので歩いて帰った。
トロイアとボアズキョイというと、トルコでもっとも著名な遺跡であり、世界史の教科書に出てくるくらいである。前者はH・シュリーマンが子供の頃の夢を実現した遺跡として、後者は長らく謎になっていたヒッタイト帝国(紀元前18世紀~13世紀頃)の首都ハットゥッシャとして有名である。どちらも世界文化遺産に指定されている。このどちらの遺跡も、ドイツ人によって発掘が始められ、中断があったとはいえ1世紀を経た今もドイツ隊によって発掘が続けられている。
研究室の僕の同僚には、この両方の遺跡の発掘に参加していた人がいる。考古学者冥利に尽きるというものであろう。もっとも、内実はなかなか大変みたいだけど。今日は飲みながらそういう話をした。
ドイツ人も日本人と同じで、結構愚痴とか人の悪口(日本と違ってかなり理屈っぽい悪口だが)を肴に酒を飲むのが好きである。もっとも、ドイツ人は酒を飲むときはひたすら話し続け、本来の意味の肴(=おつまみ)を食べるということはあまりないが。
僕がドイツに留学したのは、つまるところドイツがトルコの重要な遺跡の多くをを発掘しているからだった。この分野を研究するにはどうしてもドイツ語が不可欠であるし(少なくとも文系ではドイツ語は未だに世界的な学術言語として健在である)、それゆえにいい研究をしている教授はドイツに多いからである。そうじゃなけりゃドイツくんだりまで留学しに来なかったろう。もともと音楽などを通じてドイツに興味は持っていたとはいえ。
2002/07/03(水) Danmark
あさってから2週間、大学の授業の一環(エクスカーション、学生30人ほど)でデンマークに行ってくる。その間は日記の更新も出来なくなる。
デンマーク王国。面積4万3千平方km(九州とほぼ同じ)。人口500万人。首都はコペンハーゲン。国内の最高地点は標高173m。とにかく平らな、ユラン(ユトランド)半島と500あまりの島嶼から構成される、農業・漁業・牧畜の国。
僕にはこの国に関する予備知識はほとんどない。コペンハーゲンにある人魚姫の像やチボリ公園、カールスバーグ(現地ではカールスベアというらしい)、トゥボルグ(同じく、トゥボー)といったビールの銘柄、ダンスクやロイヤル・コペンハーゲンといった高級工芸品、そしておもちゃのレゴといったところくらいか。
昨日デンマーク語の会話練習帳を買ってぱらぱらめくってみたが、ぱっと見はだいぶドイツ語とは違うなあ、という印象を受ける。それでも同じゲルマン系の言語だけに、構造や基本的なところは似ている。
ドイツ人は休暇でデンマークに行く人が多いので、結構デンマークのことを知っている。彼らの感想を並べてみると、こういう国らしい。
「とにかく雨が多い。海が近いので湿度が高く、蚊がたくさん居る。ドイツに比べ夏でも涼しい。食べ物はとにかく脂っこい。もわもわした発音の変な言葉を話す」
一方デンマークにとってドイツは、南方のヨーロッパ文明の供給源であると共に、恐るべき隣人だった。
ユトランド半島の付け根、ドイツとデンマークの国境に近いところに(今はドイツ領内)、ダンネヴェルク(デンマーク語ではダネヴィアケ)と呼ばれる土塁がえんえん7kmも続いている。これは8世紀半ばに、南方から勢力を拡大するフランク王国(今のフランス及びドイツ国家の原型)の圧力に対してデ―ン人が作った長城である。そもそもデンマークという国名自体が「デーン人のマルク(辺境領)」というフランク王国の行政上の命名から発している。
続くヴァイキングの時代が、デンマークにとっては黄金時代といえるものだろうか(「ヴァイキング」には他にノルウェー系やスウェーデン系がいたが)。海に乗り出した彼らはイングランドやアイルランド、フランス沿岸部を略奪・征服した。グリーンランドが今もデンマーク領なのは当時の名残である。
しかしその後は北欧の小国としての地位に甘んじていくことになる。1864年には大国オーストリアとプロイセン(ドイツ)の連合軍に袋叩きにあってシュレスヴィヒ地方を奪われている(ドイツ国籍をもつデンマーク人が今もこの地方にはいる)。その前後のナポレオン戦争や第1次世界大戦では中立を保った。
第2次世界大戦初期の1940年4月9日、ドイツは中立国だったデンマークに突如侵攻し、デンマークはほとんど無抵抗のまま即日降伏した。ドイツにとってはデンマークはノルウェー侵攻のための足がかりに過ぎなかった。その後デンマーク人による抵抗運動もあったが(現在それに関する博物館まである)、結局終戦の1945年までデンマークが解放されることはなかった。
S君が見せてくれたドイツ人向けのデンマークのガイドブック(Marco
Poloシリーズ)の最後にある「デンマークでするべきではないこと」という項がふるっている。
「デンマークの海岸に行って、砂でお城を作ってはいけません。ドイツ人観光客ということがばれてしまい、彼らにドイツ人の領土拡張への欲求という誤解を招くことになります」
「ドイツ国旗をデンマークで掲げてはいけません。それはデンマークの法律で禁止されており(本当だろうか?)、デンマーク人の敵意を招くことになります」
「デンマーク人が誰でもドイツ語が出来ると思いこんでいるような言動をしてはいけません(実際のところ、ドイツ語の出来るデンマーク人は多いのだろうか?)。デンマークはドイツの一部ではないのです」
「何かにつけて、ドイツでは・・・・などと言ってはいけません」
かなりブラックなユーモアである。
デンマーク人は自らを「小国」と位置付けているらしく、隣国ドイツに大きく依存しているが、もちろん警戒もしているようである。EUに加盟していながらユーロ通貨圏への加入を国民投票で否決したのも、この辺に原因の1つがあるんだろうか。
僕が毎年行っているトルコの村では、最近はドイツではなくデンマークへの出稼ぎがトレンドになっていた。最近の選挙でデンマークでは保守系政党や右翼が躍進したようだが、こうした移民問題が背景なんだろうか。
果てさてどういう国なんだろう。まあ僕らが見て周るのは博物館や遺跡ばかりなんだけど。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- コストコのホノルルクッキー★パイン…
- (2024-11-06 10:12:11)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 南城市の大里城址公園で「うふざとヌ…
- (2024-11-27 13:50:12)
-
© Rakuten Group, Inc.