「ちーちゃん」と過ごした日々 その6~8
「ちーちゃん」と過ごした日々 その6
前回までで、「ちーちゃん」のことは一応書き終えました。
もっともっと、細かな事件やちーちゃんの成長について書きたいのですが、
何しろ随分以前のことで、記憶があいまいなことと、自分の思い込みで、
本当はそうではなかったというようなことがあってはいけないので、
大きな行事や出来事にまつわることだけで終わることにします。
今回は、このブログで登場した「担任」について書きます。
私の中学校では、クラス替えは毎年あるものの、担任の先生は学年ごとに
持ち上がるスタイルをとっていました。ところが、1年から2年になるときに、
3つの小学校から集まってきていた中の一つの学校が分かれることになり、
向こうの学校に担任が取られたことから、新たな担任が加わることになりました。
それが、くだんの先生です(「S先生」とします)。
私が小学校にいるころから、中学校に「暴力教師がいる」ということが
うわさになっていました。とにかく生徒を殴る。有無をも言わさず殴る。
口ごたえすると殴る。体育大学出身で、警察官上がり、というのが
恐怖の暴力教師のプロフィールでした。
私は一つ上の兄から「現実はそんなものではない」と聞かされていました。
「想像を絶する」ということです。
入学すると、それは現実のものだと知らされました。
男子は全学年S先生の授業を受けます。だれもが口をそろえて
「怖い」と言います。体育の授業の後は、皆無口になっているほどでした。
しかし、女子には関係ありません。体育は男女が分かれて授業を受けます。
しかも、S先生は3年の担任でした。
私には何の影響もなく、1年間を過ごしました。
が、秋の文化祭のとき、S先生の恐ろしさを目の当たりにしたことがありました。
S先生のクラスは「展示」という分野の発表で、「占い」をやっていました。
結構人気で、いい加減な占いだとわかっていても、バスケ部の人気選手や
後輩に人気のある男の子が占い師に扮している時間帯があるので、
同級生はもちろん、下級生の女生徒が群がっていたのです。
そんな、浮かれた内容だったためか、「お酒」を持ち込む輩がいたようです。
それが発覚したとき、S先生はクラス全員を廊下に正座させ、棟が違う教室にまで
聞こえるような大声で怒鳴りつけていました。最後には、首謀者の頬を激しく
殴ったという記憶があります。
私は震え上がりました。
「暴力教師」という私の意識は「暴力団一味」くらいの意識にまで変化していました。
そんな中のクラス替え。
何と、不運にも、S先生が担任です。しかも、1年生のときに同級生だった女子は
一人もいない。張り出された名簿を見て、私は急速に気力が萎えていくのを感じました。
始業式の後、S先生は、クラス全員の顔をねめつけるように見ながら言いました。
「俺のクラスはみんな坊主や。男子、明日、坊主にしてこい。わかったな」
女子にも何か言及されるのかと思い、ヒヤヒヤしていると、私の前まで歩いてきて
ピタリととまり、
「お前、ええ度胸しとるの」
と吐き捨てるように言います。私には思い当たる節がありました。
校則違反をしていたのです。靴や制服、髪型が校則に抵触していました。
でも、学習や部活をきちんとしていれば、細かなことは見逃してくれる
学校でした。
が、S先生には通じないのかもしれない、という恐怖が脳裏をよぎりました。
翌日、私は校則違反を改善せずに登校しました。
確たる意味はありませんでした。何か言われたら、
「お金がかかることなので、お金ができたらすぐに改善します」
くらいのことは言おうと思っていたのかもしれません。
あるいは、
「やくざのような言い方をする教師の言うことは聞けない」
と言うつもりだった……、あり得ない。そんな度胸はありません。
ドキドキしながらS先生の登場を待っていると……、S先生は坊主にしてこなかった男の子を前に呼び出しました。二人いました。
「おい、何で坊主にしてこんかった?」
一人は、
「きのう、ちょっと行く暇がなくて…。きょう、切ってきます」
と言いました。もう一人が、
「校則には、耳にかからなかったらいいって書いてある……」
そこまで言うと、S先生の鉄拳が飛びました。
「校則は関係ない! 俺のクラスは坊主が規則じゃ! あした切ってこい!」
「……」
「ん? どうするんじゃ、切ってくるのか、こんのか!」
「き、切ってきます」
「よし。席に戻れ」
ひどい話です。まさに暴力教師です。
私の中学2年は、暗闇の1年間になるだろうと、暗い気持ちになりました。
クラブ活動が終わって、校庭で同級生や下級生とダベッているとき、
S先生がやってきました。手には箒の柄くらいの細い棒を持っています。
「まさか、打たれるのでは……」
と思わせるような怖さのある表情で近寄ってきます。
「ゴルフって知ってるか?」
「は、はぁ」
「あんな大きなヘッドで、こんな(指で輪をつくって)大きなボールを打つなんて、できて当たり前や。俺はこの棒の先で石ころを打つぞ」
と言うなり、箒の柄で小さな石ころを打ち始めました。
ゴルフのことを理解しているいまなら、このことのすごさがわかるのですが、
中学生の私には何のことかわからず、“何の自慢や”と打ち捨てていました。
が、これは、ゴルフの自慢でも何でもなく、私に話しかけるきっかけに過ぎなかったのだと思います。
S先生にしたら、決意の上の行動だったのだと察することができます。
そんなふうに自分から生徒に接する人ではなかったのです。少なくとも
私の担任になるまでは。
そうして打ち解けるようになったころ、生徒同士が殴り合うけんかが勃発しました。
一人が口から血を出しています。そこに、たまたまS先生が通りかかりました。
そこにいた生徒は全員が凍りつきました。S先生からどんな叱責(体罰)があるかと思ったからです。
S先生は軽く言いました。
「お前ら、殴り方も知らんくせに、けんかなんかすんな」
けんかした二人の男子生徒の腕を持ち、殴った生徒に
「もう手を出すな」
強烈に怖い顔をして言い、殴られた生徒に
「その水道で口をゆすげ」
と言いました。殴られた生徒は言われるままにしました。
「あかん。ほっぺたの内側が切れとる(口の中を見る)。保健室に行け。
保健の先生に痛~い薬を塗ってもらえ。そのうち血がとまる」
S先生は、取り巻いて見ている野次馬の生徒をグルッと見回して、
「何見てんねん。お前ら、何でけんかをとめへんかってん。
けんかしてる奴らをあほな奴らやと思ったんか。そうや。けど、とめへんかったお前らもあほや」
そう言い残して、口の切れた男子生徒を保健室に連れていきました。
そんな事件の後、部活の後にS先生と話す機会がまたあったので、私は無謀にも
S先生に聞きました。
「生徒を殴るって、怖くないですか?」
「何がや」
「けがをさせるかもしれないじゃないですか」
「S先生は笑いました。○○先生(理科の先生の名前。決して生徒を殴りません)に
殴られたら、救急車を呼ばなあかんやろうな。俺は大丈夫や」
「何でですか?」
「俺に殴られた男子に聞いてみいや」
S先生は自信あり気な顔をしてそう言うと立ち去りました。
早速翌日、私は殴られたことのある男子に聞いてみました。
皆が口をそろえて言ったことは、次のようなことでした。
S先生に殴られても痛くない、という意外な答え。派手な音はするけれど痛くないし、口の中が切れないように殴るテクニックを持っているというのが皆の合意でした。
また、女子のことを殴らないというのも、男子皆が知っていることでした。
「何でやろ」
と聞くと、
「知らんけど、殴る意味がないからやろ」
「え、どういうこと?」
「殴ったところで、効果がないからな」
彼らの意見をまとめると、女子は殴られたら、殴られたことへの屈辱しか考えず、殴られた原因を見ようとしない。それでは殴る意味がない、ということのようでした。
「女でよかった」
と思いました。
私は、殴られた原因を考える人間ですが(親が子どもを殴る人間だったので)、
「女子」というカテゴリーでくくられた私は殴られずに済んで幸せでした。
いずれにしても、生徒を「殴る」という、いまでは「懲戒免職」にすらなり得るというような行為をすらりとやってのけ、何も問題にもならずに済んだという、驚くような教師でした。
しかし、この先生のすごいことを「すごいこと」にしたのは、ある事件です。
そのある事件まで、S先生はただの「暴力教師」でした。
だって、「殴る」ことへのポリシーやテクニックはS先生自身のもので、だれかが
理解してそれを皆に伝えなければ、あるいは、S先生自身が「ただの暴力ではない」と
言わなければ、それは単なる「暴力」だったのです。
S先生から「暴力教師」の冠をはずすきっかけになったのは、2年生の秋に勃発した
こんな事件でした。
長くなりましたので、次回に続けます。
Last updated 2009.01.08 00:13:39
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
「ちーちゃん」と過ごした日々 その7
中学3年生のときのクラスは、ちーちゃんと一緒でした。
前回に引き続き、そのときの担任の話です。
2年生のとき、「暴力教師」が突然変貌しました。
それは、文化祭を控えたある日のことです。
我が校は、文化祭の発表内容を「展示」か「舞台発表」か選ぶシステムで、
「展示」は時事ネタや歴史などの研究結果をパネルにして展示したり、
皆で絵を描いたり、木工などの作品を展示するといったもの。
「舞台発表」は、芝居や合唱、ダンスなど、舞台上で発表する何らかの活動を
意味します。
うちのクラスは「舞台発表」を選び、発表内容は「芝居」と決まっていました。
太宰治の「走れメロス」をべースにすることや、シナリオ担当、キャストも
決めた後、なぜか作業は遅々として進みませんでした。
原因は、シナリオ担当の怠惰です。それは成績優秀な男子で、端から
「早くしろや」
とか、
「いつになったらシナリオが上がるの?」
と言えない何かがったのです。そうしているうちに、クラスメートから不協和音が
起き始めました。
「こんなに時間がなくなっては、芝居なんてもう無理だ」
という声が次第に大きくなっていったのです。それに気づいた担任が、
終業のホームルームのとき言いました。
「どうするか、皆で話し合え」
学代だった私は書記をし、男子の学代が議長になって、話し合いが始まりました。
皆の意見は、大勢が
「練習する時間がない」
「中途半端な発表になったら恥ずかしい」
というものでした。で、
「展示に変更してはどうか」
というだれかの意見に皆が同調し始めたのです。書記をしていた私は、
辛抱たまらず、“ちょっと意見を言わせて”と議長に頼み、少し声を荒らげて言いました。
「ちょっと待って。それはおかしいでしょう。舞台発表が無理だから、
展示に変更するって……。それじゃ、舞台発表より展示の方が手軽に、簡単に
できるということ? いい加減なことを言ったらダメでしょう。そんな考え方は、
展示を選んで一生懸命やっているクラスに対して恥ずかしい。
いいじゃない、中途半端な舞台発表になったとしても。それが、いまのうちのクラスの
文化レベルだってことでしょう。恥をかいたらいい。それがいやなら、残された時間で
一生懸命やることだと思う」
すると、現実派の男子がふてくされた顔で言いました。
「君の言うことは正しいかもしれないけれど、現実、いまの状態で舞台発表は無理
じゃないか?」
「そうかな……。私はそうは思わないけれど。無理というあなたの根拠は、
やる前の取り越し苦労かもしれない」
士気が下がり切った状態になっているのを感じました。私は、一か八か勝負に出ました。
「ちょっと待った! 提案! これ以上話しても平行線をたどってしまうと思う。
自分の考えが間違っていると思いながら意見を言う人はいないだろうから。
だから、きょうは帰って、頭を冷やしてよく考えましょう。
明日の朝、少し早く来てもう一度話し合う方がいいと思う。
ね、それでいいでしょう、議長」
私は議長を強くにらんで、合図しました。議長はうなずきながら
「そうしましょう」
と言いました。すかさず私は言葉を続けました。
「それから、Tくん(シナリオ担当)、シナリオを書くのが無理なら、だれかに
変わってもらってもいいと思う。シナリオができなければ、何も始められないのが
現実だから。そのこともよく考えてきて」
私には、秀才でプライドが高いT君が、シナリオづくりを投げ出すとは思えなかった
のです。やる気を出させるための念押しでした。
こうして話し合いはお開きになりました。翌日の朝、私の思ったとおりの結果になるか、
やはりネガティブな意見が大勢を占めてしまうのかはわかりませんでしたが、
力づくでも押し通そうと思っていました。Tくんがダメなら、自分がシナリオをつくる
覚悟で。
夜、自宅で夕食を食べていると、電話が鳴りました。近くにいた私が電話に出ると、
担任のS先生でした。
「悪い、家にまで電話して。明日のことで頼みがある。○○(私の姓)、明日、
お前の意見を絶対通してくれ。俺がバックアップする。やってくれるか?」
「はい。もちろん。何としても」
「ありがとう。頼むで」
電話は切れました。S先生はとても酔っぱらっていました。
電話をするかしないか、ものすごく迷ったのだと思います。多分、担任として、
これほどクラスの心配をしたことがなかったのではないかと思いました。
S先生に限らず、どの先生も文化祭の出し物に手を貸したり、心配したりは
しませんでした。心配せずとも、生徒が皆で何とかするものだからです。
が、うちのクラスはかなり出来が悪かったのかもしれません。
翌朝、始業よりも1時間も前に集まってきたクラスメートは言葉少なでした。
私は、口火を切って言いました。
「最初に聞いといていいかな。Tくん、どうかな。シナリオ、できそう?」
この子を押さえておかなえれば、話が進まないし、この子がやってくれると言って
くれたら、頑になっているネガティブ派の気持ちが変えられるかもしれないと
思ったからです。
「やります。きのうから書き始めました。内容がOKなら、できた部分から
練習してもらえると思います」
私は内心『やった』と思いました。
「シナリオの問題はクリアできたみたいです。どうでしょう。まだ、展示に
変更したいという気持ちは変わりませんか? 議長、裁決を取りましょうか」
「はい。展示に変更するという人」
顔を見合わせる生徒はいるものの、だれも手を挙げません。
「予定どおり、頑張って芝居を発表するという人」
ほとんどが手を挙げました。
「手を挙げていない人は、どうですか?」
きのう、ネガティブな意見を言った男子生徒とその仲間たちでした。
「……ボクは、みんなができるって言うんなら、それでいいです。いまから、
うまい芝居ができるようになるとは思えませんが」
「演技はうまくなくても、みんなが力を合わせてやったことがわかればいいし、
それが文化祭というものでしょう。短い時間だからこそ集中してできるかもしれないし」
私がそう言うと、シナリオ担当のT君が立ち上がりました。
「ボクの作業が遅れたせいで、迷惑をかけました。急いでつくりますから……」
「じゃ、きょうの放課後から、できたシナリオを見ながら、裏方と配役に分かれて
作業を始めましょう」
多分、初めて皆に向かって頭を下げただろうT君の心情を察して、私が言葉をつなぎ、
話し合いは終了しました。
私はほっと胸をなでおろしました。教室の端で見守っていたS先生の方をチラと見ると、
ニヤッと笑いました。
散会して廊下に出た私のところにやってきたS先生は、私の肩をポンとたたき、
「ありがとう」
と言いました。
「いえ、皆の合意です」
私の言葉には答えず、S先生は立ち去りました。その後ろ姿は安堵したようでもあり、
意気揚々としているようでもあり。
その日から、S先生の活躍が始まりました。
「走れメロス」の時代背景からすると、簡単な布をまとったような衣装が必要です。
S先生は学校が分かれて使われなくなった教室のカーテンを根こそぎはずして
持ってきてくれました。
「先生、これ、いいんですか?」
「こんな汚いカーテン、使えんやろ。今度教室を使うときは、新しいカーテンを
かけてもらうよ。洗って使え」
私たちは皆でカーテンをきれいに洗濯し、四角く切って縫い合わせ、ギリシャ時代の
衣服もどきの衣装を被服室のミシンを借りて(これもS先生の手配)女子全員で
つくりました。
舞台の演技指導はS先生です。我々が体育館が使える日をほかのクラスよりたくさん
確保してくれ、S先生の怒号の中、舞台練習がみっちり続けられました。
結果的には、辛うじて間違いなく、きちんと舞台発表をこなせた、というレベルの
内容でした。もう少しスタートが早ければ、もっといい発表ができたかもしれない、
という思いはありますが、それはもう仕方ない。ここまでできたのが奇跡とも言える
くらい頑張りました。その多くはS先生のおかげです。怖いだけ、何かあると
暴力を振るうだけだったS先生のイメージは、我々の中で確実に変わりました。
クラス全員がそういう思いになったからか、それ以降、S先生との距離は格段に
縮まりました。先生の中にあった壁というか、生徒に対する距離感も変わったのだと思います。
そうこうしているうちに2学期が終わり、短い3学期もあっと言う間に過ぎて、
私は3年生になりました。
また長くなりました。
字数制限にひっかかりそうですから、続きは次回に。
Last updated 2009.01.09 00:12:15
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
「ちーちゃん」と過ごした日々 その8
「3年の担任は、だれかな……」
希望に満ちた思いで、玄関に張り出されたクラス名簿を見たとき……
「……S先生……」
がっかりしました。そのとき、S先生がいやだという感覚はなかったのですが、
2年の最初にがっかりした感覚が明確に蘇りました。また、緊張感あふれるシーンを
経験するのか、と思いました。
「できればA組の先生がよかった」
A組の担任は、学校で人気のある理科系のK先生でした。
そのときに抱いたそんな気持ちは、後に見事に打ち砕かれますが(その4に登場します)。
そうして私は、S先生のもとであと1年間を過ごすことになるのです。
同時に、ちーちゃんとの1年間も始まりました。
何でもないことなのですが、思い出の残っていることがあります。
私はソフトボール部に在籍し、ピッチャーをやっていたのですが、
キャッチャーだった女の子が足首の骨を折ってしまいました。バッテリーを組む
間柄でもあり、杖をついて登校しなければならない彼女をサポートするために、
通常の登校時間より1時間くらい早く(杖をついているのを人に見られるのが恥ずかしい
と言うので)一緒に登校しました。私は荷物持ちです。
1時間も早く登校してもすることがない。で、校舎の裏にあるはずの花壇を見に行きました。
一応、クラスごとの花壇があるということを知っていました。時は春。
何かが植わっているなら、間もなく芽を出すだろうし、そのとき存在している植物は
手入れしてあげる必要だあるだろうと、私は一人で花壇の世話をすることにしました。
暇に飽かせて雑草を抜き、石ころをどけ、水をまき、という行為を毎日続けました。
彼女の足が治るまでは、と決めて。
ある日、S先生が朝のホームルームのときに言いました。
「お前ら、うちのクラスの花壇、見たことがあるか?」
皆黙っています。私は当然知っていますが、S先生が何を言いたいのかはかりかね、
黙っていました。
「校舎の裏に花壇があるのは知っていると思う。しかし、見にいったことすら
ないやろう」
当然といえば当然です。用がないのですから。学校からも「花壇の世話をするように」
と言われた記憶はありません。
「その花壇を○○(私の姓)が毎日手入れしてくれてる」
私は驚きました。暇に飽かせて世話をしていた姿をS先生に見られていたのです。
「毎日水をまき、雑草を抜いてきれいにしてくれてるんや。うちのだけやない。
ほかのクラスのも面倒をみてくれてる。だれかに言われたわけやないはずや。
だれかに言われたからする、というだけやったらだれでもできる。だれにも言われんでも
できる人間にならなあかん」
いい話です。でも、私は恐縮至極です。そんな高尚な話ではありません。
すぐさまS先生の元へ行きました。そして、事と次第を説明しました。
S先生は笑って言いました。
「俺の言うたことに間違いはないやろ。お前はマンガを読んでてもよかったのに、
花壇の世話をしとったんや。俺が指示したわけでもないのに、自分からしたんや。
何を恐縮することがあるねん」
いま考えると、私がどういう動機でそうしたかはどうでもよかったのだと思います。
私のことをネタに、いい話がしたかったのではないかと。
怒ったり、怒鳴ったり、殴ったりばかりしている毎日に飽きて、少し静かに
いい話をしたかっただけではないかと思ったりしています。
(余談でした)
ちーちゃんのこと、Mさんのこと、球技大会や体育祭などの行事、受験など
いろいろな出来事を経験し、私は卒業しました。常にS先生がそこにいました。
高校の入学式前に、制服の採寸などで高校に出向いた後、中学校に報告に行きました。
K先生とS先生がいました。K先生が先に声をかけてくれました。
「おう、○○(私の姓)、高校に行ってきたか」
「はい」
「高校でもソフトボールやるのか?」
「部がないんです」
「ほかのクラブに入るのか?」
「いえ」
「何でや。せっかくスポーツ部で頑張ってたやないか。何かしろよ」
親のすすめで私学に入学することになった私は、のうのうと部活などしていられない立場なのです。家の手伝いはもちろん、アルバイトをする必要があるだろうと予想していました。
そんな、クラブに入りたい気持ちを抑えるしかない状況を説明することができませんでした。
「入りたいクラブがないし……」
私が言いよどむと、
「ふうん、お前のスポーツに対する気持ちはその程度やったんやな」
この先生にこんなことを言われる筋合いはないと思うと、涙がこみ上げてきました。
「○○、ちょっと見ん間に大人っぽくなったな」
S先生がそれに気づいて声をかけてくれました。K先生から少し離れたところへ導いてくれ、
「俺はお前を信じてる。お前が一生懸命ソフトやってたこと知ってるよ。お前が部活せえへんいうのは、よほどのことやと思う。お前が思うようにやったらええ」
もっと涙が出そうになりました。
「なぁ、俺はな、3年のクラス編成のとき、お前を俺のクラスに入れたんや」
「え、そんなこと、できるんですか?」
「うん」
「なんで私だったんですか?」
「2年のとき、俺はお前が俺のクラスにおってほんまによかったと思った。
さぁから、3年でもお前におってほしかったんや」
「そうですか……」
「ありがとう。よかったよ。お前がおって」
言葉が見つかりませんでした。
「俺は、4月から別の学校に転任になる」
「えっ? そうなんですか?」
「俺はどこに行っても、お前のことを思ってるから、何かあったら連絡してこい」
「……」
「ええな」
「はい」
S先生との別れはそんな感じでした。
誇張や先生独特のデフォルメがあったことと思います。でも、私の気持ちを考え、
私を肯定する言葉をかけてくれたことは、一生忘れません。
激しく落胆した2年生の初日から2年、S先生とはいろいろありました。
担任がS先生でなかったら、ちーちゃんとのことも、A組のMさんとのことも
こんなにうまくいかなかったかもしれません。
必要以上に言葉をかけることなく、密かに、温かく見守ってくれていたからこそ、
自由に、やりたいようにできたのかもしれないと思います。
きのうは書きませんでしたが、2年の文化祭が終わった日、
S先生は再び自宅に電話してきました。もちろん、酔っぱらって。
「ありがとう、ありがとう。俺はうれしい。ありがとう」
生徒たちが文化祭を無事やり遂げたことに大きな感慨を覚えたのでしょう。
何度も何度も礼を言われました。
先生らしからぬ行為ですが、私にはとても感動的でした。
生徒である自分に、ストレートに感情を表現してくれた先生に
信頼感と師弟愛のようなものを感ぜずにはいられませんでした。
いま、巷では「体罰はいけない」と一口に言います。
それが間違いだとは言いませんが、教師や親が子どもを「殴る」というとき、
単に「体罰」だけととらえるのは、とても貧困な発想だと思います。
どんな先生にも共通して言えることではありませんが、少なくともS先生が
「殴る」という行為に込めた思いやポリシーは、多くの生徒に理解できていたし、
それ以上に何かを与えてくれていたことも理解できています。
男の子はS先生から「殴り方」を教えられ、「痛み」や「悔しさ」を実感することで、
ケンカの仕方、相手への配慮がわかる人間になったと思います。
もちろん、S先生とて、最初から達観していたわけではないと思います。
「教師」であることの責任、義務、権利、立場などいろいろな自覚を通して
会得していったことであったはずです。最初は、誤解を生むような体罰もあったと
思います。しかし、生徒との信頼関係ができてくれば、互いが多くのことを学び合い、
すべてが意味のある行為になっていく、そんなふうに思えるのです。
ちーちゃんの成長はよく見えました。文字の読み書きを初め、表情や表現力、
相手への思いやりの心などが見違えるほど進化したからです。
それほど目には見えなくても、同じようにクラスメートも成長し、
私も成長し、S先生も成長しました。その原因の幾つかは、ちーちゃんに出会えたことに
あったように思います。
そして、その成長の中で獲得したものは、いまの私の人生にとても役立っています。
そうやって、人は人と出会い、命を生きていくのだと思います。
出会えた奇跡に感謝し、ふれあえた時間を大切に思いながら、
明日、また新たな出会いに命を震わせるのです。
Last updated 2009.01.09 21:53:11
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 普通の日記
- 筋トレで生き返ったよー
- (2024-06-27 12:57:49)
-
-
-
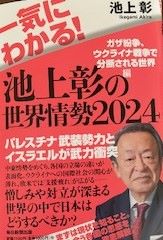
- 政治について
- アメリカ大統領選挙の少々回りくどい…
- (2024-06-27 10:27:40)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 傘 和傘 雨傘 晴雨兼用 モダンカラー…
- (2024-06-27 01:50:08)
-
© Rakuten Group, Inc.



