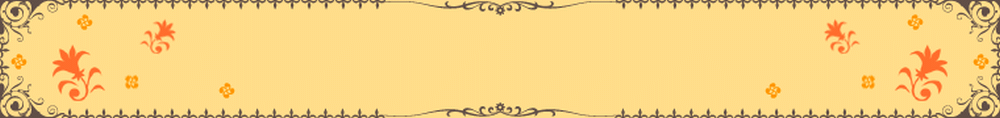干支ガール 後編
その晩もベッドで俺はイノシシ女を抱いた。
このイノシシ女、なぜか最初から夜もOKだった。だから毎晩抱き合ってる。ただ、一番最初のときは、恥じらいも無くガバッと目の前で脱いで素っ裸になり、
「えへへ」
とばかりに笑うので、ちょっと萎えそうだったけど。
世話になるのでお礼のつもりだったのか・・・そうかもしれないけれど、イノシシ女は俺のことが嫌いじゃないらしい。むしろ好きかもしれない。会ったばかりで変かもしれないけれど、でもなんとなく俺はそう思った。
「ところで君のこと、なんて呼べばいいんだろう?」
出会って一週間も経ってからこんなことを聞くなんておかしいかもしれないが、何しろ普通の出会いではなかったので、そういえば思いつかなかったのだ。
「なんでもいいわよ。もともとわたしにはちゃんとした名前なんて無いから」
「でも・・・」
「じゃ、イノ子って呼んでよ」
「それじゃあんまりだろ」
「ブタ子でもいいわ」
「ほんとにそれでいいのかよ」
「うん、いいわよ、わたしはね」
「俺は嫌だよ」
「そう。なんでもいいのよ。いいけど・・・、じゃ、『りっこ』って呼んで」
「りっこ?」
「そう、わたしが小さいときから、マリちゃんにはそう呼ばれていたの。うりぼうだからりっこ、って。だから」
「なんだそのマリちゃんって?友達か?」
「マリちゃんは神様よ」
「神様?なんだよそれ。そんなものいるのかよ」
「は?いるに決まってるじゃない。マリちゃんの他にも、神様なんかいーっぱいいるわよ。マリちゃんはわたしの係なの。わたし、間抜けだから、マリちゃんにはいつも怒られていたわ。今回も、日にちを間違えてフライングしちゃうし・・・きっと今頃、カンカンに怒ってるに違いないのよね」
りっこがため息をついた。
自分でもヤバイ、と思う。
たった一週間で、俺はすっかり骨抜きになってしまった。
相手がたとえイノシシであったとしても、今は普通に女の体をしているのだ。
確かに美人とは言えないけれど、りっこはとても愛らしい。それに肌はきめ細かくて滑らかだ。要するに触り心地がいい。
おまけに親切で優しくて作るメシも美味くて、いつもにこにこして愛想がよくて、抱き心地がよくて・・・。
なんだか俺は、りっこにすっかり馴染んでしまった。
(まずい、これはまずいぞ)
相手がイノシシだということは重々承知のはずなのに、気がついたら・・・なんだか俺、りっこのことを好きになってしまったかもしれない。それもなんだか、邪念が入らない好意というか・・・あまり複雑な心境ではなくて、ただ、好きなのだ。例えるなら、この感じはかなり動物的というか、懐かれて、そしてこちらも懐いた、そんな感じなのだ。
俺にはもう何がなんだかわからない。こんなこと初めてだ。
今夜も、隣でスヤスヤと眠っているイノシシ女・りっこの寝顔は、申し分なく可愛かった。
いや、他のヤツから見たらこんな地味な女、いやイノシシ、さっぱり可愛くないのかもしれないが・・・
俺にとっては、たまらなく可愛く見えた。
俺はうっすらと前の彼女のことを思い出した。
二年くらい前に合コンで知り合い、半年くらい前までつき合っていた女。経理の資格を持っていて、いろんな会社を渡り歩いていた。 そこそこ美人で頭も良く、つき合っていてまぁ楽しくはあったけれど、正直、最後まで何を考えていたのかわからないところがあった。
おそらくつき合っていたのは、俺一人ではなかったのだろう。性に奔放なところがあるのはなんとなくわかっていた。それに、それだけじゃなく、彼女は自分に有利な条件の結婚を考えていたのだと思う。俺のことも悪くないと考えていたフシがあったが、たぶんもっと条件のいいのが出て来たので、結果として俺は乗り換えられたのだ。
その男とは、どういう経緯で知り合ったのかは俺は知らない。もしかしたらお見合いだったのかもしれない。
結婚が決まったから別れてくれと、あっさりと彼女に言われたとき、俺は妙になんだか腑に落ちた感じがした。
だから俺は、この女に夢中になりきれなかったんだなと思ったのだ。
一応好きだったからそれなりにショックではあったけれど、驚愕を伴うショックではなかった。
彼女は、案外落ち着いて別れ話を受け入れた俺に安心したのか、「これからも友達でいてね」などと定番のセリフを残し、去って行った。そして本当に結婚式を挙げたあと、ウエディングドレス姿の写真入りで、結婚報告のハガキなどをいけしゃあしゃあと出してきたのだった。
しかし、このあいだまではまだ存在が近いように感じていて、そこはかとなく腹も立っていたのだが、りっこが来てからは、前の彼女のことなど、もうどうでもよくなってしまった。かなり遠のいたような気がする。
でも・・・、と俺は思う。
りっこは、「12月31日まで置いてくれ」と最初に言っていた。そのあとは、どうなるんだ?どうして31日までなんだ?そのあと、俺たちは、付き合い続けることはできるのか?
次の日は土曜で、俺は会社を休んだ。
年末なので、仕事は立て込んでいたのだが、日曜は休めないことがわかっていたので、無理矢理休んだのだ。
「無理することないのに。和弘さん、忙しいんでしょ」
りっこはこの近くで見つけたというおいしいパン屋から買って来た食パンを厚切りにして、何度もバターを塗り直しながらトースターでゆっくりゆっくり焼いている。このパンの上に、りっこが手作りしたオレンジマーマレードを乗せて食べると最高に美味い。
そして濃く入れたコーヒーに熱くした牛乳を入れて、たっぷりとしたカフェオレボウルで飲む。りっこはそれに砂糖を二袋も入れる。俺は砂糖なしで。
目玉焼きは半熟、ベーコンはカリカリに焼いてある。それにフレッシュサラダ。
りっこの手で優しく整えられたそれらを食べて、俺はここ一週間、毎朝幸せな気分で出社していた。
朝メシなんか食ったこと、ここ何年も無かったのに。
「いいよ。これから年末にかけてますますたて込んで行く予定だしさ。たまにはりっこをどこかへ連れて行ってやりたいんだ」
「優しいのね、和弘さんは。大好き」
りっこは突進してくると、俺を押し倒してキスをしてきた。何しろ俺は小柄な男なので、少々太めのりっこに勢いよく来られると簡単に倒されてしまう。
「やっやめろよ、朝から」
「なんでえ?だってうれしいんですもの」
りっこがブルブルっと、体を震わせながら言う。
一瞬だけど、俺を押さえつけているりっこの手が、イノシシの前足に見えた。
俺は目を閉じて首を左右に振る。そうしてゆっくりと目をあけると、前足は、ちゃんと人間の手に戻っていた。
俺は、ゆっくりと起き上がった。
「ところで、りっこはどこに行きたい?」
「うーん、そうねえ。じゃあ、上野」
「上野?なんで?」
「実は昨日、マリちゃんからわたしのケータイに電話が来たのよね。そうしたら、やっぱり今回のことについてかなり怒っていて、あなたにも会いたいって。・・・ほんとはひとりで怒られようと思ってたんだけど、そんなことして余計にマリちゃんを怒らせたら、かえって和弘さんに迷惑をかけるかもしれないし」
俺は、ちょっと迷った。
マリちゃんっていうのは、りっこの話では神様だというじゃないか。
イノシシが人間に変わるところを見た俺には、もう不思議な物など無いに等しいが、それにしても「神様」にはあまり、直接会いたいとは思わない。
俺、無神論者だし・・・つーかだって、そんなの怖いじゃないか。 何しろ怒っていると言うのだし。
「うーん、そっかぁ・・・俺は映画とかのほうがいいと思うんだけどなあ・・・」
「じゃあ、マリちゃんに会ってから、上野で映画を見ればいいよ」
「イヤ別に・・・映画だったらほら、渋谷でも間に合うしさあ・・・別に上野まで行かなくたって・・・」
「そっか和弘さん、やっぱりイヤなんだね。ムリ言ってごめんね。いいよ、マリちゃんには、そのうちわたしがひとりで怒られに行くからさ、心配しないで」
りっこがちょっと心細げに微笑みながら言った。
ここまで女に言われて、「そうだね、そうしなよ」という男が一体どこにいるだろうか。いや、いるかもしれないが俺はそんな腰抜けではない。
「わかったよ、俺も一緒に行くよ。怒られに」
「え。だって、別に和弘さんは悪く無いのよ」
「でも、あっちは、怒ってるんだろ」
「それは、わたしが間抜けだからよ」
「いいんだ、そんなことは」
そんなわけで、俺とりっこは電車を乗り継ぎ、上野に到着した。 りっこに案内されるまま、アメ横の中の狭い小路に入ってくと、徳大寺というお寺があった。
石段を上って行くと、騒がしい場所にあるはずなのに、狭い境内の中は不思議と静かだった。人もそれほどいない。
りっこは、ちょっと溜め息をついてバッグからケータイを取り出した。そして何やら電話をかける。
「マリちゃん、ついたよ。うん、目の前」
電話を切ると、りっこはますます暗い表情になっていく。
その顔を見ていたら余計に、
(一緒に来てやって良かった)
と俺はしみじみ思った。
「ところでマリちゃんって神様なんだろ。お経読んだりとかさ、鐘とか叩いて呼ぶもんじゃないのかよ」
「昔はそうだったんだろうけど、今はケータイがあるから」
「ふーん」
俺は信仰心のない男なので、そんなものかと納得した。便利になったものだ。
すると間もなく、そんな信仰心の無い俺もビックリのことが目の前で起った。
まぁイノシシが目の前で人間に変わるところを見た俺にとってはそれほどでもないことなのかもしれなかったが・・・しかしやはり驚いた。
なんだか急に回りが静かになった、と思ったら、境内にいたはずの人々が、かき消すように消えていたのだ。そんなはずはないのだが・・・
そしてそんな中、目の前のお堂の奥から、女がひとり、スタスタと歩いて出て来た。
そう、歩いて・・・来たのだが、明らかにその女は空中を歩いて来たのだった。まるでそこに道があるみたいに・・・
そうして女は俺とりっこの側まで来ると、音も無く地面に降りた。
その途端、かき消すように消えていた人々がまたちらほらと境内に現れた。まるで一瞬だけ、時間が止まっていたようだった。
「マリちゃん、久しぶり」
りっこがおずおずとその女に言った。
女は、痩せていて顎が細く、美人だがきつい顔立ち。背も高く、170センチは確実にありそうだ。とりあえず俺よりもカンペキにでかい。スタイルも抜群でまるでモデルのよう。
服装はスタイリッシュな黒のパンツスーツ。
どこのブランドか知らないが一目見ただけで、俺が普段着ている量販店製2パンツスーツの何倍も良いものだというのを感じた。
神様はきっと安っぽい服など着ないのだろう。
女は渋い顔をして、しょっぱなからガミガミと言いはじめた。
「久しぶりじゃないわよ全く。なんてことしてくれたの。ありえないんだからねこんなこと!」
「はい、ごめんなさい」
「一ヶ月間違えて来ちゃうなんて、ほんとにバカじゃないの?普通は絶対、間違わないわよ。まぁあなたのことだからって、ちょっと心配はしていたけど、さすがにここまでのポカをするとは思っていなかったわ。それであなた、今は一体どうしてるの」
「はぁ、ここにいる和弘さんちでお世話になってます」
「そうだったわね。それは知ってるわ。そういうことじゃなくてね、あのね、りっこ」
「はい」
「いくら困ったからって、人間のお世話になっていいとでも思っていたの」
「でも、この世界は寒いし・・・、どうしたらいいかわからなくて、最初はビルの間に隠れてたんですけど、そのうちお腹も空いてきて・・・」
「だったらどうして最初からわたしのところに来ないわけ?」
「だって、怒られると思ったから」
痩せた怖そうな女にりっこが一方的に怒られている・・・ 気の毒になった俺は、とりあえず割って入ることにした。
「あのー、事情はよくわからないんですけど、りっこも悪気はなかったみたいだし、間違いはよくあることですよ。それに、見ていて思ったんですけど、やっぱり会ったとたんに、こんなにいきなり怒られるんでは、最初に連絡しろって言われても、誰だってしたくないですよ」
「あなたねえ~」
女は俺の方を向いた。そうして、怖い目で睨んだ。
こんな怖い目の女に、俺は会ったことが無かった。
りっこのためと思って勇気を奮い起こし、俺も女を睨んでやったが、完全に貫禄負けしてしまった。
さすが神様というだけのことはある。
「よくいろいろ言うわねえ。事情もろくに知らないくせに。ほんとこの始末、一体どうしてくれるつもりなのよ。責任も取れないくせに口出すんじゃないわよ。ケツ持つのはこっちなのよ!」
「お願い怒らないでマリちゃん!和弘さんは何も悪く無いの。悪いのはわたしなのよ」
りっこが泣きべそをかきながら必死に割って入る。俺は黙った。 とにかく女は怒ってるらしいし・・・どちらにしてもあまり興奮させるのは良くないだろう。
女・・・マリちゃん、は、すぐまたりっこにあれこれ説教をはじめた。
そばで聞いていると、どうもこのマリちゃんというのはりっこが子どもの頃からずっと面倒を見ていた人物・・・いや、神様のようだった。
そして、ぐずで間抜けなりっこを、それでも今回の、何やら大役に推したのに、りっこが失敗をしたことで、マリちゃんの評判もちょっと落ちたというか、どうも周りの連中に笑われているらしい。
(ところで、神様って、どういうことだよ。この寺となんか関係あるのか?)
周囲を見回す。
すると、何やら寺の由来が書いてある看板が目に留まった。
俺はそれをとりあえず斜め読みしてみた。こういうのってわけわからないから苦手なほうなんだけど。
なんでもこの寺は「摩利支天」とかいうのを祀っているらしい。
なんだよこの摩利支天って。
なになに?
インドの神話に登場する仏教の守護神・・・太陽の前にあって陽炎そのものを神格化した女神・・・梵天の子・・・武士の守護神・・・財福の神・・・亥の日が縁日・・・猪に乗った姿が特徴的・・・・こういうのってほんと基礎知識無くてよくわかんないんだけど・・・摩利支天・・・読みがなは、まりしてん・・・この女は神様のまりちゃん・・・まさか、んなわけねえだろうと思うけど、
「まさか君が摩利支天?」
俺は思わず、ガミガミとりっこに説教を垂れている女に、唐突にそう言ってしまった。
すると女はこっちに向き直った。
「そうよ。だけどっ、何あんた、軽々しくわたしを呼び捨てにするんじゃないわよ!」
「まりちゃん怒らないでー、和弘さんは何も知らないのよ」
俺はやっぱりちょっとクラクラした。
その後、とりあえず俺たちは、徳大寺の境内からアメ横へ降りて、目についたコーヒーショップに入った。
あんな寒いところでいつまでも立ち話しているのもなんだし、俺が二人を誘ったのだ。
「わたし、ブレンド」
「わたし、紅茶。レモンティがいいな」
二人はカウンターで注文すると、俺を見上げた。
「いっとくけど、わたし、お金もってないからね!あんたが払うのよ」
「えへへ、わたしもお願いします」
「あー、はいはい」
俺は3人分の飲み物代を払った。
しかし、おごってもらうのにこんなに高飛車な女も初めてだ。いや、りっこはいいんだけど、なんだよマリちゃんって。
「ねえ、財福の神なんじゃないの?摩利支天ってさ。さっきちょっとお寺の看板読んだんだけどさ」
俺はアメリカンコーヒーを口に運びながら、ちょっとイヤミを言ってしまった。
「そうだけど、わたしはお金なんか持ってないに決まってるでしょ」
「そういうもんなの?」
「必要がないから」
「ふーん、金がいらないなんて、いいね神様って」
「うるさいわねえ。ま、じゃあこうやってコーヒーをおごってくれたお礼に、そのうちなんかあなたにいいことがあるようにしてあげるわよ」
「お、助かるよ!マリちゃん、マジで頼むよ」
「まぁ、これもご縁ってヤツだからねえ」
暖かいものを飲んで人心地がついたせいか、やっと雰囲気がほぐれ出した。
やはり俺が思った通り、喫茶店作戦は成功したようだ。
「ところで、りっこのことなんだけど。一ヶ月早く来たって怒られてるけど、どういうこと?」
「ああそうか。あなたほんとに何もわかってないのね。えーと、ちなみに今年の干支って覚えてる?」
「うーん、戌、だったかなー」
「はい、よくできました。じゃ、来年は?」
「は?えーと、ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、・・・・い」
「そう。亥年です。ようするにイノシシ。わかるかしら」
「ええ、まぁ」
「わたしは亥の係なのよ。来年は12年に一度の忙しい年なの。そのパートナーにわたしはりっこを選んだの。何しろ小さな頃から知ってるし、真面目さは折り紙つきだからね。でもねー、りっこはちょっと頭が足りないから、そこが心配だったんだけど、まさか最初からこんな大間抜けをするとは思わなかったのよね」
「ごめんなさい。わたし、まさかこんな大役に選ばれるとは思ってなくて・・・ほら成績もイマイチだったし、だからせめて時間に遅れちゃいけないって、その一心で・・・そうしたらなんか勘違いしちゃってたみたいで」
りっこは神妙な顔で俯いている。
「悪気がなかったのはわかるわ。でもね、ちょっとわたしの立場も考えて欲しいわ。すでに結構笑われてんのよわたし、帝釈天とかにさ。あいつ、ムカつくー」
マリちゃんは、さすがにさっきほどの勢いは無く溜め息をつきながらりっこと語っていた。
「ねー、ケーキ食べたい。甘いものでも食べなきゃやってられないわよ。ちょっとあなた、さっさとケーキ買って来て!えっとチーズケーキにしてね。あと、コーヒーもお代わり」
しかし初めて会った男にここまで堂々と金を払わせる女・・・やはりただものではないよな、と俺は思った。
仕方なく、ケーキを二人分と、コーヒーの追加を頼んで運んで来た。
「はい、どーぞ」
「ありがとう。あ、そうだ、あなたにも話があるわ」
マリちゃんはケーキにフォークをぐさりと突っ込みながら言った。
「なんでしょう」
「わかってると思うけど、このことは他言無用よ。りっこがイノシシだってこともよ、あとわたしのことも」
俺は小さく溜め息をつきながら答える。
「ってゆーか、例え言ったとしたって誰も信じないから大丈夫だよ。下手にそんなこと回りに言ったら俺、とうとうアル中がひどくなったって思われて、どっかの精神病院に入院させられるだけだと思うよ」
「ま、そんなところかもね。わかってりゃいいんだけど。とにかく、絶対よ!あとはまぁ、とりあえず31日までりっこを頼むわ。こうなったらもう、あなたに頼んでおくしかないものね。ま、これも何かのご縁ってことで、来年はあなたにちゃんといいことを用意するからさ。大事にしてやってよ、どうせあとちょっとだから」
ズキン。
俺の心に、何かが刺さった、ような気がした。
そうだ俺、その話をこの女と詰めなくちゃいけないんじゃないか、もしかしたら。
「あのさ、俺のほうでも君に話があるんだけど」
「何よ?」
マリちゃんはうさんくさそうなものを見るような目で俺を見た。ほんといちいちヤな感じのやつだ。
「31日まで、って言ってたけど、そのあとりっこはどうするんだ。俺のところからいなくなるのか?」
「いなくなるわよ。当たり前じゃない。りっこはわたしと仕事しなくちゃいけないんだから」
「えーとさ、その仕事、通いじゃできないのか?俺のところからりっこが君のところに通うって形で」
「ムリね。なんたって出張が多いから。それに、基本的にはずっと一緒にいないとダメなのよ。りっこは来年の干支なのよ、そのへん、わかってる?通いの干支なんて聞いたこと無いでしょ。あなた、今年の干支は9時から5時まででーす、とかそういうの通用するとでも思ってるの?」
やっぱりそうか。りっこはいなくなるのか。俺は段々、暗い気持ちになってきた。
「でも俺、りっこと一緒にいたいんだよ」
「そんなこと言われてもねえ。ほらっりっこ、あなたからもきちんと言わなきゃダメよ」
するとりっこは小さい声でおずおずと言い出した。
「あのね、マリちゃん・・・わたしも和弘さんのこと好きかもしれないの」
「は?何言ってるのよりっこ」
マリちゃんは呆れたように言った。
「あなたはイノシシなのよ。人間と一緒にいても仕方ないのよ」
俺は必死で訴えた。
「とにかくりっこと一緒にいたいんだ。マリちゃん、頼むよ」
マリちゃんがこっちを向いた。
よく見ると、マリちゃんの目には黒目が無かった。
だから怖い感じがするのだろうか。
そうしてその目で、マリちゃんは俺をじーっと見た。
色白で小さめの顔立ちで、肌はツルツルときれいでシミも皺も無い。
下手すると毛穴も無いかもしれない。
ボブスタイルの髪は黒々として不自然なほどツヤがあり、目は一重なのだが腫れぼったい感じはなく大きくて、美しかった。
美しかったが、怖かった。
しかし、怖いからとここで怯んではならないと思った俺は、目をそらさずとにかく耐えた。
「バカねえ」
マリちゃんは笑った。俺を茶化すような笑い方だった。
「そうだわ、ねえあなた、宝くじに当たってみたくない?そうねえ、一億円くらい。コーヒーとケーキと、りっこを預かってくれたお礼に、それくらいしてあげてもいいかなと思っていたのよ」
一億円。
いきなり出て来たとんでもない金額に、さすがに俺は一瞬考えたが、すぐに結論は出た。
たとえば一億円が当たったからって何だって言うんだ?そりゃうれしいけど、でもそうしたらりっこはいなくなっちゃうんだろ。もう二度と会えないんだろ。
たとえ金があったって、寂しい一生なんか俺はイヤだ。やっと、愛を知ったような気がしているっていうのに。金と幸せを交換なんかできるか?そりゃ、両方手に入れば言うことないけど。
「金なんかいいよ。当たらなくていい、宝くじなんて。それより、りっこを俺のところに置いてくれよ」
俺は言い張った。ここは頑張るしかない。交渉あるのみだ。
「ふーん」
マリちゃんは、ちょっと困った様な表情で、ケーキをぱくつきながら考えているようだった。
「まぁでもね、そう言われてもムリなものはムリよ。もうすでに来年の干支はりっこに決まってるんだし。まさか一足飛びに子年にしちゃうわけにいかないし」
「そうですよねえ」
りっこもそこは責任を感じるようで、悲しそうな顔で俯いてしまった。
「どうしてもダメなのか」
俺は思わずりっこの手を握りしめた。
いっそここから、逃げ出してしまえば、りっこは俺のものになってくれるのだろうか。
「あなたねえ、バカなこと考えるのやめなさいね」
マリちゃんはあっさりと言った。なんで俺の考えがわかるんだろう。神様だから当然なのか。しかし。
「でも、俺思うんだけどさ。もともと、こんなことになっちゃったのは、君のせいでもあるんじゃないの?りっこが間抜けだってことは承知の上で大役に抜擢したんだろ、どうしてもっとちゃんと見ててやらなかったんだよ。そうしたら俺とあんなところで出会うこともなかったわけだろ。出会わなかったら好きになったりしなかっただろ」
理屈とも言えない理屈だが、俺の言葉にマリちゃんはうっと詰まった。
「まぁねえ」
「だろ。どう責任を取ってくれるんだよ。俺、金なんかいらないぞ。別に神頼みしなけりゃならないこともないしさ。今の願いは、りっこのことだけだ」
マリちゃんは、しばらく考えているようだったが、立ち上がると店の外に出て行った。そして、何やらケータイでどこかに電話してる様子だった。
「ねえ、和弘さん。でも、いいの?」
りっこがポツンと言った。
「どういうことだよ」
「あんなこと言って。わたしたち会ったばかりだし、それに、わたしはイノシシなのよ」
「いいんだよ。だって好きになっちゃったんだもんな」
美人のマリちゃんに比べると、りっこはいかにも地味だ。
マリちゃんはたしかに、女神という感じ・・・りっこはというと、確かに家来のイノシシのような雰囲気の女。
でも俺は絶対にりっこがいい。りっこが好きだ。
「わたしも和弘さんのこと、好きになっちゃった。最初は、いい人そうだなって思っただけだったけど。でもね、和弘さん優しいし、親切だし、それにわたしのことをとっても好きなんだっていう気がするの。そこに全く迷いが感じられないの」
「うん」
「だから安心できるの。わたし、できればいつまでも、和弘さんと一緒にいたい」
俺は頷いた。もちろん俺だって同じ気持ちだった。
そこへマリちゃんが戻って来た。
「上に相談してみたけど、来年に関してはやはりもう変更できないわ。でも、そのあとに関しては、りっこをあなたのところに行かせることができるかもしれない」
「ほんとに?」
りっこがうれしそうに言い、マリちゃんの手を取った。
「ねえりっこ、でもほんとにそれでいいの。そうなったらもう、二度とこっちへは戻って来られないのよ。人間の世界でずっと暮らさなくちゃいけないのよ」
「がんばります」
「あなたにできるかしら。ただでさえ間抜けなのに。心配だわ。それから、あなた」
マリちゃんは俺に向き直った。
「あなたも相当な覚悟が必要なのよ。りっこは人間ではないわ。かといってただのケモノでもない。わかりやすく言えば、りっこは神の使いなのよ。あなたにちゃんとそれがわかっているのかしら。りっこを裏切らず大事にして、けして離れないと、あなたに約束できるのかしら。わたし、ちゃんと見てるわよ。りっこを不幸にしたら、ただじゃ済まないわよ」
「わかりました」
俺ってもしかしたらこれから先、絶対に浮気できないのかも、と思ったが、
(いいんだ、りっこさえいれば)
と、俺は決心した。
「確約はできないわ。でもできるだけわたしもがんばってみます。わたしもりっこのことは可愛いし、幸せになってもらいたいから。ま、とにかく今年は31日までりっこを置いてやってちょうだい」
マリちゃんは、残ったコーヒーを飲み干しながら言った。
それからの日々は・・・俺は仕事に追われて休みも取れず、いよいよ年末になってしまった。
朝と夜しかりっこに会えないなんて俺は寂しくて仕方なかったけど、とにかく毎晩、俺たちはしっかり抱き合って眠った。
29日からは休みになる予定だったのだが、なんとこんなときに限って急な変更が入り休めなくなってしまうという不運さ。
これでも俺は真面目なサラリーマンなので、こういうときもきっちり仕事をしようとしてしまう。上手に抜けて帰ってしまったヤツもいるのに・・・
30日、そろそろ世の中のヤツらはみんな休日だ。
田舎の実家に帰ってみたり、正月の準備をしたりしているんだろう。
けれど俺は、もうすぐいなくなってしまうりっこと一緒に過ごすこともろくにできないでいる。
夜に帰宅した俺はテレビをつけた。
そうしたら深夜のニュースショーをやっていて、コメンテーターのひとりが、「来年は亥年ですねえ~」などと言いやがった。
(亥年になど、ならなければいいのに・・・)
俺の目には涙が浮かびそうになる。
りっこはそんな俺に気がついているのかいないのか、食事の後片付けや洗濯物の片付け、そのほか大掃除のつもりなのかあちこちきれいにしている。
「そんなこといいから、早くこっちに来いよ」
俺はちょっとイライラしながらりっこに言った。
「ちょっと待って、もう少しでお掃除が終わるから。わたし、明日からいないでしょ。和弘さん大変だから、きれいにしておきたいの」
「いいからこっち来いよ」
俺は構わずりっこを呼んだ。
そんなことちっとも重要じゃないじゃないか。今は二人で、ただ体を寄せ合っているほうが、どんなにか大事に違いないんだ。
「りっこ。ほんとうに明日になったら、いなくなっちゃうのか」
俺はりっこを抱きしめた。
「仕方ないわ。仕事だもの。でもね、この次に、わたしがあなたのところへきたら、もうあとは毎日一緒よ。毎日、離れないで暮らすのよ」
泣くまいと思っていたが、やはり涙が出てしまった。
りっこの暖かい体が、もう明日には俺の側からなくなってしまうのだ。
そのあとどうしていたらいいのか、どうやってりっこを待っていればいいのか、俺にはさっぱりわからなかった。
「大丈夫。和弘さんの気持ちさえ変わらなければ、わたしはきっと戻って来るから・・・お願い、泣かないで」
りっこが泣いている俺を見上げて、そっと唇を寄せて来た。
そして31日になってしまった。
大晦日だっていうのに、俺はまだ仕事が残っていて、出社しなければならなかった。
俺が家を出たあと、りっこもマリちゃんの元へ向かうらしく、もうこれっきりしばらく俺はりっことは会えないことになる。
「いってらしゃい、和弘さん」
りっこはいつも通り俺を玄関まで送ってくれた。
「ああ。行って来る」
俺はどこか呆然としていた。しかしどうしようもない。
りっこはちょっと寂しそうだったけれど、でもにこにこしていた。
そして新年が明けて・・・俺のところにもイノシシ柄の年賀状が何枚か届いた。りっこが働いているらしい。
まぁでも、正月が過ぎれば干支なんてそんなに関係が無くなる。
一体、りっこはどこで何をしているのか。
買い物に行った先の大手スーパーでふと見つけたことがきっかけで、俺は生まれてはじめて干支の置物を買った。
いくつか種類があったが、丸っこい形で、目がつぶらな、可愛いものを選んだ。
それはどこか、りっこに似ているような気がした。
家に帰り、俺はそれをベッドサイドに置いて、眺めながら毎晩眠った。
ひたすら会社と家を往復するだけの日々が過ぎて行った。
俺の会社も、昨今の不況でリストラが進み、一人が請け負う仕事量はどんどん増えている状況だった。
そんなわけで毎日が忙しく、何も考えるヒマなど無いほどだったのだが、それでも俺はりっこのいない寂しさに、時折押しつぶされそうな気持ちになった。
俺はたまに徳大寺へ行った。
でもマリちゃんのケータイ番号を知らない俺は連絡手段も無く、ただお参りするだけだった。
たまの休日は、じっとしているとりっこのことばかり考えてしまうので、全国のイノシシや摩利支天を祀っている神社を回って歩いた。
出張も多いと言っていたから、きっとそういうところに二人は行っているのに違いないと思ったのだ。でもタイミングが合わなかったのか、りっこもマリちゃんも姿を現してはくれなかった。
俺は毎晩のように酒ばかり飲んでろくに食べないので、ただでさえ細い体がさらに痩せた。そして酔っぱらって寝ていると、たまにりっこが夢に現れたりした。
「飲み過ぎよ、和弘さん。わたしが行くまで元気でいて。食事もちゃんとして」
俺はそんなとき、泣きながらりっこに縋った。
「ダメだよ俺、りっこがいなかったらダメなんだ。だから早く来てくれ、頼む、そうじゃないと俺死んじゃうよ」
そんな日々を繰り返し、季節は過ぎて行った。
そして夏が過ぎ、涼しくなった頃のことだった。
俺のケータイに前の彼女から電話が入った。
「久しぶり」
「ああ、久しぶり」
夜の10時を過ぎたところで、ちょうど渋谷で同僚との飲み会に出ていたときだった。
「今、何してるの?」
「渋谷で飲んでる」
「そう。じゃ、これからそっちに行くから、会わない?」
「・・・別にいいけど」
結婚した前の彼女は、確か祐天寺に住んでいるはずだった。渋谷までなら確かに東横線ですぐだから、出て来ることは簡単だろう。
でも、結婚したばかりの主婦がいきなり夜の10時過ぎに出て来るなんて尋常ではない。俺はちょっと不思議に思った。
しばらくしてから、同僚との飲み会を適当に抜け出し、待ち合わせのバーへ行くと彼女はもうカウンターで飲んでいた。以前は二人でよく来ていた店だ。
「どうしたんだよ」
ウィスキーをロックでもらうと、俺は前の彼女をしげしげと眺めた。しばらく見ないうちに、美人は相変わらずだが、ちょっと落ちついたというか、老けたような気がした。
「別にどうもしていない。飲みたかっただけよ。で、ふと和弘のことを思い出したりしたのよね」
「旦那はどうしてるんだよ」
「あ、今出張に行ってるの」
「なるほど、そういう訳か」
「そういうことよ」
彼女はふっと笑った。笑うとやはりきれいで、俺好みだなと思った。老けたような気がするのは、いわゆる所帯やつれというやつかもしれない。
さらさらとしたロングヘアは相変わらずで、爪もきれいに塗ってある。マリちゃんなんかは美人だが痩せすぎていてあまり色気は感じられないし、りっこはそういう意味では問題外なのだが、彼女はほっそりしているけれど出るところは出ていて、肉感的だ。身長はおそらく160センチくらいだけれど、ヒールのある靴を好むので俺と並ぶと同じくらいに見える。
今日の彼女は、落ち着いたボーダー柄のぴたっとしたワンピースに黒のロングカーディガン、足元はヒールのあるショートブーツを履いていた。シックないでたちは、以前と変わらなかった。
「なんだよ。結婚して一年もしないうちから、他の男と遊びたくなっちゃったのか」
「違うわよ。和弘だから、誘ったのよ」
「よく言うよ。幸せなんだろ?」
俺と前の彼女は、遊ぶ分には気が合っていた。そういう相性っていうのはあるかもしれない。
それに、なんていうか、俺は久しぶりに、
(人間の女と話してるな)
と感じた。どこかお互い牽制しつつも、それなりの連帯感があるとでもいうか。こんな感じは俺にとってなぜか、とても懐かしいもののような気がした。
「うーん。ちょっと後悔しているのかもしれない」
彼女はジントニックをお代わりしながらそう言った。この女も酒豪でザルなのだ。きっと早いうちに肝臓を壊すだろう。俺もひとのことは言えないが。
「なんだよ後悔って。俺を捨てて行ったくせに」
俺が笑いながら茶化すと、彼女はちょっとムキになったようだった。
「だってそうなんだもの」
「ふーん。なんで後悔なんかしてるんだよ」
「それは、まぁいろいろあるのよ」
「いろいろねえ」
どうでもいい話をしながら、ウィスキーを何杯も飲んでいると、さすがの俺もいい感じに酔って来た。彼女も同じみたいだった。
「とにかく、後悔してるのよ。そうしたら、和弘のことばかり思い出しちゃって」
「そりゃ光栄だな」
「ねえ、真面目に聞いてる?わたし、旦那と別れるかもしれないのよ」
「聞いてるよ」
「いっつもそんな感じね、和弘って」
「じゃあ、どうすればいいんだよ。俺にどうして欲しいの?」
彼女はいつのまにか、ずいぶんと俺のほうへ体を寄せて来ている。
「わかってるでしょ」
彼女はそっと俺の指を握りながら言った。
「うーん」
俺は、自分の指を彼女に預けながら、しばらく考えていた。酔ってはいたが、まだ判断力が無くなるほどではなかった。
「やめとくよ」
彼女はまだ俺の指をいじっていた。
「どうして?新しい彼女でもできたの?」
「まぁ、そんなところかな」
「これから会うの?」
「いや、しばらく会えないんだ」
「じゃあ、いいじゃない」
「ダメなんだ。なんていうのかな、俺、愛を知っちゃったからさ」
「何それ」
彼女は呆れたように言い、俺の指を離した。
「うまくいえないけど、なんかもう仏門に入っちゃったみたいなもんなんだと思う、俺」
「どうしちゃったの和弘。なんか、ヘンな新興宗教みたいなのに引っかかってない?」
「違うよ。まぁでも、似たようなものなのかな」
彼女は間もなく、適当に切り上げて帰ってしまった。
たぶんもう二度と、俺に連絡を寄越すこともないだろう。
ひとりになった俺は、まだしばらくその店で飲んでいて、そして終電で高井戸に帰った。
仕事は普通にしていたが、俺はちょっぴり気難しくなり、他人にはあまり隙を見せなくなった。
その分、なぜか会社での評価は高くなったようで、冬のボーナスがかなり増えた。うちの会社は査定がそのままボーナスに響くシステムになっているので、そのあたりのことはすぐにわかるのだ。
(そっか、もう12月なんだな)
亥年が終るのはもうすぐだ。
そうしたらりっこは来てくれるはずだ。
俺はそれだけを楽しみに、年末の殺人的な忙しさに耐えていた。 それどころか、りっこが来るのだからと、夜中に帰宅したあと部屋の掃除までしてしまう有様だった。
ところがである。
大晦日の夜、除夜の鐘が鳴っても、朝になって明るくなっても、子年の柄の年賀状が届いても、りっこは全く現れなかった。
俺は焦った。そして目の前が暗くなった。
(どうしたんだよりっこ。もう干支じゃなくなったはずだろ)
そういえばマリちゃんは、確約できないと言っていた。
もしかしてダメだったのか。
そう思うと、とても寝てなどいられなかった。
俺は一睡もしないまま電車に乗り、徳大寺へと向かった。とにかく行ってみなければと思った。
上野に到着すると、そこそこは混んでいるがおそらく年末ほどではなく、アメ横も休みの店が多かった。しかし徳大寺へ到着すると、そこにだけは大勢の参拝客がいた。
よく考えたら神社仏閣が元旦に混み合うのは当たり前で、俺はその行列を見ただけでげんなりした。
(マリちゃんも大変だな)
俺はいつか、三人でお茶を飲んだコーヒーショップで一休みすることにした。
暖かいコーヒーを飲み、ひとりでぼうっと考えていたら、まるで体が地面にめり込んで行くかと思うほどの疲労と悲しみを感じた。 俺はもう二度とりっこには会えないのかもしれない。そしてそれは当たり前のことなのかもしれない。
涙も出なかった。胸に何かが詰まったようで、出口が見つからなかった。
コーヒーを飲み終わると、俺は高井戸に帰ることにした。初詣客で混み合った電車に乗り、駅まで帰り着くと、コンビニに寄ってビールのロング缶を三本とウィスキーを買った。
おせち料理の代わりのつもりなのか、ちょっと豪華な弁当なども売っていたが、全く食欲は湧かなかった。
「高井戸ローズマンション」まで歩くと、俺は重い足取りで階段を上がり始めた。
普段ならあまり気にならない4階までの階段が、なんだかとてもおっくうに感じた。
(なんだかここもイヤになっちゃったな。今度はエレベーターのあるところにでも引っ越すか)
そんなことを思いながら、階段を上がり切り、部屋のあるほうに向かって角を曲がると、ちょうど俺の部屋の前あたりに、誰かが立っていた。
それを見た途端、俺はその場から動けなくなってしまった。
そして急に苦しいくらいに胸がいっぱいになり、その次に今度は、息が浅くなるほどの喜びがこみ上げてきたのだった。
俺の部屋の前に、女の子が立っていた。それは、紛れもなくりっこだった。
茶色いダッフルコートに、ベージュのロングブーツ。肩までだった髪もそのままだった。けれど、一年間の仕事で疲れたのか、前よりちょっと痩せた気がした。
手には重そうな買い物袋を下げていて、俺を見ると、にこにことうれしそうに手を振った。
俺は夢中で駆け寄った。
「りっこ」
「和弘さん。ただいま」
「なんで、すぐに来なかったんだよ」
「ねずみさんへの引き継ぎもあったし、スーパーで買い物もしたかったから。和弘さん、お腹空いてるでしょ。またおいしいもの、作ってあげるからね」
俺はりっこを抱きしめた。いくら抱きしめても足りなかったし、そうやって確認しなければ、気が済まなかった。
「ねえ和弘さん、苦しいよ」
りっこはそう言ったけど、俺はそのままりっこの唇にキスをした。
りっこの手から買い物袋が落ちて、カシャ、と音がした。
「卵、割れちゃったよ」
りっこがつぶらな瞳で俺を見つめた。キスをしたせいかちょっと顔が赤い。
卵が割れようが地球が割れようが、俺はもう二度と絶対にりっこを離さない。
そう思った。
終り
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- バーバラ・H・ローゼンワイン/リッ…
- (2024-11-30 22:57:12)
-
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ 2024年第52号
- (2024-11-28 11:10:37)
-
-
-

- 人生、生き方についてあれこれ
- 京都占い・魔法使いの家・
- (2024-11-30 10:08:09)
-
© Rakuten Group, Inc.