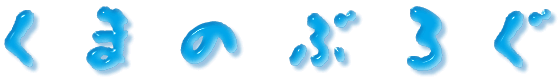PR
X
Free Space
くまのぶろぐ
Freepage List
Calendar
カテゴリ: カテゴリ未分類
毎年この大会が終わると、気が遠くなります。
まずは、数年前に打法が大きく変革し、その打法を取り入れたチームの選手から放たれたボールの弾道が以前とは大きく変わっている事に気がつきます。
また、特別に設けられた席で、その選手達の小さなプレイのサーブとレシーブなどを見ると、やはり肘、肩の動きなど、TVでは分らない部分がはっきりと見えます。正直、目標にするにはあまりにも遠く感じてしまいます。
今年は技術的には大きな変革はありませんでしたが、数年前から使われ出した新技術が上位に残る選手達だけではなく、早く敗退する選手にも浸透しておりました。
しっかりと底上げがされていると感じました。確実に日本の卓球は変わりつつあり、指導者もするべき練習方法を大きく再考しなくてはならないと感じました。
わたくしの様な年代の指導者が、自分の経験による指導をしていたのでは、良い選手は育たないのはすでに理解しております。
また、メンタルについても同じで、21本でしか戦った事のない年代が、11本になってからの事を子供達に指導、またベンチコーチをするためにはかなりの勉強が必要でしょう。
さて、女子では、目の前で数年前まで世界で戦っていたスーパーシードの選手達が、緒戦で敗れる光景を多く見ました。
また、こういった選手の試合を見ると、北海道の宝梅村礼選手が日本チャンピオンの頃、張怡寧選手に勝った事を思い出し、その方向性は誤っていないとも感じました。
男子では、チキータなどのレシーブとカウンター技術について意見交換をする指導者が多く、綺麗に決まったカウンターを賞賛する声を多く聞きましたが、上位戦になると実際にはそうそうカウンターを打つことは難しいので、勝ち上がる選手達に共通していたのは、サーブレシーブで先手を取るか、鍛えられた身体で強烈な両ハンドを打ち込んだ後、フォアハンドの連打か、チャンスメーク後のカウンターで得点するケースでした。
あらためてフィジカルの重要性を認識させられた試合が多くありましたし、総じてバックハンドに安定を求めて繋ぐ技術しか持ち合わせていない選手は、戦術的に幅がなく、試合の中盤以降そこに気がついた相手サイドに押し切られる試合が多く見られました。
また今年は、吉村選手が優勝した時のような、中陣から一発で抜き去るバックハンドを持つ選手も多く見られました。
フォアハンドでは中陣から一発で抜き去る事は中々難しいのですが、バックハンドだと台から離れても得点になる事に早く着眼し、理論に基き練習方法を構築した指導者群が、現在上位戦で優位に立っております。
また、その技術を習得するための練習はそれだけではなく、全体的な身体の使い方を理想に近づけ、二次的効果を高く得ているのも特徴的であると感じました。まさに「大は小を兼ねる」を痛感しました。
以外だったのは、愛工大、明治大学など、大学生の中の強豪選手の多くが「筋肉の鎧」をしっかりと身につけていた事でした。
もちろんインナーマッスルもしっかりと鍛えてはいるのでしょうが、今や一流の卓球選手は、我町の体育館にごろごろいる日本一流の「ウエイトリフティング選手」にも引けを取らないような身体になっており、また、そこへ到達するために普段から地味で厳しい努力を継続したおかげで、この大会での活躍があるのだろうと、その力強いボールを見ながら感じ入っておりました。
長谷川選手。伊藤選手。他の日本人世界チャンピオンもそうでした。
もちろん今の新しい技術、指導、考え方は正しいのです。しかし、この鍛え方もまた必要な事であり間違ってはおりません。もちろんそこだけに特化しては違うスポーツになってしまいますが、必要な事は古くても認める事も重要な事です。「温故知新」これもまた真実でしょう。
卓球が好きでなくてはこんな事を考えたりはしませんが、また、大きな壁に立ち向かって行こうと動き出す事には、大きな気力体力が必要であるのもまた事実であります。
まずは、数年前に打法が大きく変革し、その打法を取り入れたチームの選手から放たれたボールの弾道が以前とは大きく変わっている事に気がつきます。
また、特別に設けられた席で、その選手達の小さなプレイのサーブとレシーブなどを見ると、やはり肘、肩の動きなど、TVでは分らない部分がはっきりと見えます。正直、目標にするにはあまりにも遠く感じてしまいます。
今年は技術的には大きな変革はありませんでしたが、数年前から使われ出した新技術が上位に残る選手達だけではなく、早く敗退する選手にも浸透しておりました。
しっかりと底上げがされていると感じました。確実に日本の卓球は変わりつつあり、指導者もするべき練習方法を大きく再考しなくてはならないと感じました。
わたくしの様な年代の指導者が、自分の経験による指導をしていたのでは、良い選手は育たないのはすでに理解しております。
また、メンタルについても同じで、21本でしか戦った事のない年代が、11本になってからの事を子供達に指導、またベンチコーチをするためにはかなりの勉強が必要でしょう。
さて、女子では、目の前で数年前まで世界で戦っていたスーパーシードの選手達が、緒戦で敗れる光景を多く見ました。
また、こういった選手の試合を見ると、北海道の宝梅村礼選手が日本チャンピオンの頃、張怡寧選手に勝った事を思い出し、その方向性は誤っていないとも感じました。
男子では、チキータなどのレシーブとカウンター技術について意見交換をする指導者が多く、綺麗に決まったカウンターを賞賛する声を多く聞きましたが、上位戦になると実際にはそうそうカウンターを打つことは難しいので、勝ち上がる選手達に共通していたのは、サーブレシーブで先手を取るか、鍛えられた身体で強烈な両ハンドを打ち込んだ後、フォアハンドの連打か、チャンスメーク後のカウンターで得点するケースでした。
あらためてフィジカルの重要性を認識させられた試合が多くありましたし、総じてバックハンドに安定を求めて繋ぐ技術しか持ち合わせていない選手は、戦術的に幅がなく、試合の中盤以降そこに気がついた相手サイドに押し切られる試合が多く見られました。
また今年は、吉村選手が優勝した時のような、中陣から一発で抜き去るバックハンドを持つ選手も多く見られました。
フォアハンドでは中陣から一発で抜き去る事は中々難しいのですが、バックハンドだと台から離れても得点になる事に早く着眼し、理論に基き練習方法を構築した指導者群が、現在上位戦で優位に立っております。
また、その技術を習得するための練習はそれだけではなく、全体的な身体の使い方を理想に近づけ、二次的効果を高く得ているのも特徴的であると感じました。まさに「大は小を兼ねる」を痛感しました。
以外だったのは、愛工大、明治大学など、大学生の中の強豪選手の多くが「筋肉の鎧」をしっかりと身につけていた事でした。
もちろんインナーマッスルもしっかりと鍛えてはいるのでしょうが、今や一流の卓球選手は、我町の体育館にごろごろいる日本一流の「ウエイトリフティング選手」にも引けを取らないような身体になっており、また、そこへ到達するために普段から地味で厳しい努力を継続したおかげで、この大会での活躍があるのだろうと、その力強いボールを見ながら感じ入っておりました。
長谷川選手。伊藤選手。他の日本人世界チャンピオンもそうでした。
もちろん今の新しい技術、指導、考え方は正しいのです。しかし、この鍛え方もまた必要な事であり間違ってはおりません。もちろんそこだけに特化しては違うスポーツになってしまいますが、必要な事は古くても認める事も重要な事です。「温故知新」これもまた真実でしょう。
卓球が好きでなくてはこんな事を考えたりはしませんが、また、大きな壁に立ち向かって行こうと動き出す事には、大きな気力体力が必要であるのもまた事実であります。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 21, 2014 08:07:45 AM
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.