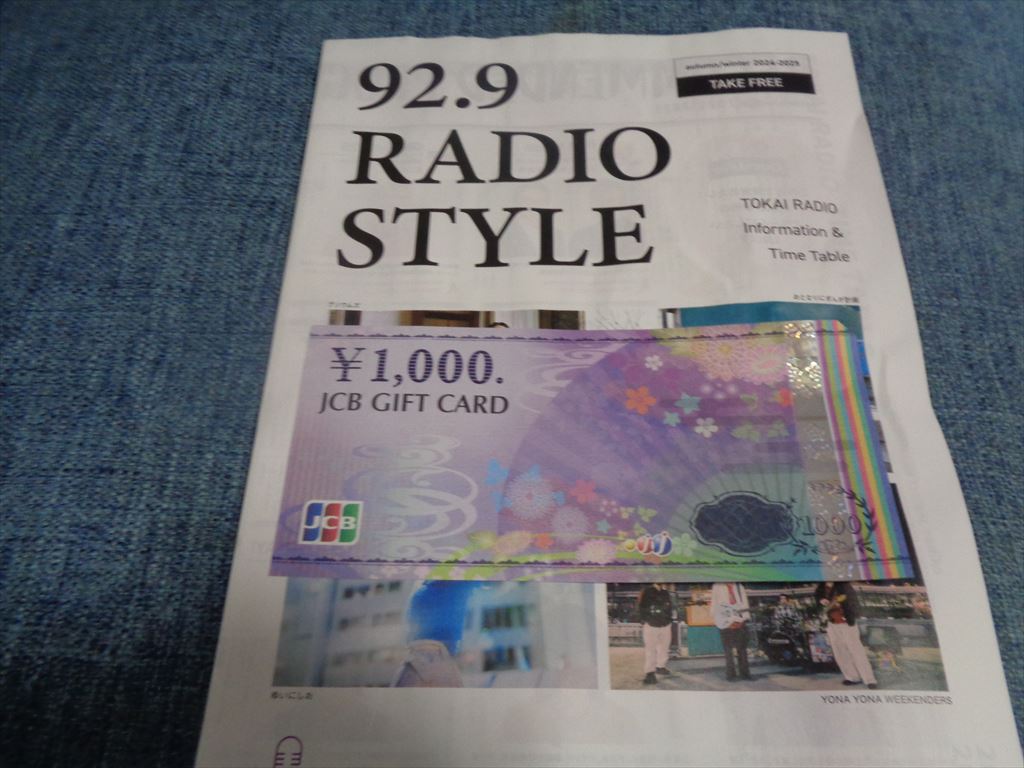8
ポケットの秘密 8
「あら、帰ってたの。ちょっといい?」
母から声を掛けてくるのは何ヶ月振りだろうと考えながら、私は声のした階下へ向かった。帰宅して間もなかったのでまだ制服のままだったけど、着替えは後回しにする。
「この前、叔父さんから聞いたと思うけど、九州へ来ないかって話があるの」
居間のソファに座ると、母が切り出した。今日の母は素面のようだった。それでもアルコールの臭いが漂っているような気がする。
私は頷いた。
「うん、聞いた」
「お母さんね、その話受けようと思うの。お兄ちゃんは大学があるからここに残ることになるけど、あなたはどうする? お母さんは、できれば一緒に行きたいと思ってる」
叔父の話では、私の希望を考慮してくれる余地などなさそうだった。実際、先日母が受けた血液検査の結果は、肝機能の数値が異常に高かったらしい。アルコール依存の気もある。
私は、母の土気色の顔を見ながら、また頷いた。
「うん。一緒に行く。お父さんにはもう話した?」
「実はお父さんね、ここを出て行く時、離婚届に判を押したものを置いて行ってたの。後はお母さんが名前を書いて提出すればいいだけ。ずっと悩んでいたけど、やっと決心がついたのよ」
「そう」
少なからずショックだった。離婚はもう決定的だと思っていたけれど、一言くらいの相談はあって当然だと思っていたから。
「ちょっと気分悪いから、部屋に戻るね」
頭に浮かんだ彼の顔を振り切るように、一つ首を振って立ち上がる。心配顔の母に、私の心配よりも自分の体を大切にして、と微笑んで居間を出た。
この期に及んで、まだ『いい子』を続けている自分にバカバカしさを感じる。
今日、自分は学校で何をしてきた? 明日、何をしようとしている?
スカートのポケットに手を入れ、カッターに触れる。刃を新しいものに取り替えなくてはならない。プラスチックの部分が、体温で生暖かくなっていた。
諦めなければいけない。彼の心に私の居場所はなかったのだから。
翌朝返ってきた靴の中に、藤田のものはなかった。
期待はしていないつもりだったが、それでもやっぱりがっかりしたところをみると、ぼくはこの返却劇に一縷の望みってやつを賭けていたのかもしれない。これで今日の放課後は藤田に付き合わざるを得なくなったわけだ。
きれいに並べられた靴の群れを前にして、ぼくはため息を吐いた。
運動部のかけ声が遠くに聞こえる。校門付近に咲いていた紫陽花には、朝露が光っていた。しかし、清々しいはずの朝の空気は、この昇降口までは届いてこない。誰もいない空間に香るのは、泥と汗と油に何かの食べ物の残りをミックスさせたような、なんともいえない臭いだ。そう、ここに漂っているのは、溝掃除の時によく嗅ぐドブの臭いに近いものだった。
どんな奴が盗んだ靴を昇降口に並べているのか見てやろうと、いつもより一時間も早く登校してきたのに、そこにはもうボロ靴が整列していた。
何か共通点はないか、一つ一つ覗き込んで確認してみる。いくつかは手に取ってもみたが、ほとんどの靴からあまり触りたくないと思うほどの悪臭が放たれていた。
だいたいのものが泥で汚れているが、あまり汚れのないものも、中敷に書かれていた文字が消えていたり、靴の裏面のゴム部分がちびてしまっていたりと、もともとかなり履きこまれていたことが窺えた。靴の紛失が始まったのは一ヶ月ほど前である。盗まれてから付いたか付けられたかした汚れを差っ引いても、新品だった物はなさそうだ。
藤田のナイキは新品同然だった。ひょっとして、古いものだけ返されてきているのだろうか。闇で売るなら、売れなかったボロだけを返してくるということもあり得る。
しかし犯人は、本当に闇で売りさばくために盗んでいるのだろうか。
それなら、もとからきれいな靴だけを盗みそうなものだ。この中には、盗まれた時点ですでに捨てられる寸前だったんじゃないかと思うようなオンボロも少なくない。それに、闇で金儲けしようと人の靴を盗むような人間なら、見つかるかもしれないリスクを犯してまで返してくるよりも、捨ててしまうだろう。
汚い靴達を目を皿のようにして見ているぼくの横を、通学してきた生徒達が怪しいものでも見ような視線をくれながら通り過ぎる。そろそろ登校してくる人間の多くなる時間帯だった。
先ほどまで、遠くから聞こえる掛け声と鳥の鳴き声しか聞こえなった空間は、たちまち喧騒に包まれ始めた。
時々、ぼくと同じように身をかがめて、靴を物色していく生徒もいる。その内の数人は、並べられていた中から一足つまみあげて自分のものらしい下駄箱に入れていた。物色しているのは、靴を盗まれていた生徒達らしい。
「きみも靴を盗まれてたの?」
声をかけられて振り向くと、赤松がいた。彼女から声をかけてくるのは、犬が木に登るくらい珍しい。
「違うけど。藤田の靴を探してるんだ」
「藤田君の?」
「うん。教室のロッカーに置いてたらしいんだけど、盗まれたんだって」
「あのナイキ?」
「そう」
どうやら、藤田があの靴をロッカーに入れていたことは、あのクラスの人間なら誰でも知っていることのようだった。
「・・・・・・あれは返ってこないんじゃないかな」
赤松が考え込むような顔で呟いた。
「どうして分かる?」
「分からないけど、なんとなく」
どうにも歯切れが悪い。しかし、問い詰める前に、彼女は慌てて校内へ入っていった。転びそうになりながら靴を履き替えて走っていく。何かに追われているような様子に後ろを振り向くと、タカヨシが走ってきていた。犬は一目散に赤松を追っていく。
仲のいい二人(正確には一人と一匹)のことだ。新しい遊びでも始めたんだろう。赤松が階段から転げ落ちなければいいが。
ぼくはぼんやりと、靴を覗き込んでいる生徒達を眺めた。自分の靴を見付けて下駄箱へ運んでいく生徒は、自然と目で追ってしまう。
距離を置いて眺めてみると、靴はどれも小さめであるように見えた。そういえば、手に取った靴はどれも二十三センチくらいまでで、それよりも大きなものはあまりなさそうだった。
もう一つ気付いたことがある。靴を見付けて下駄箱に入れている生徒を見ていると、下駄箱の位置がどれも下の方にあるのだ。高い所でも、ぼくの腰より少し上くらいのものだ。
犯人を捕まえようなんて気は毛頭ないが、藤田の靴を取り返すには、犯人に会うのが一番の近道だろう。
ぼくはこの二点が犯人の手がかりにならないかと考え、頭の中に書き付けた。
放課後。わざわざ部活を休んだ藤田と共に、ぼくはトイレの衝立に隠れて見張りをすることになった。トイレは昇降口の前にある。靴の盗難が頻発するのは放課後なので、運が良ければ現行犯を捕まえられるというわけである。
「犯人が泥棒する前にトイレに入ったら丸分かりじゃん」
ぼくは呆れて、提案者の藤田に言った。
「その時はその時だ」
どうやら藤田は怒りだけで動いているらしい。目を吊り上げて衝立の陰から昇降口の方を覗いている。これじゃあ、捕まるものも捕まらないんじゃないかと、ぼくはため息を吐いた。
もう帰宅ラッシュは過ぎており、昇降口に人影はなかった。クラブ活動をしている人間は、今の時間は練習の真っ最中。居残りをしていた者や、なんとなく残っていた人間が時折現れる程度だ。靴泥棒は、そういった遅くまで残っている人間の靴を狙うことが多いようだった。
「あ、誰か来た」
カチカチと床に硬いものが当たる音が近づいてきた。ぼくは藤田に促されて洗面台の上に足をかける。いつかのように衝立の上から頭を出して廊下を見回すと、薄汚れた白い犬が爪音を響かせてうろついていた。
「なんだ、タカヨシじゃん」
ぼくの声に気付いて、タカヨシが上を向く。ぼくは手だけで「あっちへ行け」と合図した。犬は一声吠えると、きれいに整列した下駄箱の向こうへ消えていった。
すると、タカヨシと入れ違いくらいに外から入ってくる人影があった。外部の人間が犯人なら、外からやってくることもあり得る。ぼくは衝立から身を乗り出して、人影の方を見つめた。影は藤田達のクラスの下駄箱へ進んでいく。
パンっと履き物をすのこの上に落とす音に続いて、ガコガコと靴を履き替える音。どうやら靴を盗んでいるわけではないらしい。
それでもそのまま見ていると、その人物が田口加奈子であることが分かった。彼女は通学用鞄の他に、体操服を入れていると思われるナイロン袋を抱えていた。
「田口さん、昨日体操服持って帰るの忘れたんだな。今日体育なかったし」
藤田がコメントする。田口は彼の目にも映る所まで来ていた。
ぼくは、あれ? と思った。たしかに今、田口は体操袋のようなものを持っているが、昨日、杉本の机に置いた荷物の中にも同じものがあったような気がしたのだ。
田口はぼく達に気付く様子もなく、階段の方へ歩いていく。何か忘れ物でもしたのだろう。ぼくはほっと胸をなでおろした。
それから三人くらい帰っていく人間がいて、三十分もしないうちにまた田口が現れた。今度はちゃんと帰るつもりらしい。上履きから靴へ履き替えている。
このまま何事もなく帰っていくかと思いきや、彼女はつと顔を上げ、こちらを見た。ぼくを見止めた彼女の目が真ん丸くなっていく様を、スローモーション映像でも見るように、ぼくは見た。
「そんな所で何してるの?」
「いや、別に」
藤田が下から「バカ」とぼくの足を小突いた。
「いつからいたの?」
「田口が階段を降りてきた時くらいから」
ぼくは適当に答えた。
「何でそこにいるの?」
「なんとなく。田口はこんな時間まで何してたんだよ?」
「え? 私? 私は瑞葉と一緒に帰ろうと思ってたんだけど、また姿が見えなくなっちゃって。今見たら下駄箱に靴無くなってたから、先に帰っちゃったのね、きっと」
彼女は寂しそうに肩を落とした。「また置いて帰られちゃった」
「昨日もあの後会えなかったの?」
「うん。昨日も先に帰っちゃってたみたい」
先ほどもここを通ったのに、今靴がないのに気付いたというのはおかしいと思いながらも、ぼくも昨日、赤松と会えなかったことを思い出し、少し同情してしまった。ぼくの場合は一緒に帰る約束をしていたわけでもなかったので、彼女を待つのに飽きてノートだけを置いて勝手に帰ったのだが。
「携帯は?」
「出ないの。メールもしてみたけど、返事まだだし」
藤田が早く切り上げろと小声で抗議してくる。
ぼくは、一時間くらい前からこの辺りをうろついていたけれど、杉本は見なかったと伝え、彼女を見送った。
「杉本さんて、優しそうなのに結構冷たいんだな」
ぼくが洗面台から降りると、藤田が声を潜めて言った。
「なんで?」
ぼくにとっては、杉本は脅威に近い存在だ。天敵と言ってもいい。嫌なことを覚えているし、やけに突っかかった物言いをしてくる。それを優しそうと表現する藤田を変だと思うが、確かにぼくを除く人間には彼女は優しいのかもしれない。赤松に対する態度や田口の慕いようを見ていると、そんな気がする。ぼくは彼女にとって、優しくする価値も無い対象であるらしい。
「昨日、田口さんは杉本さんの机に荷物を置いてただろ。杉本さんの荷物は、あの時まだあった。だから杉本さんは帰る時、田口さんが自分を探してるって気付いてたはずだ。普通、一緒に帰ろうとも思ってない人間の机に、荷物を置いて消えたりしないだろ」
「それもそうだな」
藤田の推測はもっともだと思えた。ぼく以外にも、冷たくあしらわれている人間がいるらしい。田口も気の毒に。しかし、だ。
「でも、田口も杉本にべったりだよな。まるで金魚の糞じゃん。女子ってなんであんなにべったりツルもうとするのかね」
田口が杉本を探している姿は、まるで母親を探す赤ん坊のようだ。あんなにべったりついて来られたんじゃ、杉本だって嫌になるかもしれない。
しかし藤田は平然と言い放った。
「女子なんてあんなもんだぞ。俺なんて、デートにまで彼女が友達連れてきたことあるからな」
「げっ。まじ?」
「まじまじ。俺とばっか遊んでると、友達を粗末にしてると思われるんだと。『恋人と友達、どっちが大事なの?』なんて女特有の質問だと思うけど、それはこっちのセリフだっての。ま、単独行動してる女の子なんて、うちのクラスじゃ赤松さんくらいのもんだな」
藤田は女子の友達付き合いの仕方について、聞いてもいないのにいろいろと話してくれた。彼女のいる奴の話は妙に説得力があり、ぼくは軽いカルチャーショックを受けた。
考えてみれば、赤松だって一人でいたくているわけではないだろう。あいつだって、べったり一緒にいられる友達がいるなら、そうしたいと思っているかもしれない。
「とにかくそういうことだから、田口さんのあの行動はそれほど異常じゃないと思うぜ。ま、俺らから見たら、多少金魚の糞に見えなくもないけどな」
藤田はそう締めくくった。ぼくは、ふーん、と頷くしかなかった。
「杉本さんって、結構かわいいし優しそうで、マリア様みたいだとか言われてるけど、実際は見かけだけなのかもな」
藤田の呟きは、寒々しい光を発している蛍光灯に照らされた空間に溶けて消えた。
結局この日、靴泥棒を見つけることはできなかった。
- つづく -
「あら、帰ってたの。ちょっといい?」
母から声を掛けてくるのは何ヶ月振りだろうと考えながら、私は声のした階下へ向かった。帰宅して間もなかったのでまだ制服のままだったけど、着替えは後回しにする。
「この前、叔父さんから聞いたと思うけど、九州へ来ないかって話があるの」
居間のソファに座ると、母が切り出した。今日の母は素面のようだった。それでもアルコールの臭いが漂っているような気がする。
私は頷いた。
「うん、聞いた」
「お母さんね、その話受けようと思うの。お兄ちゃんは大学があるからここに残ることになるけど、あなたはどうする? お母さんは、できれば一緒に行きたいと思ってる」
叔父の話では、私の希望を考慮してくれる余地などなさそうだった。実際、先日母が受けた血液検査の結果は、肝機能の数値が異常に高かったらしい。アルコール依存の気もある。
私は、母の土気色の顔を見ながら、また頷いた。
「うん。一緒に行く。お父さんにはもう話した?」
「実はお父さんね、ここを出て行く時、離婚届に判を押したものを置いて行ってたの。後はお母さんが名前を書いて提出すればいいだけ。ずっと悩んでいたけど、やっと決心がついたのよ」
「そう」
少なからずショックだった。離婚はもう決定的だと思っていたけれど、一言くらいの相談はあって当然だと思っていたから。
「ちょっと気分悪いから、部屋に戻るね」
頭に浮かんだ彼の顔を振り切るように、一つ首を振って立ち上がる。心配顔の母に、私の心配よりも自分の体を大切にして、と微笑んで居間を出た。
この期に及んで、まだ『いい子』を続けている自分にバカバカしさを感じる。
今日、自分は学校で何をしてきた? 明日、何をしようとしている?
スカートのポケットに手を入れ、カッターに触れる。刃を新しいものに取り替えなくてはならない。プラスチックの部分が、体温で生暖かくなっていた。
諦めなければいけない。彼の心に私の居場所はなかったのだから。
翌朝返ってきた靴の中に、藤田のものはなかった。
期待はしていないつもりだったが、それでもやっぱりがっかりしたところをみると、ぼくはこの返却劇に一縷の望みってやつを賭けていたのかもしれない。これで今日の放課後は藤田に付き合わざるを得なくなったわけだ。
きれいに並べられた靴の群れを前にして、ぼくはため息を吐いた。
運動部のかけ声が遠くに聞こえる。校門付近に咲いていた紫陽花には、朝露が光っていた。しかし、清々しいはずの朝の空気は、この昇降口までは届いてこない。誰もいない空間に香るのは、泥と汗と油に何かの食べ物の残りをミックスさせたような、なんともいえない臭いだ。そう、ここに漂っているのは、溝掃除の時によく嗅ぐドブの臭いに近いものだった。
どんな奴が盗んだ靴を昇降口に並べているのか見てやろうと、いつもより一時間も早く登校してきたのに、そこにはもうボロ靴が整列していた。
何か共通点はないか、一つ一つ覗き込んで確認してみる。いくつかは手に取ってもみたが、ほとんどの靴からあまり触りたくないと思うほどの悪臭が放たれていた。
だいたいのものが泥で汚れているが、あまり汚れのないものも、中敷に書かれていた文字が消えていたり、靴の裏面のゴム部分がちびてしまっていたりと、もともとかなり履きこまれていたことが窺えた。靴の紛失が始まったのは一ヶ月ほど前である。盗まれてから付いたか付けられたかした汚れを差っ引いても、新品だった物はなさそうだ。
藤田のナイキは新品同然だった。ひょっとして、古いものだけ返されてきているのだろうか。闇で売るなら、売れなかったボロだけを返してくるということもあり得る。
しかし犯人は、本当に闇で売りさばくために盗んでいるのだろうか。
それなら、もとからきれいな靴だけを盗みそうなものだ。この中には、盗まれた時点ですでに捨てられる寸前だったんじゃないかと思うようなオンボロも少なくない。それに、闇で金儲けしようと人の靴を盗むような人間なら、見つかるかもしれないリスクを犯してまで返してくるよりも、捨ててしまうだろう。
汚い靴達を目を皿のようにして見ているぼくの横を、通学してきた生徒達が怪しいものでも見ような視線をくれながら通り過ぎる。そろそろ登校してくる人間の多くなる時間帯だった。
先ほどまで、遠くから聞こえる掛け声と鳥の鳴き声しか聞こえなった空間は、たちまち喧騒に包まれ始めた。
時々、ぼくと同じように身をかがめて、靴を物色していく生徒もいる。その内の数人は、並べられていた中から一足つまみあげて自分のものらしい下駄箱に入れていた。物色しているのは、靴を盗まれていた生徒達らしい。
「きみも靴を盗まれてたの?」
声をかけられて振り向くと、赤松がいた。彼女から声をかけてくるのは、犬が木に登るくらい珍しい。
「違うけど。藤田の靴を探してるんだ」
「藤田君の?」
「うん。教室のロッカーに置いてたらしいんだけど、盗まれたんだって」
「あのナイキ?」
「そう」
どうやら、藤田があの靴をロッカーに入れていたことは、あのクラスの人間なら誰でも知っていることのようだった。
「・・・・・・あれは返ってこないんじゃないかな」
赤松が考え込むような顔で呟いた。
「どうして分かる?」
「分からないけど、なんとなく」
どうにも歯切れが悪い。しかし、問い詰める前に、彼女は慌てて校内へ入っていった。転びそうになりながら靴を履き替えて走っていく。何かに追われているような様子に後ろを振り向くと、タカヨシが走ってきていた。犬は一目散に赤松を追っていく。
仲のいい二人(正確には一人と一匹)のことだ。新しい遊びでも始めたんだろう。赤松が階段から転げ落ちなければいいが。
ぼくはぼんやりと、靴を覗き込んでいる生徒達を眺めた。自分の靴を見付けて下駄箱へ運んでいく生徒は、自然と目で追ってしまう。
距離を置いて眺めてみると、靴はどれも小さめであるように見えた。そういえば、手に取った靴はどれも二十三センチくらいまでで、それよりも大きなものはあまりなさそうだった。
もう一つ気付いたことがある。靴を見付けて下駄箱に入れている生徒を見ていると、下駄箱の位置がどれも下の方にあるのだ。高い所でも、ぼくの腰より少し上くらいのものだ。
犯人を捕まえようなんて気は毛頭ないが、藤田の靴を取り返すには、犯人に会うのが一番の近道だろう。
ぼくはこの二点が犯人の手がかりにならないかと考え、頭の中に書き付けた。
放課後。わざわざ部活を休んだ藤田と共に、ぼくはトイレの衝立に隠れて見張りをすることになった。トイレは昇降口の前にある。靴の盗難が頻発するのは放課後なので、運が良ければ現行犯を捕まえられるというわけである。
「犯人が泥棒する前にトイレに入ったら丸分かりじゃん」
ぼくは呆れて、提案者の藤田に言った。
「その時はその時だ」
どうやら藤田は怒りだけで動いているらしい。目を吊り上げて衝立の陰から昇降口の方を覗いている。これじゃあ、捕まるものも捕まらないんじゃないかと、ぼくはため息を吐いた。
もう帰宅ラッシュは過ぎており、昇降口に人影はなかった。クラブ活動をしている人間は、今の時間は練習の真っ最中。居残りをしていた者や、なんとなく残っていた人間が時折現れる程度だ。靴泥棒は、そういった遅くまで残っている人間の靴を狙うことが多いようだった。
「あ、誰か来た」
カチカチと床に硬いものが当たる音が近づいてきた。ぼくは藤田に促されて洗面台の上に足をかける。いつかのように衝立の上から頭を出して廊下を見回すと、薄汚れた白い犬が爪音を響かせてうろついていた。
「なんだ、タカヨシじゃん」
ぼくの声に気付いて、タカヨシが上を向く。ぼくは手だけで「あっちへ行け」と合図した。犬は一声吠えると、きれいに整列した下駄箱の向こうへ消えていった。
すると、タカヨシと入れ違いくらいに外から入ってくる人影があった。外部の人間が犯人なら、外からやってくることもあり得る。ぼくは衝立から身を乗り出して、人影の方を見つめた。影は藤田達のクラスの下駄箱へ進んでいく。
パンっと履き物をすのこの上に落とす音に続いて、ガコガコと靴を履き替える音。どうやら靴を盗んでいるわけではないらしい。
それでもそのまま見ていると、その人物が田口加奈子であることが分かった。彼女は通学用鞄の他に、体操服を入れていると思われるナイロン袋を抱えていた。
「田口さん、昨日体操服持って帰るの忘れたんだな。今日体育なかったし」
藤田がコメントする。田口は彼の目にも映る所まで来ていた。
ぼくは、あれ? と思った。たしかに今、田口は体操袋のようなものを持っているが、昨日、杉本の机に置いた荷物の中にも同じものがあったような気がしたのだ。
田口はぼく達に気付く様子もなく、階段の方へ歩いていく。何か忘れ物でもしたのだろう。ぼくはほっと胸をなでおろした。
それから三人くらい帰っていく人間がいて、三十分もしないうちにまた田口が現れた。今度はちゃんと帰るつもりらしい。上履きから靴へ履き替えている。
このまま何事もなく帰っていくかと思いきや、彼女はつと顔を上げ、こちらを見た。ぼくを見止めた彼女の目が真ん丸くなっていく様を、スローモーション映像でも見るように、ぼくは見た。
「そんな所で何してるの?」
「いや、別に」
藤田が下から「バカ」とぼくの足を小突いた。
「いつからいたの?」
「田口が階段を降りてきた時くらいから」
ぼくは適当に答えた。
「何でそこにいるの?」
「なんとなく。田口はこんな時間まで何してたんだよ?」
「え? 私? 私は瑞葉と一緒に帰ろうと思ってたんだけど、また姿が見えなくなっちゃって。今見たら下駄箱に靴無くなってたから、先に帰っちゃったのね、きっと」
彼女は寂しそうに肩を落とした。「また置いて帰られちゃった」
「昨日もあの後会えなかったの?」
「うん。昨日も先に帰っちゃってたみたい」
先ほどもここを通ったのに、今靴がないのに気付いたというのはおかしいと思いながらも、ぼくも昨日、赤松と会えなかったことを思い出し、少し同情してしまった。ぼくの場合は一緒に帰る約束をしていたわけでもなかったので、彼女を待つのに飽きてノートだけを置いて勝手に帰ったのだが。
「携帯は?」
「出ないの。メールもしてみたけど、返事まだだし」
藤田が早く切り上げろと小声で抗議してくる。
ぼくは、一時間くらい前からこの辺りをうろついていたけれど、杉本は見なかったと伝え、彼女を見送った。
「杉本さんて、優しそうなのに結構冷たいんだな」
ぼくが洗面台から降りると、藤田が声を潜めて言った。
「なんで?」
ぼくにとっては、杉本は脅威に近い存在だ。天敵と言ってもいい。嫌なことを覚えているし、やけに突っかかった物言いをしてくる。それを優しそうと表現する藤田を変だと思うが、確かにぼくを除く人間には彼女は優しいのかもしれない。赤松に対する態度や田口の慕いようを見ていると、そんな気がする。ぼくは彼女にとって、優しくする価値も無い対象であるらしい。
「昨日、田口さんは杉本さんの机に荷物を置いてただろ。杉本さんの荷物は、あの時まだあった。だから杉本さんは帰る時、田口さんが自分を探してるって気付いてたはずだ。普通、一緒に帰ろうとも思ってない人間の机に、荷物を置いて消えたりしないだろ」
「それもそうだな」
藤田の推測はもっともだと思えた。ぼく以外にも、冷たくあしらわれている人間がいるらしい。田口も気の毒に。しかし、だ。
「でも、田口も杉本にべったりだよな。まるで金魚の糞じゃん。女子ってなんであんなにべったりツルもうとするのかね」
田口が杉本を探している姿は、まるで母親を探す赤ん坊のようだ。あんなにべったりついて来られたんじゃ、杉本だって嫌になるかもしれない。
しかし藤田は平然と言い放った。
「女子なんてあんなもんだぞ。俺なんて、デートにまで彼女が友達連れてきたことあるからな」
「げっ。まじ?」
「まじまじ。俺とばっか遊んでると、友達を粗末にしてると思われるんだと。『恋人と友達、どっちが大事なの?』なんて女特有の質問だと思うけど、それはこっちのセリフだっての。ま、単独行動してる女の子なんて、うちのクラスじゃ赤松さんくらいのもんだな」
藤田は女子の友達付き合いの仕方について、聞いてもいないのにいろいろと話してくれた。彼女のいる奴の話は妙に説得力があり、ぼくは軽いカルチャーショックを受けた。
考えてみれば、赤松だって一人でいたくているわけではないだろう。あいつだって、べったり一緒にいられる友達がいるなら、そうしたいと思っているかもしれない。
「とにかくそういうことだから、田口さんのあの行動はそれほど異常じゃないと思うぜ。ま、俺らから見たら、多少金魚の糞に見えなくもないけどな」
藤田はそう締めくくった。ぼくは、ふーん、と頷くしかなかった。
「杉本さんって、結構かわいいし優しそうで、マリア様みたいだとか言われてるけど、実際は見かけだけなのかもな」
藤田の呟きは、寒々しい光を発している蛍光灯に照らされた空間に溶けて消えた。
結局この日、靴泥棒を見つけることはできなかった。
- つづく -
© Rakuten Group, Inc.