-
1

<645> 生活保護受給者こそクレジットカードを持つべき
“生活保護受給者”こそクレジットカードを持つべき なぜそう「断言」できるのか徹底解説カード会社が生活保護受給者をどう見るかクレジットカードを実際に発行する立場のクレジットカード会社は、国や自治体とは別の視点で、生活保護受給者とクレジットカードの関係を見ています。前編記事『生活保護受給者とクレジットカード その意外すぎる“使用実態”とは』に続くこの後編記事では、さらに生活保護とクレジットカードの関係を深掘りしていきます。クレジットカード会社は、基本、貸金業者ですから申込者に安定した収入があり、返済能力があれば、クレジットカードは発行できると判断します。一方で、カードの入会審査の項目には生活保護受給しているかどうかの項目はありません(個人情報保護の観点から国が伏せているのです)。その意味で、入会審査は極めて公平に行われていると言って良いでしょう。 とはいっても生活保護者は基本的には不利になります。「無職」の人が多いので、それが大きなハンデになっているのです。そのため、申込書に「無職」と書いてしまうと、返済能力がないとしてすぐにはねられます。パートやアルバイトをしているならば、収入が少なくとも、「年収」とその「勤務先」は書いたほうが良いでしょう。(※働いていても収入が最低生活費以下の場合は生活保護を受けられます)ブラックリスト入りしているケースただ、そこまでしても審査に通るとは限りません。というのも生活保護を受けようとする人の多くが、金銭的なトラブルの末に保護を受けることになっていることが多いからです。 「長期延滞」や「多重債務」「任意整理」「自己破産」などで、いわゆるブラックリスト入りしているケースがあります。このため、信用情報機関(CIC)に照会された時点で、アウトになる場合が多いといわれます。 その結果、生活保護者の多くが返済能力がないとして、または金融事故の経験者として、クレジットカード所有を認められなくなっているのです。この点は今のところ仕方のないところでもあります。 しかし、現在はキャッシュレス全盛の時代なので、クレジットカードがないと購入することのできない商品も増えてきています。最低限の暮らしの中でクレジットカードで生活必需品を購入したいという場面が増えていることも事実です。クレジットカードはもはや従来的な価値観の贅沢なものではなく、生活の必需品という時代です。ポイントの付与なども考えれば、現金だけで生活するより、生活保護受給者の生活費のいくらかの足しになることも間違いないでしょう。 それは生活保護受給者を監督する自治体側からしても歓迎すべきことではないでしょうか。正当な理由が必要生活保護を受けている人がクレジットカードを持つ場合、一般的な申込者と比べて気をつけるべき点がいくつかあります。 (1)必ずケースワーカーに相談すること まず、クレジットカードを取得しようという時に、必ずやってほしいことですが事前に担当のケースワーカーと福祉事務所に相談することです。無断でクレジットカードを取得したことが発覚すると、生活保護の減額、停止、最悪の場合は生活保護の受給を打ち切りにされてしまう可能性もあります。 (2)少しでも「年収」があるなら書く カード会社の審査で重視しているのは安定した収入があるかどうかです。少しでも収入があるのなら年収の項目に必ず書き込むことです。ただし収入状況によっては一般のカード会社では審査に通過しない場合が十分に考えられますがカードの種類によっても発行されやすいカードがありますからよく選んでください。 (3)クレジットカードが必要な理由をしっかり書く 「ステーキを食べたい」とか「レジャーで息抜きしたい」「クルマを買いたい」などでは話になりませんが、「スマホ料金を支払うため」など、毎日使う通信手段の使用のためなど、正当な理由があれば問題はないでしょう。さらに購入は生活必需品に限られますが、飲料数のまとめ買いなどは、スーパーなどで買うより、ネットでカード決済したほうが安い上に、自宅まで送られてくるので便利です。 このような手続きを踏めば、生活保護者もクレジットカードを持ってキャッシュレス生活を送れるようになるでしょうが、すでに示したように、クレジットカード利用はあくまで最低限の生活の範囲内と言う厳しいルールがあるので、事前に商品価格を吟味して購入しなければなりません。 しかしここ数年でクレジットカードに代わる新しい決済手段が出てきています。生活保護受給者が持ちやすいカードキャッシュレス機能を使えるという点で私がオススメするのはデビットカードです(Visa、JCBなど国際ブランドの付いたデビットカードをブランドデビットと呼び、特にその種類がオススメです)。 こちらは借金になりませんし審査もほとんどありません。年会費も安くて誰でも持てます。 銀行の口座から買い物したお金が直接即時に引き落としになるので、借金になりませんし、残高の範囲内ならいつでも自由に使うことができるから便利です。当然、ネットショッピングも可能です。 このデビットカードは都市銀行だけでなく地方銀行もたくさん発行していますから銀行口座を作るときに一緒にデビットカードを作るのが良いでしょう。当然、生活保護受給者だからといって厳しい制約を受けることはありませんから安心して使えます。そう考えると、申し込みの時から買い物の時までピリピリしていなければならないクレジットカードに比べると全然自由なカードということができるでしょう。 問題は使いすぎですが、もともと口座にはギリギリの生活費しか入っていませんから、生活必需品(小物)の買い物にしか使えません。これも安心できます。そう考えるとデビットカードこそ生活保護者にぴったりのカードということができるかもしれません。 それにしても不思議でならないのはマイナンバーカードでは行政のデジタル化にあれほど熱心な官僚たちが、どうしてこの生活保護の分野ではクレジットカードやデビットカード等のデジタルツールの導入に積極的でないのか、分かりません。カードがケースワーカーの仕事を代行すべてデジタル化して見える化したほうが管理するのも楽だと思うのに、ケースワーカーに丸投げしようとするのは確かにおかしいことです。 デジタル技術を使えば、「上限額が近づくとアラームが鳴ったり」「贅沢品を買おうとしたらピカピカ光って知らせる」とか、様々な機能でこれまでケースワーカーの行ってきた仕事を代行することができるのです。そうしたすべてをデジタル化できればケースワーカーも福祉事務所も随分と楽になるのに、と思うと残念な限りです。 キャッシュレス化が叫ばれる時代ですから、その流れに逆らうのでなく流れに乗って生活保護者専用のクレジットカード(デビットカード)を作ろうと考えて動くくらいのことはやって欲しいものです。 そして、そこに様々な機能を盛り込めばケースワーカーや福祉事務所の助けになりますし、生活保護受給者も助かります。 クレジットカードが「贅沢品」という認識は時代遅れです。ぜひ努力していただきたいところです。
2023年02月09日
閲覧総数 1360
-
2

<457> 楽園の夜
暴力団の構成員テグは、大切な家族を殺された報復として敵対組織の幹部を襲撃する。ボスの指示で済州島に身を隠した彼は、そこで心に傷を抱える女性ジェヨンと出会い、反発しあいながらも心を通わせていくが……。
2025年04月27日
閲覧総数 21
-
3

<1425> 愛の中へ by オフコース
2024年09月04日
閲覧総数 27
-
4

<1451> 元気すぎる高齢タレントの衝撃的な真実
テレビではカットされる「元気すぎる高齢タレント」の「衝撃的な真実」老いればさまざまな面で、肉体的および機能的な劣化が進みます。目が見えにくくなり、耳が遠くなり、もの忘れがひどくなり、人の名前が出てこなくなり、指示代名詞ばかり口にするようになり、動きがノロくなって、鈍くさくなり、力がなくなり、ヨタヨタするようになります。世の中にはそれを肯定する言説や情報があふれていますが、果たしてそのような絵空事で安心していてよいのでしょうか。 医師として多くの高齢者に接してきた著者が、上手に楽に老いている人、下手に苦しく老いている人を見てきた経験から、初体験の「老い」を失敗しない方法について語ります。 *本記事は、久坂部羊『人はどう老いるのか』(講談社現代新書)を抜粋、 編集したものです。スーパー元気高齢者の罠欲望肯定主義の世の中はまったく油断がならず、不幸と不満を増大させる勘ちがいを引き起こす「罠」に満ちています。 その最たるものが、スーパー元気高齢者の活躍です。 もう亡くなられましたが、スーパー元気高齢者の代表といえば、元聖路加国際病院名誉院長の日野原重明氏でしょう。百歳を超えても現役の医師であり、晩年にもベストセラーの著作を発表し、テレビ出演もされていました。 かつて日野原氏はあるテレビ番組で、次のように発言していました。 「六十五歳で助走がはじまり、七十五歳で飛躍するんです」 なんと希望に満ちあふれた言葉でしょう。しかし、現実的ではありません。むしろ、弊害が多いです。たとえば、せっかく引退する気になっている高齢の社長や会長が、またやる気になってしまったりとか。 「老害」という言葉はあまり使いたくありませんが、現実にはそこここでささやかれています。職場で頑張る地位の高い高齢者は、たいてい周囲には有害であって、当人はそれに気づいていません。中には、「若い者がどうしてもやめさせてくれない」などと言う人もいますが、そんな人にかぎって、裏では若者たちがリタイアを熱望しています。 さらに日野原氏は番組で、「わたしはエレベーターは使いません。 階段も二段飛ばしで上がります」と発言していました。そんな言葉を聞けば、「よし、ワシも負けておれん」とばかり、突然、階段を二段飛ばしにして転倒、骨折して寝たきりになったり、あるいは途中で心臓発作を起こして永眠ということになったりしかねません。 日野原氏の著書には、階段飛ばしについて、「急激な無理は禁物」と書いてありますが、テレビではそこは省略されます。視聴者の盛り上がりに水を差すからです。TVで見かける有名シニア女優も、裏では…昨今は高齢の女性俳優がテレビに出演して、その若さと美貌、元気はつらつなようすを、ごく控えめを装いながら堂々と披露しています。自然な人間の姿とはとても思えませんが、おそらく並外れた努力と巨額の投資が裏にあるのでしょう。もちろんそんな秘訣が明かされることはなく、明かされるとしてもごく当たり障りのないもので、ほんとうに効果のあるものは秘されてしまいます。 そんな元気な高齢女性俳優も、カメラがオフになれば「フーッ」と息を吐き、シャンと伸びていた背中もくにゃっと曲がるのではないでしょうか。家に帰ればさらに緊張は緩み、年齢相応の老化現象が露出するはずです。 しかし、視聴者はそこまで想像しません。ふだんの生活も若々しく美しいのだろうと思います。それで困るのは、未だ老いの手前にいる中年世代の人たちが、老いの厳しさに対する心の準備をおろそかにしてしまうことです。八十歳をすぎてもあんなふうにいられるのか、九十歳に近づいてもあんなに元気でいられるんだと、楽観的になって安心してしまいます。 スーパー元気高齢者が元気でいられるのは、投資もあるでしょうが、基本的には持って生まれた体質のおかげでしょう。もともと長寿の体質でなければ、何をやっても効果は得られません。もともとの体質(すなわち遺伝子)は変えられませんから、快適な老いを実現するには、自分の体質の中で満足を得ていく以外にありません。 ところが、スーパー元気高齢者の活躍を見せられると、自分もそうなりたい、なれればいいな、なれるのではないか、きっとなれるだろうと思う人が増え、そうなれない場合、不満と失望を抱え込んでしまうのです。 私が老人デイケアのクリニックにいたとき、身体が弱って不自由になったことを嘆く人は多かったですが、あまり不愉快そうでもない人もいました。そういう人は、「年いったらこんなもん」と、現状を受け入れていました。老いの現実を正しく認識し、高望みをせず、身の丈に合った状況で満足するすべを、身につけている人なのでしょう。それはある種の智恵にほかなりません。 さらに連載記事<じつは「65歳以上高齢者」の「6~7人に一人」が「うつ」になっているという「衝撃的な事実」>では、高齢者がうつになりやすい理由と、その症状について詳しく解説しています。
2025年04月26日
閲覧総数 12
-
5

<824> 60代夫婦の過酷な現実
老後2000万円どころか「月5万円」で苦しむ、60代夫婦の「過酷な現実」老後のお金の難しさ寺田洋子さん(65歳・仮名)と浩志さん(66歳・仮名)は、65歳で会社(継続雇用)を辞めた夫と専業主婦の2人暮らしのご夫婦。今後の老後生活に不安をおぼえた洋子さんが浩志さんとともに、ファイナンシャルプランナーである筆者の元に相談に見えた(プライバシー保護のため内容は大幅に変えてあります)。まず家計簿を見せていただくと、毎月の生活費は月額25万円、年金は2人合わせて約20万円。退職金などのまとまった預金があるのですぐに暮らしに困ることはない。でも毎月少しずつ預金が減ることがとても不安で、お金の使い方で夫婦げんかも絶えず、家の中がギスギスしている。 旅行や趣味などあれこれ老後の楽しみを考えてきたが、とてもじゃないがやる気にならない。洋子さんはこのままでは預金が底をつくのではと考えると、夜も目がさえて眠れなくなり悶々としてしまう。もちろん浩志さんはまだ働くつもりでハローワークに通っているが、デスクワーク希望で思うような仕事がなく今に至っている。 この相談への筆者の回答は後述するとして、このような「老後にあと毎月5万円の定期収入があれば問題は解決するんだけどなあ」という相談がとても増えた。というわけで今回は「プラス5万円の老後」の意味とそれを実現する方法を考えてみたい。 若い人と老後資金の話をすると「最低でも何千万円必要ですか?」という話になることが多い。金融資産はあるに越したことはないが、それだけでは安心とならないのが、老後のお金の難しさだ。 まず老後のお金の現状を見てみよう。高齢者はいくらお金をもっているのか? 70歳以上の2人以上の世帯の場合、金融資産は平均値で2209万円、中央値(金額を並べた真ん中の数字)で1000万円。単身の70歳以上では平均値1786万円、中央値800万円(2021年金融広報中央委員調査)である。 平均値だけ見れば「かなり持っている」印象だが、あくまで平均値なので、1億円以上持っている人がいる一方で、貯蓄ゼロが18%もいるので中央値が実態と近いのかも知れない。また高齢者は持ち家率が80%を越える。何も持たない若い人から見たら「家があって1000万円の預金がある」高齢者はうらやましい限りだ。 しかし、悠々自適の老後かと言えばそうでもない。問題は月々の生活費である。老後資産はあっても、月々の生活費が足りないという高齢者の家計は実際多い。老後の明暗を分けるもの2021年の家計調査(総務省)によると、高齢者の消費支出と非消費支出(税金や健康保険料、介護保険料など)をあわせた家計支出は、以下のようになっている。 ●65歳以上の2人以上の世帯(無職):月額25万5100円 ●65歳以上の単身者世帯(無職):14万4747円 一方、収入の柱(約9割を占める)である公的年金の平均受給額(2021年 厚労省発表)は、この通りだ。 ●国民年金:5万5946円 ●厚生年金:14万4268円 これでは夫婦ともに厚生年金だった共稼ぎの夫婦と、厚生年金が女性より多い単身の男性以外は、月々の生活費が足りない。じゃあどうしているかと言えば、しぶしぶ貯金を取り崩しているのである。 ただ生活費が足りないからと毎月平気で貯金を取り崩す度胸のある高齢者は多くない。今までずっとコツコツ「貯める」で来た人が、頭ではその必要性を理解しても「取り崩し」する生活は精神的にきついようだ。 病気や介護の心配をし、この先何歳まで生きるかと考え始めると、怖くて手持ちの金融資産は使えなくなる。洋子さんたちのように仕方なく取り崩して生活費に充てている人は、残高が少しずつ減っていく通帳をどきどきしながら見ている。 誰だってお金の不安があると心の底から生活を楽しめない。生活費を切り詰めていては、時間はいっぱいあってもちょっとしたお金がないために、外出できないで家に閉じこもりがちになる。資産は持っていても、月々のお金がちょっと足りないという状況は老後の日常生活を本当に暗くする。 本来、「老後」は仕事や家族の扶養などの負担から解放され、自分の人生を好きに生きられる充実の時であるべきだ。特に仕事を引退してから介護が必要となるまでの20年~25年ほどは、持病はあってもそこそこ元気で貴重な時間だ。月にあと何万円の収入があれば、気楽で楽しい老後生活を送れるだろう。 もちろん多いに越したことはないが、沢山稼ぐためには無理をしなければならない。しかし老後に無理はきかない。だから私が考える金額は毎月プラス5万円だ。これがあれば、まず貯金を崩さなくても生活できる人がグンと増えるだろう。これだけでかなり気分は軽くなる。 年金だけのカツカツ生活で外出したくてもできない人も、5万円あれば元気なうちはひとりでも、夫婦や友人をさそっても、気軽に映画や日帰り旅行に出かけたり、おいしいお総菜や和菓子を買ったり、ちょっとお金のかかる趣味だって始められるし、健康のためのジム通いもできる。 また、プラス5万円の老後は介護期に威力を発揮する。要介護認定以前の、ちょっと助けがあれば生活できるプレ介護期に、「すぐに駆けつけるホームセキュリティ」や「宅配弁当」、「週1回のお掃除」、「ヘルパーさんなどの自費サービス」が頼めるようになる。 本格的な介護期になれば、在宅介護の費用が毎月ほぼ5万円だ。施設介護の場合、特養の4人部屋と個室の差額が大体5万円ぐらいだろう。遠距離介護してくれる子供やときどき顔を見せてくれる孫がいれば「交通費だよ」とこづかいも渡せる。 では「プラス5万円の老後」は具体的にどうやって実現すればいいのか? 後編記事『老後に「毎月5万円」を稼ぐ、簡単な「3つの方法」があった…! 』ではその方法を紹介していく。
2023年08月07日
閲覧総数 54
-
6
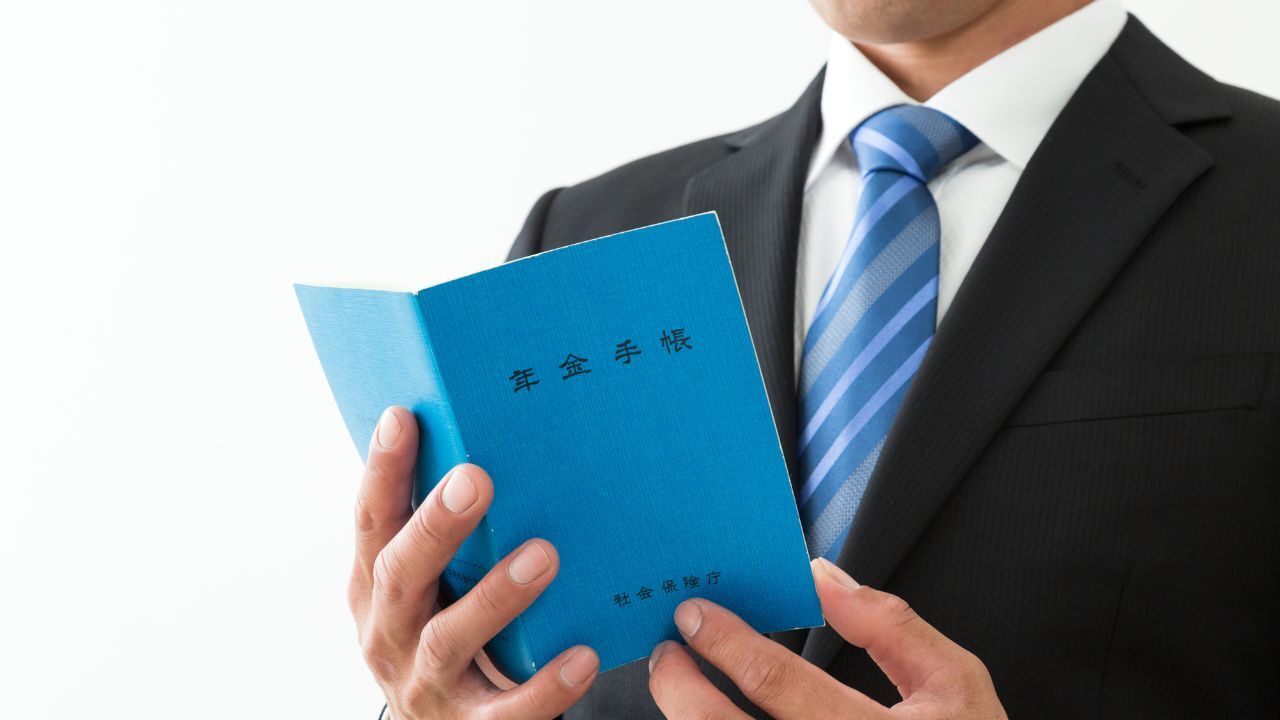
<1448> 知っておきたい、 繰下げ受給の注意点
年金の繰下げなんてしなければよかった…そんな後悔をしないために知っておきたい、繰下げ受給の注意点年金の受給時期を遅らせる代わりに受給額が増える「繰下げ受給」。受給額の増加は魅力的ですが、お得かどうかの判断が難しく、繰下げるべきか迷っている人もいるでしょう。そこで本稿では金﨑定男氏とAIC税理士法人による著書『会社が教えてくれないサラリーマンの税金の基本』(日本能率協会マネジメントセンター)から一部を抜粋・再編集し、繰下げ受給の基本や注意すべきポイントについて解説します。2つの年金制度サラリーマンは、国民年金と厚生年金という2つの年金制度に加入しており、国民年金については10年間以上の加入期間があり年金を納めていれば、受給権があります。65歳になると、国民年金からは老齢基礎年金、厚生年金からは老齢厚生年金の受給を受ける権利が発生し、年金受給を申し込むことにより、年金を受給することができるようになります。年金の繰下げ受給65歳になって年金を受け取る権利のある人は、年金受給の申し込みを行わないことを選択して66歳以降に受給することもできます。その場合には、年金の支給開始が繰り下がります。繰下げを行うことにより、年金額を多くもらうことができるようになります。繰下げのメリットとしては、受給できる年金額が、1か月当たり0.7%増加します。1年間では0.7%×12=8.4%となります。2年間繰下げすると16.8%、5年間繰下げすると42%増加します。例えば、65歳から受給できる年金額が月額10万円だと仮定すると、5年間繰下げすることにより月額14万2,000円の年金を受給できることになります。この繰下げは、老齢基礎年金、老齢厚生年金それぞれ独立して適用できますので、例えば、いずれか一方は65歳から受給することにして、他方のみ繰り下げるといったことも可能です。繰下げは、最大10年間(75歳まで)できますので、10年間繰り下げた場合には、年金額は84%増加した額を受給することができます。ただし、受給開始日が繰り下がるため、長生きする自信がない方は、早めに受給開始したほうが、総受取額は多くなります。繰下げ受給の損益分岐点繰下げ受給をした場合に、どれぐらい長生きすれば、繰下げ受給をしなかった場合(65歳から受給した場合)と比べてお得になるのか、計算過程を省略して結論を言うと、約11.9年で損益分岐点となり、66歳から12年後の78歳になった時点で損益分岐点を超え、それ以上長生きすれば繰下げをしたほうがよいということになります。詳しい説明は省きますが、繰下げ期間が2年であっても、5年であっても、何年であってもこの損益分岐点となる年数は変わらず、約12年で回収が可能となります。例えば、仮に10年間の繰下げをして75歳から年金を受給する場合には、そこから12年後の87歳が損益分岐点となる年齢になります。したがって、もし確実に87歳以上長生きすることがわかっていたら、10年間の繰下げをして75歳から年金を受け取ることが有利になります。繰下げ受給の注意点さかのぼり請求可能年金の繰下げを請求する場合に、通常は年金請求しない状態にしておくことになり、何歳から繰下げして受給するなどという予約は行いません。66歳を過ぎた以降であれば、いつでも年金の繰下げ受給の請求をすることが可能となります。ここで重要なポイントがあります。当初、年金繰下げ受給をするつもりで、年金の請求を行わずに放置しておき、68歳になった時点で、やはり繰下げは行わないでおくことも選択可能です。その場合には、年金の請求時に繰下げの申し出をせず、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することができます。したがって、繰下げ受給待機中の人が68歳になった時点でがんになったことがわかり余命1年などと宣告された場合には、その時点から繰下げ受給の申請をするよりも、65歳の時点にさかのぼって繰下げ増額されない年金を一括して受け取ったほうが有利となります。なお、繰下げ受給をせず、さかのぼって受け取ることができる最大期間は5年間となりますので注意が必要です。このさかのぼり受給にはもう一つ注意点があります。それは、もらった年金は所得になり、課税されるということです。課税の方法は、過去の各年分の所得計算に反映され、過去にさかのぼって各年分の雑所得が増えることになります。過去に確定申告をしていなかった場合には、確定申告をしなければならない可能性が出てきます。過去に確定申告をしている場合には、修正申告をしなければならない可能性が出てきます。そして過去の各年度別に追加税額が発生した場合には、ペナルティとしての延滞税が課税されることがあります。インフレとデフレの影響2020年代に入り、コロナ禍を契機として世界的な物価高、インフレ傾向となっており、日本でもインフレが進行しています。上記の年金繰下げの損益分岐点の大前提として、デフレ、インフレ、金利の影響は考慮に入っていません。もし、日本も一部の外国のようにハイパーインフレの状態になり、消費者物価指数が年率8.4%を超える状況になった場合には、繰下げによるメリットはなくなり、少しでも早いタイミングで年金受給するほうが有利となります。繰下げ待機中に死亡の場合繰下げ請求は、本人が死亡したときは遺族が代わって行うことはできません。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。この点を考慮すると、制度設計としては10年間の繰下げができますが、繰下げ期間は、最大5年にとどめておいたほうがよいかもしれません。繰下げ受給で加給年金・障害年金・遺族年金はどうなる?加給年金との関係老齢厚生年金を受給する際に、併せて受給できる加給年金という制度があります。65歳になった年金受給者に扶養家族である年下の配偶者がいた場合に、その配偶者が65歳に達するまでの間、当該配偶者分として加給年金という追加的な年金が支給されることになります。その加給年金の金額は年間約40万円程度になるため、5年間で約200万円の追加的年金を受け取ることになります。ただし、繰下げ待機中で老齢厚生年金が支給されていない人には、この加給年金は支給されません。また、加給年金部分には繰下げによる増額などもありません。したがって加給年金を受給見込の方は、老齢厚生年金については繰下げ支給しないほうが有利であると考えられます。障害年金・遺族年金との関係66歳に達した日以後の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合や、障害年金を受給することとなった場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。
2025年04月23日
閲覧総数 13
-
7

<1449> 60代・ひとり暮らしになって始めた7つの習慣
60代・ひとり暮らしになって始めた「7つの習慣」。好きなことに集中できてストレスも減った昨年5月に長年一緒に暮らしていた夫と別れてひとり暮らしを始めた、カナダ在住のミニマリストで、ブロガーの筆子さん(現在60代)。ひとり暮らしを始めたことをきっかけに、自分の時間と空間をより充実させるための習慣を取り入れることにしたそうです。今回は筆子さんが始めた7つの習慣について紹介します。1:仕事の時間をしっかり決めた私は在宅でブログを書いています。以前から、毎日To doリストは書いていましたが、離婚をしたことで、以前よりも集中できる環境が整い、引っ越してからはもっと明確に仕事の時間を決めるようにしました。これにより、日々のリズムができ上がり、以前よりも仕事の量が増加。さらに、自分の時間も確実に確保できるようになりました。基本は週6日、30時間~35時間働き、1日記事を2本書いています。2:家事は週末にまとめてする掃除や洗濯は週に1度、週末に行っています。洗濯は土曜日の朝、掃除は日曜日の午後にすることが多いです。洗濯は、洗濯機と乾燥機がやるので、放っておいて問題ありません。下着やソックスは手洗いすることも増加しました。掃除は、ひとり暮らしだとそんなに汚れず、日頃から汚さない工夫をすれば、週に1度でも大丈夫です。ふだんは汚れが目立つところだけ、ふいたり掃いたりします。生活をシンプルにし、家具を含めて少ないもので暮らせば、散らかっても片づけるのは簡単で、掃除そのものもラクです。3:タスクはデジタルで管理するもともと私はアナログの紙やノートを使うことが好きでしたが、効率化とものを増やさないことを考え、数年前からはペーパーレスを目指すようになりました。また、筋金入りのアナログ派だった夫と別れたことも、デジタル化が進んだ要因です。去年、手もちの紙のノートを使いきってからは、日々のタスクはGoogleカレンダーとデジタルプランナーを中心に管理しています。カレンダーはPCで、プランナーは手書きとデジタルの両方の利点を享受できるタブレットを使っています。4:食事のメニューを定番化以前から、食事のメニューは同じものをローテーションしていましたが、ひとりになったことで、この傾向がさらに強まりました。朝はスープ、目玉焼きとホウレンソウのソテー、サツマイモが定番です。昼と夜は玄米ご飯にチキンかサーモン、もしくは魚の缶づめに、つけ合わせの野菜とみそ汁というメニューを繰り返しています。同じメニューだと飽きると思うかもしれませんが、たとえばスープは味つけを変えることで、飽きることなく楽しめます。スープはおいしく、残り野菜を処理できるので気に入っています。5:買い物はすべてデリバリー引っ越した場所はクルマがないと不便なため、食品や日用品はすべてデリバリーですませています。たとえば、食材はオーガニックスーパーで週に1度届けてもらっています。米といつも飲むハーブティー、トイレットペーパーはアマゾンのサブスクリプションを利用。アマゾンで取り扱っていないものや、割高な商品は、娘に頼んで買ってきてもらうこともあります。すべてデリバリーにすると、自分で買いに行くよりもお金がかかるかもしれません。しかし、店舗に行くと、どうしても店内のディスプレイに惹(ひ)かれて、予定外のものを買ってしまうことや、セール品に誘惑されることがあります。買い物に使う時間が浮き、余計なものを買わずにすむというメリットもありますよ。6:電子レンジを使わない現在住んでいる家には電子レンジがないため、レンジを使わないことにしました(カナダの賃貸住宅は家電が備わっていることが多いです)。その理由は、レンジを買うとキッチンのカウンタースペースを取られるし、庫内の掃除など余計な家事が増えるから。ご飯は一度に3合炊き、すぐに食べない7食分を冷凍しています。以前は冷凍ご飯の解凍にレンジを使っていましたが、今は蒸しています。ご飯はレンジを使うより蒸した方がおいしいです。蒸す時間は10分。その間におかずを用意しているので、とくに問題はありません。レンジを使わないほうが、全体的にヘルシーな食事になると思っています。7:シビアに家計管理するこれまでもお金の管理はしていましたが、ひとり暮らしを始めてからは、生活費を自分ひとりで稼がなければならないため、よりシビアに数字をチェックしています。昨年まではスプレッドシートを使っていましたが、今年はタブレットで手書きに変更しました。スプレッドシートに数字を打ち込むのは、クレジットカードを使う感覚に似ていて、お金を使っている実感が薄くなってしまいます。しかし、手書きをして電卓で計算すると、「ああ、お金が出ていってる」とひしひしと感じます。月初には、手もちのお金をすべて計算し、前月の残高と比較しています。以上、ひとり暮らしを開始してから取り入れた習慣を紹介しました。ひとり暮らしのメリットは、自分のペースで暮らせること、そして生活空間を完全にコントロールできることです。私の場合、好きなことに集中できるようになり、以前よりもストレスが減って日々の満足度も高まりました。
2025年04月24日
閲覧総数 44
-
8

<667> From The Beginning Until Now by Ryu
2021年08月07日
閲覧総数 51
-
9

<813> 電車内での「リュックの持ち方マナー」
手に持つ? 前に抱える?電車内での「リュックの持ち方マナー」鉄道会社8社に見解を聞いてみた「リュックって、混雑時の電車内では前に抱えるもんじゃなかったの?」「いつの間に、リュックは手に持つことに……?」最近SNSなどがザワついたきっかけは、3月1日から関西の鉄道事業者19社&局による共同マナーキャンペーンで「手荷物の置き方、持ち方」をテーマとしたポスターが掲出されたこと。「手荷物の持ち方・置き方は、まわりの方にご配慮ください」とした上で、「大きな荷物は網棚に」「リュックは手に持って」「手荷物はヒザの上に」と呼びかけていたのだ。 ちなみに、’18年のキャンペーンでは「前に抱えて」という表現が使われていたそうだ。にもかかわらず、変更した理由について、関西鉄道協会は各種メディアに対して「身体的な理由など、何かしらそれができない人がおり、前に抱えられない人はどうしたらいいかと指摘されることがあった」と説明している。 繰り返すが、これは関西の鉄道事業者19社&局によるキャンペーンでの呼びかけだ。 しかし、もしかしたら東京をはじめ、通勤通学で満員電車が生じる都市部ではすでに「リュックなどの荷物は前に抱えるのではなく、手に持つ」ことが、今はマナーになっているのだろうか。 東京の鉄道会社8社(京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、西武鉄道、東武鉄道、東京都交通局、JR東日本、東京地下鉄)に緊急アンケートを行った。 ◆東京では「リュックは前に」が主流 リュックなどの荷物について、「前に」という表現を用いて呼びかけているのは、京王、小田急、西武、東武、JR東日本、東京地下鉄。そのアナウンス方法と具体的文言も聞いた。 「車内に『リュックは前に』『スリ等の防止にも役立ちます』といった ステッカーを掲出しています」(京王電鉄) 「弊社ではリュックやカバンなどのお荷物を前に抱えてご乗車いただく か、座席上の棚をご利用いただくようにお客さまにアナウンスしてお ります。 また、特に決まり(ルール)は設けておりません。 理由につきましては、お荷物を背負うことで他のお客さまと接触する こと、混雑状況によっては背負っている本人の身動きが取れなくなる 恐れがあるためです」(小田急鉄道)「リュックなどのお荷物は、周囲のお客さまにご配慮いただくべく、 体の前に抱えるか、網棚をご利用いただくようマナーポスター等でご 案内しています」(西武鉄道)「リュックについては、手に持つか、前に抱えていただくよう案内して います。 理由については、背負ったままの状態では他の方に十分な配慮がなさ れないためです」(東武鉄道) 「列車内混雑時、リュックサックを背負った状態でのご利用は、周囲の お客さまのお身体にあたり、思わぬお怪我やトラブルに繋がる恐れが ございます。 また、列車内混雑時において、リュックサック等の手荷物品は手でお 持ちいただいたり、お身体の前に抱えていただくことの他に、網棚に お乗せいただきたく存じます。 駅や列車内では混雑状況に応じて 『混雑時は、大きなお荷物は荷物棚をご利用ください。 また、リュックサックは、前に抱えるか、手にお持ちください』 と案内しております。 なお、すべてのお客さまに安心して快適に車内をご利用いただけるよ う、お客さま同士でもお互いにご配慮いただきたいと考えております」 (JR東日本)乗客同士のトラブルは報告されていないが…一方、「前に」抱えることは具体的に掲げず、配慮を呼び掛けていたのは東急と東京都交通局、東京地下鉄。 「お客さま同士でご配慮いただくことをお伝えする目的で、車内アナウンス(乗務員の判断等による)により、お客さまへ呼びかけを行っています。リュックに限定せず『お荷物』という表現としています。※「アナウンス文案『混み合いました車内ではお荷物により周りのお客 さまのご迷惑となりませんようにご配慮ください』」(東急電鉄) 「統一した『きまり』は設けておりませんが、他のお客様のご迷惑と ならないよう配慮をお願いする場合はあります」(東京都交通局) 「弊社では車内環境を考慮し放送内容を都度検討しており現在は以下 の内容にて車内状況をみて必要に応じ肉声及び自動放送にて実施し ております。『リュックサックに関する放送』をお客様にお願いい たします。 リュックサック等(など)大きな鞄をお持ちのお客様は、手にさげ てお持ちになるか、座席上(うえ)の荷物置きをご利用ください」 (東京地下鉄) ただし、これは「お客様の乗車法を否定するものではなく、混雑する車内を快適に、 また、一人でも多くの方にご利用いただくための放送であることをご 理解頂ければ幸いです」「車内の状況に応じて行う放送であり、リュックを背負っている方を指 摘したり、注意するための放送ではありません」とその意図を説明する。 ちなみに、満員電車の中で荷物の持ち方について、乗客同士のトラブルなどの報告があるかという問いには、以下の一部を除き、「特にない」という回答がほとんどだった。 「トラブルとなった事例は関知しておりませんが、車内でリュック等お 荷物の持ち方・置き方に関してご意見をいただくことはあります」(東急電鉄) 「リュックの持ち方についてのご意見は年間で10件程度頂戴しています が、トラブルにつながった件数については把握していません」(東武鉄道) 「列車内混雑時におけるリュックサックのご利用マナーについて、お客 さまからご意見をいただくことはあります。 今後も引き続き、お客さまのご利用状況やご意見等を踏まえながら、 ご利用マナーに関する啓発や周知に取組んでまいります」(JR東日本) 「’22年度中に寄せられた『車内でのリュックのマナーに関するご意見・ ご要望』は40件あり、『混雑した車内でのリュックは前に抱えるよう に周知して欲しい』『前に抱えるのではなく手に持つように周知して 欲しい』などの持ち方に関する様々なご意見が寄せられました」(東京地下鉄株式会社) 東京では今もリュックを「前に抱える」ことをマナーとする鉄道会社が過半数。また、大きなトラブルに発展しているケースは少ないようだが、「ご意見・ご要望」をわざわざあげるレベルに苛立ちを感じている人がいるのは事実。 かと言って、東京では現時点で少なくともリュックの持ち方について、鉄道会社による呼びかけは統一されていない。上記の鉄道会社ごとのアナウンスに従うのが正解というわけでもない。 そうなると、余計なトラブルを避けるために、リュックは結局、「前に抱えるのか」「背負ったままで良いのか」「手に持つべきなのか」を全鉄道会社統一でルール化してほしいと思う人もいるだろう。 しかし、仮に「前に抱える」をルールとすると、妊婦や赤ちゃん連れ、負傷者や高齢者など、前に抱えるのが困難な人もいるだろう。その一方で、例えば進学校の高校生のリュックなどは肩に食い込み、あざができるほどの凄まじい重量で、「手に持て」というのは現実的に不可能だ。もちろん背負ったままだと、振り返った際などに、周囲の人を弾き飛ばす可能性だってある。 少なくとも「前に抱える」「手に持つ」など、マナーやルールを守っていればOKなのではなく、大切なのは、スマホやお喋りに夢中になってしまい、周囲が見えなくならないように気を配ること。当たり前だが、リュックの持ち方云々も、目的は公共の場で多くの人が気持ち良く過ごせるようにするための呼びかけだということを忘れずにいたい。
2023年07月27日
閲覧総数 758
-
10

<1450> 身近な人が亡くなった後の絶対NG行動
税務署が許さない「身近な人が亡くなった後」の絶対NG行動人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。 本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。 ●知らないと絶対損する! お金の話 本日は「相続と税務署」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。 本日のテーマは「税務署が葬儀用に引き出した現金をマークする理由」です。税務調査が行われた時に、相続が発生する直前に引き出した現金、特に葬儀用として引き出した現金については、税務署が実際の使い道を徹底的にマークしてきます。ここは相続税の申告漏れにつながりやすい、怖い論点がたくさん詰まっていますので、今日はどういった点に注意しなければいけないのかをお話しします。 まず、葬儀費用の取り扱いということで、相続税の計算上、葬儀費用はどのように扱われるのかを見ていきます。相続税の計算は、亡くなった方の財産から一定のものを差し引いて計算しますが、葬儀にかかった費用は差し引くことができます。そのため、財産額から葬儀費用を引いた差額部分が相続税の対象になります。これが前提となるお話です。 ここから本題に入りますが、葬儀費用のために引き出したお金がポイントになります。相続が発生すると銀行口座が凍結されてしまうことは有名な話です。銀行が亡くなった事実を知ると、その方の口座は凍結され、誰も引き出せなくなります。これを避けるため、多くの方が「お父さんがもう危ない、葬儀費用を出せなくなるかも」と思い、相続発生直前に急いでATMからお金を下ろすケースが世の中でよくあります。 しかし、この行為は税務署が徹底的にマークしています。なぜか。その理由を詳しく見ていきましょう。誤解しないでいただきたいのは、お金を引き出すこと自体は問題ないということです。お父さんの同意があれば問題はありません。ただ、気をつけなければいけないのは、相続税の申告上の扱いです。 具体例として、葬儀準備金を引き出したケースを考えます。相続開始直前、残高1000万円の通帳から200万円を現金で引き出すと、通帳残高は800万円、手元現金200万円という状態になります。その後、お父さんが亡くなった瞬間には「預金800万円+手元現金200万円」が存在していました。そして葬儀費用200万円をその手元現金から支払いました。 ●申告漏れに要注意! 相続税の申告上、葬儀費用は差し引くことができます。つまり、申告書には「葬儀費用200万円」として記載できます。しかし、それだけでなく、相続開始時点で手元にあった現金200万円も財産として申告しなければなりません。相続発生時点では預金800万円と現金200万円があったわけですから、それらを合計して1000万円、そこから葬儀費用200万円を引くことで、最終的に800万円が相続税の課税対象となるのが正しい計算です。 このように正しく申告すれば税務署からも「漏れなし」となります。しかし多くの方は、この現金200万円を申告しないミスを犯します。「もう葬儀で使い終わって手元に現金なんて残っていない」という感覚があるでしょうが、相続税は「相続が起きた瞬間」にいくらあったかで見るため、その瞬間には確かに現金200万円が存在していたことになります。申告しないと、結果的に財産が少なく申告され、税務署に「直前に引き出した葬儀用の現金は相続開始時点で存在していたはず」と指摘され、追徴課税となるケースが非常に多いのです。 以上から、相続開始直前に葬儀費用として引き出した現金は必ず相続税申告に含めてから、葬儀費用として差し引くことが重要です。 一方、相続開始「直後」に引き出した現金はどう考えるか。相続開始後、銀行はまだ亡くなった事実を知らないため、ATMで引き出せることがあります。これは税務上は問題ありません。亡くなった日の残高で申告して納税した後に引き出すお金なので、計算上問題はありません。ただし、民法上は他の相続人の同意なしに引き出すことは問題になる可能性があるので注意が必要です。 また、相続開始前に引き出した現金をすでに生活費や入院費などで使い切っていた場合は、その分は手元に残っていないので問題ありません。領収書がなくても、相続開始時に現金が残っていなければ申告はそのままで構いません。 まとめると、税務署が葬儀用に引き出した現金をマークするのは、相続開始時点で存在していたはずの現金を申告漏れするケースが多いためです。引き出すこと自体は悪くありませんが、相続税申告の際は手元現金として申告し、その後葬儀費用として差し引く、この手続きを忘れないよう注意してください。 年末年始が近づいてきました。親族で顔を合わせる機会がある人も多いかと思います。相続や贈与のことで家族と話し合う際、ぜひ参考にしてください。 (本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加編集 を行ったものです)
2025年04月25日
閲覧総数 28
-
11

<1452> 65歳以上高齢者の6~7人に一人が「うつ」
じつは「65歳以上高齢者」の「6~7人に一人」が「うつ」になっているという「衝撃的な事実」うつになりやすい高齢者少し古いデータですが、「日本老年医学会雑誌」によると、六十五歳以上の人の六パーセントに大うつ病(本格的なうつ病)があり、小うつ病(いわゆるうつ状態)を入れると、一五パーセントに達するそうです(二○一○年)。つまり、高齢者は六~七人に一人がうつに陥っていることになります。なぜこれほど多くがうつになるのでしょう。それは高齢になると、いろいろ不愉快なことが増え、忍耐力も衰え、将来の希望も持ちにくくなるからです。まず、年を取ると心身の機能が衰え、身体が弱って、それまでできていたことができなくなります。視力低下、聴力低下、味覚低下、筋力低下、反射力低下、性機能低下で、見たり聞いたり食べたりの楽しみが減り、活動性も落ちて、不自由と不如意が増えてきます。脳の働きも衰え、記憶力低下、判断力低下、順応力低下、集中力低下、持続力低下、忍耐力低下と、低下のオンパレードで、物忘れが増え、勘ちがいも増え、判断を誤ったり、物事が決められなかったり、応用がきかなかったり、ひとつのことが続けられなかったり、ひとつのことにこだわったり、すぐにキレたり、些細なことで苛立ったりもします。さらには、退職して社会的役割が低下すると、出番がなくなり、人から注目されなくなり、年寄り扱いされて不愉快になり、逆にいたわってもらえなくてガッカリしたり、邪魔者扱いされて腹が立ったり、敬ってもらえなくて悲しかったりもします。加えて、病気の心配、寝たきりの不安、家族との別れ、忍び寄る孤独、そして最後は死ぬことへの恐怖もあります。いずれもイヤなことばかりですが、ふつうに考えて、だれにでも起こり得ることばかりです。それをあり得ない不幸に見舞われたように感じるから、うつ状態に陥るのです。もちろん、長生きは悪いことばかりではありません。仕事や義務から解放され、ゆったりとした時間をすごし、これまでの人生を振り返ったり、子どもや孫の成長を見守ったりして、喜びを感じることもできます。しかし、経済的な余裕のない人は、自由な時間があっても好き放題には楽しめないでしょうし、お金があっても寝たきりでは動けませんし、お金も健康も不自由なくても、することがなければ何をしていいのかわからず、退屈のつらさを味わいます。人生を振り返るといったって、まったく悔いのない人生をすごした人は少ないでしょうし、子どもや孫の成長を見守るとしても、関係が常に良好とはかぎらず、子や孫の進学、就職、結婚などに心配や不満があったり、病気やひきこもりや家庭内暴力、不登校やイジメ、非行など、さまざまなトラブルに悩む人もいるでしょう。長生きには喜びや楽しみもある代わりに、思い通りにならないこともあるのが現実です。いつまでも元気で若々しくというのは万人の望みでしょうが、そればかりに気持ちが向いていると、老いの現実が受け入れにくくなってしまいます。老化による衰えを認めざるを得ない状況にぶちあたったとき、心の準備がないと、苛立ちや落胆、納得できない思い、嘆き、悲しみ、憤りなどで精神が疲弊して、気づけばどっぷりうつに浸っているということになりかねません。ですから、長生きに伴って起こり得る不具合を、前もってイメージしておくことが大切です。それもできるだけ多く、できるだけよくない状況を想定するのがよいでしょう。イヤなことを考えるのは、楽しくありませんし、それこそうつのきっかけになると思う人もいるかもしれませんが、能天気なまま日々を送っていることのほうが危険です。長生きをすればするほど、さまざまなイヤなことが押し寄せてくるからです。「うつ」とはどういう状態か自分がうつなのか、それとも単に気分がふさいでいるだけなのか、不安になる人もいるでしょう。医学的には「うつ病」の診断基準は次のようになっています。(1)一日中、気分が落ち込む。(2)何事にも興味が湧かず、喜びを感じられない。(3)食欲がなくなり、体重が減る。(4)よく眠れない。(5)焦って落ち着かず、じっとしていられない。または身動きが取れない。(6)疲れやすく、気力が出ない。(7)自分には価値がない、何かあると自分が悪いと思う。(8)物事に集中できず、ものを決められない。(9)この世から消えてしまいたいとか、死にたいと思う。このうち(1)または(2)を含む五つ以上に当てはまると、うつ病と診断されます((3)と(4)については逆の場合、すなわち過食で体重が増えるとか、寝すぎるということも含まれます)。ほかにもくよくよして、何もできず、一日ぼーっとして何も考えられないとか、頭が働かない(「思考渋滞」といいます)とか、元気が出ず、嬉しいことがあっても気が晴れないとか、ほとんど口もきかないなどの症状もあります。また、本来のうつ病の特徴として、「日内変動」と「自責傾向」があります。日内変動は、午前中に症状が重く、午後から夕方にかけてやや軽快するというものです。午前中にはまた一日を生きなければならないという精神的な負担があり、夕方近くになると、やれやれ一日が終わるという安堵があるせいだと考えられます。自責傾向とは、(7)にもある通り、悪いことはすべて自分の責任だと考えて、罪悪感を抱くことです。いずれも高齢者のうつにも共通していますから、逆に言うと、朝から晩までずっと調子が悪いと言う人(日内変動がない)や、調子が悪いのをだれかのせいにする人(自責傾向がない)は、うつ病ではないことになります。本格的なうつ病になると、ほとんどしゃべらなくなりますから、愚痴を言い続けている人はいくら憂うつそうでも、うつ病ではないことになります。厳しい言い方になりますが、そういう人は病気ではなく、性格の問題です。さらに連載記事<長生きして「心安らかにすごす」のはこんなに難しい…「高齢者」が「うつ」を発症する「8つのきっかけ」>では、高齢者がうつを発症するきっかけについて具体的に解説します。
2025年04月27日
閲覧総数 11
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 【山崎愛生(モーニング娘。'25)】ア…
- (2025-04-27 22:16:24)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- John Wetton - Walking on Air Vocal…
- (2025-04-25 00:00:15)
-
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- 還暦とは思えない!
- (2021-02-28 20:19:39)
-







