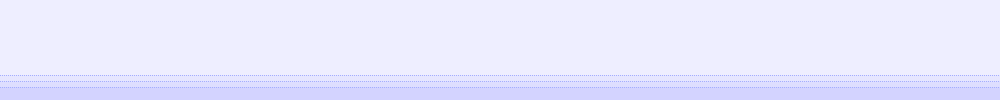【蝉のおしっこ】---(掌説5)
奈々が、庭の隅の柿の木に、そろりそろりと近づいている。まだ幼稚園のそのあどけない姿が可愛らしい。柿の木では、アブラゼミがジワジワ、ジワジワと、暑苦しい声をあげている。
縁側でその様子を見ていた奈々の祖母が、声をひそめて嫁を呼んだ。
「ちょっと、きてみてごらん。奈々が蝉を捕ろうとしているよ。うまく捕まえられるかねえ。」
「あののろまな奈々が? 本当、手を蝉に伸ばして。奈々に捕まる蝉なら、あきれたのろまな蝉だわねぇ。」
「まあ、見ていましょうよ。」
奈々は、二人が見ているのに気づかないほど、気持ちを蝉に集中している。小さな足が、草をじわりと踏み締める。
蝉の背中まであと30センチほどというところで、彼は「ジ、ジ……」と鳴き止んだ。
はっとしたように、奈々は手の動きを止める。時間が止まったように、奈々の動きがぴたりと止まる。
蝉は、幹の表面を、じりじりと横に回り込む。
奈々の時間も開放された。蝉の動きに合わせて、小さな手がスイと動いた。さらに手が蝉に近づいた。あと15センチほどだろうか。
「あんまり奈々の動きが遅いもので、蝉が気づかないのかしら。」
「うまく捕まえられるかもしれないねえ。捕まえたら、喜ぶだろう。」
祖母は、顔をくしゃくしゃにして喜ぶ孫の顔を思い浮かべた。きっと、ジャウジャウと騒ぎ立てる蝉をしっかり握り締めて、家に駆け込んでくることだろう。
「羽を広げたら、奈々の小さな手に入らないんじゃないかしら。もうあのあたりで、パッと捕まえちゃえばいいのに。早くしないと、逃げちゃうじゃない。見てられないわね。」
「そこがあの子の善いところさね。案外うまく捕まえるよ、きっと。」
奈々は、蝉に手を伸ばすにつれて、その大きさに気づいた。
『蝉って、こんなに大きかったんだ。木の上で鳴いているときは、随分チッチャイと思ったのに』
片手で捕まえることができるだろうか。
『エイッ、掴んじゃえ』
目をつぶって、思い切って手を蝉に向けて突き出した。
指先が、蝉の背中に触れた。と思った瞬間に、蝉は堅く乾いた羽を奈々の柔らかい手のひらにぶつけて、バシッと飛び立った。奈々は驚いて手を引いた。
彼は飛び立つときに、「ジイッ」と短く一声鳴いて、ちゃっと彼女の頭におしっこをかけて逃げて行った。
「ああ、惜しい。もう一寸だったのに。」
母の大きな声で、奈々は二人が見ていたことに、初めて気づいた。恥ずかしそうにうつむいて草を蹴っていると、祖母が声を掛けてくれた。
「奈々ちゃん、すごいね。惜しかったけど、大冒険だったね。また今度頑張ってごらん。そして今度はきっと捕まえて、おばあちゃんに見せてね。」
奈々はおずおずと縁側に歩み、祖母の横に座って、その優しさが伝わるような腕にもたれかかった。いつも優しい気持ちで見守ってくれる祖母が、奈々は大好きだった。
公園に出かけると、祖母はスーパーマンだった。奈々が知らないことを、いろいろやって見せてくれる。ススキの葉をちょっと破いて、中心のスジをスイッと飛ばして見せてくれたことがある。まるで魔法を見るような気持ちがした。タンポポの茎をちぎって口にくわえたと思ったら、プーッ、プーッと大きな音をだす。
「ねえ、私にも作り方を教えて。」
「ほらこうやってね、茎の端を少しつぶしてから吹いてごらん。長さや太さが違うと、音の高さも違うんだよ。」
「ふうん、簡単なんだ。」
タンポポの音は、奈々の小さな手でも、作り出すことができた。
シロツメクサの花を集めて、レイを編んでくれたこともある。草の匂いが緑色に漂うような、ひんやりとした大きな輪を、奈々の首に掛けてくれた。その編み方は、おばあちゃんが子供のころに、おばあちゃんのお母さんに教えてもらったのだという。
奈々のお母さんは、そんなことを、奈々に教えてくれたことがない。
ナズナの種を破いて少しずつ垂らし、そっと振って耳を澄ますと、小さくカラカラと音がすることも、おばあちゃんに教わった。
ススキの葉で作った笹舟を、蛍が飛んだこともない公園の[ホタルの小川]に浮かべて遊んだこともある。
ホオズキの、夕日のように赤い実を取り出して、いつまでもいつまでも柔らかくなるまで揉んでから、中の白い種を全部取り出して、口に含み、キュッキュッ、ビュッビュッと鳴らして見せてくれたこともあった。
これは、幼い奈々にはどうしてもできなかった。白い種を真っ赤な夕日の中から出すときに、その夕日の口がどうしても破れてしまうのだ。
おばあちゃんにもらったホオヅキを口に含んでも、きれいな音が出ない。ぐちゅぐちゅと変な音がするだけだ。それでも、甘酸っぱくて少し苦いホオズキの味が、奈々は好きだった。
祖母は、自転車にも乗れないのに、お手玉が上手だった。3個のお手玉を、片手でひょいひょいと投げて遊んで見せる。やっぱりスーパーマンだ。
奈々が小学校の5年生になったときには、その大好きな祖母は、あまり外に出なくなっていた。時々蝉を捕まえて、
「おばあちゃん、ほら、私もう、いくらでも蝉を捕まえられるよ。」
と祖母に見せると、
「おや、えらいね。可哀想だから元気なうちに逃がしてやんなさいよ。ところで、あんたは誰だっけね。おばあちゃん家にも、あんたと同じくらい可愛い女の子がいるよ。」
などと、時々言うようになった。
齢をとって目が悪くなったんだと思って、
「私、奈々だよ。おばあちゃんの孫だよ。」
と教えてやる。
「そうかい、マゴマゴしちゃうね。家の子も奈々と言うんだよ。そっくりだねえ。」
なんて言っては、けらけらと笑う。
目が悪いにしては、変だ。昔は、太陽が笑っているように温さが伝わるような笑顔だったのに、最近の笑顔からは元気が伝わって来ない。
最近になって、ようやくホオヅキをうまく鳴らせるようになったのに、祖母にそれを知らせても、張り合いがない。
奈々は、[ホタルの小川]のあたりで、一人でホオヅキをキュッキュッと鳴らして、祖母と遊んだ昔を思い起こすことが多かった。
友達は、学習塾や勉強が忙しくて、外でほとんど遊ばない。家で遊んでいても、ゲームマシンばかり相手にしている。奈々も父に買ってもらったゲームがあるが、スーパーマンだった祖母に教えられた遊びが忘れられない。
● ● ● ● ● ● ● ●
ある日、奈々が遊びに飽きて帰ってくると、両親の話し声が聞こえた。
「おばあさんたら近頃は、私の顔が判らないときが多いのよ。それに、自分がどこに居るのかも判らなくなるみたいで、『奥さん、私はどうしてここに連れて来られたんですかね。主人はどうして顔を見せてくれないのかしら』なんて言うのよ。」
「おじいさんは、2年前に亡くなったじゃないか。あんなに悲しんだのに、それも忘れたって言うのかい。」
「奈々のことも、判らなくなるみたいよ。」
「俺のことだって、本物の自分の息子なのかって、疑うことがあるみたいだからな。」
「それはそれで、丁寧に優しく説明すると判ってくれてるみたいだからいいんだけど……。それよりも困るのが、おトイレなのよ。」
「そういえば、おまえ、最近愚痴ってたなあ。どうなってる?」
「おばあちゃん、あまり歩かなくなって、足腰が弱っちゃったでしょう。それなのに、おトイレは近くなっちゃったのよ。2時間おきに、呼ばれるの、私。家の仕事が、なにもできなくて。」
「だからって、俺が会社を休んでもどうなるってもんじゃないしな。」
「奈々が肩を貸して連れて行ってくれることもあるけど、いつも頼めるもんじゃないでしょ。それよりも大変なのは、間に合わなくなって、漏らしちゃうことなのよ。大騒ぎでパジャマやシーツを取り替えるんだけど、そんなに何枚もあるわけじゃないから、足りなくなっちゃうのよ。1日に3回も取り替えることがあるんだもの。」
「そうか。俺が会社に行っている間に、大変な悪戦苦闘をしているんだ。仕方がない、紙おむつを使ってもらおうか。」
「嫌がるわよ。誰がその紙おむつを着けてあげるのよ。他人にそんなことをされたら、恥ずかしいに違いないでしょ。あのお年頃の人は、プライドが高いのよ。」
「優しいようでも、お母さんは確かにプライドは高いよな。おまえがまず、自分で紙おむつを着けて見せたらどうだ。『つけ心地がいいですよ。お母さんもおひとつどうです?』なんて。」
「こんな時に、何を言ってるんですか。怒りますよ。といって、お義母さんを放っとく訳にはいかないし。」
「冗談は兎も角として、やはり紙おむつで納得してもらおうよ。俺が説得するよ。」
奈々には、紙おむつを着けたおばあちゃんなんて、想像もできない。今も少しは元気でいられるのは、何とかしてトイレに行きたいという気持ちがあるからだ、と思う。祖母のその意欲を奪ってしまったら、今よりももっとなにも判らなくなってしまうに違いない。
「お父さん、お母さん、おばあちゃんは私ができるだけおトイレに連れて行くから。おばあちゃん、軽くなったから、私が肩を貸すと歩けるのよ。」
紙おむつなんておばあちゃんが可哀想、と思う一心で、奈々は両親がいる部屋に飛び込んだ。
『私が昔、蝉を捕まえ損なって頭におしっこをかけられたときに、おばあちゃんは優しくそれを拭いてくれた。今度は私がおばあちゃんに優しくして、お返しをするんだ』。
© Rakuten Group, Inc.