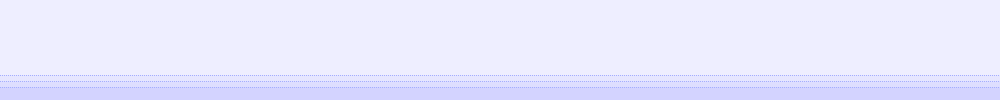新説【竹取物語】・・・3
k_tombowの『新説・竹取物語』
k_tombowの『新説・竹取物語』
k_tombowの『新説・竹取物語』
新説【竹取物語】・・・《11》
“燕の子安貝”と言い渡された『石上中納言』は、
最後になって『かぐや姫』の課題が緩んだかと、
どことなくホッとした気分も、味わっていた。
『さすがに姫ものぅ。先の皇子たちや大納言殿に、あまりにも過酷な注文を出して、
その結果が、いずれも“偽物”出現ということに、なってしまわれた。
そんなことで、求婚者は儂が残るばかりに、なってしもうた。彼の方々の評判をも、
貶めることになってしまい、姫ご自身としても、嬉しいことではあるまい。
その反省があって、この儂には、手を緩めてくださったものと思われるわいな。』
そのようなことを、いつまでも考えながら、
まるで“宝物”を手に入れてしまったかのような軽い足取りで、
中納言屋敷に戻った。
「殿は、いかがでおじゃいまいたか?」
「おうよ。此度は、お手のもんやないかと、嬉しゅうてなぁ。」
「そないな、ヤワなお言葉を、頂戴なさいまいたか?」
「ふふふ・・・」
「お心当たりでも、おありなさいまするかや。」
「あらいものかは。」
(何度も言うけど・・・)
(へえへえ、言ってくれはり・・・)
(いかがわしい『もっともらしい言葉遣い』を、やめれ!)
(雰囲気だけでも、楽しもうかと思うたに)
(まだ、気分が抜けていないな)
(なりきりやすい性格なもので)
(でたらめ言葉でも良いけど、もちょいと、解りやすく頼むわ)
(任せておくんなせえヤシ)
(いきなり、どこの言葉になったのやら)
(知らん)
(そればっかり・・・)
「では、これまでのいきさつとは違って、我等が出番は、なさそうでしょうや?」
「何の、そなた等のお力も、借りようぞえ。
探さねばならんことには、変わり無きよってな。」
「幻のような“お品”では、探しようも御座いませんが、解りやすければ、どうにか。」
「解りやすいも何も。」
中納言は、ここでおもむろに、『かぐや姫』から与えられた課題を、家人に伝えた。
「“燕の子安貝”とぞ。どうや? 解りやすかろうが。」
「殿のお顔が緩むは、察せまするわいなぁ。」
「さもあろう?」
「下々の我等でさえも、“子安貝”なら、話に聞いたことは御座いますれば。」
「さすれば、それを“燕”が所持していれば、それが“燕の子安貝”であろう。」
「ごもっともにございます。明日から探し始めても、間に合いそうですなぁ。」
「今宵は、ゆるりと休んで、明日から気張ってもらおう。」
翌朝から、情報収集が始められて、“これは?”と思われるところへは、
家人が駆けつけて、確認作業を急いだ。
しかし、思いの外に“燕の子安貝”は、本物が見つからなかった。
寄せられた情報を頼りに駆けつけた、家人からの報告では、
『燕の巣にあった“貝”は、“はまぐり”でした。』
ということも、多かった。
さらには、山里の農家から
『お探しの“お宝”が、我の軒先に作られた燕の巣に、入ってます。』
と、連絡を受けて訪ねてみると、確かに子安貝が巣の中に入っていたが、
問いつめると、農夫が放り込んで置いたものだということが、解ったケースもあった。
そんなものを、素知らぬ顔で届けても良かったのだが、中納言は、
『先の失敗例を、心して掛からねば、儂もアホの仲間入りやからなぁ。』
と、“本物”に、こだわり続けた。
かぐや姫が、“燕の子安貝”について、どこまで真偽のほどを知っているのか、
そこのところが解らない。
解らない以上は、妙な“出物”を持ち込まないに限る。
簡単に思えた“燕の子安貝”探しも、手詰まりになり始めていた。
期限の日が近付くに連れて、気軽に考えていた中納言にも、焦りの表情が見え始めた。
「なんや、大元で、心得違いをしていたんと、ちゃいますかなぁ。」
「と申されますと?」
「『燕の巣』やて、あてどなくどこぞの燕の巣を探し回って居るようやが、
そこらそんじょの『燕』とは、違うんやないかえ?」
「京では見たことがありませんが、断崖に懸かる『岩燕』なる巣かも、知れませんなぁ。」
「それ、それよ! どうしてそれに、早う気づかなんだろか?」
「『岩燕の巣』に絞って、探し直してみましょ。」
「そこまで絞り込めたなら、儂も自ずから動かな、いかんやろ。忙しゅうなりそうやわぃ。」
無数に懸かる“農家の燕の巣”を探し回る必要が無くなり、
“岩燕の巣”にターゲットを絞ったことで、
今度こそは、発見につながりそうで、期待がいや増した。
中納言も、『岩燕の巣がある』と噂されれば、自ずから出向いて、探し始めた。
そんなときに、せり出した断崖からふと見下ろした、その中程に、
『子安貝を抱えた岩燕の巣』が、見つけられたのである。
偶然の出来事であり、付近には供の者も居ない。
中納言に与えられた、天恵のように思われた。
中納言には、『かぐや姫』が巣の中で、手招いているようにも見えた。
「さあ、早うに私をここから、あなたの手に掬い上げて賜れ。」
潤んでキラキラと光るかぐや姫の目に見つめられるように、
課題を授けられた“あのとき”の姫の“鈴を転がすような澄んだ声”が、
今またここで、中納言の耳奥で囁き始めたように、石上中納言を、不安定な崖へと誘った。
『もう少し、あと僅か・・・』

新説【竹取物語】・・・《12》

『もう少し、あと僅か・・・』
その僅かな距離が、無限の彼方にあるようで、
またほんの一息、手をさしのべれば届きそうで・・・。
中納言は・・・。
かぐや姫の手を取って、天女の羽衣に包まれて天空を飛んでいる、
至上の幸福気分を味わっていた。
中納言の手には、幻と思われた“燕の子安貝”が、しっかりと握られていたのである。
『この幸せを、かぐや姫が喜び、迎えてくれている。ついに、姫は儂の妻になる・・・。』
“夢”と“幸せの子安貝”を握りしめたままで、天空を翔た中納言の“至福の時”は、
瞬くほどの“時”でしかなかった。
悲報は、中納言屋敷を駆け抜けて、『かぐや姫』の元にも、伝えられた。
「まさか、あのお言葉が、本当のことになるとは・・・。
あの『この中納言の、命に替えても』というお言葉が・・・。」
なまじ、実現可能な課題だったがために、無理をさせてしまった。
『憶良』は、この知らせが姫に届かないようにと、腐心したが、人の口に戸は立てられない。
『かぐや姫』は、漏れ聞いたこの知らせを知って、悲嘆にくれた。
いよいよ、自室から出ることが少なくなり、窓から月を見上げては、
嘆息を吐くばかりになった。
『憶良』も、市井の人々も、『姫の責めにはあらず』と慰めてくれるが、
気休めにもならなかった。
“子宝に恵まれる”と言われる“燕の子安貝”などと、思わせぶりな課題を与えたことが、
中納言に無理を強いることになったのではあるまいか。
『かぐや姫』の噂は、天皇の元にも、伝わっていた。
事の成り行きを見守っていた天皇だったが、意外な展開になり、
『かぐや姫』が籠もってしまったと聞くに及び、沸き上がる興味を、抑えきれなくなった。
「その者、“わらわ”の元へ呼び寄せることは、叶わぬかぇ?」
「『かぐや姫』なる者、“この世の者に在らざる”とぞ、聞こえまする。呼び寄せ賜うべきか。」
「して、何処ぞの者と言うか?」
「月より参り侍らす『姫』で、あらせらるると。」
「されば、“わらわ”が出向いても、不都合ではないな?」
「お待ちあれ。それにや及ぶ。我等が説き伏せる努めをば、致しましょう。」
「よい。明日にも、会いに参ろうぞよ。」
女帝は、かぐや姫との結婚に、興味があったわけではない。
多くの貴人を翻弄する、『かぐや姫』の“美貌”を、確認してみたくなっただけである。
月から参られた『姫』であろうとも、“倭の国”を混乱させるとあっては、
放置するわけにも行かない。
できるだけ早く、その処置を考慮しなければなるまい、と考えたのである。
「大君が、直接、行幸召されることは、いかがでありましょうや。」
疑問を呈する家臣に対して、持統天皇は、
「月より参らせられた“姫”にお会いするに、“日の本の皇”であるわらわが参る。
不思議は、どこぞにあろうや。」
と、進言を押し返した。
(ねえ、ちょっと良いかな?)
(また出たな! 今度は、何だい?)
(いいの?)
(解りやすく質問してね)
(ここで、“持統天皇”なんて、特定の実在人物名を出しちゃってさぁ)
(『竹取物語』の最初の誕生は、天武天皇~持統天皇の頃って言われているから、いいの)
(ここで『日の本の皇』って言うのは?)
(『新説』の『新説』たる部分を、ちょっとは見せないとね)
(いわゆる“でたらめ”?)
(そうとも言えない。『日本』という呼称は、持統天皇が使い始めたとも言われるようだから、
『月の王女』かぐや姫との対比には、ピッタリでしょ)
(『新説』だったよね。ここまでの、どこが『新説』なの?)
(大まかには、『5つの宝物』なんかは、ほとんど原型と同じだよ。
4番目と5番目の順序が、もしかしたら、逆。話の展開上、こんなふうにした)
(きっと、ほかにも『新説』はあるんだよね)
(あらすじ以外は、全部『新説』なんだけど、これからもっと、『新説』になりそうな予感)
(それならいいけど。18禁はどうなった?)
(古い言葉が多いから、断らなくても18歳以下は、読みたくもないでしょ)
(そう言う意味かぁ)
(まぁ、ね)
「憶良殿の佳き歌は、かねがね目にとめております。」
「畏れ多いお言葉、申し上げることもなく・・・。」
突然に天皇の訪問を受けて、『憶良屋敷』では、上を下への大騒ぎになった。
「急な決定で、断りもなく、申し訳ない。」
「勿体ないお言葉。このようなあばら屋に、お越しくださるとは、
思いも及びませぬ事でありますれば、
どのようにお持てなしを致さばよろしいのか、皆目・・・。」
「よい。此度の目当ては、月より参らせ賜うと聞き及ぶ、『姫』にお会いすることである。」
「お耳を汚して参らせるかと存じ上げまするが、姫は、石上中納言殿の一件以来、
どなたにもお会いしません。」
「ふうむ・・・。」
すかさず従者が、言葉を挟んだ。
「日の皇が、月の姫にお会いしたいと、おみ足を運ばれ申した。いかが?」
「いかにも。そのお言葉を、姫に伝えましょう。」
憶良が応じて、天皇とかぐや姫との会談が、実現した。
天皇とかぐや姫との会談は、山の端に陽が隠れるまで、続けられた。
やがて姫の部屋を出てこられた天皇は、
「話は、あいわかった。確かに、姫はこの世界の者に非ず。
固持なされて、理由は確かめられなかったが、なにやら深い曰くがあるような。」
「お察しのほど、痛み入りまする。」
「憶良殿が宝である。大事になされよ。追って、沙汰を伝えましょう。」
「なにとぞ・・・。」
“お手柔らかに”の言葉を飲み込んだ憶良だった。希望などを、伝えられる立場にはない。
● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★
天皇の決断は、早かった。
数日後には、『憶良』に沙汰が下された。
『身分の貴卑を問わずに、あまたの求婚を断り続けるは、
姫が月より参らせた意味以上に、深く意図することがありそうな。
然れども、それによって生じた此度の災難は、
姫の呵責には能わず。
とは雖も、このまま都に留まらせ置くには、さらなる騒動も、予見されよう。
ついては、姫は生まれ故郷へ、お帰り願うのが相応しかろう。
従者に土産を持たせるので、それをお持ちになって、『古き竹の里』へお帰り戴くように。』
天皇の従者が、この通告とともに、牛車一杯の宝物を、憶良屋敷へ届けた。
天皇の、四囲を治めるための配慮が、憶良には感じられた。
否応を言っている場合ではない。
出立を“次の満月の夜”と決めて、『筑紫国』への旅立ちの準備を始めさせた。
都の若者たちの間には、
“『かぐや姫』がまたもや、手の届かない遠国に去ってしまう”という噂が、
一気に広まった。
どうにかして翻意させようと、嘆願運動まで沸き上がったが、すでに時は遅し。
『かぐや姫』の意志でも、『憶良』の考えでも、
この決定を変えることはできない段階まで、進んでいたのだ。
彼らは、“天皇の決定である”ことまでは、知るよしもない。
『姫が月に帰るときが近付いている』という事実だけが、広まっていった。
そして、その“満月の日”が、訪れた。
都の若者たちは、仕える手の者を武装動員して、姫を連れ去ろうとする『異界の者』を、
阻止しようと試みた。
だが、去りゆく『かぐや姫』一行に縋って嘆く『憶良夫妻』が、盾のような具合になり、
矢を射かけることもできなかった。
その『迎えの使者たち』は、憶良の従者たちと、天皇から遣わされた、
護衛の一行だったのである。
満月に照らされた牛車の一行は、黄金の車を煌めかせて、静かに、周囲を圧しながら、
山の端に、消えていった。
一行が消えた山頂には、昇りかけた満月が、
この世のものとは思えないほどに、巨大な姿になって、
『かぐや姫一行』を、包み込んでしまったように見えた。
まさに“かぐや姫は月に帰った”ように、見えたのである。
憶良屋敷の『かぐや姫の部屋』には、憶良夫妻に宛てられた感謝の手紙が、
一通だけ置かれていた。
文机の上で、今しも昇った月の光に照らされ、主の想いを含ませて・・・。
憶良夫妻は、その手紙を開く気力も失せて、
姫が去ったあとの部屋に、ぽつんと、並んで座っていた。
夢やぶれた『4人の求婚者たち』にも、
『かぐや姫』が月に去ってしまう噂は、伝わっていた。
が、今更、行動を起こす事はできない。
4人は、並んで満月を見上げて、それぞれの『過ぎ去った夢』を、偲んでいた。
(はい。めでたしめでたし・・・と)
(勝手に終わらせるな)
(終わりじゃないの?)
(原作では、こんなところで終わったケースもあったみたいだけどね)
(だから、終わりじゃないの?)
(ここで終わったら、『新説』でも何でもないでしょう)
(今まででも、新説と言えなくもなかったと思うけど)
(だって、まだ『オチ』もなければ、『ハッピーエンド』にもなっていないでしょ)
(ハッピーエンドになるんだ? もう、いい加減に終わりにしようよ)
(もうちょい。あと・・・3回分くらいかなぁ)
(長すぎて、ダレちゃう)
(あと3回は、短めにするから・・・)
(何を企んでいるんだか)
(『月光仮面』なんて、登場させないから、安心して)
(『月光仮面』は出なかったけど、『結婚仮面』が出たなんて・・・)
(深読みのしすぎ!)

新説【竹取物語】・・・《13》

都では、『かぐや姫』が月よりも明るく輝く牛車に乗り、迎えの者たちに守られて、
満月の中に飛んでいった、と噂された。
黄金の馬車は、まさに『月よりも眩しく輝く』気高い姫を迎えるに相応しい乗り物であり、
今まさに昇り切らんとする満月に向かって、峠を登る姫の一行は、
『月へ帰った』という表現が、みごとに相応しかったのである。
その行く手を阻止しようとした、都の武士たちが、矢を射かけることもできずに、
動きを封じられてしまったのは、傷つけることさえも畏れ多く感じさせる、
絢爛豪華な車の仕立てにあった。
天皇たちは、姫が都を去るときに、阻止行動に出る武士たちがいることを予測して、
戦わずにその動きを封じる手段は? と熟慮した上で、編み出した手法でもあった。
とにかくこのようにして、『かぐや姫』一行は、都を去って、南の故郷へと、向かった。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
親子の縁を切られて、『継男』の許に嫁いだ『清』は、残してきた娘の幸せを願いながら、
実父が孫娘を他人に託したという、その現実から逃れることができずに、
『継男』との子供を、もうけることがでlきなかった。
修行から帰った『継男』は、家業を継いで、仕事に精を出し、
何不自由ない生活ができるようになっていた。
ただ一つの不満は、愛する『清』との間に、どうしても子供ができなかったことである。
『清』は、指も触れさせない、ということではない。
だが、気持ちが乗っていないと言うべきなのか、“そのとき”になると、
素っ気ないほどに、『継男』のタイミングを、逸らしてしまう。
「焦らずとも、そのうちには・・・。」
と言ってくれる『継男』には、申し訳ない気持ちが募るが、無意識に身体が反応してしまう。
いや、拒否してしまうのである。
それでも『継男』は、『清』を気遣い、無理押しはしなかった。
(お? 久しぶりに『18禁』だね)
(・・・の、つもりなんだけど、際どい表現になってる?)
(拍子抜け。もっと過激に! なんて思うんだけど)
(ここから『過激』な想像力に辿り着けるのが、“大人の証明”にならないかなぁ)
(ならない・・・と思うよ)
(このくらいで諦めて、これを読んで、胸をときめかせてよ)
(今までで、一番難しい注文かも)
(父兄同伴で読む必要なんて、なさそうだね)
子供は作れなかったが、『継男』の両親も、『清』を厳しく責めることはなかった。
『清』が家柄の良い娘だ、ということが解っているからというだけでなく、
『継男』と同じように、心根の優しい両親だったのである。
しかしそれでも、家業を継がせる子供は、必要になる。
そこで、将来の家業が発展するような相手を選び、養子を迎えることになった。
『清』と『継男』がもうけた子供よりも、少し年長だったが、しっかりした子供で、
家柄も、『清』の出自と、釣り合いがとれるほどの、官僚の次男だった。
二人は、この男の子に、自分の子供と全く変わりなく愛情を注ぎ、
家業を教えながら、大切に育てた。
男の子も、竹のように真っ直ぐな、好青年に成長した。
やがて、この青年にも、方々の村から、縁談が持ち込まれるようになった。
だがなぜか、どうしてもうまくまとまらない。
そうこうするうちに、青年は20歳を過ぎていた。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『かぐや姫』の道中は、難行の連続だった。
輝く牛車は、盗賊の格好の目標になり、その危険を嫌う従者たちも、
少しずつ零れるように、宝物の分け前をもらい、それぞれの故郷へと、
離れて行った。
それでも、天皇から直接選ばれて護衛に付いた者たちと、
憶良が信頼を寄せて、護衛に付けた屈強な精鋭たちは、欠けることなく、
『かぐや姫』を、『筑紫国』へ送り届けた。
その後、ある者はそのまま『姫』の元に留まり、またある者は、褒美を手にして、
道中で知り合った娘の元へ、またある者は都へと、散っていった。
道中の苦難を物語るように、『姫』の牛車は、
汚れるに任せて、見る影もなくなっていた。
だが黄金作りの車は、召使いたちが磨くと、また元のような輝きを、取り戻した。
都を離れて、幾月が過ぎたことだろうか。
奇しくも、『かぐや姫』が故郷の丘に麓に帰ったときは、満月の夜だった。
『姫』は、この丘で遊んだ幼い日を、憶良夫妻に大切に育てられた、幾多の記憶を、
満月を見上げながら偲んで、一夜を明かした。
磨かれた牛車は、『姫の輿入れ』を想わせるほどに、満月の光りを滲ませている。
幸いなことに、憶良たちが住まいにしていた粗末な家屋は、
その後も住む人もなく、荒れてはいたが、
手直しをすれば、仮の住まいには使えそうだった。
『憶良』からの知らせは、先んじて『筑紫国』に届けられていたので、
住まいを探す必要はなかったのだが、『かぐや姫』一行は、まだそのことを知らない。
憶良の、ある意味で“粋な計らい”で、あったかも知れない。
『筑紫国』で、『姫』の一行を待ち望んでいた人たちは、
逐一、入国の状況を、把握していた。
『姫』の本質を知るために、敢えて遠くから見守っていたのだ。
筑紫に入った一行が、まず生まれ故郷に向かい、
古家に住み着く決意を固めたらしいことが、
『大伴旅人』にも、伝えられた。
「憶良殿が、見事な娘御に育てられたものよ。
都に於いては、若者どもが羨望の的だったと伝わるに、いかような性根に育ち居るかと、
気をもんで居ったが、見目麗しさを偉ぶることなく、古家を偲ぶとは、
なんと愛おしいことよ。」
「都で姫を娶らなかった者どもは、さぞや悔いて居ることでしょう。」
「さもあらん。憶良殿に替わって、わが娘として、大切に引き取ろうぞ。」
「しかしながら、姫のお気持ちもございますれば・・・。」
「“竹から産まれた姫”なれば、竹林の匂いと名月を楽しめる、
彼の屋敷こそが相応しいのかも知れぬ。」
「姫のお心をば、確かめると致しましょう。」
「彼の屋敷に住まうと言うなれば、心地よう住まえるように、
如何様にも力添えを惜しむまいぞ。」
「お心を、そのまま『姫』へ、お伝えいたします。」
『かぐや姫』が、幼い日のように、
貧しい建物の隙間から漏れ入る月の光を楽しみ始めてから、数日の後に、
『旅人』の使いが、『姫』の心を確かめるために、訪ねてきた。
古家は早くも、改修工事を始めていた。
憶良たちと姫が育った『古家』の佇まいは、そのまま残されて、
周囲の敷地に、従者と供に『かぐや姫』が住まう新居が、質素ながらも、
不足を生じない状態に、整えられようとしていた。
「お疲れは、取れ申したでしょうや?」
「故郷の空が、疲れを吸い取ってくれるようです。
懐かしさに、1日が惜しいほどに思われます。」
「それは、何よりにございます。ところで主人(旅人)よりの言伝でございますが、
もそっと町中に住まわれるお心は、有りやなしや? と。」
「この地は、わが(育ての)『親』でありまする、『憶良』が私を育ててくださった土地。
なれば、この地にて『実の親』が名乗り出るを、待ちたいと思いまする。」
「おう。『育ての親』をお待ちなさるとは、殊勝な。」
「都を離れるときに、『憶良』殿が、私に持たせてくださった“物”がございますれば、
それを手懸かりに、きっと『育ての親』が見つかるものと、確信しております。」
「その“物”とは、如何なるものでしょうや?」
『かぐや姫』は、道中でも肌身から離すことがなかった『匂い袋』を、取り出した。
「幼少より、私が懐かしい思いで、触れ遊びし“匂い袋”にございます。」
「思い起こせば、『姫』はこの匂い袋によって、『芳し姫』とも呼ばれておりましたことが・・・。」
「幼き時分のことなれば、そのような噂は、私は記憶しておりません。
しかしながら、『憶良』殿がこれを大切に保っておわしたは、
この日の来るを予見していらっしゃったからかと。」
「さもあらめ。では、『姫』の実の親御を求める手助けを、主からも為すようにと、
お言付けいたしましょう。」
『かぐや姫』が、故郷の竹林に近い古家に、居を構えたこと。
『芳し姫』の謂われに因む“匂い袋”を、今も大切にしていることは、
セットにして、田舎町の隅々までに、喧伝された。
その噂が広まるまでもなく、心波立つのを抑えきれない夫婦がいた。
(それって、誰よ?)
(ふん! 解っているくせに)
(実は、解っていた)
(だろう? 誰にだって、解るはずだよ。)
(そうね。だけど、これからの展開は? もうすぐ“最終回”だよね)
(あと2回か。まとめを考えていないもので、今日もまた、引っ張っちゃった)
(なぁんだ。“無責任”なだけか)
(実は・・・そうなの)

新説【竹取物語】・・・《14》

『かぐや姫』の“屋敷建設”は、順調に進んでいた。
都から持たされた資金は、路銀として消耗されたが、新居建設に使うためのゆとりは、
まだ残されていた。だが無尽蔵に、残されているわけではない。
供の者たちが、“生活資金”を稼ぎ出すようになっていたが、
都の暮らしのようには、贅沢はできない。
『かぐや姫』は気づいていなかったが、この暮らしぶりは、
都の『山上憶良』に、あらかじめ庇護を託されていた『大伴旅人』によって、
見守られていた。
姫の様子は、逐一『憶良』に知らされていたのだ。
『憶良』も、『旅人』がいるからこそ、安心して、『かぐや姫』を送り出したのである。
屋敷建設が進むうちに、大工等に混じって、内装工事の職人も、
出入りを始めた。『姫』が筑紫入りをしてから、1ヶ月もたたない頃のことだった。
この年になって2度目の麦の穂が、蒼いさざ波を平地にうねらせて、
屋敷を緑の風で、包み込む季節になっていた。
このころ、“ある男”が、屋敷に出入りを始めた。
内装を仕上げるために、屋敷の様子を確認に来たのである。
男も、『かぐや姫』の噂は、聞き知っていた。
その男は町の職人で、家業を継ぐ、評判の『腕のいい男』だった。
成長するにつれて、男っぷりに惚れた女性たちから、親や縁者を通じて、
数多の縁談が持ち込まれていた。
世間は彼を、『満弦(みつる)』と、親しみを持って呼称した。
数多の縁談を断りはしているものの、円い人柄は、誰にも好まれたのである。
“月にたとえれば、上弦でもなく、下弦でもない。弦が満つるがごとくに、
丸く引き絞られたような・・・”
ということで、このように呼ばれたのである。
その若い男は、親の『継男』から与えられた“匂い袋”を、
そっと取り出しては、時折確かめるように、顔先を通す仕草をした。
子供の頃から慣れ親しんだ匂いではあったが、
今一度、蒼い麦の匂いに慣れた嗅覚を、呼び戻してみたくなったのである。
彼の親の『継男』は、母の『清』が肌身離さず持っている“匂い袋”と同じものを、
彼にも与えたのである。
「この“匂い袋”は、おまえの母様が若い頃に手放した赤子に、
実家の親が持たせた“匂い袋”と同じ薫りが忍ばせてある。
この薫りと同じ匂いの娘さんを、探し出せるならば、見つけてほしい。」
という言葉を添えられて。
公家なら知らず、町の職人の若い男が、匂い袋を持つことは、
どことなく恥ずかしさを覚えるものだった。
だが、『この匂いと同じものを持つ娘御が、義理の妹になる。』と思うと、
それを手放すことはできなかった。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『継男』と『清』の夫婦は、都から来た『かぐや姫』が、以前にこの地に住んでいた
『芳し姫』の成長した姿だということを、ほぼ確信を持って、認識していた。
だが養子(息子)が、その屋敷の調度品を見繕いに出入りするようになるとは、
思いもよらないことだった。
都から帰ってきて、天皇の従者までを遣わされたという“高貴な身分”になってしまった
『かぐや姫』には、近寄りがたさを覚えていたのである。
自分たちでさえも近寄れない『姫』が、実子であるかも知れないなどとは、
息子にも話せないことだった。
そこへ、天恵なのか、息子が通い始めることになったのである。
何も知らされずに屋敷に入った『満弦』は、主の『かぐや姫』に、目通しを許された。
『かぐや姫』の持つ“匂い袋”を噂に聞いていた『満弦』にとっては、
密かに心騒ぐものがあった。
初めて会った『姫』の、輝くような、匂い立つ美しさにも、心を奪われたが、
その美しさを包む柔らかな匂いも、『満弦』の心を捉えたのである。
表に出てから、その薫りを一旦、風に運び去らせてから、
自分が持つ匂いとの違いを、確かめてみたのだった。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『かぐや姫』も、出入りする職人の多さに、めまいがするほどの気ぜわしさを、
感じる日々だった。
己が何をしているのか、何をしようとしているのか?
それさえも、感覚が朧になりかけていた。
そのような日々の中で、時折、ふと心安らぐときがあることを、感じ始めていた。
慌ただしさに紛れて、それがなぜなのか、思い返すこともなく過ごしていた。
だがそれが最近になって、頻繁に感じられる。
忙しさに紛れることなく、その気配を、心に留めることができるようになったのである。
『なぜであろう? この安らいだ心地は、どこから来るのか?』
その思いが、『満弦』が訪れたときに強まることを、確信できたのは、
二人だけで新居の中を、見ていたときだった。
はじめには、『初めて見る素敵な男』に心を奪われたのか? と思った『かぐや姫』だったが、
それだけではない“ある感覚”が、“ふぅわり”と、『姫』の胸に忍び込んだのである。
『おや? この薫り・・・。男が、私と同じ匂いを?』
その不思議な感覚が、“安らぎ”の元であることを、
このときになって、覚醒させられたのだった。
『不思議な縁によって、結ばれている』
そう感じた『姫』は、『満弦』の訪れる時を、心待ちするようになっていた。
だがこの二人の想いは、世間の誰も、知らないことだった。
“一目惚れ”というには、互いに惹かれながら、その思いに気づかずにいたことと、
“匂い”によって、『縁』を強く感じて、知らずのうちに惹かれあったことなど、
『強烈な恋の意識』が互いを引き合ったというよりも、
『楚々とした柔らかな月の光』が、穏やかに二人を引き寄せたようでもあった。
(今回は、出番がなかった・・・)
(忙しかったからね)
(だけど、この話の展開を見ると、ぼちぼち『決まり』だね)
(『相思相愛』になり始めたんだから、そうなるんだろうね)
(今まで誰にもなびかなかった男女が、ついに相手を見つけたか?)
(多分・・・)
(多分、って? おい! 話の逆転はないんだろうね)
(例によって、何にも考えていないから、わからない)
(もう一度言うけど、出番がなかった)
(『出 番 』は『明 晩 』に先送り。 バンバン !!)
(くっだらない)

新説【竹取物語】・・・《15-結》
当初は、ほのかな薫りに気づかなかった二人だが、
互いに同じ匂いの“贈り物”を持つと知ってからは、
従前にも増して、相手への想いが強くなっていった。
(はい、18禁の始まりぃ。父兄同伴のコーナーですよぉ。)
満月を待つことなく、二人の出会いは回数を重ねられるようになった。
十三夜も、十六夜も、二人にとっては、満月と変わりがなかった。
新居に納める品のサイズを測るにも、意図的に時間をかけて、
夜に掛かるように、企図した。
帰りを見送る『かぐや姫』と、夜になっての新たな逢瀬をも、楽しむことができた。
麦の穂を押し倒して、身体を横たえる『姫』は、昼とは違った肌の白さが、
優しい月明かりの下で、輝いてさえ見えた。
『満弦』は、弾むような乙女の身体を、息を詰めて見つめた。
『かぐや姫』も、『満弦』の仕事で鍛えられた身体を、熱い眼差しで、瞬きを忘れて見つめた。
『満弦』の身体からは、姫の周囲にいる武士(もののふ)たちとは違って、
険しさのない“男らしさ”が、迸っている。
この“月を見上げる斜面の畑”が、『かぐや姫』の父母が、18年を遡る同じ満月の夜に、
身体を横たえていた同じ所であることは、『姫』も『満弦』も、思い及ぶべくもない。
(今回は、いきなりの18禁だね?)
(最終回だから、元気を出してみようかと言うことで・・・。)
(これで、元気が出るか?)
(いいの。残りは、想像力で補って。)
(“これぞ大人の世界”だねぇ。)
(ということにしといてね。)
『満弦』の帰りが、少しずつ遅くなり始めたことを、『継男』と『清』夫婦も、気づいていた。
『かぐや姫』の屋敷完成が迫ったことで、最後の調整に手間取っているのだろう、と思う一方で、
自分たちの経験から、『もしや・・・。』と思う気持ちも、心の奥に抱いていた。
「あなた、『満弦』の帰りが、最近は遅くなることが多いと思います。どうお思いでしょう?」
「うむ。これほどに、あの子が手間取る調整とは、どのようなものであろうかのぅ。」
「さにはあらず。18年前の、私どものことをば、思い起こしなさいませな。」
「18年前・・・。そうか、さもあらめ。彼の子供らは、吾等が血を引く・・・。」
「しかも、なにやら気がかりなことも。」
「おんし、何やら気づき申したかや?」
「はい。気のせいとは思えませぬ。蒼い匂いが・・・。」
『継男』は、『清』の言葉に、“ハッ”と気づかされることがあった。
“蒼い匂い”とは、“あの畑”の匂いではあるまいか?
「蓬の香りならば、迂闊な儂でも、気づきましょうが。もしや・・・。」
「その“もしや”かと。あれは、麦畑の匂い。」
「『満弦』が歩んで行ける道筋には、麦畑に入る要はあらめ。」
「左様に思われましょう。であれば、あの匂いが確かなものなれば・・・。」
「明日にも、儂が注意を払ってみよう。」
「私も改めて。」
そして、その翌日の夜。
帰宅した『満弦』に、何気なく仕事の進み具合を確かめるそぶりで、
『継男』が呼び寄せた。
「いかがかな、『姫』のお屋敷は?」
「は。間もなく落成の日が、参りましょう。」
「何?儂も疲れて居るものか、お主の話が遠い。もそっと近う寄りやれ。」
「や、これは。」
「で、いつの落慶に相成るとな?」
「細部の仕上げには、も少しばかりの日にちが要すかと存じますが、
それでもひと月とは掛かりますまい。」
「その後は?」
「はい? おっしゃる意味が、解りかねますが。」
「よい。疲れたのではあるまいか? 今宵は早うに休むが良かろう。」
「お言葉のように。」
二人の会話を聞きながら、『清』も時折、『満弦』の背後を、幾度か通り抜けた。
「いかがです? 『満弦』の匂いは、今宵は変わりなきや?」
「確かに、いつもならず、“蒼い匂い”がしたよなぁ。」
「やはり、そうでありますか。私もそのように嗅ぎましたぞ。」
「違いあるまい。」
「いかがなされますや?」
「捨て置くわけにも行くまい。吾等が二の舞は、二人をも、そして『お子』をも、
哀れにさせよう。ここはひとつ、意志を確かめねばなるまい。」
両親に問われた『満弦』は、『かぐや姫』への想いを、両親に打ち明けた。
両親にも、異存はない。
“できちゃった婚”がブームでないこともないけれど、
包み隠すことなく、“嫁”に迎えて、
堂々と孫を産ませてやりたいと、『清』たちは願った。
残るは、『姫』の意志を、確かめるだけである。
性根を据えて、『満弦』が、『姫』に気持ちをぶつければいい。
『かぐや姫』も、もともと“初めての恋”であれば、今後もこれほどの男が現れるとは、
期待が持てない、と考えていたところである。
落成した屋敷から、輿入れすることを、承諾した。
従者たちは、引き続きその屋敷に住まうもの、帰郷するものへと、
分けられることになった。
だが多くの従者は、姫の元の住まいに留まり、あるいは姫の嫁ぎ先で働くことを望み、
筑紫に永住を決めたようだった。
『かぐや姫』を『憶良』に託した形になった祖父たちは、
転任によって、すでに出雲へと離れていた。
“孫娘”であっても、その行く末に、嫌も応もない。
娘夫婦に引き取られて、嫁ぐとなれば、それ以上の心強いことはない。
『かぐや姫』には、『自分が幾人もの貴人から求婚された』といった気負いは、
微塵もなかった。
都から遠く離れた土地に来て、栄華を求めても、それはうたかた。
その“束の間の現世”を求め続けるよりも、確かな腕を持つ職人の下へ嫁ぐことのほうが、
新たな“旅立ち”ができそうに思われた。
そして、挨拶に訪ねた『満弦』の家で、
自分と同じ匂いを、その母の『清』からも受けることによって、
気持ちを一層堅いものにした。
『かぐや姫』の輿入れは、『大伴旅人』の援助などもあって、
一地方の嫁入りとしては、破格の華麗さで執り行われた。
まさに、『月から参った姫』と言われるに相応しい、輝くような煌びやかさだった。
『かぐや姫』は、『満弦』のもとで、実の父母に温かく迎えられて、
表に出ることがなかった都での生活が嘘のように、明るい表情が戻った。
『家具屋』の看板奥様として、その人気は、再び都にまで届いたのである。
都では、『姫』に振られた“貴人”等が、
「『かぐや姫』が、輝く牛車に乗って、またもや“月”に帰られた。
しかも、『かぐや姫』が『家具屋妻』になられて・・・。」
と、嘆くまいことか。
-------- めでたし、めでたし。---------
(これで終わりなの?)
(ごめん)
(詫びればいいってものじゃない、ような気がするけれど)
(オチが付いたから、いいでしょう?)
(だからぁ・・・そのオチがひどすぎるんじゃないか? って言うの)
(だって、『継男』は家具職人だったんだし、『満弦』はそこに貰われた養子だったわけだし)
(そういう問題じゃないの)
(『満弦』は養子で、『かぐや姫』は実子。近親結婚にはならないでしょう?)
(だから、そういう問題じゃなくて、結末が雑!)
(でもさぁ、今回で連載15回目。ちょうど区切りということで・・・)
(へ?)
(十五夜だから、区切りに相応しいでしょう)
(強引だなぁ)
(きっと、読んでくださっているかただって、途中で“結末”に気づいていたと思う・・・)
(また、逃げるぅ)
(それにね、兎に角、ハッピーエンドだったんだから、めでたしめでたし)
(豪華な結婚式まで辿り着いたんだから、目出度くないこともないのか・・・)
(食えないけどね。“目で鯛”は)
(最後まで、ダジャレか!?)
強引でも、兎に角これで、15回連載の『新説 竹取物語』は、無事に? 完結しました。
次回は、かいつまんで、本物の『竹取物語』を、ご紹介して、“結びの章”と致します。
次は、どんな話をテーマにするか、未定です。
また、くだらない結論が待ちかまえているかも、と思うと、『もう、いらねぇ』ですよね?

原典『竹取物語』・・・終わりに

非常に粗い解説になりますが、“そもそもの『竹取物語』とは?” という原典を
ここで簡単に、たどっておきます。
私の『新説』には、どこまでが本当で、どこが嘘なのか、判らなくなっていますので、
混乱を防ぐためです。(本気にしないから、大丈夫ですって?)
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『竹取物語』の原典は、南洋島嶼系の羽衣伝説などに加えて、中国南部の稲作地帯で、
説話となっていたものが、日本に取り込まれたものといわれる。
その説話が、日本で『物語』として創作・定着させて、平安時代に、現在の物語として
安定したものだそうである。
その昔に、“紫式部”が『源氏物語』の中でも、「日本の物語の祖(おや)」と述べている。
だがこれに対して、同時代の“清少納言”は、『竹取物語』の存在自体に、触れていない。
『日本古来の物語』として、妥当性を疑問視したともとれる。
『枕草子』のどこにも、『竹取物語』が登場しない。というよりも、触れられていない。
『竹取物語』の背景を示すようで、紫式部と清少納言、二人の見解が面白い。
それ以降も、『原典』がどこにあるのか? といった探索活動は、本居宣長や柳田国男ら、
錚々たるメンバーが、国内外に類似性のある物語を求めて、続けてきた。
『万葉集』にも、“竹取翁の物語”が出てきて、それとの関連性も、注目される。
別物といわれるが、その後の『物語』の発展性に、何らかの影響を与えた可能性はある。
“竹”は、成長力・生命力の旺盛さから、『呪力』を持つとされて、神仏に因む各種の行事にも、
広く採用されてきた。これは、“伊弉諾、伊弉冉”の神話の時代から受け継がれてきた、
“竹の呪力”に縋るものであるかも知れない。
『竹取物語』には、チベットに、非常に似た物語があるそうだが、詳細は知らない。
『斑竹姑娘』という、その物語のあらすじは、
【竹の中から生まれた娘が、母子家庭のひとり息子に出会って、
その後に領主の息子等の求婚を受るが、5つの難題を与えてそれを退け、
“ひとり息子”と、めでたく結ばれる】
といった内容であるという。
その“5つの難題”は、見事に『竹取物語』と符合する。
どちらが、どこの影響を受けて成立した『物語』であるのかも、知らない。
初期の『竹取物語』では、5人の貴人が“求婚者”になっているが、“富士縁起”などは、
出てこない。数百年の時を経て、新たに構成された『物語』の中で、
“求婚者とかぐや姫との和歌交換”、“十五夜昇天の細密描写”などが、付された。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
ところで、『新説』でも書いた『かぐや姫』の育ての親だが、
竹取翁の年齢は、かぐや姫が月に帰るときに、“齢70”とされるものと、
『昇天前』の“50”という部分がある(原典)。どちらの説を採用するかによるが、
かぐや姫を20余年間育てた翁が、姫を拾い上げたときの年齢は、50歳台とも言える。
そのことから、『新説』では、『山上憶良』(没年74歳)を、“翁”に充てたのである。
時期は藤原京か平安京の、微妙な時代だが、『都』と表現することで、
“都”が京都であるか、奈良であるかの限定をも、避けてみた。
原典の『かぐや姫』名は、“満月信仰”による“輝く姫”から付けられたものだろうが、
この命名は、単純すぎるように思われる。そこで、『新説』では、ひねってみたものである。
『かぐや姫伝説』は、『天女伝説』、『浦島伝説』や『鶴の恩返し』など、
多くの説話、物語に共通する部分がある。
そのように見ると、古くは一つの原典であったものが、時を経て分枝した物語とも思われる。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『竹取物語』のあらすじを、書くつもりでした。
でもそれよりも、詳しく書かれたサイトがありますので、詳細は、そちらをご覧戴いたほうが
判りやすく、楽しめるかと思います。
★ 『古代史の扉』→ 『竹取物語と「壬申の乱』
★ 『日本古典文学テキスト』→ 『竹取物語』(國民文庫)
★ 『かぐや姫の里を考える会ホームページ』
★ 『山上憶良』

“燕の子安貝”と言い渡された『石上中納言』は、
最後になって『かぐや姫』の課題が緩んだかと、
どことなくホッとした気分も、味わっていた。
『さすがに姫ものぅ。先の皇子たちや大納言殿に、あまりにも過酷な注文を出して、
その結果が、いずれも“偽物”出現ということに、なってしまわれた。
そんなことで、求婚者は儂が残るばかりに、なってしもうた。彼の方々の評判をも、
貶めることになってしまい、姫ご自身としても、嬉しいことではあるまい。
その反省があって、この儂には、手を緩めてくださったものと思われるわいな。』
そのようなことを、いつまでも考えながら、
まるで“宝物”を手に入れてしまったかのような軽い足取りで、
中納言屋敷に戻った。
「殿は、いかがでおじゃいまいたか?」
「おうよ。此度は、お手のもんやないかと、嬉しゅうてなぁ。」
「そないな、ヤワなお言葉を、頂戴なさいまいたか?」
「ふふふ・・・」
「お心当たりでも、おありなさいまするかや。」
「あらいものかは。」
(何度も言うけど・・・)
(へえへえ、言ってくれはり・・・)
(いかがわしい『もっともらしい言葉遣い』を、やめれ!)
(雰囲気だけでも、楽しもうかと思うたに)
(まだ、気分が抜けていないな)
(なりきりやすい性格なもので)
(でたらめ言葉でも良いけど、もちょいと、解りやすく頼むわ)
(任せておくんなせえヤシ)
(いきなり、どこの言葉になったのやら)
(知らん)
(そればっかり・・・)
「では、これまでのいきさつとは違って、我等が出番は、なさそうでしょうや?」
「何の、そなた等のお力も、借りようぞえ。
探さねばならんことには、変わり無きよってな。」
「幻のような“お品”では、探しようも御座いませんが、解りやすければ、どうにか。」
「解りやすいも何も。」
中納言は、ここでおもむろに、『かぐや姫』から与えられた課題を、家人に伝えた。
「“燕の子安貝”とぞ。どうや? 解りやすかろうが。」
「殿のお顔が緩むは、察せまするわいなぁ。」
「さもあろう?」
「下々の我等でさえも、“子安貝”なら、話に聞いたことは御座いますれば。」
「さすれば、それを“燕”が所持していれば、それが“燕の子安貝”であろう。」
「ごもっともにございます。明日から探し始めても、間に合いそうですなぁ。」
「今宵は、ゆるりと休んで、明日から気張ってもらおう。」
翌朝から、情報収集が始められて、“これは?”と思われるところへは、
家人が駆けつけて、確認作業を急いだ。
しかし、思いの外に“燕の子安貝”は、本物が見つからなかった。
寄せられた情報を頼りに駆けつけた、家人からの報告では、
『燕の巣にあった“貝”は、“はまぐり”でした。』
ということも、多かった。
さらには、山里の農家から
『お探しの“お宝”が、我の軒先に作られた燕の巣に、入ってます。』
と、連絡を受けて訪ねてみると、確かに子安貝が巣の中に入っていたが、
問いつめると、農夫が放り込んで置いたものだということが、解ったケースもあった。
そんなものを、素知らぬ顔で届けても良かったのだが、中納言は、
『先の失敗例を、心して掛からねば、儂もアホの仲間入りやからなぁ。』
と、“本物”に、こだわり続けた。
かぐや姫が、“燕の子安貝”について、どこまで真偽のほどを知っているのか、
そこのところが解らない。
解らない以上は、妙な“出物”を持ち込まないに限る。
簡単に思えた“燕の子安貝”探しも、手詰まりになり始めていた。
期限の日が近付くに連れて、気軽に考えていた中納言にも、焦りの表情が見え始めた。
「なんや、大元で、心得違いをしていたんと、ちゃいますかなぁ。」
「と申されますと?」
「『燕の巣』やて、あてどなくどこぞの燕の巣を探し回って居るようやが、
そこらそんじょの『燕』とは、違うんやないかえ?」
「京では見たことがありませんが、断崖に懸かる『岩燕』なる巣かも、知れませんなぁ。」
「それ、それよ! どうしてそれに、早う気づかなんだろか?」
「『岩燕の巣』に絞って、探し直してみましょ。」
「そこまで絞り込めたなら、儂も自ずから動かな、いかんやろ。忙しゅうなりそうやわぃ。」
無数に懸かる“農家の燕の巣”を探し回る必要が無くなり、
“岩燕の巣”にターゲットを絞ったことで、
今度こそは、発見につながりそうで、期待がいや増した。
中納言も、『岩燕の巣がある』と噂されれば、自ずから出向いて、探し始めた。
そんなときに、せり出した断崖からふと見下ろした、その中程に、
『子安貝を抱えた岩燕の巣』が、見つけられたのである。
偶然の出来事であり、付近には供の者も居ない。
中納言に与えられた、天恵のように思われた。
中納言には、『かぐや姫』が巣の中で、手招いているようにも見えた。
「さあ、早うに私をここから、あなたの手に掬い上げて賜れ。」
潤んでキラキラと光るかぐや姫の目に見つめられるように、
課題を授けられた“あのとき”の姫の“鈴を転がすような澄んだ声”が、
今またここで、中納言の耳奥で囁き始めたように、石上中納言を、不安定な崖へと誘った。
『もう少し、あと僅か・・・』

『もう少し、あと僅か・・・』
その僅かな距離が、無限の彼方にあるようで、
またほんの一息、手をさしのべれば届きそうで・・・。
中納言は・・・。
かぐや姫の手を取って、天女の羽衣に包まれて天空を飛んでいる、
至上の幸福気分を味わっていた。
中納言の手には、幻と思われた“燕の子安貝”が、しっかりと握られていたのである。
『この幸せを、かぐや姫が喜び、迎えてくれている。ついに、姫は儂の妻になる・・・。』
“夢”と“幸せの子安貝”を握りしめたままで、天空を翔た中納言の“至福の時”は、
瞬くほどの“時”でしかなかった。
悲報は、中納言屋敷を駆け抜けて、『かぐや姫』の元にも、伝えられた。
「まさか、あのお言葉が、本当のことになるとは・・・。
あの『この中納言の、命に替えても』というお言葉が・・・。」
なまじ、実現可能な課題だったがために、無理をさせてしまった。
『憶良』は、この知らせが姫に届かないようにと、腐心したが、人の口に戸は立てられない。
『かぐや姫』は、漏れ聞いたこの知らせを知って、悲嘆にくれた。
いよいよ、自室から出ることが少なくなり、窓から月を見上げては、
嘆息を吐くばかりになった。
『憶良』も、市井の人々も、『姫の責めにはあらず』と慰めてくれるが、
気休めにもならなかった。
“子宝に恵まれる”と言われる“燕の子安貝”などと、思わせぶりな課題を与えたことが、
中納言に無理を強いることになったのではあるまいか。
『かぐや姫』の噂は、天皇の元にも、伝わっていた。
事の成り行きを見守っていた天皇だったが、意外な展開になり、
『かぐや姫』が籠もってしまったと聞くに及び、沸き上がる興味を、抑えきれなくなった。
「その者、“わらわ”の元へ呼び寄せることは、叶わぬかぇ?」
「『かぐや姫』なる者、“この世の者に在らざる”とぞ、聞こえまする。呼び寄せ賜うべきか。」
「して、何処ぞの者と言うか?」
「月より参り侍らす『姫』で、あらせらるると。」
「されば、“わらわ”が出向いても、不都合ではないな?」
「お待ちあれ。それにや及ぶ。我等が説き伏せる努めをば、致しましょう。」
「よい。明日にも、会いに参ろうぞよ。」
女帝は、かぐや姫との結婚に、興味があったわけではない。
多くの貴人を翻弄する、『かぐや姫』の“美貌”を、確認してみたくなっただけである。
月から参られた『姫』であろうとも、“倭の国”を混乱させるとあっては、
放置するわけにも行かない。
できるだけ早く、その処置を考慮しなければなるまい、と考えたのである。
「大君が、直接、行幸召されることは、いかがでありましょうや。」
疑問を呈する家臣に対して、持統天皇は、
「月より参らせられた“姫”にお会いするに、“日の本の皇”であるわらわが参る。
不思議は、どこぞにあろうや。」
と、進言を押し返した。
(ねえ、ちょっと良いかな?)
(また出たな! 今度は、何だい?)
(いいの?)
(解りやすく質問してね)
(ここで、“持統天皇”なんて、特定の実在人物名を出しちゃってさぁ)
(『竹取物語』の最初の誕生は、天武天皇~持統天皇の頃って言われているから、いいの)
(ここで『日の本の皇』って言うのは?)
(『新説』の『新説』たる部分を、ちょっとは見せないとね)
(いわゆる“でたらめ”?)
(そうとも言えない。『日本』という呼称は、持統天皇が使い始めたとも言われるようだから、
『月の王女』かぐや姫との対比には、ピッタリでしょ)
(『新説』だったよね。ここまでの、どこが『新説』なの?)
(大まかには、『5つの宝物』なんかは、ほとんど原型と同じだよ。
4番目と5番目の順序が、もしかしたら、逆。話の展開上、こんなふうにした)
(きっと、ほかにも『新説』はあるんだよね)
(あらすじ以外は、全部『新説』なんだけど、これからもっと、『新説』になりそうな予感)
(それならいいけど。18禁はどうなった?)
(古い言葉が多いから、断らなくても18歳以下は、読みたくもないでしょ)
(そう言う意味かぁ)
(まぁ、ね)
「憶良殿の佳き歌は、かねがね目にとめております。」
「畏れ多いお言葉、申し上げることもなく・・・。」
突然に天皇の訪問を受けて、『憶良屋敷』では、上を下への大騒ぎになった。
「急な決定で、断りもなく、申し訳ない。」
「勿体ないお言葉。このようなあばら屋に、お越しくださるとは、
思いも及びませぬ事でありますれば、
どのようにお持てなしを致さばよろしいのか、皆目・・・。」
「よい。此度の目当ては、月より参らせ賜うと聞き及ぶ、『姫』にお会いすることである。」
「お耳を汚して参らせるかと存じ上げまするが、姫は、石上中納言殿の一件以来、
どなたにもお会いしません。」
「ふうむ・・・。」
すかさず従者が、言葉を挟んだ。
「日の皇が、月の姫にお会いしたいと、おみ足を運ばれ申した。いかが?」
「いかにも。そのお言葉を、姫に伝えましょう。」
憶良が応じて、天皇とかぐや姫との会談が、実現した。
天皇とかぐや姫との会談は、山の端に陽が隠れるまで、続けられた。
やがて姫の部屋を出てこられた天皇は、
「話は、あいわかった。確かに、姫はこの世界の者に非ず。
固持なされて、理由は確かめられなかったが、なにやら深い曰くがあるような。」
「お察しのほど、痛み入りまする。」
「憶良殿が宝である。大事になされよ。追って、沙汰を伝えましょう。」
「なにとぞ・・・。」
“お手柔らかに”の言葉を飲み込んだ憶良だった。希望などを、伝えられる立場にはない。
● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★
天皇の決断は、早かった。
数日後には、『憶良』に沙汰が下された。
『身分の貴卑を問わずに、あまたの求婚を断り続けるは、
姫が月より参らせた意味以上に、深く意図することがありそうな。
然れども、それによって生じた此度の災難は、
姫の呵責には能わず。
とは雖も、このまま都に留まらせ置くには、さらなる騒動も、予見されよう。
ついては、姫は生まれ故郷へ、お帰り願うのが相応しかろう。
従者に土産を持たせるので、それをお持ちになって、『古き竹の里』へお帰り戴くように。』
天皇の従者が、この通告とともに、牛車一杯の宝物を、憶良屋敷へ届けた。
天皇の、四囲を治めるための配慮が、憶良には感じられた。
否応を言っている場合ではない。
出立を“次の満月の夜”と決めて、『筑紫国』への旅立ちの準備を始めさせた。
都の若者たちの間には、
“『かぐや姫』がまたもや、手の届かない遠国に去ってしまう”という噂が、
一気に広まった。
どうにかして翻意させようと、嘆願運動まで沸き上がったが、すでに時は遅し。
『かぐや姫』の意志でも、『憶良』の考えでも、
この決定を変えることはできない段階まで、進んでいたのだ。
彼らは、“天皇の決定である”ことまでは、知るよしもない。
『姫が月に帰るときが近付いている』という事実だけが、広まっていった。
そして、その“満月の日”が、訪れた。
都の若者たちは、仕える手の者を武装動員して、姫を連れ去ろうとする『異界の者』を、
阻止しようと試みた。
だが、去りゆく『かぐや姫』一行に縋って嘆く『憶良夫妻』が、盾のような具合になり、
矢を射かけることもできなかった。
その『迎えの使者たち』は、憶良の従者たちと、天皇から遣わされた、
護衛の一行だったのである。
満月に照らされた牛車の一行は、黄金の車を煌めかせて、静かに、周囲を圧しながら、
山の端に、消えていった。
一行が消えた山頂には、昇りかけた満月が、
この世のものとは思えないほどに、巨大な姿になって、
『かぐや姫一行』を、包み込んでしまったように見えた。
まさに“かぐや姫は月に帰った”ように、見えたのである。
憶良屋敷の『かぐや姫の部屋』には、憶良夫妻に宛てられた感謝の手紙が、
一通だけ置かれていた。
文机の上で、今しも昇った月の光に照らされ、主の想いを含ませて・・・。
憶良夫妻は、その手紙を開く気力も失せて、
姫が去ったあとの部屋に、ぽつんと、並んで座っていた。
夢やぶれた『4人の求婚者たち』にも、
『かぐや姫』が月に去ってしまう噂は、伝わっていた。
が、今更、行動を起こす事はできない。
4人は、並んで満月を見上げて、それぞれの『過ぎ去った夢』を、偲んでいた。
(はい。めでたしめでたし・・・と)
(勝手に終わらせるな)
(終わりじゃないの?)
(原作では、こんなところで終わったケースもあったみたいだけどね)
(だから、終わりじゃないの?)
(ここで終わったら、『新説』でも何でもないでしょう)
(今まででも、新説と言えなくもなかったと思うけど)
(だって、まだ『オチ』もなければ、『ハッピーエンド』にもなっていないでしょ)
(ハッピーエンドになるんだ? もう、いい加減に終わりにしようよ)
(もうちょい。あと・・・3回分くらいかなぁ)
(長すぎて、ダレちゃう)
(あと3回は、短めにするから・・・)
(何を企んでいるんだか)
(『月光仮面』なんて、登場させないから、安心して)
(『月光仮面』は出なかったけど、『結婚仮面』が出たなんて・・・)
(深読みのしすぎ!)

都では、『かぐや姫』が月よりも明るく輝く牛車に乗り、迎えの者たちに守られて、
満月の中に飛んでいった、と噂された。
黄金の馬車は、まさに『月よりも眩しく輝く』気高い姫を迎えるに相応しい乗り物であり、
今まさに昇り切らんとする満月に向かって、峠を登る姫の一行は、
『月へ帰った』という表現が、みごとに相応しかったのである。
その行く手を阻止しようとした、都の武士たちが、矢を射かけることもできずに、
動きを封じられてしまったのは、傷つけることさえも畏れ多く感じさせる、
絢爛豪華な車の仕立てにあった。
天皇たちは、姫が都を去るときに、阻止行動に出る武士たちがいることを予測して、
戦わずにその動きを封じる手段は? と熟慮した上で、編み出した手法でもあった。
とにかくこのようにして、『かぐや姫』一行は、都を去って、南の故郷へと、向かった。
親子の縁を切られて、『継男』の許に嫁いだ『清』は、残してきた娘の幸せを願いながら、
実父が孫娘を他人に託したという、その現実から逃れることができずに、
『継男』との子供を、もうけることがでlきなかった。
修行から帰った『継男』は、家業を継いで、仕事に精を出し、
何不自由ない生活ができるようになっていた。
ただ一つの不満は、愛する『清』との間に、どうしても子供ができなかったことである。
『清』は、指も触れさせない、ということではない。
だが、気持ちが乗っていないと言うべきなのか、“そのとき”になると、
素っ気ないほどに、『継男』のタイミングを、逸らしてしまう。
「焦らずとも、そのうちには・・・。」
と言ってくれる『継男』には、申し訳ない気持ちが募るが、無意識に身体が反応してしまう。
いや、拒否してしまうのである。
それでも『継男』は、『清』を気遣い、無理押しはしなかった。
(お? 久しぶりに『18禁』だね)
(・・・の、つもりなんだけど、際どい表現になってる?)
(拍子抜け。もっと過激に! なんて思うんだけど)
(ここから『過激』な想像力に辿り着けるのが、“大人の証明”にならないかなぁ)
(ならない・・・と思うよ)
(このくらいで諦めて、これを読んで、胸をときめかせてよ)
(今までで、一番難しい注文かも)
(父兄同伴で読む必要なんて、なさそうだね)
子供は作れなかったが、『継男』の両親も、『清』を厳しく責めることはなかった。
『清』が家柄の良い娘だ、ということが解っているからというだけでなく、
『継男』と同じように、心根の優しい両親だったのである。
しかしそれでも、家業を継がせる子供は、必要になる。
そこで、将来の家業が発展するような相手を選び、養子を迎えることになった。
『清』と『継男』がもうけた子供よりも、少し年長だったが、しっかりした子供で、
家柄も、『清』の出自と、釣り合いがとれるほどの、官僚の次男だった。
二人は、この男の子に、自分の子供と全く変わりなく愛情を注ぎ、
家業を教えながら、大切に育てた。
男の子も、竹のように真っ直ぐな、好青年に成長した。
やがて、この青年にも、方々の村から、縁談が持ち込まれるようになった。
だがなぜか、どうしてもうまくまとまらない。
そうこうするうちに、青年は20歳を過ぎていた。
『かぐや姫』の道中は、難行の連続だった。
輝く牛車は、盗賊の格好の目標になり、その危険を嫌う従者たちも、
少しずつ零れるように、宝物の分け前をもらい、それぞれの故郷へと、
離れて行った。
それでも、天皇から直接選ばれて護衛に付いた者たちと、
憶良が信頼を寄せて、護衛に付けた屈強な精鋭たちは、欠けることなく、
『かぐや姫』を、『筑紫国』へ送り届けた。
その後、ある者はそのまま『姫』の元に留まり、またある者は、褒美を手にして、
道中で知り合った娘の元へ、またある者は都へと、散っていった。
道中の苦難を物語るように、『姫』の牛車は、
汚れるに任せて、見る影もなくなっていた。
だが黄金作りの車は、召使いたちが磨くと、また元のような輝きを、取り戻した。
都を離れて、幾月が過ぎたことだろうか。
奇しくも、『かぐや姫』が故郷の丘に麓に帰ったときは、満月の夜だった。
『姫』は、この丘で遊んだ幼い日を、憶良夫妻に大切に育てられた、幾多の記憶を、
満月を見上げながら偲んで、一夜を明かした。
磨かれた牛車は、『姫の輿入れ』を想わせるほどに、満月の光りを滲ませている。
幸いなことに、憶良たちが住まいにしていた粗末な家屋は、
その後も住む人もなく、荒れてはいたが、
手直しをすれば、仮の住まいには使えそうだった。
『憶良』からの知らせは、先んじて『筑紫国』に届けられていたので、
住まいを探す必要はなかったのだが、『かぐや姫』一行は、まだそのことを知らない。
憶良の、ある意味で“粋な計らい”で、あったかも知れない。
『筑紫国』で、『姫』の一行を待ち望んでいた人たちは、
逐一、入国の状況を、把握していた。
『姫』の本質を知るために、敢えて遠くから見守っていたのだ。
筑紫に入った一行が、まず生まれ故郷に向かい、
古家に住み着く決意を固めたらしいことが、
『大伴旅人』にも、伝えられた。
「憶良殿が、見事な娘御に育てられたものよ。
都に於いては、若者どもが羨望の的だったと伝わるに、いかような性根に育ち居るかと、
気をもんで居ったが、見目麗しさを偉ぶることなく、古家を偲ぶとは、
なんと愛おしいことよ。」
「都で姫を娶らなかった者どもは、さぞや悔いて居ることでしょう。」
「さもあらん。憶良殿に替わって、わが娘として、大切に引き取ろうぞ。」
「しかしながら、姫のお気持ちもございますれば・・・。」
「“竹から産まれた姫”なれば、竹林の匂いと名月を楽しめる、
彼の屋敷こそが相応しいのかも知れぬ。」
「姫のお心をば、確かめると致しましょう。」
「彼の屋敷に住まうと言うなれば、心地よう住まえるように、
如何様にも力添えを惜しむまいぞ。」
「お心を、そのまま『姫』へ、お伝えいたします。」
『かぐや姫』が、幼い日のように、
貧しい建物の隙間から漏れ入る月の光を楽しみ始めてから、数日の後に、
『旅人』の使いが、『姫』の心を確かめるために、訪ねてきた。
古家は早くも、改修工事を始めていた。
憶良たちと姫が育った『古家』の佇まいは、そのまま残されて、
周囲の敷地に、従者と供に『かぐや姫』が住まう新居が、質素ながらも、
不足を生じない状態に、整えられようとしていた。
「お疲れは、取れ申したでしょうや?」
「故郷の空が、疲れを吸い取ってくれるようです。
懐かしさに、1日が惜しいほどに思われます。」
「それは、何よりにございます。ところで主人(旅人)よりの言伝でございますが、
もそっと町中に住まわれるお心は、有りやなしや? と。」
「この地は、わが(育ての)『親』でありまする、『憶良』が私を育ててくださった土地。
なれば、この地にて『実の親』が名乗り出るを、待ちたいと思いまする。」
「おう。『育ての親』をお待ちなさるとは、殊勝な。」
「都を離れるときに、『憶良』殿が、私に持たせてくださった“物”がございますれば、
それを手懸かりに、きっと『育ての親』が見つかるものと、確信しております。」
「その“物”とは、如何なるものでしょうや?」
『かぐや姫』は、道中でも肌身から離すことがなかった『匂い袋』を、取り出した。
「幼少より、私が懐かしい思いで、触れ遊びし“匂い袋”にございます。」
「思い起こせば、『姫』はこの匂い袋によって、『芳し姫』とも呼ばれておりましたことが・・・。」
「幼き時分のことなれば、そのような噂は、私は記憶しておりません。
しかしながら、『憶良』殿がこれを大切に保っておわしたは、
この日の来るを予見していらっしゃったからかと。」
「さもあらめ。では、『姫』の実の親御を求める手助けを、主からも為すようにと、
お言付けいたしましょう。」
『かぐや姫』が、故郷の竹林に近い古家に、居を構えたこと。
『芳し姫』の謂われに因む“匂い袋”を、今も大切にしていることは、
セットにして、田舎町の隅々までに、喧伝された。
その噂が広まるまでもなく、心波立つのを抑えきれない夫婦がいた。
(それって、誰よ?)
(ふん! 解っているくせに)
(実は、解っていた)
(だろう? 誰にだって、解るはずだよ。)
(そうね。だけど、これからの展開は? もうすぐ“最終回”だよね)
(あと2回か。まとめを考えていないもので、今日もまた、引っ張っちゃった)
(なぁんだ。“無責任”なだけか)
(実は・・・そうなの)

『かぐや姫』の“屋敷建設”は、順調に進んでいた。
都から持たされた資金は、路銀として消耗されたが、新居建設に使うためのゆとりは、
まだ残されていた。だが無尽蔵に、残されているわけではない。
供の者たちが、“生活資金”を稼ぎ出すようになっていたが、
都の暮らしのようには、贅沢はできない。
『かぐや姫』は気づいていなかったが、この暮らしぶりは、
都の『山上憶良』に、あらかじめ庇護を託されていた『大伴旅人』によって、
見守られていた。
姫の様子は、逐一『憶良』に知らされていたのだ。
『憶良』も、『旅人』がいるからこそ、安心して、『かぐや姫』を送り出したのである。
屋敷建設が進むうちに、大工等に混じって、内装工事の職人も、
出入りを始めた。『姫』が筑紫入りをしてから、1ヶ月もたたない頃のことだった。
この年になって2度目の麦の穂が、蒼いさざ波を平地にうねらせて、
屋敷を緑の風で、包み込む季節になっていた。
このころ、“ある男”が、屋敷に出入りを始めた。
内装を仕上げるために、屋敷の様子を確認に来たのである。
男も、『かぐや姫』の噂は、聞き知っていた。
その男は町の職人で、家業を継ぐ、評判の『腕のいい男』だった。
成長するにつれて、男っぷりに惚れた女性たちから、親や縁者を通じて、
数多の縁談が持ち込まれていた。
世間は彼を、『満弦(みつる)』と、親しみを持って呼称した。
数多の縁談を断りはしているものの、円い人柄は、誰にも好まれたのである。
“月にたとえれば、上弦でもなく、下弦でもない。弦が満つるがごとくに、
丸く引き絞られたような・・・”
ということで、このように呼ばれたのである。
その若い男は、親の『継男』から与えられた“匂い袋”を、
そっと取り出しては、時折確かめるように、顔先を通す仕草をした。
子供の頃から慣れ親しんだ匂いではあったが、
今一度、蒼い麦の匂いに慣れた嗅覚を、呼び戻してみたくなったのである。
彼の親の『継男』は、母の『清』が肌身離さず持っている“匂い袋”と同じものを、
彼にも与えたのである。
「この“匂い袋”は、おまえの母様が若い頃に手放した赤子に、
実家の親が持たせた“匂い袋”と同じ薫りが忍ばせてある。
この薫りと同じ匂いの娘さんを、探し出せるならば、見つけてほしい。」
という言葉を添えられて。
公家なら知らず、町の職人の若い男が、匂い袋を持つことは、
どことなく恥ずかしさを覚えるものだった。
だが、『この匂いと同じものを持つ娘御が、義理の妹になる。』と思うと、
それを手放すことはできなかった。
『継男』と『清』の夫婦は、都から来た『かぐや姫』が、以前にこの地に住んでいた
『芳し姫』の成長した姿だということを、ほぼ確信を持って、認識していた。
だが養子(息子)が、その屋敷の調度品を見繕いに出入りするようになるとは、
思いもよらないことだった。
都から帰ってきて、天皇の従者までを遣わされたという“高貴な身分”になってしまった
『かぐや姫』には、近寄りがたさを覚えていたのである。
自分たちでさえも近寄れない『姫』が、実子であるかも知れないなどとは、
息子にも話せないことだった。
そこへ、天恵なのか、息子が通い始めることになったのである。
何も知らされずに屋敷に入った『満弦』は、主の『かぐや姫』に、目通しを許された。
『かぐや姫』の持つ“匂い袋”を噂に聞いていた『満弦』にとっては、
密かに心騒ぐものがあった。
初めて会った『姫』の、輝くような、匂い立つ美しさにも、心を奪われたが、
その美しさを包む柔らかな匂いも、『満弦』の心を捉えたのである。
表に出てから、その薫りを一旦、風に運び去らせてから、
自分が持つ匂いとの違いを、確かめてみたのだった。
『かぐや姫』も、出入りする職人の多さに、めまいがするほどの気ぜわしさを、
感じる日々だった。
己が何をしているのか、何をしようとしているのか?
それさえも、感覚が朧になりかけていた。
そのような日々の中で、時折、ふと心安らぐときがあることを、感じ始めていた。
慌ただしさに紛れて、それがなぜなのか、思い返すこともなく過ごしていた。
だがそれが最近になって、頻繁に感じられる。
忙しさに紛れることなく、その気配を、心に留めることができるようになったのである。
『なぜであろう? この安らいだ心地は、どこから来るのか?』
その思いが、『満弦』が訪れたときに強まることを、確信できたのは、
二人だけで新居の中を、見ていたときだった。
はじめには、『初めて見る素敵な男』に心を奪われたのか? と思った『かぐや姫』だったが、
それだけではない“ある感覚”が、“ふぅわり”と、『姫』の胸に忍び込んだのである。
『おや? この薫り・・・。男が、私と同じ匂いを?』
その不思議な感覚が、“安らぎ”の元であることを、
このときになって、覚醒させられたのだった。
『不思議な縁によって、結ばれている』
そう感じた『姫』は、『満弦』の訪れる時を、心待ちするようになっていた。
だがこの二人の想いは、世間の誰も、知らないことだった。
“一目惚れ”というには、互いに惹かれながら、その思いに気づかずにいたことと、
“匂い”によって、『縁』を強く感じて、知らずのうちに惹かれあったことなど、
『強烈な恋の意識』が互いを引き合ったというよりも、
『楚々とした柔らかな月の光』が、穏やかに二人を引き寄せたようでもあった。
(今回は、出番がなかった・・・)
(忙しかったからね)
(だけど、この話の展開を見ると、ぼちぼち『決まり』だね)
(『相思相愛』になり始めたんだから、そうなるんだろうね)
(今まで誰にもなびかなかった男女が、ついに相手を見つけたか?)
(多分・・・)
(多分、って? おい! 話の逆転はないんだろうね)
(例によって、何にも考えていないから、わからない)
(もう一度言うけど、出番がなかった)
(『出 番 』は『明 晩 』に先送り。 バンバン !!)
(くっだらない)

当初は、ほのかな薫りに気づかなかった二人だが、
互いに同じ匂いの“贈り物”を持つと知ってからは、
従前にも増して、相手への想いが強くなっていった。
(はい、18禁の始まりぃ。父兄同伴のコーナーですよぉ。)
満月を待つことなく、二人の出会いは回数を重ねられるようになった。
十三夜も、十六夜も、二人にとっては、満月と変わりがなかった。
新居に納める品のサイズを測るにも、意図的に時間をかけて、
夜に掛かるように、企図した。
帰りを見送る『かぐや姫』と、夜になっての新たな逢瀬をも、楽しむことができた。
麦の穂を押し倒して、身体を横たえる『姫』は、昼とは違った肌の白さが、
優しい月明かりの下で、輝いてさえ見えた。
『満弦』は、弾むような乙女の身体を、息を詰めて見つめた。
『かぐや姫』も、『満弦』の仕事で鍛えられた身体を、熱い眼差しで、瞬きを忘れて見つめた。
『満弦』の身体からは、姫の周囲にいる武士(もののふ)たちとは違って、
険しさのない“男らしさ”が、迸っている。
この“月を見上げる斜面の畑”が、『かぐや姫』の父母が、18年を遡る同じ満月の夜に、
身体を横たえていた同じ所であることは、『姫』も『満弦』も、思い及ぶべくもない。
(今回は、いきなりの18禁だね?)
(最終回だから、元気を出してみようかと言うことで・・・。)
(これで、元気が出るか?)
(いいの。残りは、想像力で補って。)
(“これぞ大人の世界”だねぇ。)
(ということにしといてね。)
『満弦』の帰りが、少しずつ遅くなり始めたことを、『継男』と『清』夫婦も、気づいていた。
『かぐや姫』の屋敷完成が迫ったことで、最後の調整に手間取っているのだろう、と思う一方で、
自分たちの経験から、『もしや・・・。』と思う気持ちも、心の奥に抱いていた。
「あなた、『満弦』の帰りが、最近は遅くなることが多いと思います。どうお思いでしょう?」
「うむ。これほどに、あの子が手間取る調整とは、どのようなものであろうかのぅ。」
「さにはあらず。18年前の、私どものことをば、思い起こしなさいませな。」
「18年前・・・。そうか、さもあらめ。彼の子供らは、吾等が血を引く・・・。」
「しかも、なにやら気がかりなことも。」
「おんし、何やら気づき申したかや?」
「はい。気のせいとは思えませぬ。蒼い匂いが・・・。」
『継男』は、『清』の言葉に、“ハッ”と気づかされることがあった。
“蒼い匂い”とは、“あの畑”の匂いではあるまいか?
「蓬の香りならば、迂闊な儂でも、気づきましょうが。もしや・・・。」
「その“もしや”かと。あれは、麦畑の匂い。」
「『満弦』が歩んで行ける道筋には、麦畑に入る要はあらめ。」
「左様に思われましょう。であれば、あの匂いが確かなものなれば・・・。」
「明日にも、儂が注意を払ってみよう。」
「私も改めて。」
そして、その翌日の夜。
帰宅した『満弦』に、何気なく仕事の進み具合を確かめるそぶりで、
『継男』が呼び寄せた。
「いかがかな、『姫』のお屋敷は?」
「は。間もなく落成の日が、参りましょう。」
「何?儂も疲れて居るものか、お主の話が遠い。もそっと近う寄りやれ。」
「や、これは。」
「で、いつの落慶に相成るとな?」
「細部の仕上げには、も少しばかりの日にちが要すかと存じますが、
それでもひと月とは掛かりますまい。」
「その後は?」
「はい? おっしゃる意味が、解りかねますが。」
「よい。疲れたのではあるまいか? 今宵は早うに休むが良かろう。」
「お言葉のように。」
二人の会話を聞きながら、『清』も時折、『満弦』の背後を、幾度か通り抜けた。
「いかがです? 『満弦』の匂いは、今宵は変わりなきや?」
「確かに、いつもならず、“蒼い匂い”がしたよなぁ。」
「やはり、そうでありますか。私もそのように嗅ぎましたぞ。」
「違いあるまい。」
「いかがなされますや?」
「捨て置くわけにも行くまい。吾等が二の舞は、二人をも、そして『お子』をも、
哀れにさせよう。ここはひとつ、意志を確かめねばなるまい。」
両親に問われた『満弦』は、『かぐや姫』への想いを、両親に打ち明けた。
両親にも、異存はない。
“できちゃった婚”がブームでないこともないけれど、
包み隠すことなく、“嫁”に迎えて、
堂々と孫を産ませてやりたいと、『清』たちは願った。
残るは、『姫』の意志を、確かめるだけである。
性根を据えて、『満弦』が、『姫』に気持ちをぶつければいい。
『かぐや姫』も、もともと“初めての恋”であれば、今後もこれほどの男が現れるとは、
期待が持てない、と考えていたところである。
落成した屋敷から、輿入れすることを、承諾した。
従者たちは、引き続きその屋敷に住まうもの、帰郷するものへと、
分けられることになった。
だが多くの従者は、姫の元の住まいに留まり、あるいは姫の嫁ぎ先で働くことを望み、
筑紫に永住を決めたようだった。
『かぐや姫』を『憶良』に託した形になった祖父たちは、
転任によって、すでに出雲へと離れていた。
“孫娘”であっても、その行く末に、嫌も応もない。
娘夫婦に引き取られて、嫁ぐとなれば、それ以上の心強いことはない。
『かぐや姫』には、『自分が幾人もの貴人から求婚された』といった気負いは、
微塵もなかった。
都から遠く離れた土地に来て、栄華を求めても、それはうたかた。
その“束の間の現世”を求め続けるよりも、確かな腕を持つ職人の下へ嫁ぐことのほうが、
新たな“旅立ち”ができそうに思われた。
そして、挨拶に訪ねた『満弦』の家で、
自分と同じ匂いを、その母の『清』からも受けることによって、
気持ちを一層堅いものにした。
『かぐや姫』の輿入れは、『大伴旅人』の援助などもあって、
一地方の嫁入りとしては、破格の華麗さで執り行われた。
まさに、『月から参った姫』と言われるに相応しい、輝くような煌びやかさだった。
『かぐや姫』は、『満弦』のもとで、実の父母に温かく迎えられて、
表に出ることがなかった都での生活が嘘のように、明るい表情が戻った。
『家具屋』の看板奥様として、その人気は、再び都にまで届いたのである。
都では、『姫』に振られた“貴人”等が、
「『かぐや姫』が、輝く牛車に乗って、またもや“月”に帰られた。
しかも、『かぐや姫』が『家具屋妻』になられて・・・。」
と、嘆くまいことか。
(これで終わりなの?)
(ごめん)
(詫びればいいってものじゃない、ような気がするけれど)
(オチが付いたから、いいでしょう?)
(だからぁ・・・そのオチがひどすぎるんじゃないか? って言うの)
(だって、『継男』は家具職人だったんだし、『満弦』はそこに貰われた養子だったわけだし)
(そういう問題じゃないの)
(『満弦』は養子で、『かぐや姫』は実子。近親結婚にはならないでしょう?)
(だから、そういう問題じゃなくて、結末が雑!)
(でもさぁ、今回で連載15回目。ちょうど区切りということで・・・)
(へ?)
(十五夜だから、区切りに相応しいでしょう)
(強引だなぁ)
(きっと、読んでくださっているかただって、途中で“結末”に気づいていたと思う・・・)
(また、逃げるぅ)
(それにね、兎に角、ハッピーエンドだったんだから、めでたしめでたし)
(豪華な結婚式まで辿り着いたんだから、目出度くないこともないのか・・・)
(食えないけどね。“目で鯛”は)
(最後まで、ダジャレか!?)
強引でも、兎に角これで、15回連載の『新説 竹取物語』は、無事に? 完結しました。
次回は、かいつまんで、本物の『竹取物語』を、ご紹介して、“結びの章”と致します。
次は、どんな話をテーマにするか、未定です。
また、くだらない結論が待ちかまえているかも、と思うと、『もう、いらねぇ』ですよね?

非常に粗い解説になりますが、“そもそもの『竹取物語』とは?” という原典を
ここで簡単に、たどっておきます。
私の『新説』には、どこまでが本当で、どこが嘘なのか、判らなくなっていますので、
混乱を防ぐためです。(本気にしないから、大丈夫ですって?)
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『竹取物語』の原典は、南洋島嶼系の羽衣伝説などに加えて、中国南部の稲作地帯で、
説話となっていたものが、日本に取り込まれたものといわれる。
その説話が、日本で『物語』として創作・定着させて、平安時代に、現在の物語として
安定したものだそうである。
その昔に、“紫式部”が『源氏物語』の中でも、「日本の物語の祖(おや)」と述べている。
だがこれに対して、同時代の“清少納言”は、『竹取物語』の存在自体に、触れていない。
『日本古来の物語』として、妥当性を疑問視したともとれる。
『枕草子』のどこにも、『竹取物語』が登場しない。というよりも、触れられていない。
『竹取物語』の背景を示すようで、紫式部と清少納言、二人の見解が面白い。
それ以降も、『原典』がどこにあるのか? といった探索活動は、本居宣長や柳田国男ら、
錚々たるメンバーが、国内外に類似性のある物語を求めて、続けてきた。
『万葉集』にも、“竹取翁の物語”が出てきて、それとの関連性も、注目される。
別物といわれるが、その後の『物語』の発展性に、何らかの影響を与えた可能性はある。
“竹”は、成長力・生命力の旺盛さから、『呪力』を持つとされて、神仏に因む各種の行事にも、
広く採用されてきた。これは、“伊弉諾、伊弉冉”の神話の時代から受け継がれてきた、
“竹の呪力”に縋るものであるかも知れない。
『竹取物語』には、チベットに、非常に似た物語があるそうだが、詳細は知らない。
『斑竹姑娘』という、その物語のあらすじは、
【竹の中から生まれた娘が、母子家庭のひとり息子に出会って、
その後に領主の息子等の求婚を受るが、5つの難題を与えてそれを退け、
“ひとり息子”と、めでたく結ばれる】
といった内容であるという。
その“5つの難題”は、見事に『竹取物語』と符合する。
どちらが、どこの影響を受けて成立した『物語』であるのかも、知らない。
初期の『竹取物語』では、5人の貴人が“求婚者”になっているが、“富士縁起”などは、
出てこない。数百年の時を経て、新たに構成された『物語』の中で、
“求婚者とかぐや姫との和歌交換”、“十五夜昇天の細密描写”などが、付された。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
ところで、『新説』でも書いた『かぐや姫』の育ての親だが、
竹取翁の年齢は、かぐや姫が月に帰るときに、“齢70”とされるものと、
『昇天前』の“50”という部分がある(原典)。どちらの説を採用するかによるが、
かぐや姫を20余年間育てた翁が、姫を拾い上げたときの年齢は、50歳台とも言える。
そのことから、『新説』では、『山上憶良』(没年74歳)を、“翁”に充てたのである。
時期は藤原京か平安京の、微妙な時代だが、『都』と表現することで、
“都”が京都であるか、奈良であるかの限定をも、避けてみた。
原典の『かぐや姫』名は、“満月信仰”による“輝く姫”から付けられたものだろうが、
この命名は、単純すぎるように思われる。そこで、『新説』では、ひねってみたものである。
『かぐや姫伝説』は、『天女伝説』、『浦島伝説』や『鶴の恩返し』など、
多くの説話、物語に共通する部分がある。
そのように見ると、古くは一つの原典であったものが、時を経て分枝した物語とも思われる。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『竹取物語』のあらすじを、書くつもりでした。
でもそれよりも、詳しく書かれたサイトがありますので、詳細は、そちらをご覧戴いたほうが
判りやすく、楽しめるかと思います。
★ 『古代史の扉』→ 『竹取物語と「壬申の乱』
★ 『日本古典文学テキスト』→ 『竹取物語』(國民文庫)
★ 『かぐや姫の里を考える会ホームページ』
★ 『山上憶良』

ホームへ戻る 初めに戻る
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- どんなお花を育てていますか?
- アサガオ観察日記5
- (2024-10-20 18:15:04)
-
-
-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…
- とうもろこし🌽栽培の悲劇
- (2023-07-06 12:55:36)
-
-
-

- 花や風景の写真をアップしましょ
- 東京の今朝の天気、神代植物公園の秋…
- (2024-11-26 09:56:29)
-
© Rakuten Group, Inc.