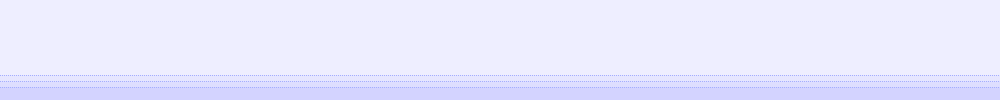幻視(まぼろし)-松の廊下で大乱心(1)
久しぶりに、そいつに出逢った。
煙のような、白く、得体の知れない『物体』である。
今までは、『それ』が思わせぶりに、私を奇妙な時代に導いて、
奇妙な光景を見せてくれた。
今回もまた、どこかの時代に連れて行こうというのだろうか。
まぁ、どこかに連れて行かれても、
その時代から戻されると、その出来事は一瞬のことだったと判るのだから、
どこに案内されようと、特に異存はない。
それで『それ』は、私をどこに導こうというのか?
そんな気持ちで『それ』を凝視しようとするのだが、
今回に限っては、なぜか『それ』に焦点が定まらない。
『それ』の意識も、どこか私から、焦点が外れているようだ。
なぜだろうか?
妙な感覚である。
『それ』の意識が向く先に、ふと目を向けた。
そこには、黒い煙のような『ヤツ』が、現れては消え、
消えては現れ・・・と、不安定な様相を呈して漂っていた。
『それ』の意識が安定しないのは、『ヤツ』の存在に、原因があるらしかった。
そう思って状況を観察すると、『それ』と『ヤツ』の出現と消滅は、
相反するサイクルで、同期していることが判った。
どちらの『煙』が主体になるのか、迷っているように思われる。
私はどちらでも構わないのだが、白い煙のほうが、親しみがあった。
いずれにしても、『白』と『黒』が、私の前に同時に出現するのは、
初めてのことだった。
そうこうしているうちに、私の『案内役』が決まったのだろう。
白い『それ』が、私に何となく目配せを送ってよこした感じがするとともに、
ふっと地上から消滅した。
残ったのは、黒い煙の『ヤツ』のほうだった。
『ヤツ』は、微妙な雰囲気の『笑い』を私に向けて、
「行こうか?」
と誘ってきた。
黒い『ヤツ』に誘われるのは、初めてのことだ。
物は試しだ。
今回は、『ヤツ』の導きに乗ってみるとしよう。
“ヤツ”の誘いに乗ってみよう・・・
そんなことを考えたのは、一瞬のことだった。
“ヤツ”は、私の意向など無頓着に、
勝手に私を、どこかの知らない世界に連れ出してしまったようだ。
こうなったら、とことん“ヤツ”について行き、
案内をしてもらうことにしよう。
“ヤツ”に責任を押しつけようという魂胆なのだが、
それほど信頼できる相手なのだろうか?
ふと、そんな疑念も過ぎったが、私が何となく彼の誘いに乗ったときから、
私の『それ以降の意志』は無視されてしまったのだから、
信頼もへったくれもなさそうだった。
兎に角、私は今まで私が見たことのない世界(時代?)に、
連れ出されてしまったのだ。
どうにも心もとない存在だが、私は“ヤツ”を見失わないように、
その気配を感じ取りながら、この『別世界』の旅を、楽しむことにした。
『別世界』なのは良いとして、いつの時代のどこの場所に連れてこられたのか、
それさえも判らないのでは、楽しむどころの騒ぎではない。
何があるのか、どんなことが起きるのか、全く予想もできない。
それでは、『この世界』を見たところで、
楽しむ余裕は起きてこないではないか。
楽しむには、何らかの『予備知識』があったほうがよい。
何らかの展開が予想できた方が、『予想外の出来事』にも対処できるし、
その『予想外』を、自分の知識に対比させて、楽しめるというものだ。
そこで“ヤツ”の出番である。
まずは、連れてきた背景を教えてくれそうな場所に、案内してもらうとしよう。
そう思って“ヤツ”の姿を探してみた。
自分の周囲をぐるりと見回すと、“ヤツ”のぼんやりとした影が見えた。
『おいおい、ぼんやりとしている場合じゃないだろう。
しっかりと姿を現して、私を案内しなさいよ。』
意識の下で私は、“ヤツ”に語りかけていた。
縋るような気持ちがあったことは、否定できない。
ところが・・・“ヤツ”の姿は、どんどん薄れていく。
どうやら、私をこの世界に放置するつもりらしい。
『冗談じゃないぞ!』
と、そんな私の気持ちを無視したままで、“ヤツ”の姿は、
ふっと消えてしまった。
まるで“煙”のように。
といっても、元来が“煙”なのだから、いつ消えても不思議はないのだ。
白い“それ”が私を連れ出したときには、元の世界に連れ戻してくれた。
黒い“煙”の“ヤツ”だって、ケリが付けば、
多分、元の世界に連れ戻してくれるだろう・・・多分。
何とも根拠のない期待だが、それを頼りにするほかは無い。
兎に角、“ヤツ”は消えたのだ。
それで、ここはいつのどこなのだ?
私は周囲を、改めて見回した。
人の気配がするが、何とも静かな雰囲気だ。
この雰囲気を、何と表現すればいいだろう。
そうだ。“厳かな(おごそかな)”と言う表現が似合いそうだ。
でも、それだけでは、状況が把握できない。
私はその“厳かな”雰囲気の場所で、事態の推移を感じ取ることにした。
間もなく私の眼前を、若い茶坊主が通り過ぎた。
その場所は、広々とした廊下だった。
だがそれだけでは、まだ状況把握の材料としては、
依然として、状況が把握できない。
時代だって判りはしない。
平成の現代でも、場所によっては、茶坊主くらいはいるだろう。
ん? 待てよ。
あの茶坊主は、髷を結っていなかったか?
平成の時代なら、まさか、髷を結った茶坊主などは、
普通に見られるわけは無かろう。
とすると、少なくとも江戸時代以前に連れてこられているわけか?
もう少し、状況を確かめねばなるまい。
また、近づいてくる人の気配がした。
“気配”なんていう、上等なものじゃない。
床を滑るような静かな音と、衣擦れの音が、確かに聞こえてくるのだ。
そして私の前を横切るふたりの人物は、
丁髷(ちょんまげ)を頭に乗せて、裃(かみしも)を、身につけている。
これはもう、時代劇の撮影か、そうでなければ、
その時代そのものに入り込んだに違いなかった。
江戸時代以前の世界だということは、決定した。
それで、江戸時代以前といっても、時代の幅が広すぎる。
一体全体、いつの時代なんだ?
ふたりの武士は、囁くような声で、話し合っていた。
ズバリと、時代が窺い知れる話の内容だった。
「吉良殿は、もうすぐお帰りになるのかな?」
「都(京都)に行っておいでだったが、
もはや江戸に帰っておられるのではないかな。」
「左様か。浅野殿おひとりでは、このたびの饗応は、
ちと荷が重いかも知れぬので、気にかかっておった。」
「浅野殿も、吉良殿の覚えめでたく、
以前にお仕えしておられ申したゆえ、気にかけるには及ぶまい。」
「それならよろしいが、浅野殿の近頃の様子が、
ちと気にかかり申しての。」
「梶川殿、そなたがお気になさることでもありますまい。」
「そうよのう。吉良殿がお帰りになれば、浅野殿も気分が楽になられよう。」
「そうに違い無いでしょうな。」
え?
吉良殿だって? 浅野殿だって?
それに、梶川殿ときたら、ここは江戸時代の、江戸城“松の廊下”か?
“刃傷事件”が起きる前の“松の廊下”に、私は居るようだ。
幸いなことに、私の気配は、彼らには察知されていないらしい。
ひとつだけ面倒なのは、彼らの時代がかった言葉が、
私には聞き取れないことがあると言うことだ。
ここを、何とかしないと、大事な内容を聞き漏らすかも知れない。
時代がかった言葉を、翻訳してくれる機械はないものか?
そう思ったところに、“黒い煙”の“ヤツ”が、ふと姿を現した。
『厄介なヤツだ。』
そんな意識を私に注いで、瞬間に“ヤツ”は消え失せた。
何が起きたのか判らなかったが、
その後の武士たちの会話が、格別に聞き取りやすくなったところを見ると、
私の意識に、“翻訳装置”のようなものが、仕込まれたらしかった。
兎に角、時代旅行が、これでかなり楽になった。
さぁ、これから起きる出来事を、聞き耳を立てて、楽しみまくるぞ!
浅野内匠頭の“刃傷の原因”は、幕府の処分が早すぎたために、
謎のままになってしまった。
その“謎”の部分が、解明できるかも知れない。
何だか、かなり楽しみなことになってきた。
「浅野殿が『おひとりで』と申されたが、勅使殿の饗応役は浅野殿だが、
ほかにも経験を積んだ院使殿の饗応役に、
伊達殿(伊予吉田藩主)が選ばれておる。
おふたりが力を合わせれば、問題なかろう。」
「まぁ、浅野殿も以前の経験がおありなのだし、
そう気張る必要も無かろうと思うのだが。
高家殿(吉良上野介)も、そのあたりを考慮なされて、
浅野殿を推挙なされたのであろうが。」
「ところがその後で、おふたりの後見役にあたられる高家殿が、
京都に出張なさってしまわれた。」
「浅野殿は、高家殿のお住まいを訪ねては、
いろいろとご教授願っておられたから、心細さが増してしまわれたのだろう。」
「いやいや、何の。それが一因ではあるまい。」
「私も、詳細は存じ上げないが、噂は伝え聞いております。」
「その“噂”のことですよ。」
「吉良殿のお小姓に、ぞっこんだという、あれですかな?」
「浅野殿の“お盛ん”なことは、 つとに有名ですからなぁ。」
「その“お気に入りのお小姓”に、高家殿の留守中、会えなかったので、
フラストレーションが溜まってしまったというわけですかな?」
フラストレーションだってぇ?
江戸時代の堅苦しい言葉が、わかりやすく翻訳されたのは良いけれど、
これはちと、飛びすぎではないのかな?
ま、また“黒い煙”にお出まし願って、このあたりの微調整をしてもらうのも、
面倒くさい。
それほど障害になるものでもないし、受け流しておこう。
さて、話の続きは、どうなることやら・・・。
「浅野殿は、お国にお帰りになられれば、市井の美女を貢がせて、
存分に楽しんでおられるそうな。」
「そうらしいですな。ところが、江戸詰の間は、
奥方(瑤泉院=ようぜいいん)の目が厳しくて、
浮き名を流すわけにはいかない。」
「そこでお小姓で間に合わせたわけだろうが、
その相手に会う機会が少なくなった・・・と。」
「つまりはそこで、ストレス発散ができなくなってしまって、
鬱になられた言うわけですな?」
広い“松の廊下”? でひそひそと語り合うふたりの会話は、
すぐそばで聞き入る私の耳に、明瞭に届いた。
「ところで梶川殿、貴殿のご用件はどうなされましたかな?」
「おっと! 忘れかけておりました。留守居番として、
お使者殿とお会いする時間の変更があるらしいので、
その変更時間の確認を、吉良殿にしなければならない。
そのために、高家殿(吉良)の所在を、探しておるのだった。」
「高家殿ならば、“休息の間”に居られるのではなかったかな?」
「おう、そうか。多門(伝八郎)殿、貴重な情報を有り難うございます。
それでは、急いで吉良殿に会いに参るとしよう。」
梶川は多門と別れて、だだっ広い松の廊下を、
休憩の間に向かって進みかけた。
ところで、このふたりが居る場所は、“松の廊下”で間違いがないのだろうか?
私には、その位置関係がよくわからない。
兎に角、江戸城の廊下は入り組んでいて、しかも広い。長い。
廊下の一角に、控え室やら、休憩所までが、設けられているらしいのだ。
いささか位置関係は複雑だが、
勅使たちは“大廊下休憩所”と呼ばれる控え室におり、
梶川たちは呼ばれたときに備えて、その前の廊下で待機していたらしい。
時間変更を、広敷番頭の土屋勘助正春から匂わされた梶川は、
その真偽を確認するために、吉良上野介に、
どうしても会わなければならなかったのである。
その“時間変更”については、浅野内匠頭には、知らせが届いていなかった。
もともと時間の変更などはなかったのだから、
浅野長矩に、時間変更が伝えられるはずがない。
だが長矩は、『なぜ自分には、情報が伝えられないのだ?』と、
指南役の高家に対して、疑念を抱いたのだ。
上野介の小姓に会えないことも、上野介の嫌がらせだと曲解して、
鬱に加えて癇癪持ちの性格も昂揚して、
長矩は自分の気持ちを、抑えられなくなっていた。
梶川は、公家たちが待機している大廊下脇の控え室に向かった。
高家(吉良)が、その付近で待機しているだろうと予測して、
大廊下の隅に向かって、歩を進めたのである。
梶川は、控え室前の廊下に、問題の顔ぶれをみつけた。
浅野内匠頭と伊達左京亮村豊(さきょうのすけむらとよ
=左京亮は役職・次官)が、並んで座っている。
浅野は勅使の柳原資廉(前大納言)と高野保春(前中納言)の饗応役であり、
伊達は霊元上皇の院使として江戸に下向する、
清閑寺熈定(前大納言)の饗応役だ。
そのふたりが並んでいるということは、
その近くに指南役の高家(吉良)が来ることは、十分に予測できる。
そう思うところに、大廊下の角を曲がったところに、吉良たちの姿が見えた。
梶川は、茶坊主を呼び寄せて、高家を呼びにいかせた。
茶坊主が戻ってきて、梶川に伝えた。
「吉良殿は、老中殿とお話し中であらせられますので、
しばらくお待ちくださいませ。」
「うむ、承知致した。浅野殿も居られることだし、
今後の予定などを話しながら、待つと致そう。」
梶川は、饗応役たちやほかの高家たちが待機する廊下に向かって、歩を進めた。
「浅野殿、伊達殿。このたびはお役目ご苦労様です。」
「や、梶川殿。貴殿も慌ただしそうで、大変でございますなぁ。」
「いや、まぁ、お役目でございますから。
ところでおふたりは、高家殿から接待時間が早まったなどとは、
お聞き及びではございませんか?」
「それが・・・伝聞ばかりで、吉良殿から直接のご指示はござらんのです。
なぜに、我らにはお伝えくださらないのか・・・。」
「そのあたりのことを確かめようと、私が駆けずり回っておりました。」
「高家殿は、時間が押し迫っているときに、何を考えておられるのやら。」
「何か、我らに遺恨でもおありなのか・・・?」
「これ、浅野殿。まだ真偽を確かめておりませんものを、
そのように決めつけるのは、いかがなものでしょうか。」
「浅野殿、ここは落ち着きが肝心ですぞ。」
ふたりは、興奮気味の浅野内匠頭を、なだめようとした。
内匠頭は、梶川、伊達の両人がなだめても、
一向に落ち着く気配を見せなかった。
「いや、この期を捉えて、意趣返しを考えてござるのじゃろう。」
内匠頭の言葉に、梶川が目を剥いた。
「意趣返しとな? それは穏やかならざることではありませんかな?」
伊達がその言葉に続けた。
「浅野殿には、何かお心当たりでもおありなのですか?」
内匠頭は、思わず口走った言葉に、それほどの意味が込められているとは、
自身でも気付かなかった。
ふたりにその部分を指摘されて、興奮の一部が冷めたように、狼狽えた。
だがその心の内を押し包むように、平静を装って、
「心当たりと言うほどのことはござらぬが、
このたびの高家殿のなさりようは、意趣返しの意味でもあるのではないかと、
そう思ったまでのことでござるよ。」
と、その場を取り繕った。
「いやいや、左様でござろう。ま、思い過ごしということで、
納めようではありませんか。」
「そのように、穏便に済ませられれば、それがよろしい。」
ふたりは、事情を感づかぬように、内匠頭の気持ちが静まるのを待つ様子だった。
だが内匠頭の中でくすぶり続けた不満の火種は、
簡単に消えることはなかった。
一時の狼狽が鎮まると、燻っていた火種が、勢いを増した。
その“勢い”は、内匠頭の表情に、ほとばしり出た。
梶川と伊達のふたりは、互いの顔を見やって、困惑気味に軽く頷いた。
内匠頭は否定したが、“意趣返し”と言った意味を、
ふたりはそれとなく察していたのだ。
だがそれでも、この日のこの時に、この場所で騒動を起こされては困る。
内匠頭の火の粉が、ふたりにまで降りかかるかも知れない。
何としても、穏便に済ませなければならない。
しかし、どうすれば内匠頭の気持ちを、抑えることができるのだろうか?
勅使饗応の刻限は、否応なく迫っている。
刻限が近くなれば、高家が姿を現すのは間違いない。
その時に、高家(吉良上野介)と顔を合わせた内匠頭が、
おとなしくやり過ごすだろうか?
彼の性格として、一騒動が起きないとは言い切れない。
『さぁて、どうしたものか?』
ふたりは顔を見合わせたが、これといった対応策は、思い浮かばなかった。
兎に角、状況は抜き差しならないものになっている。
内匠頭から目を離さずに、突発的な状況に対応する心構えを、
持つことにした。
ちょっと待て!
梶川と伊達のふたりは、内匠頭が話した“意趣返し”の意味を、
知っているようだ。
だが私は、その意味を知らない。
意味を知らないのでは、3人の現場に居合わせながら、
私だけが蚊帳の外に置かれた状態になるではないか。
かといって、梶川殿に、その意味を教えてもらうことはできない。
さて、困ったな。
『おい、“煙“! 出てこい! そして事情を説明しろ!』
そう思いながら周囲を見回すと、
私の気持ちを察していたのだろうか。
広い廊下の片隅に、モヤッとしたヤツの黒い姿が浮かび上がった。
『そうかそうか、今までの成り行きを説明してくれるのか。』
私が期待したその気持ちに、不安を抱かせるように、
ヤツの黒い口角が、ニヤリと跳ね上がったような気がした。
しかしこの場では、私はヤツに身を任せるほかはない。
ヤツは広い廊下を這うように流れてきて、私の身体を包んだ。
さて、今度は何をしようというのだろう?
そう思う間もなく、先ほどまでの“江戸城松の廊下”とは、
全く雰囲気の違う場所に、移されていた。
そこがどこなのか、私にはわからない。
江戸城とは違って、柔らかく和やかな雰囲気がある場所だということは、
すぐに理解できた。
時代は、先ほどまでいた“江戸時代”のままのようだった。
その屋敷の庭に面した座敷には、二人の侍が相対していた。
高齢の武士は、吉良上野介のようだった。
そして若い武士は、浅野内匠頭・・・。
え? 浅野内匠頭がここに?
しかも、吉良上野介と、穏やかに談笑しているではないか?
一体全体、どうしたことだ。
そして、ここはどこなのだ?
静まりかえった邸宅は、枯れた植え込みが冬の日射しを柔らかく透して、
豪壮な雰囲気を醸し出している。
江戸時代の屋敷としては、なかなか見事なものだろう。
そしてまた、塀の外の喧噪も、ほとんど聞こえてこない。
冬の風が、日射しが注ぐ障子を撫でている。
吉良上野介が、浅野内匠頭の屋敷を訪ねているとは思えない。
かたや大名、もう一方は旗本という身分ではあるが、
年齢的にも、格式としても、上野介が内匠頭の屋敷を訪ねることは、
よほどの理由がなければ、あり得ないことかも知れなかった。
そうだとすれば、この場所は吉良邸江戸上屋敷のある 呉服橋 だろうか。
「騒がしいところで申し訳ないのう。」
年配の武士が、言葉を発した。
“騒がしい”とは思われないが、現代の呉服橋を思い浮かべるからだろう。
当時の江戸としては、中心部からやや外れているとはいえ、
塀の外を通り過ぎる人々の話し声が忍び込むこともあり、
やや雑然とした雰囲気もあったのかも知れない。
「何の、私の鉄砲州屋敷( 浅野内匠頭上屋敷 )は、静かではありますが、
付近に番所もござらぬ寂しいところで、お城からも遠くて不便を感じております。」
鉄砲州と言えば、築地あたりの、聖路加病院があるところ。
江戸時代は、静かすぎるほどの所だったのだろう。
「広大なお屋敷で、静かで、潮の香りも良いところだそうですな。」
「いや、恐れ入ります。」
「ところで、浅野殿、本日のご用の向きはいかがなされましたかな?」
「早速本題に入らせて戴きますと、高家殿にお骨折り戴きました、
勅使殿饗応役について、今回の細やかな注意点などをご教示戴きたく、
お邪魔をさせて戴きました。」
「その件については、浅野殿が以前にもお役目を無事にお勤めくださったので、
適役であると進言したまでです。」
「前回と申されましても、18年も前のことであり、
私がまだ17歳の折りでありましたから、今でもあのときの所作が、
そのまま応用できますものやら、不安がございます。」
「あのときの饗応役指南は・・・。」
「御指南役は、あのときも吉良殿にお世話になりました。」
「おお、そうであったかのう。」
上野介は、とぼけた表情で、内匠頭をちらりと見やった。
内匠頭の訪問の意図が、饗応役についての指南を仰ぐことにあるのでないことは、
上野介は察していた。
「何かと記憶に遺漏があってはいけませんので、
高家殿に細部を再度、御指南戴きたく。」
「儂がお役目(高家)で留守にするのは、ひと月ほど(25日)のこと。
京から帰ってからでも良かったのではありませんかな。」
「それでは、何かと慌ただしくなりもうそうと存じて、本日お伺い致しました。」
「儂が留守中には、高家肝煎の畠山民部大輔殿に、お世話頂くように、
言い伝えておきましょう。」
「私の御指南役は吉良殿おひとりでありますので、
おふたかたの御指南を仰ぎますと、何かと行き違いが出るやも知れません。
それが気がかりです。」
「そろそろ、本題に入りませんか? 内匠頭殿。」
一瞬の笑みを片頬に浮かべて、吉良上野介が、ズバリと切り込んだ。
「“本題”と申されますと・・・。」
狼狽えた表情を押し隠すように、内匠頭が、上野介に問いかけた。
「儂も、こう見えても忙しい身でのう。ご用の向きは察しが付いており申す。
饗応役の件については、話が済んだと思いまするが、
それよりも大切な用向きについて、お伺いしたいと存ずる。」
「では、私も持って回ったことではなく、お願いをお話し致しましょう。」
何だよ。これからが、この屋敷で知ることができる“本題”なのか?
今までのやりとりは、前哨戦ということか。
この吉良上屋敷で、饗応役についての遺恨とやらが生まれるのかと思ったら、
それは見当違いだったらしい。
これから起こることが、『松の廊下』での刃傷事件の原因になるらしいので、
推移を楽しみに、見ているとしよう。
「ふむ? 本題に入ってくださるか。ではその前に・・・。」
「その前に?」
「これ! 浅野殿に、茶をお持ち致せ。ついでに、儂にもな!」
上野介が、奥に向かって吠えた。
「はい、ただいま、すぐにお持ち致します。」
「ま、茶などを飲みながら、落ち着いて話をお伺い致すとしようか。」
「恐れ入ります。」
二人が居る座敷の襖が、静かに引き開けられた。
茶坊主が、茶を運んでくるものと思っていたが、そこに現れたのは、
15歳を少しばかり過ぎたかと思われるほどの、若武者だった。
『これが、小姓というものか?』
私が小姓を見るのは、初めてのことだったので、興味深かった。
私が知る小姓とは、織田信長に仕えていた森蘭丸といった印象なのである。
もちろん断るまでもなく、本物を知っているわけではない。
森蘭丸ならば、信長の寵愛を受けたと言っても、
明智光秀の軍勢に囲まれながら、華々しく戦った武人である。
ところが、ここに現れた“小姓”は、着飾っているせいではなく、
雄々しさが無いどころではなく、所作それ自体までが、
男性らしくなく、しなやかで、女性と見まがうばかりの雰囲気を、
発散させていたのである。
森蘭丸とは、時代が違うのだから、“小姓”の役割も、
変わって当然なのだろう。
「ご苦労。下がって良い。」
上野介が、小姓に言い渡した。
内匠頭が、襖を閉めて退室する小姓を、名残惜しげに、
食い入るように見つめている。
眼差しに宿る光が、揺らめいているように感じられた。
上野介も、それに気付かぬはずがない。
いや、気付いていながら、わざと彼の小姓に用を言いつけたのだろう。
「浅野殿、今の幡豆(はず)を、お気に召されたかな?」
「吉良殿もお人が悪い。ご存じのはずでしょうが。」
“幡豆”と呼ばれているのが、今の小姓らしい。
「もそっと、この座敷に留め置いた方がよろしかったかな?」
「いやいや、それには及びませぬが・・・。」
「及びませぬが・・・とは? 留め置く理由が見つかりませぬで、帰してしまいましたわ。」
「それよりも、折り入ってご相談がござる。」
内匠頭が、膝をせり出した。
眼差しは、真剣そのものである。
上野介は、その様子を察せぬように、ふと窓の外を見やった。
「冬にしては、温かいのう。」
気勢を削がれたふうに、内匠頭も、障子の柔らかな日射しに目を向けた。
「そうは思いませんかな?」
「は? 何のことでしょうか?」
「浅野殿、少し冷たい風に当たってみませんかな?」
「いや、私は今が丁度良いのですが。」
「冬にしては、温かすぎるようですのでな。」
上野介は、内匠頭の意識が小姓に傾きすぎていることを、
このように揶揄して表現したのだ。
私にもそれが察せられたのに、内匠頭には、その意図が量れない。
「折り入ってのお願いと申すのは、私に幡豆殿をお譲り頂けまいかということ。」
「ふう・・・。」
上野介が、軽く息を吐いた。
私には、それが溜息に見えた。
その上野介の“溜息”には、『呆れた』といった意味が、込められているようだった。
「浅野殿は、お国に帰られれば、
好きなようになされて居られるというではございませんか。
なぜにまた、私の小姓などに、執着なさるのか。」
「江戸には、妻がおります。
妾を持つことには、非常に厳しい妻ですので、我が身を思うに任せぬのですよ。」
「女人ではいかぬと。それで、お気に入りの小姓を側に置きたいと。
こういうことですな。」
「恥ずかしながら。」
「浅野殿のご事情は、あい解った。しかしながら、幡豆の都合も聞かねばなるまい。」
「そこのところは、ご主人である上野介殿のお言葉ひとつで、有無を言わせず・・・。」
「そうはいかぬよ。主従だといっても、幡豆も生身の人間だからのう。」
「そこを、たってのお願いということで。」
「江戸では、そのような具合には行かぬのよ。
幡豆に限らず、『嫌だ』と言われれば、なかなかに難しいものがある。」
「生ぬるい。我が播州では、家老と雖も、
私の一言で蟄居させることもできるものを。」
内匠頭が、留守を守る大石内蔵助を疎んじて、一時要職から外した、
そのことを指しているらしい。
業を煮やしたように、上野介が、内匠頭に告げた。
「田舎とは違うのだよ。お解りくださらぬか。」
「吉良殿は、私を”田舎侍”と申されますか?」
「どのように受け取られようとも、家人の気持ちを重んじるのが、
儂のやりようでの。」
「まずは、幡豆殿のお気持ちをお確かめ願えませんでしょうか?」
この場はとりあえず、自分の気持ちを抑えて、内匠頭が上野介に
繰り返して“お願い”を試みようと努めたようだ。
気短な内匠頭にしては、精一杯の努力といったところだろう。
「浅野殿は、拙宅においでになったのは、何度ほどになりますかな?」
「さあ、どれほどになりますか・・・。それがどうかなされましたか?」
「儂も数えたことはござらんが、片手で数えられるほど少のうはございませんな。」
「私も、気にしたことはございませんが、高家殿に教えを請うために、
幾度と無くお手間を頂戴したことは、御座います。」
「その折に、いつしか幡豆がお気に召したということでありましたな。」
上野介が言いたいことは、私には予想できた。
内匠頭には、その意図が、まだわからないのだろうか。
わからないはずがあるまい。
駆け引きが含まれた対話になっているのだろう。
内匠頭の執着心の強さを考慮して、
上野介が、家人の身の上を気遣っている、と、そんなところなのだろう。
「その通りで御座います。ですから、幡豆殿のお気持ちを、
まずはお確かめ願いたいと、このようにお願い申しております。」
「よろしいかな? 儂は既に、幡豆に気持ちを確かめてあるのですよ。
改めて、確認するまでもありますまいよ。」
「なぜに、幡豆殿は私の元に来ることを拒まれるのか・・・。」
「幡豆は、儂の元で努めたいと申す。それだけで十分でありましょう。」
「理由がわからぬが・・・。」
「『たって、と望まれたらいかが致すか?』と、幡豆に尋ねたことがあります。
幡豆は、『その時には、お勤めを休みまする。』と、思い詰めた様子でしたぞ。」
「そこまで嫌われましたか?」
「いや、嫌ったわけではあるまいよ。
この屋敷に勤めたいと、それだけの理由でしょう。それだけではいけませんか?」
「『勤めを休みます。』と、高家殿は、その我が儘をお許しになるのですか?」
「動かしがたい理由があっての、従わせるようなことでもありませんので、
『我が儘』とも言えんでしょう。
領民の幸せ、家人の暮らしやすさを重んじるのが、吉良の家風です。」
「うむ・・・。」
内匠頭は、言葉に窮した。
「今までのように、浅野殿が拙宅をお訪ねくだされば、
今までのように、幡豆にお会いできましょう。」
「他人事、ですな。」
「長矩殿、ここは江戸で御座いますれば。」
その上野介の言葉には、『うんざり』したという、
ぞんざいな気持ちが、含まれているようだった。
それまでの『浅野殿』の呼称が、『長矩殿』に変わっていることで、
上野介の心情が察せられた。
内匠頭は、その微妙な変化よりも、
『ここは江戸で御座いますれば』のほうに、強く反応していた。
怒りを抑えきれないように、顔を紅潮させて、畳の縁を見つめている。
「これ以上は問答無用と言うことで御座いますか。」
「有り体に申しますと、そうなりましょうかな。」
「問答無用と・・・。」
再び呟いて、内匠頭は沈黙をした。
「長矩殿は、今回のご用の向きは何で御座いましたかな?」
上野介が、内匠頭の気持ちを切り替えさせようと、話題を元に戻そうとした。
「は? その用件は、済ませたはず。これにてお暇致しましょう。」
「また何か、儂でお役に立てることがあれば、是非おいでください。」
「は・・・。」
「饗応役は大役なれど、田舎者の私でも、そう難しいお役目では御座いません。
これまでに教わったことで、あとのご心配には及びません。」
上野介のムッとした表情を眼の隅にとどめて、
わずかに仕返しをした気分になって、内匠頭が立ち上がった。
内匠頭は、心ここにあらずといった、夢の中を漂うような表情で、
そそくさと吉良邸上屋敷をあとにした。
「吉良めが、儂を『田舎侍』と言いよった。」
内匠頭は、そんなことを呟きながら、駕籠に揺られていた。
上野介が、内匠頭の最後の言葉に、どのような“意趣返し”を企むのか、
その心配をも抱きながら・・・。
領国に帰れば、若い女性を身の回りに侍らすことができるが、
正妻が目を光らせる江戸では、妾を持つことは許されない。
そこで、小姓を代用にしたかったのだが、最もお気に入りの小姓は、吉良家にいる。
その小姓の“幡豆”を譲り受けようと、上野介に掛け合ったが、固く断られてしまった。
内匠頭にしてみれば、『恥を忍んで頼み込んだ』のに、
それを無下に断られた、という思いが強い。
爆発しそうな気持ちを、深く鬱積させていた。
その場で爆発させなかったのは、内匠頭としては上出来だった、
と言うべきかも知れない。
その後の“結果”を見れば、“上出来”ではなかったわけだが。
「梶川殿(与惣兵衛頼照)は、浅野殿から、“意趣返し“をうける理由とやらを、
お聞き及びになっていられますか?」
「それとなく・・・。浅野殿からの一方的なお話なので、
客観性には欠けるとは思いますが。」
「そうですか。私も多少のことは聞き及んでおり申すが、
あの程度のことで、高家殿(吉良上野介)が“意趣返し”を企てるとは思えません。」
「『饗応役なら、自分がやりおおせて見せましょう』と、
浅野殿が高家殿に言い放ったという、あの件でしょうか?」
「そうです。その前後のいきさつは、浅野殿が詳しく話さないので、
周囲の者たちの噂話を、統合するしかないのですが。」
「伊予殿(伊達左京亮村豊)も、そのようにお聞きでしたか。
しかし、それしきのことで遺恨を持つほど、
高家殿の器量が狭いとは思われませんがなあ。」
「高家殿とて、そのように言われて良い気分はしないでしょうが、
かといって意趣返しなどと、子供じみたことをなさるお方ではあるまい。」
「そのことですよ。浅野殿のお話には、さらに裏があると・・・。」
「“お小姓の件”で御座いましょう?」
「や、梶川殿もお聞き及びでしたか。」
「この場ではまずいでしょうから、これについては後ほど、
折を見て、ということに致しましょう。」
「そうですな。それよりも、浅野殿の“遺恨”のほうが、気がかりですな。」
「浅野殿のあのご様子では、大事が起きなければよろしいのですが、
ちと心配ですわ。」
「それでは私は、高家殿にご指示を伺って参りましょう。
そろそろ刻限も近いことですから、急いで・・・。」
伊達伊予守が、静かな足取りで、しかも急いで、
廊下を滑るように離れると、少し離れた場所で、
茶坊主に状況を尋ねていた内匠頭が、戻ってきた。
梶川と浅野の二人が、吉良上野介の姿を認めて、
松の大廊下で待つ状態になった。
内匠頭は、上野介から目を逸らさずに、
瞬きを忘れたように、その姿を見据えている。
梶川は、その内匠頭を、気がりな様子で、ちらりちらりと見やっている。
その二人に向かって、上野介が近づいてきた。
「いやぁ、ご苦労をおかけいたしましたなぁ。さて、いよいよ忙しくなりますので、
気を引き締めて励んで下され。」
上野介は、接待時間の変更などについては、全く気にするそぶりも見せない。
梶川は、『自分たちの今までの騒動は何だったのか?』と、
拍子抜けしたように、あっけにとられて上野介を見やった。
「浅野殿も、よろしくお願い申しますぞ。」
殿中のこととて、さすがに上野介の高笑いが響くことはなかったが、
鼻先に『フフン』と、軽い笑いが浮かんだように思われた。
気のせいだったかもしれないが、私にもそう思われたのだから、
気が立っている内匠頭には、さらに敏感に、
上野介の雰囲気が、伝わったことだろう。
一瞬、毒気を抜かれた梶川には、そのふたりの『心の火花』が、
感じ取れなかったようだ。
その梶川の隙をつくように、内匠頭の感情が、一気に燃え上がった。
3人の間の“凍り付いた時間”は、数時間も続いたように思われた。
実際には“一瞬の間”に過ぎないのだが、
上野介の作り出した“惚けたような間”と、呆然とした梶川の“間”に、
内匠頭の“異質な緊張感”が、三人三様の“間”を作り、
それが“凍り付いた時間”を生みだしたらしい。
「わあ! 何をする!」
静かな廊下に響き渡った大声で、梶川は我に返った。
梶川と内匠頭が、上野介を挟むように立っていた。
内匠頭の方を向いていた上野介が、くるりと向きを変えて、
梶川の横をすり抜けるように、逃げ出していく。
その上野介を追うように、小刀を振りかざした内匠頭が、足を踏み出している。
勅使を迎える準備に勤しんでいた、武士や茶坊主たちも、
意外な出来事を目にして、一瞬、身を固くした。
次の瞬間には、3人を包み込むように、そちこちから駆け寄ってきた。
内匠頭の間近にいた梶川も、どのようなことがあろうとも、
内匠頭が殿中で抜刀するとは、想像もできないことだった。
刀に手を掛けただけでも、重大な処罰が下されることは、十分に予想できた。
ましてや、抜刀したとなると、それだけで藩のお取りつぶしは免れない。
一時の感情で、そのような事態を引き起こすとは、
信じられなかったのである。
「この間の遺恨、はらさずに置かぬぞ!」
内匠頭は、まだ息を荒げて、上野介を追い立てようとする。
逃げる高家の背を目がけて、小刀を振り下ろそうとしている。
梶川は、内匠頭に向き合うように、その右腕を押さえ込んだ。
そのままの姿勢で、内匠頭の背後に回り込んで、
羽交い締めにして、押さえるような体勢になった。
事件がそこまで展開したところで、廊下の方々から駆けつけた人々が、
内匠頭を押さえつけて、刀を奪い取った。
「これ! 長矩殿。殿中でござるぞ! 鎮まりなされぃ!」
力強い声で、内匠頭長矩を諫めた武士がいた。
『長矩殿!』と呼びかけたのは、内匠頭よりも格上の武士なのだろう。
内匠頭が、観念したように静かになった。
「上野介はどうなりもうしたか?」
内匠頭が、自分の首尾を確認するように問いかけた。
「命に別状はあるまい。それにしても貴殿は、畏れ多いことをしでかしてくれたものよ。」
「覚悟の上のことなれば、やむを得ません。」
「左様か。しからば、無用な理由は問うまい。」
「ただ残念なのは、遺恨を果たさずに終えたことであります。」
内匠頭は、まだ“遺恨”にこだわっている。
落ち着きを取り戻しつつある様子だが、
それほどまでに“深い遺恨”を抱くに至ったとは、私の理解の範疇を、超えている。
このようにして、松の廊下における大騒動は、
あっけなく終演を迎えた。
しかし・・・それにしても・・・
松の廊下の刃傷事件の真相が、浅野内匠頭の“男色”に端を発したものだったとは。
あまりにもつまらない経緯ではないか。
こんなことでは、後の世にまで語り継がれて人気を博す“忠臣蔵”の、
立つ瀬がないではないか。
例によって、この先のストーリーは、全く考えていません。どんな展開になるか、自分でも予想できません。
どんな展開、顛末になりましても、一切は単なる妄想に過ぎませんので、 クレームは無しということで、お願いします。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- グランドカバー
- クラピアの記録2024年11月定点…
- (2024-11-24 06:27:21)
-
-
-

- みてみて♪お花の画像!!
- 載せたい花が多すぎて、11月も一気載…
- (2024-11-27 01:12:53)
-
-
-

- フラワーアレンジメント
- 秋色のフラワーアレンジ
- (2024-10-29 11:19:30)
-
© Rakuten Group, Inc.