全2943件 (2943件中 1-50件目)
-

おじいちゃんの里帰り(ドイツ、トルコ映画)
戦後の急復興に労働力を必要としたドイツは最初、スペインとイタリアから出稼ぎ労働者を呼んだ。それでも足りなくなると今度は中東のトルコなどに「ゲスト労働者歓迎」のアピールを送り、応えて大勢のトルコ系の人々がドイツににやってきた。主人公もその一人で、監督のヤセミン・サムデレリさんは彼女の父たちの体験を含めてこの映画の脚本を書き、監督した。時は1960年の頃、トルコとドイツの賃金差はかなり大きく、ドイツでの一か月の給料で、故郷で中古車を買ってタクシー業を始めた、などという噂を聞いて続々と出稼ぎ人がドイツへと向かった。現代でも大勢のトルコ系住民がドイツに住んでいることの始まりだ。最初はパパのフセイン・イルマズは単身で働きに行った。そして故郷の妻と3人の子供(男二人、女一人)にどんどん送金した。郵便局か銀行に金を受け取りに来る奥さんの嬉しそうな笑顔を観れば、今までトルコでは手にできなかったくらいの良い給料なのが察せられる。トルコのゲスト労働者たちは一生懸命働いた。そしてドイツで働けることを、喜びと感じた。しかしパパが家族の顔を見るためにトルコへ帰ってみると、、子供らはママに甘やかされて、とんでもない腕白坊主になっている。こりゃ、いけない、子供にはお父さんの威厳が必要だと思ったパパは家族全部を連れてドイツに引っ越した。それでイルマズ家の子供はトルコ人であるが、ほとんどドイツ人のようにして育った。お金のためとはいいながら、故郷アナトリア(東部トルコ)の人間であることを、据え置いて、ドイツ社会で50年暮らした男の人の原点回帰の物語だ。50年後の現代になって、また家族を連れて(孫も入れて人数は増えている)トルコ人たる意識を心から消さないために、トルコに帰ろう、と決めた。ミニバンを買って8人の家族を乗せてさとがえりの旅に出発した。たぶん飛行機に乗ったのだろうが、空港には買っておいた車が用意されていた。このお話で家族の絆とか、母国の文化を知るとか色々教えられることは多い。私はこれを遠方の地に住み着いて働いてすっかりその地に馴染んでしまった人が、故郷の国ともしっかりまだ精神的につながっている事、つまり出稼ぎ地と出身地と二つの故郷を持つ人の、すべての人に共通する物語ではないかと思った。ドイツで暮らす方がレベルの高い生活ができるし、環境も良いだろう。しかしドイツ人とトルコ人は宗教も歴史も文化も違う、真底は異国の民なのだ。子供たちの世代はもうドイツ人であることしか考えられないだろう。それはそれでよい。だが、おじいちゃんは皆に自分たちの出自を忘れて欲しくなかったのだろう。(おまけ)トルコの村々を車で走っていると、ある町のバスターミナルで一人の10歳くらいの少年に出会った。「スィミックはいかが?美味しいスィミックはいかが」と頭の上に大きなお盆を乗せて売っている。ドーナツのチュロの輪っか型のお菓子のようだ。お祖父さんは沢山かってその子は喜んだ。小さな子供に働かせてというドイツ流の意見が出たが、少年の屈託ない笑顔と仕事を楽しんでいるような元気さを見ると、トルコではこれでいいんだと思えた。たちまちイルマズ家の孫のチェンク少年と仲良しになった。
2015.02.06
コメント(0)
-

ベツレヘム(イスラエル、ドイツ映画)
ベツレヘムという街はエルサレムから10キロほど離れた街で人口3万、大きなビルこそないが、中心部は住宅が密集して、賑やかだ。今はパレスチナ解放自治区に入っている。ここに住む17歳の少年サンフールの物語だ。最近、イスラム過激派というと、かなり印象が悪くなっているが、ここパレスチナでは対イスラエルのアラブ人組織は今に始まったことではなく、歴史は古い。二つの名前の組織が登場するが、その一つはエルサレムで自爆テロを決行し、エルサレム市民が数十名死んだ。犯行声明を出したのは組織のリーダーでサンフールの兄のイブラヒムであった。イブラヒムの身はイスラエル警察の追うところとなり、彼は地下に潜伏した。イブラヒムと連絡が取れるのは弟のサンフールだけ。毎週、木曜日にあって活動資金を渡していた。サンフールの身に悲劇が起きる。実はサンフールは兄には忠実で信用できる部下であったが、片や敵イスラエルの情報部のスパイでもあった。なぜこんな複雑なことに?訳は後でサンフールが泣きながら告白するが、選択の余地のない結果だった。サンフールとつながるイスラエル情報部のラジはサンフールの人柄をよく知っていて、身内のような愛情を抱いていた。連絡役の弟をたどってアブラヒムを逮捕せよとの署長命令が出てラジは行き詰まってしまった。丁度サンフールは地元の悪童と肝試しの撃ち合いをやって腹に怪我してしまう。彼は10キロ歩いてエルサレムの病院に行き、ラジに連絡を取った。厳しい父にバカな肝試しで怪我したというと叱られるからだ。そしてラジは思いついた。このまま木曜を通過させよう、怪我が分からなくなるまで、ヘブロンの叔母の家に行ったら良いと、サンフールに教唆した。こうしておけば金を受け取りにアブラヒムは自分で出てこざるをえないし、サンフールを巻き込むこともない。そしてイスラエル警察軍はアブラヒム逮捕に向かった。アブラヒムがいよいよ待ち合わせのマーケットに現れるところはスリル満点だ。長い闘争生活でやつれ顔のアブラヒムが現れた。たちまち追手が彼を追う、彼はある家に逃げ込んだが、その家は四方を壁に囲まれた出口にない家だった。中2階の暗い屋根裏に上がって身をひそめるアブラヒム、下の部屋の戸口に見える狙撃兵、壁の穴から手りゅう弾を投げ込まれアブラヒムは絶命した。アブラヒムの遺体を二つの組織が取り合うなど、パレスチナの複雑さがうかがえる。老父はいかに殉教者といわれても嘆いた。サンフールは急いでヘブロンから駆け戻ったがすべて終わった後だった。もう、パレスチナ、イスラエル問題の奥の深い怒りや恨みがあちこちに噴出して見ていても、心苦しくなるくらい。この後の顛末も、語りたくないほど悲しい。復讐の連鎖が増えるほど、深い傷跡が増える。日本人からは遠い出来事のようだが、この物語でパレスチナの問題を少しでも多く知ることができた。(おまけ)イスラエル警察軍が解放自治区に入ると、、、何しに来たか察した群衆がばらばらと集まってきて、軍の車に投石を始める。防弾ガラスの丈夫な車だが、車外の兵士は投石の直撃を受けた。イスラムの組織の要人を逮捕に来たと分かると、市民の方から銃の発砲が起きてイスラエル兵士は倒れた。「早く終えて撤収しろ!」と本部は躍起になっていた。
2015.02.04
コメント(0)
-
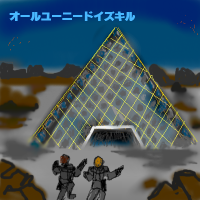
オール・ユー・ニード・イズ・キル(アメリカ映画)
何とわかりにくいタイトルだろう。別のタイトルとして「エッジ・オブ・ツモロウ」「ライブ・ダイ・リピート」というのもあるらしい。この二つは中身にあっているように思うがタイトルとしてもう一つピンとこない。調べてみるとこの原作は日本のライトノベルで桜坂洋さんという人が書いていて、その小説の名前が「オール・ユー・ニード・イズ・キル」。日本ではこの題名で知られていたのだった。主人公の人格なども原作の通り、弱虫から段々強くなって行くといういきさつは小説通りだとか。わきの人物はかなり置き換えられている。そのころ、地球は謎のエイリアンの攻撃でほぼ壊滅状態、ヨーロッパ大陸は破壊され、かろうじて島国のイギリスが残っていて抵抗をしていた。何しろエイリアンの破壊力はすごい。普通の武装ではあっという間にやられるが、強力な戦闘スーツが作られ少しはましになった。戦闘スーツに身を包んだ美女リタ(エミリー・プラント)が目覚ましい働きを見せ、「ジャンヌダルク」とあだ名されていたのだが、彼女をもってしてももう大陸からの侵入は阻止できないだろう。明日の総攻撃に備える基地にトム・クルーズが着任する。危険は大嫌いのトムだが、否応なくノルマンジーかドーバーカレー海岸かに連れて行かれるが、オタオタする間にエイリアンにやられて、あっけなく死亡。トムは開巻早々死んだ!トムは死ぬとき無我夢中で自爆地雷を爆破した。相手のエイリアンは粉々に吹っ飛んでトムはエイリアンの発する青い液体を浴びて、そこで死んだのだが、、、はっと気が付くと彼はまだ出発前の基地に居た。こうして何度も死んでは生き返りを繰り返すうち、彼はいろいろと学習し戦い方が上手くなっていった。これから何が起きるか分かっているからだ。信じられないほど勇敢な女戦士のリタも同じ体験をしていたのだった。もしここで死んでも、気が付けば過去の時間に生き返っていて、また戦いを繰り返せる、だから勇敢になれるのだった。トムが弱虫兵士からまわりも驚く勇猛兵士になったのも、原因はそこだ。時間をワープして何度も繰り返せるのはエイリアンの根源のボスエイリアンのなせるワザであるということから、トムとエミリー=リタはある作戦に出た。エイリアンの巣食うルーブルのピラミッドの地下へと降りてゆく。という、大変込み入ったお話で、ちょっと分かりにくいところもあるが、面白かった。アクション劇としては蜘蛛かヒトデのようなエイリアンと戦闘スーツの人間の戦いで別に目新しいところはない。要はストーリーの珍奇さだ。エミリー・ブラントはミッシエル・ロドリゲス顔負けの筋肉モリモリの女戦士で、格好良い。媚の無い個性が似合っている。(おまけ)なぜか同じ時間を繰り返すというストーリーは1993年の「恋はデジャ・ブ」が何といっても思い出される。ビル・マーレイの根性の悪いお天気キャスターが、罰が当たって(?)2月2日を何度も繰り返す。朝、目覚まし時計が6時に鳴ると、その日もまた2月2日、今日も田舎町の広場で、彼の言うところのくだらない「地ネズミ祭り」をしなければならない。道中起きることもいつも全く同じ、何度も同じ日を繰り返してゆくうち、時間は変わらなくともビル・マーレイ自身が変わってゆく。相手役のアンディ・マクドウエルが素敵だった。彼女どうしているかな?
2015.02.02
コメント(0)
-
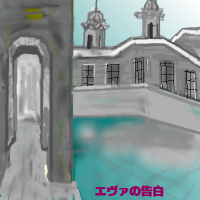
エヴァの告白(アメリカ映画)
ポーランドから移民船に乗ってやってきたエヴァ(マリオン・コティヤール)という若く美しい女性。彼女をめぐる二人の男(ホアキン・フェニックスとジェレミー・レナー)の物語のようである。けれども私は本当の主人公はニューヨーク沖にあるエリス島ではないかと思う。映画はエリス島に始まってエリス島に終わる。エリス島は今は観光施設になっているが、過去には大切な場所であり、19世紀末から約60年間移民局が置かれおそらくフル稼働していた。移民はまずこの島に上陸し、ここを通ってアメリカ本土に入った。長い苦しい船旅の末、左の島に自由の女神が見える、そしてエリス島がある、アメリカに着いた!と感慨無量だっただろう。1200万から1700万人がここを通って入ったといわれている。エヴァはその中の一人であろう。監督のジェームス・グレイの先祖も迫害を逃れてやってきたユダヤ人で彼のお祖母さんかひいお祖母さんかがエアヴァの原型になっているとか。1921年にエヴァは両親が戦乱で死に、妹と苦労してアメリカに来た、英語が話せるのが強みだ。だが、希望を持ってきた人も2パーセントの人は母国へ送還されたという。当座の生活費がないとか引受人がいないとか理由は様々だが、せっかく来たのに入れてもらえなかった。入国審査は簡単でわずか29の質問(名前、年、故郷の名など)に答えればよいというのに。エヴァと妹マグダは妹が病気であるので隔離され、エヴァはお金もなく迎えの叔父も来ず船中でトラブルを起したというので入国拒否された。必死で係官にすがるエヴァに助けの手を伸べた人物ブルーノ(ホアキン)がいた。移民を助ける団体だというが、どうもいかがわしい、ためらったがこんな場合彼にすがるしか手立てがない。こうしてエヴァはブルーノのバーレスク劇場の出演者になった。クイーン地区らしい下町に或る劇場は酒は表向きでない(1921年で禁酒法だったから)踊りがあって後で希望の女性に紹介するという宿であった。妹をエリス島から出すためにお金を稼ぐ、、どうのこうのといってられなかった。ブルーノも移民で来た男、その従兄の芸人(ジェレミー・レナー)も移民出だ。劇場の女優もオーナーもすべてそうだ。ブルーノと従兄に愛されたエヴァ、ホアキン・フェニックスとジェレミー・レナー、なんて素敵じゃない、なんて言わないで。二人は一筋縄ではいかないほとんど悪党で、ずるく、嘘つきだ。純粋なエヴァは二人のウソに翻弄されるが、ウソの中にも真実があった。ホアキンの最後の誠意のおかげでエヴァとマグダの姉妹はカリフォルニアへと旅立つ。マリオン・コティヤールが今までで一番きれいで良い。(おまけ)エリス島は石造りの大きな建物が立ち並ぶ小さな島だ。今は観光客以外は人影もなくその少し黒ずんだ古びた建物の姿をさらしている。アメリカに来ても希望が目も前にころがっているわけではない、苦労の連続が待っているわけで、移民で来て知らない国で生活するのは大抵のことではない。ブルーノや従兄の生きざまも理解できる。
2015.02.01
コメント(0)
-

パークランド ケデネィ暗殺真実の4日間(アメリカ映画)
パークランド病院、何の変哲もない地方都市の病院がアメリカじゅうの注目を浴びるようになった。1963年、11月22日、テキサス州ダラスを訪問したケネディ大統領が狙撃され急きょ、担ぎ込まれたのがパークランド病院だ。誰か重要人物が来るらしいというので、睡眠不足の若い研修医(ザック・エフロン)は休む間もなく搬送を待ち受けたが、やってきたのは頭を銃弾で打ち抜かれた大統領で、ジャクリーン夫人も手を血まみれにして、降りてきた。夫人の手の中には大統領の頭蓋骨のかけらが握られていた。まだかすかに心拍が感じられたので、上の階に居た外科医も駆けつけ必死で蘇生処置がとられたが、大統領の命が戻ることはなかった。まずこの緊迫した救急治療室の様子が生々しくて迫力がある。驚き慌てたのは側近だけではない。地元のFBI支局の面々、シークレットサービスダラス支局の面々も目の前で行われた暗殺に呆然とした。メンツも何もあったものではない。なぜダラスで?と彼らは思ったであろう。この映画は側近の人、病院の医師、警察の人、ジャーナリスト、FBIの人、警備会社、などの大勢の関係者の群像劇になっていて、ドキュメント風に描かれている。間もなく容疑者リー・オズワルドが逮捕されると、今度は兄であるロバート・オズワルドの視点にピントが絞られてロバートとリーの兄弟が中心になる。が、逮捕後輸送されるときオズワルドは至近距離で撃たれまたパークランドへ運ばれる。重要人物二人がこの病院のERで死んだ。映画は登場人物が錯綜し、観ていて慌ただしい。でもこの4日間はアメリカの誰もが何も手につかないくらいに浮ついた動揺状態だったのだろう。その雰囲気を表現しているならば映画は良く出来ている。病院のチーフ看護師のマーシャ・ゲイ・ハーデンは仕事柄落ち着いていたがやはり動揺は隠せない。マーシャは存在感あり。逮捕されたリーの兄のロバート・オズワルドは穏健な性格の全く政治には無関心の市民だ。演じるジェームス・バッジ・デールという俳優が地味ながらよい味を出している。シークレット関係のビリー・ボブ・ソーントンは相変わらずの不敵な存在で、目立っている。大統領がワシントンDCへ送られるとなって、監察医が異議を唱えた。この事件はテキサスで起きたから州法どおり、テキサスのおいて調べると言い張ったが、説き伏せられた。いろんな経緯がもしそうしていたら、とかこうしていたら、とか後になって想像できるが、今となっては遅い。犯人について、真相について、黒幕がいたかなどの詮索は別のお話で、映画としてはかなり生々しく忠実で、忠実すぎてやや細かすぎるという感がある。ともかく驚きの4日間の出来事だ。(おまけ)ダラスの中小企業の社長(ポール・ジアマッティ)はその日、自慢のコダックの8ミリカメラを手にパレードを待っていた。「そら来たぞ!」とカメラを回していると、なんと、目に入ったのはオープンカーのケネディが倒れるところだ。約30メートルの距離から撮ったフイルムは貴重なものとされたが、彼はショックでもう2度とカメラを手にしなかったそうだ。
2015.01.30
コメント(0)
-

ヴァチカンで逢いましょう(ドイツ映画)
マリアンネ・ゼーゲブレヒト、、スクリーンに姿を観なくなってから何十年にもなるのに、すぐにあゝあの人か、と思い出せるのは大したものである。いかに彼女の個性とか容姿とかが特別観客の印象に残っているのかが分かる。彼女はあまり変わっていない、最初からこんな感じだった。全体にずんぐりふくよか。しかし彼女が画面に現れると不思議にもひきつけられて彼女に見入ってしまう。もう一度姿を見せてくれて嬉しい。カナダに住むドイツ人の家族が中心だ。長女のマリーは老齢で一人暮らしになった母(マリアンネ)を心配して自分の家庭へ連れてくる。しかし単なる思いやりだけではなく、母の家を処分して、落ち着いたら、老人ホームに入ってもらうつもりだ。つまり母の財産も自分が管理して、母に関する心配をなくそうという利己的な考えも充分あった。だが母には母の考えが。亡き夫と過ごした家を処分して身軽になったら絶対ヴァチカンへ行って法王様にお会いする、という計画をずっと胸に温めてきた。とうとうその時が来た、決行あるのみ!そして舞台はイタリアへ。ローマにはすでに孫娘が留学していて大学生活しているはずだ、はずだった、が行ってみると驚きの生活があった。聞いてきた住所には、ヒッピー的な若者つまり自由人のヤングたちが住んでいて、孫娘はそこで大学を辞めてロック歌手と同棲していた。マリアンネ祖母ちゃんはそんなことよりもヴァチカン参詣が第一希望だ、成るか?法王様に謁見して祝福を授かることが。つまり孫娘の変化ぶりよりも、もっとずっとマリアンネ祖母さんの方がローマで大変化、大変身をするのである。ローマで次から次へと彼女の身に起きる事件がユーモラスかつスピーディに描かれ、コメディ味のドラマとして大いに楽しめた。マリアンネと知り合うイタリア男を代表するような不良ぽい2枚目老人にジャンカルロ・ジャンニーにが扮し、彼が結構笑いを生んでいてマリアンネと良いコンビだ。法王様に逢いたいというものの、マリアンネの信仰はいわゆる敬虔な信仰ではない。カトリックは彼女の一種の生活習慣であり、「私のベネディクトちゃん」などと言ってるように、法王を崇めているのでなく、まるで友達扱いに思っている。まえから逢いたかったが遠くにいて会えなかった偉い地位の友達ということか。現代の信仰はこれで良いのかも。ドイツからカナダへ行ってイタリアに来る、多分イタリアに住み着く。本人はドイツ人意識を持ってはいるが、異国に移っても定着できる能力を持っている人のお話なのだ。ドイツも良い、カナダも良いが、イタリアも面白いところ。こんな幅広い移住生活をしてみたいが、私には無理だ。(おまけ)食べ物は母国の味が一番良い。マリアンネ祖母さんはウイーン風カツレツやジャガイモ料理やコケモモソースでおいしそうな料理を作っていた。ウイーン風カツレツはかなり量のバターを溶かして浮かして作る。
2015.01.27
コメント(0)
-

ニューヨーク、バーグドルフ魔法のデパート(アメリカ映画)
ニューヨークにはメイシーズやブルーミンデールやサックスフィフスアベニューやバーニーズなど名前をどこかで聞いたことがあるデパートがいくつかある。しかし5番街の通りにに面して建つワンブロックの大きな建物の中を占めるバーグドルフ・グッドマンというデパートは他を引き離して超高級なのだ。このニューヨークで一番高級なデパートに関するドキュメンタリー映画である。威厳ある入口から中に入ると、香水、靴、ドレスが目に入ってくるが、ディイスプレーはいかにもという感じのスマートさ、洗練されていて、態度の良い店員が、さりげなく客を迎える。別に良い服を着た金持ちそうな客でなくともその接客はバーグドルフならではのあしらい方で決してバカにしたりはしない。今や伝説になっているらしいが、ある日、ホームレスのお婆さんが紙袋を下げてやってきて、ウインドウのセーブル(青テン?)の毛皮のコートが欲しいという、「お金はあるの?」などという失礼なことは言わない。丁寧に商品を見せると紙袋から札束を出して買って行ったという。こちらでは商品を買ってくれる人は誰でも大切なお客様なのだ。今のはごくまれな一例であってここのお客はアメリカでトップのセレブが多い。エリザベス・テイラー、ジャクリーン・ケネディ、バーブラ・ストレイザンド、ライザ・ミネリ、ウーピー・ゴールドバーグなどなど。一回の買い物金額も目玉の飛び出る高額だろう。毎日のように超金持ちがやってきて、庶民感覚では考えられない金高の買い物がされている、これが普通に行われるのがバーグドルフデパートだ。以上からデパートはデパートでも日本の百貨店とは全然違うと分かる。庶民が来て、ささやかな非日常の時間を過ごして、ご飯を食べて、新しい服の一枚も買って、地下で美味しい夕食のおかずを仕入れて地下鉄で帰る。これが日本のデパートの割合普通のあり方だ。だから明るく楽しく、心がときめく空間が必要だ。日本でもデパートが次々改築されて立派になるにつけても段々高級感を出すことに向かっている。最終がバーグドルフか?でもここまでは必要ない。年末ジャンボで数億円当たればバーグドルフヘ行っておもいきり買い物できるかもしれないが、まず縁のない世界だ。バーグドルフ設立の歴史から始まって、ここで売らせてもらう特権を得たデザイナーたちの意見とか、デザイナーを発掘してくるバイヤーの意見とかが披露されるが、すべて「ウチは最高にススンデいる」という意識が見え見えで、ちょっと辟易するが、これくらいのプライドの高さがこの店を特徴づけているのかも。(おまけ)日本の愛すべき百貨店とは別物だが、こんなところもあるのかと勉強にはなった。バーグドルフに食堂はあるようだが、地下の食品売り場はもとよりない。日本のデパートが呉服屋から発祥したようにデパートの売るべき商品は衣服なのだ。
2015.01.26
コメント(0)
-
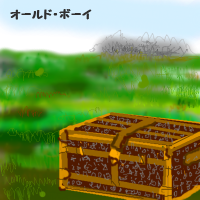
オールド・ボーイ2013(アメリカ映画)
日本のコミック(土屋ガロン作)が韓国でまず映画化され、アメリカでリメイクされた、という珍しい経歴のお話だ。何しろ、そのストーリーたるや特異で異常、普通人の感覚をはるかに離れている。ゆえにどちらかというと常識人の日本人の手に余って、他国で作品が出来たのかも。パク・チャヌク監督に代わって今度はスパイク・リーが監督した。難しいことに挑戦するのが好きなリー監督のこと、意欲満々さがうかがわれる。主人公はチエ・ミンシクと少し雰囲気が違うジョッシュ・ブローリンだ。謎かけのような筋がきなのでほとんど何も言えないが、なるべく白紙で見た方が面白い。リー監督の選択は間違っていない。ミンシクよりもブローリンの方が似合っているように思う。広告会社の幹部という地位まである人だが、普段からだらしない。酒を飲むとどんぞこまで泥酔し、暴言、暴行が無意識のうちに爆発し、とても危険な危ない男だ。この性格が物語の素になっている。彼は監禁されるが、その住居は閉鎖されてはいるがトイレ、バス、食事、睡眠、空調に至るまで充分な生命維持の設備がされている。韓国版では薄汚れたタイル張りの共同浴場のような空間だったが、今度はだだっ広い四角の部屋といった感じ。髭も髪も伸び放題になって、ブローリンはミンシクと見分けがつかないくらいになる。でも健康は維持して20年がたつ。そして突然草原の真ん中でトランクに入れられていた。彼はトランクから出て行動する。なぜこうなったのか?(いけない!こんなにもしゃべりすぎた)ジョッシュ・ブローリンの激しい暴力性が発揮され、ストーリーは真実の方角へとだんだん向かってゆく。20年費やしても人の基本的性格は治らないものなのか。何度誰が作り直してもショックなストーリーだから、比べるのも難しいが、結構ひきつけられて最後まで見た。(おまけ)前作では、監禁した関係者の道筋を探るのに、毎日食事として差し入れられていた餃子の味を頼りに探し始めた。今回はアメリカだから別の食べ物になっているかな、と思ったがやはり餃子だった。ひとくちに餃子といっても少しづつ各店で味が違う。20年間食べ続けた餃子!味は忘れない。
2015.01.24
コメント(0)
-

グランド・ブダペスト・ホテル(ドイツ、イギリス映画)
ウエス・アンダーソン監督の今迄での最高傑作だ。彼は若いのでこれからはもっとすごいのが出来るだろう。ヨーロッパのど真ん中の山の中の名門ホテル、グランドブダペストホテルで繰り広げられる華麗なドラマ、多彩な登場人物たち、でもどこか現実のものとしては影が薄く、幻の物語、影絵のようだ。つまりこれは消えてしまった古いヨーロッパ文化へのオマージュだろう。1935年から始まっていても、この優美なホテルには第2次大戦もヨーロッパの戦火も及ばない。ここは下界の嵐はこないが、すでに文化の灯は消えて残るはほのかな残照のみ。ヨーロッパ社会が作った金持ちと使用人の存在が作る特別の甘美な世界がここにあるし、それはかっては確かにヨーロッパにはあった。テレビドラマでもてはやされている「ダウントン」シリーズもひょっとしたらそういうものへの憧れなのかも。今だってヨーロッパには文化がある、立派なホテルがあるといえるが、近代科学の世の文化と、昔の文学芸術中心の文化は違う。その前世紀の遺物的な古く黴臭く美しいホテルに住まう古く懐かしき人々の織りなす物語を楽しんだ。主人公のレイフファインズ、Fマーリーエイブラハムはじめジュードロウ、エドワード・ノートン、マチュー・アマルリックらは喜んで小さな役でも引き受けただろう。「ダージリン急行」「ムーンライズ・キングダム」も忘れられないが、あらたに「グランドブダペストホテル」が脳裏に加わったのは映画ファンとして何よりのの喜びだ。(おまけ)シュテファン・ツヴァイクにインスパイアされたとあるが、そんな匂いがこの映画にはある。ビル・マーレイ、ジェイソン・シュワルツマンの二人の顔がないとアンダーソン映画観た感じがしないが、もちろん、二人は出ている。
2015.01.23
コメント(0)
-

それでも夜は明ける(アメリカ映画)
1862年アメリカの奴隷解放令が成立した。この映画の時代は直前の1841~1853年までの12年間を描いている。北部と南部では黒人に対する見方がずいぶんと違っていたことが分かる。北部では自由黒人という身分が存在し職業的な制約はあっても技能を認められれば充分優遇されていた。主人公は優れたバイオリン弾きだったので、黒人と言えども市民生活はほとんど白人と変わりなかった。だがこの当時のアメリカ社会には大きな危険が潜んでいた。小遣い稼ぎにと軽い気持ちで遠出演奏に出かけたソロモン・ノーサップはまさか自分という「人間」が「一つの商品」として売られるとは思いもしなかった。眠り薬でも入っていたらしい酒を呑まされ、目が覚めてみると南部へ向かう奴隷船の中だった。こうしてこの後12年間にわたる奴隷暮らしが始まった。監督はカリブ海の島国出身のアフリカ系のステイーブ・マックイーンで、ソロモン役はキウエルティ・イジョフォーという人だがこの人がとても好い。人格の良さとか頭の良さが感じられ、苦難に耐える精神の強さも見せてくれて、良い俳優だ。リドリースコット&ラッセル・クロウ的にマックイーンとコンビのできているマイケル・ファスビンダーが南部の綿花農場の主人で熱演の怪演、奴隷にに対して異常で横暴な狂気じみた心を持つ南部人に扮する。彼のもとに居たらいずれ殺されると感じたソロモンは何とか北部の友人に連絡して、助けてもらおうとしたが、その手紙一本すら誰かに託せない。あきらめかけたころ、やっと願いがかなう。監督の出身地のカリブ海地方にも北アメリカ全土にも多くの黒人が住んでいる。彼らの先祖は別に来たくて来たのではないだろう。無理やりにアフリカ大陸から連れてこられた人たちの子孫だ。アメリカの歴史に消すことのできない問題を感情的にならず描いている映画で強い感動を受けた。しかしマックイーン監督は美術的には素晴らしいが、話のつなぎ方などにちょっと喉の詰まりそうな感じのするところがあり、そこが気になった。(おまけ)最初のご主人が林業の大地主のベネデクト・カンバーバッチだ。彼はソロモンの能力を認めていたが、運悪くソロモンが農場の白人監督官の憎しみを買ってしまったため彼を売る。こうなると暗闇に隠れて目の届かないところで、いくらでも奴隷を殺せる立場の監督官の下では危険だ。
2015.01.21
コメント(0)
-

ハミングバード(イギリス映画)
ジェイソン・ステイサムが久々に古巣のロンドンの下町に戻る。現代のロンドンの下町では、どっと外国籍の人が増えた。ジェイソンが用心棒兼カツアゲ屋として雇われるのが中国人、彼が助けられる修道院のシスターがポーランド人、と見知らぬ国の人ばかりになっている。そして昔なら悪党の一人ぐらい姿を隠すことはたやすい街だったのに、表通りには無人監視カメラがあって、姿をとらえられると脱走兵であるステイサムは逃げなければならない、世知辛い世の中だ。そもそもジェイソンが逃げなければならなくなったのはかってアフガンで私的な怒りに任せて現地人を殺して、その場をハミングバード(無人監視偵察機)に写されてしまったからだ。如何に部下を待ち伏せでやられたからと言って、無実のアフガン人を殺すことは軍法会議ものだ。こうして彼は本名も使えずホームレスの中に交じって暮らしていたのだが、、、いさかいがあってジェイソンは屋上のある家の天窓から誰かの家の室内に侵入する。かなり金持ちの家だ。独身男らしいインテリアだが、飾ってある写真はどうも普通でない。明らかにゲイの人の趣味である。だから金はあってもこんな下町の隠れマンションみたいな家に住んでいるのだろう。喧嘩で怪我したジェイソンにとってありがたいことにその家の主は10月まで留守にすると留守電にメッセージが入っている。約半年以上を無断で住まわせていただける好都合な家だった。いつまでもこの家の金で生活できない。彼は仕事に就いたがそれは中国人の食堂の皿洗い兼用心棒兼カツアゲ屋兼殺し屋という物騒な仕事だった。荒稼ぎはできた。さてこのような状態の彼に一つのなすべき事柄が起きる。ホームレス時代に親しかった少女は娼婦にされ無残に殺された。復讐を誓う彼だった。そして相棒というべき人が何と修道院のシスター、クリスティナだ。ジェイソン・ステイサムと修道女、考えられないほど合わない存在のように思えるが、無料配布の食事をもらったころから互いに顔は知っていた。二人のやり取りが面白い。ジェイソン・ステイサムのように人気があって次々出演する人は作品の選択が今後の方向を決するので大切だ。この映画は方向として間違っていない。彼の大暴れはあの「アドレナリン」シリーズで頂点に達して、その後、徐々に暴れるよりも中身重視の作品になりつつある。この映画でも少しは暴れるが、むしろ怪しげな暗黒社会での彼の動き方に重点が置かれ、唯一の理解者のシスターとの淡い恋が味わいを添えている。お互いに、また追われる脱走兵の身分と、アフリカへ転勤する修道女の身分に戻って別れたが、その最後の場面は悲しく美しい。劇場の前の深夜の広場の路上に座る二人。まるで聖母マリアの膝に泣き伏す罪びと、または「嘆きのピエタ」とも見えた。二人ともいわゆる型通りの信仰の人ではない。しかし神の存在が信じられない人間同士でも、罪びと同士の許し合いの涙の贖罪があった。ちなみにジェイソン・ステイサムの泣きべそ顔(あまり似合わない)は初めて見た。(おまけ)勝手に見知らぬ金持ちの留守宅の間借り人になったステイサム。ホームレスから脱して身ぎれいにして、その家にあった背広を着ると、別人のよう。「モデルかい?」などといわれていた。それにしても「ハミングバード」って優しい名前に似合わず恐ろしい機械だ。そしてロンドンの下町も様変わりしたものだ。
2015.01.07
コメント(0)
-

あなたを抱きしめる日まで(イギリス映画)
離ればなれになった我が子を探し求めるお話で実話だとか。いつまでも子供を忘れず思い続ける母の心が痛ましいというところはメロドラマ要素なのだが、全体は全く社会的に位置の違う年齢も違う二人が一緒に旅をするロードムービーでもある。一人はテレビで国中に名の知れたジャーナリストのスティーブ・クーガン、もう一人は看護師として50年間働き続けた庶民階級の主婦ジュディ・デンチだ。大学を出て知能的な仕事に就き、付き合いもそれ相当の人たちとしているようなクーガンのような人と、一介の庶民のオバサンの間の開きはイギリスでは日本よりもはっきりしている。ほんとなら一緒に旅行することなどあり得ない。初めて飛行機に乗るらしいデンチは本来ならエコノミーに乗るはずだが、クーガンが取材費用をもったのでビジネスクラスになった。何かに付けて物珍しそうな態度のデンチおばさんだった。事の起こりは或るパーティでクーガンがケイタリングサービスの女性に話しかけられたこと。その女性の母親は50年前に彼女から取り上げられて養子に出された赤ん坊の息子の行方を知りたがっていた。赤ん坊と彼女が世話になっていた修道院では記録がなくて調べられない、とすげなく断られ、探すすべもなく困っていた。ちょうど仕事のポストをなくし暇そうなクーガンに何とか調べて欲しいと頼んだのだが、、、。第一線の政治関係のニュースを担当していたのに、三面記事か!とクーガンは乗り気でない。しかし知り合いの雑誌編集長から面白い記事になるとけしかけられやる気になった。そして経緯を調べてゆくうちに、昔の出来事ながら驚くべき事実が浮かび上がってくる。スティーブン・フリアーズ監督の作品で、クーガン演じるマーティン・シックスミス氏の取材した原作小説があり、主人公の中年(老年?)女性がジュディ・デンチとくれば安心して見ていられる映画だろう。しかし我が子捜索の旅は1転2転、結構スリルに富んでいて飽きさせない。立派なのはジュディ・デンチだ、御年80歳にして若い女優よりも華があり、魅力的だ。インテリクーガンから見ればバカみたいなことで喜び、たわいないロマンス小説を熱読し、会話はかみ合わないように見えて、結構しっかり世の中を生きてきた人間の物の味方と意見があって、クーガンも侮れず、それどころか彼女のもつ良さに感心し、階級を超えた親友の境地になる。この映画の面白いところだ。お互いにちがった生き方をしていても、相手を知って相手を認める、子供の行方よりも私はここが面白かった。ちょっと腹が立ったのは修道院の取った態度だが、もう今はこんな悲劇はなくなったであろう。未婚の母となった少女たちがアイルランドの修道院のランドリーできつい仕事をさせられていたことが出てくる。(おまけ)デンチがクーガンと相談するのに指定したレストランはいわゆるファミリーレストランらしく、サラダバーがあった。クーガン氏は戸惑って手が止まる、デンチおばさん嬉々としてサラダ大盛り取り、ファミレスというのは庶民の物なのか?
2015.01.06
コメント(0)
-

プリズナーズ(アメリカ映画)
アメリカ東部の田舎町の静かな住宅地、今日は感謝祭の休日とあって、町の家々には明るい灯火が輝き、ゆったりした雰囲気に包まれていた。仲の良い2家族が集まって食事する。一つはヒュー・ジャックマンの家族で夫婦と長男(10代)と幼い娘、もう一つはテレンス・ハワードの家族で娘(10代)と幼い娘、よく似た年齢構成の家族でテレンスは黒人家庭だが、そんなことに関係なく仲の良い2家族だった。テレンスの家で食事後、二人の娘は家に置いてきたおもちゃを取りに行くといってヒューの家の方へ歩いて行った。そしてその後、忽然と姿を消した。誘拐物語であるし、犯人捜しの謎解きでもあるので、ストーリーは言えない。地元警察では頭のキレる刑事として有名なジェイク・ギレンホールが登場する。彼は町人についてかなり知識があり、資料も充分入手できたので、必ずや二人を見つけ出せると自信を持っていた。間もなく幼い娘たちが面白がって覗いていたキャンピングカーとその運転手が拘置された。キャンピングカーの持ち主は近所の青年アレックス(ポール・ダノ)といい、体は大きいが知能は10歳児並であった。この青年が車を運転するのは違法だが、田舎町では何も言われなかったらしい。警察の訊問にもろくに答えられないオドオドした鈍そうな青年だ。彼は孤児で伯母さん(メリッサ・レオ)の家に住んでキャンピングカーで時々うろついていたが、大人しい青年のようだ。これで主要人物は出そろった。大掛かりな山狩りにもかかわらず幼女たちは発見できない。ヒュー・ジャックマンは気が気でなく、早く容疑者アレックスを締め上げて自白させてくれとジェイク刑事に迫るが、警察は安易に犯人を断定することはしない。遂に辛抱が切れたヒューは自分なりの行動に出た。この映画でのヒューはいささか困った存在だ。夜は冷え込むところだから心配なのは分かるが、とにかくカッカしてしまった。自分の力でアレックスから聞き出せると思ったのだが、、、。アメリカ的直情パパの行動がハラハラさせる。ジェイク刑事は必死なのはヒューと同じだ。彼のように過激なことはできないのだが、寝る間もなく、どこかに幽閉されていると思われる娘たちを探した。ヒュー・ジャックマンはもとより熱演だが、この映画で印象的なのはジェイク・ギレンホールの刑事だろう。彼は最近「エンドオブウォッチ」でもいいところをみせていたが、まだ若い俳優(34歳)だがメキメキ腕を上げている人だ。もう一人、ポール・ダノがすごい。よくこんなひどい役を引き受けたなと思ったが、うまくしゃべろうとしてもものの言い方すら思うようにならない青年を演じて気味悪いくらいの快演だ。静かな街での熱気あふれる誘拐サスペンスで近頃見た映画の中では出色の出来で傑作だ。う~ん、すごい!と思って観おわったが、監督はあの「灼熱の魂」のドウニ・ヴィルヌーブ、納得だ、「灼熱の魂」の興奮再びの作品だった。(おまけ)ジェイク刑事が犯人を捜すうち、サブ的な事件が発生するが、事件の全容というものは底の方まで調べないとわからないものだなと実感。映画「プリズナーズ」の終わり方も非常に意味深だ。
2015.01.04
コメント(0)
-

アクト・オブ・キリング(デンマーク、ノルウエー、イギリス映画)
文字通りの「アクト・オブ・キリング」つまり殺人を演じる、がこのドキュメンタリー映画だ。インドネシアで1965年のクーデター後起きた殺人は、半端なものではない。その数30万人とも100万人とも言われているが、今も口を閉ざしたまま語られることのない大量虐殺である。映画を撮ったのはアメリカ人の若い監督二人だが、現地で協力したインドネシア人スタッフは匿名を希望したそうだ。65年9月30日軍部のクーデターが起きた。急進左派の将軍によるものといわれていて、すぐに右派の将軍たちがクーデターを鎮圧し、その後右派が軍の実権を握った。当時のインドネシア大統領は左翼のスカルノだったが、国内の情勢は一変し、共産党支持者、華僑、等は強引に連れ去られ殺された。殺しに携わったのがプレマン(愚連隊、暴れ者)集団だった。そのひとりアンワル・コンゴという爺さんが「よし、俺たちがやった沢山の殺人のもう一度映画で演じて見せてあげよう」といい、出来たのがこの映画だ。こうしてここでこういう風に殺した、と説明するアンワルは何というか得意げだ。カメラ写りのため歯を直し髪を染めた、もともと衣服には凝った趣味がある。かくして殺人者本人が説明しつつ、勧めてゆくうちに、身の毛もよだつ虐殺の様相が見えてくるが、本人は明るく反省の様子も見せず語る、、、ちょっとこの映画では不快感を覚えていや気がさしてしまった。あとで、彼は「後悔してる」という言葉と共にかっての殺人現場で嘔吐していたが、彼は本当に悪かったと反省しているのだろうかそれならば、この殺人再現の様子の彼の表情はどうなんだ!そもそもオッペンハイマー監督らがこの事件に着目したのは、別のドキュメンタリーでパーム油のプランテーションへ取材に行ったとき、パンチャシラ青年団という団体が、労働者に組合など作らせないように圧迫していることを知り、そこから発展して65年のプレマンに至ったという。プレマンとパンチャシラは反共産党という点で同じなのだ。アンワルの引け目をみせない強気さの裏にはインドネシアの中の勢力地図が影響しているのだろう。パンチャシラはスマトラ最大の民兵集団で朱色、濃い赤、濃い茶色の赤茶系の迷彩服が団体のシンボルである。インドネシアといえばジャワ、バリ島などの贅沢な観光地だけが知識でいつか行きたいと思っていたが、こんな隠れた恐ろしい歴史があったとはショックだ。あまりにも大きな顔で堂々として誇らしげでさせある殺人者には、不快を通り越して、こんなことが許されて良いのか!と言いたくなった。しかも共産主義者を見つける世の流れが今も続いているとは!(おまけ)決して後味の良い映画ではない。かっての出来事、当事者たちの登場、それを描く今の製作人と監督の目、それらが合わさってこのドキュメンタリー作品となった。生きている間に、このような魔の世代、魔の殺戮者に出会わなかったら幸いだと思う。
2014.12.29
コメント(0)
-

ナイトライダー(ロシア映画)
そもそも「ナイトライダー」はアメリカのテレビシリーズだったはず。高性能車で走る正義の味方というところだけをいただいて、さらに車の性能をアップしたお話になっている。最近のロシアの特撮技術の発展ぶりは目覚ましいものがあり、ご本家アメリカに引けを取らないという自負が「ナイトライダーロシア版」の製作となったのであろう。モスクワの夜景がきれいで、ライトアップされたクレムリン宮などの観光的見どころも十分で、空飛ぶスーパーカーの活躍が楽しめる。お話は正義と悪のせめぎ合いみたいな七面倒なことは出てこない。主人公の目立たない大学生ディマ君は誕生日のプレゼントとしてパパから自分用の車をもらう。喜び勇んで駐車場へ行ってみればそこに停まっているのはやや古ぼけたボルガだった。旧ソ連時代にはゴーリキー自動車工場で量産された国民的な車だ。昔アメリカのフォードと技術提携していたとやらでどこかフォードの昔のムスタングなどの形に似ていて、クラシックな感じではあるが格好は悪くない。しかし今や、モスクワの若者たちに人気なのはベンツなどのドイツ製高級車だ。駐車場にもBMWやフォルクスワーゲンなどがズラット並んでいる有様。プーチン大統領も乗っているという純国産の、しかも古い型のボルガ、、、嬉しいことは嬉しいけれど、ちょっと顔の曇ったディマ君であった。ボディのフロントカヴァーに付いているトナカイ君の飾りが可愛い。所がこの車、お父さんがどこで買ったのか知らないが、大変な車であった。最近見たロシア映画「メトロ42」ではモスクワの大通りのものすごい渋滞が登場したが、モスクワでは身動きのできないぎゅうぎゅうの渋滞が慢性的に起きているのである。(というので地下鉄に振り替えてひどい目にあったわけだったが)マイカーを使って花屋の配達アルバイトをしているディマ君はイラつきのあまりどこかをさわりつつアクセルを思わず踏んだその時、車が宙にふわっと浮いた。その車は空を飛べる特別仕様車だったのだ。車のダッシュボードに入っていたディスクをたどって車製作に携わった科学者たちにたどり着く。引退老人になった科学者はナノ動力の研究の結果があの車ボルガだったと教え、トリセツを彼にくれた。研究の悪用をおそれたため車はどこかに消えたことになっていた。大変な車を手に入れてしまったディマの大冒険が始まる。ストーリーから言うとアメリカのお家芸みたいな話なのだが、どこかにロシア味が感じられ面白い映画である。ロシア映画であるがゆえに未公開とは惜しい。ファンタジーアドヴェンチャーがお得意のロシアのスピルバーグことティモール・ベクマンベトフが製作者になっている。(おまけ)ディム君が通っているのがモスクワ大学なので、大学の構内も良く出てくる。知り合って恋人になる女子大生がきれいで可愛い。飛び車のおかげで花屋のダメ配達員だったのがいっぺんに優秀配達員になるところが笑える。
2014.12.23
コメント(0)
-

ポンペイ(アメリカ映画)
2014年9月27日、突然木曽の御嶽山が噴火した。その生々しい映像を見た後からでは、この映画は一層実感を持ってみられるわけだ。西暦79年のヴェスビィオ山の噴火で滅んだポンペイの災禍を3D映画で再現している。監督は「バイオハザード」シリーズのポール・WS・アンダーソンで、最近アクションを色々手がけているらしいが、ついにサンダル劇(ローマ時代物)に発展したようだ。今までの映画と違ってリットン卿の歴史小説とは離れて、オリジナルに近いストーリーになっていて、主人公はブリタニア出身の剣闘士マイロで、キット・ハリントンという男優が演じる。もしテレビドラマ「ゲームオブスローンズ」を見ていた方ならああ、スノウだ!とすぐ分かるが、テレビドラマでは準主人公ながら印象的な人だ。彼、なかなか映画の主人公として立派にやり遂げられる人だとわかった。これから期待したいが、現代調とはいえない暗さが気になるが。相手役のヒロインの貴族の令嬢はエミリー・ブラウニングで、映画「エンジェル・ウォーズ」で贔屓になった女優さんだ。新鮮な二人に好感度大!身分違いの二人は馬が好きという点が共通する。火山の噴火でうずもれた街はナポリ湾に面するヘルクラネウム人口5000人、とポンペイ人口2万人だ。79年の噴火の約10年前大きな地震で二つの町はかなり被害を受けたが、それも忘れられ街は再建発展した。ポンペイは葡萄酒の一大産地として栄えていて、市民は豊かな生活を楽しんでいた。8月24日地震と噴煙と火砕流があったが、市民はまだ避難しなかった。そして翌25日、火砕流がどっと街に押し寄せ、まず近いヘルクラネウムが全滅し、ポンペイに火の海の流れが押し寄せて人々は逃げ場を探して押し合った。町の街路は2輪戦車や馬車のわだち分の幅があるだけで、あとは両脇の狭い歩道しかない。2万人の人が逃げ惑ったらどうなるか?このあたりはアンダーソン監督が力を入れてセットを立て再現してくれるのでありがたい。リアルな場面がすごい!人々は海へと向かったが海からは地震による津波が逆流してきて余計に危険だった。「南の丘に上がれ!」と誰か言っていたが、そこまでの道は火災でふさがれている。何とも凄惨な光景だった。リットン版では海へ逃げていたように思うがここではダメ。だが、主人公の剣闘士はそれどころではなかった。と、言うのはコロセウムで死闘の最中だったから。高い座席が取り囲むコロセウムは崩れて多くの人が下敷きになった。競技をやめて脱出して剣闘士は場外へ出るが、主人公は屋敷に閉じ込められている貴族の令嬢のカッシア(エミリー)を救わねばならない。スリルの中をエンドへと。グラディエーター劇は人気だし、噴火という自然災害も歴史上の事実だ、この二つをうまく組み合わせて、最後まで面白く見せてくれるスペクタクル映画である。(おまけ)黒い熱い噴煙が空に広がり、火のような灰が降ってくるあたり、もし御嶽山で遭遇された方が観られたら、実感がありすぎるのでは。燃えた石炭のような岩が飛んできて御嶽山の山小屋の屋根はボロボロになっていた。この映画でも飛んでくる火の岩が3Dですごかっただろう。
2014.12.22
コメント(0)
-

神様がくれた娘(インド映画)
知的障害のある男性が男手ひとつで娘を育てる。同様のアメリカ映画「アイアムサム」は観ていない。南インドの田舎の村で、村のチョコレート工場で働きながら、クリシュナ(ビクラム)は愛する妻ナージに死なれてから女の赤ちゃんをとてもかわいがって育てた。「月」という意味のニラーとなずけた。親子は小さな家に住み、いつも一緒、工場へ行くときも買い物に行くときも抱っこして連れてゆく。ハイハイするようになりよちよち歩きするようになり娘は5歳になり、私立学校には入った。パパの知能を補ってチョコレート工場社長や上司や仕事仲間がいつも助けて、学校に入れたのもどうやら工場長の世話らしい。それほどクリシュナは大人しくて優しくて皆から愛されていたからだ。もちろん娘のニラーも世界一パパが好きだった。こんな童話めいた夢のようなお話が、死んだ妻の父親の実業家が娘の忘れ形見のニラーを見つけて取り上げようとするところから、世知辛い社会一般人の見方が全面に出てきて、知的障害の父に対する見解がどうしようもなく立ちはだかってくる。裁判で親権を取り上げられそうになるが、女性弁護士とその部下が彼を助ける。というようなお話だが、これはインド映画だ。タミール語圏の人気俳優ビクラムは本当は超ハンサムらしいがここではおどおどした目つきのはっきりしない顔つきで、演技力は大したもの。知らなかったら彼の正体がこうなのかと思いそうだ。けれどもインド映画としては当然だが、全然暗くならず楽しいエンタメ部分が沢山挿入されている。女弁護士が相手方の雇った大ベテランの大物弁護士を相手に互角に戦うところも、厳しいながら娯楽要素は忘れていない。やはりインド映画はいいなあ、と思うのはこんなところだろう。エンタメ要素といえば暴力とセクシーシーンだと勘違いしているどこかの国の映画と大違いだ。もちろん歌や踊りや、ユーモアの方が本当の正しいエンタメなのだ。知能6歳の父とまもなく6歳になる子供をどうするかという難しい問題も、涙と人情のうちに解決して納めるところは、常套手段でやられたな、と感じたが、すべて気持ちよく納得できるのもインドの人の心の広さという良さが画面からにじみ出るからだろう。ニラーちゃんを演じる少女がとても可愛い。(おまけ)裁判所風景が面白くてみもの。インドでは弁護士が有り余っているらしい。裁判所の玄関に警察から犯罪容疑者を乗せたトラックが付くとどっと仕事を求めて弁護士がとりかこみ、「開廷したら、即無罪で釈放にしてみせますよ!是非私に弁護させて!」と口々に叫んで勧誘していたのが笑える。マドラス州高等裁判所の中も、裁判風景も面白く司法の世界が娯楽になるとは驚きだ。
2014.12.19
コメント(0)
-

サイレント・ウォー(香港=中国映画)
1950年の中国は国民党と共産党の内戦もほぼ終結し、蒋介石は台湾へ移った後であろうか、中国国内に残る国民党との通信は頻繁に行われていた。交わされる無線の暗号通信、モールス信号、などを解読するのが701部隊の仕事で、部隊は誰も存在を知らぬ南部の山中で任務に携わっていた。ある日、突然に今までの無線の暗号の電波が変えられ、国民党の者たちが交わしていた通信ではなく、天気予報などの意味のない内容の電波になっていた。あわてた局長は、香港に居た有名なピアノ調律師を呼んで新規に使われている暗号電波の解読を頼んだ。多くの電波の中から一つのつながりを読み取れる耳の特別に良い人が必要だったからだ。こうして親分の調律師の手伝いをしていた下っ端の盲目のトニー・レオンが701部隊の重要人物に抜擢される。元のタイトルが「風聴者」というくらいだから、目が見えないだけに音に関する感覚は天才的に鋭かった。トニーは自分を勧誘した美しい女スパイのジョウ・シュンと心惹かれあうが、スパイと盲目の解読人では結ばれる率は低い。ジョウ・シュンは任務で上海へ、トニーは仲間の通信士の娘さんと結婚する。トニーの解読した情報からコードネーム重慶という国民党スパイが上海に居ると分かった。その正体を突き止めるためジョウ・シュンは身分を偽ってある金持ちの麻雀サークルへもぐりこんだ。前半はこのようなモールス信号や無線の周波の研究ばかりのお堅い部分がかなりを占め、トニー・レオンのような華のある人が演じていなかったら、全く地味で退屈だったろう。彼の盲目演技が上手くて、つい乗って見せられてしまう。女スパイのジョウ・シュンはポスト、チャン・ツイーを意識したかのような新進女優だ。2002年の「中国の小さなお針子」で硬い蕾だったのが、2006年「女帝エンペラー」2008年「画皮あやかしの恋」2011「ドラゴンゲート」と進むにつれて花咲くように美しくなった。この映画でも1950年代のレトロな洋装に身を包み、白い花のような美貌が輝かしい。しかし残念ながらトニー・レオンとは心で結ばれていても夫婦にはなれない運命なのだ。自分の信号の読み誤りのためジョウ・シュンを死に追いやってしまったトニーは必死で国民党のテロリスト重慶を探す。お堅いドキュメント的な解読仕事から一気に、対テロリストのスパイアクションとなって、舞台は共産党幹部が全員参加する空軍記念式会場へと移り、クライマックスに入る。中国南部の秘密基地での仲間だけの静かな生活の描写がながくて、ラスト近くになってテロリスト潜入の会場場面が出てくると、おやおや、これはスパイ映画だったのか!と今更ながら気が付いてあたまを切り替えねばならない。これは映画を見る者には混乱を与えるだろう。トニー・レオンとジョウ・シュンは魅力的だが、映画全体はやや中途半端な印象におわった。(おまけ)トニーレオンの聴覚はすごい。たくさんの無線の電波が一度に聞こえても混線せずに頭の中で聞き分けられて、中から必要な物だけを取り出せる。周りの人の動きも空気の微妙な波で掴んでいる。
2014.12.18
コメント(0)
-

ルートヴィッヒ(ドイツ映画)
ヴィスコンティ作品の記憶もやや薄れたところへ、143分かけてじっくり新たに印象を焼直してくれる映画だ。1845年生まれの王の41年の短い生涯を、父王が崩御した時点から、途切れず年を追って描いている。だんだん悲壮な状態になる王を見ているのは、辛い気がするが、ある時点から、自分というものをふさわしい立場に維持して、社会的に生活してゆくということから、脱落して、逃避、引きこもり、に落ち込んでしまう人はなにもルートヴィッヒ一人に限らない。良く見受けられることだ。そのまま立ち直れない人もあれば、何かのきっかけで気が付いて前向きになる人もいる。彼の狂気についても、むりやり退位させたのは、原因は王国の財政の逼迫のためで、退位させるために病気だと医師に診断させたという説もある。もしルートヴィッヒがそこらの貴族か富豪の跡取り息子で、芸術にのめりこんで親の財産を消費し破産寸前になったということなら、ざらにある話で、歴史的逸話にならなかっただろう。バイエルン王国という豊かな国の王で、浪費も劇場や大きな城を3つ4つ建てるという大スケールの浪費だったのでいまも「狂王ルートヴィッヒ」のレッテルを張られているのである。お金が無くなったのは戦争の賠償金のせいでもあった。この頃のドイツは最大の領土を持つプロイセンが他の小国を統合してドイツ帝国を作ろうと働きかけていた時だ。プロイセンは多民族国家オーストリアを排除して戦争する。オーストリーに付いたバイエルンは負けてビスマルクの構想に従わざるを得ない。「私も皇帝になる権利がある」と調印に不満だったのは狂王と呼ばれる人らしくもないと思った。王制は保ちつつドイツ帝国の一員になったが。ルートヴィッヒを演じるルーマニア人俳優のサビン・タンブレアは細い体に、筋肉の弱そうな体格で白く女のような力のない顔つきだ。男性的なセックスアピールゼロの中性的な弱弱しさ。ストレートの髪の毛をコテでカールさせたり、黒い服をよく着たりナルシストぶりが目立つ。はっきり言ってヴィスコンティ版のヘルムートバーガーよりもずっと病的な感じがする。彼のお気に入りは秘書官のルッツと厩舎係の美青年だが、秘書官の方はたんにワグナー好きのために登用されたが、厩舎係はあきらかに美貌のため側近になった。オペラや騎士物語に夢中の人だから、騎士を思わせる金髪の美青年には変な意味ではなく心惹かれたのであろう。噂の性癖にもそんなにひどいとは思えなかった。彼の特筆すべき点は、ワグナーへの尊敬とお城作りだ。ノイシュバンシュタイン城、リンダーホーフ城、ヘレンキームゼン城、など美しいではないか。作りたくて作れたとは幸せな人だ。精神的に健康人とは思えないが、悪い王ともいえないと感じた。国民が戦争で死ぬことには耐えがたい苦痛を感じる王なのだ。ロマンチストすぎた施政者の悲劇だ。ワグナーは偉大な作曲家ではあるが食えない人物に見えた。(おまけ)名門ウイステルバッハ家のうんだ問題児。ただ後世の観光には大いに貢献している。
2014.12.14
コメント(0)
-

ハンガー(イギリス映画)
最近、問題作を生み出しているスティーブ・マックィーン監督が2008年に撮った映画で、彼の初長編作品だ。カンヌ国際映画祭でカメラドール賞を獲得したが、監督はもともと美術系の人なので、映像の美しさを買われたのであろう。確かにカメラは美しい。しかし矛盾するが写されていることがらは全く美しくない!一般向きの映画ではない。出来れば見たくないような場面が登場するからだ。壁一面にに塗りたくられた排泄物、誰も好んで見たくはない。そのすごさは息を呑むくらいで、さらに画像ではわからない、臭いを想像すると、もう、、、何とも形容しがたい。しかしこれが1981年の北アイルランドのメイズ刑務所で本当に起きていたことなのだ。囚人はIRAアイルランド共和軍の逮捕者だ。彼らは自らの信条に従った行動で逮捕されたので、普通のいわゆる犯罪者ではない。政治犯であるという自負を持っている。しかし時のサッチャー政権は彼らを政治犯と認めなかった。このため囚人は囚人服を拒否、他の数々の抗議行動をした。裸で毛布をかぶっただけという「ブランケット運動」尿を廊下に流し排泄物を壁に塗る「ダーティ運動」などで抵抗の気持ちを表した。看守たちは(ひそかに同情するが)大変だったろう。汚い房をジェット水流機で洗っていた。抗議行動の状態の描写だけで、もう閉口する鑑賞者もあるかもしれない。私も実は少し気分が悪くなった。さらに後半は観ていられない非情な映像が出てくる。マイケル・ファスビンダー演じる囚人のボビー・サンズが先の抗議行動を止めてハンガーストライキに入ったからだ。そして66日後死んだ。だんだん衰えてゆくファスビンダーの様相がすごい。痩せて骨と皮になり、唇は割れ、顔色はまったく血の気なく、よくここまで演じたな、と思うくらいリアルな死相の現れ方だった。彼の様子は当時テレビで時々伝えられたそうで、マックィーン監督は子供の頃見たとか。上記の理由で、もし映画をエンタメ目的で見ようとする方には絶対お勧めしない。気分が悪くなるのを覚悟で、1981年の出来事を見てみようと思われる方だけどうぞ。アイルランド問題の奥にはこんな出来事もあったのかとただ驚くだけだ。(おまけ)囚人の家族の面会日だけは、普通に服を着て面会していた。アイルランドの冬は寒いのに裸で毛布だけとはよく耐えられるものだと思った。
2014.12.12
コメント(0)
-

アイアンクラッド ブラッド・ウォー(イギリス映画)
前作の「アイアンクラッド」は大変面白かった。マグナカルタにいやいや署名させられたジョン王が腹いせのやけくそで、私兵の軍を集め、フランスから乗り込んでくる。マグナカルタを提唱した貴族に仕返ししようとロンドンへ向かうのを、道中のロチェスター城で阻止するお話で、城を守って戦う十字軍帰りの騎士が主人公だった。今度はその5年後、スコットランドの出身のケルト人たちが宿敵イングランド人、この時代にはノルマン人であったが、に歯向かってくるお話だ。「5人対ケルト騎士団の戦い」とうたわれているが、ケルト騎士団なんて立派な名前はふさわしくない。野蛮な感じの略奪隊といった感じで、スコットランド人が痛めつけられた時代ゆえ、憎しみの気持ちだけが猛烈に燃えている野党団である。野党団はロチェスター城を狙った。単独で建っていて、要路に昔から居座っているので、獲りたかったのだろう。夜盗の頭の息子が城に忍び込み殺される。これを根に持ってケルト族は城を攻めた。城主は重傷を負い、危険とみて、城主の甥で今はイギリス各地を放浪しているガイという武者を見つけ出し頼んできてもらう。ガイは武術の腕だけが、持てるすべてで、賭け格闘技の選手になって小銭に命を賭けていた。呼びに行ったのがヒューバートというロチェスター城主の若い息子で、まだ少年であるが、可愛い顔ながら、城の跡取りの人格は備えている。久しく逢わなかった従兄ガイとのやり取りが面白い。結局、人助けではなく金で雇われた傭兵としてガイはロチェスターへ行くことを承諾する。過去に、ヒューバートの姉の姫様となにか悶着があったらしい。心惹かれるが行きたくないという複雑な気持ちのガイである。さて、戦いが始まってみると、もうただ、圧倒的なリアルな切り合いの続く城攻めだ。ロチェスターへ来たガイはまず城を点検し、食料一か月分、OK!飲料水は山から湧き出す地下水の井戸で毒を入れられる心配なし、OK!侵入口は正面入口と外からは分からない裏口だけ、OK!といったように見てゆく。高い垂直の石垣はそう簡単に登ってこれない、と籠城作戦を立てた。ちょっと面白かったのは、トイレの話。石の古城のトイレは壁のそばに或り、穴が壁際に並び、穴から排泄物が下の堀に落ちる仕掛けになっている。そのトイレの穴に登ってきたケルト人がいて城の中に侵入したのだ。ありうるといえばありうる、出来うる話だ。映画の目玉とみえるロチェスター城は本当の城にロケしたと思われる。なぜなら、塔から見た中庭など、いかにも古めかしく作り物ではないからだ。刀での白熱の切り合いも全くCGなしだそうで、武器のぶつかる音など本物の迫力だった。昔の城攻めの面白さを堪能できる。風雲のロチェスター城はこういった面白い時代劇アクションにぴったりの舞台だ。しかしケルト人の恨みはちょっとおかしい。ケルト人の頭の息子は城に勝手に入り斬りあったのだから殺されて当然で、恨みかたが度が過ぎている。(おまけ)前作は史実だったが、今度もそうなのか知らない。ただ、ケルト人たちが野党団を作ってイングランド各地を荒らし、ロチェスターも何度も標的になったのは確かだろう。城の映像は素晴らしく、例の低く垂れこめた、落ちてきそうな(スカイフォールしそうな)雲の様子が美しい。
2014.12.11
コメント(0)
-

バトル・オブ・ワルシャワ 大機動作戦(ポーランド映画)
ポーランド映画の超大作だが、わが国では未公開。ポーランド国内では高く評価されヒットしたのには、訳がある。この映画で描かれているのは1919年のポーランドで、長い抑圧の歴史の中で、しばしの栄光に輝いた短い時代を描いているからだ。第一次大戦が終わってみれば、宿敵ドイツとオーストリアは敗戦国となり、もう一つの宿敵ロシアは革命で内戦状態だ。期せずしてポーランドは念願の独立を果たした。この時ポーランドのトップの地位にいたのがビウスツキーという人物で、彼はこの機会に元はポーランドの領土だった、ウクライナやベラルーシ(北方のリトワニアの地方部も)などを取り返したいと画策した。ポーランド軍をウクライナに進め、キエフまで取るところまで行き、国民を歓喜させたのであろう。しかし軍力から言ってかなり無理な作戦だったのかも。ロシア側から見ると共産主義をヨーロッパに広めるには、ポーランドを抑えねばならないし、西側諸国から見ると、共産主義の進出を食い止めるのはポーランドの力がいる。裏での思惑も絡んでいた。ビウスツキーを演じるのがポーランド映画でおそらく最も良く顔を見る俳優の一人のダニエル・オルブリツキーだ。昔の金髪の美青年の面影こそないが、オルブリツキーのビウスツキーは権力を握った政治家で軍人といった風で風格がある。ちょっとユーモラスな人間味もみせる実在の政治家だ。何だか彼の意気込みにひっぱられての進軍のように見えた。物語の主人公のポーランド青年とその恋人の歌姫の方がメインストーリーだが、私にはオルブリツキーの動きの方が興味があった。しかし喜ぶのは早かった。ロシア革命も決着が見えてきて、やってきた共産軍の将軍が兵を率いてポーランドと対決した。第一次大戦と同じ時代ゆえ、前近代的軍隊なのが面白い。騎馬が主体で、大砲も戦車もあるが今のより型が小ぶりで威力もない。騎馬戦が主戦力なのだ。共産主義革命軍を中央で指導するのが当時トップだったトロッキーで軍事会議には若きスターリンも参加していた。革命軍は赤軍と呼ばれていたが長い内戦で、貴族側の白軍を破りなかなか意気軒高だ。ウクライナの地にはまだ白軍に味方していたコサック兵もいて、あちこちに出没する軍隊は何軍やら、近くに行って初めて分かる。主人公の青年は共産主義のビラをたまたま持っていたため死刑になりそうになり、共産軍が来て助かり、脱走して、今度はコサックに拾われ、と転々とする。コサック兵は自分の主義主張よりもリーダーの将軍に従うことの方が多いように小説などで読んだ。この映画でもどこに味方するのかわからないが、一人のリーダーについて軍隊がぞろぞろ移動していた。リーダーのコサックの若き将軍が何とも格好良いイケメン男だった。コサックは戦争が仕事みたいなもの、果たして最終的に勝つ方についていればよいが、コサックたちよ、何処へ行く、、、という感じ。(おまけ)共産ロシア軍に逆に攻め寄せられ、あわやワルシャワまで落ちそうになったが、賭けのような陽動作戦を使ってロシア軍を撤退させた。輝かしい自由ポーランドの歴史の1ページだ。しばしポーランド人の心境になって映画を見た。しかし独立も第2次大戦であっけなく崩れたが。
2014.12.10
コメント(0)
-

汚れなき祈り(ルーマニア映画)
ルーマニアの片田舎の丘の上に立つ修道院、そこで24歳のアリーナという娘が死んだ。彼女は修道院にいる親友のヴィオキツアという娘を訪ねてドイツからやってきた。そして二人は連れ立ってドイツへ行って仕事探しをするはずだったが、、アリーナの死で修道院の司祭と修道院長の女性は監禁過失致死罪という思ってもみなかった罪に問われることになった。2005年に実際に起きた事件である。ルーマニアのキリスト教はロシア、ギリシャと同じ東方正教会といわれる宗教のうちに入り、ルーマニア正教会として存在するが、この映画の修道院は正式に正教会から認められていない、いわば独立系の修道院だ。司祭をお父様、修道院長をお母様と呼んできわめて孤立して独自の信仰を守っている。若い人、少し年の取った人など7,8名が一緒に仲良く住んでいて、ヴィオキッツアもその一人だ。アリーナが来てみると一緒に旅に出るはずのヴィオキッツアの気持ちが変わっていた。アリーナとヴィオキッツアはおなじ孤児院で育ったが、アリーナが里子に行って、さらにドイツに行って離れているうちに、ヴィオキッツアはすっかり修道院での信仰の生活にはまっていて、気に入った此処を動こうとしなかった。じゃ、アリーナの方が修道院に入ったら、ということになるが、アリーナは信仰がなくっても、唯一愛するヴィオキッツアと一緒に居られるなら修道院に入りたいとまで考えた。しかしここで信仰生活に触れるうち、アリーナは一種のヒステリー状態になり、異常な興奮を示すようになった。もともと、統合失調症の兆しがあったのか、そこまでいかなくても精神の不安定な人だったのかもしれないが、暴れて暴言を吐き司祭に逆らった。医者にも見せたが、医者は薬を処方しただけで、治療は修道院の生活の中でするように、アリーナを退院させた。精神が弱って苦しんでいる人を助けるのは宗教家の仕事でもある。アリーナの中にいる悪魔の種を追い出し、きれいな魂に浄化させてあげたいと全くの善意から修道院では皆の手を借りて宗教儀式が行われた。それが結果として上記の悲しい死になったわけだ。この映画で胸を打つのは、アリーナのことではなく修道女らの暮らしぶりだ。21世紀の社会から隔絶して、ほとんど中世のような生活だ。井戸水だけ、電気もなく、ランプを使う、料理や暖房は薪だ。食べるものは修道女らの仕事として、近くの孤児院の子らの食事つくりを請け負っていて、食材の入手はツテがあるようだった。もちろん野菜は作っている。食事つくりはかなり大事な仕事のように見えた。そして他の時間は祈りに当てられる。精神的には乱されるものがなく、平安だ。だが中世的な生活は修道院にアリーナという異物が入った時、混乱した。そもそも病気というものに対する考え方が違う。彼らとしては正しいと思う治療法だったが、世間では異常で非常識だった。彼らは気が付いただろうか?警察の車に修道院の主な人が乗せられ、都会に或る検事局へ向かうとき、その胸中はどうだっただろう。たぶんまだ、正しいことをしたと思っているだろう。それほど彼らは現代とは隔たっているのである。(おまけ)修道女の衣装は我々が良く目にするカトリックの尼僧のとかなり違う。ルーマニア正教会の修道女姿は映画では見たことなかったが、黒い被り物やシンプルな黒い服などが印象的。ずっと中世の生活で進んでゆくが、アリーナの危篤で、救急車を呼んだ(隣の家の電話を借りた?)そして突然、現代に突入した。
2014.12.06
コメント(0)
-

フォンターナ広場 イタリアの陰謀(イタリア映画)
イタリアの政治的事件を描いた映画としては、2003年のマルコ・ヴェロッキオ監督の「夜よ、こんにちは」があった。フォンターナ広場事件よりも約10年後、イタリア首相になっていたアルド・モーロ氏の誘拐殺人を描いていて印象に残っている。「フォンターナ」ではモーロは外務大臣として出てくる。ミラノのフォンターナ広場に面した全国農業銀行の閉店間際のロビーで何者かが爆弾を発火させ、17名死亡88名負傷の大事件が起きる。爆弾の威力は大きく普通には入手できない種類のものだった。しかしそのころ鉄道や劇場で爆弾が仕掛けられたり爆破が起きることが多かったので、犯人の目星は絞られていて警察は糾弾を急いだ。130分の長時間映画で、中身は濃い内容がギュッと詰まっていて、観るのが大変だ。それだけにジュゼッペ・トウリオ・ジョルダーナ監督の意気込みが感じられる。何しろ、この事件には謎が多く、真犯人は分からずじまい、そのごのイタリアの政治が混乱する元になった事件なのだ。決して娯楽的に面白い映画とは言えないが、一つの事件にかかわる多くの関係者をじっくり手を緩めず描いていて、見ごたえは十分だ。たまにはこういう固い内容の作品も良いものだ。銀行の爆発が起きたのは1969年12月12日(金)だった。ミラノ市警のカラブレージ警視が捜査を担当したが、たちまち上司や検事筋や役所筋からどんどん横やりが入った。そして間もなく容疑者が拘束され始めたが、顔ぶれがほとんどがアナーキストのグループの者か左翼団体の者ばかりだった。イタリアには彼らと同じかそれ以上に過激な右翼団体やネオファシスト団体があって、怪しいのはむしろそちらかも知れないのに彼らには嫌疑が行っていない。カラブレージ警視はともかくも一番名前が挙がっているアナーキストのピネリを逮捕したが、内心、これで良かったのかと不安だった。と、言うのはピネリの人柄は彼が良く知っていたからだ。左翼運動に詳しい新聞記者ノッツアも彼と同意見で、調べるなら左翼と右翼両方調べるべきであると言った。実は思想家たちには左翼から右翼へまたは逆に、と、行き来するものがいるし、相手陣に潜入している密偵もいて人物関係は複雑を極めていた。ところが3日間警察で調べられていたピネリが4階の窓から落ちて死んでしまう。そしてアナーキストたちの仲間も次々と怪死した。背後に何かの勢力を感じたカラブレージだった。ここまでで事件が続発し、関係する人物たちが次々と数多く現れて、よっぽどしっかり見ていないと分からなくなる。難問に直面するような気分だ。ピネリの死も自殺か他殺か不明だ。アナーキスト仲間(一応、正体は不明)が高圧線に触れ焼死した事件などショッキングだった。そしてピネリの死で、白眼視されるようになったカラブレージにも悲劇が待っていた。やはり一通りの事件ではなく仕掛けたものが、右か左かどの陣営に居たか、調べるにつけ、奥が深くなるような奇妙な謎の事件で、ちょっと日本人には理解の手が届かないかな、と感じた。(おまけ)アナーキストの面々、右翼の旧軍人団体の面々、左翼の活動家や知識人の面々、たくさん出てくるが、それぞれの「つらがまえ」が面白く、イタリア人らしい熱気のある顔つきが見ていて飽きない。政情不安で騒がしかった時代の人たちは、現代の平和な間延びした(?)顔とだいぶ違うようだ。
2014.12.05
コメント(0)
-

ワールズ・エンド 酔っ払いが世界を救う(イギリス映画)
イギリス人の酒好きはつとに有名だが、酒からはどうしても足を洗えないイギリス人がひそかに拍手しそうなお話だ。ロンドンからほど近い田舎町ニュートン・ヘイブンへ帰ってきた元悪ガキの5人の男が、町の12軒のパブを最後の一軒まで全部梯子しようと計画する。というか、一番のワル大将のサイモン・ペッグが4人の男を引っ張り出したのだ。小さな町なのに12軒もパブがあるとは、香川県のうどん屋なみではないか!さすがイギリス人の生活になくてはならぬのが酒なのだ、と実感する。高校卒業の年、彼らは12軒を回ろうとチャレンジしたが、5軒目くらいでダウン。あれから年齢を重ね、酒歴にみがきをかけて、今度こそ、というわけだ。パブの名前が「ファースト・ポスト(出発点)」に始まって「オールドファミリア(昔馴染み」「フェイマスコック(名高い雄鶏)」「クロスハンド(組手屋)」「グッドコンパニオン(良き仲間)」「トラスティサーバント(忠実なる召使い)」「ツーヘッドドッグ(双頭犬)」「マーメイド(人魚軒)」「ビーハイブ(蜂の巣)」「キングスヘッド(王様の頭)」「ウオールポケット(壁の穴)」そして最後が「ワールズエンド(世界の終わり)」である。5人の男はサイモン・ペッグ(アル中で無職)ニック・フロスト(酒立ちして弁護士)エディ・マーサン(父と中古車屋経営)マーティン・フリーマン(不動産屋)バディ・コンシダイン(職業は忘れたが、ちゃんとした仕事人)という内訳だ。マーティンの妹で昔、みんなのマドンナ的存在だったのが、ロザムンド・パイクで、華やかさを添えている。彼女もパブ周りに加わる。社会的に収まらないどうしようもない落ちこぼれのサイモンが皆をかき回し、引っ張り回すが、だが、本当の危機はこの静かな田舎町の大人しい町民の中にあった。「ホットファズ」でも、きれいで静かで出来過ぎの町に意外な黒い影があったということになっていた。どうもへそ曲がりのイギリス人は管理され過ぎた清潔さなどに、皮肉を言いたくなるらしい。申し分のないこの町の中に恐ろしいエイリアンの計画が着々と進んでいたのだった。ストーリーは半分悪ふざけしながらの対エイリアン戦で、笑って観られるいつもの調子のコメディだ。昔の学校の人気教師がピアーズ・プロズナン、エイリアンの組織のボスがビル・ナイという豪華な顔ぶれ、ただしビル・ナイは声だけの出演。バデイ・コンシダインとは誰?と思ったが、前に観た「思秋期」という渋い映画の監督さんだった。どうでしょうか?好きな人なら絶対好きになる映画で、顔ぶれを聞いたらみたくなるはずだ。(おまけ)パブの看板と入口は変わっていない。店内は片付いた感じでどこも同じインテリアになっている。「あれ!ここもスタバ化されてる!」と言っていた。
2014.12.03
コメント(0)
-
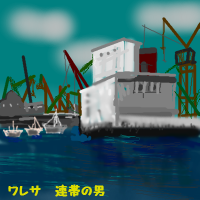
ワレサ 連帯の男(ポーランド映画)
ポーランドの監督アンジェイ・ワイダにとっては、ポーランド人の独立の魂がすべてで、その象徴ともいえるレフ・ワレサと連帯を描くことが一種の執念でもあるようだ。昔からロシアとドイツに挟まれ辛酸をなめてきたポーランドだが、その魂はいさささかも失せず、圧迫によってさらに強くなる。けっして頭を下げないポーランドだった。ポーランドに始まりソ連邦全体に自由化をもたらす元となった連帯は正しくは独立自主管理労働組合というのだから、決して政党などではなかった。バルト海に面するグダンスク造船所の労働組合から始まったのだ。グダンスクの名を聞いて思い出すのはドイツ映画「ブリキの太鼓」だ。原作者ギュンター・グラスもグダンスク出身で、あの映画の舞台もそうだった。ドイツ流にはダンツィッヒと呼ばれる古くから造船業の盛んな工業都市グダンスク、連帯とワレサの活躍したのがここと知って、感無量(!)だ。1939年「ブリキの太鼓」でのダンツイッヒ郵便局に立てこもってドイツ軍と決死の戦いの後華々しく散ったポーランド守備隊、忘れられない印象的な場面だった。グダンスク近郊の村で生まれ造船所の電気工だったワレサの根性はポーランド守備隊に通じるような気がした。ワレサと呼ばれているが正しくはレフ・ヴァウエンサというらしい、1943年生まれ、連帯から出て大統領になりノーベル平和賞ももらっている。しかし映画に出てくる若き頃(1970年頃以後)のワレサはそんな偉大な人物らしくない。労働組合の世話をしていたが、とても面倒見の良い人だ。そのころの共産主義ソ連主導の造船所ではいつも慢性的に問題が起きていた。ノルマが達成できないとお叱りが来る。そのたびにそれなら電気を止めないでくれ(停電だらけ)、鉄の板をもっと送ってくれ、粉じん対策を早くしてくれと、会社の幹部に掛け合いに行くのはいつもワレサだった。仲間が困るのを放っておけない、何とかしてもらうまで頑張るというのがこの熱い行動派の男ワレサだ。こうしてストライキと会社の間に立ってただ労働者の待遇改善だけを考え走っているうちに、会社だけではだめだ、政府を相手に訴えないと、ということになって行ったのだろう。工業高校だけ出て、ねっからの労働者だったワレサ氏はぜんぜん偉ぶらない人好きのする人だ。そんな実像が分かった。ワレサ氏と親しいワイダ監督だから信じられる。大統領をやめてからまた労働者に戻ったというから、働くことが好きなんだろう。ただ労働者の地位はちゃんと社会的に守られねばならない。これは世界共通だ。(おまけ)なんども警察に拘留された。1980年ごろは6人の子持ちだったので、逮捕されたとき、子連れだったパパワレサは赤ん坊を乗せた乳母車ごと警察へ。留置房の前に置いていたら泣き出して、おむつ用にタオルをもらったり、婦人警官がお乳を呑ませてくれたり、ユーモラスな場面があった。何しろワレサ夫婦はカトリックなので子供はできたら全部生んで育てるのだ。
2014.12.01
コメント(0)
-

ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅(アメリカ映画)
インチキな広告でだまされて100万ドル当選したと思い込んでいる老いた父(ブルース・ダーン)と仕方なく付き合って旅に出た次男の息子。お父さんは頑固だ、どうしても取りに行く気だから、心配で付いて行ったものの途中で何度もあきらめさせようと息子は説得した。けれどついに旅はモンタナからネブラスカまで、続く。アメリカの田舎のどちらかというと貧しい老人をウソの当たりくじで釣るなんて人が悪いが、日本のオレオレ詐欺と似たようなものだろう。くじを主催している街へ行くのに、昔家族が暮らしていた故郷の田舎町を通った。親類が集まって歓迎してくれるというのでお母さんもバスではるばるやってきた。この集まりが何ともすごい。老人になった兄弟が集まり、食卓を囲んで黙々とご飯を食べる。誰も成功者は居ない、老後の生活がやっとという様子だ。息子たちもこれる者だけがやってきた。頑固爺ブルース・ダーンが生まれ故郷の町に来てみれば、、、ここからのドラマが面白い。誰からも見捨てられているようなウディ・グラント(ブルース・ダーン)だったが、息子は「100万ドルのことは言うな」と口止めしていたが、あっさりしゃべってしまう。たちまちに皆の目が変わる。小さな町では町出身の男が100万ドルあたったというのは大ニュースだ。新聞にも載せるというので息子は止めに行った。新聞社で出会った小柄な可愛い老婦人が思いがけなくも、父の若かりし頃の姿を話してくれる。父のこと、母のこと、昔の仕事のことなど知らなかった息子は、老婦人の話で今までの見方が違っていたことに気が付いた。頑固で自分勝手な父、大して金儲けもせず酒ばかり飲んでいた父、何事も頭から決めつけてガミガミ言う母、どちらもダメ親なのか?本当にそうなのか?小さな老婦人は昔の父の恋人だった。もしこの人と結婚していればもっと幸せに、という思いが息子の頭をよぎったかもしれない。父は彼女と結婚せず今の母と結婚した。身持ちの固い娘とはなれて肉欲に負けたのだろう。しかし!この新聞社主の老婦人は父の良いところを認め、いまだに好いている。気が良くて成り行きにまけせてしまう騙しに弱い男、そこが好きだ、とそう思って心配している。この女性から見ると父は決して頑固で嫌な奴ではなかった。あらためて父という男の姿を見直したくなった次男だった。では、うるさくて下品な老婆の母親はどうだ?こんな女と結婚したから酒飲みになったのはある程度そうかもしれない。ところが、母親がエッと思わせることをする。金があたったことを知ってタカろうとする見苦しい親戚の者たちに向かって、胸がスカッとするような啖呵をきって「みんな、くたばっちまえ!」と一喝したお母さん。彼女は気の弱い夫をこのようにずっとかばって長年やってきたのだろう。お母さんの実像も案外知られていなかったのだ。老ブルース・ダーンあっての映画みたいだ。彼のことを覚えているのは昔のヒッチコックの映画「ファミリープロット」だ。主人公の女性を助ける男友達のタクシー運転手の役で飄々として(若かったが)良かった。あとは脇役で見かけた。チビで太目で口の悪いウルサお母さん役のジューン・スキップがダーンに負けない大好演だ。(おまけ)寂しい国道を走る場面がほとんどだ。モーテルに止まっても酒を呑みに行った呑み助のお父さんはどこかで入れ歯を落としたという。線路のあたりだというので、父子で探しに行く場面が良い。
2014.11.29
コメント(0)
-

ダリオ・アルジェントのドラキュラ(ハンガリー映画)
ヨーロッパ映画におけるホラーの帝王たるダリオ・アルジェントはまだドラキュラを作っていなかったのか?こんなままにしておけようか?今からでも作るべし。というとこじゃないかと想像する。しかもイタリアでは3Dで上映されたとか、しかし日本も他の国でも2Dで上映されたようだ。観てみると、懐かしや、かってイギリスのハマープロで1958年に造られた「吸血鬼ドラキュラ」と雰囲気がよく似ている。ブラム・ストーカー原作に忠実なのかもしれないが、ほぼ筋書きは共通している。最初の犠牲者ジョナサン・ハーカーはルーマニアの伯爵の城の司書として働くためにやってくる。伯爵が棺桶に入ってイギリスに来て屋敷を買うという映画もあったように思う。城に来て案外あっさりセクシーな女吸血鬼にやられてしまうところも同じだ。伯爵が司書を募集したのもすべて彼の婚約者のミナを呼び寄せるためであった。元のアルジェント作品の3Dがどのように使われたかは想像するしかないが、多分、伯爵が色々の生き物に変身するのに使われたのでは?蠅、カマキリ、オオカミなどに姿を変える。ミナの要請でやってきたのが精神医学にもくわしいエイブラハム・ヴァン・ヘルシング博士で、扮するのがルトガー・ハウア、吸血鬼対策に精通した人物だ。ヴァンヘルシングがアクションヒーローになった映画もあるが、ここではあくまで地味な学者風で、ハマープロのピータ-・カッシングと同じタイプだ。そしてまた一人の新たなドラキュラ伯爵が誕生している。カラー映画になってからの歴史では、元祖クリストファー・リー、フランク・ランジェラ、ゲイリー・オールドマン、リチャード・クロスバーグ、(最近ではルーク・エバンスも)などが演じていたが、この映画ではトーマス・クレッチマンという俳優がドラキュラになっている。怖いながらもややロマンチストなのはアルジェント好みだろうか。鏡に映らない、夜しか生活しない、影がない、垂直壁に吸い付いて走る、などなど要素はちゃんと踏襲されている。ロケ地はよくわからないが、ドラキュラの城とされているのはイタリア、ピエモンテ州のモンタルトドラ城でこれが何とも言えないドンピシャの城で、この城を見つけたのが成功の素だろう。内部の部屋部屋、図書室も同城内ならばさらに素晴らしい。(おまけ)ヒロインのミナはマルタ・ガスティーニという若い女優さんだが、ミナの親友ルーシーにはアーシア・アルジェントが。相変わらずきれい。ドラキュラ伯爵はコッポラの映画のおしゃれな吸血紳士ゲイリー・オールドマンに比べると魅力に乏しい。
2014.11.24
コメント(0)
-

バトル・オブ・プエブラ 勇者たちの要塞(メキシコ映画)
私は歴史的出来事を扱った外国映画が大好きなのだが、いかんせん数が少ない。ファンタジーはあっても史実物はなく、あっても観る人が少ないので入ってこない。ウエリントン将軍とナポレオンの攻防を描いた「皇帝と公爵」なんか早く見たくてうずうずしているが、何時みられることやら。かくして見つけた「バトル・オブ・プエブラ」、これはメキシコ映画でメキシコの歴史ものだが、結構結構!さっそく観るべし!だ。メキシコの歴史なんか関係ないわ、とおっしゃる方には用のない映画だが。時は1862年、スペインから独立はしたが、経済的に未熟なメキシコはヨーロッパの強国から借りた債務が返せない。これを理由に、イギリス、スペイン、フランスはメキシコのファレス大統領に返済を迫り、フランスは軍隊を派遣した。イギリス、スペインは金を返してもらえば良いと思っていたが、フランスはメキシコという国に或る野心を抱いていた。初代ナポレオンの兄がスペイン王になり、メキシコもあわや我がものとなった過去もあり、フランス皇帝のナポレオン3世は政権を追われたメキシコの有力軍人らがフランスに来て派兵を要請したとき、彼らに力を貸すことを承諾した。メキシコをフランスの物として、さらにはメキシコを基点にして南北戦争のアメリカの南部連合を応援しフランスの勢力を南北アメリカに広げようと企んだ。お気に入りの貴族の将軍にメキシコ制覇を命じた。さて、メキシコは王政が倒れ自由派のファレスが大統領だった。経済立て直しが急務で軍備どころではない。そこに大軍を乗せたフランスの軍艦がヴェラクルス沖にやってきて、上陸せんとしている。国家の危機だ。全メキシコから軍隊を集め、メキシコシテイと海岸の間のプエブラ要塞で、フランス軍を食い止める作戦に出た。圧倒的に強そうなフランス軍に対してメキシコ軍は見るからに土俗的で弱弱しい。ヨーロッパと新大陸の差がはっきり出ていた。ファレスは全軍の指揮を若い33歳のイグナシオ・サラゴサ将軍にゆだねて、相手に攻撃をかけるな防備だけに専念せよ、と命じた。地の利と要塞を大切に無駄な力を使うなということだ。5月5日、両軍はプエブラの原野で大決戦をしたが、天気は大豪雨となり悲惨な戦いになった。銃(連発できない)、銃剣、サーベル、大砲が武器で騎馬隊も交じっている。メキシコ軍は白い農民服でソンブレロのような帽子を着た百姓臭い兵士が多いが、何しろ侵略に対する怒りがある。フランス軍はメキシコ軍をなめていて、油断があった。しかも兵隊はアルジェリアやモロッコから連れてきた植民地兵が多い。彼らはなんでメキシコなんかで戦わなくちゃいけないんだ、というところだろう戦意の芯がない。じわじわメキシコ軍はフランスを追い込み撤退に追いやった。メキシコ人の心意気を示した歴史上の出来事だ。映画としても戦争場面がものすごく真にせまっていて、目を離せない強烈な迫力があった。戦争映画の傑作に入れてもいい。(おまけ)ヒーローはイグナシオ・サラゴサ将軍だろう。名家の出らしく上品で無口で、静かだが頼もしい。彼はプエブロ戦勝の5か月後病気で急死したという。ナポレオン3世は特大のヒゲをぴんと伸ばした王様だが、オペラを観ながら謁見するなど、真剣みにかける。これではメキシコ人のファイトに負けても仕方ない。
2014.11.22
コメント(0)
-
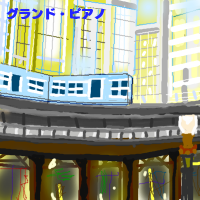
グランド・ピアノ 狙われた黒鍵(スペイン映画)
主演はイライジャ・ウッドだが、スペイン映画である。若手有望ピアニストだったが、演奏でミスタッチをしていらい舞台恐怖症になったピアニストが主人公だ。結婚した新妻に引っ張られ、いやいや舞台に復帰することになった。5年ぶりのコンサートのためシカゴにやってくる。空港からコンサートホールまでのリムジンの走行が外空間のすべてで、あとはホールの中の楽屋などで進行する一種の密室劇だ。ストーリーははっきりしたミステリーなのでネタバレは禁物だろう。イライジャ扮するピアニストは現在最も指が速く動き指の力の強い人として知られている。その彼をして弾きこなせずミスしてしまう難曲が「ラ・シンケッテ」という曲で、かれの今は亡き師匠が作曲し、師匠と弟子のイライジャだけが弾きこなせる曲だった。今回は舞台復帰第1回なのでプログラムには入れないはずなのに、いざ、始めて見ると楽譜が挟まっていて、「必ず弾くように」と書かれていた。彼は楽譜を捨てた。ところが、演奏中のべつの楽譜の上に「ラ・シンケッテ」を一音も間違えずに弾け、さもないと命をもらう、会場にいる新妻をも殺す、という脅迫文が書いてあり、銃の照準の赤い火が胸に止まっていた。こうなるとひかざるを得ないイライジャだ、だが楽譜は捨ててしまった、暗譜で行くしかない。彼の必死の演奏が始まった。なぜこんな脅迫が行われたかはミステリーゆえの説明ご勘弁ということにして、このピアノが面白い。前にスタンウエイ社のピアノ調律師の映画「ピアノマニア」が面白かったが、この映画もかなりの部分がピアノが主人公だ。この映画で使われるのはドイツの老舗ベーゼンドルファー社のピアノで、大型グランドピアノ、モデル290と呼ばれる97鍵の特別注文ピアノだ。普通は88鍵だが、端に白鍵が5つ、黒鍵が4つ、9鍵多い。誤演を防ぐため9鍵は真っ黒に塗られている。「ラ・シンケッテ」の最後の12小節には黒い特別の鍵が使われる。ここを絶対間違えるな!とはなんというプレッシャーだろう。イライジャの透き通った青い目が緊張にふるえる瞬間だ。ベーゼンドルファーを愛好するピアニストは多い。ウイルヘルム・バックハウスがそうだったらしいが、私がレコードで聞いたのはアルフレート・ブレンデルのモーツアルトの協奏曲だった。やや硬い響きの強い音が特徴で、高音部は澄んでいてきれいだった。生産量も少なくて希少なピアノで一般向きではないだろう。ちなみに問題の難曲「ラ・シンケッテ」は弾かれるが、そんなに名曲とは思えない。実は監督のエウイニオ・ミラさんの作曲で、この際無名の曲でもなんでもよいから、弾きにくそうな曲だったらよかったのかも。ミステリーとしてはまあ面白く出来ているのではないだろうか。(おまけ)イライジャ・ウッドは「ホビット族」が定着しすぎて、気の毒なくらいだ。でもピアニスト役なかなか似合っていた。役幅を広げてくれるだろう。狙われた奥さんは映画女優ということになっているが、愛嬌振りまく落ち着かない女性で、これじゃ長続きしない夫婦だなと思った(筋の中なのでどうでも良い事)ジョン・キューザックの出演場面は少なく、何のために彼のような有名俳優が出たのか不明だ。
2014.11.15
コメント(0)
-

鑑定士と顔のない依頼人(イタリア映画)
監督がジュゼッペ・トルナトーレ、舞台となる街がローマらしいので、イタリア映画ではあるが、主演はジェフリー・ラッシュ、ジム・スタージェス、他で英語版なのでかなり国際的な映画である。有名にして権威あり、人気の高い鑑定士で、美術オークションの主催者ヴァージル・オールドマン氏(ジェフリー・ラッシュ)は私の目から見ると、嫌味な人物だ。美術品の真贋を見る目は天才的かもしれないが、私生活はいびつだ。あまりにもキチンと身なりを整えすぎ、髪形(毛染めしている)にまで気を使うこと、少し病的なくらいだ。彼は50歳くらいだろうか、中年すぎの今まで、独身で恋人なし、女性に興味がないように見える。彼の周りには金持ちの老婦人の取り巻きがいるが、取り巻かれるのは良い気持ちらしいが、それ以上のものではなく、高慢で人嫌いだ。家はホテルのように整然と片付き、彼は誰もいない家に夜、帰る。そして秘密の隠し部屋へ行く。大きな部屋だが壁一面に女の肖像画がかかっている。時代は古い物から新しいものまでさまざまで、女の顔も個性的で、彼女らの目は一斉にヴァージル氏にそそがれているよう。彼は絵の美女に取り巻かれ、癒され、至福の時を過ごす。この映画ははっきりしたミステリー映画で、トリックは最後まで隠されている。上記の完璧紳士のヴァージル・オールドマン氏が、身も心もボロボロになり、廃人同様になってゆく恐るべき事件が静かに進行する。きっかけはクレアという女性から電話がかかり、相続した古いヴィラ(別荘風屋敷)の中の絵を含む家具類を鑑定してほしいといってきたことだ。クレアは外出恐怖症のため絶対人と会わないという。とにかくもヴィラに行ったヴァージルは、黴臭い地下で一つのぜんまいネジを拾うが、これは昔から探されている幻の機械人形の部品だった。これに気を引かれヴァージルはクレアとそのヴィラにのめりこんでいった。声だけで姿なしの女はついにヴァージルが隠れていると知らずに出てきたが、一見して、私はこの人はクレアじゃないと感じた。若くてきれいな女性だ、隠れているのはなぜか?しかしヴァージルはこの若い女がクレアだと信じた。信じたかったのかも。そして巧妙にもクレアと名乗る女は彼をひきつけ夢中にさせてゆく。犯罪が存在したのは確かだが、結果はヴァージル・オールドマンの自業自得とも言えるのでは?私は彼の生きてきたやり方と人を寄せ付けない性質が、最後の事態を呼び寄せたのだと思った。一時、廃人になったが、立ち直りプラハの喫茶店ナイトアンドデイで、いつか現れるクレアを待ち続けるヴァージルに未来はあるのか。絵の美女よりも生身の女を知った彼にはクレア以外に惹かれるものはもう何もない。これもまた至福の時かも。(おまけ)ある時のヴァージル・オールドマン氏、、、鑑定に行ったお屋敷の汚い物置のような居間や客間に、いろいろの家具などが埃をかぶっておかれている。「ガラクタだな」という顔をしてみていたオールドマンの顔が突然止まった。真っ黒の板切れがあった。汚れの中から一つの目が覗いている。果たして汚れを落とすと、ルネッサンス前期のフランドル派画家が描いた少女の肖像が現れた。こうして消えかけた美術品を骨董の中から見つけるのが鑑定士の醍醐味なのだろう。
2014.11.09
コメント(0)
-
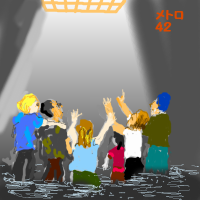
メトロ42(ロシア映画)
先だって「オーガストウォーズ」という戦争パニック映画で「う~ん、やるな!!」とうならせてくれたロシア映画がまた、やってくれました。今度は地下鉄での大惨事の話。モスクワの地下鉄は冷戦時代からご自慢の地下鉄で、写真でしか見たことがないが、駅のホームの天井の高さ、壮麗さに圧倒されたものだ。路線も複雑に張り巡らされて、最も便利な足になっているのだろう。何しろ地上は、気の毒なくらいのひどい交通渋滞だから。日本もそうだが、御多分にもれずモスクワには川が多い。川の下をくぐる鉄道は考えてみれば危ういものなのだ。もし川の水がもれて浸水したら?この恐れが現実になったのが映画の線路内の大洪水だ。1930年ごろ作られたトンネルは天上のコンクリートが川の水分で劣化し亀裂が入っていた。これは他人ごとではないかと思うことだ、トンネルの天井の崩壊なんて無いとは言えない。現に天井が落下し多数の人が日本でも死んだ。危なそうな古いトンネルは各地に或る。そう思ってみれば身近に起きそうな惨事である。朝の地下鉄線42号車は前方より水のラッシュが来たので運転手は手動で急ブレーキをかけた。この時の社内の様子はすさまじい。満員の乗客の体が芋の子を洗うように車内でかき回され悲鳴が上がる。どこに座っていたかなど関係なさそうな人間の転がり方で、死ぬか助かるかは、全く予想できない。治まってから線路に出て急ぎ足で近い通過駅に向かう群衆。先頭集団はたどり着いたが、いったん切れたレールの電流が後続車を動かすために入れられて大勢が感電死する。というような予想される非常事態が迫力満点に続けて出てくる。ロシア映画最近の大アクションエンタメ作品だ。地下鉄そのものを水浸しにできないので、大きな長いプールに大容量の水を流し、実際の車両を入れて撮ったとかそれだけの値打ちのある場面だった。東京でも大阪でも起こりかねない地下鉄浸水の恐怖がショッキングだった。かなり複雑な路線のモスクワだが、地下鉄には、保線用トンネルがあることは知られているが、モスクワにはさらに軍事用防空壕があった。冷戦時に核戦争になった場合に備えて作られた防空壕で、その路線図は機密扱いで、誰も知らない。映画では趣味の地下路線マニアの若い地下鉄局員だけが、一部の防空壕を知っていた。防空壕へのがれた生存者は水の中から、地上の光の見える鉄格子に声を掛けて助けを求めた。その鉄格子は公道の車道上にはまっていたが、地下道マニア君のおかげで見つけられた。(おまけ)アメリカ映画にまけないゾ、と言わんばかりにアクション映画競争にロシアが参入!大国だけにスケールが大きい。映画つくりに鉄道局や警察、必要なら軍隊も協力してくれるのも有利な点だろう。
2014.11.05
コメント(0)
-

ハンナ・アーレント(ドイツ、ルクセンブルグ映画)
ハンナ・アーレント(1906~1975)は政治哲学の分野では有名な学者だったらしい。たぶん、その方面で勉強した人なら、誰でも知っているくらい偉い学者なのだろう。ドイツでは切手になっているくらいだから。だが、この映画から初めてハンナ・アーレントに入った者には、そんな偉い学者というよりも、中年のきびきびした先生という感じだ。飛びきりの美人ではないが、男性的な思想が顔に現れて、キリットした聡明な女性に見える。映画上では1960年ごろのことで、アメリカ人となってすでに20年たった彼女はすっかりアメリカの大学の先生になっている。ヘビースモーカーであることがはっきりしているが、総体にこの時代にはだれでも相当煙草を吸っていたので珍しい事ではない。名著「全体主義の起原」が定番の書となり、学界では一目置かれていた彼女は、映画で描かれる事件で世間を騒然とさせた。それはナチの戦犯アドルフ・アイヒマン裁判傍聴記を雑誌「ニューヨーカー」に連載したことに端を発する。アイヒマンは戦犯のなかでもユダヤ人最終抹殺指揮者だったということで、イスラエル情報部モサドは必死で行方を追っていたが、アルゼンチンに潜伏中をやっとのことで見つけて逮捕した。映画は夜帰宅途中のアイヒマンを尾行してきたトラックが追いついて逮捕するショッキングな場面から始まる。アイヒマン逮捕、エルサレムで裁判、という記事を読んだハンナはニューヨーカーに記事を書くことを申し出た。ハンナは裁判中アイヒマンなる人物をつぶさに肉眼で観察した。そして書いた。記事は彼女の観て考えたそのものをしょうじきに書いたものだが、世論は驚いた。というのは、アイヒマンイコール悪魔、冷酷無残な殺人鬼うんぬんといった世評が出来ていたのに、ハンナの記事によると「悪魔」などとよばれるような大なるものは無い、「凡庸な悪」だ、ただ自分で思考することを止め組織の命令にのみ従った凡庸な悪人がいるだけ、といった意味の記事であった。「私は命令通りにやっただけ」と執拗に繰り返すアイヒマンから受けた印象だった。もっとアイヒマンの極悪の面を掘り下げるかと期待されていたのが裏切られたのだ。もちろん、期待通りの記事は書けただろう、しかし彼女は書かなかった。もう一つある世代の人の怒りを買ったのは、ユダヤ人迫害時のユダヤ人指導者の取ったやり方だ。かれらがユダヤ人のために頑張ることは可能だったはず、という意味の記事が批判を産んだ。世間の逆風を受けても、彼女は信じることをつら抜いて大学辞職勧告も蹴り、悠然と対処した。所で話は変わるが、私はこの映画を見て以前見たもう一つの映画を思い出した。それはウォルナー・ヘルツォーグ監督の「神に選ばれし無敵の男」という映画だ。まだユダヤ人強制収容の始まる前の1932年ころ、二人の人物がいた。一人は予言者で千里眼のハヌッセン、一人はヨーロッパ一の力持ちの若者ジシェ、ハヌッセンはユダヤ人であることを隠し、ナチの高官らの心をつかみ操った。ジシェはポーランド生まれのユダヤ人であることを公けにしてユダヤ人民衆に圧倒的人気があった。もし二人が力を合わせ、せまってくる危機から安全な方向に民衆を導けば、あるいは虐殺を防げたかも。という内容の映画だったが、あいにく二人は非業の死を遂げた。事実に元ずく映画である。そしてユダヤ人は受容として死に導かれた。ラビらはそれを阻止せず、従うように言い続けた。というのを思い出し、ハンナさんの「ユダヤ人指導者がどうの」の言葉に重なって頭に浮かんだのである。(おまけ)主人公ハンナにはバルバラ・スコヴァ、親友のメアリー・マッカーシーにはジャネット・マクテア、秘書にはユリア・イエンチが扮した。ちなみに「神に選ばれし、、」のジシェには本当の力持ちの人フィンランド人のヨウコ・アホラが扮し無垢の清らかな怪力男を好演した(この映画に関係ないが)
2014.11.04
コメント(0)
-

さよなら、アドルフ(オーストラリア、ドイツ映画)
元のタイトルは「ローレ」、主人公の14歳の少女の名前だ。ローレを筆頭に妹リーゼル、双子の弟ギュンターとヨルゲン、赤ちゃんのペーターはドイツ敗戦まではナチ将校の家庭の子として威張って暮らしていたのだろう。6歳くらいの弟ギュンターの平気で他所の食べ物を盗んだりするあたりに、傲慢に暮らした面影が見える。しかし敗戦とともに立場が逆転する。お父さんは家族を山の中のあばら家の別荘風の家に疎開させて、どこかに消えた。お母さんもナチ党員として、おおやけに行動していたため、近所の人からは食べ物さえ売ってもらえないどん底の立場に落ちた。そしてお母さんは居ればどっちにしても逮捕されるからといういいわけで、一人で子供を残し去って行った。小さな赤ん坊にいたるまで、ローレの手にゆだねられたのだ。ハンブルグのお祖母さんの家に行きなさいと言われたが、1945年6月、敗戦直後のドイツでは簡単に旅行などできる状態ではなかった。子供を残して消えた両親が不可解だ。如何に逮捕されるからと言って、よくも去って行けたものだ、と思ったが、そうしなければならない理由があるのだろう。お金と少しばかりの宝飾品を手に子供5人は家を出て南の地方のシュバルツバルトから北へ向かった。この旅の始終が描かれている。交通機関は戦争で寸断されていたのだろう、ほとんどの行程が徒歩だ。荷物を満載した村人の馬車が来ても乗せてもらえない。あたりの村は焼かれ壊され、なぜ撃たれたのか死体があちこちにあったが、目指す食べ物はない。彼らは飢えた。赤ん坊はお腹を空かせて泣く。彼らの後を一人の若い男が付けてきたが、彼はトーマスといってユダヤ人の身分証を持っていた。実はローレはユダヤ人を嫌っていたが、、。或る農家の主婦が助けてくれたが、その人はまだこうなっても熱心なナチ崇拝者だった。この頃、南西ドイツはアメリカ占領区、北西はイギリス占領区、西はフランス占領区、東部はソ連占領区だった。通行証となる身分証がなければ行き来できない。子供らのいるところではアメリカが占領していてナチ党員だったものには戦犯逮捕されかねない恐ろしいところであった。だが、ここではユダヤ人身分証は有利だった。ユダヤ人の青年と行動していたから子供らは北へ移動できた。ただしこれから行こうとするハンブルグはソ連占領区だ。敗戦を受け入れるについてドイツ人は個人的にばらつきがある。村の広場にはユダヤ人収容所でいかに悲惨なことがあったか、写真で宣伝している。素直に驚く人もいるが、これはプロパガンダだ、うその写真だ、ドイツはまだ完全に負けていないという人がかなりいた。ヒトラー総統が死んだというニュースが来ていても、まだ最終勝利があると言い張る。あきらめが悪い?いや、日本の場合と比較してみると、こうなるのが分かる。日本では8月15日、有名な玉音放送があり、全国民は天皇の声から、敗戦したことをはっきり告げられた。それをすんなり受け入れたというか、受け入れるしかなかったのだ。ドイツにはこれがなかった。まだユダヤ人を憎む人や、今度はナチスに報復しようとする人が混在していて、負けてすぐの国の4分割が精神的にさらに混乱を助長した。こんなドイツの様子がくわしく描かれた映画は珍しい。(おまけ)苦しい旅(本当に苦しい旅)が終わり、ハンブルグの祖母の家で風呂に入り、食事をする。ここで、最後の大切なポイントがある。つぶさに国内を見て現状を知って、味方してくれたユダヤ人や冷たい態度のドイツ人に接してきたローレの心には、ドイツ人の優越感の塊のような祖母の姿は嫌悪を覚えるものだった。生まれたギャップは深い。
2014.11.01
コメント(0)
-

ウォール・フラワー(アメリカ映画)
原作はスティーブン・チョボスキーという人が書いたベストセラー青春小説だとか。映画化にあたって脚本も監督もチョボスキーさんがやってしまったとは、なかなか度胸のある人だ。ペンシルバニア州ピッツバーグ郊外の高校での出来事。主人公の16歳高校一年生のチャーリー(ローガン・ラーマン)は孤独で静かな生活の中にいたが、学校でサムという女の子に出会ってから、生活が変わる。サムがエマ・ワトスン、サムの義理の兄パトリックがエズラ・ミラー、この3人が織りなす青春ドラマだ。時は1991年まだ誰もが携帯を握って離さない時代にはなっていない。電話は家の備え付け電話である。アメリカの高校生ドラマは私の苦手の分野の映画である。男女交際に没頭し、誰かの家に集まって馬鹿馬鹿しい大騒ぎパーティ、スポーツ選手がスター扱いされて、いったいどこに静かな学園生活があるのだ!と、私は自分の全く面白い事のなかった、図書館に入り浸っていた生活を思い出して、嫌な鬱状態になってしまう。うらやましいのではない。アメリカのより何もなかった自分の時代の方が良かったと懐かしいのだ。何も騒がしいことがなかったから、学校へ毎日行って帰るだけで、それだけで落ち着いて成長できたのではないかと思う。それはさておき、如何に主人公が引っ込み思案で、目立たない壁の花的存在の人間だったとしても、これがありのままらしいアメリカらしい浮かれぶっ飛んだ学校生活が描かれている。エマ・ワトスンはピックアップトラックの荷台の上に立って風を受けて手を広げる、、、はたしてこれが格好良いのだろうか?少なくともローガン=チャーリーから見ると格好良いことだった。エマの女友達たちに紹介され親しくなる。どの子もきついメイクだ。派手でセクシーな衣装にきついメイク、もううんざりだ(もちろん私はセーラー服だった)男子は結構喧嘩しやすい。すぐ殴る、我慢も勉強の一つだろうに。というわけで、私的には合わない物語だった。エマはハーマイオニーちゃんの名残で好きだが、どうも粒が小さい。ローガン・ラーマンは適役だが、もっと中身のある大人物に出るべきだ。エズラ・ミラーが何かと目立っていた。さんざんな感想になってしまった。(おまけ)彼らの時代1990年は「ロッキーホラーショー」がもてはやされていた。町の上映館ではスクリーンでの上映に合わせて舞台でロッキーホラーの仮装をした高校生たちがスクリーンの音楽に乗って自分たちのショーを繰り広げる。オカマのクイーンに扮したエズラ・ミラーが見もの。
2014.10.30
コメント(0)
-

少女は自転車に乗って(サウジアラビア、ドイツ映画)
サウジの首都リヤドに住むワジダという10歳の少女が主人公だ。サウジアラビアの映画というのは確か初めてのはずだ。女性監督ハイファ・アル・マンスールがサウジの人なので、リヤドを舞台の映画が誕生した。もう見るもの何から何まで珍しいことだらけで、生活ぶりも家庭環境も社会のなりかたも、すべて我々の国と違っている。国の名前からして「サウド王族のアラビア」という意味らしいが、宗教は言うまでもなくイスラムだ。学校は男女別の学校、外へ出るときは女性は黒い布で頭と顔を覆っている。自動車は男しか乗れないので「運転手」というのが職業として存在し、各婦人たちは特約の運転手と契約している。そうでないと仕事にも買い物にも行けない。町の中では黒い長い服ですっぽり全身を隠した女性たちが2人連れ(滅多に一人はない)で歩いている。女性の遊び場などないだろうが、ブティックはあってワジダの母は派手なドレスを買った。もちろん家の中だけできているだけ外ではまっ黒だ。お母さんは一軒の家にワジダと二人で暮らし時々お父さんがやってくる。「もう一週間も来ない」と言っていたから、夫婦と言っても不安定なものだ。第1夫人だが子供がワジダという女の子だけなので、お父さんはまもなく第2夫人をもらうつもりだ。男の子が欲しいのである。家には「樹の家系図」が貼ってあるが、枝に書かれた名前は男だけ、ワジダは載っていない。学校の先生は女ばかりだが、お転婆で言うことを聞かないワジダは校長先生にいつも睨まれている。近所の仲良しの男の子が素敵な自転車を買ってもらったので、彼女も欲しくなった。値段は800レアル、調べてみると日本円で25000円くらいだから、ほぼ同じくらいの売値だ。どうしても800レアル欲しいので、コーラン暗唱大会に出て賞金1000レアル取ることを狙った。宗教がためのお堅い生活ぶりのようで、家にはプレステゲーム器があってワジダとお父さんがやっていたり、「コーラン暗唱と質疑応答のソフト」のセットもあって、コーランのにわか勉強も家で簡単にできるところが面白い。とにかくイスラム圏の女性の暮らしが驚きの連続で映画の価値のほとんどを占めている。ワジダを演じるワード・ムハンマドという子がきれいで賢そうなので好感がどんどん高まる映画だ。お母さんはふくよかで美しい人だ。アラビアでは太っている方が美人とみられるらしい。どんな環境でも子供は順応して精いっぱい生きるものだと元気な彼女に感心した。(おまけ)家にお客さんが来てご馳走を出す場合、お母さんは客の前に出ない。料理の皿をドアの前に置いてコンコンとノックする、お父さんが出てきて廊下の床にある皿を取る。それが当たり前らしい。
2014.10.30
コメント(0)
-

ネイビーシールズ・チーム6(アメリカ映画)
アメリカ海軍特殊部隊の中でもテロ対策デブグルーチームと呼ばれるチーム6はある作戦で有名だ。それはオサマ・ビンラディン殺害計画コード名ジェロニモを遂行したことだ。数年前、映画「ゼロダークサーティ」で描かれていた2010年5月2日の深夜の決行が、別の映画で描かれるというとやはり観たくなるもの。ちなみに「ゼロ・ダークサーティ」とは深夜12時30分をいう軍隊言葉なのだが、12時30分についに決行の命を受けたチーム6が出発したのが12時30分、現地到着が1時であった。こちらも結構、スリル満点の軍事作戦映画であった。2001年9月11日以来、アメリカの念願となっていたアルカイーダのビンラディン逮捕殺害は、こぎつけるまで長い時間が必要だった。ラディンはアフガンの山に潜伏というのが一般的な見方だったが、意外にもパキスタンの首都イスラマバードからほど近い地方都市アボッターバードに屋敷をもって平穏に暮らしていると分かった。これは逮捕された部下の口から洩れた事で、まもなくラディンの腹心の部下がアボッターバードのある家に頻繁に行ったり連絡していることから、ほぼ事実であるとみられてきた。絶対にあの家に居ると確信した女性捜査官が「ゼロ、、」ではジェシカ・チャスティンによって演じられていたが、この映画にも登場、キャスリーン・ロバートソンというギスギスした仕事いのちの女性として出てきて活躍している。彼女の意見、確実にあの家にいる、早く攻撃しないとスパイが通報する、という意見に周りの同僚や上司が不安をもっておさえこもうとするところは二つの映画とも同じだ。攻撃して間違いだったはゆるされない。だが衛星写真などで背の高い男(ラディンは身長194センチ)が時々庭を歩き回っているのが目撃され憶測は信じられるものとなって行った。しかしビンラディンを屋敷で逮捕するといっても、なんといっても土地はパキスタン国内だ。もしパキスタンが匿っているとしたら、早晩情報が漏れるだろうし、突入すればパキスタン軍の知るところとなり厄介なことになる。かなりの危険を承知で決行はなされた。決行までのそのあたりのいきさつが面白い。2台のヘリが屋上と庭に降りてからは、シールズ兵の銃撃戦がすごくて、あっという間もなく作戦が終結する。実際の出来事としてみれば戦力のスゴさが印象的だ。シールズ兵は生きた人間の武器のようだ。(おまけ)三角地形の堅固な要塞風の屋敷はすでに「ゼロ、、」でおなじみ。深夜、犬の騒ぐ声とヘリのかすかな響きに目ざとい少年が起きだして、庭に出て空を見上げる。その時すでにヘリが家の上に来ていた。
2014.10.23
コメント(0)
-

インフェルノ大火災脱出(香港=中国映画)
間をおいて忘れるころにやってくる、ビルの大火災映画だ。映画史に燦然とそびえる古典的名作「タワーリングインフェルノ」を超えるのはかなりのワザがいるが、タイの監督ダニーとオキサイドのバン兄弟はよく頑張っている。彼らのいいところはハリウッドに負けない新しい技術や表現を持ちながら、あくまでアジア人の目で撮っているところかも。舞台は中国本土の広州市で、ここも高層ビルが乱立する新興の発展都市だ。広州産業ビルとかいう大きなビルで火災が発生するが、この映画の場合地下の空調設備室から出火し、上に燃えてゆくパターンだ。上に行くといっても火の走りは予測を超えて意外な進路を取るのでそこが怖いところだろう。天上の薄い弱いところや吹き抜けやあるいは階段など見えない部分の中を火が猛烈なスピードで駆けあがりたちまち30階くらいまで達する。外から見ているといきなり上の方の階の窓が爆風でとび黒煙と火炎が噴出する。広州の大きな消防ステーションから多くの消防車が駆けつけて、まず低層階の取り残された人を助け、上階には梯子を用いて救助するのであるが、息も告げぬスリルの連続で火災映画の醍醐味(?)が味わえる。人物関係は消防署の部隊長の兄のダーグン(ラウ・チンワン)とビル内に防災警備会社を設立し立ち上げたばかりの弟のクン(ルイス・クー)の二人が中心だ。過去に心のこだわりを持つ兄弟と兄ダーグンの妻が火災の危険の中でドラマを繰り広げる。こういう危険が迫るという設定の映画の中で時々、長々と思い出話などされると、「やめてくれ」と言いたくなるが、そんなイラつくところはあまりなかった(少しある)20階以上の上のいた人は、何階か毎に設けられた避難階へ誘導された。ほとんどの高いビルには中間の階に太い柱だけでできている窓のないコンクリートむき出しの階があるが、これは避難階と言って梯子を伸ばしてかけて脱出するとか、梯子を伝って消防手が入って救助するとかに使われる階なのだ。所が不心得な人がいて勝手に避難階を倉庫代わりに使って有毒薬品を置いていたという、非常に悪い行いがあって、人々を危険にさらす。避難階は倉庫ではないのだ!!ハラハラドキドキは多いが、近くの工事現場から大クレーンを火災ビルに伸ばしてクレーンを伝って脱出するという場面も迫力があった。ビルが進化しても消火法が進歩してもいったん燃えれば炎と人間の戦いだ。エンタメではあるが、自分はビル火災などに遭遇したくないなと思わせられる。(おまけ)消火に放出された大量の水はエレベーターに流れ込み、エレベーターは深い井戸のようになっていた。
2014.10.23
コメント(0)
-

大統領の執事の涙(アメリカ映画)
主人公のモデルは実在するが、1950年ごろからホワイトハウスに勤務し7人の大統領に仕えたアフリカ系アメリカンのお話だ。演じるはフォレスト・ウイテッガー、私の記憶では「ラストキングオブスコットランド」で悪名高いアミン大統領を演じた時の他はほとんど善人を演じている(皮肉にもあの映画でアカデミー賞をもらったのだが)少し下がり目で独特の表情があり好感度の高い黒人俳優だ。セシル・ゲインズというこの男は南部の農園に生まれ、過酷な綿花積み労働についていたが、脱走し、ある町のホテルのウエイターとして拾われる。ここで親切な老ウエイターに仕込まれ、ハウスニガー(家宅の中の使用人)として生きる道を選べと諭される。農業よりも仕事は楽だが、あくまで召使いとして自分というものを殺して白人に仕えねばならない。徹底して「空気になれ」と言われた。ホテルのボーイ、ウエイター、として本腰をいれて修行に励んだ。やがてワシントンDCのホテルに転職したが、思いがけなくもホワイトハウスに雇われることになった。彼に目を付けたのはホワイトハウスの事務主任の白人だったが、ホテルで彼のウエイターとしての見事な仕事ぶりを見てスカウトした。最近は「ダウントンアビー」というドラマがあるおかげで、大きなお屋敷の執事という仕事がどんなものか我々もかなり知識を得られたものだ。仕事は屋敷内のすべての仕事、靴の手入れや銀器磨きや、ご案内、食事の給仕などいろいろある。執事は大統領の部屋へ飲み物を運んだりするのでいつも大統領をすぐそばで見ている。この映画の面白さの一つはアイゼンハウアにはじまり、続く大統領たちを実力派俳優が演じているところだろう。アイゼンハウアがロビン・ウイリアムス、ニクソンがジョン・キューザック、ジョンソンがリーブ・シュライバー、ケネディがジェームス・マースデン、レーガンがアラン・リックマン(意外にもそっくり)と顔を見ているだけで楽しめる。ナンシー・レーガンがちらりと出てくるが鮮やかなファーストレディ振りにうっとりしたが、なんとジェーン・フォンダ!たった数秒の出演なのに印象は強烈だった。執事には大統領もナマの顔を観せる人が多く、各人の個性がうかがわれ面白い場面だ。さてこの映画はただ大統領が次々現れて楽しませるだけが目的ではない。大切なのは執事という仕事での黒人のアイデンテイテイだ。執事は気を遣う難しい仕事だが、黒人たりとも立派にやり遂げ、お褒めの言葉も頂戴する。これは良いことだが、一歩外の社会では黒人は多くの差別の中にいた。公衆バス、学校、食堂内、などでの差別に抗議する運動が高まる。運動に反対ではないが、主人公は息子たちが公民権運動にかかわるのを反対した。こうして彼の心の中での差別撤廃への動きが少しづつ高まりるが、長年、白人に仕えてきた気持ちを切り替えるのは大変だった。仕事をやめて一人の黒人として街に出た時初めて息子たちの運動に心から参加できたのだった。そしてついにオバマ大統領の時代になり、黒人の誇りは当然のものとなった。執事の仕事を描きながら公民権運動の進み方も描くという2刀流の映画だった。(おまけ)土だらけの綿花畑から、町のキンキラのホテルへ。ホテルの黄色の制服がまばゆい。ホワイトハウスでは白シャツと黒服のいわゆる執事服となった。
2014.10.21
コメント(0)
-

ニシノユキヒコの恋と冒険(日本映画)
ほんわかと明るく、寂しくて悲しい。ニシノユキヒコとはいったい「ひと」なのか「霊」なのか?最初から居なかったのか、居たが途中で死んでいなくなったのかある程度好きに考えても良いだろう。ストーリー上では彼は突然トラックの前に飛び出して死んだとなっている。その翌日、彼は昔知り合った女性の家に来た。恋人だったその家の奥さんは居ず、ミナミさんという中学生の女の子がいたが、彼はひょっとするとミナミを訪ねてきたのかもしれない。彼がミナミの母と知り合ったのは10年位前のことで、ミナミはまだ子供だった。彼女の記憶には海岸で母と男の人と3人で喫茶店に入ったことしか覚えていない。平気で家に上がり込んできたユキヒコは当時と変わっていない。彼は自分のお葬式に行こうとミナミを誘った。もう死んだ人の幽霊とその人の家へ葬式に行く、、、変な話だが、ミナミ(中村ゆりか)は半分夢の中のような気分でついていった。鎌倉に或る実家は立派なお屋敷だ。葬式には違いないがどこかが変だ。庭には葬送曲を奏でるための楽団がいて演奏が始まった。ドンドンピーピーまるで音の合わない聞いたこともないおかしな葬送音楽。演奏する人も変人ばかり。式に来ているのはきれいな落ち着いた女性ばかりだ。ミナミは一人の和服の女性としりあってニシノユキヒコなる人物の人生について聞かされた。飄々として楽しげな竹之内豊のユキヒコは多くの女性と知り合っていた。和服の女性は阿川佐和子、あのエッセイストの阿川さんだ。彼女はやんわり微笑みながらユキヒコのついて語る。ユキヒコが会社で知り合った上司の尾野真千子、東京のマンションの隣部屋のネコ女二人、成海瑤子と木村文乃、ユキヒコを追っかけるお嬢さんの本田翼たちとの付き合いが描かれている。果たして幽霊のユキヒコは本当にミナミのところに来たのだろうか?白昼夢のようでもあるし、誰も気が付かないところにいる優しい霊のようでもある。ユキヒコは彼女の子供の頃の思い出に或るお母さんの好きな男性だ。昔のミナミも彼が好きだったかも。子供が大人の男性を好きになってもおかしくない。ユキヒコがどんな人だったか和服の女性に聞いたことがすべてなのだろうか、ミナミの想像で出来たものがすべてなのだろうか?ユキヒコは柔らかい夏の日の光線の中であらわれてそして消えた。ユキヒコさんと女性たち、大人の世界の恋愛を想像するとき、ユキヒコさんは頼りないが好感の持てる男の人として存在した。どうみても掴み所のないユキヒコさんは自分自身を生きるというよりも、他人の生きている生活の中を漂っていた人のように見えた。庭で水やりしていたら突然ホースの水が止まった、風鈴が急になりだした、犬が顔を上げて何かを見ている、、、そんな時はユキヒコのような幽霊が遊びに来ているかもしれない。彼は生きているときもほとんど幽霊のような存在だった。(おまけ)現実的だが非現実。本田翼と伊香保温泉にいったが、温泉地で射的あそびだけしているような変なアベックだった。
2014.10.21
コメント(0)
-
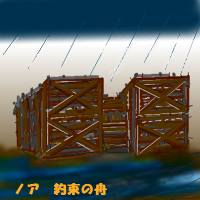
ノア 約束の舟(アメリカ映画)
「ブラックスワン」「レスラー」などの監督のダーレン・アロノフスキーがラッセル・クロウを主演に旧約聖書の洪水伝説を映画化する、、いかなる「箱舟物語」が出来るのであろうか?聖書の創世記の記述はいたって簡単で細かいことは言っていないので、描写にしろ解釈にしろかなりの幅をもって作れる部分でもある。ノアは最初の人間アダムとイブの子供のアベルとカインの二人の息子のうち、アベルがカインに殺された後、神に願って授けられた末子セツの子孫だ。この映画にはカインの子孫のトバルカインが登場し、ノアの舟の中に忍び込み密航者となっているので驚いた。聖書にはもちろんそんなことは書いていない。だから大筋では聖書に元図いてはいるがかなり脚色も入った物語として見た方が良いだろう。正義の人ノアは神に命じられる。神はご自分の判断で救うべきもの、滅ぼすべきものを選ばれるので命令は訊くというのでなく、選ばれたということがすでに命令通りに行動することなのである。簡単な記述といえども命令は作るべき船の寸法などは正確に記されていて松の木で作ること、松ヤニで木の隙間を埋めることなど記されていてなかなか細かい。40日間雨がふりつづき地上の肺で呼吸する生物は全滅して、その後150日間船は漂い、トルコの東アルメニアに近いアララテ山標高5136メートルの上にどかんと漂着した。その後一週間ごとに鳩を飛ばし帰ってこなくなったので地上に出た。この洪水で大規模な地殻変動が起きて大陸が切れたりつながったりしたという。高地に岩塩が会ったりする理由だ。解釈はいろいろあるが、この映画では人類絶滅も考えられていて、ノア一家は動物たちの守り手として使われたという意味の事が言われている。地球は動物だけの方が良いのだということか。ノアの3人の息子の妻は長男の妻一人だけだ。長男に女の子の双子が生まれたので人間が増える可能性が出来たが、ノアは増えないように殺そうとさえ思った。結局殺さなかったが、彼は自分の判断にのちに悩んだようで、ぶどう園を作り葡萄酒をのみ、アル中気味になったのは悩みのせいであろうか。人類最初に酒で悩みを忘れようとした人がノアだ。裏を考えれば面白い映画だが、単に洪水伝説のスペクタクルショーとして見ても面白い映画だ。或る説には洪水までは天空は厚い水蒸気の層でおおわれ地上は温室状態だったが、急に冷えて雨となって落ちた。急速に冷却し(氷河期)恐竜など冷温に対応できないものは死に絶えた。聖書の記述では当時の人間の寿命は700歳、800歳と長生きだったが、有害な紫外線が直接届くようになるとばったり短くなった。長生きはノアが最後だった。もし第2の洪水か洪水に変わるようなものが来てオゾン層が消えたらもっと短くなるだろう。しかし洪水だけは2度とない、神が約束されたからだ、これを虹の約束という。虹が出ている限り洪水は来ないだろう。(おまけ)箱舟に乗る動物たちが乗っている間寝ていたとは新解釈でなるほど上手い考えだと思った。これなら管理しやすい。それから箱舟作りにウォッチャーと呼ばれる怪人(?)たちが手伝ってくれたとは興味深い。神と人間の間の生き物が地上に多くいてネピリムと呼ばれていたというがその者たちだろう。仕事が済んで彼らは天に戻されたらしい。
2014.10.15
コメント(0)
-

利休にたずねよ(日本映画)
千利休の実像に迫る映画で、しかも市川海老蔵さんが演じるとあって期待高まる映画だった。確かに非常に勉強になった。堺商人の家に生まれ、師の竹野紹鴎から茶道について学んだ利休は優れた美意識でまもなく師匠を追い越したようだ。紹鴎を海老蔵さんの父の団十郎さんが演じているが、歌舞伎役者のもつ独特の空気は茶人の風格に自然と似合っていて、この配役だけでも満足すべきだと感じた。原作者山本兼一さんの希望された配役だと聞いた。海老蔵の利休は人格的にスケールの大きな人を現していて、当時の大名や、関白秀吉すら彼の前では一目おきたくなるような感じの大物を感じさせる。ずっと昔からなぜ利休が突然、切腹を命じられたか謎になっているのだが、映画ではそれについて一つの答えが明かされる。まだまだ彼の死については諸説の解釈がなされるだろう。永遠の謎を残した偉大な茶祖である。堺の町で放蕩息子だったころが描かれるのは興味深い。私はずっと長く堺に住んでいたことがあるので親しみがあるが、戦国、桃山時代の面影はちょっと偲べないにしても、南宗寺などがかっての面影をしのばせる場所はある。利休は堺では南宗寺で茶の修業をし、南宗寺とゆかりの京の大徳寺に移った。秀吉の茶僧になって実力を発揮し、聚楽第内に屋敷をもらい3千石もらっていたというからちょっとした小大名並だ。すべてにおいて明察なこの人に秀吉はかなり意見を聞いて頼っていたのではないか。だから三成らの家来が彼を煙たがり、追放の原因になったように見える。賢すぎてねたまれるのも考え物だ。今のお茶の家元が千という苗字を名乗っておられるように侘茶の基礎を作ったのは千利休だ。映画全体は静かなトーンでやや退屈な感じすらしたが、この時代に彼によって確立された茶室の様式、茶室を建てる場所、などが画面に出てくる茶室を見ていて良く分かった。究極のシンプルさの中に最大の美を見つけた利休は素晴らしいと思う。茶道具についても値段や来歴などよりも如何に侘茶の精神にぴったりくるかで選んでいて、今でも茶道具を見立てる際は、「これを利休ならどう評価するか」が基準となっているかと思うくらい、大きな影響を残している。こういう利休の積み立てて行った茶の道を映画の映像で見てゆけるのは最大の特典だろう。彼の無二の親友(?)だったのに切腹を命じ(一説には利休が折れて謝ってくるのを期待していたとか)た秀吉という人も、大友南朋によってかなり良く描かれている。茶については好きで熱心だったが、彼の性格は「侘び」とは合わない。金の茶室を設計させたのは秀吉だった。だが、秀吉の案で企画を利休や当時の大茶僧がして、開催した有名な北野大茶会(1587年10月)が面白い。茶の好きな人は誰でも参加でき、2畳のスペースをもらって茶席を設けられる庶民参加の大イベントで、服装も問わない、お菓子に干し柿を使った人もいるそうだから前代未聞の茶会だったろう。10日間の予定が1日で終わったのは残念だが。もちろんこの茶会で一番人気の茶席は利休のだった。大きな業績を残し謎のうちに死んだ利休、いったい何があったか尋ねたい人は多くいるだろう。(おまけ)堺には古い饅頭屋が多い。京都や金沢やそのほか島根などお茶の盛んだったところには、美味しいお饅頭が多い。茶道の残したありがたい置き土産だ。饅頭を食べるときはせめて煎茶でもいいからお茶と一緒にたべて欲しい、饅頭への敬意をこめて。
2014.10.06
コメント(0)
-

小さなおうち(日本映画)
ベテラン山田洋次監督が、彼のお得意の昭和初期(15年ごろから)の家庭を描く。今までとちょっと違うのは登場人物がこれまでスポットライトを浴びたことのない女中さんが中心になっているのが珍しい。山形から東京に来た二十歳の若い女中さんのタキさんを演じるのが黒木華で、初々しく可愛い。タキは東京の新興住宅地の丘に建つ小さな赤い屋根の洋風の家の平井さんの家に働きに来た。平井さんの仕事はサラリーマンで奥さんと男の子が一人、今なら女中さんを必要としない家であるが、戦前の昭和の家庭では中流の下くらいでも女中さんがいた。居なければ困るのだ、何しろ掃除、洗濯、料理、縫い物、すべて手作業である。これを全部奥さん一人で片づけるとなると座る間もなく奥さんはお茶の一杯もゆっくり飲めなかっただろう。奥さんの助手の女中さんがいて初めてゆとりの時間が生まれる。平井さんの家は子供が一人だけだが、この時代は大概5,6人の子供はいたから女中さんは必須だった。近所でも目立つ赤い屋根の洋風(中は応接間以外和室)の綺麗な小さなおうちに住み込み、きれいな若い奥さん(松たか子)と会社勤めの旦那さんと坊やと一緒に住めるなんて山形から来たタキさんは幸福だと思った。田舎生活ではない都会の暮らしも味わえるし、仕事も畑仕事よりも楽だし、女中さんはそんなに悪くない仕事だった。さてタキさんの女中暮らしは順風満帆に続くはずだったが、小さなおうちにも変化が起きはじめる。現実主義の凡人である旦那様に対して、ややロマンチストで夢見がちな奥様が目の前に現れた若い文学青年風の男(吉岡秀隆)に惹かれて行って不倫に走ってしまうのだ。家庭の外ではだんだん戦雲が厳しく近づき世の中が戦争待望になりつつある。タキの愛する「小さなおうち」の平和は守りきられるだろうか?映画は家の中の風雲と家の外の騒然とした世相が同時進行で描かれて行く。戦争に行く恋人と最後の逢瀬に行こうとする奥さんを女中のタキは必死で止めた。奥さんと恋人の運命を左右したかもしれないこの制止は、若いタキの心に重い石となってのしかかった。制止せずにいられなかったタキだが、その責任は彼女を苦しめた。全体として映画は山田調ともいえるなめらかで手慣れた調子で進んでゆく。良いテーマだと思う。しかし苦言を呈したいのは、現代の平成になってのタキが思い出を話し、弟の孫の青年
2014.10.05
コメント(0)
-

ペコロスの母に会いに行く(日本映画)
監督の森崎東さんという人を知らなかった。この映画を見てみずみずしい感覚と物事を受け止める柔らかなふところの大きさからたぶん、まだ若い新進の監督さんだろうと思ったら、全く外れ。なんと御年86歳の立派なご老人だった。2013年の日本映画で各方面から諸手を挙げて歓迎され堂々ベストワンになった映画である。原作者の漫画家岡野雄一さんも64歳、主演の赤木春恵さん88歳とまわりは老人だらけなのに、なんという軽やかさ、明るさなんだろう!雄一さんと母親のミツエさんの人生を描き、人生肯定、生命讃歌の物語だ。ペコロスという芸名(?)で歌をうたう歌手であり、漫画家でありサラリーマンもやっていた雄一さんは老母と息子の3人暮らしらしい。長崎の坂の或る住宅地に住んでいる。雄一の父、ミツエさんの夫が亡くなって以来、ミツエさんはボケだした。家族の誰と誰が居て、誰が死んでいなくなっているのかわからない。毎日起きるトンチンカンな出来事がユーモラスに描かれる。作者はずっと長崎市に住んでいるし、監督森崎さんも長崎出身なので、長崎という町の中身をよく知った人の目線で描かれていて、それだけでも大いなる特色である。家を無断で出て歩く母に、雄一は手を焼いてついに老人ホーム(グル-プホーム)に入れる。ずっと家に居る場合は母は息子を認識していたが、ホームにいて息子が会いに来るとなると会ってすぐには彼を息子と認められないらしい。雄一が毛糸の帽子を脱いでハゲ頭を母の目の前に突き出して「雄一だよ!」というと途端に分かり、ニコニコして頭をなぜる。これが繰り返されると、ハゲ頭~喜んでなぜ回す~親子の気持ちが通じる、というコースになってきてユーモラスだ。幸せ感が母の手を通じて伝わってくるような気がした。認知症がひどくなってゆく母にどうにもできない息子というストーリー展開なのであるが、私はこの映画を見ていて、母のミツエさんの人生の方に感動した。それも実に平凡な人生だ。天草の百姓の家の10人姉弟の一番上に生まれ、妹たちの子守に明け暮れた少女時代であった。サラリーマンの夫(加瀬亮)と結婚し長崎市内へ。だが夫は気が弱く、酒におぼれ、給料も酒に消え決して楽な生活ではなかった。しかし彼女は夫を愛していたらしい。雄一さんはそんな母と父を見て成長したが、酒飲みでもお父さんは大好きだった。この女性の長い暮らしの中で少しの光として輝いた家族や親友への愛の想いがキラリと光っているような気がした。ラスト近くの長崎ランタン祭りの夜のメガネ橋の場面に彼女の人生が凝縮されていて、感動で涙があふれた。このミツエお母さんは2014年8月に91歳で亡くなられたそうだ。年取って、頭がボケて、あるいは頭がハゲて、そのほか色々あってそれでも暮らしは続いてゆく。人間は皆そうなんだ、とこの映画言っているようだ。長崎の町には今日も明るい朝が来た。(おまけ)赤木春恵さんは名演だが、私は若いころのミツエさんを演じた原田貴和子さんがとても良いと思った。やや武骨で、不器用そうな女の人だが、素直な感情がほとばしるような純粋な女性だ。
2014.10.04
コメント(0)
-

鉄くず拾いの物語(ボスニアヘルツェゴビナ、フランス映画)
ファーストシーンは髭の濃い彫りの深い顔つきの男たち。住んでいるのは森に近い掘立小屋の集落、家の周りには車の残骸や雑多な物が積まれている。これはトルコかイランの映画か?と思わずパッケージを見直すと監督ダニス・タノヴィッチとある。あの「ノーマンズランド」の監督のボスニアの映画であった。この人たちは何人か?ヨーロッパに出稼ぎにきた中東人か?だが、そうではなくロマつまりジプシーの人たちであった。彼らは何世紀も前からヨーロッパの各地にひっそりと町から離れて暮らし独特の集団を形成している。バルカン半島にはロマは多いようであった。さて、ドキュメンタリーのような感じのするこの映画に登場するのはムジチ一家だ。ロマ集落の一角に小さな家があり、パパのナジフ、ママのセナダ、女の子二人でサンドラとシエイラの4人家族だ。子供は5歳と3歳くらいだろうか。毎日は平穏の日々だ。仕事は集落の男たちがほとんどそうであるらしく、鉄くずを集めて売って暮らしている。捨てられる廃車も彼らはきれいに分解して鉄の部分を集め売りに行く。鉄なら何でも集めて売って、ささやかではあるが食べるには間に合っているようだ。今日も寒い外からパパが帰り、みんなで食事する。ジャガイモやベーコンやほかの物を鍋で焼いたものを食べていたが美味しそうだ。ところがある日ママがお腹が痛いといって寝込んでしまった。妊娠中の胎児が死んで流産しかけている。遠い街の病院へ行ったが保険に入っていないので手術には大金がいると告げられた。分割払いもダメ、結局家に帰る。こうして2度も行ったが手術してもらえなかった。ロマの支援会にも頼んだがダメだった。元が放浪の民で社会機構に属することを避けてきたというか、オミットされてきたロマは保険に入らないことがあるのだろう。金があれば問題ないがパパにはない。そしてママの状態は放っておけない容態になってきた。こんな家族の危機を描く映画だが、演じているのはこの体験をした本人たちだそうでロマ族の人なのだ。観ていて感じたが彼らは血のつながりが強い。まずは家族だ、パパは子煩悩で娘を可愛がる。困った時は近所のひとの力を借りる(金はダメだ)それでだめなら親類に助けを求める。社会から除外されればされるほど血族が固まる。あるいは余計孤立してしまう事の原因かもと私は想像した。ロマの暮らし方、置かれた社会の位置などがこの出来事でかなり分かった。結果が良かったので微笑ましい物語になったが、もし悪い方へ行っていたら気の毒なことになっただろう。思わず物語に引き込まれ感動した映画である。(おまけ)国の片隅で鉄くず拾いしながら静かに暮らすロマ達が印象的。都会では犯罪者のように白い目でみられることもあろうが、集落での暮らしは穏やかで幸せそう。危機が起きなければよいが。「おれたちだって戦争に行った、死んだ身内もいる」と言っていたが、兵役は来ても社会保障が届いていないようだ。
2014.10.03
コメント(0)
-

マッキー(インド映画)
原寸の蠅が主人公の映画なんて考えられない。しかし驚いたことにインド映画には存在する。しかも猛烈に面白い!蠅と侮るなかれ、蠅パワーおそるべし!だ。陽気で元気な若者ジャニが、恋敵で腹黒の悪者のスディーブに殺され、倒れたジャニの体からスゥーッと魂が抜けだして、たまたまそばにあった蠅の子供(つまりウジですね)の中に宿り、ジャニは蠅に転生した。同じ生まれ変わるならもっと良い動物がいい、なんて欲言ってられない、運命の出来事だ。ジャニは蠅であってもスディーブに復讐を誓う。どうして復讐するか、ここがインド映画お得意のエンタメ技術の粋の見せ所だ。とにかく理屈抜きで面白い。だからこの映画の主人公は悪役のスディーブってことになるかもしれない。これでもかこれでもかと蠅にやられ、苦しめられ、痛い目にあわされ、七転八倒するのである。あんまりやられるので気の毒になるくらいだが、見るからに憎々しい面がまえで、威張りくさった嫌な野郎なので、蠅の方に味方してしまうのは当然、こちらにはビンディという可愛いお嬢さんが付いていて彼に力を貸している。彼女の仕事はミニマルアクセサリ作りなのでマッキーのゴーグルや小物の道具も作ってくれるので便利だ。ビンディはジャニの愛する恋人だが、スディーブが横恋慕したというわけ。マッキーとはヒンドウ語で蠅のことだという。蠅だからこそできるギャグの数々はよくぞこれだけかんがえたものと感心するくらいだ。手をこすり目をクルクル動かすマッキーは人間よりも愛嬌がある。歌はあっても踊りがあまりないのは寂しいがアクションは満足できる多さで絶対見るべし!蠅映画の大傑作だ。(おまけ)インド映画のアイデアの広さにはかねがね感心していたが、蠅に転生、蠅が仇に復讐とは!何が出てくるやら楽しみなインド映画だ。
2014.10.02
コメント(0)
-

ペインテッド・ヴェール(アメリカ映画)
「ある貴婦人の過ち」というサブタイトルが付いているが、女主人公のナオミ・ワッツ扮するキティという女性は上流階級の人には違いないが、貴婦人というほどのものではない。ナオミ・ワッツはイギリス生まれながら、固さがなくアメリカナイズされているので、古くはグレタ・ガルボが演じたというヒロインに果して適役だったか疑わしい。ガルボなら絶対固さは十分だっただろう。相手の夫役はエドワート・ノートンが演じるが、こちらはぴったりの適役で、誰にも犯させない自分の世界を堅持するイギリス紳士の役にはまっている。中国の奥地に行っても身なりはきちんとして、顔も清潔にと保つ生き方だが、人を寄せ付けない雰囲気があり、いくら「あなたを愛している」と言っても彼なりの限界を設けた愛し方であるのが想像できる。この人は細菌学者で自分の研究が第一なのだ。中国が任地であったが任地に帰るにつけて妻を必要としてナオミのキティを熱心に口説き落として連れて帰る。時代は1923年のこと、上流の娘たちはほどほどの恥ずかしくない夫を見つけて結婚するのが風習だ。細菌学者なら夫として合格だ、キティは彼と結婚して中国へ渡った。中国の上海に居住して地元の社交界にも顔を出す。イギリスと変わりない生活をするはずだったが、キティは女たらしのタウンゼントに言い寄られ、不倫をしてしまう。タウンゼントがナオミの現実の夫リーブ・シュライバーなのが、内輪っぽくてシラケるが、そういうことだ。夫ノートンは冷静だがすべてを見抜いていた。むしろ、これを動機にして、自分が行って研究したかったコレラ流行地方への旅に、妻の同行を求めた。なかば強制的な求め方だった。こうして、山また山の僻地もいいとこ、猛烈な淋しい桂林の奥地に夫妻は行く。罰のようなコレラ地帯への旅、その地ではたった一人のイギリス人と修道院ノシスターが英語の会話のできる人たちだ。夫はさっそく研究に没頭し、ナオミは暇を持て余す。この映画は不倫から愛が無くなった夫婦の無謀なまでの危険な旅が描かれている。その先に待つものは夫婦の再生かコレラの死か?原作者サマセット・モームはさすがに簡単には夫婦の和解を許さない。そして最後に至って光が見えた時、、、。この映画でなによりも印象に残ったのは、100年以上前のアジアで猛威を振るったコレラという病気だ。発病して36時間ほどであっという間に脱水症状で死ぬ。それほど嘔吐と下痢がひどい。映画では病人たちのありさまがかなり詳しく描かれていてコレラは怖いものだと感じた。今でも潜伏した菌があばれだして流行が起きることがあるそうだ。近年、O-157のようなコレラに近いものも流行ったが、コレラそのものははるかに感染力は強く致死率も高い。エドワート・ノートン、トビー・ジョーンズらイギリス勢に対してアジア代表は地元の軍(国民党か?)の隊長のアンソニー・ウオンが知性を感じさせる中国人として出ている。モームが良く描いたアジアの辺境に住むイギリス人の暮らしぶりが映画として描かれて興味深い。(おまけ)約50年前、サマセット・モームの書くものはイギリスはもとより日本でも大人気だった。新潮文庫から出る濃紺と渋いグリーンのモダンな表紙カバーの本は手に入れたい憧れの本だった。モームはスパイ物、伝記風、恋愛もの、多岐にわたる器用な作家で、私は彼の「人間の絆」に感動してしばらくは最も大切な小説としていた。アジアが舞台の物も多くモーム自身も旅が好きでシンガポールの名門ラッフルズホテルがお気に入りだった。
2014.10.02
コメント(0)
-

もうひとりの息子(フランス映画)
ユダヤ系フランス人の女性監督が脚本を書き、イスラエルのテルアヴィブとヨルダン西岸地区のパレスチナ居住地区で撮影されたこの映画。脚本は入り混じるスタッフのためにフランス語、英語、アラビア語、ヘブライ語の4通りが用意された。登場するのはイスラエル人の家族とパレスチナ人の家族で、お互いのうちの18歳の息子が産まれた病院で取り違えられていたと判明するのが発端だ。ハイファーの病院で新生児の時、爆撃の心配から避難することにになりどさくさまぎれに間違えられ、18年経過し、兵役のための血液検査で分かった。パレスチナ人とイスラエル人は仇敵の間柄だ。しかし母と子の愛情は人種を越えてつながり、再会した2組の母子は互いに家族のように手を取り合った。父はそういかない。イスラエル軍の大佐の父と、パレスチナ人で立派な技術者なのに、隔離のために職に着けず自動車修理しかできない父同士は政治状態が原因で、反目した。イスラエル側と西岸地区との行き来が家族の間で頻繁に行われるが、まず必要なのが通行証だ、検問所で必ず調べられ、行く理由も聞かれる。何度も行くので検問所の兵士たちが、「また来たぞ」といわんばかりに面白がっている様子があったが、そのようにややのんびり感のある検問だった。緊張感はあるものの、東西ベルリンのチエックポイントチャーリーほどの怖さはない。つまり通行証を持っているということはかなり認められた行き来だという事らしい。パレスチナ人地区は高い塀に囲われ、中では遊牧民がヤギを放牧して、土煉瓦の家などがあり、アラビア風歴然としている。二人の息子の人格が重要なポイントだ。ユダヤ人の家でユダヤ人の子として育てられたヨセフはお坊ちゃん風の美少年で音楽家志望だ。ユダヤ人であったがパレスチナ人の両親と兄と妹と育ったヤシンはキリットした顔の賢そうな青年で、パリのフランスの親類に寄宿して大学受験に合格し、医師になる予定だ。ちょうどバカンスで帰ってきて事情を知って驚いた。それぞれの家族に動揺が起きるが、波乱の結果、2家族は共存に形に移ってゆく。異文化、異民族、異宗教でも、突然あらわれた「もう一人の息子」が本来くっつくはずのない家族をくっつける、感動作だった。甘ちゃんで頼りなくみえるヨセフが今までの自分を振り返って、勇気ある行動に出るのが意表を突く。アラブ地区に一人でゆき、実親の家に行き、まるで親類の子が遊びに来たようにさりげなく溶け込む。歓迎の夕食でアラビアの民謡を歌いだしお父さんがギターで唱和するところ、この子の優しさと強さが分かって良い場面だった。俳優はユダヤ人家族の母親のエマニュエル・ドヴォスしか知らない。私の好きな女優さんだ。ロケ地のヨルダン西岸地区がみもの。(おまけ)エマニュエル・ドヴォスは医者だ。実の子ヤシンも理由は父の足を直したい一心からだが、医者を希望した。軍人と医者の両親なのにヨセフはミュージッシャンに憧れる。実父はアラビア風ギターの名手でセミプロの音楽家だ。血は争えないもの
2014.10.02
コメント(0)
-
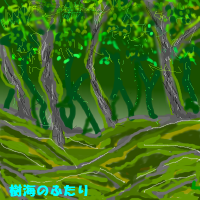
樹海のふたり(日本映画)
テレビのバラエティ番組を全く見ないでいると、疎遠になってしまうのがお笑いコンビの人たちだ。私は「インパルス」という人たちを今まで見たことも、名前を聞いたこともなかった。だから主演の二人を見て、どういう関係の俳優だろうと思った、映画の新人でもなく舞台の人でもないが、素人ではない。常に顔を見られることに慣れている人のようだし。と感じた。お笑いコンビとは後で知って驚いた。映画の中身はそれほど軽いものではない。富士の裾野の樹海での出来事だ。ここはご存知のように自殺の名所として知られている。竹内哲と阿部の二人は自殺しに行ったのではない。二人はテレビ番組製作の会社の社員で、作った番組が好評なら次回も仕事が来て、悪ければ人の手伝い仕事に回されるという不安定な立場にいた。他人のやらないような目新しいテーマを見つけ、レポートして印象付けなければ忘れられるというところに追いやられた。哲は樹海の自殺者をレポートしようと阿部に持ち掛ける。樹海、青木が原、へ入るには本栖湖口他8つのバス停が接して存在する。二人は自家用車の中に陣取りバスが着くたびに降りてくる人の中から怪しい素振りの人を探した。もしその人が林道を外れ樹海へ足を踏み入れて行ったら、間違いなく目指す目標だ。こうして段々自分たちも樹海に近づき、とうとう樹海の中に入り歩き回るようになった。樹海では毎年の一斉捜査で必ず数十人の遺体が見つかる。しかし見つからない遺体はもっと数があるはずで、自殺者たちは見つからないことを望んでさらに奥の奥へと入ってゆくのである。溶岩流の固まってできた樹海の大地は土が浅く、木の根が縦横に地表を走っていて、湿気が多く苔が根を覆っている。緑の迷路で今どこにいるか観ようとしても大きな木がかぶさっているのでわからない。迷ったら最期なので、二人は幅広のビニールテープを何巻も買って出口の樹から体に結んで伸ばして歩いていた、戻りたかっら紐をたどればよい。だが、ひもがほどけた、二人は真っ青になる。ここは鉄を含む地層のため電波も磁石も狂ってしまうことがある。樹海の中で一人のホームレス風オジサンに出会い、出られたわけだが、このおじさんも樹海で出会い収録できた「樹海に入った人」のひとりだった。この映画はテレビドキュメンタリーの樹海の自殺者を追うだけの物語ではない。何度も何度も樹海に足を運び中に入り、いろいろの人に会い(白骨になった人も)取材者であるはずの彼らは自分たちの東京での生活に、知らず知らずに影響を受ける。出会った人の生きた道に思いをはせ、番組を作る目的以上のことを感じとった。大げさに言えば自分の人生に対する見方が変わったのである。死ぬ人にも理由があり、死のうとしたがやめた人にも理由がある。私の感想としては死ぬのも生きてゆくのも疲れる事である、ということだった。(おまけ)番組は高視聴率を取った。表彰され金一封をもらった二人。だが笑顔になれないのは取材した事がらの重さが心を占領しているからか。哲の板倉俊之と阿部の堤下敦はお笑いコンビであっても、そのために映画を壊したりしてはいない、それどころか雰囲気がテーマにふさわしい人たちだ。
2014.09.24
コメント(0)
-

死霊館(アメリカ映画)
アメリカの有名な心霊研究家のエド アンド ロレイン・ウォーレン夫妻の扱った心霊現象の中で最も厄介で恐ろしかった事件をもとに作られた映画という。事件は1971年、ロードアイランド州ハリスヴィルで起きる。郊外の森の中の古い大きな家にロラン一家が引っ越してくる。この家は1860年ごろに建てられたもので、あたり一帯200エーカーの農場の中心で地主が住んでいた。しかしこの家を建てた農場主の奥さんバシーバはかのマサチューセッツ州セイラムで起きた魔女事件の生き延びた末裔であった。自分の子供をいけにえにしたところを見られてバシーバは自殺、その後農場の周りで奇妙な自殺事件が続発した。1970年になって、この家に来た一家は全く知らなかった。一家は父母と娘5人の7人家族で町で窮屈な家に住んでいたのだろう、競売で格安の古い家を買って喜んで引っ越してきた。異変が起きたのは地下室の発見からだった。地下には前の家族たちの持ち物がたくさん残されていて、気味悪く、人引き込むような気配があった。さあ、怖くなるぞ!と観客は待ち構えるだろう。実際、怖い!かなり怖い!いろいろの怖さが出尽くしたころ、たまりかねたお母さんが有名な心霊研究家ウォーレン夫妻に相談に行く。ウォーレン夫妻もこれは確かに本物の悪霊、悪魔憑きだと断定し悪魔払い儀式を申請したが、悪魔の攻勢も勢いを増し、お母さんは完全に悪霊に支配されてしまう。ホラーにもいろいろあるがこれは「エクソシスト」系統の悪魔の仲間が人間にとりついたお話に属する。ウォーレン夫妻に扮するのが夫のエドがパトリック・ウイルソン、妻のロレインがヴェラ・ファーミガ、で巻末に出てくる本当のウオーレン夫妻にイメージが似ている。特に適役なのがヴェラ・ファーミガで、か細く、青白く素晴らしく美しいが生気に乏しい霊能者にぴったりだった。霊感のために人よりも余計に怖い思いをしている気の毒なくらいの感覚の鋭どそうな女性だ。悪魔憑きは実際に或るらしいが、この映画の怖さはお話が半分くらいは事実に基づいているというのが一番怖い点で、映画の怖さとはまた別のものである。映画自体の怖さはほどほどで驚くほどのことではなかったが、地下室は確かに気味悪い。(おまけ)「死霊館」というタイトルはどうなんだろう。まるで見世物のオバケ屋敷のように聞こえるが、実話に基づくオカルト劇でかなり真面目な話なんですが。
2014.09.22
コメント(0)
全2943件 (2943件中 1-50件目)
-
-

- TVで観た映画
- 「ゴジラ-1.0」 【監督 山崎貴。20…
- (2024-11-21 18:14:04)
-
-
-

- 東方神起大好き♪♪ヽ|●゚Д゚●|ノ
- ZONE (2CD+スマプラ)<JACKET(B)>(…
- (2024-11-11 00:00:15)
-









