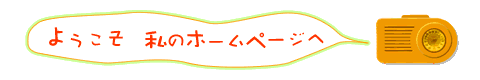インディー(13)
「田舎は・・・?」
うなづいてくれた
(おれの郷里からも、こんな美しい子が出現するんだ・・)
彼女は、ティーカップの口紅の跡を指で拭いながら、話し始めた。
「ことばですぐにわかってしまいますね。わたしの彼も同じ関西出身やけど、ことばの違いについていちいち細かいですわ」
(ですわ・・は語尾が下がる)
「ここははじめてだよね?」
(口を真一文字に結んで、真剣な眼差しでうなづいた)
常に緊張したように背筋をピンと伸ばしている
「姿勢がいいね!」
「バレエやってましたから」
(また真剣な眼差し)
「いつごろまで?」
「ついこのあいだまで」
「大学に入ってからやめたんだ?」
「そうです」
(いつもきっぱり)
「ぼくは、バレエのことは、ほとんど知らない」
「・・」
「ここの眺めはいいだろ?」
(黙ってうなづく)
窓の外は、夕闇が迫っており、行き交う人たちの顔は、もう判別できないほどになっていた。
「専攻は?」
「美学です」
「あぁ・・」
「ぼくは専攻は生物だったけど、2回生のとき美学の先生にずっとついて回っていたことがあるよ。近松良之っていうおもしろい先生だった。」
「もともとはドイツ美学が専門だったみたいだけど、行き着いた先は、日本文化論」
「大蓮生まれのおぼっちゃまでね。生き方すべてがユニークだったね。大学教授を途中でやめて、養護施設を始めたんだ。学生時代に何度かボランティアで施設まで行ったよ」
(しゃべり過ぎ・・)
「ここは良く来られるんですか?」
「うん、常連だよ」
「君が今、座ってるところに陣取って、いつも無意味に時間を浪費している」
(初めて少し微笑んでくれた)
(笑うとえくぼができる)
「おなかは空いてない?」
「軽くおごってもいいよ」
「近くにいい店があるんだ」
すかさずママがチャチャを入れる。
「まあ、そんな風にここで女の子をナンパするのは何人目でしょうね~~」
ママのいつものバカ笑い。
ナオミも釣られて笑っていた。
(つづく)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 気になる売れ筋CD・DVD
- 劇場版『ウマ娘プリティーダービー新…
- (2024-12-02 11:22:27)
-
-
-

- やっぱりジャニーズ
- 楽天ブックス予約開始!ドラマ「マウ…
- (2024-09-16 22:53:26)
-
-
-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- あさって、ジンのI’ll be there 楽し…
- (2024-10-23 23:53:52)
-
© Rakuten Group, Inc.