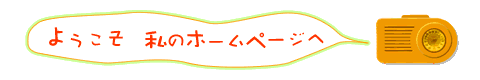インディー(146)
いつの間にやら、わいわいがやがや状態。
ユキの面接なんて吹き飛んでしまった。
「サラミのピザはまだ?」
と伊原。
「ランブルスコ持って来てよ」
て私。
「ユキちゃん、一曲聴かせてくれる?」
と常務。
一通り仕事をこなしたやっさんが、アコギを手に取ってテーブル席にやって来た。
ユキに手渡して
「チューニングはできてるよ。さっきまで弾いてたから」
とキザに言う。
ユキは、渡されたギターを抱いて、ポロロンと弾き始めた。
騒がしかった私たちは、一瞬にして静まり返る。
私も、ユキの生歌を聴くのは、初めてだった。
一緒に暮らしていたユキの安アパートでは、練習することさえできなかった。
ユキが歌い始めたのは、もの悲しい恋の歌。
コード進行は、ごくオーソドックスだったが、ユキの歌声が、ことばがハートに染みた。
こんな歌は、デモテープにも入っていなかった。
ユキが歌い終わった後、しばらく静寂が店内を支配し、まっさきに藤沢常務が、ゆっくりと拍手を始めた。
私たちも釣られて、拍手をはじめ、しばらく止めることができなかった。
「今の曲のタイトルは?」
と常務。
「ソーブルーって言います」
と珍しく恥ずかしそうにユキ。
「すんごく良かった」
と一言、伊原。
立ったまま、たばこに火を点けて、眉間に皺を寄せて、ユキを見つめるやっさん。
内心、してやったりと叫んでいた。
私が、してやったりではない。
すべてユキの霊魂のなせるわざ。
しばらくの間、だれもことばを発せず、空白の時間が流れた。
誰もアンコールは、要求しなかった。
ソーブルーただ一曲だけで、ユキという存在をその場に居合わせた者たちに刻み付けることができたのだった。
(つづく)
© Rakuten Group, Inc.