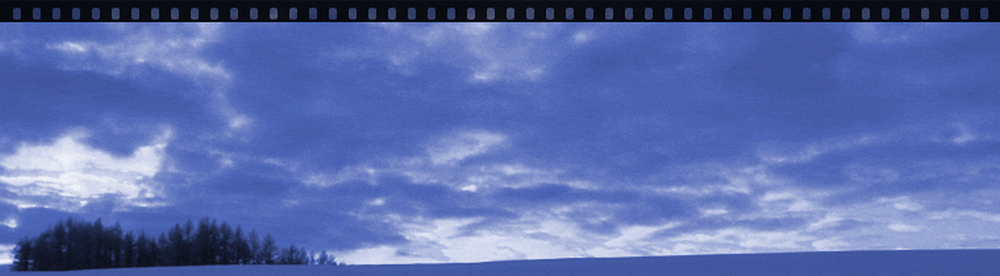僕が君に、君が僕に渡せたモノ
僕と彼女が出会って2ヵ月。
それは短い、けれどとても幸せな日々でした。
そう。
あの時は、確かに幸せな日々だったのです―――。
彼女の体はガンに侵されていました。
彼女の気付かぬ間に病気は進行し、発覚した時には既に手遅れだったのです。
人は、自分にとって信じ難い事があるととにかく否定しようとするもの。
僕と彼女が出会ったのも、ちょうどそんな時だったのかもしれません。
ある時、彼女は僕にこう言ったのです。
「一人は寂しいよ…」
と。
僕と彼女の出会いは、病院の、真っ白な部屋の中でした。
当時入院していた母親の看病で病院に通っていた僕は、同じ部屋の中で悲しそうに佇む彼女が気にかかっていました。
彼女はいつも佇んでいるだけなのです。
何をするでもなく、ひっそりと。
後で知った話なのですが、僕が彼女を初めて見たときには、もうどうしようもない程病気は進行していたそうです。
それ故に、彼女は集中治療室ではなく一般病棟にいたのです。
彼女が一般病棟にいた理由は他にもいろいろあったそうですが、主な理由は
「手の施しようがない」
というのが大きかったそうです。
そんな彼女と初めて話したのは、僕が彼女を初めて見てから1週間ほど経ったある日のことでした。
母が検査中で暇だった僕は、本を読んでいました。
部屋には僕と彼女の2人しかいませんでしたが、話しかける勇気が僕にはなかったのです。
「…何を読んでいるのですか?」
読み始めてすぐのことでした。
彼女が話しかけてきたのです。
僕は内心喜びながらも、彼女の質問に答えました。
「ただのライトノベルだけど…読む?」
僕がそう言って本を彼女に差し出すと、彼女は少し嬉しそうに受け取ってパラパラと読み始めました。
それからしばらく、僕は彼女が本を読んでいるのを眺めていました。
病室の中で、白く細いその手がページをめくる様はとても綺麗で、とても悲しくて、僕は彼女に見入ってしまい、時間が過ぎるのを忘れてしまっていました。
パタン、といきなり彼女は本を閉じ、僕がしたように本を差し出しました。
「ありがとうございます」
笑顔で、感謝の言葉を添えて。
「え…もういいの?」
僕は思わず聞き返してしまいました。
僕が見た限りでは、彼女は10ページ程しか読んでいません。
彼女は僕の問いに、はい、と答えるだけで、理由を言ってはくれません。
何度か聞いてみましたが、結局その日はそれ以上進展はなく、別れる時も軽い会釈を交わしただけでした。
それでも、それからは少しずつ彼女と話をするようになりました。
母が検査の時だけでしたが、会話の回数は日に日に増えていったのです。
趣味、日常の出来事など、とにかくいろいろなことを話しました。
ただ、ある時から気になり始めたことがあるのです。
それは彼女の家族のことでした。
彼女の言葉の中に、家族の話が一度も出てこないので思いきって聞いてみたこともありました。
しかし、彼女は答えませんでした。
僕はそれ以上彼女に聞くことが出来ず、そのまま月日が過ぎていきました。
僕は毎日のように病院に行っていましたが、結局は一度も彼女の家族が見舞いに来ることはありませんでした。
しばらくして、僕の母が退院することになりました。
そのことを彼女に話したとき、彼女は一瞬ひどく落ち込んだ顔になり、僕の手を震える手で掴みこう言ったのです。
「一人は寂しいよ…。お願い、一人にしないで…」
それは彼女が初めて見せた「弱さ」であり、心の底からの本当の言葉でした。
白い彼女の頬には滴が流れていました。
僕はしばらく何も言えずに立っているだけでしたが、不安そうな彼女の瞳を見たとき僕はある決心をしました。
「わかった。これからも暇なときはここ に来ることにするよ」
そう言った瞬間、彼女が抱き着いてきて僕はそれ以上何も言えなくなりました。
「また来て下さいね」
涙の跡の残る顔で彼女は微笑みます。
あれからしばらく、彼女は僕に抱き着いたまま泣いていました。
今まで溜め込んできた孤独を吐き出すように、大声で。
僕はやっと離れた彼女に微笑み返すと、静かに彼女を抱きしめました。
「えっ?あ、あの…」
彼女は顔を赤らめて少し抵抗していましたが、僕は構わずに、強く彼女を抱きしめていました。
しばらく彼女は僕の腕の中でもがいていましたが、諦めたように彼女ももう一度僕に抱き着いてきました。
そして―――。
「好きです。あなたのことが好きです」
「―――僕も好きだよ」
そうして、しばらくの間僕達は2人抱きしめ合っていました。
僕は毎日病院に通い続けました。
バイトがある日でも、少しでも彼女の側にいるために、僕は病院までの道を自転車で急ぎました。
僕が病室に入ると、彼女はいつも満面の笑みで僕を迎え入れてくれます。
それに僕は微笑みで答え、彼女の横に座ります。
僕達はそんなことを毎日繰り返していきました。
部屋には母が入院していた頃から彼女以外いなかったので、人目を気にする必要もありませんでした。
時には抱き合い、時には唇を重ね、僕達は互いの愛を確かめるように毎日を過ごしました。
彼女に残された時間は少なく、僕も彼女もそれを理解していたのです。
だから、僕と彼女は話しをしました。
2人でいる時間を少しも無駄にしたくなかったのです。
そしてある日、僕は初めて彼女の家族の話を聞くことができました。
その瞳は悲しげに潤んでいて、それは初めて彼女を見た時の瞳と同じ瞳でした。
とある街のとある家庭に、彼女は次女として生まれました。
小さい頃の彼女はとても幸せでした。
優しい家族に囲まれ、毎日を楽しく過ごしていたのです。
そんな日々が少しずつ壊れ始めたのは、彼女が中学生の時だったそうです。
彼女には、頭がよく有名な進学校に通う姉がいます。
それに対して彼女は、姉とは正反対で成績が悪く、いつも下から数えてすぐのところにいたそうです。
彼女の両親はそれをよく思っていなかったらしく、彼女はいつも姉に比べられていました。
そうして彼女は、段々とコンプレックスを抱くようになったそうです。
それから彼女は一生懸命勉強して、なんとか普通高校に進学することが出来ましたが、状況は全く変わりませんでした。
それから何年か経って、彼女の病気が発覚します。
その時既に家族内で邪魔者扱いをされていた彼女は、さらに邪魔者となります。彼女が集中治療室でなく一般病棟に居たのもそういう理由があったからでした。
それ故に彼女の家族は一度も見舞いにくることがなかったのです。
僕は泣きながら話す彼女を、何も言えずに見つめていました。
正直、彼女がそんな過去を抱えているとは思ってもいなかったのです。
「すみません、こんな話をしてしまって…。しない方がよかったですよね」
やっと泣き止んだ彼女が言いました。
暗い悲しみを携えたその瞳は、上を向くことはありませんでした。
僕は彼女に何か言おうとしましたが、何も言えず彼女を抱きしめただけで、そのままゆっくり時間が過ぎていきました。
後で知ったことですが、彼女の支えは後にも先にも僕だけだったのです―――。
別れは、突然でした。
ある土曜の晴れた日に、僕は「バイトがあるから」と言って病室を出ました。
彼女は寂しそうにしていましたが、明日は丸1日休みだよ、と笑って言うと彼女も笑って僕を送り出してくれました。
それが、僕の過ちだったのです。
携帯に何十回と着信が来ているのに気付いたのは、夜8時を過ぎていました。
見たことのない電話番号。それも、携帯電話からではない、明らかに近所からの電話です。
その着信は、僕が彼女に見送られてから1時間後ぐらいから始まって、5時ぐらいに途絶えていました。
頭に浮かんだモノを消すことができず、震える手で僕は電話をかけました。
無感動な音が鳴っては途絶え、また鳴っては途絶え。
永遠のように感じる時間でした。
「はい、こちら○○総合病院です」
一瞬、世界が白く染まりました。
頭は全て理解しているのに、心の一番やわらかくて脆い部分が必死に抵抗しようとしたけど。
やっぱりソコは脆くて、虚しく崩れました。
それから病院に、彼女のところに着くまでの間はよく覚えていません。
覚えているのは、バイト先を飛び出して泣きながら走ったことぐらいです。
確かめたくないのに、確かめようと走る自分が馬鹿みたいで、涙が溢れました。
医師に案内された先には、顔に純白の布を被った彼女が眠っていました。
布をめくって触れた彼女の肌は、白くて、冷たくて。それは、どうにかして否定しようとしていた僕の心を押し潰しました。
「う、ぅあああぁああぁぁ!!」
覚悟していたはずたったのに。
目の前の光景が信じられなくて、僕は彼女の名前を何度も何度も呼びました。
でも、彼女は目を閉じたままでした。
それからどれくらい経ったのでしょう。
泣き続けていた僕は、一冊のノートを看護士の人から渡されました。
そのノートは、彼女が僕に遺したノートだったのです。
ノートの中にはびっしりと言葉が並べられていました。
彼女が想いを乗せた、言葉が―――。
多分、いきなりのお別れになってしまったでしょう?
本当は、お医者さんには「ここまで持ちこたえたのは奇跡だ」って言われてた。
我慢してたんだよ?
少しでも長く笑っていたかったから。
少しでも長く一緒にいたかったから。
それももう終わりだね。
二つだけお願いしてもいいかな?
お願いさせて下さい。
どうか、泣かないで。
あなたには私が心から誇れる恋人でいてほしいから。二つ目。
忘れないで、なんて言わないけど、時々思い出して下さい。
そうすれば、私は死なないから。
お願い、聞いてくれると嬉しいです。
泣かないでね。
私は涙が止まんないけど、しょうがないよね、お別れなんだもん。
あなたはいつの日か私に笑顔をくれた。
私はあなたに何か渡せたかな?
渡せてるといいなぁ。
あ、ごめんなさい、もう一つお願い。
幸せに、なってよね。
それ以上、僕はページをめくることができませんでした。
一つ目のお願いを聞いてあげることなんて、できるはずがなくて、僕の目には全てが霞んで見えていました。
やっと涙が止まった頃、静かに彼女の唇に僕の唇を重ねました。
彼女の体はやっぱり冷たくて、僕はそこにある「死」をやっと理解できました。「…さようなら」
溢れようとする涙を堪えながら、何とかそれだけ言うと、彼女と別れたのです。
僕は、彼女の通夜にも葬式にも出ませんでした。
多分、泣いてしまうだろうから。
だから僕は行かなかったのです。
彼女が死んで1日。
ようやく少し気持ちの整理ができた僕は、彼女が遺したノートを読んでいました。
結局のところ、彼女が僕に渡したモノは何だったのでしょうか?
まだ僕はわかりませんが、受け取ったモノは確かにあります。
それは確かに僕の胸に、心の一番やわらかい部分に根付いているのですから。
僕はページをめくり、彼女の丸みを帯びた文字を読んでいきます。
彼女から受け取ったモノを確かめるために。
彼女のことを忘れてしまわないように。
そうやって生きていくために。
そう。
僕は、君のことを忘れない。
-End-
-Epilogue-
「もう、またそれ読んでるの?」
少し嫉妬気味に妻が言った。
「別にいいだろう。大切なモノなんだ」
「はいはい。いつもそればかりね」
あれから10年と少し。
私は妻をもらい、子供もできた。
それでも彼女のことは忘れていない。
それは遠い彼女との約束であり、また誓いでもあるからだ。
実のところ、彼女から受け取ったモノはまだはっきりとはわかっていない。
それはいくつもあって、何個かはわかったのだが、取るに足らないモノだった。
だからこうして今も探している。
妻はそれを不快に思わないようだし、何よりも私が知りたい。
大丈夫だ。
時間はまだまだある。
このノートと記憶が有る限り、探すことはできるんだ。
私が忘れない限り、彼女は死なないのだから―――。
© Rakuten Group, Inc.