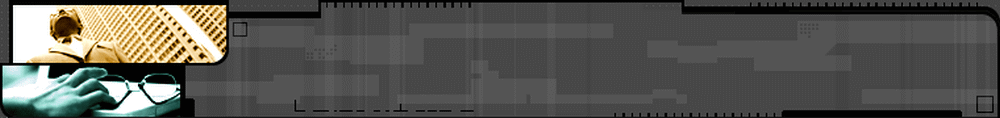PR
X
コメント新着
flamenco22
@ Re:ニッポンの魚ビジネスを牽引するメンバーが一同に介し、ブース出展者と情報交換を行うとともに、世界に向けた取り組みへとつなげることを目的とした「ニッポンの魚ビジネスEXPO2025」が開催されます!(02/16)
こんにちにゃん^^ "にせちゃ"…
elsa.
@ Re:慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。(12/12)
大学も今やあれこれと社会貢献しています…
和活喜
@ Re:東京港区立産業振興センターから NPO法人女性ウェルネス食推進機構主催の、”女性の不調は食で何とかなる!”食べるフェムケア無料セミナーを開催いたします(01/07)
こんにちは。水曜日です。北九州も宗像…
和活喜
@ Re:慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。(12/08)
お早うございます。北九州小倉は晴れで…
和活喜
@ Re:慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。(12/08)
お早うございます。北九州小倉は晴れで…
elsa.
@ Re:住友商事がセブン&アイ・ホールディングス傘下のスーパー、イトーヨーカ堂の事業を統括する会社の買収に名乗りを上げていることが26日、分かった。セブン&アイによる統括会社の株式売却に向けた入札手続きに参加する。(11/27)
コンビニも独自のセンスを編み出していま…
和活喜
@ Re:慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。(12/08)
お早うございます。日曜日です。福岡宗…
ニッポンの魚ビジネスを牽引するメンバーが一同に介し、ブース出展者と情報交換を行うとともに、世界に向けた取り組みへとつなげることを目的とした「ニッポンの魚ビジネスEXPO2025」が開催されます!
FP2級をとって、AFPになって、日本FP協会に入ろ募集がはじまりました。
東京港区立産業振興センターから NPO法人女性ウェルネス食推進機構主催の、”女性の不調は食で何とかなる!”食べるフェムケア無料セミナーを開催いたします
東京港区立産業振興センター主催、【GO GLOBAL 日本編】世界各国におけるスタートアップエコシステムのキーパーソンと繋がるセミナーの第14弾のお知らせとなります。
港区立産業振興センターにて、アパレル特化のEC・DX 企業が集結した合同展示会を開催します! 前回ご好評いただきました『ファッションテック展2024』の第二回となります。
慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。
慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。
七十七銀行が結婚相談所「ななむすび」 地銀が婚活のワケ
住友商事がセブン&アイ・ホールディングス傘下のスーパー、イトーヨーカ堂の事業を統括する会社の買収に名乗りを上げていることが26日、分かった。セブン&アイによる統括会社の株式売却に向けた入札手続きに参加する。
ミキハウスより【クリスマスフェア】のお知らせです
FP2級をとって、AFPになって、日本FP協会に入ろ募集がはじまりました。
東京港区立産業振興センターから NPO法人女性ウェルネス食推進機構主催の、”女性の不調は食で何とかなる!”食べるフェムケア無料セミナーを開催いたします
東京港区立産業振興センター主催、【GO GLOBAL 日本編】世界各国におけるスタートアップエコシステムのキーパーソンと繋がるセミナーの第14弾のお知らせとなります。
港区立産業振興センターにて、アパレル特化のEC・DX 企業が集結した合同展示会を開催します! 前回ご好評いただきました『ファッションテック展2024』の第二回となります。
慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。
慶應義塾大学医学部主催のビジネスコンテスト、『健康医療ベンチャー大賞』の最終審査会が2024年12月15日(日)に開催されます。
七十七銀行が結婚相談所「ななむすび」 地銀が婚活のワケ
住友商事がセブン&アイ・ホールディングス傘下のスーパー、イトーヨーカ堂の事業を統括する会社の買収に名乗りを上げていることが26日、分かった。セブン&アイによる統括会社の株式売却に向けた入札手続きに参加する。
ミキハウスより【クリスマスフェア】のお知らせです
フリーページ
テーマ: 新型コロナウイルス(10920)
カテゴリ: カテゴリ未分類
日本人は「コロナ倒産の増加」を恐れすぎている
「企業数の減少=失業の増加」という思い込み
2020/05/21 5:20
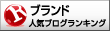
日本人は「コロナ倒産の増加」を恐れすぎている
「企業数の減少=失業の増加」という思い込み
2020/05/21 5:20
デービッド・アトキンソン : 小西美術工藝社社長 著者フォロー
「日本人は「コロナ倒産の増加」を恐れすぎている 「企業数の減少=失業の増加」という思い込み | コロナショックの大波紋 - 東洋経済オンライン」をはてなブックマークに追加
大切なのは「企業の数」ではなく「雇用の数と質」だといいます(撮影:今井康一)
退職後も日本経済の研究を続け、日本を救う数々の提言を行ってきた彼は、このままでは「①人口減少によって年金と医療は崩壊する」「②100万社単位の中小企業が破綻する」という危機意識から、新刊『日本企業の勝算』で日本企業が抱える「問題の本質」を徹底的に分析し、企業規模の拡大、特に中堅企業の育成を提言している。
コロナ後に激変する日本人の意識について解説した前回に続き、今回は「企業数と雇用数」にまつわる「日本人の大誤解」を解説する。
企業数が減ることと雇用が減ることは別問題
一般的には、企業の倒産が増えると失業者が増えるなど、雇用面に悪い影響が出ると考えられがちです。短期的には、それはありえます。
『日本企業の勝算』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら)
しかし、実は日本の場合、企業の倒産・清算・廃業による企業数の減少と雇用には、ほとんど関係がないことが明らかになっています。倒産件数のデータには、一般的に言われるほどの意味はなく、もっとその中身に注目しないといけないのです。
実際、1999年から2016年の間に、企業数は126万社も減っているにもかかわらず、就業者数は3万人も増加しています。その後も、就業者数は継続的に増えています。2018年の就業者数は6664万人で、過去最多を記録しました。
日本の大企業と中堅企業を合わせた数はおよそ53万社ですので、仮にこれらがすべて倒産したとしても、126万社には到底およびません。つまり、減った分のほとんどは小規模事業者であったことがわかります。
小規模事業者の平均雇用者数は3.4人なので、1社倒産してもその影響は極めて軽微です。大企業が1社倒産すると平均1307.6人が失業することになりますし、中堅企業でも平均41.1人の雇用者がいるので、影響の大きさは小規模事業者の比ではありません。
日本人は「コロナ倒産の増加」を恐れすぎている
「企業数の減少=失業の増加」という思い込み
デービッド・アトキンソン : 小西美術工藝社社長 著者フォロー
シェア
64
ツイートする
一覧
1
Lineで送る
2011年から2018年までの間に、日本では生産年齢人口は618万人も減っているのに、就業者数は371万人も増加しています。
残念ながら、データがあまりに充実していない日本では、企業数の最新データは2016年のものなのですが、2011年から2016年までに27.5万社減っていることから、2011年から2020年までの間、企業数は減っていると推測されます。
小規模事業者を集約し、中堅企業を育てよ
以前発表した「『日本は生産性が低い』最大の原因は中小企業だ」という記事でも説明しましたように、先進国の生産性の高低は主に産業構造によって決まります。極端に言うと、3000人の労働者を1000人ずつ3社に配分するか、3人ずつ1000社に配分するかによって、生産性は決まるのです。
日本は人口減少に対応するために、生産性を高める必要があります。もちろん企業数を3社にする必要はありませんが、小さい企業をある程度まとめて、次第に企業の規模を拡大させるべきです。
何度も言いますが、企業数が減るからといって雇用が減るとはかぎりません。先の例で考えれば、1000社に配分されている3000人を、10人ずつ300社に配分すれば、企業数は減りますが、雇用は減りません。
つまり、小規模事業者の数を減らして労働者を中堅企業に集約することで、雇用を犠牲にすることなく生産性を高めることが可能なのです。
小規模事業者を少しずつ減らしながら、労働者を中堅企業と大企業に移管する戦略を巧みに実践すれば、企業数が減ったとしても、失業者を増やさないことは可能です。しかも、この戦略によって、生産性も向上し、それに伴い給料も上がるのです。
簡単にいえば、中堅企業政策を経済政策の中心にすることこそ、この国の復活のカギなのです。
実際のデータを分析すると、企業数と雇用は連動していないことがハッキリします。こんなところでも、エビデンスの重要性を痛感します。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.