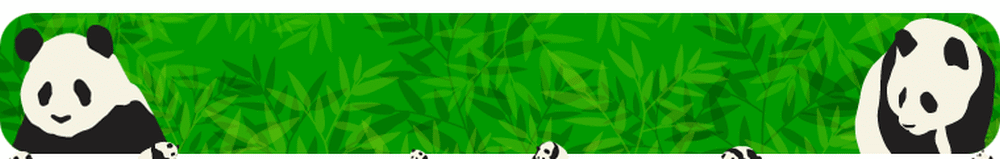進撃の巨人小説『過去』
進撃の巨人「過去」
あれは雨音の煩い夜だった。窓を締め切った部屋でリヴァイは
男に抱かれながら、叩きつけるように降り続ける雨を見つめていた。
軋むベッドの上で男が果てるのをただひたすらにリヴァイは待っていた。
王侯貴族や軍の上層部や商会の豚どもと寝るようになって、
十年の歳月が流れていた。最初は調査兵団の軍資金が足りないから
投資してくれる商会の豚に金を出させる為の接待をするよう
エルヴィンに頼まれたのが始まりだった。噂はすぐに広まり、
一晩だけでも良いから接待してくれと頼む金持ちが山ほど現れた。
子供の頃から客を取る事に慣れていたリヴァイがそれを受け入れると、
エルヴィンは毎週のように性接待をリヴァイに強要した。
大地に降り注ぐ雨水のようにお金を落としていく男たちはリヴァイにとって
雨風と同じだった。どんなに風が強くてもどんなに激しく雨が降っても
誰も守ってくれない路地裏に咲く花のごとくリヴァイは耐えた。
不幸な環境で育つと恋愛なんてものとは無縁になる。エルヴィンとは
幾度となく身体を重ねても愛を感じた事は一度もなかった。
他の男たちも同様で、欲望に忠実にリヴァイの身体を貫くだけで、
誰もリヴァイと恋愛をしようとはしなかった。ただ一人を除いては・・・
真っ直ぐに見つめる少年の瞳をリヴァイはふと思い出した。
エレン・イェーガー。リヴァイは子犬のように懐くエレンが好きだった。
最初はエレンを苛めたりもしたが、告白されてからは純粋な気持ちで
エレンと付き合っていた。男に抱かれても何の愛情も感じなかった
リヴァイがエレンにだけは抱かれる度に愛情が湧いてくる。
子犬の飼い主に似た感情も無きにしもあらずだったが、
陽のあたる場所で咲く花が幸せそうなようにリヴァイも
エレンといる時だけ幸せだった。ずっと陽のあたらない場所で、
雨風に曝され、人に踏みつけられて、孤独に咲いていた花だった
リヴァイはエルヴィンに拾われ、エルヴィンの所有物となった。
だが、エルヴィンは人が地面に咲く花を摘んで、花瓶に生け、
水を与えて、部屋に飾り、枯れ果てるまで愛で続けるように
愛玩物としてリヴァイを扱った。強欲な男たちは美しい花を絶賛し、
奪い合い、花は花で人ではない事に気付くと、共有しあった。
リヴァイは賤しい身分ゆえに人と認めてもらえなかったのである。
豚のように心が醜く肥った男にリヴァイは両手を鎖で縛られて、
組み敷かれ、激しく腰を突き動かされていた。
恍惚とした顔の豚を見るには耐えがたく、リヴァイはエレンの事を想った。
リヴァイしか知らないリヴァイだけの無垢な少年。
耳元で愛を囁く少年をほんの少し思い出しただけで、
リヴァイの身体は熱く火照り、絶頂に達してしまった。
「あっ、イク・・・ああ・・・エ、エレン・・・」
リヴァイの嬌声に恍惚とした顔で果てた豚は顔色を変え、
リヴァイを殴った。
「わしの寝所で他の男の名を呼ぶな!エレンと言ったな。
あの巨人化する少年とも寝ているのか?本当にお前は誰とでも
寝るのだな。あんな化け物のどこが良いのだ?」
「・・・」
「王族であるわしを愚弄した罪は重いぞ。値打ちのない男娼なら、
その舌を引っこ抜いてやるところだ。謝れ。返答によっては
両手両足切り落として花瓶に詰めて、部屋に飾ってやっても良いのだぞ。
こんなに愛しているのに・・・何故、わしの気持ちが分からぬのか?」
豚が泣き出した。愛というのは厄介なものだ。妻子ある身で、
花を貪り喰う卑しい豚に成り下がり、たらふく喰った後で、
愛まで欲しいと言うのだから、貪欲にもほどがある。
身分の高い人間ほど己を蔑にする者を嫌う。
リヴァイはうんざりした顔で、こう言った。
「別れてくれ。もう今日で最後にしてくれ。」
男は泣き崩れた後、怒りの形相で鞭を振るい、リヴァイを打ち据えた。
そして、恐ろしい責め具の入った箱をベッドの下から取り出し、
リヴァイを責め立てた。
「わしがお前を殺せぬのを知っていて、反抗的な態度をとるのは卑怯だぞ。
その腐った性根を叩き直してやる。わしに跪き許しを請うまで
今夜は帰さぬからな。覚悟しろ。」
身分の高い人間はいつでも暴力で支配しようとする。
リヴァイは踏まれた花のように朝までじっと耐えた。
朝陽が上る頃、雨は止み、風も心地よく吹き始め、鳥が飛び立ち、
穏やかな朝を迎え、人々が神に祈りを捧げる時間になって、
リヴァイはようやく拘束を解かれた。
踏み散らかされてボロボロになった花を嗤う豚が家来を呼んで、
リヴァイを馬車で送るように指示した。泥にまみれた汚い花に
家来たちは恐怖し、無言でリヴァイの身体を洗い、服を着せ、
まるで荷物を運ぶように馬車に乗せ、送り届けた。
エルヴィンに引き渡す時も彼らには侮蔑しかなかった。
翌日、エレンは夕食のパンとシチューを持ってリヴァイの部屋を訪れた。
体調不良で2日間も寝込んでいるリヴァイに食事を届けるよう
エルヴィンに命令されたのだった。エレンは静かにドアをノックした後、
部屋に入り、ベッドの横の机に夕食のトレイを置いた。
「兵長お体は大丈夫ですか?お城の階段から落ちたって聞いたけど・・・」
壁のほうを向いて寝ていたリヴァイの顔を覗き込んだエレンに
「・・・あとで食べるから、置いたら、さっさと出て行け。」
とリヴァイは言った。
「兵長、食欲ないなら、俺が食べさせてあげましょうか?」
エレンは子犬のような笑顔でベッドの端に腰かけて、肩を揺すり、
自分のほうを向かせた。死んだ魚のような目をしたリヴァイに
キスをしようとした時、エレンは首に鬱血した痕を見つけた。
リヴァイの服を脱がせて、身体をよく見ると、首には痛々しい
縄の痕が残り、背中には無数の鞭の痕が残っていた。
「一体、何、されたんですか?」
笑顔の消え去ったエレンをリヴァイはじっと見つめて、
「見た通りだ。ロープで首を絞められて、気を失ったらしい。
傷の手当は昨日の朝、エルヴィンがしてくれた。背中の傷も
・・・こんなのは・・・軟膏を塗っとけば、そのうち治る。」
と言った。
「まさか下も酷い事になってるんじゃないでしょうね?
見せてください。」
ズボンを脱がそうとしたエレンをリヴァイは制止して、
「今は無理だ。まだ使えない。明日はベッドから出られそうだから、
明後日また部屋に来い。可愛がってやる。」
と言った。
「あんたって人は・・・そんなこと俺は考えてない。・・・
誰にやられたんですか?・・・こんな酷い。こんな惨いこと・・・」
悔しそうに歯を食いしばるエレンにリヴァイはそっとキスをして、
「心配するな。」
と言った。エレンはリヴァイの優しい顔とは裏腹の絶望的な瞳に
言葉を失った。
エレンが部屋から出た数分後、エルヴィンが部屋に入って来た。
「ノックくらいしろよ。」
リヴァイは物憂げな表情でそう言った。
「また食べないのか?少しは食べないと体に悪いぞ。
エレンに食べさせてもらわなかったのか。」
「・・・」
「公爵が調査兵団への投資を止めたいと言ってきた。しかも、王族の機嫌を
損ねるのが恐いのか、他の貴族たちも投資を中止したいと言い出したよ。
どうするんだ?月1回の接待で馬5頭を毎月投資してくれていた公爵様に
嫌われたせいで、馬1頭から3頭を毎月投資していた貴族たち7人からも
投資を辞退されたよ。俺はお前の身体の事も考えて、週に1回程度の
接待で済むように、投資額の多い者は月1回、投資額の少ない者は
数ヶ月に1回の接待というようにシフトを組んでやっていたというのに・・・
あとは商会の金持ち二人が残っているだけだ。もう、こうなったら、
その二人になんとか頼んで、投資額を増やしてもらうしかない。昔、お前が
まだ公爵と知り合う前、1回の接待で馬1頭と決めて接待していた奴らに
もう一度投資してくれと持ちかけるよりはずっと楽だと思うがな。
調査兵団には馬が必要なんだ。分かるだろ?」
「・・・」
「あと、もう一つ考えられる手は、公爵に土下座して謝る事だ。だが、
公爵はこう言っている。『どんな責苦にも屈せず、謝らなかったのは
見上げた根性だ。その強い精神力に免じて、望み通り縁を切ってやる』とな。
あの公爵はサディストで有名だが、これまで酷い事はしなかっただろう?
きっとそれは本当に惚れていたからだと思う。もちろん、あの公爵に
引き合わせたのが、お前を女王様に仕立て上げたマゾヒストで有名な子爵で、
公爵はお前の事を勘違いして、別格に扱っていたのも事実だ。だから、
あの公爵に詫びを入れるのは、この先ずっと家畜のように扱われるのを
覚悟しなければならない。俺はお前の美しい肌に傷ができるのは忍びない。
公爵のお気に入りだからと、お前を有難がって抱いていた貴族たちも
一斉に手の平を返したように酷い仕打ちをするかもしれないぞ。
何しろ貴族の大半は変態だからな。」
「・・・」
「おいっ。さっきから黙ってないで何とか言えよ。」
「チッ。・・・ベラベラとうるせぇなぁ・・・要するに、商会の豚2人と
寝ればいいんだろ?その代り、他はもう勘弁してくれ。」
「分かった。俺も今となっては、それがベストな選択だと思う。
だがな。リヴァイ。忘れるな。お前は俺が拾ってきたという事を・・・
お前が誰を好きになっても構わないが、所有権は常に俺にあるという事を
忘れるな。」
エルヴィンはリヴァイの顎に手をかけ顔をあげさせると唇にキスをした。
そして、ゆっくりとベッドに押し倒し、服を脱がせ始めた。
「やるのか?まだ傷が痛むんだが・・・」
リヴァイが物憂げな瞳でエルヴィンをじっと見た。
「薬を塗ってやろうと思っただけだ。鞭の傷は背中だから
一人じゃ塗りにくいだろ?」
エルヴィンはそう言うと、リヴァイの衣服を脱がせ、軟膏を手に取り、
縦横無尽に背中に残る赤い線に沿って指を走らせ、軟膏を塗りつけた。
「もう傷が治ってきたな。これなら、明日から通常任務に就けそうだな。
だが、心配なのは下の傷だな。塗ってやるから、全部脱いで
四つん這いになれ。」
冷ややかな笑みを浮かべてエルヴィンは言った。
いつも彼がそういう顔をする時は逆らうと後が恐い。
リヴァイは気が進まなかったが、エルヴィンの命令に従った。
「ふむ。まだ赤く腫れているが、切れていた部分は治ってきたようだな。」
エルヴィンはそう言うと、軟膏をベッタリつけた中指をリヴァイの尻に入れ、
内壁に塗りつけた。
「うっ。・・・あっ。」
グリグリと指を動かされて、リヴァイは思わず声を漏らした。
「薬を塗っているだけなのに気持ち良いのか?何にでも反応してしまうなんて
相変わらず淫乱だな。そういえば、一昨日、公爵に入れられたディルドの
大きさはどのくらいだったんだ?通常の1、5倍くらいか?こんな小さな身体で
そんなものを入れられたら、漏らしても仕方がないよな。」
「・・・言うな!」
「おっと。すまない。潔癖症のお前には辛過ぎるよな。
でも、これだけは聞かせてくれ。ディルドに粗相したのと、
首を絞められて失禁したのと、どっちが恥ずかしかったか?」
「や、やめろ!」
「フッ。どっちも恥ずかしくて、答えられないか。可哀相に・・・
俺だったら公爵に謝ってるがな。何故、謝らなかったんだ?
エレンの為か?それにしてもエレンのどこが良いんだ?ひょっとして、
人間扱いされなかったお前の少年時代と似てると思ったからか?
化け物と男娼じゃ全然似てないぞ。お前の父親は飲んだくれの博打打ちだ。
借金の返済の為に自分の子供の身体を売る無職の親の子じゃ身分も違う。
人間としてはエレン以下だ。お前は俺の所有物じゃないと
入団もできないような底辺で生きる人間だったんだぞ。」
エルヴィンは動かしていた指を止めて、こう言った。
「お前の過去をバラしたら、エレンはどうするかな。きっと
逃げ出すと思うよ。」
週末、調査兵団の宿舎に2台の馬車が来た。
商会の中でも有名な金持ち二人が資金調達の為に招待されたのだった。
エルヴィンは食堂のコックに豪華な料理を作らせ、応接室で晩餐会を開き、
ゲストルームに二人を宿泊させる計画を立てた。
無論、ゲストルームでの接待はリヴァイに任せるので、誰も近づくなと
言われていたが、飲み物などを客に運ぶ給仕係はエレンに任命された。
エレンは夕食後にワインを部屋に届けるよう言われて、ゲストルームの
ドアをノックした。
「入れ。」
と、エルヴィンの声がして、いささか不安だった性接待というものは
まだ始まっていないのかとエレンは安堵して、扉を開けると、
ホッとしたのも束の間、声を押し殺したような低い喘ぎ声が聞こえた。
リヴァイは全裸でベッドに腰掛けるような体位で後ろから男に抱かれ、
ベッドの前で跪いているもう一人の男の肩に両足をかけて、身体の中心を
口に含まれていた。思わず息を呑む光景にエレンは困惑し、
立ち尽くしていると、エルヴィンが
「早く中に入れ。ワインはそこのテーブルに置け。」
と言った。エレンは黙って指示通りにすると、いつの間にかリヴァイの
身体を舐めていたはずの商人がエレンの目の前にやってきて、
「へぇー。この子も可愛いな。」
と言って、ニヤニヤ笑いながらエレンの手を握った。
「まだ15歳です。童貞ではありませんが、処女ですので、
よろしかったら、どうぞ。」
とエルヴィンは笑顔で答え、
「エレン。お前も接待しろ。」
とエレンに命令した。エレンは驚いて、
「い、嫌です。」
と言ったが、商人は手を掴んだまま恐い顔で
「許可が出たんだ。大人しくしろ。」
と言った。
「や、やめてください。」
嫌がるエレンの唇を奪おうと商人が抱き寄せたその時、
「おいっ!その汚い手を放しやがれ!」
とリヴァイが怒鳴った。
後ろから貫かれていたリヴァイは抱いていた商会の豚を突き離して
ベッドから降りた。
「エレンに指一本触れるな!俺はどうなってもいい。だが、
そいつにだけは手を出すな!」
いきり立つリヴァイにエルヴィンは
「化け物を調教してみたいって貴族は多いのでな。おまえの代わりに使える
と思って、おまえが接待を怠けても大丈夫なように俺は考えたのだが・・・
エレンに手を出すなというのであれば、接待が嫌だなんて言わずに、
おまえが励まなければな。」
と言った。それを聞いたエレンは驚いて、
「えっ?!接待が嫌ってどういうことなんですか?リヴァイさんは
無理やり強要されてたんですか?今まで俺はリヴァイさんが
好き好んで男と寝てると思って、我慢してたのに・・・」
と言った。すると、リヴァイは失礼な誤解をされていた事に腹を立て、
「誰が好き好んで、こんな豚ども相手にするか!嫌々エルヴィンの
命令に従ってるに決まってるだろ?」
と吐き捨てるように言った。
「リヴァイさん、何故あなたは嫌だって断らないんですか?
調査兵団の為に自分を犠牲にする必要はないと思います。」
「・・・」
エレンの質問に言葉を詰まらせたリヴァイの代わりにエルヴィンが答えた。
「リヴァイは俺の所有物だ。俺の命令には絶対服従だ。俺が
寝ろと命じた相手とは寝なければならない。リヴァイはたまに
遊び相手のペットを欲しがるが、そんなものは勝手に作っても
俺はどうでもいい。しかし、俺の命令に背く勝手な真似はもう
二度としないと誓わせたんだ。」
「そんな・・・本当ですか?」
「ああ。本当だ。」
俯いたまま動かないリヴァイにエルヴィンはこう言った。
「リヴァイ。ベッドに戻って接待の続きをしろ。さもないと、
おまえの過去をエレンに話すぞ。」
「・・・」
「過去って何です?リヴァイさんは脅されてたんですか?
卑怯ですよ。エルヴィン団長。」
「卑怯とは何だ!ペットの分際で出しゃばるな!」
声を荒らげて怒ったエルヴィンにエレンも声を張り上げて言い返した。
「俺はペットじゃない。リヴァイさんの恋人だ!」
「恋人だと?何を言ってるんだ?リヴァイは俺のものだ!」
「恋人を他人に売るような奴は人間じゃない。エルヴィン団長は
リヴァイさんのことを本当に愛してるんですか?愛してるなら、
こんな酷い仕打ちはできないと思います。」
だが、エルヴィンはエレンを鼻で笑った。
「愛なんてないからな。リヴァイは俺が拾ってきた所有物だから、
抱きたい時に抱き、利用できる限り利用してただけだ。恋人なんて
代物じゃない。奴隷さ。金で買ってきたわけではないが、リヴァイは
性奴隷のようなものなんだ。」
「酷い。あんたって人は・・・見損ないましたよ。エルヴィン団長。
リヴァイさん、こんな奴の言いなりになんかなってちゃダメだ。」
依然俯いたままのリヴァイを見て、エルヴィンはこう言った。
「どうとでも言え。そうだな。リヴァイに選ばせよう。
エレンに従うか俺に従うか。だがな。エレンを選んだら、
おまえの未来はないと思え。さあ、どっちにする?」
「エルヴィンに従う。」
と、リヴァイは俯いたまま答えた。
「そうか。リヴァイは良い子だな。聞いたか。エレン。
もうお前に用はない。さっさと出て行け。」
と、エルヴィンは勝ち誇ったように言った。エレンは
「リヴァイさん!本当にいいんですか?あんたはエルヴィン団長に
従うべきじゃない。自分の心に従うべきだ!もし、脅されて、
逆らえないのだとしたら、俺がエルヴィン団長を脅してやる!
リヴァイさんに接待を強要するのはやめろ!さもなければ、
巨人化して駆逐してやる!」
と、必死に訴えた。しかし、エルヴィンはエレンの脅しを嘲笑った。
「ハハハ・・・血迷ったか。何を言ってるんだ?エレンが巨人化して人を
襲ったら、リヴァイが殺すことになっている。殺されるのは、おまえだぞ。」
すると、リヴァイは押し隠していた感情を初めて出した子供のように
「殺せない。たとえ、エレンが街中の人を襲っても・・・エルヴィンを
殺したとしても・・・俺は愛してしまったんだ。愛してしまったから、
たとえ、何が起きても、エレンを殺せない。」
と言った。
「何だと?!おまえの過去をばらすぞ!それでもいいのか?」
エルヴィンは顔色を変えて怒った。だが、リヴァイはこう言った。
「構わない。話せ。それに、法律上、俺の犯した罪は既に時効になっている。
俺は脅しに屈したわけじゃない。拾ってもらった恩があるから従っていただけだ。
エルヴィンが俺の事を愛していないのは知ってたさ。でも、俺は愛されたいと
思ってた。ずっと・・・エルヴィンの役に立つことだけを考えて生きてきた。
エレンに出会うまでは・・・でも、エレンと出会って、俺は変わった。
エレンは多分、俺の過去を知っても俺のことを嫌いにならないと思う。」
「たいした自信だな。」
「裏を返せば、エルヴィンは俺の過去が嫌いなんだろ?それとも身分が
違うから、愛するに値しないと言うのか?俺は調査兵団をやめるよ。
俺は人間で、奴隷じゃないから、職業は自分で選べるだろ?辞職する。」
「小学校も出ていないおまえに再就職先なんてあるものか!
また身体を売って暮らす気か?こうなったら、ばらしてやる!
エレン、こいつはガキの頃に父親に売られて、客と父親をナイフで刺して
逃げたんだ!逃亡先では街のゴロツキのボスの愛人におさまって、
しばらくは暮らしていたが、ボスが捕まると、仲間にまわされて、
捨てられたんだ。ゴミ捨て場に倒れているのを俺が拾ってきた。
俺が綺麗な服を着せて、字も教えて、立派な軍人になるように育てたんだ。
だから、俺のものなんだ。エレン、おまえも上官に逆らって、調査兵団に
いられると思うな。」
エルヴィンは最後の切札を出したが、エレンは屈しなかった。
「俺もやめます!俺は子供の頃、人を殺した。でも、罪にはならなかった。
正しい事をしたからだ。リヴァイさんもきっと親をナイフで刺す行為が
リヴァイさんにとっては正しかったんだと思う。俺はここを出て、
リヴァイさんと二人で暮らします。行きましょう。リヴァイさん!」
エレンはリヴァイの手を取り、部屋を出た。
エレンはリヴァイの手を引っ張って廊下を走った。
階段を駆け下り、玄関ではなく、勝手口のほうから中庭に出て、
敷地内の倉庫に身を隠した。
「追って来るかな。」
エレンは心配そうに言った。
「多分、部屋のほうに行ったと思って、まず俺の部屋を探すだろう。」
リヴァイは落ち着いた声で言った。
「エルヴィン団長、面食らったような顔をして、唖然としてましたね。」
エレンがクスッと笑った。
「笑いごとじゃない。俺は服を着てないんだ。12月に全裸で
走らされるとは思ってなかった。」
リヴァイは真顔で言った。
「あ、すみません。寒いですか?」
「当たり前だろ。」
「確か倉庫に支給される前の軍服がしまってある箱があったと思います。
今、服を出しますね。Sサイズあるかな。あった。あった。どうぞ。」
エレンはSサイズの服を手渡した。リヴァイは受け取ると、服を着ながら、
「これからどうする?エレンは以前、家に行きたいと言っていたな。
壁の外にでも行くか?」
と言った。エレンは
「え?いいんですか?じゃ、ここにある武器弾薬も持って行きましょうか?」
と言って、武器を物色し始めた。
「そうだな。そうしよう。でも、その前に・・・最後になるかもしれないから、
1回だけやっとくか。」
リヴァイは微笑んで、誘うようなキスをした。舌を入れてくるリヴァイに
エレンは戸惑いながら、
「リヴァイさん・・・服せっかく着たのに・・・また脱がせなきゃ・・・」
と言った。
「どうせ。外の世界に出たら、生きては帰れない。明日、
死ぬかもしれないんだぞ。」
リヴァイは本気だった。だが、エレンは死を恐れて話を逸らす小心者のように
「そういえば、明日はクリスマス・イブですね。巨人を駆逐しながら
クリスマスを過ごす事になりそうですね。」
と言って、笑った。
「聖なる夜に死ぬのも悪くない。」
リヴァイはもう一度エレンに接吻した。長い接吻の後、エレンは
リヴァイの服を脱がして、リヴァイの首筋を甘噛みし、喉仏の辺りを
舐め、胸の突起を摘まんだ。
「あっ。」
よろめいたリヴァイは倉庫の棚に背をもたれた。
エレンは首から胸へとゆっくりと舌を這わせて、リヴァイの胸を
舐めまわした。
「あっ。そこばっかり・・・じれったいな。早く入れろよ。」
「リヴァイさん。もう欲しいの?」
エレンは蜜を垂らしているリヴァイのものをじっと見た。
「ああ。そうだ。早くしろ。」
「じゃあ、後ろ向いてください。」
リヴァイは棚に両手をついて、エレンに後ろを向けた。
エレンがリヴァイの尻を掴んで左右に押し広げると、先ほどの接待で
仕込まれたローションが零れ出てきた。リヴァイは両足を広げて立ち、
更に尻を突き出して、受け入れやすい体勢をとったが、リヴァイの
待ち望んだものではなく、エレンは舌をリヴァイに入れた。突然
内壁を舐められたリヴァイは狼狽えて、
「あっ。やめろ。そこ・・・汚い・・・」
と言ったが、エレンは止めなかった。
「何で?俺はリヴァイさんを気持ち良くさせてあげたいんだ。」
「あ、ああ・・・エレン・・・さっきまで他の男のものが入ってたんだぞ。
汚いと思わないのか?」
「汚くなんかない。少し変なローションの味はするけど・・・
そんな事どうだっていい。・・・汚いとは思わないけど・・・もし、
リヴァイさんがそう思うなら・・・舐めてきれいにしてあげますね。
俺の舌でリヴァイさんを清めてあげる。」
エレンは舌でグルグルっと内壁を舐め回した。
「あっ、ああ・・・バ、バカ・・・もう、や、やめ・・・
あっ、イ、イク・・・ああ・・・」
リヴァイは前を触れられていないのに、後ろだけで達してしまった。
「リヴァイさん。いっぱい出ましたね。接待ではまだイってなかったんだ。」
「当たり前だろ。誰があんな豚野郎なんか・・・エレン。
もしかして、妬いてたのか?」
「そうですよ。気持ち良さそうに抱かれてるリヴァイさんを見て、
妬かないほうがどうかしてますよ。でも俺はリヴァイさんがイっても
イってなくても気にしないです。リヴァイさんは何をしてもきれいですよ。
汚くなんかない。」
エレンはそう言うと、リヴァイの右足を抱えあげ、挿入した。
「あっ。あっ。あっ。」
棚の柱を右手で掴み、背を棚に頭を棚の段ボール箱の上に乗せ、
床から自然と離れる左足のつま先を床につけようともがきながら
嬌声をあげるリヴァイに
「俺にしがみついて下さい。リヴァイさん小さいから足の長さが違うんで、
動きにくいです。」
とエレンは言った。チッ。とリヴァイにまた舌打ちされるかと
エレンは思ったが、意外と素直にリヴァイは左腕をエレンの首にまわし、
両足を腰に絡めてきた。
「あっ。深い。ああ~」
身体を繋いでる部分でリヴァイを支え、奥まで入った状態のまま
エレンは腰を激しく動かした。
「あっ。クソ。あっ。また・・・イ、イキそうだ・・・ああっ。」
棚の柱を掴んでいる右手にグッと力が入り、リヴァイは我慢している
ように見えた。
「リヴァイさん。イって良いですよ。俺もイキそう。」
「あっ。ああ~」
「リヴァイさん。好きです。」
「あっ。お、俺も・・・好きだ。エレン。あっ。ああ。ああ~」
リヴァイの身体が仰け反り、ビクビクっと身震いしたのと同時に
エレンはリヴァイの中にドクッと欲望を解き放った。
リヴァイは体内にエレンを感じながら、安心したように目を閉じた。
「リヴァイさん。寝ちゃダメですよ。」
意識が遠くなりかけたリヴァイが目を開けると、エレンの笑顔があった。
「チッ。寝てなんかいないぞ。」
リヴァイはわざと嫌そうな顔をして、エレンから身体を離した。
「今、タオルで拭いてあげますね。この倉庫は何でもあって便利だな。」
エレンはそう言うと、新品のタオルで身体の白い液体を拭い取った。
「馬が必要だな。だが、盗んだ馬を壁の外に持ち出すのは不可能に近い。
壁の外の村で調達するか。」
リヴァイが服を着た後、言った。
「俺が巨人になってリヴァイさんを肩に乗せて運んであげますよ。」
とエレンは言った。
「俺の事を喰うなよ。まあ、おまえになら喰われても本望だがな。」
リヴァイは自分で言って少し照れたように俯いた。
「嬉しい事を言ってくれますね。」
エレンはリヴァイの顔を覗き込んで、キスをした。でも、次の瞬間、
エレンは唇を離し、
「あっ、すみません。リヴァイさんは潔癖症だから、
舐めて舌が汚れた後はキスはしちゃいけないんでしたよね。」
と謝った。
「かまわないさ。」
リヴァイはエレンの両頬を手で掴んで引き寄せ、唇を重ねた。
すると、その時、倉庫の扉が開いた。
「ここにいたのか。探したぞ。」
エルヴィンだった。リヴァイはエルヴィンを見るとすぐに無言で
手榴弾を手に取り、投げつけようとした。
「お、おい。待ってくれ。話を聞け。公爵から使いが来たんだ。」
エルヴィンは慌ててリヴァイを落ち着かせようとした。
「公爵が馬を20頭プレゼントしてくれるそうだ。寄付も今まで通り
続けると言ってきた。」
「チッ。俺はもう誰とも寝ないぞ。」
「寝なくて良いんだ。もう接待は必要ないそうだ。リヴァイの勇気と信念に
心を打たれたから、今後は何の見返りもなく寄付をするとの仰せだ。
馬20頭はクリスマスプレゼントだそうだ。俺も忘れていたが、
明日はクリスマス・イブだろ?俺が悪かった。もう誰にも接待させないから
戻ってきてくれ。」
エルヴィンが頭を下げた。
「エルヴィンとも寝ない。それでもいいか?」
リヴァイが真剣な顔で聞いた。
「残念だが、仕方ない。これからは友人として、おまえと接する事にするよ。
性奴隷なんて言って本当にすまなかった。」
「反省してるなら、それでいい。戻ってやるよ。」
リヴァイはそう言って、手榴弾を棚に置いた。
「良かったです。リヴァイさん。きっと神様が味方してくれたんですよ。」
エレンは喜んで、最高のハッピーエンドなクリスマスプレゼントを
神に感謝した。
「さあ、こっちにおいで。」
エルヴィンが手を広げて、倉庫の外に出るよう促した。
人を疑う事を知らないエレンは無邪気にエルヴィンのいる
扉のほうに歩いて行った。リヴァイもエレンの後に続いて歩き、
神の祝福を受けるようにエルヴィンの目の前に立った。
「聖なる夜に乾杯!」
突然エルヴィンはそう言うと、身体をひるがえし、二人を倉庫の扉の外に
突き飛ばした。エレンとリヴァイは一瞬何が起こったのか分からなかった。
外に出た瞬間、何発もの銃声が聞こえて、自分の身体が銃弾に打ち抜かれた。
ドサッと地面に倒れた時にはエレンは死んでいた。リヴァイは手を伸ばして、
エレンを抱きしめようとしたが、エルヴィンに阻止された。
「この世界は残酷なんだ。騙されるほうが悪い。二人そろって、
あの世に旅立て。俺からのクリスマスプレゼントだ。リヴァイ。喜べよ。」
いつも冷静なエルヴィンの顔が醜く歪んで見えた。
エルヴィンの頬に涙が伝った時、リヴァイは息を引き取った。
リヴァイの身体から流れる血が冬の大地に真っ赤な花を咲かせていくのを
エルヴィンはいつまでも見つめていた。
(完)

ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 読書
- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…
- (2025-12-04 22:26:18)
-
-
-
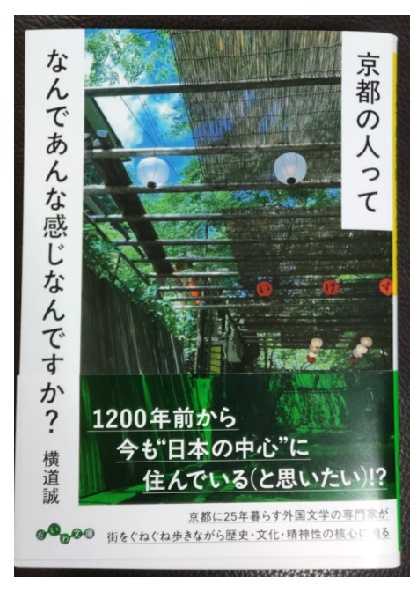
- 最近、読んだ本を教えて!
- タイトルを貫き通して欲しかった
- (2025-12-03 11:30:22)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0949 スピノザの診察室
- (2025-12-05 00:00:15)
-
© Rakuten Group, Inc.