-
1

★ なぜ「ぼく地球」以外は駄作なのか 日渡早紀 『ボクを包む月の光 「ぼく地球」次世代編 』 花とゆめCOMICS
困ったな。新作がでちまった。迷って、ほっておいたら、買うの忘れてやんの(llllll´▽`llllll)読了する。分らない部分が出てくる。そんで『ぼく地球(たま)』を読み直す羽目になってしまった。読み直して驚いた。やっぱり圧倒的に面白い。全21巻。万人がこれより面白いとみとめる少女漫画なんて、いくつあるんだろう。そんなの、無いんじゃないか、と思うくらいの至福の喜びをふたたび味わった。やっぱり、凄いッすよね。はじめ読んだときは、ショックさえうけた。「時空」をこえた2つの惑星。「前世」と「現世」。よくてSF、悪くいえばオカルトにすぎない。それなのに、「前世」における謎が、ひとつひとつ解きほぐされて、圧倒的なまでの全体像が、ミステリ-仕立てで浮かび上がる。分らない面白さに圧倒された。なんというか、切迫感がたまらなかった。ある種、社会現象まで生んだ、「ぼく地球」。オカルト誌『ムー』の読者コーナー、「ムー民広場」は、「ぼく地球」の直撃をうけて、自分の「前世」を語る人々に占拠された。この面白さを考えれば、無理もない。とはいえ歳月と読み直しは、その印象を一変させていた。「オカルト」「SF」…そんな珍奇な「道具」が、その新鮮さからくる面白さを失ったとき、「ぼく地球」に潜む、本当の面白さがうかびあがってきたようにおもえた。われわれは、否、作者自身をふくめて、みな珍奇な「道具」立てに騙されていたのではないか。僕には、ずっと、不満だったことがあった。日渡早紀は、なぜ「ぼく地球」以外、面白くないのだろう。「アクマくん」、とくに「未来のうてな」以降…みんなつまらない。「ぼく地球」だけ、奇跡的な面白さをもたらしたものは、いったい、なんだったのか。あとにも、さきにも、「ぼく地球」でしか、彼女がやっていなかったこと。読み直すまで、まったくそれに気づかなかった。「ニセモノにしがみつく」「ニセモノであることが暴かれる」そう。「ぼく地球」とは、ニセモノの物語なのだ。木蓮(ありす)の膝の上で、手に入れた地球での安寧な生活をニセモノと糾弾する、紫苑(輪)のシーンを思いおこしてほしい7名は、「ニセモノ」にしがみつく。かれらは、お互いに「ニセモノ」をみせあい、遮蔽幕をはっている。その張られたスクリーンは、ずたずたに引き裂かれてしまう。エンジュ(錦織)は、玉蘭(迅八)に「友人」というスクリーンをはる。繻子蘭(国生桜)は、エンジュに「女ともだち」というスクリーンをはる。玉蘭は、手に入れられないものをみないため、周囲に良心的な人物を演じる。キチェでなければ、愛してもらえない、強迫観念に駆られる、木蓮。そのスクリーンは、つぎつぎと紫苑・輪たちによって、食い破られてしまう。王様は裸だ。ウソは、常に暴かれる。あれほどまでに、切迫感に満ちあふれたストーリーだったのは、ニセモノであることを糾弾する物語だったからにちがいない。木蓮を陵辱したい欲望を指摘された秋海棠(春彦)。前世を美しい思い出に終わらせ、基地運営から目をそむけさせたい、柊。エンジュ(錦織)の思いを知りながら、知らないふりをする、迅八。いや、ニセモノにしがみつく究極の存在は、紫苑だろう。周囲に提示する紫苑の言葉は、つねにフェイクにすぎない。木蓮とリアン・カーシュにのみ、本音を話すことができた紫苑。なにか敵を定めないと、内からもたげてくる何かに飲みこまれてしまう。それから目をそらすため、余裕あるものを、サージャリムを、敵と定めて攻撃する紫苑。ニセモノにまどわされ、ニセモノにしがみつき、ニセモノの下にうごめく「本当の欲望」にたどりつく物語。全編が、まるで心理劇。だからこそ、「ぼく地球」は傑作だったのだ。SFやオカルトや、そういった小道具に、われわれは騙されていたのだ、たぶん。以後、この主題が日渡早紀によって演じられることはなかった。今回のこの連作短編集も然り。しかし、こうもおもう。ニセモノであることが暴かれただけで、人は「ホンモノ」にたどりつくことができるのであろうか、と。輪の身体に埋め込まれた、「輪」「紫苑」の2つの主体。「月基地を壊したい」「月基地を制御したい」と叫ぶ矛盾した主体「輪」。それを、木蓮が「輪」「紫苑」の2人の違いに裁断したとき、そこにかすかな「虚偽」が混じっていなかったか。紫苑は「制御したい」と叫ぶ。とはいえ、それは「月基地」にある、あるものを確かめたいがためのウソ。いや、「あるものを確かめる」というホンモノの欲望を通して、紫苑は他の6名とも、否、「輪」という人格とさえ、「和解」し「癒された」かにみえる。この2つの「叫び」の対立は、すでに「月基地は木蓮の歌の中に沈んでいる」ことで、揚棄されたかのようだ。しかし、その過程で捨てられたものは、あまりにも大きかったのではないか。あれほどまでに紫苑を突き動かして、われわれをも感動の渦に巻きこんだ(?)「月基地を制御したい」=「地球を守りたい」という欲望。それは最後になって、そもそもニセモノだったことが宣告されてしまう。おかしくはないか。それでは、そもそもなぜ、そんなものが必要だったのだろう。「癒され」てしまえば、そんなものは必要なくなってしまうのか。われわれは何のために読んできたのか。フィナーレ。『ぼくの地球を守って』は、愛を選びとることで、感動の物語であるフリをする。それは、「ぼく地球」全編について、決定的にウソくさい物語としたのではないだろうか。思い返そう。この究極のフェイク、「地球を守る」は、表題にまでなっているのだ。だから、それをニセモノと葬ってしまうわけにはいかない。なんか、それらしい、結末をつけねばならない。地球の大気に溶け込んで融合してしまったとされる、木蓮…サージャリムによって地球は守られるらしい。キサナド(聖書)ぬきにですか? なんですか、そりゃあ。そもそも地球に、たった1人のサージャリムで、何ができるというのでしょうか…以後の日渡早紀の作品。何作か出ているので、読ませてもらっている。とはいえ、それらに共通しているテーマとは、ウソくさくしてしまった「地球を守る」をいかにウソ臭くさせないか、という代物のような気がするのだが、どうだろうか。彼女の以後のあらゆる作品は、ウソくさくなってしまった、「ぼく地球」の敗者復活戦として存在しているのではないのか?。変なSF設定。妙な社会派作品。彼女の作品を読むたびに、感じてきた違和感は、今回の読み直しでやっと理解できたようにおもえた。イデオロギーをいかにウソくさく見せないかという究極の試み。でも、あらゆるイデオロギーとは、所詮、ウサンくさい代物ではないのか。それこそ、あたかも誰もたどり着けない処へ行って貴方の真実を見い出しなさいこと、リアン=カーシュの言葉のような。とはいえ、「1度目は悲劇として、2度目は喜劇として」という言葉もある。本編の1度目こそ、悲劇ですみ感動のフィナーレをもたらしたものの、2度目以降の、ウソくさくない「ぼく地球」の試みは、それこそ喜劇ではないのか。皆さんはどう思われるんだろう。<番外編>評価 ★★☆価格: ¥410 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 28, 2005
閲覧総数 92565
-
2

★ ガヤトリ・C・スピヴァク 『デリダ論 「グラマトロジーについて」英訳版序文』(田尻芳樹訳) 平凡社ライブラリー
ええ、読みましたよ。面白そうでしたし。悪いっすか。すみませんねえ。デリダ関連の書といえば、東浩紀『存在論的 郵便的』(新潮社 1998年)くらいしか読んでいなかった評者です。こんなものをレビューするなんて、ふざけた話ということくらい、分かっているのです。許してください。とにかく、『存在論的 郵便的』がとっても面白くって。「哲学すること」って、こんなに楽しいものなんだ、ということで、ついついこっちも読んでみたの。スピヴァクだし。おまけにデリダだし。そんで、これがスラスラ読めるんですよ。ハイデッカー『ニーチェ』(平凡社ライブラリー)のときの苦労が、ウソのように、もうスラスラと。いやあ、これも東浩紀『存在論的 郵便的』(新潮社 1998年)の偉大さ、なんですかね。これ読むと、浅田彰『構造と力』なんて、いかに皮相なだけの紹介で、ぜんぜん踏みこみがたりない本だったかということがわかります、ってこれ『デリダ論』の紹介でしたよね。すみません。ガヤトリ・チャクラボーティ・スピヴァク。1942年、カルカッタ生まれ。1961年渡米し、英文学研究。コーネル大のポール・ド・マンに師事。現在、コロンビア大教授。1976年、アメリカで刊行された彼女の処女作の和訳。そもそも、フランス現代思想がアメリカに本格的に流通するまえのお話し。だから、そのすばらしさをアメリカ人にも伝えようと、その熱気がそのまま封じ込まれ、この本自体がアメリカにおけるフランス現代思想受容の証言となっている稀有の書です。本来なら、日本でも1980年代前半までには訳さなければならなかった本、と訳者あとがきで書かれていますが、まったく同感ですよ。ちなみに、スピヴァクの英訳グラマトロジーの「本体」の方は、あまりの難解さに、散々な評判でした。ついでに、『グラマトロジー』は和訳もひどい。たまらんなあ。1970年代まで、ジャック・デリダはどんな哲学者だったのか。それがよく分かるようなつくりになっています。デリダとニーチェ。デリダとハイデッカー。デリダとフッサール。そしてデリダとフロイト。デリダを通して、これらのテクストを縦横無尽に引用して、議論していくスピヴァク。そして、デリダと構造主義。フーコーの『狂気の歴史』における、デカルトのコギトをめぐって、デリダがはなつ批判。エピステーメーの構造からきりはなして、「言語の考古学」ははたして可能なのか。ややヌルいのが、デリダとラカン。決定的違いにふれながら、あまり展開されていません。このあたり、1976年に書かれたという限界が宿しているみたい。ただ、どれもとても分かりやすい。デリダをとおして、現代思想をマッピングするスピヴァク。ただ、サルトルやバタイユ、バルトやドゥルーズはまったく出てまいりません、残念!今となっては、デリダはヌルいのかもしれませんね。う~む。あまりにもメジャーだし、底が割れてしまったというのか。フリー・ジャズ・ミュージシャン、オーネット・コールマンによばれて、詩の朗読会をやって散々な目にあったデリダ。なんでわしが来ることを聴衆に伝えなかったんだ、とコールマンに不満たらたらだったそうですが、この話、本当なんでしょうか。コールマンの方がエクリチュールを実践していたというオチつき。そこへいくと、スピヴァクには、やけどしそうな熱さの前兆が感じられます。文学と批評双方が脱構築的に開かれる必要性、自民族中心主義の脱構築、などをかたるときの、スピヴァクの生き生きとした筆致。やがて、「反対向きの自民族中心主義」をも批判し、脱中心化された中心をも批判する、スピヴァクの熱い人生出発点にあたるのでしょう。評価 ★★★★価格: ¥1,155 (税込)
Mar 16, 2005
閲覧総数 422
-
3

★ バカ右翼たちの迷走 ~ 昭和天皇の「靖国神社不参拝理由メモ」をめぐって
▼ いやー。昭和天皇の靖国神社メモ。「だから 私あれ以来参拝していない それが私の心だ」▼ 20日朝刊で『日経新聞』がスッパ抜いて以降、ネット界では、何だかバカ右翼たちが爆笑ものの右往左往ぶりを示しています。これほど笑えることが起きていたのに、今までまったく気づかんかった。これ、漫才のつもりなんでしょうかネ。▼ バカ右翼反応その1 『天皇を政治利用するな!』いやー、ホント馬鹿ちゃいますか? 保守ちゃん、ウヨちゃん。そもそも、なんで左翼やリベラルが、天皇の政治利用なんかしなけりゃならんの? 天皇制なんて、打倒するためにあるものでしょ。せいぜい、京都御所にお引取りいただくのが、もっとも天皇家への暖かい対応ではないですか。 天皇を政治利用できるのは、あなた方のお仲間。「天皇の御心」を大事に思う方、すなわち保守・右翼しかありませんぜ。 左翼・リベラルな人々は、このようにキミたちに問いかけているだけです、靖国神社に行きたいなら、個人の勝手なんだから、好きに行けばよろしい、しかしそれは、お前らの思想信条と矛盾してはいないかね?、とね。キミたちは、今後2度と「戦後民主主義・個人主義が公を堕落させた」なんて言ってはいけません。もちろん、「個人主義」「自由主義」批判も、してはいけません。「天皇の大御心」という「公」に背き、「個人主義」に基づいて参拝するんだから。▼ バカ右翼反応その2 背後には政治的思惑が隠されている!!いやー、ホント馬鹿ちゃいます? 保守ちゃん、ウヨちゃん。ミーちゃん、ハーちゃんではあるまいし、今さら何カマトトぶってるんだヨ、おまえら。政治的思惑のない記事なんて存在する訳ないだろう。新聞はそもそも、編集会議で重要とおもわれる順に記事の大きさを決めてるんだから。世間における重要かどうかのラインに、政治性なるものが存在しないはずがない。ナイーブさを装ってる分だけ、キモすぎ。止めてくれんかな、ホント。▼ バカ右翼反応その3 日経報道は、安倍晋三潰しだ!!!いやー、ホント馬鹿ちゃいますか? 保守ちゃん、ウヨちゃん。その程度で潰れんなら、そんな奴首相になる資格はねえよ。たしか彼のカルフォルニア大2年留学は、学歴詐称という話だったし(1年間は英会話学校で、1年しか行かなかったと言われてたけど、裁判どうなったんだよ? 安倍事務所はよー)、統一教会と深い関係のある政治家のようだし、パチンコ利権の鬼だし、安倍晋三なんて最初から首相の資格なんてない、といえばそうかもしれない。 まあとにかく、自意識過剰はキモイとだけ言っておきます。小沢民主党にとっては、君のようなオッチョコチョイの人間に首相になってもらった方が扱いやすいんだからネ。いい機会だから、首相になるの止めたら? まだ麻生とか谷垣の方が、なんぼかマシなんだから。▼ しっかし、アニメ・漫画オタクだからって、麻生支持する人いるらしいネー。俺の周りにもいたりする。ブルックナーとワグナーを愛聴したクラオタの小泉純一郎が首相になっても、ちっとも良いことは無かったことを忘れたのかなー。日本人って学習しませんねー。▼ バカ右翼反応その4 富田メモは、ニセモノだ!!!徳川侍従長の発言だ!!!いやー、ホント馬鹿ちゃいますか? 保守ちゃん、ウヨちゃん。ホント、今回、これが一番の大笑いでした。受けに受けた。そりゃそうだ。「天皇」に否定されたら、保守も右翼も終わり。「大御心」に背く逆賊。立つ瀬がないもんなー。分かるよ、その否定したがる気持ちは(笑)。 たとえば「依存症の独り言」。他にも色々あって実に笑える。そもそも、メモという書いた本人だけが分かればいいものに、メモ全体の記述やスタイルの「一貫性」を見つけようとして、いったい、どうするんだろう……… こいつら日記とかメモとか、書いたことないのか? 後でメモを読み直してみても、何を書きたかったのか分からないという、当たり前の経験さえしたことがないのか? 素直に読むしかないでしょ、詰まっても。 このネット騒動を見ても、日本人の知性の低下ぶりが良く分かる。 当然、徳川侍従長の発言メモだとしても、矛盾はいくらでも出てきてしまうでしょ。 たとえば、松平宮司に向かって、徳川侍従長が「親の心子知らず」というのか?なんだそれ。 そもそも、富田宮内庁長官が「私参拝しない」なんて侍従長発言メモって、いったい何の意味があるんだろう。理性のカケラもないのか保守はって、元々無いのかも知れないが (笑)▼ バカ右翼の迷走ぶりを心おきなく笑うためにも、毎日新聞の朝刊に出た特集をネット共通の資料にするため、転載させてもらいます。秦郁彦氏のこのメモの評価は、スタンダードとなるもんでしょう。ご本人から苦情がくれば削除します。では。● 合祀の手順の説明を 秦郁彦(日本大学講師)従来の推定を裏付ける第一級の歴史資料靖国神社は天皇参拝の中断覚悟で決断 日本経済新聞社が入手した故富田朝彦元宮内庁朝刊の日記とメモに、目を通す機会を得た。日記は1986年まで、メモ手帳は86年から昭和天皇が崩御される半年前の88年6月までで、両者は重複していない。 日記は害して簡潔だが、メモは天皇の発病(87年9月)以降は病状を記録する意味もあってか詳しくなり、昭和天皇も信頼する富田氏に言い残しておきたいとの気持ちもあってか、自らさまざまな話題を取り上げ、秘話的なエピソードを含めて語っている。皇室の内情に触れた部分もあり、全面公開は無理だろう。 第一級の歴史資料であることはすぐに分かったが、この時期に公開することによる波及効果の大きさを思いやった。 富田氏は天皇が亡くなられた直後の89年1月9日から数回、「亡き陛下をしのぶ」と題したエッセーを読売新聞夕刊に寄稿している。比べてみると、日記やメモを参照しつつ書かれたことは明らかだが、今回発表された靖国神社関連の話題への言及はない。 さて、論議の的になっている富田メモの靖国部分の全文についてだが、97年に故徳川義寛侍従長の「侍従長の遺言 昭和天皇との50年」(注 岩井克己 聞き書き・解説 朝日新聞社刊)が刊行されて以来、他の関連証言もあって、天皇不参拝の理由がA級戦犯の合祀にあったことは研究者の間では定説になっていた。徳川氏は松平永芳宮司とのやりとりを、「天皇の意を体して」とあからさまには書いていないものの、関係者や研究者はそのように読み取ってきた。 したがって、私は富田メモを読んでも格別の驚きはなく、「やはりそうだったか」との思いを深めると同時に「それが私の心だ」という昭和天皇発言の重みと言外に込められた哀切の情に打たれた。なぜか。 応対した徳川氏がA級合祀に疑問を呈したところ、「『そちらの勉強不足だ』みたいな感じで言われ、押し切られた」(「侍従長の遺言」)という。また、当時の靖国神社広報課長の馬場久夫氏によると、「こういう方をおまつりすると、お上(天皇)のお参りはできませんよ」(21日付毎日新聞朝刊)と宮内庁の担当者から釘を刺されたという。 つまり、当時の松平宮司は天皇の内意を知らされた時、今後の天皇参拝が不能となってもかまわないという覚悟のうえで合祀に踏み切ったことになる。それは「私は就任前から『すべて日本が悪い』という東京裁判史観を否定しないかぎり、日本の精神復興はできないと考えておりました」という松平氏独特の歴史観に発していた。 しかも、合祀を期待していなかったはずの遺族(と本人)の事前了解もとらず、神社の職員に口止めしてこっそりまつったため、半年後に共同通信がスクープ報道するまで、国民も知らされていない。松平路線を継承しているかに見える現在の靖国神社は、当然の手順を踏まなかった理由を説明する責任があると考える。▼ なんというか、真夏の漫才という雰囲気である。ぜひ、もっともっと笑わせてほしい。←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jul 28, 2006
閲覧総数 2678
-
4
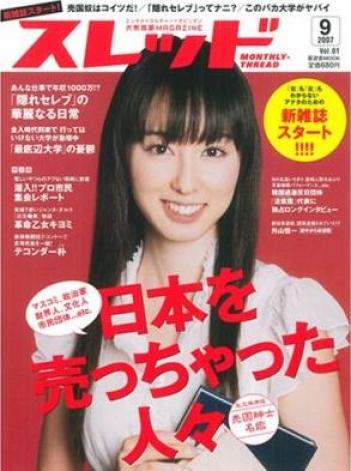
★ 維新政党新風よ、永遠なれ 『スレッド Vol.1 』 晋遊舎ムック、(最新刊)
▼ 維新政党新風が、「9条ネット」「女性党」にまで比例で大敗北した、参議院選挙翌日。 とてつもない雑誌が創刊された。 その名は、『エンタメ×カルチャー×オピニオン大衆啓蒙 MAGAZINE』なる謳い文句をかかげる、極右雑誌『スレッド』。 どうだろう。 皆さんの近くの本屋に並んでいないだろうか。 ▼ もう、表紙からすごい。 今をときめく、尻美人、モデルの秋山莉菜。 その微笑みの下の赤字の帯、「日本を売っちゃった人々」をみよ。 マジなんだか、ネタなんだか、さっぱりわからない。 もの凄くサイケである。▼ 中身はさらに凄い。 ほとんど、2ちゃんねるの「ニュー速」「極東アジア板」「ハングル板」あたりの右翼スレでみかけるような内容がならぶ。 みていて、なにもあたらしく得るようなものがない。 左翼批判が、一見、カジュアルな感じで語られるんだが、所詮、バカウヨの限界。 最後には、「特ア」「反日」のオンパレード。 なにやらデジャブーが … いけているんだか、いけていないんだか、さっぱり分からない ▼ うーん、これって、新左翼が70年安保で敗北して、サブカルチャーに戦場を移したアレの、右翼版なのだろうか? それにしても、ほとんど、2ちゃんねるの焼き直しなんすけど、これ。▼ 右翼連中は、勘違いしているのではないか。 左翼に牛耳られるマスコミ。 このままでは、プロパガンダ戦に敗北してしまう(私がそう信じているわけではない)。 こちらも、プロパガンダで対抗しなければならん。 とりあえず、あまり政治に関心をもたない若者でも分かるようなものにしなければ。 そう考えて、「大衆啓蒙」のため、こんな雑誌を作ったんだろうか。 自称保守論壇の『諸君』『正論』は、荘重で重々しくて暑苦しい。 だから、カジュアルな路線、というわけか。 秋山莉奈だしね。▼ でも、政治とはパブリックな空間で展開されるものだ。 そこでは、説得と討議が欠かせない。 大衆啓蒙のプロパガンダ雑誌である以上、討議がないのは許そう。 しかし、カジュアルな政治雑誌、しかもネタ元2ちゃんねるレベルの雑誌。 そこに、ヘラヘラと軽薄な文章で、「売国奴」「朝鮮総連」なんて語られて、どうして「説得力」を感じるだろうか? ▼ 『諸君』『正論』で断定調で重々しく書かれるのは、重々しい宣告に「説得力」が感じられるからだ。 あまり中身がないものでも、定められた様式、フォーマルとされる形式で語られれば、それなりに説得力があるように感じられる。 だから、どれも似たような口調だ。 退屈きわまりない。 ▼ 一方、ファッション雑誌は、「これが売れ筋」「これが流行」というカリスマの宣告と、その宣告を信じた人々が買うことによって生じる、「予言の自己実現」に支えられている。 日本に張り巡らされた「反日ネットワーク」に代表される右翼の妄想ほど、「予言の自己実現」からほど遠いものはないだろう。 ▼ まして内容は、2ちゃんねるレベル。 おまえら、2ちゃんねるレベルの見も知らぬ厨房から「啓蒙」されたいかよ。 見も知らぬ左翼がこんな雑誌作ったら、おまえら「啓蒙」されるか? されないだろ。 最初から戦略を間違えているとしかおもえない。 もう少し真面目にやらんかい。 そういえば、維新政党新風のせと利幸も連載していたっけ。▼ そんなこんなで、外山恒一の連載ぐらいしか楽しめるものがなかった。 このおっさん、ファシストをなのるけど、どうみてもなりすましだからな。 あと、反日漫画が、凄まじく不愉快で楽しかった。 ▼ こんなもんで長続きするとは思えないんだけど、まあ頑張れ評価: 採点不能(維新政党新風支持者にお勧めします)価格: ¥ 680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Aug 7, 2007
閲覧総数 538










