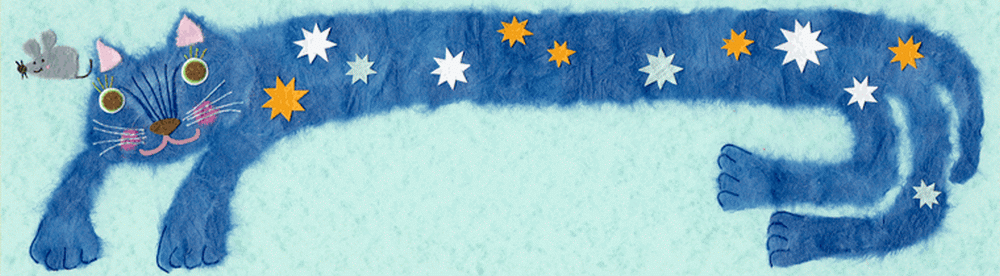自分が選んだ人の伝記…を読むなんて…人生では早々ない。特に大人になると…あまりない。なのに、世の中の大人は何で「過去の偉人」の伝記を読ませたがるんだろう⁉ …それにさぁ、伝記なんていいところしかほとんど書いていないじゃん。(…実はそうでもないものもあるけど…。いや、最近、マゼラン(彼は偉人かどうかはわからないが)の絵本を読んだときに、結構嫌な奴で最後食べられちゃったという、アタシにとっては衝撃の事実を知り、ビックリした)
とかなんとかほざいてみたけれど、「中村 哲」さんの伝記は読んでみたいな…とつい最近思い、読んでみた。
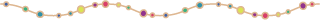
舞台の多くはアフガニスタンとパキスタンの国境周辺。昔からそこに住んでいる民族は、強国(この本ではイギリスって書かれていた)の植民地政策の関係で、その生活圏を国境が分断してしまっているらしい。国が違えば、民族や生活圏が受けられる公的サービスも違う…っていう当たり前のことが、この本には書いてあって、まったくその通りだな…って思った。(日本では、人は自分で住むところを選べるけれど、住んだ自治体によって、受けられる公的サービスは違うもんね。)
中村さんのいいな…って思うところは、「その地域の慣習や文化について、(日本人の価値として)良い悪い、優れている劣っている」という目で見ないところや、「住民が、どういうことで喜ぶのか悲しむのか、どういうことで起こるのか」を知り対応することを大切にしたこと、「住民がそのシステムを作ることに参加して、自分たちで維持できるものを目指すべき」と考えていたところ。そしてそこの地域に適応することが難しい外から来た人(日本人の支援者)に「GO HOME!」と言えるところだと思う。(無理なものは無理だし、そのコミュニティで大切にしているものを崩すリスクのある人は、その人の能力を発揮できるほかの領域で活動したほうがいいもんね)
それから、この本を読んで、ああそういうことなんだろうなぁ…と思うことは、自分の信仰がきちんとある人は、他人の信仰もきちんと認められることなんじゃないかな…っていうこと。中村さん、はっきりとは書いていないけど、クリスチャンなんじゃないかな?洗礼を受けたって書いてあるし。でも、自分のフィールドはイスラーム
を信仰している人が多いエリアだったんだと思う。それでも、慕われていたのは…多分、信仰をきちんと持っていたから(中途半端ではなかったから)相手を認められたんだと思うし、そもそものキャラクターがとても愛される人たらしだったんだと思う。
いまさぁ、「多様性! 多様性!」とかよく言うじゃん。でもさぁ、本当にそれ、できているかな? 簡単にいう人ほど、自分のうわべの良心を押し付けているんじゃないんだろうか?(公的サービス…保育園とか公立の義務教育の学校とか…選ぶことのできない集団は、お互い断れないものがあるよなぁ
きっと) でもさ、中村さんは多様性を受け入れられて受け入れてもらえる人でもあったんだと思う。これって、すごいこと。「 日本流の医療を持ち込むのではなく、いかに少ないお金で、いかに多くの人に、いかに効果的に、医療の恩恵を及ばすかー常にそのような考えのもとで活動してきた
」…という言葉は、「ぐッ」とくる。
「国連の機関(UNHCR 国連難民高等弁務官事務所)が過去に立てた計画も、意味がないわけではないけれど、現地での実際の生活の改善に即したものではない…とも感じていた」…というところが、また「ぐッ」と来た。(今の子育て施策みたいなもんだよね)
そんな中村さんの偉業は…「緑の大地計画」にかかわったこと。 職業…医師なわけで、土木のプロではなかったけれど、自分でもできる範囲で知識を得ようとしたしいろいろな人の支援を受けることができて、実行しちゃったんだもんなぁ。すごいよな。中村さんの講演会、1度行ってみたかったな…つくづくそう思う。
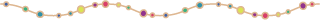
今回、この本を読むきっかけになったのは…「カブのチャレンジ章」。
#3-8技術博士(1)水がどのように各家庭に送られてくるのか…を調べる下準備で、上下水道のことを調べようと思って読んだ絵本(って言っても、内容はかなり高度だと思うよ)に中村さんの話が出てきたことなんだよね。(「 100の診療所より1本の用水路を
」っていうことを中村さんが言っていた…というのがすごい印象的だったから、そんなことをいうのはどういう人なんだろう!?って思って)
…恐るべし、「カブのチャレンジ章」。これ、やっていると、マインドマップ状で、どんどん知りたいことやりたいことが増えていく…。