ティンパニーの歴史
ネジ式のティンパニは20世紀初頭まで主流でした。しかし、この方式の楽器ですと、ネジを手で回して締めなければならず、連続して演奏している間に音程を変えるという操作はできません。そのため、19世紀までの作曲家たちは、基本的にはティンパニの音程を固定したまま使用し、音程を変えるには奏者が調律するために必要な休みを考慮して作曲しなければなりませんでした。どうしても同時にいろいろな音程が必要な時は、必要な音程の数と同じ数のティンパニを用意したのです。しかし、そのような特殊なケースを除いて、作曲家たちは、4度間隔(例えば、ハ長調ならばソ-ド)で調律された2台の楽器を使用したのです。
実は、19世紀になってから、瞬時に音程を変えられる装置をもったティンパニが数多く試みられましたが、それらはあまり使用されませんでした。そのなかで、20世紀になって注目され始めたのが、手ではなく、足ペダルの操作によって音程を変えることのできるティンパニです。ペダル・ティンパニは音程の変更が容易になっただけでなく、グリッサンド奏法なども可能にしました。それによって、オーケストラにおけるティンパニの役割は、時には独奏楽器風に使用されるなど、飛躍的に変化を遂げたのです。被膜の材質も、1950年代になってから耐久性に優れた合成樹脂が用いられるようになりました。しかし、今でもなお、昔ながらの子牛の皮を好んで使う演奏者もいます。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-
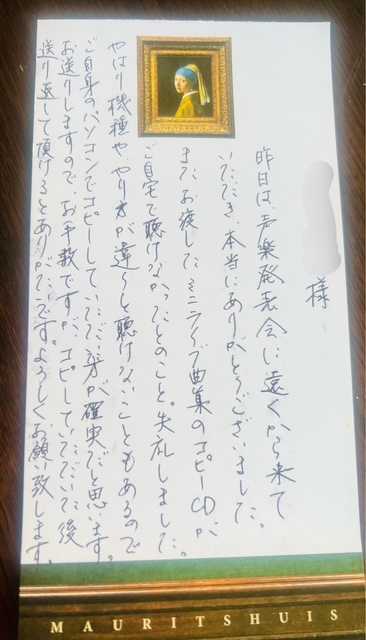
- ライブ・コンサート
- Sさんにミニライブ曲集のCDを送り自…
- (2025-11-21 00:37:43)
-
-
-

- いま嵐を語ろう♪
- 26周年💚&新作♪スエード調 巾着バ…
- (2025-11-03 00:00:11)
-
© Rakuten Group, Inc.



