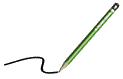ネット書店というものが登場し始めてから、これまでの街の書店はリアル書店とも呼ばれるようになったわけですが、よく考えてみると、ネット書店も現実に存在している書店であり、その意味ではどちらもリアル書店であることは確かです。 というわけで、 改めて言うまでもないことですが、 “リアル” というのは、読者が実際に本を手にして選んで購入できる、ということを意味しているのでしょう。
編集者だけでなく、企画に関わる仕事をしている人であれば、街の書店を訪れ、本棚に並べられた様々な本の背表紙を眺めながらいろいろとアイディアを練る (思索に耽る) ということをしているのではないかと思います。 私も、もちろんその一人であるわけですが、“アイディアを練る”、 “企画のヒントを得る” ということで言えば、その活用度は圧倒的にリアル書店ではないかと思います。
私の場合について言えば、 ネット書店に並べられた書籍情報を眺めていても、 新しいアイディアはなかなか湧いてきませんが、もちろん、これは人によると思うので、 「自分はリアル書店もネット書店も一緒」 という方もおられるかもしれません。
なぜネット書店を眺めていてもアイディアが湧かず、リアル書店だとアイディアが湧いてくるのか。 これは、両者の大きな違いは何か、ということを考えることが大切のように思うのですが、私が思うに (自分の勝手な解釈ですいません) 、リアル書店では、お店に入った瞬間から、自分が選択するしないに関わらず、 自分にとって未整理な (混沌とした) 情報が飛び込んでくるのに対し、ネット書店では、自分が選んだカテゴリー (例えば、大きなカテゴリーでは、人文系、ビジネス系、科学系、・・・) の情報ずつしか見ることができない、というところにあるのではないかと思います。
つまり、リアル書店では、一歩お店に入れば、 “自分にとって未整理な情報が自然に目に飛び込んでくる” のに対し、ネット書店では、“情報が自然に目に飛び込んでくるのではなく、一度振るいにかけられた (自分が選んだ) 情報を目で追いかけて見ることになる” ということが大きな違いであって、何か新しいアイディアを得ることにおいては、前者の “自分にとって未整理な情報が自然に目に飛び込んでくる” という環境 (空間) が大切なのではないかと思います。
人は混沌とした情報から組み合わせや関連付けを行なうプロセスを通してアイディアが浮かんでくるのだとすれば、 この点が、 「リアル書店だとアイディアが浮かびやすいけれど、 ネット書店だとなかなか浮かばない」 ことの理由の一つなのかなぁとも思うわけですが、新しいアイディアが浮かぶためには、日頃から様々なことに関心を持って情報を眺めることが大切なことは言うまでもありません。
関心を持って情報を眺めているからこそ、「これとあれを組み合わせるとどうなる? これって、面白くないかな?」などと考えを巡らせることができるわけで、 ただ漠然と情報を眺めていたのでは、 企画のヒントに成り得た情報さえも、目の前をただ素通りしてしまいます。
同じ情報やモノを眺めても、人によってそこから新たに掴むこと (発想) ができることが違うのは、その人の中にある引き出しの数と視点、様々な情報への関心の高さにあるのかもしれませんが、人が何か新しいアイディアを得るための場 (空間) として、リアル書店がネット書店よりも秀でているのだとすれば、逆にこの点を活かした工夫をすることで、これまでにないリアル書店のカタチを創ることができるのかもしれません。
-
新しい取り組みに向けて 2011.07.10 コメント(1)
-
紙の書籍と電子書籍の同時発売のこと 2011.06.25
-
何事もチャンスを大切に 2011.06.12