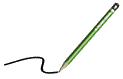全410件 (410件中 1-50件目)
-
シニア世代となって
いまなお、このブログを見にきてくださる方々がおられることに心から感謝しております。ありがとうございます。気づいてみたら、「EDITOR NAVI」の更新を終えてから、すでに10年以上も経過していて、私自身もシニア世代となりました。今後は、定年のない自身のライフログの場として、twitterを中心に、興味・関心の赴くままに時折呟いていこうかなと思います。*知らない間に楽天ブログのレイアウトが変わっていたようで、字間が妙に空いていたり、句読点が文章の先頭にくるなど、読みにくくなっている箇所が多々あることを、お詫び致します。
2022.01.04
コメント(2)
-
新しい取り組みに向けて
電子書籍への取り組みや新しいプロジェクトの立ち上げなど、紙の本の編集以外の仕事を同時並行で進めることになって、自分のブログとゆっくり向き合うことが難しくなってしまいました。 もちろん、このことは残念なのですが、新しいことに取り組むことは本当に楽しいものです。 これからのスケジュールを考えると、今後も思うように時間がとれそうもありませんが、本ブログがアーカイブ的にでも何んらかの形でお役に立てればと思い、しばらく、このまま残していこうと思っています。
2011.07.10
コメント(1)
-
紙の書籍と電子書籍の同時発売のこと
著者から頂いた原稿を紙の書籍と電子書籍の両方で出版しようとする場合には、 ・ それぞれの価格をいくらにするか ・ 著者の印税率をどうするか ・ 電子書籍を販売するプラットフォームをどこにするかなど、いろいろと考えなくてはならないことがあります。 出版社によっては、(同じ紙の書籍ですが) まずは単行本を出版し、その後、それを文庫化して出版といった展開の経験はあるにしても、1つのコンテンツから紙以外の異なるアウトプット・異なる価格・販路で出版するといった経験はほとんどなかったと思います。 もちろん、時代の流れがワンソース・マルチユースに向かっていることを感じていた編集者 (出版社) は多かったと思いますが、それが現実のものとなり、その課題に悩んでいるのではないかと思います。 上の3点について書き始めると膨大な量になりそうなので、今回は価格のことについて。でも、これが本当に悩むところです。例えば、単行本として刊行したものを、後に文庫本として刊行するといった場合も、より読者層の幅を広げることを狙った展開であり、ワンソース・マルチユースの一つと言えると思いますが、この両者には、例えば1年や2年といったように、それぞれの発売時期に開きがあるのが一般的です。 電子書籍の場合にも、紙の書籍との発売時期に開きがある場合には、ある程度思い切った価格設定に踏み切れるかもしれません。 しかし、紙の書籍と電子書籍をほぼ同時期に発売するとなると、それぞれの価格をいったいいくらにするかといったことに悩まされることになります。 電子書籍には印刷代や用紙代、流通コストなど、紙の本の出版でかかるコストがかかっていない分、価格を低く設定できるのではないかということは確かです。 ただ、そうだからといって、両者の価格差をあまり大きくし過ぎてしまうと、紙の書籍が売れずに在庫として残ってしまうことのリスクも課題となります。 もちろん、 両者の売り上げの合計 > 両者のコストの合計 となってくれればよいのですが、 このコストというのが問題です。 紙の書籍の場合には電子書籍とは異なり、売れない場合には社内 (あるいは借りている社外) の倉庫に在庫として残ることになるので、在庫として抱えている限り、それがいつまでもコストを生み出す (膨らませる) 要因になってきます。 つまり、紙の書籍が売れなくても、その分、電子書籍が売れてくれればよいと単純に考えるわけにはいかないところが悩ましいところです。 また、紙の書籍が早く完売できるように最初から印刷部数を抑えれば単価が上がってしまいますし、刊行したばかりの本を品切れにすることはできませんから、やはり印刷をして在庫を持つことが必要となります。 その印刷部数は、紙の書籍と電子書籍の両方の売り上げ動向を見ながら検討する、ということになるのでしょう。 それならば、最初から紙の書籍は作らずに電子書籍だけで発売すればいいのでは?と考えたいところですが、現在の国内の電子書籍市場、読者の読書形態の状況では、電子書籍にすることでその魅力が存分に発揮できるという内容のものでない限り、すべてを電子書籍でというのは現実には難しいのではないかと思います。 ということで、紙の書籍と電子書籍の同時発売を考えるときには、価格や印刷部数を決めるために考慮しなくてはならない要素も多くなり、未経験の出版社を悩ませることになります。 ある程度経験を積むことで、経験則から判断するということになるのかもしれませんが、それがうまくいくかどうかは、いまはまだわかりません。
2011.06.25
コメント(0)
-
何事もチャンスを大切に
大きな出版社では毎年のように新入社員を募集するかと思いますが、 (これまで何度か書いてきたように) 出版社というのはほとんどが中小企業であり、欠員が出ると募集するというのが一般的です。 また、その欠員による募集というのも、必ずしも編集職とは限らないのと、(即戦力となることを期待して) 経験者を募集という場合も多く、そういったことも、出版業界を狭き門と言われる状態にしている一つの要因かもしれません。 今年もそろそろ (私が勤める出版社では) 入社面接の時期となりました。 面接にのぞむ学生さんたちはきっと緊張するでしょうが、面接する側も緊張するものです。 (緊張して硬くなっているからといって、面接でマイナスの印象になることはありません。 大切なのは、そうした中でも、どのくらい自分というものを出せるかだと思います。) 私などは普段は人事を担当しているわけではなく、編集者として仕事をしている身。 そんなこともあって、限られた面接時間を、面接される側・面接する側の双方にとって価値あるものとすべく、いつも頭を悩ませてしまいます。 これはどんな職業でも同じだと思いますが、 短い時間内で、 その人がその仕事に向いているかどうかを判断するのはできないことですし、本人自身も、そこは未知の部分が大きいと思います。 そのため、何度か面接を重ねたり、本採用までのある一定期間を仮採用という形にしたり、あるいは、インターンシップ制度を導入している企業も増えてきているようです。 もちろん、ある短い期間だけ仕事 (の一部分) を体験しただけで、自分がその仕事に合っているかどうかまで見極めることは現実には難しいでしょう。 また、最初から自分に合った (と感じられる) 仕事に出会える人はごく一部であって、その仕事にやりがいを見出し、楽しいものとできるかどうかは自分次第、という見方もあると思います。 ただそれでも、自分が憧れている仕事を体験することができるというのはとても貴重な機会だと思いますし、 職場の雰囲気を感じることができたり、 社会人の先輩方にいろいろと話を聞くことができるという点で、本を読んだり机で勉強するだけでは得られないメリットがインターンシップ制度にはあると思います。 現在、インターンシップ制度を導入している出版社がどのくらいあるのかはわからないのですが (残念ながら、自分が勤めている出版社では導入していません) 、自分が就職を希望している ・ 関心を持っている会社や業種がこうした制度を導入しているのであれば、活用してみるのもよいのではないかと思います。
2011.06.12
コメント(0)
-
復刊書のこと
今日は、録りためたTV番組やDVDの映画を見たりして、久しぶりにのんびりとした一日を過ごすことができました。 ここのところ、復刊書の刊行に向けての手続き、連日の責了作業で根を詰める日が続いてバテ気味だったので、やっとエネルギーの充電ができてよかったです。 復刊書というのは、すでに多くの方がご存じのように、昔に発売された本で、発売当時はそれなりの話題や売上げ部数を誇っていたものの、次第に部数が伸び悩んで重版 (増し刷り) が難しくなり、その後、品切れに至ってしまった本を、装丁を変えたり (場合によっては、組み直しもして) 新たに刊行した書、というものです。 一度に何千、何万部と刷るのではなく、1冊単位で印刷・製本ができるオンデマンド印刷・製本が可能となってから、従来の印刷・製本では採算が難しくて出版を断念していた本を復刊する出版社が増えてきました。どの本を復刊するかということについては、読者の方々から寄せられる復刊のリクエストや営業部が過去の販売動向に基づいて選び出す、というのが一般的なのではないかと思います。 復刊する本が決まると、まず最初に、その本の著者 (相当に古い本もあるので、すでに著者の方が亡くなられている場合も多く、そのときには著作権の継承者) に復刊に関する許可願い書をお送りします。 著者がお一人の場合には復刊の可否のご返事も比較的スムーズに得ることができるのですが、著者が複数名の本になると許可願い書をお送りする先も多くなり、また、お一人でも同意頂けない場合には復刊を断念せざるをえないこともあって、復刊にはハードルもあります。私自身の経験では、 著者の方々が復刊に同意できない理由として一番多く挙げて下さるものは、 いまと比べると内容 (記述) が古くなっているために、読者の方々に誤解を与えかねない、というものです。 「若いときに読んだ、あの本をもう一度」 という思いを持つご年配の方、「当時の本を見たことはないけれど、うわさを聞いて」 など、リクエストを下さる読者の方々は内容的な古さは問わないことがほとんどなのですが、その本に対する著者の思いもあり、難しいところです。 今後は、復刊もオンデマンドから電子書籍へという方向に次第にシフトしてくると思いますが、最初から電子書籍で刊行した場合には品切れになるということもなくなるでしょうから、未来には復刊書という言い方も消えてしまうのかもしれません。
2011.05.29
コメント(0)
-
Sigil な日々
Google が提供しているフリーの電子書籍製作ソフト Sigil 。 英語表記なので最初は戸惑ったのですが、ボタン操作や機能がシンプルなので、いろいろと触っているうちに、(まだ使い始めてから1ヶ月も経っていないのですが) 少しずつ慣れてきました。 実は、Sigil をダウンロードするまではよかったのですが、肝心の、電子書籍化する原稿 (素材) をどうしたらよいだろうかと、結構悩んでしまいました。 Sigil は text はもちろんですが、 html 形式も読み込めるので、単に自分のパソコンで試作品を作るだけなら、ネット上に山ほど素材があるのですが、折角取り組むなら、やっぱり自分が書いたものにしようと思い直し、今は院生のときに書いた修士論文を電子書籍化してみることに取り組んでいます。 本文は言うまでもなく、 (一部の図を除いては) 図や表も著作権は私にあるので、どう調理してもいいやと、電子書籍化の良い実験素材となっています。 それなりにボリュームもあるので、論文の電子書籍が完成する頃には、Sigil の操作も習得できるかなぁと思っています。 毎回作業を終えるときに、(とても他人には見せられない) 自分の顔写真をカバーデザインにした作りかけの電子書籍を Adobe Digital Editions を使ってライブラリに入れてブックシェルフに並べ、それを開いて仕上り具合いをチェックしています。 これもちょっとした楽しみの一つです。 何でもそうだと思いますが、周囲から強制されて仕方なくといった感じで取り組むとモチベーションも維持できにくいものですが、帰宅してから自分のペースでコツコツと取り組んでいるので、とても楽しいです。 少し慣れと知識が必要ですが、 Sigil はフリーで使えるソフトなので、 自分で電子書籍を作ることにトライしてみたい方はお試し下さい。
2011.05.17
コメント(0)
-
久しぶりのパソコンショップ巡りで
愛用のノートパソコンがついに壊れてしまって、 久しぶりにパソコンショップ巡りをしました。 自分が求める機能は予め決まっていたので、あとはデザイン、価格、サービスなどで決めればよいかと思っていたのですが、陳列された膨大な商品と、そこに示されたわずかな商品情報を前に、いったいどれを購入するのがベストなのか、悩んでしまいました。 皆さんも、何かを購入するとき、泊まるホテルを決めるとき、食事場所や飲む場所を決めるときに、ネットでユーザーの声を参考にすることが多いと思います。 もちろん当然のことながら、人によって好みが分かれたり、感じ方も違うので、そうした声をすべて鵜呑みにするのは問題かもしれませんが、 (その点を踏まえた上で) 私も必ずと言っていいほど、そうした声を参考にしています。 今回も、事前にネットでユーザーの声を見てからお店を回ったので、最初はピンポイントで目的の商品を見つけることができたのですが、周りに並べられた同じような商品を眺めているうちに、こっちの方がいいかなとか、これとあれはいったい何がどう違うの?使い勝手はどうなの? といったことで悩み始めてしまいました。 商品を眺めているうちに思ったことは、リアルショップでも各商品のユーザーの声がすぐに見られるような仕組みが導入されていたらいいのに、 ということでした。 確かに、 あまり良くない意見が多い場合には、 その商品が売れなくなってしまうということになるかもしれませんが、 それはネットショップでも同じことだと思うので、あとはどういう仕掛け (システム) にするのかという点が課題となるのかもしれません。 書店では、書店員の方の手書きのポップや出版社の方で作成したポップが、本の魅力を伝えるためのツールとして活用されています。 出版社側で作成したポップは 「売りたい、売りたい」 の気持ちが前面に出てしまいがちなのか、実際にその本を読んで下さった書店員さんの作る手書きのポップの方が、読者の方々の心に響くものがあるようです。 そうしたポップに加えて、書店でもユーザーの声ならぬ読者の声が見られるような仕掛けがあると、また書店の魅力が広がるのかもしれません。ここに挙げることがすべて、というわけではないと思いますが、 リアルショップ 利点:実際に商品に触れることができる、お店の人と対面でコミュニケーションができる 欠点:ユーザーの声がわからない、商品の比較や検索がしにくい ネットショップ 利点:ユーザーの声を知ることができる、商品の比較や検索がしやすい 欠点:実際に商品に触れることができない、お店の人と対面でコミュニケーションができないのように、リアルショップとネットショップでは互いに利点と欠点が入れ替わっていることなどを考えると、ネットショップに押され気味のリアルショップでも、アイデア次第でまだまだ面白い仕掛けができそうな感じもします。 話がだいぶ脱線してしまったのですが、 久しぶりのパソコンショップ巡りで、 リアルショップとネットショップの両者で発信されている情報量の違いを改めて感じました。 でも今回は、良い点だけでなく、欠点まで丁寧に説明をして下さった店員さんに納得して、リアルショップでの購入となりました。 人と人とのコミュニケーションを大切にする。 やっぱり、これがリアルショップの良さですね。
2011.05.11
コメント(0)
-
書籍編集者のデジタル・デバイド
デジタル・デバイド(情報格差)という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。 この言葉は狭い意味と広い意味を含んでいますので、ここでは、これからの書籍編集者のスキルという点から見たデジタル・デバイドを考えてみたいと思います。 いまは (さすがに) パソコンやインターネットが使えない編集者はいないと思うので、おそらく書籍編集者のデジタル・デバイドは、これまで紙の書籍の編集作業を、 1. アナログ的に行なってきた編集者 2. InDesignなどを使ったDTP (デスクトップ・パブリッシング) で自ら行なってきた編集者との間で起こってくるのではないかと思っています。 1での “アナログ的” というのは、 著者から原稿をWordなどのデータで頂いた後に、それを紙の原稿として出力して割付 (用字・用語の統一、文字の級数・フォントの指定、レイアウトの指定などを赤ペンで入れる作業) をして、割付原稿と原稿データを印刷所に入稿し、 組版は印刷所のオペレーターに任せている、という場合を指しています。私も、まさにこれに当てはまる編集者の一人です。一方、2については、雑誌の編集者はこれに該当する方が多いと思いますし、書籍の編集者でも、印刷所に入稿せずにDTPで編集作業をしている方も多いと思います。 今後、 電子出版が広まってくるであろうということを考えると、 編集者が電子出版のプロセスや、これに関わる周辺の技術、販売手法を理解することが求められます。 そうしたことを考えると、 これまで紙の書籍の編集作業をDTPで行なってきた編集者と、 デジタルデータの操作に深く関わってこなかった (例えば私のような) 編集者との間には、大きなデジタル・デバイドが生じる可能性があります。 実は、こうした背景が (自分としては、このことに危機感を持っていて) 、大学院で深く学んでみたいと考えた理由の一つとしてもありました。 電子出版のことを直接学んだわけではありませんが、2年間の学びを通して、少しはデジタル・デバイドが減ったかなぁ、と思っています。 まだ、電子書籍元年と言われてから2年目に過ぎません。 私のようにこれまでアナログ的な編集作業にどっぷりと浸かってきた編集者でも、 今からしっかりと勉強していけば、 全く問題はないと思います。 私も日々あれこれ (いまは、EPUB と Sigil について) 勉強しております。
2011.05.03
コメント(0)
-
素敵なライブでした
先日の土曜日、BS JAPANで 「坂本龍一 LIVE in EUROPE」 という番組を見ました。 坂本龍一さんと言えば、YMO (イエロー・マジック・オーケストラ) を思い浮かべる方も多いと思います。 私も中学生のときに初めてYMOの音楽を聞いたときには、コンピューターとシンセサイザーを駆使したその斬新な音楽 (テクノポップ) に衝撃を受けたことを今でも覚えています。 楽譜が読めないのにYAMAHAのCS15というシンセサイザーを購入して、 友達とYMOのマネごとなどもしたり ・・・。 当時、 「ライディーン」 や 「テクノポリス」 を始め、次々とヒット曲を生み出していったYMOの名は一気に有名になって、ファンも急増していたように思います。 私もLPレコードが発売される度に購入していましたが、 「BGM」、 そして、それに続く 「テクノデリック」 という (良い意味でデビュー当時からのファンの期待の裏を行くような実験的な) アルバムを出すことで、YMOの音楽のコアのファンが残っていったようにも思います。 坂本龍一さん (ファンは皆、教授と呼びます) やYMOのファンの方は多いと思いますし、 その後の活躍は私が改めて紹介するまでもないと思います。 今回のライブでは、坂本さんが演奏する生ピアノと、 (それに対面するように置かれた) 予め坂本さんの演奏データがプログラミングされたコンピューター制御の自動演奏ピアノの合計2台、 そしてバックには、美しくも、ある種のテンポを持って映しだされる映像、という3つの仕掛け。 見た目にはとてもシンプルなライブではありましたが、自動演奏のピアノと一緒に奏でられる音楽と、バックに映しだされる映像とのコラボを見て、坂本龍一さんは常に新しいことに挑んでいるなぁと感じました。 久しぶりに坂本龍一さんのライブを見て、その素晴らしい音楽に浸ると同時に、 「自分は編集者として常に新しいことに挑んでいるか?」 と、考えさせられるきっかけにもなりました。
2011.04.25
コメント(0)
-
情報に振り回されないように
今は、就職・求人の情報もネットでの提供・収集がメインになっていると思いますが、私が大学生だった頃は、(確か大学3年生の頃だったと記憶していますが) それぞれが電話帳ぐらいの厚さをした業界別の就職情報誌・求人誌がセットになって自宅に何箱も送られてきたりして、学生たちは皆、それらとニラメッコしながら企業を検討していくような感じでした。 もちろん、就職セミナーなどは当時もありましたが、紙媒体での情報収集が中心であったように思います。 ネットによって当時と比べて格段に情報過多になった現代では、情報の取捨選択と判断が上手にできないと、膨大な量の情報に振り回されてしまうように思います。 そういう意味では、情報への接し方がきちんとできるかどうかも、編集のセンスが問われるところと言えるのかもしれません。 自分の欲しい情報を効率良く探すことができる、登録しただけで手元に自動的に送られてくる、というのはとても便利なことだと思います。 でも、あることを調べるのに、わずかな情報や浅い情報だけで簡単に判断してしまったり、あるいは (現時点で) 自分が関心を寄せている情報だけを集めるようにしてしまうと、偏った見方しかできなくなって視野が狭くなるだけでなく、新しい発見や出会いの機会を自らの手で奪ってしまうことにもなると思います。 就職活動での情報収集がそれに当てはまるかどうかはわからないのですが、自分の実感では、簡単に楽して得られた情報よりも、時間をかけて苦労して集めた情報の方が、 (その後も役立つ) ずっと深い内容を持っていることが多い、ということが言えるように思います。 就職は人生の大きな岐路でもあるので、就職活動中の学生さんたちには、広い視野を持って情報と上手に付き合いながら頑張って欲しいと思っています。 (編集者を目指している方であれば、 日頃から様々なことに関心を持ってアンテナを張り、 情報への感度を高めておくことも大切です。)
2011.04.18
コメント(0)
-
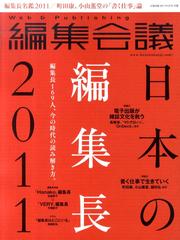
「編集会議」 が発売されました
すでにご存知の方も多いと思いますが、 先月の28日に、 「編集会議」 の2011年春号が発売されました。 残念ながら、地元の書店さんには置いてなかったので (そんなこともあって、発売されていたことに気がつかなかったのですが)、 早速、楽天ブックスで注文した次第です。 いまはBlogやTwitterなどを使って個人が手軽に情報発信をすることができるようになったので(私も含めて) 現役の編集者の方々も参加するようになりました。そういうこともあって、比較的新しい情報や、まさにリアルタイムの情報を得るには、こうしたメディアはとても優れているように思います。 その一方で、書籍や雑誌は、あるテーマや切り口で情報が編集され、手元に置いていつでも読めるように実体のあるカタチに情報がパッケージ化されているという点で、BlogやTwitterとは一味違った良さがあります。 そんなこともあって、「編集会議」 は編集者を目指している人や現役の編集者を対象とした情報をパッケージ化しているとても貴重な存在とも言えるので、これからも頑張って刊行を続けてほしいと個人的には思っています。
2011.04.11
コメント(0)
-
入社おめでとうございます
この4月から出版業界に入った皆さん、そして、新人編集者となった皆さん、入社おめでとうございます。 皆さんにとって、いろいろな意味で決して忘れることができない年となるのではないかと思います。 出版不況が続く中、電子書籍元年と言われた昨年は、各メーカーから様々な電子書籍端末が発売され、まだごく一部の出版社に過ぎませんが、それに対応する電子書籍も発売されるようになりました。 ただ現状は、いま着々と準備を進めている所、まだ様子見をしている所、あくまでも紙の本の出版に拘っていこうする所など、各社各様の姿勢を見せているような状況にあります。 また、 電子書籍はICTを駆使した一つのカタチですが、 いまはまだ、 C (Communication) の要素があまり活用されていないように思います。以前にも記したように、今後は 「つながり感のある読書」 という新しい読書のスタイルも広がってくると思います。 同じように、というわけではありませんが、 新社会人となった皆さんも、 高い Communication 能力を養うとともに、様々な人たちとの 「つながり」 を広げて (深めて) いけるように努めて欲しいと思います。 そして、この度の東日本大震災によって、出版業界にも多大な影響が出始めています。 印刷用紙やインキの安定確保が非常に難しくなっていること。 本と読者との出会いの場である書店が被災し、未だ復旧の見通しが立たないところもあること。 輸送手段の確保の問題や道路の寸断などにより、発売日に合わせて予定通りに配本することが難しい状況にあること。 などなど ・・・ 今年入社された皆さんには、いま出版業界が置かれている状況をしっかりと理解してもらいながら、 出版というメディアを通して自分は何をしたいのか、 自分には何ができるのか、 といったことをぜひ考えてみて欲しいと思います。
2011.04.04
コメント(0)
-
情報を正確かつ適切に編集して発信する
東日本大震災から2週間が過ぎ、日々、多くのテレビ・ラジオ番組、新聞、Webサイトにおいて、震災に関する様々なニュース (情報) が発信されています。 そして、情報が錯綜している中で少しでも速く多くの人たちに伝えたいということから、現状では、どこも同じような内容の情報を発信しているように感じます。 でも、事態が長期化することを考えると、いま、どこで何が必要とされているのか、そして、将来の復興に向けてどのように進めていくべきかということを、(情報の発信側・受け手側の双方が) それぞれのレベルできちんと理解し、行動していくためにも、速報的なニュースの一方で、読者 (ターゲット)を絞り込み、「これは、こういう人たちに向けた情報です」 という “尖った情報発信” をすることも求められてくるのではないかと思います。 それは、例えば (下に挙げる例は、さらに細かく分けることができると思います) ・食に関わること ・医療や介護に関わること ・物流に関わること ・住宅、店舗建設に関わること ・教育に関わること ・行政に関わること ・漁業に関わること ・農業に関わること ・・・のように被災地で得た情報を編集し、それぞれの分野の知識・経験を持っている情報の受け手側とのマッチングがすぐにできるようにしてから発信する、といったようなことです。 もちろん、 一つの情報が分野横断的な場合もあるでしょうが、 現状は、 次々と発信されている膨大な情報の中から自分に協力できそうな(あるいは必要な)ことを情報の受け手側が取捨選択しなくてはならない状態になっているように思います。 でも、「情報の編集」 という一手間を加えることで、 発信された情報が有効に活用されるようになるのではないかと思います。 (もちろん、 この一手間に多くの時間がかかってしまってはいけません。) 本づくりにおいても、読者のことを常に考えながら編集作業をしていくことが求められます。 著者と編集者だけが良い内容、正しいことだと思っていても、読者 (読み手) のことを考えずにつくると、決してうまくいきません。 また、 「多くの人を対象にしようとしてターゲットを絞り込まないと、中途半端なものになってしまい、 結局は誰にも伝わらないことになる」 というのは、 よく言われることです。 情報の発信と本づくりがすべて同じだとは思いませんが、読み手のことを考えて、情報をどのように編集して発信するかということが、長期化するであろう事態に一つ一つ対処していくためにとても大切になってくるのではないかと思います。
2011.03.27
コメント(0)
-
あの日から、1週間
あの日から、1週間が経ちました。 刻々と明らかになっていく被害の大きさ、 亡くなられた方々の数、 被災された方々の状況に、 言葉がありません。 すでにご覧になった方も多いと思いますが、 ・ 新文化 ・ 「東北地方太平洋沖地震」 発生以降の書店の状況 の各サイトにおいて、東北地区の書店の被害状況や頑張っている姿を知ることができます。 こうした貴重な情報をまとめて頂いたことに、とても感謝しています。 とっても小さなことでも、 それが積み重なれば、 大きな力になる。 それを信じて、私は今の自分にできることをしていきたいと思います。 追伸 現在、 輸送手段や運送・配送に不可欠なトラックの燃料確保が難しい状況にあり、 印刷会社への洋紙の搬入、印刷会社から製本会社への搬入、取次から書店への配本などに影響が出ています。 そのため、 本や雑誌が予定通りに入荷・発売とならず、 読者の皆さん、書店の方々に大変ご迷惑をお掛けしておりますことを、 出版社の一社員として、 そして、 一編集者としてお詫び申し上げます。
2011.03.18
コメント(0)
-
私自身に対しての記録
私自身に対して記録を残す意もあって、ここに記します。 2011年3月11日の14時46分頃、三陸沖で超巨大地震が発生し、東日本全域にわたって被災。 今日現在、大きな余震が続いています。 地震発生当時は、会社のデスクで校正作業をしていましたが、あまりに大きな揺れであったため、揺れが静まったと同時に、社員全員で近くの広場に避難しました。少し落ち着いてから会社に戻ると、デスクの上はめちゃくちゃで、原稿や校正中のゲラも飛び散っていました。 また、窓ガラスが割れたり、ビルの壁にも一部ひびが入っているような状況でした。 固定電話・携帯電話とも繋がりにくく、カミさんや両親、大学・大学院時代の友人ともしばらく連絡がとれなかったのですが、インターネットの方は比較的安定していたこともあって、mail や twitter、skype を使っての安否確認の方がうまく行きました。 その日は社員のほとんどが会社で一晩を過ごし、翌12日(土)の午前中に、駅間を歩いたり電車を乗り継ぎながら、自宅に戻りました。 幸い、自宅は棚の荷物が乱れたぐらいで特に大きな損傷もなくホッとしました。 水は以前からペットボトルを備蓄していましたが、食料は震災後に買い溜めをしました (これは反省すべき点でした)。 この度の地震で甚大な被害を受けた東北地方にお住まいの著者の方々の安否確認がまだとれていないので、週明けも継続することになると思います。 付記 Google Crisis Response の Person Finder で、著者の安否確認ができました。
2011.03.13
コメント(0)
-
カバーデザインの価値は何処へ・・・
最近、執筆依頼や著者との打合せの場面で、 「この本は電子書籍としても出すのでしょうか?」 といった質問をよく頂くようになり、 読者だけでなく、 書き手の側も電子書籍に対してとても関心を持っていることを実感しています。 従来の紙の本と電子書籍では、買い方・読み方・蔵書の管理が大きく異なっていることは、すでに多くの方が理解していることですが、 そうした中で、 いま自分が気になっていることは、 カバーデザインについてのことです。 もちろん、 紙の本を出版した後で電子書籍化するといった場合や、 紙の本と電子書籍の両方を発売するといった場合であれば、いずれにしても紙の本のカバーデザインを考えなくてはならないわけで、その意味では、カバーデザインに対する考え方も従来通りでよいのかもしれません。でも、 「紙の本は作らずに電子書籍として出版」という場合には、カバーデザインについても、また違った考え方が求められるのではないかと思っています。 それと、手で持ってリアルに感じることができない電子書籍のカバーデザインは、紙の本のように静的なものだけではなく、 動的な要素を取り入れたりなど、 電子書籍が存在している仮想空間 (ネット空間) の特性を活かしたデザインが求められてくるのではないかとも思っています。 ただ、その一方で、読者の方々が電子書籍を購入する際にカバーデザインをどれだけ重視するか、という点も気になるところです。 単純に比較することはできないのかもしれませんが、音楽分野では、 ジャケットも楽しめたLPレコード ⇒ 小さなジャケットのCD ⇒ ジャケットへのこだわりよりも、好きな音楽を1曲単位でダウンロードして購入する時代へという大きな変化がありました。 電子書籍も、 読者のカバーデザインへの関心は薄まり、 読みたい章単位でダウンロードする (そういうスタイルでの販売を狙った電子書籍が登場する) ようになっていくのでしょうか・・・。 カバーデザインの大切さについては以前に記したことがありますが、読者の方々は電子書籍を購入する際にも、これまでのようにデザインをその購入の一つの動機として、あるいは本を楽しむ一つの要素として見て頂けるのか。 それとも、あまり重視はしなくなってしまうのか。 そこのところは、これから少しずつわかってくるのだろうと思っています。
2011.03.06
コメント(0)
-
第三者が客観的に読むことの大切さ
本の編集は雑誌の編集とは異なり、基本的には、企画を立てた担当編集者と著者との二人三脚で原稿の執筆から刊行まで進めていきます。 もちろん出版社によっては、 担当編集者以外に、 校正や校閲といった形で他の人が編集のプロセスに関わるような体制になっているところもあると思います。 私が勤める出版社では、 最後まで担当編集者が編集作業を進めていきますが、 担当者が三校のチェックを終えて印刷所に責了で渡す直前の段階で、上司が担当編集者のゲラ(校正刷のこと)を “一読者として客観的に読む” ということをしています。全く同じではないにしても、 担当編集者以外の第三者が一度目を通す作業は、他の出版社でも行なっているのではないかと思います。 この、第三者が読むということは、本作りにおいて、とても大切な役割をしています。 というのは、原稿やゲラには著者と担当編集者の2人で何度も慎重に目を通しているとはいえ、 やはり人は完璧ではないですから、何等からのミスや見落としをするからです。 これはどうしようもないことなのですが、何度も同じものを読んでいると、頭の中には正しいと見える文章が擦り込まれてしまい、ゲラには確かに誤植や文章的に変な箇所があっても、全く気がつかないことがあるからです。このエラーを見つけ出すために、第三者の目がとても大切なのです。 実際、 他の人が目を通すことで、 「どうしてこんな誤植に気がつかなかったのだろう」 と、著者と担当編集者が驚くようなミスが結構見つかります。 そのため、このプロセスは、たとえ経験を積んだ編集者であっても、編集者同士で互いにゲラを交換し合って読むようにして行なっています。 (経験を積んだ編集者ほど、このプロセスの大切さがわかっているからです。) しかし、 編集者になって数年が経って上司や先輩からの細かい指導もなくなり、 漸く独り立ちをしたばかりの頃というのは、最初から最後まで著者と2人だけで進めていき、「この本は他の人の力を借りずに自分の力で最後までやり遂げたい」 という思いが強く、他の人のチェックが入ることにとても抵抗があるものです。 いまは部下や後輩のゲラをチェックする立場ではありますが、私も独り立ちをした頃はそういう思いを持っていたので、その気持ちはよくわかります。 確かに、第三者のチェックは、担当編集者には 「なぜチェックするの?」 という気持ちを起こさせるものとなるのですが、 でも、特に独り立ちしたばかりの編集者には、 このプロセスの大切さ、 重要性をわかってもらいたいと思います。 なんだか、自分の部下や後輩へのメッセージのようになってしまいました・・・。
2011.02.26
コメント(0)
-
出張の友は本でした
月曜日から昨日まで、普段はなかなかお会いすることのできない遠方にお住まいの著者の方々への原稿催促と、日頃お世話になっている著者の方々へのご挨拶で、出張に行っていました。 いつものように新幹線と在来線を使っての移動ということで、 この移動の時間を有効に使おうと、 自宅に溜め込んでいた本の中から5冊ほど選んで、出張の友としていました。 今年の目標の一つに、「日々溜まり続けている (買い溜めしている) 本を少しでも多く読み終えること」 というのを立てたこともあって、その目標を達成すべく、普段は3日で1冊を読み終えるくらいのペースで読書をしています。仕事場では原稿や校正刷りを読み、行きと帰りの電車の中では本を読む日々では、どう考えても目には良くなさそうですが・・・。 最初の1冊を読み始める前に、自分はいったいどんな本を買い溜めしていたのかをチェックしようと、 本の山を崩さないように1冊1冊手に取っていたところ、 同じ本を2冊買っているものが3組もあったり。 まぁ、単行本とその文庫本 (単行本が文庫化されたもの) を買ってしまうことは仕方がないにしても、完全に同じ本を3組も買っていたことがわかって、ちょっとショックでした。 今ではあまり見かけなくなった街のレンタルビデオ屋さんでは、過去に見たビデオと同じビデオを再度借りようとすると、カウンターの方に 「以前にも借りているようですが、よろしいですか?」 と聞かれ、そのビデオを元の棚に戻して別のビデオを借りたりしたことがありました (何のビデオかは言えませんが、時には、 「いいんです!」 と言いながら、再度借りたこともありましたが・・・)。 ネット書店でも、自分の購入履歴をチェックすれば同じ本を買っていないかどうかがわかりますが買い物カゴに入れた瞬間に、「この本は以前に購入しておりますが、よろしいですか?」 といったアナウンスが画面に表示されるようになると、読者にとっては役立つサービスかもしれません。 リアル書店では、その書店の会員になった人に対するカウンターサービスの一つとして、提示された会員カードを読み込んで過去の購入履歴を検索するということは考えられる (すでに行なわれている?) と思いますが、会員と非会員の不特定多数の人が入り混じったレジのところでそれを行なうとなると、時間もかかってレジが混雑し、現実的ではないと思います。 意図せずに同じ本を複数冊買ってしまった経験がある人は結構いるのではないかと思います。 私の場合はこれまで人に譲ったりしていたのですが、よく考えてみると、私自身は人から何気なく貰った本はそのままにしてしまって、あまり積極的には読もうとしないので、相手に読む気を起こさせるには、渡すときのちょっとしたプレゼンがポイントかもしれないですね。 なお、今回の出張の最大の (というか驚くべき) 成果は、ある著者の方に 「この方は書き手として良いと思いますよ。いつか、何かをお願いしてみては?」 と紹介された方が、私の大学時代の同級生であったこと。 ほんと、世間は広いようで狭いなぁと思います。
2011.02.18
コメント(0)
-
企業を選ぶということ
これから就職活動を始めようという学生さん、就職活動中の学生さんの多くが、一部の大企業への就職を希望し、中小企業にはあまり目を向けていないとのこと。やはり学生さんには、「安定性」 や 「知名度」 といった要素が企業を選ぶ際の優先順位として大きいのでしょう。 もちろん、 このことは、 何も今の学生さんに限ったことではなくて、 私の学生時代にもそうでしたし、今日まできっとそうであったのだと思います。 なので、こうした傾向を否定するつもりはありません。でも、今のその 「安定性」 や 「知名度」 が今後もずっと続くかどうかは誰にもわからないことですし、個人的には、もっともっと中小企業に目を向けて欲しいなぁと思っています。 (出版社も、ほとんどが中小企業です。) これは当たり前のことですが、どんな大企業も、最初は 「安定性」 も 「知名度」 もないところからスタートし、 そして、 (もちろん株主の力も必要ですが) 社員一人一人の努力と、リーダーの手腕と決断によって 小 ⇒ 中 ⇒ 大企業 と少しずつ発展してきました。 そう考えれば、今は小さな企業でも、将来、大きく飛躍する可能性を持っているわけです。 また、規模は小さくても、すでにある分野では超一流で、大企業にも負けていないといった所もあります。 自分が成長でき、 自信とやりがいを持って働けるフィールドとなるならば、 企業の規模の比較など意味がないのではないかと思います。 大企業に就職したから勝ち組、 名も知られていない小さな企業に就職したから負け組といったことではなく、 自分が誇りをもって働ける企業・仕事であるかどうかが大切なのではないでしょうか。 人が一生のうちに働く時間は、人生の多くを占めるものです。 そうした大切な時間を過ごす企業 (あるいは、企業という組織に限らず、そのフィールド) を、 現時点の 「安定性」 や 「知名度」 だけで判断して選んでしまうのは、とてももったいないことだと思います。 これからの日本の未来を切り拓いていく若い人たちが、世間体や他人との比較といった狭い視野から解き放たれて、自分の人生を大きく切り拓いていくことを期待しています。
2011.02.08
コメント(0)
-
自分なりのスタイルを掴むということ
出版社に就職して、自ら望んでいた編集者という職に就いたばかりの頃というのは、一日も早く仕事を覚えて 「自分なりのスタイル」 を確立し、「自分が企画した本を出版したい」 と思うものです。 私も新人の頃は、まさにそんな気持ちを持って日々仕事をしていたように思います。 でも、入社してしばらくの間は、 ・ 原稿のコピー ・ 原稿を読んで、その評価 (自分の意見) を上司に述べる。 ・ 初校の作業をする。 ・ 上司が校正した再校・三校の校正刷を読み、赤字の入れ方を学ぶ。といったことが、私の主な仕事であったように記憶しています。 そして、 「自分で企画を立てて、本を出版する」 ということよりも、目の前の仕事をこなすだけで精一杯の状態でした。 また当時は、自分が行なっている仕事の一つ一つが単なる 「点」 としてしか捉えられず、編集者の仕事の全体像 ( 「線」 としての繋がり) が見えていなかったことも確かです。 1冊の本ができるまでの仕事の流れを把握し、著者とのやり取りの基本的な作法を覚え、先を読んで仕事ができるようになるまでに、私の場合は3年ぐらいはかかったのではないかと思います。 そして、編集者として独り立ちするまでには、さらに数年の月日が経っていました。 いまとなっては良い思い出ですが、当時は、なかなか独り立ちできないことに悩むこともありました。 でも、次第に自分が企画した本を出版するようになり、それなりの評価を頂く中で、少しずつ自分に自信を持つことができるようになりました。 と同時に、自分なりのスタイルもできてきたように思います。 そんなわけで、私自身を振り返ってみると、入社したばかりの頃に安易に思い描いていた 「自分なりのスタイル」 というものは、そう簡単には掴めるものではありませんでした。 拙い経験に照らして言えば、自身のスタイルは、基本となることをきちんと身に付けた上で、そこに自分なりの工夫や方法を加えていく中で、少しずつ自身の中に形作られていくものではないかと思います。 そして大切なことは、一度自分の中に形作られた 「自分なりのスタイル」 を過去の成功体験や経験に頼っていつまでも変えずにいるのではなく、柔軟に変化をさせること、自ら変化を求めることで、常に新しいことに挑戦していくことだと思っています。
2011.01.31
コメント(0)
-
今年の2つの目標
皆さんは、今年の目標などを立てましたか? 私はと言えば、毎年同じような目標を立てている気もするのですが、 1. 日々溜まり続けている (買い溜めしている) 本を少しでも多く読み終えること 2. アートやデザインに触れる機会を多くつくることの2つを、仕事以外での目標とすることにしました。 日々溜まり続けているというのは少し言い過ぎかもしれませんが、 私の場合、 買った本をまだ読み終えないうちに、 気に入った (気になった) 本は次々と買ってしまうこともあって、 自宅には自然と本の山が出来上がってしまっています。 これが電子書籍ならば端末にダウンロードするだけですから、 こうした本の山もできなくなって、その点では良いように思います。でも、本の山が見えているからこそ、これを何とかしなくては、と (良い) プレッシャーになったりすると思うので、電子書籍で買い溜めして (ダウンロードして) 本のカバーだけが仮想の本棚に整然と並んでしまうと、そうしたプレッシャーもあまり持たなくなり (すでに読んでしまったような錯覚にも陥ったりして)、私の場合は更に買い溜めが加速してしまいそうです。 まず今年は、このリアルな本の山を何とかしようと、仕事の行き帰りや移動のための電車の車内での過ごし方が大切だなぁと改めて思い直し、できるだけ読書の時間に当てようと思っています。 アートやデザインに関しては私は特に専門的に学んだこともないので、知識は乏しいのですが、見たり触れたりするのがとても好きです。 そんなわけで、美術館に行ったり、デザインショップや街の雑貨屋さんを見て歩くのも大好きなのですが、昨年はなかなか行く時間がとれなかったので、今年はできるだけ足を運んで、アートやデザインに触れる機会も多くつくりたいと思っています。 このことは自分の趣味でもあるのですが、デザイナーの方と一緒に本の装丁を考えたりするときに、そうした経験が何らかの形でフィードバックできればいいなぁ、なんてことも思っています。
2011.01.17
コメント(0)
-
今年はどんな1年に ・・・
「1年の計は元旦にあり」 などと言われますが、私も、この正月休みを使って、今年の刊行計画の確認と、昨年まで考えていたアイディアを練り直して、企画にまとめたりしました。 すでに編集作業を進めているものや、著者が原稿の最後の修正にとりかかっている段階であれば、いつ頃に本として刊行できそうとか、あるいは、イベント時期に合わせて刊行しようなどと、ある程度の見通しが立つものです。でも、原稿がまだ粗稿であったり、書きかけの段階だったりすると、その年の刊行計画に入れるべきかどうか迷います。 これは当たり前のことですが、その年の刊行計画に入れるとなれば、◯月に刊行予定といった形で社内で情報が共有されると共に、取次や書店などにも案内を行なうことを考えなくてはいけません。 そのため、 「原稿がくるかどうかわからないけど、とりあえず、刊行計画に入れておこう」 といった軽い気持ちで考えるわけにはいかないのが悩ましいところです。 また、刊行計画を立てて進めていても、脱稿までは時間がかかりそうだなぁと思っていた著者から 「書き上げたよ」 と思わぬ吉報が届いたりして、その完成度によっては進行中のスケジュールでも見直しをして、その年の刊行計画に組み入れることはよくあります。 ただ、その冊数が多くなってくると、嬉しい悲鳴状態となってしまいます。もちろん、気持ちとしては、当初に刊行計画に入れた原稿と吉報の原稿の両方を本として刊行したいものの、やはり一人の編集者が年間に刊行できる冊数には限界があるのも確かだからです。 それにプラスして、 当然のことながら、 1冊の本を刊行するまでには一定の期間がかかることもあり (これまでの経緯から言って、その原稿を他の編集者に任せることができないのであれば) 刊行時期が翌年にずれ込んでしまうということを、著者の方に正直にお話する場合もあります。 「著者」 という 「人」 を相手にしているからこそ、なかなか計画通りにはいかないのが常なのですが、だからこそ、この仕事は面白くてやりがいのあるものです。 今年はどんな吉報が飛び込んでくるかを楽しみにしつつ、また1年頑張っていきたいと思います。
2011.01.09
コメント(0)
-

2011年 年賀状
明けましておめでとうございます。 昨年の3月までの2年間に亘って本サイトを休止していたにもかかわらず、 またこうして多くの皆様にお越し頂くようになったことを、とても嬉しく思っております。 本年も、 EDITOR NAVI を宜しくお願い致します。 そして、2011 年が皆様にとって幸多き年となりますように。 2011 年 元旦 Cafe Wien
2011.01.01
コメント(2)
-
編集者の、無くて七癖
「無くて七癖」 と言われるように、人には多かれ少なかれ、癖というものがあるものです。 私が日頃お付き合いのある著者の方々も、それぞれに癖をお持ちですが、(さすがに記すのは控えさえて頂きますが) 実にユニークな癖をお持ちの方もおられます。 そして皆さんも、きっと一つや二つは癖をお持ちでないかと思います。 もちろん私にも癖がある (自覚症状がなくて、特にカミさんから指摘される) のですが、編集者になって数年が経つと、編集者としての癖 (癖というよりも職業病で、しかも自覚症状のあるもの)がプラスアルファとして身に付いてしまうように思います。 編集者になってからプラスされたと思われる、私の主な癖 (というよりも、職業病の一種) ・ 街中や車内で広告や文章を目にすると、 その表現や言葉の使い方、 句読点や改行の位置まで気になってしまう。 おまけに、ついつい誤植探しまでしてしまう。 ・ 街 (特に、初めて訪れた街) で書店を見つけると素通りができず、入らずにはいられない。 ・ 書店に入ると、ほとんどすべての本棚を端から端までチェックする。 ・ 書店で本を手にすると版数 (重版の回数) が気になって、まずは奥付をチェックする。 ・ 新しい企画のネタ探し (テーマや著者探し) が頭の中で年中無休状態 自覚症状のあるものを5つほど挙げてみたのですが、特に2つ目と3つ目は一緒に買い物に出かけるカミさんには大迷惑のようで、その間、私は放置されて、一人フリータイムとなってしまいます。 人に迷惑をかけるものは直した方がよいのかもしれません。でも、癖がすべて悪いかと言えば、 そんなこともなくて、 ユニークな癖の持ち主は、 他の人に覚えられやすいというのも確かですし、 その人の個性として見られることもあると思います。 ただ、その場合に、 「知ってる、知ってる! 〇〇をする人でしょ?」 と、癖の方だけを覚えられていて、 肝心な名前の方は覚えられていない場合も多々あるので、 自分の癖に誇りを持っている方はその点にどうかご注意下さい。 私の小さな課題は、上の2つ目と3つ目の癖 (癖というよりも衝動に近いもの) をどうするかですが、これは私にとっては趣味にも近いものなので、どうにもこうにもやめられそうにありません。 でも、今後、街の書店が様々な商品を扱うようになって本の売り場を縮小したり、書店そのものが少なくなってしまうと、書店でたくさんの本棚を眺めながらじっくりと本選びをすることもできなくなるのかなぁ、と少し悲しく思っています。
2010.12.29
コメント(0)
-
教えることは、学ぶこと
“先輩として後輩を指導する、あることについて人に教える” という場面や機会は、社会人になってからというよりも、すでに学校生活やアルバイトなどを通して、誰もが一度や二度は経験していることではないかと思います。 出版社の編集部においては、入社して数年 (毎年、新規採用をしているところでは入社して2年目くらい) の編集者に、新人編集者の指導を任せるところもあるのではないかと思います。 私も日頃、後輩の指導をする機会が多いのですが、そうした経験を通して、 「人に教えるということは、自分自身が学ぶことである」ということを常々感じています。 “教えることは自分の知識のアウトプット” であり、 “学ぶことは自分へのインプット” と見ると、一見、それらは相反するものに思うのですが、 「教えることで、自分自身の理解も深まるし、自分が実はよく理解していなかったことも明らかになる」 といった点では、この両者は表裏一体のものなのだと思います。 おそらく皆さんも、人にわかるように教えることが、いかに大変であり、 「人に教える中で、自分自身が本当はよく理解していなかったこと、曖昧な理解をしていたことに改めて気づかされた」 という経験をお持ちでないかと思います。 人にわかるように教えるためには、 自分が本当に基本から理解していないと、できないことです。 大学時代の輪講、そして、入社して2、3年の若手編集者に新人の指導を任せることの狙いも、そうした点にあると思います。 その意味で、入社1年目の編集者は、1年後、2年後には自分が後輩の指導をきちんとできる (後輩からの質問に自信を持って答えられる) ように、編集者の仕事をしっかりと学んでいってほしいと思います。 もちろん、 これは他の仕事でも同じだと思いますが、編集者の仕事も、先輩が手取り足取り教えてくれることはありませんから、先輩や上司の仕事を見様見真似で学んでいくことが大切です。
2010.12.21
コメント(0)
-
山積みの校正刷りを整理して
まだ1年の締め括りには少し気が早いのですが、先日、今年に入ってから自分が担当したすべての本の校正刷りをまとめて整理しました。新人時代は、それほど溜め込まずに整理していたように記憶しているのですが、今では、デスク脇に積み上げた校正刷りを年末に整理することが、私の恒例行事となりました。 社内の他の編集者たちの様子を見ていると、本が刊行されると、それほど間をあけずに、その本の校正刷りを整理する人もいるのですが、自分の場合はすぐに整理ができなくて、年末にまとめて整理するようになってしまいました。 一つには、整理の時間がとれなくて (面倒に思ってしまって) ついつい後回しにしてしまっているということもあるのですが、やはり一番の理由は、たとえ本になって用済みとなってしまった校正刷りとはいえ、いろいろと思い入れがあって、本ができたからとデスクの脇からすぐに整理してしまうのは気が引ける、というところにあったりします。 通常 (私の場合)、1冊の本を刊行する間に、 初校 ⇒ 再校 ⇒ 三校 (⇒ 必要に応じて念校)と3回の校正をしていて、初校と再校の際は正校正 (せいこうせい) と控校正 (ひかえこうせい= 正校正のコピー) の2通を印刷所から出して頂いています。 そのため、1冊の本が完成するまでに、 初校 (2通) + 再校 (2通) + 三校 (1通) = 合計 5通の校正刷りができることになるので、 ボリュームのある本が数点あったりすると、 1年後には校正刷りの立派な山が出来上がります。 そんな校正刷りですが、編集者が単に著者の原稿との照らし合わせをするだけのものではなく、著者と編集者とが何度も何度も 「読む・書き込む・議論する」 場とも言えるものであり、傍目には単なる紙の束であっても、1冊分の校正刷りには、著者と担当編集者の格闘の跡がいっぱい残っています。 「デスクの脇に、すでに本になった校正刷りをいつまでも置いておくのはだらしがない」 と言われてしまいそうなのですが、この山積みの校正刷りを整理しながら、 「このときは、著者とこんなやりとりをしたなぁ」 と思い出しながら1年を振り返ることが、 私にとって年末の楽しみの一つとなっています。
2010.12.14
コメント(0)
-
一つの考え方に固執せず、柔軟かつ広い視野で
出版業界への就職を考えている方々が悩むことになるのが、「自分はどの出版社を目指すべきなのか」 ということではないかと思います。 皆さんの中には、 編集者という職業に何となく憧れがあって、 「本 (雑誌) 作りができるのであれば、どこでも」 という姿勢の方も少なからずいるのではないかと思います。 そうした姿勢を否定するわけではないのですが、 編集者になりたいというからには、 “自分はどんな本 (雑誌) を手掛けたいのか” ということを、しっかりと考えることがとても大切だと思います。 もちろん、 「自分はいろいろな分野に取り組める出版社に就職したい」 と考えている方もいると思います。 そうした場合には、社内に複数の編集部があるような総合出版社を目指すことになると思います。でも、 出版社のほとんどが、 ある分野に特化した (どんな分野でも扱うのではなく、自社の強みを発揮できる分野に注力している) 専門出版社であることを考えると、あまり上の考えに固執し過ぎると、それに適した出版社が必然的に限られてしまいます。 また、 すでに自分が手掛けていきたい分野が明確になっている方は、 その分野に強い (その分野で有名な) 出版社への就職を目指して活動しているのではないかと思います。でも、やはりこのことに固執し過ぎても、上と同じように出版社が限られてきてしまうと思います。 (これは以前から変わらないことではありますが) 出版社の採用状況が厳しいことを考えると、 1. いろいろな分野に取り組める出版社に就職したい 2. 手掛けたい分野はこれしかないので、それが実現できる出版社に就職したいのどちらの考えでも、そのことに固執してしまうと、就職のハードルをますます高いものにしてしまうと思います。 もし1のように考えているのであれば、さらに一歩踏み込んで、「いろいろな分野の中で、自分が特に興味・関心が高いのは何か」 と掘り下げてみて、そして、2のように考えているのであれば、 周辺の分野へと横に広げてみるとよいと思います。 総合出版社の編集者、専門出版社の編集者にかかわらず、編集者というものは好奇心が旺盛で、常にアンテナを張って、日頃からいろいろな分野に興味・関心を持つことが大切なわけですが、就職活動という場面においても、 一つの方向や考え方に固執し過ぎて、 開けるべき扉も開けず、 トライすべきこともトライせずにチャンスを逸しないよう、柔軟かつ広い視野を持って頑張って下さい。
2010.12.07
コメント(0)
-
原稿催促とは難しいものです
新しい本が生まれるための第一歩は、編集者自らがアイディアを練って企画を立て、著者に執筆依頼をすることから始まります。 そして、 その一歩を踏み出すと次に待っている大切な仕事が、 著者への原稿催促というものですが、編集者として何年経験を積んでも、「原稿催促というものは難しいものだ」 と日々実感している私です。 著者の執筆が進んでいない理由には、例えば、 1.編集者が著者に対してほとんど催促をせず、日頃からコミュニケーションをとっていない。 2.著者がアイディアやストーリーに煮詰まってしまい、筆が前に進まなくなってしまっている。 3.他の原稿や仕事と重なって多忙を極め、お願いした原稿に取り組む時間がとれない。 4.健康上の理由などがあるのですが、1番目については、著者に執筆依頼をした後はすべて著者任せというものであって、編集者としては失格とも言えることだと思います。 これは2番目とも繋がっていくことなのですが、編集者は単に原稿催促をするだけではなく、著者の良き相談相手となることがとても大切であり、執筆が前に進まず著者が悩んでいるときには、(時には盃を交わしながら) いろいろと話をしたり、精神的な支えとなることも求められます。 したがって、 原稿をお願いした後はそれっきりというのではなく、 “タイミングをはかりながら” 著者とコミュニケーションをとって、 ・ 原稿が予定通りに進んでいるかどうか ・ 著者が悩んでいること、困っていることはないかといったことに注意を払っていくことが必要です。 そして、4番目の理由においては無理なお願いはできないことは言うまでもないことですが、著者が3番目の状態に置かれている場合には、何としても書き上げてほしいという編集者の粘り強い姿勢が求められ、その力量が試される場面でもあります。 私が原稿催促において難しいと感じていることは、 上に記した “タイミングをはかりながら” という点であり、こればかりは公式のようなものが適用できず、どういうタイミングで著者に原稿催促をするかというのは、まさに一人一人異なっていると経験的に理解しているからでもあります。 著者によっては、執筆依頼の段階で 「頻繁に催促してほしい」 と言う方もいれば (原稿をいくつも抱えている方に多いように思います)、 「あまりプレッシャーにならないように、スローペースで」 と言う方もいたり、・・・。 でも、多くの方は催促のペースを事前にリクエストしてくることはないので、「前回催促したのはいつで、そのときはこんな進捗状況だったから、そろそろ次の催促をしてみようか」 と、毎回ドキドキしつつも期待感を持って原稿催促をしています。 (催促する時間も、著者によって異なってきます。) 編集者は原稿の割付や校正などの編集実務上の進行管理と同時に、著者の進捗状況をきちんと把握して、著者と二人三脚で原稿の完成に向けて進めていくことが大切となっています。
2010.11.29
コメント(0)
-
出版業界を目指す皆さんへ
現在、就職活動中の学生さんはもとより、これから就職活動を始めようという学生の皆さんも、今年の大学生の就職内定率が過去最悪を記録していることはご存知のことと思います。 そうしたなかで編集者を目指している皆さんに、今から20年も前の自分の就職活動のことは何ら参考にならないかもしれないのですが、何かのきっかけにでもなればと思います。 私が大学3、4年生の頃は、いわゆるバブルの時で、自分の友人や同級生たちは、一人で20社近くの内定をもらったりという (すごい) 時代でした。 でも、 出版社への就職を目指していた私には、 そうした話は全く無縁でした。 大手の新聞社など一部のマスコミ企業を除いて、大学の就職相談室 (資料室) に求人募集の情報を送ってくるところはなく、 就職指導の担当の方からも 「出版業界を目指すのであれば、自分の力で探しなさい」 と意見されたことをよく覚えています。 時代はバブルであったのですが、 残念ながら出版業界は当時も非常に狭き門で、 私にとっては (おそらく、出版社を目指す多くの学生にとって) バブルはほとんど関係ありませんでした。 とても短期間でしたが、小さな出版社でアルバイトをしてみたり、大学3年生のときに編集の学校に半年間通ったのも、そうした背景があったからで、このまま不安に思ったままで何もしないでいるよりも、自分から何か動いていかなければいけないのかもしれない、と思ったからでした。 もちろん、編集の学校に通ったからといって出版社への就職が保証されたわけでもなく、将来への不安は抱えたままでした。でも結果的には、この半年間が、自分にとっては大きな転機となりました。夜学には自分と同じように現役の大学生もいましたが、その多くが、営業部から編集部への配置転換に備えて編集の勉強に来ていた出版社の現役社員の人たちであったために、夜の講義が終わって皆で居酒屋に繰り出しては、出版業界の生の声や励ましの言葉を頂くことができたからです。 ときには、忙しいなか貴重な時間を割いて私を会社に招待して下さり、編集部を始め、社内をいろいろと見学させてくれたり、編集部の方々の飲み会に同席させて頂けることもありました。こうした経験をさせて頂いた方々にはとても感謝していますし、今でも決して忘れることのできない大切な思い出となっています。 こうした経験によって、当時の自分の就職活動の厳しさが解消されたわけではありませんでしたが、「自分は絶対に編集者になる!」という強い気持ちを持ち続けるための大きな原動力になったことは確かでした。 編集者を目指している学生の皆さんにとって、 出版業界は今も昔も、 そして、 きっとこれからも、厳しい狭き門であることは変わらないだろうと思います。ここで自分が伝えたかったことは、私自身が就職活動を前にどんなことをしてきたかということではなくて、狭き門であることがわかっているのであれば、何となく出版業界への憧れの気持ちを持ったまま就職活動を迎えるといった待ちの姿勢でいるのではなくて、(それがベストな選択かどうかはわからないにしても) 自分から積極的に一歩踏み出してみることが大切なのではないか、ということです。 厳しい就職活動のなかで頑張っている、 頑張らなければならない皆さんを、 陰ながら応援しています。
2010.11.21
コメント(0)
-
知識や情報を蓄積・共有・活用すること
日々の仕事の中で常々感じていることは、書籍の編集者は、各自が持っている知識や情報を互いにもっと共有・活用することが大切ではないか、ということです。 書籍の編集者は、企画の段階から本を完成させるまでの間、基本的には自分でコツコツと作業を進めていくことが一般的であるため、何か困ったことやトラブルが起こったりした場合を除けば、周囲の編集者と話し合いをしながら進めていくということはあまりありません。 そうした中で、以前、こんなことがありました。編集者Aさんが、自分にとって (また会社にとって)初めて執筆をお願いする著者による企画を出し、それを企画会議で検討し始めたときのこと。 「この方とは以前から知り合いなのでよく知っていますが、この方向性は向いていないのでは」 との編集者Bさんの意見。 企画書を書いたAさんは、初めての著者ということで、その方が過去に書いた作品を読んだり、いろいろと下調べをしていたのですが、一番身近なところに、その著者のことをよく知る人がいたわけです。 もちろんAさんは事前に、自分が今考えている企画のことや著者候補として考えている方について、上司や先輩の編集者に相談していたらしいのですが、 そこにはBさんは含まれていなかったため、 企画会議で初めて知ることに・・・。 結果的には、執筆を依頼する前の企画会議の段階でわかったので、 企画の練り直しなどはできてよかったわけですが、 もし、 Bさんが持っている情報を事前に共有できていたなら、 Aさんの企画も、 それを踏まえたものになっていたのではないかと思います。 現在、ナレッジマネジメントを重視する企業が増え、組織として、その仕組みが非常にシステム化された所もあるようですが、それには及ばないまでも、各編集者の持つ知識や情報の蓄積・共有・活用がもっとできないものかと考えています。 (最終的には、営業部なども含めた、社内全体として。) もちろん、(これは編集者に限ったことではありませんが) 編集者はそれぞれ、自分の中で密かに温めているアイディアや掴んでいる情報、独自の人脈などを持っていて、それらの情報をすべて共有するということは簡単ではない (共有化することに抵抗を感じる編集者もいるかもしれない) と思うのですが、 編集部として、 そして出版社という一組織として より良い出版物を刊行していくためには、大切なことの一つではないかと思っています。
2010.11.14
コメント(0)
-
作品にとってベストなカタチを選択する
先日、ある著者の方から、待ちに待った原稿が届きました。 その原稿は、久しぶりの手書き原稿。 手書きの原稿を頂いた場合には、入力した原稿とは違って著者の手許に元データが残っているわけではないので、 最低でも1通はコピーをとって保存し、 不測の事態に備えるのが鉄則となっています。 私が出版社に入社した当時は、(当時もワープロはありましたが)ほとんどの著者の方が手書きということもあって、 上司や先輩から原稿を手渡された新人の私は、 コピー機の前に陣取って、 一日何時間も原稿のコピーをしていたこともありました。 実は、これには2つの理由があって、執筆依頼の際に著者に渡していた当時の原稿用紙がとても薄くて柔らかったことと、今と比べてコピー機の性能がそれほど良くなかったために、連続コピーをすると紙詰まりを起こしやすかったのです。 そのため、 原稿を1枚1枚ガラス面に置いてコピーすることが多かった、という事情がありました。 出版社が舞台のテレビドラマで、新人の編集者がコピー機の前でひたすら原稿をコピーする場面がよく出てきますが、当時の私は、まさにそうしたことの繰り返しだったような気もします。 今は著者から頂く原稿はほとんどが入力原稿なので、原稿をプリントアウトしたもの(ハードコピー)と入力データ(MOやUSBなど)の双方を頂けるようになり、そうした点では、当時と比べて作業の効率が上がったことは確かです。 そのため、著者から手書きの原稿 (生原稿) を頂くと、今でも私は緊張します。 一つには、 やはり生原稿には作品を完成するまでの著者の格闘の跡が生々しく残っていること。そして、もう一つは、目の前の原稿が、この世に2つとない(入力原稿のように、データとして残っているわけではない) からです。 もちろん、入力原稿には著者が苦労した跡が見られないということではなく、手書きの原稿では、それをリアルに感じやすいということが言えるのではないかと思います。 将来、 (今でも少なくなってしまった) 手書きの原稿が更に減ってしまい、その一方で、電子書籍で読書することが当たり前の時代になったとしても、個人的には、手書きの原稿は、できれば紙の本として出版したいという思いがあります。もちろん、手書きの原稿も(編集者が割付した後に) 印刷所のオペレーターの方がそれに基づいて組版し、結局はデータ (入力された原稿) になってしまうわけですが、手書き原稿にはそれが醸し出す独特の雰囲気があって、それは、手触り感のある紙の本の方が (言葉でうまく表現できないのですが) 似合うのではないかと思っています。 でもこのことは、今後は入力原稿は電子書籍がいいとか、今後も手書き原稿は紙の本がいい、ということではなくて、大切なことは、その作品にとって最もベストなカタチを選択することではないかと思います。
2010.11.07
コメント(0)
-
ちょっと残念な一日
10月30日(土)、31日(日)、古本街・書店街として有名な東京神田の神保町において、 「第20回 神保町ブックフェスティバル」 が開催されるのですが、30日の今日は台風接近の影響もあって、残念ながら屋外イベントは中止となってしまいました。 既にご存知の方も多いと思いますが、屋外イベントの一つに、各出版社による本のワゴンセールがあります。 私も数年前までは営業担当と一緒にワゴンでの販売を行なっていたのですが (最近は、いろいろと経験してもらおうということで、若手の編集者が担当することが多くなりました)、 毎年多くの方々が何か掘り出し物はないかと来られて、わずか2日間ではありますが、大変楽しいイベントになっています。 また、編集者としても (もちろん、営業担当にとっても) 、読者の方々と直接お話しができるということもあって、このイベントは大変貴重な機会となっています。 「この本、面白かったよ」、「期待して読んだけど、いまいちだったよ」、「このシリーズ、いいですね」 、「こういう内容の本はない?」 などなど、嬉しいこと、 ちょっと残念なこと、 そして、 次の企画のヒントになるようなことなど、 普段はメールや葉書きで頂くことが多いご意見を読者の方から直接頂けることは、大きな刺激になります。 (その本の読者層も見えてきたりします。) 本そのものが無くなることはないと思っていますが、将来、電子書籍で読むことが当たり前の時代になってしまったとしたら、こうした楽しいイベントも縮小あるいは無くなってしまうのかなぁと、ちょっと気になったりもします。 何でもネット、メール、ダウンロードの時代は便利ではありますが、新しいモノを創造するためには、デジタルではないリアルな空間における互いに面と向かってのコミュニケーションがとても大切だと思うので、もし、電子書籍の時代を迎えたとしても、そのカタチを変えて、多くの人たちが集まる こうしたイベントを残していきたいものです。 本好きな皆さんは毎年楽しみにしていると思いますし、参加する各出版社も読者の方々と出会える このイベントを大変楽しみにしています。また編集者を目指している皆さん、ワゴンセールには編集者の方々も多く参加しているので、各出版社のワゴンの向こう側にいる人たちをちょっと観察してみる、ワゴンの本を選ぶ・買うタイミングで話しかけてみる、というのもいいかも・・・。 そんなことで、31日はどうか良い天気となりますように。 追記(11/1) 31日は残念ながら良い天気とはなりませんでしたが、多くの方々にお越し頂き、各出版社のワゴンセールも大賑わいでした。 お越し頂いた皆様、有難うございました。
2010.10.30
コメント(0)
-
編集・出版の機能を持った電子書籍端末の可能性
昨今、様々な電子書籍端末、電子書籍が読める機能を持ったPCが各社で開発され、発売されてきていますが、現在の電子書籍端末は電子ブックリーダーとも呼ばれるように、「電子書籍を読む」 ことを第一の目的に作られているように思います。 しかし、 電子書籍の誕生によって、 誰もが著者になれる (紙の書籍よりも手軽に出版できる) 時代を迎えたことを考えれば、現在の単なるブックリーダーとしての機能だけではなく、将来的には、電子書籍端末を使って電子書籍を出版できる (原稿の執筆から編集作業まで可能とし、最終的に、ブックストアーへの販売委託 (登録) までできる) ところまで進化することが求められてくるのかもしれません。 もちろん、 より魅力的な電子書籍を出版しようとすれば、 それを著者一人だけの力で実現するのはとても大変なことであり、そこに編集者 (あるいは出版社のような規模ではないにしろ、何らかの組織) が介在する意味があるのかもしれません。 でも、使い慣れた電子書籍端末を使って読者が本を出版することまでできるようになれば、それは一つのイノベーションとなるのではないかと思います。 まだ、いくつもの課題を抱えているとはいえ、現在の電子書籍端末はそれが誕生した当時と比較すれば、大きな進歩を遂げてきています。そして、その課題の多くは、至極当たり前のことですが、電子書籍を読む端末としての利便性や性能という視点から捉えられているものです。 したがって、本の執筆・編集・出版までできる端末を目指すことになれば、更に別の課題を積み上げることになることは容易に想像でき、結果として、端末価格を上昇させることになることも予想されます。 そうして考えると、“電子書籍の読者と著者の双方を実現可能とする機能” を持った手頃な値段の電子書籍端末が登場するためには、越えなくてはいけない壁は相当に高いのかもしれません。
2010.10.22
コメント(0)
-
本のもつ可能性を広げる一つのツール
街角の広告・ポスター、雑誌の広告、包装紙やレシートを始め、 今やさまざまな媒体に取り入れられているQRコードは、消費者にケータイのバーコードリーダーで読み取ってもらうことで、より詳細な情報やサービスを提供したり、ある特定のサイトに誘導するためのツールとして、幅広く使われています。 きっと皆さんも、ケータイのバーコードリーダーでQRコードを読み取った経験があるのではないかと思います。 (QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。) 出版の世界では、雑誌 (特に広告のページ) で比較的よく取り入れられているわけですが、本の場合には、奥付やその裏の自社広告のページに小さく入っていることがあるぐらいで、本文中で使われている例はほとんどないように思います。 でも、本とICTの融合の一案として、アナログ媒体からデジタル空間へと広がりを持たせ、読書を楽しくする、より読者の理解を深める仕掛けとして、読書を阻害しない程度の数とサイズでQRコードを本文中に配置するということも考えられます。 安易な例となりますが、QRコードを読み取ると、 ・写真 ⇒ その動画を見ることができる ・クイズ問題 ⇒ 解答が現れる ・序文や後書き ⇒ 著者から読者へのメッセージ映像が流れるといったものや、 ・QRコードで部分的に隠された、文章やイラスト ⇒ 隠れた部分の正体が現れるといった仕掛けが浮かびます。 もちろん、これらのことは、電子書籍ではQRコードではなくリンクを設定するだけでできてしまい、読者もケータイのバーコードリーダーを立ち上げる必要もなく、クリック一つで済んでしまうことではあります。 でも、既存のツールをうまく取り入れる、組み合わせることで、本のもつ可能性はまだまだ広げることができると思います。 “読書を楽しむのに、ケータイも開く必要がある” ということは、読書のスタイルとしては現実的ではないと考えられてしまうかもしれません。 でも、そうしたちょっとした仕掛けが読者の理解を深める、楽しませる、ワクワクさせることにつながっていくのであれば、その試みもありなのではないかと思っています。 ここ数日は、責了間近の数冊の編集作業に追われ、まさにお尻に火が付いた状態でした。脂がのった私のお尻は少しばかり焼き焦げた感もありますが、何とか間に合わせることができて、今はホッとしています。 この週末は、久しぶりにのんびりできそうです。
2010.10.15
コメント(0)
-
これからの編集者に求められること
これまで編集者というのは、著者を影から支えつつ、本の完成に向けて黙々と仕事をこなす姿から、黒子のような存在とも言われてきました。私が出版社に入社した頃(20年くらい前)を例にとっても、今と違ってblogやtwitterのような個人で手軽に情報発信ができるようなものもなかったですし、編集者がテレビやラジオに登場するなんてこともほとんどなかった時代でもありました。 そんなこともあって、これまでは、編集者の名前が公になる機会というのもあまりなかったように思います。 (これは今でも見られることですが、 著者のご好意で、 本の序文や後書きに、その本の担当編集者の名前が記されるということはありました。) でも、これからの編集者は黒子としての存在だけではいけないように思っています。 もちろん、これは 「本の編集よりも、自分を売り込むことに注力しよう」 ということではなく、いろいろなメディアを使って自ら情報発信する、情報を編集できる力が求められる、ということです。 仕事として編集者が自ら情報発信するとすれば、これまでは宣伝部や営業部が中心となって行なっていた、新刊情報や書店で開催する各種のフェア・サイン会などのイベント情報がすぐに浮かぶわけですが、それ以外にも、今進行中の本の舞台裏みたいなものを紹介するというのも、読者の期待感を高めることに繋がっていくように思います。 仕事を離れてとなれば (とは言うものの、常に仕事のことが頭から離れないのですが) 、趣味の領域に始まり、それこそいろいろなことが考えられるわけですが、自ら情報発信をしていると、情報に対する感度が高まると同時に、不思議と情報が集まってくるようにもなるものです。 また、 (これは多くの方がすでに経験していると思いますが) 仕事の延長線上では決して出会うことはなかった人たちとの出会いがあったり、そこから何か面白いコラボレーションが生まれて、仕事にもフィードバックが起こるということもあります。 以前にも同じようなことを記したことがあったと思いますが、これからの編集者は、本や電子書籍の編集という狭い範囲の編集にとらわれずに、多様なメディアを上手に使いこなし、アウトプット先のメディアに合わせて情報を的確かつ柔軟に編集できる力が求められてくるでしょう。 そうした意味では、多様なメディアに囲まれて育ってきた、これから編集者を目指す若い人たちには、情報発信力と情報編集力をぜひ養ってもらいたいと思いますし、私も含め、現役の編集者の方々も、若い人たちに負けないように頑張っていかなくてはいけないと思います。
2010.10.06
コメント(0)
-
本のカタチとユーザビリティ
一般に 「ユーザビリティ」 と言えば、使いやすさや、わかりやすさといったことを意味していることもあって、 身近なものでは、家電製品やウェブページの操作性やデザインなどに対して使われることが多いのではないかと思います。 それに対して、「本のユーザビリティ」 といった話は、これまでほとんどされたことがなかったように思います。 本のカタチは、 扉・序文・目次・本文・後書き・索引・奥付といった中身 (内容) をカバーと表紙で包み込んだシンプルなものであり、「それを手に持って、開いて読む」 ことになるわけですが、あえてユーザビリティを評価するとすれば、目次や索引のわかりやすさ、本文のレイアウト (これらはエディトリアル・デザインにも属するものだと思いますが)、 紐のしおりの有無などといったことになるのでしょうか。 前に記したように、 電子書籍の登場によって紙の本が消滅してしまうということではなく、 紙の本と電子書籍は読者の好みやその目的に応じて使い分けられ、共存していくことになると思っています。 でも、今後、ユーザビリティの優れた電子書籍端末が次々と登場してくることを考えると、これまではおそらくほとんど考えられてこなかった紙の本のユーザビリティについて、考えてみたい気もします。 もちろん、紙の本は今のカタチで十分と思っている方も多いと思いますし(それ以前に、本のカタチについて考えたことがある人がほとんどいないかもしれませんが)、本は中身 (内容) が一番に大切でしょう、ということもあると思います。 でも、 そうしたことを踏まえた上で、 もしかしたら、 まだ私たちが思いもしないような、読書することが楽しく、そして心地良くなるような、全く新しい (そして、ユーザビリティにも優れた) 斬新なカタチの本があるかもしれません。 紙の本のカタチは、 時代を超えて、 今に至っています。 でも、 その当たり前と思っているカタチを一度リセットし、もう一度、一から考えてみたらどうなるでしょうか。それでもやっぱり、今のカタチに行き着くのか、それとも、何か思いもしないようなカタチが生み出されるのか・・・。 そんなことをちょっと考え始めただけでも、紙の本にも、まだまだいろいろな可能性が潜んでいるのではないかなぁと、紙の本が大好きな私は思ってしまいます。
2010.09.27
コメント(2)
-
「つながり感のある読書」 という新しいカタチ
本というものが誕生してから今日まで、 読書というものは、 (グループで読書を楽しむといった場合などを除けば) 基本的には、 読者が一人でその作品の世界に入り込むことができる、 とても個人的な楽しみ・行為であったと思いますし、そのことは、今後も、紙の本でも電子書籍においても変わらないものだと思います。 しかし、 電子書籍は、 これまで個人的な行為であった読書というものを、 これまでにない新しいカタチにする可能性を持っていると思います。以前少し記したことがあったかもしれませんが、ネットにつながる環境にある端末を使っての読書は、同じ本を読んでいる人同士がリアルタイム (同期) あるいは非同期でつながることを可能にするからです。 電子書籍は読者がネット上で本を購入した後に各自の端末にダウンロードして読むわけですが、ダウンロードした本のページを開くと同時にネットとつながることが可能です。 そのため、 例えばその本を開くと同時に、出版社側が予め用意しておいた、その本に付随したサイトとつながり、同じ本を購入した人同士がコミュニケーションをするということも可能となります。 さらに、 もっとつながり感を感じるカタチとして、 同じ本の同じページを今まさに読んでいる人同士がコミュニケーションをするということも可能になるかもしれません。もちろん、本は一人でじっくりと味わって読むもの、ということからすれば、読書しながら他人とコミュニケーションをとる必要などない、ということもあるかもしれません。 でも、こうしたことが技術的に可能であるならば、逆にそのことを積極的に取り入れて、 「つながり感のある読書」 という新しいカタチも考えられるのではないかと思っています。 例えば、推理小説というのは最終的には犯人がわかってしまうものですが、本の中では犯人をあかさず、読者に犯人探しをさせる、という本も考えられます。 確かに、紙の本であれば、 「最後まで読んだのに、 結局、犯人がわからないまま?」 と独りで悩むことになってしまいそうですが、 同じ本 (同じページ) を読んでいる人たち同士がつながることで、「ここに書かれているこの行動が怪しいから、この人が犯人では?」 と読者同士で犯人探しを楽しむということもできるかもしれません。 (メールやパスワードの入力で、 最終的には読者に犯人をあかすことが必要となるでしょうが・・・) ここでは少し安易な例となってしまったのですが、電子書籍の特性をうまく使うことで、これまで非常に個人的な行為であった読書というものから、 他の人とつながることで楽しむ読書、 という新しいカタチを生み出すこともできるのではないでしょうか。 電子書籍はそんな新たな可能性も秘めたものではないかなぁと思っています。
2010.09.16
コメント(0)
-
過信せず、謙虚さを大切に
先日、入社して数年になる若手の編集者が、とある失敗をしてしまいました。 彼の中では、この程度のことは周りに (先輩や上司に) 相談しなくても一人で何とかなると思い、自分を過信してしまったのでしょう。 結果として、大切な著者を怒らせる事態となってしまいました。 入社して間もない頃というのは、すべてがわからないことばかりで、毎日必死になって仕事を覚え、心にも余裕がありませんが、3年を過ぎた頃になると、編集作業も一通り経験して仕事の段取りも覚え、作業の全体を見渡しながら、先を読む余裕も生まれてきます。 でも、この “ちょっとした自信が芽生えた頃” が、 “思わぬトラブルを起こす頃” なのかもしれません。 僅かな経験から掴んだ “ちょっとした自信” 。 このこと自体は、次へのステップとして、とても大切なことだと思います。 でも、途中で何か問題が起こったときに、この僅かな経験だけに照らして事を判断してしまい、胆略的に (自分には正解と思える) 方針を導き出してしまいがちであることも確かです。 でも、自分も新人時代に経験がありますが、何か問題が起こったときに (自分なりの考えを導き出した上で) 先輩や上司に相談してみると、 「そんな方法や解決策があったのか・・・」 と感心させられる (勉強になる) ことが多かったものです。 自分に (自分の仕事に) 自信を持つことはとても良いことですが、決して、独りよがりになってはいけませんし、わからないことを他人に聞くことは決して恥ではありません。 恥なのは、わからないのに、わかったふりをすることです。 判断に悩んだら、自分の周りの人に聞いてみる。 そのために、先輩や上司はいるのですから。 私が知る、 経験豊富な敏腕編集者の方々は、 決して “自信過剰” ではなく、“自分に自信があるからこそ、謙虚であることを大切にしている” ように思います。
2010.09.08
コメント(0)
-
アメーバ化が予想される出版
私が出版社に入社した頃は (実際は、もっと以前からですが)、「出版社は机と電話一つあればできる」 と言われていました。 もちろん、実際には印刷会社・製本会社・取次会社などとの繋がりも大切になるわけですが、 「出版というものは企画力こそが勝負であって、それさえ他に負けていなければ、小さくてもやっていける」 ということを言い表したものではないかと思います。 だからと言って、これが誇張した表現かというと決してそういうことではなく、実際に個人で出版社を立ち上げているところもそれなりにあるわけで、そういう意味では、昔から出版というものは小回りがきくものであったと言えると思います。 そして、現代における電子書籍の登場は、これがさらに小さくなって、出版社という形態はとらずとも個々 (著者と編集者) の繋がりだけで出版原稿を完成させ、それを電子書籍として販売するということを可能としてしまいました (実際には、著者だけですべてを行なうことも可能となっていますが)。 これは、もともとは生物用語ではあるけれども、社会における 「アメーバ」 の用法でいけば、これからの出版は “アメーバ化する” ということが予想されます。 出版社というような組織を作らなくても、役割分担の機能を持った小さなかたまり (アメーバ) で出版が手軽にできることになり、そのことで、「私も電子書籍を出版しよう」 という動きが高まり、このアメーバがどんどん増殖していく、というのが (近い) 未来の出版の姿なのかもしれません。 このことによって、これまで以上に多様な出版物 (電子書籍) が誕生してくると思いますが、多くの読者の共感を得る内容 (質) とするためには、著者の執筆力は言うまでもなく、編集者の編集能力もこれまで以上に問われてくるのではないかと思っています。 (著者自身が執筆と編集までも行なうということになれば、それはなおさらのことでしょう。) そうした未来の姿を想像した上で、力のある出版社には力のある編集者がおり、優れた企画力・編集能力が備わっていることを考えれば、出版社 (編集部) の組織内もアメーバ化し、例えば、「編集部全体での企画会議で検討してOKが出なくてはいけない」 という形ではなく、より小回りのきいた組織でその都度判断して動く、という変幻自在のスタイルも求められてくるのではないかと思っています。
2010.09.01
コメント(0)
-
新しい著者の開拓と著者との信頼関係の大切さ
先日、初めて執筆をお願いすることになる著者の方との打合せに行ってきました。 その方は東京から少し離れたところに住んでいるということもあって、一日かけての執筆依頼となりましたが、久しぶりに特急とローカル線を乗り継いでのことで、ちょっとした旅気分を味わうこともできました。 出張というと、普段は新幹線を使ってのことが多く、それだと気分も仕事モードから抜け切らないのですが、今回はのんびりとした車窓の風景を楽しめたことが、旅気分を感じさせてくれたのかなと思っています。 ところで、編集者がどのように (自分にとっての) 新しい著者を開拓していくかということは、編集者によって様々だと思いますが、一般的には次のような場合が多いのではないかと思います。 ・他社で執筆した著者の作品や雑誌の記事を読んで惚れ込み、自らもその著者に依頼する。 ・いろいろな会合やセミナー、イベントなどに参加する中で、顔見知りとなる (関係を築く)。 ・すでに自分と繋がりのある著者から紹介される (紹介してもらう)。 ・ネットでの情報や良い意味でのうわさ話などから、著者の候補となりそうな方の情報を得る。 編集者であれば、他社での執筆経験がなくても秘めた力を持った、まだ無名な方を著者として発掘し、その方と一緒になって良い作品を創りたいという思いを持っているものです。 しかし、過去に一度も執筆経験がないということで、その方の力量が読み切れないということもあり、企画会議においては大きな決断が迫られることになります。 もちろん、これまで安定して読者の高い評価を受けてきた著者が、次の作品でも同じような評価を受けるということは決して言えません。その意味では、新しい作品を執筆して頂くという点においては、経験豊富な著者も、まだ無名な著者も同等と言えるわけですが、作品の完成度に対するある程度の予想ができるという点で、経験豊富な著者に執筆をお願いする傾向が高いことも確かです。 そして、これが結果として、出版社 (編集者) 同士での著者の奪い合いを引き起こすことに繋がっています。 そうした著者の争奪戦がある一方で、編集者として嬉しいことの一つは、こちらから執筆をお願いする前に、自分が信頼する著者の方から 「こんなのを書いてみたんだけど (こんなのを書こうと思っているんだけど)、ちょっと読んでみてくれないかな (相談にのってくれないかな)」 と声をかけられることです。 (どこよりも先に) 信頼する著者から声をかけられることは何よりも嬉しいことですし、このことは、編集者としての力量を表すことでもあります。 秘めた力を持った新しい著者を開拓する (見つけ出す) こと、そして、すでに繋がりのある著者との信頼関係を保ち続けることは、編集者としてどちらも欠かすことのできないとても大切なことの一つとなっています。
2010.08.23
コメント(0)
-
情報リテラシーの変化と電子書籍の登場
今から5年ほど前に、 「結局最後はプリントアウト」 というテーマで、 じっくりと思考を巡らせながらの読解には、 画面を通して直接読むよりも、 それをプリントアウトして読む方が向いている (頭に入りやすい) のかもしれない、というようなことを書いたことがありました。 パソコンがどのオフィスにも当たり前のように導入された当時、文書の電子化によるペーパーレスの時代がやってきたことが叫ばれ、「これで紙ゴミも減る」 と言われたことがありましたが、実際は、なかなかその通りにはなりませんでした。 それは、人は 「結局最後はプリントアウト」 したものを読んだり、 (文書データの保存だけでなく) プリントアウトしたものも同時に保存する傾向が強かった、というところにあったのでしょう。 でも、いまの私たちはどうでしょうか。 当時から比べれば、 必ずプリントアウトして読む、 プリントアウトしたものも同時に保存する という行為は減っているのではないかと思います。 当時は、いま一つ思惑通りには進まなかったペーパーレス (文書の電子化) も、環境や資源に対する企業の意識向上などもあって、それが社員一人一人に徹底 (あるいは、外力として作用) し、浸透してきた感もありますが、それに加えて、一人一人の情報リテラシーの変化もあるのではないかと思います。 (本来であれば、情報リテラシーの “向上” と書きたいところですが、自分も含め、必ずしも皆が “向上している” とは言えないでしょうから、あえて “変化” という表現にしました。) 私自身は、ペーパーレスに抵抗感がなくなったということと、紙の本ではなく電子書籍でも抵抗感がないということが、何らかの形で関連していて、 紙に書かれたものを読まなくても抵抗感がない 目に見える実体として保存する (棚に並べる) ことに拘らないということの背後には、現代人の情報リテラシーの変化も影響しているのではないかと思います。 そう考えていくと、(もちろん、端末自体の性能の向上もかなり大きな要因だと思っていますが)、電子書籍の登場は別に驚くことではなく、ごく自然な流れであったと言えるのかもしれません。
2010.08.16
コメント(0)
-
新しいアイディアを得ることができる空間
書店は、編集者にとって、自社の本 (自ら編集を担当した本) を販売してもらう空間であり、また、一読者として本を購入する空間であると同時に、新しい企画の種 (アイディア) を得ることができる情報空間でもあります。 ネット書店というものが登場し始めてから、これまでの街の書店はリアル書店とも呼ばれるようになったわけですが、よく考えてみると、ネット書店も現実に存在している書店であり、その意味ではどちらもリアル書店であることは確かです。 というわけで、 改めて言うまでもないことですが、 “リアル” というのは、読者が実際に本を手にして選んで購入できる、ということを意味しているのでしょう。 編集者だけでなく、企画に関わる仕事をしている人であれば、街の書店を訪れ、本棚に並べられた様々な本の背表紙を眺めながらいろいろとアイディアを練る (思索に耽る) ということをしているのではないかと思います。 私も、もちろんその一人であるわけですが、“アイディアを練る”、 “企画のヒントを得る” ということで言えば、その活用度は圧倒的にリアル書店ではないかと思います。 私の場合について言えば、 ネット書店に並べられた書籍情報を眺めていても、 新しいアイディアはなかなか湧いてきませんが、もちろん、これは人によると思うので、 「自分はリアル書店もネット書店も一緒」 という方もおられるかもしれません。 なぜネット書店を眺めていてもアイディアが湧かず、リアル書店だとアイディアが湧いてくるのか。 これは、両者の大きな違いは何か、ということを考えることが大切のように思うのですが、私が思うに (自分の勝手な解釈ですいません) 、リアル書店では、お店に入った瞬間から、自分が選択するしないに関わらず、 自分にとって未整理な (混沌とした) 情報が飛び込んでくるのに対し、ネット書店では、自分が選んだカテゴリー (例えば、大きなカテゴリーでは、人文系、ビジネス系、科学系、・・・) の情報ずつしか見ることができない、というところにあるのではないかと思います。 つまり、リアル書店では、一歩お店に入れば、 “自分にとって未整理な情報が自然に目に飛び込んでくる” のに対し、ネット書店では、“情報が自然に目に飛び込んでくるのではなく、一度振るいにかけられた (自分が選んだ) 情報を目で追いかけて見ることになる” ということが大きな違いであって、何か新しいアイディアを得ることにおいては、前者の “自分にとって未整理な情報が自然に目に飛び込んでくる” という環境 (空間) が大切なのではないかと思います。 人は混沌とした情報から組み合わせや関連付けを行なうプロセスを通してアイディアが浮かんでくるのだとすれば、 この点が、 「リアル書店だとアイディアが浮かびやすいけれど、 ネット書店だとなかなか浮かばない」 ことの理由の一つなのかなぁとも思うわけですが、新しいアイディアが浮かぶためには、日頃から様々なことに関心を持って情報を眺めることが大切なことは言うまでもありません。 関心を持って情報を眺めているからこそ、「これとあれを組み合わせるとどうなる? これって、面白くないかな?」などと考えを巡らせることができるわけで、 ただ漠然と情報を眺めていたのでは、 企画のヒントに成り得た情報さえも、目の前をただ素通りしてしまいます。 同じ情報やモノを眺めても、人によってそこから新たに掴むこと (発想) ができることが違うのは、その人の中にある引き出しの数と視点、様々な情報への関心の高さにあるのかもしれませんが、人が何か新しいアイディアを得るための場 (空間) として、リアル書店がネット書店よりも秀でているのだとすれば、逆にこの点を活かした工夫をすることで、これまでにないリアル書店のカタチを創ることができるのかもしれません。
2010.08.08
コメント(0)
-
編集者として、日々思うこと
編集者になったばかりの頃は、先輩や上司となる編集者が担当している書籍の編集を手伝うことになるわけですが、そうした経験を積んでいく中で、やがて、編集者として独り立ちする(自分の立てた企画の原稿が著者から入稿し、最後まで独りで編集作業を担当する)ときがやってきます。 一人の編集者が年間に刊行する書籍の数は、編集者としての経験年数や進行している企画の数などによっても異なりますが、 出版社によっては “最低でも一人で年間◯点は刊行すること” ということが言われているところもあると思います。もちろん、会社からノルマのように言われても、こればかりは相手があることですから、なかなか思うように運ばないわけで、だからこそ、著者に対する日々の原稿催促がとても大切になってきます。 ( 「来年は、この本とこの本を刊行しよう」 と、こちらが好き勝手に計画していても、著者を放っておいては、それは叶いません。) 私自身は、 編集者として独り立ちしてから、 平均すると常に5点くらいの編集作業が同時進行しています。 ただ、ここで言う編集作業は本の刊行予定日が既に決まっていて動いているものなので、 その他に、 著者が書き上げ途中の粗稿を読んでコメントして返すといったものまで含めると、それなりの点数が常に動いています。 そんなわけで、 (これは編集者としては当たり前のことですが) 編集作業をしながらも原稿催促を並行して行っているので、 “1冊刊行になると次の原稿が入稿する” という流れがずっと続いているような感じです。 (これから編集者になる皆さんも、こんな感じになるんだなぁということを頭に入れておいて頂ければと思います。) 正直言うと、日々このように数冊の本を並行して進めていて、あれもこれも読まなければならないという状況に陥ると、 「これは (この原稿や校正刷りは) ざっとだけ目を通せばいいかなぁ」 という “楽したい” という気持ちが起こってきてしまいます。 でもこれまで、私がその気持ちを何とか抑えてこれているのは、 「一度でも手を抜いたら、その時点で、編集者として終りである」 と心に強く思っているからです。 この気持ちが、楽な方に行きかけている自分を何とか引き戻して、支えているように思います。 こうした気持ちは、別に編集者に限らず、人が生きていく中で誰もが経験することだと思いますが、大変ながらも頑張って進めて、それが達成できたときには、その経験が次への糧になるものです。 ただ、ちょっと残念に思うのは、諺のように 「苦あれば楽あり」 とはならず、「苦過ぎれば、またその先に苦あり」 というのが、実際の編集者の仕事だったりすることです。 でも、だからこそ、編集者の仕事はやりがいがあって、面白いのかもしれません。
2010.07.31
コメント(0)
-
企業の商品 (広告) が現れる電子書籍の可能性
一時は時代を旋風し、街中の至る所で目にしたフリーペーパーも、企業広告の減少や読者離れなどによって、かなりの数が淘汰されてしまった感があります。 単に地元のイベント情報やお店の情報を掲載するのではなく、書店で売られている雑誌と同等レベルのフリーペーパーが登場した当時は、「これだけ読み応えがあって無料?」 と驚いたものですが、フリーを支えていたスポンサー企業の減少が、大きな痛手となっています。 ところで、将来、雑誌やフリーペーパーのように企業の商品広告が掲載された (商品にリンクした) 電子書籍というものが登場してくる可能性もあるかなぁと思っています (もしかしたら、私が把握していないだけで、すでにあるかもしれません) 。 皆さんもよく目にすると思いますが、出版社はこれまで、紙の本の場合には本の最後のページに自社広告 (既刊の本や新刊の情報) を掲載していたわけですが、他社の商品の広告を載せた例はなかったのではないかと思います (本のテーマそのものが、他社の商品を紹介するもの、というものはありますが) 。 しかし、電子書籍の特性を活かせば (ちょっと安易な例になりますが) 、小説の中で主人公が “〇〇駅前のカフェで一杯のコーヒーを飲む” といったシーンで、本文中の “コーヒー” をクリックすると、その広告が現れる (ホームページが現れる) といったものや、本の適当なページに、その本の読者層にマッチした商品の広告を入れるということも考えられます。 つまり、出版社側にとっては、“その本のターゲット (主要な読者層) にアピールしたいという商品を持つ企業に対して、広告掲載を促す” ということも可能ではないかと思っています。 紙の本の場合には、(重版の際に差し替えるということは可能であっても) 一度出版するとその後もずっとその形として残っていってしまうということや、著者が苦労して書き上げた作品が広告のオンパレードでは申し訳ない (作品が台無しになってしまう) 、ということもあります。 電子書籍でも作品の価値を大切にするということは大前提としてあるわけですが、“読者が作品を読んでいる間、常に端末を介してインターネットに繋がった環境にある” という特殊性を活かし、単に著者の作品を読むだけではなく、新しい読書のカタチを提案するということも考えられるのではないかと思っています。 もちろん、上のコーヒーの例ではないですが、本文中でリンクする語句の頻度が多くなると、読者が作品の内容に集中できなくなることも考えられますし、(仮に本のターゲットと商品のターゲットが同じだとしても) 自分の本に見知らぬ商品の広告が現れることに同意できない著者の方も多いと思いますから、こうした仕掛けをするためには著者への了解が必要なことは言うまでもありません。
2010.07.21
コメント(0)
-
最初は従来のスタイルや手法を真似ることから始めてみる
新人の編集者にとって、自分が初めて企画した本の原稿を著者から頂く瞬間ほど嬉しいものはないでしょう。 自分にもそうした経験があったわけですが、 (もちろん、いつまでも新人の頃の思い出に浸っているわけにはいきませんが)次第にその思い出も薄れてしまっていることを感じます。 出版社に入社し、 編集者になったばかりの頃というのは、 (至極当たり前のことですが) 自分が企画した本の原稿がないこともあって、先輩や上司の企画した本の編集作業を手伝うプロセスを通して、編集者としての仕事を一から学んでいくことになります。 そうして何冊かの編集作業を経験し、次第に独り立ちができるようになってきます。 ただそれまでは、常に上の人の指示に従って仕事を進めなくてはならないこともあって、一日も早く独り立ちしたいという先走る気持ちと、(まだまだ独りでは不安な面があるという) 編集者としての自分の力不足に悩む日々が続くこともあると思います (自分もそうでした)。 そうしたこともあって、自分の企画としての最初の1冊目には、“これまでになかったような何か新しいことをしてみたい” という思いが湧いてくることもあると思います。 でも、これまでのスタイルや手法を自ら経験する (真似る) ことなしに、新しい発想が生まれてくることはないと思います。 1. まずは、先人たち (先輩や上司、他の編集者) のスタイルや手法を真似てみる。 2. 一度自分の中で消化してから、それに自分なりの工夫を加えてみる。 3. その経験を踏まえて、さらに新しいアイディアを加えてみる。 ・・・ということを繰り返す中で、次第に編集者としての自分のスタイルも確立してくるのではないかと思います。最初から新しいことを試みたいという前向きな姿勢はとても良いことだと思いますが、 それにはこれまでのスタイルや手法を経験してみる (真似てみる) ことがとても大切だと思います。 多くの人に、そして、多くの場面で取り入れられてきたスタイルや手法というのは、それなりに洗練されているからです。 また、人は経験を積むほど知らず知らずのうちにそうした経験に縛られて、新しいことをしようという気持ちが薄れてしまうということが言われますが、この点は、自分も含め、ある程度の経験を積んだ人たちが注意しなければならない (そうならないように意識して努めなければならない) ことだと思っています。
2010.07.13
コメント(0)
-
情報を適切かつ的確に編集できる職人が求められる時代
一般に編集者と言えば、出版社や編集プロダクションに勤務する編集者、あるいは特定の出版社には属さないフリーの編集者がいます。 この中で、フリーの編集者の方を除くと、多くの編集者は会社に属しているわけで、言うまでもなく、編集者も会社員 (あるいは契約社員) ということになります。 私自身も出版社の一社員であるわけですが、個人的には、会社に就職したというよりも、編集者という “職” に “就いた” という意味での “就職” という意識を持っています。 もちろん、だからと言って、 組織の一員として自分に課せられた役割を軽く見ているということではありません。 ただ、編集者という職種は、 “職に就く” という意味合いが高いのではないか、という感じはしています。 ところで、 いま電子書籍をめぐる一つの流れとして、 印刷会社や出版社が中抜きされ、 書き手と (フリーの) 編集者が手を組んで、電子書籍の販売を請け負う会社と直接に契約を結ぶような形が作られ始めています。 ここでの編集者の役割は著者の原稿の内容を商品と言えるレベルに高めることにあって、従来の編集者の役割と大きく異なるというわけではありません。 しかし今後は、従来の編集者の仕事をこなせる力を持ちながら、電子書籍の特性をよく理解している編集者は、これまでのフリーの編集者とはまた少し違った、“電子書籍の編集者” として独立するという新しいスタイルも考えられるのかもしれません。 いずれにしても、これからの時代は、 “与えられた情報を、 アウトプットするスタイルに合わせて適切かつ的確に編集できる職人” がますます求められてくるのではないかと思っています。
2010.07.07
コメント(0)
-
本のタイトルも時代を映す鏡
今週は、いま進めている本のうち、2冊の書名を決めなくてはいけない (最終決定ということではなく、候補を絞り込む) ということで、アレコレと頭を悩ませています。 本のタイトル (書名) について考えるときには、その本の内容のことはもちろんですが、どんな人たちが、どんなシーンで (どんなふうに) 読むだろうかと、読者の人たちが本を手にして読んでいる様子まで想像したりします。 編集者たちがアレコレと考えて付けてきた1冊1冊のタイトルを過去に遡って眺めてみると、本のタイトルも時代を映す鏡の一つであることに気が付きます。 例えば、 いま刊行が相次いでいる電子書籍関連の本のタイトルをこれから数年後に眺めてみると、 「この年に電子書籍が人々の間に広がり始めたんだなぁ~」 ということが掴めるように思います。 つまり、過去に刊行された本のタイトルを各年代ごとでスライスしてみると、そこから、その時代に旬であったテーマ (その時代のキーワード) が見えてくるように思います。 また、本のタイトルの付け方の変化 (いまとなっては既に当たり前のようになっていますが、タイトルが文章のように長いものが流行り始めた時代など) も見えてきたり ・・・。 これとは少し異なる視点かもしれませんが、皆さんも、自分の本棚や床に積み重なった本のタイトルを眺めてみると、その頃に自分が関心を持っていたことや、「そう言えば、この頃はこんなことがテレビや新聞で話題になっていたなぁ~」 なんてことを思い出すのではないかと思います。 編集者にとっては、過去に刊行された本のタイトルは、まるで宝箱のようなものです。 うまい付け方を見つけて、 その言葉の使い方に学ばされることもありますし、 逆に、 「これはこうした方がよかったのでは?」 なんて感じに、自分なりの考えを引き出すきっかけにもなったりします。 「時代を映す鏡」 と呼ばれるものは他にもいろいろとありますが、本のタイトルもその一つと言えるのではないかと思います。
2010.06.30
コメント(0)
-
「ワンソース・マルチユース」 というメガネ
昨日は仕事の後、 久しぶりに (とは言っても、 まだ修了して3ヶ月しか経っていないのですが) 大学院時代の友人と再会し、とても楽しい時間を過ごすことができました。 私が編集者との2足の草鞋を履いていた大学院での2年間で学びたかったことの一つは、ワンソース・マルチユースの考え方や手法でした。 また、当時はiPadなるものが登場するとは思ってもいませんでしたが、それ以前から電子書籍端末がいくつか出てきていたことで、自分なりにこうした分野への関心が高まっていたことや、本とICT (Information and Communication Technology) をうまく融合できないかなぁという漠然とした思いもありました。 これまで多くの出版社は、 印刷用に組版した最終データ (ワンソース) を、 紙の本へのアウトプットだけに用いてきました。 でもこれからは紙の本だけではなく、それを例えば電子書籍を刊行するためにも利用するという、マルチユースの考え方がとても大切な時代になったと思います。 iPadやKindleなどの電子書籍端末の登場によって、電子書籍が急速に広まってくることは間違いないと思いますし、紙の本は作らず、最初から電子書籍として刊行するということも当然のように広まってくると思います。 でも、こうした時代になったことを、自分たち編集者 (出版社) はピンチになったと捉えるのではなく、アイディアと工夫次第で何か新しいことができる可能性を秘めた時代が来たと考えるべきではないかと思っています。 例えばワンソース・マルチユースの考え方では、上とは逆の発想で、最初に電子書籍として刊行し、その動向や読者の評価次第では、その組版データを紙の本へのアウトプットに展開するということも、自然な流れの一つです。 確かに、電子書籍があるのに (それよりも高い定価設定になるであろう) 紙の本を買う人がいるかどうかということはありますが、この点については相乗効果で成功した例も出てきています。(もちろん、今後もすべてうまくいくというほど単純ではないと思っています。) また、ICTを活用して、同じ本 (電子書籍) を購入した人たち(読者)を端末を介してネットワーク化し、そこに作られた新しいコミュニティの中で (例えば、その本の内容をKeyとする) 別のストーリーを展開する、ということも考えられます。 こうしたことは一つの例に過ぎないのですが、 これまでの “凝り固まった” 自分に 「ワンソース・マルチユース」 というメガネを一つ掛けてみるだけでも、何か新しい可能性を生み出す小さな種が見えてくるのではないかと思っています。
2010.06.23
コメント(0)
-
いま、興味深く思っていること
現在、 iPadの解説書や活用ガイドがいろいろと出版されています。 楽天ブックスにも iPad特集 のコーナーが設けられたようです。 新しい情報ツールやアプリケーションが発売されると、それをテーマに特集を組んだ雑誌や書籍が発売されるのは出版界では常なので、特に驚くことではありません。 自分が興味深く思っているのは、 それらが皆、 電子書籍ではなく紙の書籍や雑誌であるということです。 iPadは電子書籍や電子雑誌が読めるということで、iPadの解説書や活用ガイドも電子書籍で、というのが自然だと考えます。 でも、現状は ・・・。 まだiPadを持っていない人をターゲットにした内容のものであったり、iPadで読めるように電子書籍化するのが間に合わなかったというのも理由として考えられます。 そしてもう一つは、iPadで解説書や活用ガイドのページを開いて読み始めるとそれ自身で画面がふさがってしまい、その解説に対応するiPadの操作がやりにくくなる、ということもあるかもしれません。 “自分自身の機能や操作法についての解説は、自分自身に内在していない方が使いやすい” ということがあれば、今後新しい電子書籍端末が出てきても、その解説書や活用ガイドは紙の本として生き残ることができるかもしれません。 もちろん、iPadや他の電子書籍端末を使って、新しく買った端末の解説を読むということは起こりうるのですが ・・・。 ほんの些細なことかもしれないのですが、私自身は、いまの現象をとても興味深く思っています。
2010.06.17
コメント(0)
-
また一つ、街の書店が ・・・
先週は土日とも、夏に刊行予定の本の校正作業で自宅に缶詰状態。 あっという間の週明けとなってしまいました。 書籍の編集者は (特に編集・校正作業に限っては) 独りでコツコツと進めていく部分が多いので、自分がやらない限りは仕事が全く前に進まないということで、私自身はこういう週末を過ごすことが時々あります。 日曜日の夕方、 さすがに このまま月曜日を迎えるのはちょっと寂しすぎると思い、 散歩がてら、しばらく通ってなかった近所の書店へと足を運んだのですが、哀しいかな、お店のシャッターには閉店の貼り紙がしてありました。 行くといつも笑顔で迎えてくれる優しいお爺さんが切り盛りしていた小さな書店だったのですが、そのお爺さんの人柄もあって、お店全体がいつも ほんわか とした雰囲気に包まれた、とてもアットホームなところでした。 まさに “街の小さな本屋さん” といった表現が似合うお店でした。 とても残念です。 昨今の読書離れだけでなく、ネット書店や大型書店などの影響もあって、昔ながらの街の小さな書店は大変厳しい状況を迎えていることはよく知られていることではありますが、自分にとって身近な存在の書店がこうしてなくなってしまうことで、このことを改めて痛感させられました。 ちょっと悲しい気持ちで帰宅し、昨今の厳しい状況の中でも元気に頑張っている書店はどんなところだろうと調べていると、 本屋の歩き方 というサイトに出会いました。 すでにご存知の方も多いかもしれませんが、キャッチフレーズにもあるように、本屋さんの持つ魅力やそこでの楽しみ方を再発見させてくれるサイトなので、ぜひ覗いてみて下さい (「1000人に聞いた気分別オススメ本」 のコーナーは面白いですよ)。 こうしたサイトをきっかけに街の書店が活性化してくれればと思いますし、一編集者としては、読者が書店で買いたくなるような魅力的な本を少しでも多く生み出すことができればと思う次第です。
2010.06.14
コメント(0)
全410件 (410件中 1-50件目)
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年52号感想その…
- (2025-11-26 13:50:15)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 今日の空が一番好き、とまだ言えない…
- (2025-11-28 19:54:11)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2026年 1月号』 ガメ…
- (2025-11-26 21:00:05)
-