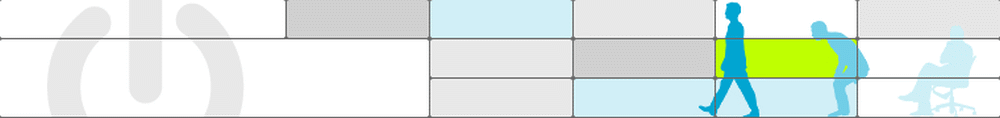全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
引っ越しました
メインブログを引っ越しました⇒ビジネス・キャリア徒然草こちらでは、書評やもう少し日常的なことを書こうかと思っています。是非、引越し先も見てください。
2008.05.16
コメント(0)
-
風邪をひきました…
提案がひと段落したと思ったら、本格的に風邪をひいてしまいました…。そんな訳で、日記のペースが落ちます…すいません。
2005.02.02
コメント(4)
-
売ると言うこと ~営業の真理とは~
最近、サービスラインにないような要望がお客様から出されることが多くなり、そのうちのある領域においては、事業企画として私も提案活動を行うようになりました。要望内容自体は、かなりバックリとしたもので、やりたいことが列挙されているものです。それを、現状のビジネスモデルに落とし込み、要望をかなえるために足りないものを探してきて、互いに利となるように組み合わせるようなものです。また、そんなことをしながらも、あるサービスのユーザーサポートや営業組織の支援も同時に行っており(どちらかというとこちらの仕組みづくりがメインのはずですが…)、営業サイドからの相談を受ける機会も増えてきました。そんな折り、社内で顧客満足度向上のために「顧客満足をあげるには」というアンケートが複数の部署に出されるということがありました。たまたま、私の部署では、私に質問が投げかけられました。その質問に対して、私は「お客様の課題・問題を解決すること」が顧客満足を高める最良の方法だと答えました。よく勘違いされるのですが、お客様はその「商品」自体を買おうと思っている訳ではありません。例えば、自分があるAV機器を買う場合でも、その商品を買いたい、という人は稀で、○○という機能と△△という機能があるHD搭載DVDレコーダーが欲しい、というように、自らが欲しい機能や、HD搭載DVDプレイヤーを買うことで解決できる現状の不満(何度も簡単に録画して消去できる等)に対して対価を払います。それは、B2Bでも同じことで、お客様が抱えている課題、例えば、売れる商品作りや広告効果の測定、効果的なマーケティング手法の選別、迫力のある資料作りなど、が根底にあり、サービスを利用しに来る訳です。ですから、サービスを売るためには、それらの課題・問題を解決するだけの全体像を示す必要があり、サービス単体をとりあえず売る、という考え方では、相当タイミングが良いか、商品力が高い(他にない、価格が劇的に安いなど)以外には売れなくなってしまいます。ただ、同時に営業は、自社の商品・サービスを売らなければいけない、という責務も負っています。これは、一見すると相反するように見えるのですが、逆にキッチリとお客様の課題・問題を理解していれば、お客様の言ったとおりではなく、自社のサービスを利用することで課題を解決する方向での提案が可能です(勿論、足りない部分は、他社のリソースも組み合わせます)。この組み合わせを行うのは、中でも難しいポイントですが、各商品をよく理解していて、尚且つ、お客様の課題を複数の視点で切り分けることができれば、Aの課題にはaのサービス、Bの課題にはbのサービス、Cの課題には他社のc’サービスを適用し、そのコントロールを行う、と言ったように、それぞれの課題に適正のあるサービスをぶつける形で、提案が可能となります。つまるところ、営業の真理とは、お客様の課題・問題を可能な限り正確に把握し、同時に、自社のサービスに落とし込んで、抜けた部分を別の方法で支える(あるいはこの部分は出来ないと正直に伝える)ことで、お客様の課題・問題を解決する、ことであり、単なる商品・サービス売りではないということなのです。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.31
コメント(0)
-
リスクマネジメント ~リスクが低いというのはどういうことか~
近年、事業環境の変化が激しくなり、ネットワークの進展で情報を閉じ込めておくことが難しくなったため、リスクをどうコントロールするか、ということで、リスクマネジメントが声高に叫ばれるようになりました。しかし、リスクマネジメントの意味を履き違えていると思しき使われ方がなされている場合も、度々見かけます。そこで、実際にビジネスや日常で行われているリスクマネジメントを参考に、リスクマネジメントとはどういうことかに触れていきたいと思います。このような例を出すのが適切かわかりませんが、例えば貴方が彼氏彼女を探しているとしましょう。ここで、出会うための選択肢を二つ提示されます。一つは、友人の紹介、もう一つは、同僚に誘われた合コン。さて、どちらがリスクが高いでしょうか?ここで、友人も同僚も好みは似通っているとします。そして、二人とも「今回の人はなかなか良いよ」と言っているとします。さて、貴方はどちらがリスクが高いと思いますか?答えは、紹介の方がリスクが高い、です。何となくわかった人も多いかと思います。では、その理由は何か。友人の紹介だと、そこに行くとその人しかいません。つまり、もう連れて来られる人だけで全てが決まってしまいます。選択肢はありません。ところが、合コンの場合、同僚の知り合いが好みでなくとも、他にも候補が数名いる訳です。勿論、その全員が好みではない場合もあるかもしれません。友人に賭けるという方法もあります。しかし、一人よりは三名、四名の方が、好みの人がいる可能性は高くなります。次に、リスクに馴染みのある金融の場合で書いてみましょう。ハイリスク・ハイリターンや、ローリスク・ローリターン、などの言葉がありますが、意味は読んだ通りの内容で、リターンが高い可能性があるものはリスクが高く、リターンが低くなるものはリスクも低い、ということです。そして、大抵の場合、ある金額を預けた際に、どの程度返ってくる可能性があるか、あるいは返ってこなくなる可能性があるか、によってリスクとリターンが決まります。多くの利益を得ようとすると、周りの人と同じレベルではいけないので、例えば、リターンと元金が約束されている国債より変動幅の大きい、株式に投資したり、企業再生や債権のバルクセールに乗り出したりすることになります。しかし、そうなると、元本の保証は一切ありません。まとめると、国債はかなり少ないにしても元本+利息は確実に返ってきますが、ハイリスクな方法の場合、大きく増えることもあれば、大きく減ることもある訳です。つまるところ、リスクが低い場合、結果が一定化している(良い方にも悪い方にも)、リスクが高い場合、結果の振れ幅が大きい(良い方にも悪い方にも)ということなのです。では、実際に仕事において、どういうリスクマネジメントがあるのでしょうか。実は、案外身近です。例えば、確実にやっていかなければならない仕事を他の会社に依頼するとき、どういう会社を選ぶのか、というと、100の仕事を要求水準とすると、「100の仕事をする確率が80%、110の出来が10%、90の出来が10%」の会社と、「100の仕事をする確率が60%、150の出来が20%、50の出来が20%」の会社とどちらに頼むかと言えば、まず前者の会社に頼みます。それはなぜか。確率論的に考えると、前者:100×80%+110×10%+90×10%=100後者:100×60%+150×20%+50×20%=100のように、同じ100の仕事をしてくれます。ところが、20%の確率で1.5倍の出来になる可能性は後者にはあり、前者には全くない訳ですが、確実に進めるのが目的であるとすれば、50の出来が20%もあるとすると、前者と比べ安定性に欠けるところが強く、安心して頼むことができません。ですから、今回の場合、前者の方がリスクが低いと言えるのです。但し、これは仕事の内容が確実にやっていかなければならない仕事だからです。もっと、アイデアベースで150や200の仕事を要求される内容であれば、実は後者に頼まざるを得ません。なぜなら、前者では150の仕事は出来ないからです。リスクがあろうとも、目的が150であれば、150できる20%に賭けるしかないのです。このように、内容によってリスクの高低を考えながら選択していくことを「リスクマネジメント」と呼ぶのであり、単にリスクを避けることではないのです。最後に、これらは例えば、転職や新卒就職にも当てはまります。当たり外れを嫌がる企業・仕事内容であれば、確実性の高い人・見せ方を好みますし、その逆も言える訳です。上手くリスクをマネジメントして、より良い成果を得たいものですね。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.29
コメント(3)
-
かなりサボってしまいました…
実は、今日(28日)、プレゼンがあります。会社の方向性に大きな影響を与えうる内容です。先週終わり頃から、それ絡みで色々な人と会って、資料も幾つも作成してきました。そんな訳で、そちらにもう少し注力しますので、もうしばらくの間、日記が不定期になります。すいません。それでは、頑張ってきます!
2005.01.28
コメント(2)
-
会社の辞め方7:喧嘩しないで辞める方法って?
会社の辞め方シリーズ、第7弾。今回は、「喧嘩しないで辞める方法ってないのかな?」について。発つ鳥跡を濁さず、ではないですが、辞めるときは皆に惜しまれて、とまではいかなくとも、誰とも揉めずに円満退職したいものです。勿論、私もそうでした。そして、揉めることもなく、ですが、求めることは求めて辞めました。ただ、幾つか譲るべきところは譲ったとも思います。同時に、辞める時に必要以上に揉めることを恐れて、結果的に最後は、裏切った、などと言われ、揉めてしまう人も私の周りにはいました。そう考えると、やはり、揉めないためのコツ、というものがあるように思えます。そこで、それ程経験は多くないですが、幾つか感じたポイントを挙げてみます。まず、辞める前に状況を把握すること。例えば、現在の仕事はどの程度で区切りがつきそうか、区切りで抜ければ影響は少なくで済みそうか、済まないなら何がネックになっているのか、等です。これは、今後のスケジュールや、誰に伝えていくか、というような関係者の整理には必須と言えます。ここを飛ばしてしまうと、言ってはいけないタイミングで言ってしまったり、言う順序を間違ってお怒りを買ったり、チーム全員から総スカンをくらったり、と不要な苦労をしてしまう確率が、一挙に高くなります。次に、状況を把握したら、何が最も周りに迷惑をかけるのか、怒らせるのか、逆にそれ程重要視されないところは何か、についてざっと考えます。例えば、辞めるタイミングであったり、人間関係であったり、社内力学であったりします。それを組み合わせて、例えば転職するなら、それを軸に入社の時期を交渉したりすれば良い訳です。そして、情報の開示タイミングと相手。退職する際には、大抵何らかの引継ぎが発生します。引継ぎは、いきなりくるとなかなか大変です。ですから、引継ぎする相手かその上司など、仲の良い人に相談を持ち掛けます。勿論、口の軽い人は避けます。変なところから辞表を出す相手に伝わってしまうと、揉めなくていいものまで揉めてしまう場合があります。そうすることで、どのようにすれば引継ぎが負荷なくできるか一緒に検討したり、新たに任される仕事を別の人を中心にすることもできます。これが上手くいくと、引継ぎ関連で揉めることは、ほとんどなくなるでしょう。最後に、自分の決めたことは曲げないこと。これは、決めたら譲らない、のではなく、○月に辞めたいと言っておきながら、上司に言われて前言撤回とか、そこまで行かずとも、それから数ヶ月も経って△月まで退職月を延ばすなど、中途半端なことはしない、ということです。どれだけ色々なことを言われても、自分の信念をキチンと伝えていけば、不満に思う人も、最後には賛同はして貰えないにしても、どれだけ真剣なのかは理解して貰え、それ以降は少なくとも普通に付き合っていけます。案外揉める人は、知らないうちに、あるいは気を遣いすぎて、自分で種を蒔いてしまっていることが多いように思います。意外と世間は狭いもの。しっかりと転職する理由を見極め、不要なイザコザを起こさぬようにしたいものですね。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.27
コメント(0)
-
ちょっと良いよね ~SONY、復活の狼煙か~
数ヶ月前、SONYのイヤホンの広告を地下鉄で見ました。「お、良いね、これ」私は、それを見たとき、そう思い、ふとウォークマン全盛当時のSONYを思い出しました。その当時のSONYを表現すると、「ちょっと良いよね」という言葉があてはまるのではないでしょうか。この「ちょっと」というのが味噌で、もの凄い技術革新、というよりは、ちょっとした一工夫でクールに見える、と言えば良いのでしょうか。そのイヤホンは、既に当たり前になりましたが、耳に挟むタイプのもので、収納時にコードが中にしまえる、というものでした。ちょうどイヤホンを探していた私は、しまった後の姿の良さに何となく惚れました。聴く時だけでなく、しまうときもクールでありたい、というちょっとした工夫で違う価値を出す。まさに、SONYの真骨頂だと思います。正直、それまでのSONYには疑問を感じていました。実際、昔ほど、欲しいと思う商品はありませんでしたし、買いませんでした。特に、高級品シリーズ「QUALIA」。今は、方針を若干転換し、価格を下げて、各商品ラインの高級版との位置付けにしていますが、昔は、完全手作りのようなもので目が飛び出るような価格付けをし、本当に趣味な人向けにのみ販売していました。その時のコンセプトは、家電・AV機器業界におけるF1カー。自動車業界は、F1という最新技術の実験場があり、それによって進歩しているから、家電・AV機器業界でも同じように、F1に変わる実験場を作ろう、ということだったのです。しかし、現実には大きな隔たりがありました。それは、一体どういう隔たりでしょうか。これは簡単で、貴方はF1カーを買って乗りますか? ということです。SONYは、実験場と言いつつ、それを販売するという方法を取りました。ある意味、実験場であれば、F1であったり、自動車ショーに出てくるコンセプトカーのようなスタンスであるはずが、超高級商品として販売する、という選択肢をとってしまったのです。そのため、新たなコンセプトを出す、というよりも、単に高性能であるとか素材が珍しい通常製品が多数出ただけに終わり、F1カーとは違った方向性で進み、最上級ラインでもなくコンセプト品でもない、中途半端な形でのリリースが続いたのです。マイバッハではないですが、専用のショップのみで買えるような展開を行いましたが、あくまで販売面でのテコ入れのみで、最初のコンセプト、F1カーとしての技術実験場としての役割は果たせず仕舞いであったと思います。そんな中、ちょっとした工夫・デザインでSONYらしさを出す、それを技術が支える、という発想が失われていったように感じます。それが、SONYが以前のような魅力を出せなくなった原因だと思っています。結果的に、社員が欲しいと思わない商品群を市場に送り出してしまったのです。SONYはその後、「QUALIA」を改めて、各商品の最上級ラインとして再設定し直しました。たぶん、全体の戦略が変わっていった一環だったと思いますが、それから地下鉄で見た広告の商品のように、ちょっとした工夫でクールさを出す、という商品作りがやや復活してきたように見えます。私は、この「QUALIA」の位置付けの再設定は、小さく見えて、非常に大きな良い判断であったと思います。後は、それをキッチリ遂行していけるかどうかでしょう。PSPは想像以上の売上を得られたと聞きます。それを軸にして生活を変える、というようなことを商品コンセプトに置くことなく、商品は商品でSONYらしさを追い求め、それとは別に、コンセプトを打ち出す実験をし続け、例えば、オール電化のように、一定まで到達した瞬間に、一気に市場へ送り出す。そんな商品づくりを続けていけば、また欲しくなる商品を産み出す企業へ復活できると信じています。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.24
コメント(3)
-
お客様は神様です ~その言葉が示す真実とは~
お客様は神様です。このフレーズ、ざっくり言うと、お客様が一番偉い、という意味ですが、最近は、NOと言える営業、とか、客を選べ、という風潮のせいか、あまり聞かれなくなりました。確かに、お客様のいうことをそのまま聞いて帰ってくる「伝書鳩営業」を是とすることは、今のビジネス環境において許されることではなく、お客様もそのようなことを望んでいる訳ではないでしょう。しかし、私はこの言葉は今も生き続けていると考えます。それはなぜか。そもそも、言葉の捉え方が間違っているのではないかと思います。お客様は神様です、ではなく、お客様の要望は神の言葉です、と言い換えると良いのかもしれません。なぜそう思うのか。お客様の要望を叶えるべく新しいサービス・事業を構築する。それが、企業が成長する上での絶対条件だと考えるからです。昨年、私はあるベンチャー企業(と言っても既に社員は150名近くですが)に転職しましたが、現在の売り上げの大半を占めるのは、創業時の事業ではなく、お客様に言われて、その事業を元に発展させた事業です。そして、私が今、関わりを深めている新規事業も、お客様からの要望を元に、現在の事業を活用して企画しているもので、もし上手くいけば、将来的に会社を支える柱の一本となりうるものです。そんな中、ふと、どのように事業が企画立案されるのだろう、と思い返したとき、確かに、どのように事業化すれば利益を産み出し発展させるモデルとなるか、その進め方をどうするかは、企画担当を中心に自社の多くの人間が関係して作り上げるのですが、その本質である事業のタネは、やはりお客様が持っている、少なくとも最も大切なヒントはお客様の要望の中にあると言えるのではないかと、改めて感じました(勿論、何が要望の本質かを見抜く必要がありますが)。お客様は神様です。もう一度、その言葉の真意を胸に入れて、お客様の言葉に耳を傾けたいと思います。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.23
コメント(2)
-
会社の辞め方6:ボーナスとか退職金って?
会社の辞め方シリーズ、第6弾。今回は、「ボーナスとか退職金ってどうだろう?」について。いざ辞めようか、と思うと気になってくるのが「お金」転職時期が、年明けや夏頃に集中するのも、ボーナスの影響だとか。そこで、今回は簡単に退職に関わるお金について触れてみます。退職すると、退職金や企業年金基金積立金(継続しない場合)など、一時収入があります。しかし、逆に、住民税の5月支払いまでの残分を、一括請求されるなど、勤続年数が少ない場合は、案外残りません。人によっては、マイナスで終わることもあるとか…怖いものです。ボーナスや退職金が、具体的にどの程度支払われるかについては、各社の規定によります。例えば、前職は素晴らしいことに、ボーナスも支給日が来ていない分についても月割りで支払われましたし、退職金も勤続年数は月割りで出ました。勿論、ボーナスは支給日が来なければ出ない会社や、勤続年数はあくまで経過年数であるという会社もあります。ですから、辞める前に、必ず人事規定を熟読し、どこで辞めれば一番良いかを検討してから、転職先と入社時期について相談しましょう。大抵の場合、月の初めの入社の方が都合が良い会社が多いので、後は有給休暇の残日数と相談しながら、何月入社にするかを決めましょう。ここで、一つ注意すべき点は、ボーナスについては支給されてから退職届を出す方が安全、ということです。前職の場合は、基本給+評価給、でボーナスが組まれており、評価期間途中で辞めると、評価給分が支給されない制度になっていたので、それ以外の判断はあまりないのですが、結構多くの会社で、退職者には最低の評価をつけて、ボーナスを減額することが多いということです。お金のことばかりとやかく言うのは何ですが、退職を理由に、色々と貰える金額が減るのは、ちょっと物悲しいものです。やはり給与=評価ですから、貰えるものは貰っておきましょう。細かな話は、転職紹介会社のサイトに載っていますから、ここまでにしますが、会社側が何と言おうとも、なるべく自分に有利に動いて、次の仕事のリスク回避に備えましょう。最悪、転職先がいきなり潰れて内定取りやめ、という話もあります。前にも書いたように、退職を取りやめると、その後、相当辛い環境に置かれます。リスク管理という意味でも、顔は笑顔でも、心を鬼にして、貰えるものは貰い、使えるものは使っておきましょう。働いている人に与えられた権利なので、行使しないで、という人はいても、行使したことで恨む人は少ないものです。そんなことで気を遣うより、しっかりと引継ぎをして、他の人の業務がボロボロになるのを防いであげましょう。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.22
コメント(3)
-
語りかける販売力 ~百貨店はなぜブランドとデパ地下に走るのか2~
前回、百貨店は競合しない領域へと、自らのブランドを守る方向へと進んでいく、と書きました。では、なぜそうせざるをえなかったのか。それは、リアル店舗がネット店舗に比して、不利な面があるからです。今までは、ものが手に取って見れない、というネットの弱みがクローズアップされてきました。例えば、服などは、実際に着てみないとわからない、というところもあり、まだまだリアル店舗が強いところではあります。しかし、ファブリックであったり、鞄などの小物であったり、ある程度一般化しているものについては、リアルである必要性は薄れています。そうなってくると、リアル店舗の有利さは薄れて、ネット店舗の強みが活きてきます。それは、何か。それは、ダイレクトマーケティングというように、データが取りやすく分析しやすい、ということや、メールという安価に消費者に到達する手段、も確かにそうですが、それが本質ではないと思っています。ネット店舗の強み。それは、このBlogのような形態と同じく、「読ませる」媒体を用いている点です。ちょっと凝った商品、例えば、製法にこだわりがあったり、素材にこだわりがあったりした時に、リアル店舗に説明の書いたボードと商品を並べて置いてみましょう。違和感、ないですか?個人的には、何か押し付けがましいというか、説明自体の信憑性が失われてしまう感じがします。ところが、ネット店舗では逆で、商品に関する説明が詳しければ詳しいほど、信憑性が上がる感じを受けます。そうなると、ついつい書かれている説明文に目がいってしまいます。それは、そもそもネットが文章を読ませる媒体であるからで、見る側も読むのが普通だと思っている。だからこそ、リアル店舗ではしきれない説明も、ネット店舗では自然とできるのです。これこそ、ネット店舗の「語りかける販売力」です。私の知り合いが経営している店舗でも、メッセージを伝えるのに苦労をしています。ダイレクトに文章を書いたりしているのですが、やはりそれではファッション性に欠ける感じを受けます。ネット店舗では、普通にできることが、リアル店舗では難しいのです。そして、ネット店舗で商品説明を読むと、商品の価値が何となくわかります。そうなると、商品価値を担保しているブランドが、それほどキーではなくなってきます。見えないブランド価値が薄れてくると、同じレベルの品であれば、例えば、製版直結や卸や代理店抜きの方が安い訳ですから、ネット店舗が一気に勝てる状況になってくるのです。重要なのは、説明し、読み手を引き込んで、同じレベルの品、であると思わせること。これが、語りかける販売力、の真の効果と言えるでしょう。単なるポップではない、語りかける販売力。これにより、競合を排斥し、長期的な優良顧客を手にすることができるのです。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.18
コメント(5)
-
会社の辞め方5:次の会社は本当に良いところ?
会社の辞め方シリーズ、第5弾。今回は、「次の会社は本当に良いところなのかな?」について。いざ転職! となると、やっぱり気になるのは、転職先が良い所なのかどうか。実は、これが一番難しかったりします。おいおい、という感じですが、難しい理由を書くと、良いかどうかの判断基準が、人それぞれ、だからなのです。ですから、全般論と言われると難しいのです。そんな訳ですので、まずは、どういうところに不満があって転職するのか、転職先で何をしたいのか、をまずハッキリさせて、転職に臨まれることを強くお薦めします。つまり、そこで上がった項目が、転職先として譲ってはいけない点となりますので、その点だけを見ていれば、少なくとも大きな失敗はしないでしょう。ただ、個人的な経験から敢えて言わせて貰うと、最も重要なのは「人」、特に自らの上司になる人と、更にその上司。その程度まで押さえておけば、大丈夫だと断言できます。その人と自分が、仕事に対する考え方を含めて合うかどうか。これがずれていると、働き始めてから、必ずと言って良いほど、不遇な環境に置かれていくことは請け合いです。なぜなら、転職者の場合、その多くは、その部署の要員として雇われ、しばらくはその部署での働きを見られて評価されるからです。つまり、合ってないから別の部署で様子を見てみるか、となるにも、評価がイマイチではそうなりません。それに、しばらくはその部署に縛られることになります。これは、会社にとっても、自分にとっても、不幸な環境でしかありません。たまたまかもしれませんが、私はこの方法で、少なくとも上手くはいっていると自分で感じています。仕事は、自分次第なので、自分で上手くいっていると思えれば、ある意味、成功したと言って良いかと思います。会社も人の集合体です。会社を選ぶ尺度として、やはり身近な人をきっちり見て判断することが、結果的に力を発揮できる環境を得られるキーであると思います。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.17
コメント(0)
-
震災から10年 ~災害対応から学ぶリスク管理~
1995年1月17日早朝、私はベッドの上で突然目を覚ましました。「こんな時間に目が覚めるなんて…勿体ないわ、はよ寝よ」そう思って、寒さに少し震えながら布団を被りなおしたのも束の間、ゴーっという地鳴りのような音がしばらく聞こえた後、何がなんだかわからない揺れに襲われました。幸いなことに、被災地の端で被害はそれほどではなかったのですが、中高を神戸で過ごした身としては、いてもたってもいられず、バイクに救援物資を積んで、西へと向かったことを思い出します。そこで、国の対応の遅さや、マスコミの横柄さに、何とも言えない怒りを覚えた記憶があります。あれから10年が経ちました。震災を教訓に、災害に対する対応力が徐々にですが上がってきているように思います。そこで得られた災害に対応する基本は、「情報を収集」し「対策を決定・決断」し「素早く実行」に移す、という三原則でした。そして、その抵抗勢力となったのが、体裁ぶる風潮であったと聞きます。たまたまですが、先日、私の犯したミスにより、提携先企業の営業マンと共に、ある顧客企業に謝罪にいく機会がありました。その際、謝罪と経緯説明の場として、簡単な場を持っていただけたのですが、その場で「今後、問題が起こらないような対策を、両社の立場で出して下さい」との要望を受けました。私は、問題が起こった理由を詳細に分析し、具体策をそれぞれに当てはめ、更に、対策が取りにくい提携先企業の分の対策まで考えて、提携先に渡しました。提携先が頭に立っていた案件でしたので、私の企業ではなく提携先が出す必要があったからです。そこで、提携先は必要以上に体裁にこだわり、幾つかの要望を提示してきました。私は、できることとできないことを分けて、できることについては対策をうつことを約束し、できないことについては「嘘はつけない」と突っぱねました。何故なら、顧客企業は、具体的にできることを要望していたのであり、うわべの話を聞きたいと思っていないと感じていたからです。提携先は、その後、私に提出前に確認を取る、との約束を反故にした上に、提携先の対策を省き、更に具体策をオブラートに包んだ表現に変えて、まさしく体裁にこだわった文章にして、顧客企業に提出してしまいました。案の定、顧客企業からは、手直しした部分について責められ、提携先は対応に追われる始末。情報を集めてみると、元々、そのような体裁にのみこだわる対応に、顧客企業は嫌気がさしていたらしく、この期とばかりに指摘をしたようでした。結局、ビジネスにおいても、体裁にこだわることなく、正しい情報の元に、具体的な策を決定し、素早く実行に移せる、ということを示すことが、顧客からの信頼を得られる方法であり、リスクをマネジメントしていく上では、忘れてはならないことだと、思い返した次第です。偉い人を連れて行くことだけがキーではありません。問題の本質を素早く把握し、解決策を提示して、確実に実行する。そして、それを的確に文書化する。情報は隠してもいつかばれます。正直に誠心誠意あたることが、解決への糸口であると確信します。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.16
コメント(0)
-
会社の辞め方4:自分が辞めて職場は大丈夫?
会社の辞め方シリーズ、第4弾。今回は、「自分が辞めて職場は大丈夫かな?」について。辞めるか辞めまいか迷う理由の代表格の一つ。本当に自分が辞めて周りに迷惑がかからないか、と心配する人は多いはず。私の経験では、大きな企業に勤めている人に多いようです。答えとしては、2つ。企業は組織なので代わりの人が必ず現れるのと、迷惑は必ずかかる、ということです。私も、転職経験があるのに加え、辞めた人の引継ぎをしたこともあるので、両者の立場がわかりますが、引継ぎしなければいけない側としては、幾ら上手くやって貰っても、仕事が増えたり、引継ぎに時間を取られたり、引継ぎしきれない事があり後で予想外の苦労をしたりと、必ずと言っていい程、誰かには迷惑がかかります。しかし、同時に企業は必要な業務であれば、何とかカバーします。今の会社でも、これはあまり褒められたことではないですが、自分しか分からない仕事がありますが、たぶん、必要と考えるなら、何が何でも引継ぎをすると思います。答えになっていないのかもしれませんが、結局のところ、仕方ないとして自らの道を歩むのか、周りに気兼ねして辞めないのか、のどちらかです。これは、自分の意思次第というところかもしれません。大抵において、会社が自分に期待している以上に、自分が会社に依存してしまっています。引継ぎを前提にして、本当にこの仕事は自分しかできないのか、よく考えてみましょう。そんな理由で、自分の道を閉ざすことは、ある意味、時間を不必要に費やしてしまっていることになります。ただ、絶対やってはいけないことがあります。それは、一旦辞めると言ったら、それを翻さないこと。大抵の企業は、辞めると言った人を引き止めます。しかし、一度口にした事実は残り、そういう目でずっと見られることになります。そんな環境で働くのは、お世辞にも良いとは言えません。辞めると言ったら、辞める。これは非常に重要です。だからこそ、不用意に辞めるのではなく、最低限、次の道を決めてから辞めるようにしましょう。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.15
コメント(0)
-
情報発信社会における優位性の確保 ~百貨店はなぜブランドとデパ地下に走るのか1~
最近、大抵のスポーツがオフシーズン入りしたせいか、更に楽天球団がスポーツニュースで登場する機会が増えました。そんな私も楽天ユーザーで、楽天内のショップでよく買い物をします。今や、楽天の影響もあってか、ネット上での売買金額は日本でもうなぎのぼり。私もそれに少しは貢献しています。逆に、今までは私たち消費者向けの小売といえば、百貨店でしたが、その百貨店の凋落振りは、目を覆いたくなるものがあります。毎年毎年、売上を落とし続ける、まさに斜陽産業の典型のようになりつつもあります。そんな中で、どの百貨店も力を入れるのが、欧米の有力ブランドショップの誘致と、デパ地下。他には、福袋に化粧品。では、なぜ百貨店はどこも同じような方法を取るのでしょうか。実は、最初にあげたネットショッピングと関連があります。百貨店が力を入れるものを、ざっと並べて見てみましょう。何か気付いたでしょうか?それは、ネットの特性です。ネットは、複数の情報処理に優れています。そして、物理的距離を一挙に縮めます。つまり、同じものを全国で比較検討するのは、ネットに勝るものがない、ということです。最近は、百貨店や家電店で実物を見て、ネットで買う人も多くなっていると聞きます。わざわざ説明するまでもありませんが、店舗設備を持たない上に、在庫をほとんど持たないネット店舗に、価格面でリアル店舗が勝つのは、正直厳しいと言わざるを得ません。そこで、百貨店に目を戻してみると、力を入れているのは、比較検討できないか、そもそもネットで販売し辛いものばかり。つまり、ネットとの戦いを避けられるものに、戦力を集中している訳です。まず、福袋はわかりやすいでしょう。百貨店の福袋は中身を公開していませんから、それをそもそも比較できませんし、元々割安な上に比較して買うものというより、ある種イベントで購入するようなものです。次に、デパ地下。かなり対応できるようになったとは言え、食料品はまだまだ取り扱い難いものです。しかも、その中でも百貨店が扱うのは、お惣菜中心。冷凍モノや乾物などはネットにかなり食われていますが、調理後の経過時間が大切な惣菜は、まだまだリアル店舗の方が有利と言えます。それは、保存が利きやすいお菓子等のお店が入る場合に、各店舗にオリジナル商品を強く要請することからもわかります。ブランドショップについては、ブランド品の販売戦略が効いています。つまり、ブランド品は安売り系のネットに流通し辛い構造になっており、直輸入品を扱う店舗で小さく商っている以外は、フルラインナップのネットショップ、しかも価格競争している店はなかなか見つけられません。最後に、化粧品。化粧品は、ネットでも取り扱っている店はありますが、化粧品には2ラインあって、対面販売を要するものと、完全に置き売りできるものがあり、ネットで取り扱っているのは、原則後者のみです。対面販売を要する商品は、ネット上での販売は難しいと言えますし、そもそもブランド品と同じく、メーカーが流通させないという現実もあります。結局、百貨店は、ネット販売とがっぷりよつで組む気はなく、入り込めない市場に力を入れて、これから戦っていこうとしているのです。では、なぜ百貨店はネットと戦えないのか。価格以外に、どういう面でネット店舗が優れているのか、次回に触れたいと思います。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.14
コメント(0)
-
お引っ越し!
使いにくいので、別の某サイトから引っ越してきました。どうぞよろしくお願いします。私も楽天ユーザーですが、ちとビジネスネタは合わないかもしれませんが、とりあえず頑張って書いていきます。
2005.01.13
コメント(0)
-
会社の辞め方3:誰に言えば良いの?
会社の辞め方シリーズ、第3弾。今回は、「辞めるときに誰に言えば良いの?」について。色々と悩んだ後、さあ辞めよう、と思った時に一体誰に言えば良いか、結構迷います。最近は、わからないし煩わしいので、一気に人事部に連絡して、手続きを進めて、いきなり辞めてしまう人もいるそうです。退職については、企業に明らかな不利益を与えない限り、退職時期を引き延ばすことはできません。つまり、正しい手続きを踏めば、問題ない限り辞めれるのです。例えば、前職は固定の明確な上司がおらず、プロジェクト単位で上司が変わり得る環境だったので、退職の手続きがかなりフロー化されていました。ただ、外資系色がそれなりにあったので、いきなり辞めてしまう人も多かったらしく、何と!退職届の提出手順まで定められていました。その手順は、所属プロジェクトにおける直属のマネージャ→プロジェクトマネージャ→エンゲージパートナー→所属ユニット長→人事部という4つの段階を踏んでサインを貰う形になっていました。ここまで書きましたが、このように定められなくても、企業組織としては、通常は直属の上司に相談してから、退職届を出すというのが手順です。つまり、辞める際には、言い難いかもしれませんが、やはり直属の上司に話をするべきでしょう。課長や部長がいて、どの上司か迷う際には、ひとまず職階の低い人から言うことをお薦めします。いきなり部長までいってしまうと、飛ばされたと思って怒る課長などもいます。これは、人が辞めると、その部署の上司が、管理不行き届きということで、更に上からお叱りを受けることになるからです。部長等にいきなり言った日には、課長が尋ねられて怒られ、今度は課長に係長が尋ねられて怒られ…、という寒い事態となるわけです。但し、相談したは良いが、こういう評価に関わる理由から、かなり引き止め工作を行う役職者がいるのも事実です。その際は、ひとまず人事部に経緯のみ説明して、辞める意思があることを証拠が残る形、すなわちメールにて伝えておきましょう。大抵の会社では、人事部に退職届が到着した時点から1ヶ月後以降であれば辞めていい、という規定になっています。ただ、法律的には、辞める意思表示をした段階から、となっていますので、例えば次の仕事が決まっていて日程的に急いでいる際は、人事部にメールで相談と言う形を取って意思表示を行うと良いでしょう。押さえるべきは、直属の上司と人事部。この二箇所だと覚えておきましょう。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.12
コメント(0)
-
売り切れ御免 ~ユニクロが抱えるジレンマ~
街を歩いていると「バーゲン!」の文字が目に付きます。もうそんな季節か~、と思ってしまいました。さて、年明けと言えばバーゲン!ではなく最近は年柄年中バーゲンをやってるような気もするバーゲンですが、代表格はアパレル商品でしょう。しかし、バーゲンとは無縁なアパレル?もあります。今や世界を狙うまでに成長した製造小売のユニクロです。ユニクロは「安売りやめます」やユニクロプラスの展開が注目されていますが、私はかなり前から、質の向上には感心していました。安かろう悪かろうではなく、その素早い生産管理と高い品質管理能力に加えて大量調達とローコストオペレーションにより、安くて良いものを、消費者に送り届けてきたのです。しかし、その質に比べて、ユニクロからはプラスのイメージを感じられません。それはなぜでしょうか?私は、ユニクロのビジネスモデルと規模が旧来型のKPIと負の相乗効果を起こしてしまった結果だと考えます。ユニクロも、いわゆる製造小売アパレルモデルを追及した形態をとっています。どういうモデルかというと、いわゆるサプライチェーンを高速化した売上連動型販売モデルです。手順をおって説明すると、まず、幾つかのデザインで多色展開を行い、初期ロット分を店舗に服を積み上げます。平行して広告宣伝の展開を行いますが、売れ始めると店舗の情報、即ちPOS情報を元に、どのデザインのどの色が良く出ているか、逆に出ていないかを判断し、若干の先行予測をかけた後、欠品しない程度に、出ているものを計画よりも多めに生産し、出ていないものは計画よりも少なく生産し、この一連の流れを繰り返しながら、なるべく多くの服を売ろうとする訳です。ざっと聞くと、非常に合理的で売上が最大化されつつ、コストも抑えられる(アパレルのコストで多くを占めるのは、余った服の製造費と処分費用になるため)良いモデルと思うかもしれません。しかし、この話の中で、大きな問題点が3つほどあります。それは、前にも触れた「旧来型KPI」とその「情報源」、そして、「売上拡大」の魔力の3点です。(1) 旧来型KPI 小売業で重要なKPIとしてあげられるものの中に『欠品率』があります。欠品率とは読んで字の如し、品切れを起こしている比率です。これは、販売機会ロス、という考え方に基づいたものです。販売機会ロス、というのは、そこにモノがあれば売れていたはずなのに、モノが切れていたために売れない、ことによる機会ロスのことです。 いざ、自販機で飲み物を買おうと思っても、欲しいものがなければ隣の自販機へ行ってしまいますよね? これが、最初の自販機にとっての機会ロスとなります。 この考え方に則ると、ロスは減らそうと努力はするが、モノが店頭からなくなることを防ぐ、という相反するドライバーが働き、結果として、ある程度のモノが残ってしまい、投売り等の要因を作ってしまいます。(2) 情報源 商品の動向を見るために、一般的に小売業は「POSデータ」を使います。POSデータとは、レジの情報を集約したもので、各商品タグに付けられた情報を読みとり、単に売上だけでなく、どのモノがどれだけ売れたかを把握できるものです。 売れた数が直ぐにわかるなんて便利ですよね? 確かに非常に便利であり、POSデータは無くてはならな指標なのですが、一つだけ大きな欠点があります。POSデータは売れた「結果」のデータである、ということです。つまり、常に市場の後追いをするしかない指標なのです。 結果から将来を予測することは、ある程度はできるかもしれませんが、需要を生み出すまでには至りません。これが、POSデータの最大の欠点と言えるでしょう。(3) 売上拡大 日本の企業、特に小売業は、規模の経済よろしく、売上高の成長に必要以上にこだわります。 実は、これだけでは、大きな問題は生み出しません。しかも、利益重視でなければならない、というつもりもありません。 ですが、これが、(1)、(2)と結びつくことで、非常に大きな問題を生む土壌を作ってしまうという、恐ろしいジレンマなのです。さて、以上の3点が融合すると、なぜダメなのか。ここで、ユニクロのイメージがイマイチ向上しない理由。例えば、インナーは買うけどアウターはね、って人が多いことを考えると、思いつくかもしれません。そうです。ユニクロの悪いイメージは、「みんな、着てるから恥ずかしい」というところからきているのです。これが、品質を追求しても、他社が出さないようなものを売り出しても、イマイチイメージ向上に繋がらない理由なのです。それを構造的に生み出すのが、上記の3点です。まず、売上拡大を常とすると、なるべく大量に売ろうとします。次に、店舗で欠品しないように生産し続けると、本当に売れなくなるまで作ってしまいます。そして、その情報源はPOSデータという過去情報。つまり、同じものを着たくない!と思う人が多い場合、非常にコモディティ化された状態というのがあるとすると、その一定水準まで到達すると販売は飽和してしまい、工夫しても同じものは売れなくなるのに、そこに到達するまで気付かずに作ってしまう(過去情報なので気付いた時点で遅い!)、というカラクリです。このような構造的なジレンマを抱えるユニクロに、一つだけ解決する方法を提案するとするなら、「売り切れ御免!」を徹底すること。これにより、商品をコモディティ化させない上に、ものによっては希少価値(プレミアム)を出すようなコントロールをしつつ、POSデータに事細かに左右されずに、新しいものを市場に投入し続けることで、不良在庫を持つことなく、その品質を活かすことができるようになるのです。ユニクロの今後に注目です。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.11
コメント(0)
-
会社の辞め方2:いつ頃、言い出せば良いの?
会社を辞めるとき、いつ頃までに伝えれば良いか、という質問をよく受けます。実は、これは非常に簡単。法律的にも定められているもので、引継ぎに問題がない場合は、最短で2週間以上前に言っておけば大丈夫です。但し、一般常識としては、1ヶ月前までに言っておく必要があります。この辺りは、大体、会社の規約に書いてあったりしますので、しっかり読んでおくことをお薦めします。ただ、これらは法的な話。やはり、社会人としては、たつ鳥跡を濁さずを目指したいもの。言い出しづらいとは思いますが、できれば直属の上司には、1ヶ月半~2ヶ月前には言っておいた方がベター。まあ、仲が良いなら一度ぐらいは、説得飲み会に連れて行かれることでしょう。そこでも、相手の顔を立てつつ、折れないように耐え抜きましょう。兎に角、相手に迷惑をかける確率を、どんどん下げること。そのために、必要な情報はしっかり集めておいて自分を守ること。狭い世の中ですから、最低限の気遣いはしておきたいものです。でも、辞めるのは、やっぱり自分の都合です。辞めるなら辞めるでリスクは負います。それでも、自分は辞めた方が良い、と思えるときまでは焦らず、でも、思えたときは迅速に動きたいものです。良い旅立ちになりますように。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.10
コメント(0)
-
戦略ドリブンから組織ドリブンへ ~マーケットインとの因果関係~
昨夏にベンチャーでネット系のマーケティングリサーチ会社に転職し、その業界動向の速さに日々もまれています。そのような環境においては、立ち止まって考えることが許されず、まさに Try and Error が常とされます。前職は、コンサルティング会社だったので(今の進めかたの方が合ってますが…)、今までの大企業のやり方との違いに、ベンチャーだからと理解はしていても、正直驚いています。では、なぜそのようなことが起きるか。単に考えずに動いてるだけじゃないのか。そう思う人も多いと思います(特にコンサルティング業界の人などは)。ですが、一緒に働いていて、そこまで考えない人じゃないと言うことはわかります。逆に業界TOPクラスのベンチャーだと、前職クライアントであった大企業・財閥企業と比べても、かなり優秀な人材が揃っています。そんな時に、本で読んだのが、戦略ドリブンと組織ドリブンの話。これを読んでピンときました。この話自体は、IT化の先行した米国では、もう10年近く前から話されていたそうですが、ITによる業務革新が起こった辺りから、旧来の「企業戦略」構築型の企業運営から、組織力による企業運営に変わってきはじめたということです。原典を詳しく読んでないので間違っているかもしれませんが、情報を徹底的に収集し分析し、まず最初にきっちりとした戦略を立てることで、他企業との差別化をはかり、市場で勝利を収められるという考えが、「戦略ドリブン」型であり、変化対応力を高め、学習する組織を構築し、組織力で柔軟に環境に対応して事業を生み出し、失敗したらあるいは目標が達成できなければ即修正、という組織力重視の考え方で結果的に市場を勝ち取って行こう、とするのが「組織ドリブン」型です。今までは、確かに「戦略ドリブン」が喧伝された時代がありました。ブランド構築先行で勝ち抜けるという話ももてはやされたこともありました。しかし、今働いている人の中で、本当に5年先も売れ続ける、と思っている人はいないように、時代は「戦略ドリブン」から「組織ドリブン」へ移行しているのは明らかでしょう。では、なぜそのようになったのか。それは、マーケットの特質が大きく舵を切ったからに他ありません。つまり、プロダクトアウトからマーケットインへの方針転換です。プロダクトアウトは、良いもの作れば売れる、型の発想であり、マーケットインは、市場の声を如何に早く捉え対応するかで売れるか売れないかが決まる、型の発想です。現代社会は、モノ余りの社会とも言われるように、良いものを作ったからと言って売れる訳ではありません。それは、「良い」モノの基準が人によって変わってきたり、基準がコロコロ変わったりするようになったからです。ですから、必然的にマーケットインへと流れざるを得なくなった訳です。そうなるとどうなるか。オチオチ頭を悩ませて、ノンビリ良いものを練ってる暇はなくなったのです。つまり、情報を収集し、分析し、製品・サービスを固め…ている間に、市場の要求は変化し、時代に取り残されてしまう。戦略を練っているだけの時間は、ほとんど失われてしまっているのです。それに対抗するには、組織力を高め、徹底的に市場の流れに乗り、更に一歩先を見据えつつ、商品・サービスを開発・修正していくしかないのです。このような環境において、コンサルティングは職業として独立するよりも、各企業と溶け合いビジネスパーソンのスキルと化していく必要があるのかもしれません。面白い・参考になったと少しでも感じていただけたらこちら!(この1クリックが励みになります)
2005.01.09
コメント(0)
-
会社の辞め方1
年始にアメリカの大学へと飛び立つ前職の仲間と会って話してきました。色んな話題で夜遅くまで(というか開始も遅かったが…)盛り上がりましたが、その時に「会社の辞め方」の話題を書くとそこだけヒットカウンターが上がる、という話を聞いたので、人集めというよりも、皆さんが悩まれることが多いポイントということで、経験者としてちょっと書いてみたいと思います。私は昨春頃に転職をしたのですが、その際には勿論会社を辞めています。同じく、幾つか不安に思ったところとかはあったのですが、その後に友人の転職を手伝ったりした時に、実は、結構単純なことに悩まれる方が多い、ということに気が付きました。まず今回は、そのポイントについて書いてみようと思います。・いつ頃、言い出せば良いの?・誰に言えば良いの?・自分が辞めて職場は大丈夫かな?・次の会社は本当に良いところなのかな?・ボーナスとか退職金ってどうだろう?・喧嘩しないで辞める方法ってないのかな?・退職の手続きってどうすれば良い?ざっとあげるとこんな感じかと思います。今後のBlogで、トピック毎にちまちまと書いていこうと思います。面白いと感じたらこちら!
2005.01.05
コメント(0)
-
書初め
新年あけましておめでとうございます。今年こそは、書こう書こうと思いながらも始められなかったBlogを書こうと思います。新しい職場にも慣れ、入社当初よりも更に忙しくなってきましたが、それに負けずに、思ったことを書き綴ろうと思いますので、よろしくお願いします。
2005.01.01
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1