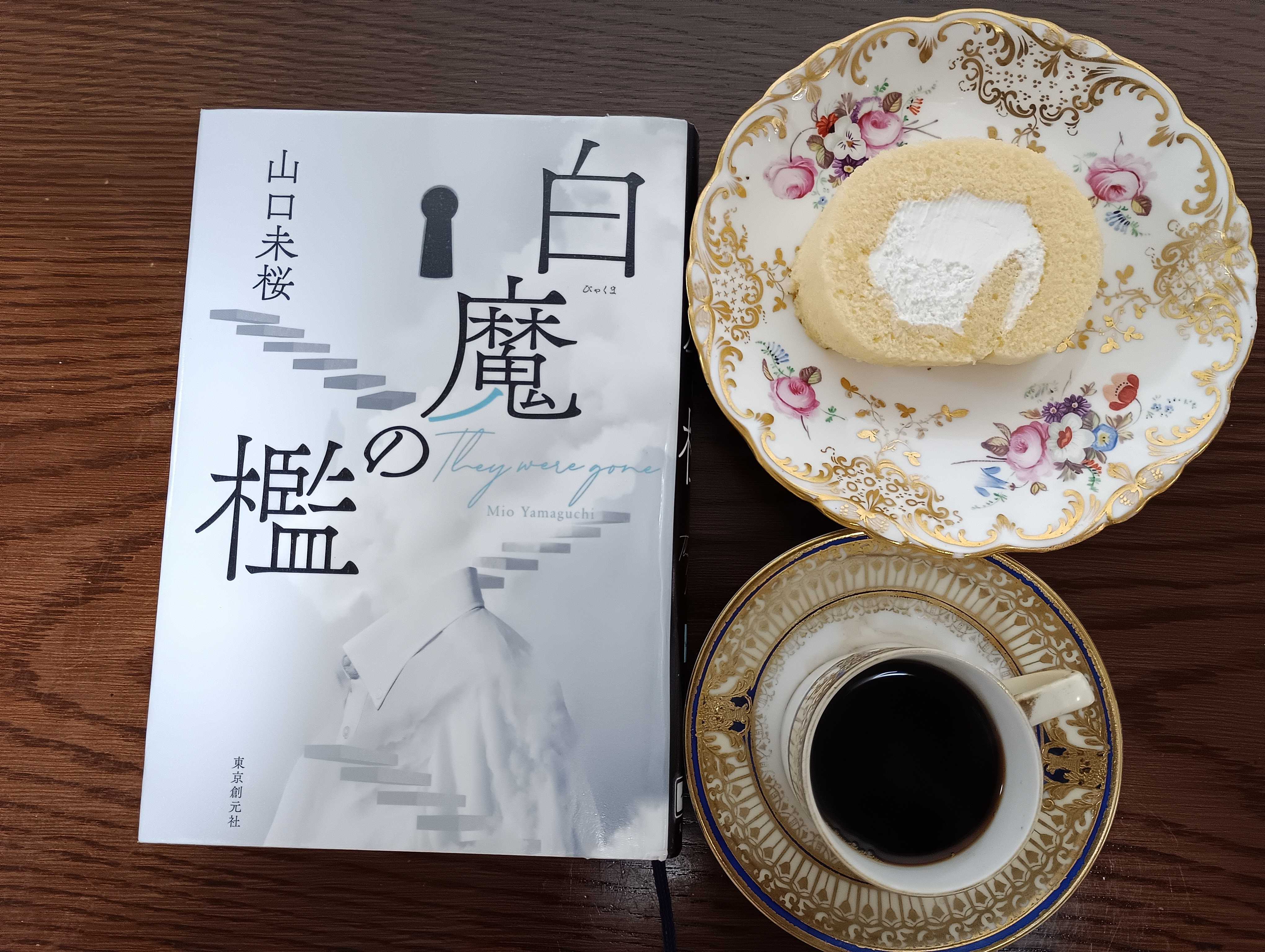ラ・サール中学H.8~H.18
| 年号 | 西暦 | リンク | 題名 | 作者 | 備考 | あらすじ |
| H.9 | 1997 | まどさん | 『まどさん』 | 阪田寛夫 | 【2日目】ちくま文庫 発行年月:1993年04月 |
「ぞうさん」で有名なまど・道雄についての評伝小説。 |
| H.10 | 1998 | 
|
『ポプラの秋』 | 湯本香樹実 | 新潮文庫 発行年月:1997年07月(つまり、 前の年の夏 ) |
内容(「BOOK」データベースより) 夫を失ったばかりで虚ろな母と、もうじき7歳の私。二人は夏の昼下がり、ポプラの木に招き寄せられるように、あるアパートに引っ越した。不気味で近寄り難い大家のおばあさんは、ふと私に奇妙な話を持ちかけた―。18年後の秋、お葬式に向かう私の胸に、約束を守ってくれたおばあさんや隣人たちとの歳月が鮮やかに甦る。世界で高い評価を得た『夏の庭』の著者が贈る文庫書下ろし。 |
| H.13 | 2001 | 
|
『夢の守り人』? | 著者:上橋菜穂子 /二木真希子 | 偕成社ワンダーランド 発行年月:2000年06月(つまり、 前の年の夏 )これは「守り人シリーズ」というものの1冊らしい。問題文が『夢の守り人』」かどうかはわからない。登場人物の名前で検索したらこれが出たので、これを挙げた。 |
人の世界とは別の世界で花をつけ実をむすぶその“花”は、人の夢を必要としていた。一方、この世をはかなんでいる者は、花の世界で、永遠に夢を見つづけることを望んだ。いとしい者を花の夢から助けようと、逆に花のために魂を奪われ、人鬼と化すタンダ。タンダを命をかけて助けようとするトロガイとチャグム、そしてバルサ。人を想う心は輪廻のように循環する。 |
| H.15 | 2003 | 
|
『これが「週刊こどもニュース」だ』? | 池上 彰 | 発行年月:2000年09月 これも、私が「こんな本、あったなあ。」と思って検索してみたので、正しいかどうかは?。 |
「全てのニュースはこどもにわかる」。今や人気番組となったNHK「週刊こどもニュース」のスタッフである著者が、ニュースの選択から伝達まで実例を挙げて楽しく語る裏話。政治、金融、世界情勢など込み入った話題をこどもにも充分に判るようにするための努力と苦労。基本の基本にまで遡ることで、大人にとっても新たな発見ができる。すらすら読めて、なるほどと納得。家族みんなで楽しめる一冊。 |
| H.16 | 2004 | 
|
『神道の逆襲』 | 菅野覚明 | 講談社現代新書 発行年月:2001年06月 |
日本人は神さまとどのようにつきあってきたのか。古代から近世、そして今に至るまで、多様に展開された「神の形而上学」を検証。 |
| H.16 | 2004 | 
|
『ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ』 | 中西進 | 出版社:小学館 発行年月:2003年07月 |
出版社/著者からの内容紹介 「聖」とは、特別な日を知っている人だから「ひじり(日知り)」。「息子」「娘」の「むす」は、「苔むす」の「むす」と同じ。日本語の基本「やまとことば」をひらがなでよむことで、日本語のふしぎ・奥深さがわかる。日本語ってふしぎだと思ったことはありませんか。 なぜ文字を書くことも爪で引っ掻くことも、「かく」なのか。照りつける太陽も燃える焚き火も、「ひ」というのはどうしてか。そういえば顔にある目・鼻・歯は、植物の芽・花・葉と発音が同じじゃないか……。 それを解明してくれるのが本書です。遥か昔から今日まで、ずっと使われつづけた「やまとことば」を「ひらがな」で読むことで、どんどん本来的な意味がわかるのです。 読み始めるとやめられなくなること請け合い。知的好奇心を刺激する、目からうろこの日本語本です。 |
| H.17 | 2005 | 家族の深淵 | 『家族の深淵』 | 中井久夫 | この年から出典が問題の本文後ろに書かれるようになる。発行年月:1995年09月 出版社:みすず書房 本体価格 3,000円 (税込 3,150 円) サイズ:単行本/p389 高くてページ数のある本ですねえ、、、。開成に比べて、本文が難しいものが多い。(これは、昭和の時代の入試問題も。)という印象を受けます。文章に使われている言葉自体が難しげです。例えば次のように。次に挙げる下の↓問題の文章です。) 金銭的報酬を得るか否かでプロとアマを区別するわれわれの通念は、古代には存在しない。 |
往診先での医師と家族のあり方を描いた表題作をはじめ、独自の文化論「きのこの勾いについて」まで。精神科医としての観察と感受と寛容が生んだ38エッセイ。 |
| H.17 | 2005 | 
|
『 古代オリンピック 』←出版社へのリンク | 井上秀太郎 | 岩波新書 発行年月:2004年07月(つまり、 前の年の夏 ) |
裸の走者が駆け、戦車が競技場を揺るがす。熱狂する観客、勝利者の頭上の聖なるオリーヴの冠―紀元前八世紀のギリシアから古代ローマ時代に至るまで、実に千二百年近くの命脈を保った古代オリンピック競技会を、最新の考古学・歴史学の成果を踏まえて語る。競技の詳細、会期中の休戦、優勝者の得る利益についてなど、興味深い話題は尽きない。 |
| H.18 | 2006 | 
|
『羞恥心はどこへ消えた?』 | 菅原健介 | 光文社新書 発行年月:2005年11月(つまり、 入試の2ヶ月前? ) |
ジベタリアン、人前キス、車内化粧、車内飲食etc. <恥の基準>が変わり始めた 近年、駅や車内などで地べたに座り込む「ジベタリアン」、所構わず濃厚なラブシーンを演じる「人前キス」、電車の中で平気で化粧をする「車内化粧」など、街中での“迷惑行動”が目につくようになった。かつて、アメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトは日本を「恥の文化」であると規定した。しかし、今、この図式は成り立つのだろうか。普段、私たちは「恥ずかしい」という感情を毎日のように体験するが、羞恥心の性質についてはあまり知られていない。人間はなぜ「恥じらう」のだろうか。「羞恥心」は何の役に立っているのだろうか。そして現代社会で何が起こっているのだろう。「恥」から見えてきたニッポンの今。 |
| 上に同じ | 上に同じ | なし | 『イヌの放課後』 | 森 詠 | これは、まだ本になってないようです。雑誌「 本の窓
」(毎月20日発売)に連載中のようです。(リンクのページの「本誌 15 ■連載■」のところを御参照下さい。) |
近年、駅や車内などで地べたに座り込む「ジベタリアン」、所構わず濃厚なラブシーンを演じる「人前キス」、電車の中で平気で化粧をする「車内化粧」など、街中での“迷惑行動”が目につくようになった。かつて、アメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトは日本を「恥の文化」であると規定した。しかし、今、この図式は成り立つのだろうか。普段、私たちは「恥ずかしい」という感情を毎日のように体験するが、羞恥心の性質についてはあまり知られていない。人間はなぜ「恥じらう」のだろうか。「羞恥心」は何の役に立っているのだろうか。そして現代社会で何が起こっているのだろう。「恥」から見えてきたニッポンの今。 |
*あらすじは主に
 による。
による。平成17年度以前のものの出典は、全面的に声の教育社の解説に頼った。(平成17年度からしか、出典を問題文に明らかにしてないから。)それに出典が載っている分、または私が類推した分だけなので、平成16年度までは入試問題に使われているのを全部扱ったわけではない。
Copyright(c) cherrybee room ブーン All Rights Reserved.
© Rakuten Group, Inc.