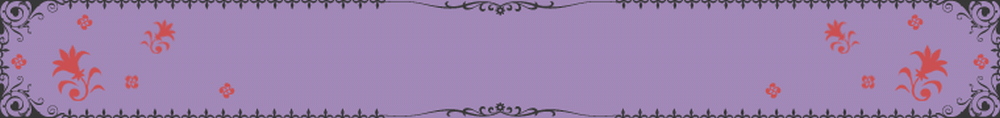もの思う葦 (その二)
もの思う葦(その二)葦の自戒 その一。ただ、世の中にのみ眼をむけよ。自然の風景に惑溺している我の姿を、自覚したるときに は、「われ老憊(ろうはい)したり」と素直に、敗北の告白をこそせよ。 その二。おなじ言葉を、必ず、二度むしかえして口の端に出さぬこと。 その三。「未だし」 感想について 感想なんて! まるい卵もきり様ひとつで立派な四角形になるじゃないか。伏目がちの、おちょぼ 口を装うこともできるし、たったいまたかまが原から来た原始人そのままの素朴の真似もできるのだ。 私にとって、ただ一つ確実なるものは、私自身の肉体である。こうして寝ていて、十指を観(み)る。 うごく、右手の人差指。うごく、左の十指。これも、うごく。これを、しばらく、見つめていると、 「ああ、私は、ほんとうだ」と思う。他は皆、なんでも一切、千々(ちぢ)にちぎれ飛ぶ雲の思いで、 生きているのか死んでいるのか、それさえ分明しないのだ。よくも、よくも! 感想だなぞと。 遠くからこの状態を眺めている男ひとりありて曰く、「たいへん簡単である。自尊心。これ一つで ある」 すらだにも 金塊集をお読みのひとは知っておられるだろうが、実朝のうたの中にm「すらだにも」なる一句が あった。 二十代の心情としては、どうしても、「すらだにも」といわなければならぬところである。ここま で努めて、すらだにも、と口に出してなって来るではないか。実朝を知ること最も深かった真淵、国 語をまもる意味にて、この句を、とらず。いまになっては、いずれも佳きことをしたと思うだけで、 格別、真淵をうらまない。 慈 眼 「慈眼」というのは亡兄の遺作(へんな仏像)に亡兄みずから附したる名前であって、その青色の二 尺くらいの高さの仏像は、いま私の部屋の隅に置いてあるが、亡兄、二十七歳、最後の作品である。 二十八歳の夏に死んだのだから。 そういえば、私、いま、二十七歳。しかも亡兄のかたみの鼠色の縞の着物を着て寝ている。二、三 年まえ、罪なきものを殴り、蹴ちらかして、馬のごとく巷を走り狂い、いまもなお、ときたま、余燼 ばくはつして、とりかえしのつかぬことをしてしまうのである。どうにでもなれと、一日一ぱいふん ぞりかえって寝ていると、わが身に、慈眼の波ただよい、言葉もなく、にこやかに、いわゆるえびす 顔になっている場合が多い。われながら、まるでたわいがないのだ。 この頃、これだけのことで、読者、不安の理屈を付さぬがよい。 重大のこと 知ることは、最上のものにあらず。人知には限りありて、上は―氏より、下は―氏にいたるまで、 すべて似たりよったりのものと知るべし。 重大のことは、ちからであろう。ミケランジェロは、そんなことをせずともよい豊かな身分であっ たのに、人手は一切借りず何もかもおのれひとりで、大理石塊を、山から町の仕事場までひきずり運 び、そうして、からだをめちゃめちゃにしてしまった。 付言する。ミケランジェロは、人を嫌ったから、あんなに人に嫌われたのだそうである。 敵 私をしんに否定し得るものは、(私は十一月の海を眺めながら思う)百姓である。十代まえからの 水呑百姓、だけである。 丹羽文雄、川端康成、市村羽左衛門、そのほか。私には、かぜ一つひいてさえ気にかかる。 追 記。 本誌連載中、同郷の友たる今官一君の「海鴎の章」を読み、その快文章、私の胸でさえ躍らせた。 このみごとなる文章の行く先々を見つめる者、けっして、私のみにあらざることを確信している。 健 康 なんにもしたくないという無意志の状態は、そのひとが健康だからである。少なくとも、ペエンレ ッスの状態である。それでは、上は、ナポレオン、ミケランジェロ、下は伊藤博文、尾崎紅葉にいた るまで、そのすべての仕事は、みんな物狂いの状態から発したものなのか。しかり。間違いなし、健 康とは、満足せる豚。眠たげなポチ。 K 君 おそるおそる、たいへんな秘密をさぐるがごとき、ものものしき仕草で私に尋ねた。「あなたは、 文学がお好きなのですか」私はだまって答えなかった。面貌だけは凛乎(りんこ)たるところがあった けれど、なんの知識もない、十八歳の少年なのである。私にとって唯一無二の苦手であった。 ポオズ はじめから、空虚なくせに、にやにや笑う。「空虚のふり」 絵はがき この点では、私と山岸外史とは異なるところがある。私、深山のお花畑、初雪の富士の霊峰。白砂 に這(は)いひろがれる千本松原、または紅葉に見えかくれする清姫滝、そのような絵葉書よりも浅草 仲店の絵はがきを好むのだ。人ごみ。喧噪。他生の縁あってここに集(つど)い、折も折、写真にうつ され、背負って生れた宿命にあやつられながら、しかも、おのれの運命開拓の手段を、あれこれと考 えて歩いている。私には、この手に余る人々、誰ひとりをも笑うことが許されぬ。それぞれ、努めて いるにちがいないのだ。かれら一人一人の家庭。ちち、はは。妻と子供ら。私は一人一人の表情と骨 格とをしらべて、二時間くらいの時を忘却する。 いつわりなき申告 黙然たる被告は、突然立ちあがって言った。「私は、よく、ものごとを識(し)っています。もっと 識ろうと思っています。私は率直に述べようと思っています。」 裁判長、傍聴人、弁護士たちでさえ、すこぶる陽気に笑いさざめいた。被告は坐ったまま、ついに その日一日おのれの顔を両手もて覆(おお)っていた。夜、舌を噛み切り、冷くなった。 乱麻を焼き切る 小説論が、いまのように、こんぐらかって来ると、一言もって、之を覆いたくなって来るのである。 フランスは、詩人の国。十九世紀のロシアは、小説家の国なりき。日本は、古事記、日本書紀、万葉 の国なり。長編小説などの国にはあらず。小説家たる君、まず異国人になりたまえ。あれも、これも、 と佳(よ)き工合には断じていかぬようになり。君の兄たり友たり得るもの、プウシキン、レエルモン トフ、ゴオゴリ、トルストイ、ドストエフススキイ、アンドレエフ、チェホフ、たちまち十指にあま る勢いではないか。 最後のスタンドプレイ ダヴィンチの評伝を走り読みしていたら、はたと一枚の挿画に行き当った。最後の晩餐の図である。 私は目を見はった。これはさながら地獄の絵掛地。ごったがえしの、天地震動の大騒ぎ。否。人の世 の最も切なき阿修羅の姿だ。 十九世紀のヨオロッパの文豪たちも、幼くしてこの絵を見せられ、こわき説明を聞かされたにちが いない。「われを売る者、この中にひとりあり」キリストはそう呟いて、かれの一切の希望をさらっ と捨て去った。刹那の姿を巧みにとらえた、ダヴィンチは、キリストの底しれぬ深い憂愁と、われと わが身を静粛に投げ出したるのちの無限のいつくしみの念とを知っていた。そうしてまた、十二の使 途のそれぞれの利己的なる崇敬の念をも知悉していた。よし、これを一つ、日本浪曼派の同人諸兄に たのんで、芝居をしてもらおう。精悍無比の表情を装い、斬人斬馬の身ぶりを示しているペテロは誰。 おのれの潔白を証明することにのみ急なる態のフィリッポスは誰。ただひたすらに、あわてふためい ているヤコブは誰。キリストの胸のおん前に眠るがごとくうなだれているこの小鳩のように優美なる ヨハネは誰。そうして、最後に、かなしみ極りてかえって、ほのかに明るき貌の、キリストは誰。 山岸、あるいは、自らすすんでキリストの役を買って出そうであるが、はたしてどういうものであ るか。中谷孝雄なる佳き青年の存在もゆめ忘れてはならないし、そのうえ、「日本浪曼派」という目 なき耳なき混沌の怪物までひかえている。ユダ。左手もて何やらんおそろしきものを防ぎ、右手もて、 しっかと金嚢を掴んでいる。君、その役をどうか私にゆずってもらいたい。私、「日本浪曼派」を愛 すること最も深く、また之を憎悪するの念最も高きものがあります故。 冷酷ということについて 厳酷と冷酷とは、すでにその根元において、相違(ちが)っているものである。厳酷、その奥底には、 人間の本然の、あたたかい思いやりで一ぱいであるのだが、冷酷は、ちゃちなガラスの器物のごとき もので、ここには、いかなる花ひとつ咲きいでず、まるで縁なきものである。 わがかなしみ 夜道を歩いていると、草むらの中で、かさと音がする。蝮蛇(まむし)の逃げる音。 文章について 文士というからには、文に巧みなるところなくては、かなうまい。佳き文章とは、「情籠もりて、 詞舒(ことばの)び、心のまま誠を歌い出でたる」態のものを指していうなり。情籠もりて云々は上田 敏、若きころの文章である。 ふと思う なんだ、みんな同じことをいっていやがる。 Y 子 そのささやきには真摯の響きがこもっていた。たった二度だけ。その余(よ)は、私を困らせた。 「私、なんだか、ばかなことをいっちゃったようね」 「私にだって個性があるわよ。でも、あんなにいわれたら黙っているよりほかに仕様がないじゃない の」 言葉の奇妙 「舌もつれる」「舌の根をふるわす」「舌を巻く」「舌そよぐ」 まんざい 私のいう掛合いまんざいとは、たとえば、つぎのごときものを指していうのである。 問。「君はいったい、誰に見せようとして、紅(べに)と鉄漿(かね)とをつけているのであるか」 答。「みんな、様ゆえ。おまえゆえ。」 へらへら笑ってすまされる問答ではないのである。殴るのにさえ、手がよごれる。君の中にも! わが神話 いんしょう、いなばの小兎。毛むしられて、海水に浸り、それを天日でかわかした。これは痛苦の はじまりである。 いんしゅう、いなばの小兎。淡水でからだを洗い、蒲(がま)の毛を敷きつめて、その中にふかふか と埋って寝た。これは、安楽のはじまりである。 最も日常茶飯事的なるもの 「おれは男性である」この発見。かれは家人の「女性」に気づいてから、はじめてかれの「男性」に 気づいた。同棲、以来、七年目。 蟹について 阿部次郎のエッセイの中に、小さい蟹(かに)が自分のうちの台所で、横っ飛びに飛んだ。蟹も飛べ るのか、そう思ったら、涙が出たという文章があった。あそこだけは、よし。 私の家にも、ときたま、蟹が這って来る。君は、芥子(けし)つぶほどの蟹を見たことがあるか。芥 子つぶほどの蟹と、芥子つぶほどの蟹とが、いのちかけて争っていた。私、あの時、凝然(ぎょうぜ ん)とした。 わがダンディズム 「ブルウタス、汝もまた」 人間、この苦渋を嘗めぬものが、かつて、ひとりでも、あったろうか。おのれの最も信頼している ものこそ、おのれの、生涯の重大の刹那に、必ず、おのれの面上に汚き石を投ずる。はっしと投げる。 さきごろ、友人保田与重郎の文章の中から、芭蕉の佳き一句を見いだした。「朝がほや昼は鎖おろ す門の垣」なるほど、これに限る。けれども、――また、――否。これに限る。これに限る! 『晩年』について
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 糖尿病
- 「オセンピック」という気持ち悪くな…
- (2025-10-13 13:53:35)
-
-
-

- 万歩計
- こんなに歩いている!
- (2025-01-23 22:18:25)
-
-
-

- 今日の健康状態は?
- 静岡の理学療法士による自費リハビリ…
- (2025-11-26 17:04:05)
-
© Rakuten Group, Inc.