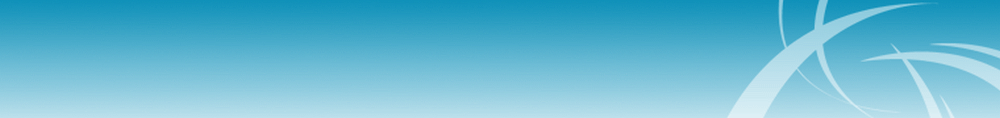PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 時事
「会社員はクレカ払いできない」
って見出しのニュース見たら下記だった。
住民税が決まる仕組みとは?意外と知らないその内訳- 記事詳細|Infoseekニュース
「どうせ住むのなら、この市区町村に住みたい!」と思ったことはありませんか?周辺環境だけでなく、行政のサービスはそれぞれの市区町村で違います。行政の一般経費をまかなうために徴収するのが住民税です。毎月の給料の中から引かれている税金や社会保険料、年金のことは、普段気にとめて考える機会は少ないでしょう。…
見出しおかしくないか?|Infoseekニュース
住民税が決まる仕組みとは?意外と知らないその内訳- 記事詳細|Infoseekニュース
「どうせ住むのなら、この市区町村に住みたい!」と思ったことはありませんか?周辺環境だけでなく、行政のサービスはそれぞれの市区町村で違います。行政の一般経費をまかなうために徴収するのが住民税です。毎月の給料の中から引かれている税金や社会保険料、年金のことは、普段気にとめて考える機会は少ないでしょう。…
住民税が決まる仕組みとは?意外と知らないその内訳
MONEYPLUS / 2018年4月10日 11時30分
写真
住民税が決まる仕組みとは?意外と知らないその内訳
「どうせ住むのなら、この市区町村に住みたい!」と思ったことはありませんか?
周辺環境だけでなく、行政のサービスはそれぞれの市区町村で違います。行政の一般経費をまかなうために徴収するのが住民税です。
今回は、自分の生活に直結する個人住民税について知識を整理していきます。
住民税に関するよくある勘違い
「4~6月の給料で住民税が決まる」とか「住民税が決まる3か月間はあまり残業しない方がいい」などの話を聞くことがあります。実際はどうなのでしょうか?
これは、実は住民税と社会保険料(健康保険料・厚生年金等)を混同されています。
後ほど詳しく解説しますが、住民税の徴収は前年の所得をもとに計算されていて、毎年6月から徴収が開始されます。一方、社会保険料の等級を決める「標準報酬月額」は、その年の4月から6月の給料の平均を参考にします。ですから、4月から6月の給料がその年に徴収される住民税にすぐに影響するわけではありません。「6月」というキーワードでおぼえていると、勘違いする場合が多いようです。
そもそも住民税とはなに?
「住民税」には、個人住民税と法人住民税とがあります。一般に道府県民税(および都民税)と市町村民税(および特別区民税)をあわせて「住民税」と呼んでいます。
個人住民税は、税額を市区町村が計算して課税する「賦課課税方式」をとります。所得税の確定申告や給与支払報告書などをもとに税額が計算されるため、所得税ほどには親しみがないかもしれません。
個人住民税は次のように区分されています。
住民税の特徴
住民税は所得税とは違ったいくつかの特徴があります。
住民税は「前年所得課税」といって前年分の所得をもとに課税するので、所得税とは1年の差があります。だだし、退職所得については、その年で課税する現年所得課税を採用しています。
(2)住民税は均等割・所得割などの5つに区分
住民税には、「均等割」といって条例で定める一定以上の所得がある人について、所得の大小に関係なく均一に課すものがあります。
住民税の均等割は年額で、市町村民税3000円+道府県民税1000円=4000円です。平成26年度から平成35年度までの間は、地方自治体の防災財源確保のために、市町村民税が3500円、道府県民税が1500円と年額で1000円引き上げられています。
さらに「所得割」といって一定の計算方法に基づいて計算した後に税率(10%)をかけるものがあります。内訳は道府県民税が4%、市町村民税が6%になっています。
このほかに道府県民税には利子割、配当割、株式譲渡割があり、あわせると5つに区分されます。
(3)住所地と納付先
1月1日現在に住所を有する都道府県および市区町村に納付します。このため、1月1日以後に住所を移転した場合でも、その前年度分の住民税は1月1日に住んでいた住所地に納付することになります。たとえば、1月1日に東京に住んでいて大阪に引っ越した場合には、納付するのは東京の市区町村です。さらに年の途中で出国した場合については、翌年に住民税は課税されません。12月31日に出国するのか翌年の1月1日に出国するのかで税負担が異なってきます。
住民税が非課税になる場合
先ほど住民税に均等割と所得割があるとお話しましたが、住民税が非課税になる場合は3つのパターンがあります。
(1)均等割および所得割の両方が非課税となる場合
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
(2)均等割が非課税になる場合 ※所得が下記の算式により算定した金額以下のとき
均等割の非課税基準
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の合計数+1)+21万円*
*算式中の21万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算される
(3)所得割が非課税になる場合 ※所得が下記の算式により算定した金額以下のとき
所得割の非課税基準
35万円×(控除対象配偶者・扶養家族の合計数+1)+32万円*
*算式中の32万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に加算される。
※(2)(3)の均等割や所得割の非課税の基準は、各市区町村によって異なります。
所得割額 住民税の計算の流れ
市区町村は所得税の確定申告書や給与支払報告書から所得の情報を入手します。それをもとに所得控除をし、市区町村がそれぞれの所得の税額を計算した後、税額控除があればそれを差し引き納税者に割り当てます。このとき均等割の5000円と併せて徴収します。
注意として退職所得は、会社などの支払者が所得税と住民税を計算し、その時点で課税関係が終わってしまうので、上記の計算には当てはまりません。
個人事業者については、所得税の確定申告を提出すると税務署が市区町村へその申告書を送付します。また、給与所得者については、給与の支払者である会社が市区町村へ送付します。
住民税の申告をしなくてもよい人は次のとおりです。
・所得が給与所得のみである人や確定申告をした人
・前年に所得がなかった人
・前年中に所得が市区町村の条例で定める金額以下の人
住民税の申告書の提出期限は、2月16日~3月15日です。
住民税の納付は、普通徴収の方法により年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて徴収されるのが原則です。しかし、給与所得者については、源泉徴収票の「給与支払報告書」の提出によって住民税が計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から税額を天引きして、翌月の10日までに市区町村に納める特別徴収による仕組みになっています。
最近では、税金をクレジットカードで支払うことができるようになりました。ポイントを貯めたいので、住民税を普通徴収に切り替えたいと思うことがあるかもしれません。しかし、事業主は従業員の住民税を特別徴収して納付する義務があるため、残念ながら会社員はクレジットカードでの支払いはできないことになっています。
なお、公的年金を受給している人で、住民税を納める必要がある人も特別徴収されることになっています。ただし、特別徴収される税額が年金収入を超える場合や介護保険を特別徴収されていない場合、特別徴収はされません。
住民税は納税だけの問題では終わらない
住民税は納税だけではなく、保育料の算定や介護保険料、国民健康保険や後期高齢者医療保険などにも影響してきます。
会社員で給料をもらっている間は、住民税を納付しないですむことは少ないでしょう。しかし、同居の家族が公的年金収入だけで住民税の納付はゼロというケースはあり得ます。
住民税は個人ごとに計算されますが、世帯全員が住民税非課税の場合には、住民税非課税世帯の優遇措置があります。たとえば、高額療養費の自己負担額が減額されたり、入院した時や介護施設に入所したときの食事代の負担が軽減されたりします。
同じ屋根の下に住んでいれば同じ世帯と思いがちですが、同じ住所であっても世帯を分けることで金銭面での負担が違ってきます。
会社を辞めるときには納税があることを忘れずに
毎月納付している住民税は前年のものです。会社を辞める時期によって納税の対応が違います。
6月~12月の間に退職する場合、退職月分の住民税は天引きされますが、以降の分は自分で納める普通徴収になります。一括か分割かを選ぶことができます。ただし、転職先が決まっている場合には特別徴収を継続する手続きができます。
1月から5月までの間に退職する場合は、退職手当を支払う際に、所得税とともに住民税を一括徴収し、その翌月10日までに納付するのが原則です。たとえば、1月に退職した場合には、1~5月分が一括で納付されます。退職前に住民税を確認しておくなど、納税のプランニングしておく必要があります。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[時事] カテゴリの最新記事
-
桂雀々さんが大物ミュージシャンたちに愛… 2024.11.23
-
たむらけんじ 文春から取材依頼も、拒否… 2024.03.15
-
陶芸家が100均の「陶芸用ねんど」使ってみ… 2024.02.21
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
フリーページ
漂流録

最初の漂流

単車乗りの聖地北海道

未踏の地-四国一周編

海沿いを走る-瀬戸内海一周編

紀伊半島を一筆書き

漂流写真

パンフの杜
単車

CB750FB BB2

通勤快速スーパーカブ

車とか自転車とか
バス釣り

釣果報告

愛すべきロッドたち

愛すべきリールたち

愛すべきルアーたち

黒鱒釣竿 計画
コインコレクション
おもしろgif集めました
部屋中ビオトープ
昔ポスト
ごはん写真
おもちゃで遊ぼう

烈車戦隊トッキュウジャー

レゴの動画たち

折り紙-Learn how to make origami
音を楽しむ

きゅうそキャンプソング
小さい大工さん-Do It Myself-
60mlの情熱
スタンプコレクション!
愛すべき道具たち
ミニ四駆
VAPEの備忘録。
老後の為?投資
鉄道動画
© Rakuten Group, Inc.