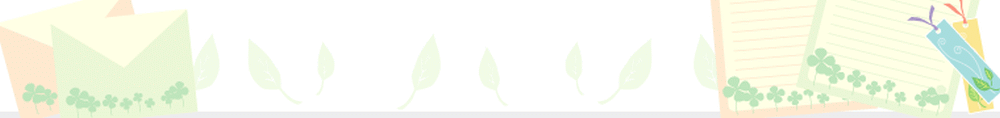2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年05月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
気の迷いと大人になるということ 【はぴぶら☆幸せ探し♪】
こんばんは、あやまです♪昨日はすごい疲れていたようです。仕事帰りにスポーツジムにいき、フラフラしながらいっぱい泳ぎ……あ、泳げるようになりました!!バタフライ!!ではなく、クロールですけど。いまだバタフライはできません、というか習ってません。というより諦めたんです。だってバタフライは水しぶきとばしすぎっ!!まだ泳げないとき、水しぶきを受けて、溺れかけましたよ。バタフライは凶暴な津波発生迷惑泳法です、はい。そんなわけで、安全なクロールを覚えました。覚えた後……ふっ、これが大人になるってことだな。と、サウナで、たそがれてたんですが。……あ、話が完全にそれてしまいました(^_^;)昨夜、すごい疲れていまして、それで気の迷いで、昔書いた短編小説を載せてしまいました(^_^;)小説『エンドレスディスピュート』 その1へ大学生のときに書いたものなので、読み返すと……恥ずかしくて、溺れかけそうになります。ちょっと長いので、おひまな、心優しい方がいらっしゃったら読んでやってください、はい(←勇気を振り絞って言ってます)。そんなこんなのはぴぶら☆幸せ探しでした♪
2007年05月16日
コメント(8)
-

神田祭をやってるのに 【はぴぶら☆しあわせ探し♪】
こんにちは、あやまです♪さっき、日記を更新したばかりなのですが……。興奮してしまいました、外にでるとお祭りやってるっっ!!お神輿(おみこし)とか、馬とかがパレードしてます♪思いっきり、練り歩いています。でも仕事しなきゃ。お囃子がとても寂しげに聞こえます。くぅ。
2007年05月12日
コメント(6)
-
一度しか言わないから…… 【はぴぶら☆しあわせ探し♪】
こんにちは、あやまです。今日はお仕事をしています。会社にひとりぼっち。そして何もやることのない昼休み。……よおし、日記の更新をしよう♪って感じで書いてます。(でも時間がないので、メルマガのネタです)僕は楽天で店長をやっています♪私店舗のことで大変恐縮なのですが……生活便利雑貨店うちのお店は少人数でがんばっているので、スタッフは仲良しです。どーんと注文が殺到したときも(お客様、ありがとうございます)みんな、とってもよくがんばって発送してくれているんです♪だから先日。外出したついでに、スタッフにケーキを買ってきました。生ものだから冷蔵庫にしまって、みんなが忘れないように、置き場所を告げようと、アルバイトさんに話しかけます。あやま「いい話だよ。一度しか言わないからよーく聞いてね」もったいぶって、ご褒美ケーキの場所を告げようとすると……スタッフ「一度しか聞かないから、よーく喋ってください♪」と屈託のない笑顔で返されました。○●○●○●○●○●○●○●二人の間に流れる笑顔の沈黙。 ↓がっくりと肩を落とすあやま。○●○●○●○●○●○●○●……うう、なんだか負けた気分。面白いことを言われ悔しがってるわけじゃあないですよ。ええ、断じて(←笑いの負けず嫌い)そんなこんなのはぴぶら日記でした♪
2007年05月12日
コメント(4)
-
小説『エンドレスディスピュート』その8(完結) 【はぴぶら☆幸せ探し♪】
こんばんは、あやまです。ちょっと、趣を変えて、短編小説を書いております。今回分は続きなので、こちらから読み始めていただけると嬉しいです。エンドレスディスピュート その1●○●○●○●○●○●○●○●○小説『エンドレスディスピュート』その8(完結) 8、「……それより」 おれは、ずっと気になっていたことを切り出してみた。「お前の学校の『水掛け事件』はどうだった? 解決できたのか?」「ああ、お兄ちゃんの推理間違ってたよ」 微笑みとともに吐き出された言葉に、おれは戸惑った。「間違ってた、だって?」「そう。事件の犯人は一匹の蜜蜂だったのよ」「……蜜蜂? なにぃ、蜂……?」「いーい、お兄ちゃん。よーく、聞いてね。真相はこうなの」 こほんと咳払いをした妹は、小学校の先生が昔話でも聞かせる風に語り始めた。「まず。事件の始まりは、あの園芸(ガーデニング)の時間です。チューリップの花の蜜を吸いにきた一匹の蜜蜂が、草むしりをしていた小鳥ちゃんの腕にとまりました。本来なら愛らしい蜜蜂も、小学生の目から見れば、注射より怖いものなんです。小鳥ちゃんは身動きもできず、声も出せずに泣き始めます。『ああ、もうだめ。刺されちゃうわ』」 妹は、しくしくと小鳥の泣き真似をした。かと思うと、やおら背筋を延ばし、おもちゃの兵隊の行進よろしく元気に腕を振り始めた。今度は拓也の真似らしい。「そこに、たまたまバケツを持った拓也くんがやってきました! 『小鳥ちゃんを助けなきゃ!』拓也くんはそう思いましたが、以前に刺された経験があり、蜂は苦手でした。拓也くんは怖くて払い除けることが出来なくて……咄嗟にバケツを振ります。驚いた蜜蜂はどっかに飛んでいって、小鳥ちゃんは刺されませんでした。ところが、気付くと水浸しの小鳥ちゃんがいましたとさ」 妹は絵本を閉じるように、ぽんと手を打ち合わせた。「はい、おしまい」「はい、おしまい、って、お前……!」「お兄ちゃん。言っとくけど、これ、亜波根小鳥ちゃんの証言と、宮野拓也くんの自白なんだからね。間違いないわよ」 おれは炊飯器を抱え、しゃもじを握りしめたまま訴える。「いいや、違うぞ。お前は純真なふりをした子どもたちに騙されているんだ!」「なによ。うちのクラスの子を悪く言うなら、許さないわよ」 妹が眉を吊り上げて、噛みつかんばかりの戦態勢をとった。おれは慌てて首を横に振る。「なぁ、いいか。よく考えてみろ。そんなの現実的じゃないし、つじつまが合わないぞ。だいたい、それなら、正当な理由のある拓也がなんで黙ってたんだ?」「『男が、蜂を怖がって思わず水をかけたなんて恥ずかしくていえねぇよ』ってさ。それに一応、理由は話してくれたじゃない。『小鳥についた二つの霊を払っただけだ』ってね。あれは、照れ隠しの『なぞなぞ』だったのよ」「なぞなぞ?」「そう。この霊っていうの、数字の『0』って考えるの。それが二つ。縦に並べてくっつけて、ごらんなさいよ。『8』になるでしょ。つまり、彼の言いたかったことは、『小鳥についた蜂を追い払っただけだ』……ねぇ、それより、お兄ちゃん、ごはん」 おれは呆然としながらご飯茶碗を渡した。いただきます、の声が小憎らしく聴こえた。「――でも小鳥は、恥ずかしいって泣いてただろう。あれはどう説明するんだ?」「ああ、小鳥ちゃん、水に濡れ時、お洋服が透けちゃって、拓也くんに見られたのがショックだったのよ。なんでも発育のいい彼女は、初めてブラジャーしてきて見られたから、もうお嫁にいけないって。古風よね……。ほら、お兄ちゃん、お味噌汁」 おれは唖然としながら、なめこの味噌汁をよそる。「それじゃあ、トイレの花子っていうのは!」「トイレの花子っていうのも、違ったわよ。単なる言葉遊びだったのよ」「ちょっと待て。答えを聞く前に考えさせてくれ」 おれは、食事もそっちのけで、紙に亜羽根小鳥の名前を書き出した。「お兄ちゃんも、よくやるわね」 妹はそんな顔で一瞥してから、カレイの煮付けを不器用に箸でほぐし始める。時々、なにか料理を褒める声が聞こえたが、おれは暗号に集中する。「くそ。小学生の作った謎なんぞに負けてたまるか! 面倒でも解いてやる!」 十分くらいはその意思も続いた。だが妹の食器の上が綺麗に片付いたころ……。「うーむ。そもそも子供の発想は大人の想像を絶する世界観があったりするもんな。解けなくたってしょがないよな、きっと。面倒だし」 おれは根性なく白旗を振った。小生意気なラスカルは、したり顔で微笑む。「お兄ちゃん。先に言っとくけど、いじめなんてとんでもなかったのよ。小鳥ちゃん、自分の名前のアナグラムを発見して大喜びで、自主的に言い触らしたっていうんだからね」「アナグラム? アルファベットを並び変えて言葉にする、あれを、小学生がか?」「最近の小学生はほとんど塾に行ってるからお利口なの。『亜波根(AHANE) 小鳥(KOTORI)』のこれをアナグラムで並び換えてみると――」「……みると?」「――なんと『TOIRE HANAKO』になるのよ」 おれは地蔵のように硬直する。妹は掌を重ねて合掌した。「はい、ご馳走さまでした。……お兄ちゃん、ごはん冷めてるわよ」 金縛りの呪縛から解き放たれたおれは喚かずにはいられない。「……なぞなぞだぁ? お嫁にいけないだぁ? アナグラムだぁ? ……そんなのやってられっか! ちっとも理論的じゃないし、論理的に繋がらないだろう!」 騒いでいるおれに対して、妹は冷静だ。食後のビールをうまそうに飲みながら諭す。「あーら。小学生なら何をやらかしても不思議じゃないって言ったのは、お兄ちゃんじゃなかったっけ?」「……ぐぅ」 腹も減ったし、ぐうの音くらいしかでない。「まぁ、お兄ちゃんの推理、理屈は通ってたんだけどね、事実は小説より奇なり、ってことかな。残念ながら、ただの、ひょうきんな推理になっちゃったみたい」「……ひょうきんな推理?」「まぁ、問題は解決したから、いいけどね。お兄ちゃんの推理は飛躍し過ぎなんだもん」 妹はいけしゃあしゃあと言ってのけた。あまりにもあんまりな言葉だ。全ての思考、全ての言語を失い真っ白になっていると、妹が忍び笑いを始めた。「おい、笑うなよ! おれだって、ない知恵を絞ってだな――!」「……ちがうちがう」 妹は、ひらひらと掌を振った。「お兄ちゃんの推理を笑ってるんじゃないって」「じゃあなんで、笑ってんだよ」「あ、うん、えっとね」 妹は、くすくすと笑い続けている。そうしてなんとも無防備な笑顔で、言ったのだ。「昔から思ってたんだけど――お兄ちゃんって、ラスカルに似てない?」 (END)○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●長い小説を読んでいただいてありがとうございました。ちょっとでも暇つぶしになれば、嬉しいです♪
2007年05月08日
コメント(7)
-
小説『エンドレスディスピュート』その7 【はぴぶら☆幸せ探し♪】
こんばんは、あやまです。ちょっと、趣を変えて、短編小説を書いております。今回分は続きなので、こちらから読み始めていただけると嬉しいです。エンドレスディスピュート その1●○●○●○●○●○●○●○●○短編小説『エンドレスディスピュート』その7 7、 次の晩。いつもより遅く帰ってきた妹から「ただいま」の声は聞こえなかった。 今日は妹の食事当番だったが、早めに帰ってきたおれが作った。それは奴の携帯電話(ケイタイ)の留守電に入れておいたから承知しているはずだ。 妹が着替えをすましている間、居間にちゃぶ台を用意して、妹の大好物を並べる。 カレイの煮付け、肉じゃが、ホウレン草のおひたし、なめこ汁。 洋食党のおれとは正反対で、妹は和食党なのだ。 ラフなトレーナに着替えた妹がやってきた。無言のまま、ぺたんと座布団に座り込む。 おれはさりげなく妹の隣を陣取りながら、よく冷えたグラスにビールを注ぐ。 恐る恐る妹の表情を窺うと――まさに顔面崩壊寸前だ。 眉と瞳が揃って垂れ下がり、唇はヘの字で、顎には何本か皺が寄っている。「お兄ちゃんっ!」 妹はホラー映画さながらの唐突さで、おれの両肩を鷲掴みにして揺さぶった。「……は、はい、なんでしょう!」「あたしは世界で一番、兄不幸な妹よ。豆腐の角に頭ぶつけて、馬に蹴られて、バナナの皮ですってんと転んでしまうべき、疫病神よ。なんて鈍感で莫迦だったんでしょう!」 おれはさんざん絶句したあげく、やっと間抜けな声を出した。「……はぁ?」「今日ね。駅で『未来のお義姉さまだった人』に偶然、会ったの」 おれはほんの一瞬、言葉というものを忘れてしまった。「……お義姉――」妹は言い直した。「――あの女、あんな人だとはおもわなかった。隣には軽薄そうな男の人を連れてたわ。あたし、黙って通り過ぎようとしたんだけど、向こうから声をかけてきたの。口には小馬鹿にしたような笑みを浮かべて『妹思いのお兄さんは元気? 落ち込んでないかしら?』なんて厭味をいうのよ」 おれは苦い思いでその言葉を聞いていた。傷口に塩を塗り込まれた気分だ。 一時は惚れたとはいえなんて女だろう。自分の女を見る目のなさにほとほと呆れてしまう。そうして心のどこかでは泣きたいほどの未練を抱えている自分が情けなくなる。 だが不快な思いをしたのは妹なのだ。きっと黙って唇をかみ締めていたに違いない。「そうか。すまなかったな、嫌な思いさせて……」「なんで、お兄ちゃんが謝るのよ!」妹は悲痛な顔をした。「ねぇ、別れた原因はあたしなんでしょ? 『結婚は妹が嫁に行ってから』とか『妹はまだ手もかかるから同居したい』とか、そんなことを積み重ねて……あたしのせいで破局しちゃったんでしょ……?」「…………」「そうなんでしょ? 本当のことを言ってっ!」「落ち着けよ、妹」おれは微笑んだ。「そんな些細なことで別れるわけないだろう。出会いに理由はないけど、別れには理由があるってな。男と女には事情ってもんがあるんだ。おれたちは別れるべくして別れたんだよ。お前なんかに関係があるものか」「嘘」即答が返ってきた。「嘘よ。お兄ちゃんが饒舌なときは、嘘ついてるときだもん」 どうして女ってやつはこうも勘がいいのだろうか。などと妙に感心している間に、妹はおれの腕を強引に掴んで、仏壇の前まで引っ張りだした。「ねぇ、天国のお父さんとお母さんに誓える?」 一瞬だけ鼻白んだ。だが、おれは次の瞬間には妹の真っ直ぐな視線を受け止めた。「……ああ。なんなら神様にだって誓うぞ」 しばしの沈黙。妹は逸らすことなく、おれを見つめている。おれも見つめ返す。 あと三秒遅ければ瞳を逸らしてしまっただろう。だが、根気負けして、重い沈黙をやぶったのは妹の方だった。妹はおれの顔を見て、ぷっと吹き出した。「なぁんだ。もう人騒がせなお兄ちゃんね。心配して損しちゃった」 根が単純な妹は素直に信じ込んだようだ。 しかし。こうもあっさりと納得されてしまうと、覚悟を決め、神様にまで背いて嘘をついた自分がとても空しくもなる。まぁ、別に構わないけど……でも。 おれは音のない溜め息をついた。 なんか最近、溜め息ばかりついている気がする。溜め息をつくと幸せが逃げるなんていうし、おれが不幸なのはそのせいかもしれない。●○●○●○(最終話 その8に続く)
2007年05月07日
コメント(0)
-
小説『エンドレスディスピュート』 その6 【はぴぶら☆幸せ探し♪】
こんばんは、あやまです。ちょっと、趣を変えて、短編小説を書いております。今回分は続きなので、こちらから読み始めていただけると嬉しいです。エンドレスディスピュート その1●○●○●○●○●○●○●○●○小説『エンドレスディスピュート』 その6 6、 両親の仏壇に線香を灯したあと、おれは座布団に座り込んだ。 やはり我が家は落ち着く。外食というのは、あんがい心を置くことができない。さまざまな疲れが重なって、もう立つ気力もなくなりそうだ。 なんだか風呂に入るのが面倒になってきた。満腹のせいか眠くもなってきた。考えてみたら明日の仕事も早かったりする。このまま、もう眠ってしまいたい。「はい、お待たせ。ご希望の熱ーい、お茶よ」 そこに愛想笑いを浮かべる妹が緑茶を運んできた。おれの分だけ、ハンドタオルを使いながらちゃぶ台に置く。おれは慎重に湯飲みを観察する。 どういう茶の沸かし方をしたのか。 緑茶はぐらぐらと煮立ち、もうもうと白い湯気が立ち上がっていた。 きっと早く真相を話せという新手の嫌がらせに間違いない。「――いいか、妹よ。よく聞け。真相はこうなんだ」 こほんと咳払いをしたおれは、大学教授のような面持ちで語り始めた。「まずは、トイレの花子さんの性質を思い出さなきゃいけないんだ」「花子さんの性質?」「どうしてトイレの花子さんは、小学校や中学校のトイレにいるのか?」「そこにトイレがあるから?」 妹のつまらなすぎる冗談は無視して続けよう。「いいか、繰り返すぞ。トイレの花子さんは、どうして、小学校や中学校のトイレにいるのか? どうして、太郎くんの幽霊じゃなくて、花子さんの幽霊なのか? どうして、血のイメージがつきまとうのか……」「どうして?」 妹は首の上のものは口以外、働かそうとしない。おれは、やれやれと肩を竦めた。「言い換える。思春期の女子トイレに血のイメージだ。何か象徴的じゃないか?」 妹が穴をあける勢いで見つめてきた。ずいぶん戸惑ったあとにやっと言葉を紡ぐ。「もしかして、女の子の――アレのこと?」「そうだ。トイレの花子さんっていうのは、少女が大人へと変わる過程においての不安な精神状態を代弁する『無意識な恐れ』の置き変わりなんだ。女子が中心になっての怪談話だというのも頷けるだろう。……かつて、子どもたちを恐怖に陥れた『口裂け女』にしろ、『人面犬』にしろ、なんらかの日常的背景がそこにあってこそ、子どもたちの恐怖の対象となりえたといわれているからな」 妹は、どういう表情をしていいのか困った様子だった。かくいうおれだって、この手の話をどういう顔で説明していいのか解らない。だから努めて真顔で続けた。「……さて。ここからが今回の事件だ。どうして小鳥が、トイレの花子さんと呼ばれていたか、ってことなんだが……実は言いにくい推測なんだが……彼女は少し発育が早いっていってただろ。つまり、小鳥は『女の子になった』ってことじゃないかと思うんだ」「小鳥ちゃんが初潮を迎えたってこと?」 おれは曖昧に頷く。熱いお茶を啜ろうとしたが、だめだ。熱すぎて飲めやしない。「小鳥は学校で突然『それ』を迎えてしまった。そこでひとつ偶発的な不幸に遭遇してしまう。拓也に恋する親衛隊にバレてまったんだ。この年代の子は早熟なことは恥ずかしいことだろ? 小鳥も秘密にしたかったはずだ。でも拓也の親衛隊たちにとって、小鳥は憎らしい存在だった。小鳥の気持ちはとにかく、憧れの拓也を奪うライバルだったんだからな。黙ってやる義理なんてどこにもなかったし、逆に仲間外れの材料にしたんだ」「それじゃあ、やっぱり小鳥ちゃん、いじめられたのね?」「ああ。でも原因は、もっと単純かもしれない。こっちも言いにくいんだが、トイレで大きい方をして、あとから入ってきた親衛隊にばれたってことも考えられる。これが男だったら直接言われて、名ざしされて、いじめられるんだぜ。でも女の子の場合はさすがに直接は言えない。だから隠喩を用いた。トイレという単語で思い付くのは、花子さん。小鳥にとって致命的なスキャンダルを持ち出すことによって、弱みを握り、拓也に近付くことを牽制したんだよ。……いじめというより、ほとんど脅迫だな」 やっと冷めてきた緑茶を啜ると、妹がいつにない暗い瞳を向けてきた。「小鳥ちゃんがいじめられてて、花子さん呼ばわりされてたことは解ったけど……。拓也くんよ。拓也くんはなんで小鳥ちゃんに水なんか、かけたの?」「それは彼女が、失禁してしまったからだ」「失禁って、えー? おもらし? そんな、小学校四年生よ。信じられない。だってトイレに行きたいって言えばいいじゃない! なにも、そうなるまで我慢しなくても――」「小鳥はトイレに行けなかったんだ。『また、アレ?』なんて、いじめられるのが嫌だったからな。だから事件の当日も、朝からずっとトイレに行かなかった。その結果、問題のホームルームの時間に限界がきても『先生、トイレに行きたいです』っていうのは絶対に言えなかった。いじめっ子を含むみんなの前だからな。かわいそうに、おとなしい彼女は極限まで我慢してたんだ。そして、ついに臨界点を突破してしまった」「じゃあ、拓也くんが水をかけたのは……!」「そう、小鳥のそれをごまかすためだ。そのあと小鳥が『拓也に会いたくない、恥ずかしい』と言ったのも解るだろう。クラスのみんなに会いたくないんじゃない。拓也に会いたくないって言ったのは、つまり彼には失態を知られていて会わす顔がなかったからだよ」「……だけど、お兄ちゃん。それはあくまで推測で……」「状況証拠もあるぞ。お前が振り向いた時、小鳥は蹲って泣き出したのではなく、泣いてたって言っただろ。変だと思わないか」「……えっ……?」「もしもいきなり水をかけられたりしたら、ふつうは自分に何が起こったかも解らず、呆然としたりしないか? それなのに水音がして振り向いた時、小鳥は蹲って泣いていた。……それが意味するところは、水をかけられる前に、すでに小鳥は蹲って泣いていたってことだろう」「……あっ!」「手荒な手段ではあったが、拓也は立派な男だよ。自分が悪者になっても構わないって、じっと沈黙を守り、小鳥を守ったんだからな。きっと拓也は、小鳥がいじめられてるのを知っていたんだ。自分が原因だとも密かに気付いていたのかもしれない。二つの霊にとりつかれているなんて言った理由ももう解っただろう? 拓也は、花子呼ばりされている小鳥のいじめを先生に知って欲しかった。そして、今回のおもらしのことを黙殺して欲しかったんだ。拓也は『小鳥のプライドのために真相を胸に秘めていなければいけない』という思いと『先生には本当のことを言わなければいけない』という良心の狭間で板挟みにあい、結局『二つの霊がとりついていたから払っただけだ』なんて謎掛けをしてしまった。……最後に拓也は先生に頼ったんだよ……」 おれはゆっくりと息を吐き出した。「これがお前のクラスで起こった『水掛け事件』の真相だ」 予想はしていたことだが、目の前には放心する妹がいる。「そんな……拓也くんは、悪いことをしてないのに、みんなに責められて、あたしにも説教をされて、それでも小鳥ちゃんのこと守っていたなんて……」 妹は、空気の抜けた風船のように、弱々しく息を吐きだした。「……なんでなんだろうな。あたし、良い先生になりたいのになぁ」 妹は無理に微笑もうとした。だがそれは成功しなかった。「どうしてかな。いつまでたっても、情けないくらい……未熟なのよね……」 おれに言葉はない。考えれば考えるほど、言葉が遠くへと飛んでいく。 妹はテーブルに額を擦りつける。そして顔を伏せたまま立ち上がった。「……お兄ちゃん、ありがと。もう、寝るね」 決して瞳を合わすことなく、妹は自分の部屋へと消える。 ばたんと扉の閉まる音がやけに大きく響いた。結局、最後に妹の表情を窺うことはできなかったが、薄いドアを通して、妹の嗚咽は聴こえてきた。その泣き声は、両親が交通事故に遭って、帰らぬ人となった、あの時のことを思い出してしまう。 ――あの時と同じだ。おれはどうして、いつも無力なんだ……? そうして、おれはただ何もできずに、湯飲みの底に残ったお茶を見つめているだけ。●○●○●○(その7に続く)
2007年05月06日
コメント(0)
-
小説『エンドレスディスピュート』 その5 【はぴぶら☆幸せ探し♪】
こんばんは、あやまです。ちょっと、趣を変えて、短編小説を書いております。今回分は続きなので、こちらから読み始めていただけると嬉しいです。エンドレスディスピュート その1●○●○●○●○●○●○●○●○小説『エンドレスディスピュート』 その5 5、 ……真面目に考えるのも、ばかばかしくなってきた。 だいたいどうして同じ血を引く兄妹で、こう性格も体質も違うのだろう。 酒の飲めない兄は、妹の問題に頭を悩ませている。 酒豪の妹は、時々こちらを見て、まだ結論がでていないとを知ると残念そうな顔をして、酒を飲む。またグラスを空にして、兄の様子を窺い、落胆し、真剣にメニューを睨む……。 この酒はもう何杯目だろう。まさかこの店のカクテルの全種類制覇などしようと考えているのではなかろうか。酒を飲んでいないおれの方がくらくらしてきた。 ちなみに今の妹の飲み物はギムレットカクテルだ。その乳白色の酒の色と同じく、おれの頭の中も真っ白である。五里まで覆われた深い霧の中を、彷徨(さまよ)っている心地だ。 なにかが間違っている。こんな話、大失恋を経験した当日に聞かされているおれこそ不幸だ。親父とおふくろの幽霊がここに現れて妹の無駄話に付き合ってくれまいか。 そんな莫迦(ばか)なとも考えた。「……ん……?」 でも、あながち愚考でもなかった。おれはあることに気付いて、妹に問いかける。「……拓也の言い訳の『二つの霊』ってなんだろうな。拓也の言葉を鵜呑みすれば、なにかの霊を水で払う。水ごりってことだろ」「みずごりぃ?」「よく僧侶の修行なんかで白装束を身に纏って、えいや、っとばかりに頭から冷水をかぶって身を清めるだろう。あれだよ」「ああ、うん。あれね」「何か悪いことをした小鳥のため――彼女の汚れを浄化するために、水をかけたとか考えられないか? 悪霊といわないまでもなにかこう……」「うーん、悪霊ねぇ」と、そこで妹は大声をあげた。「あっ、そっか! 花子さんよ、お兄ちゃん!」「なんだよ、藪から棒に」「小鳥ちゃん、そう呼ばれてたんだわ!」「花子さん? おい、お前の学校じゃ、そういうのが流行(はや)ってるのか?」「ううん、流行ってるのは『なぞなぞ』と『言葉遊び』それに『ドッヂボール』かな」 また脱線だ。妹はふるふると首を振って続ける。「でも、あのね。三日くらい前に、ごく一部の女子が、小鳥ちゃんのこと『花子さん』って呼んでたの。なんでそういう風に呼ぶのって聞いたら、トイレの花子さんだって」 トイレの花子さん。 それは知名度の高い、学校の怪談だ。 トイレでしゃがみ込むと、どこからともなく『赤いチャンチャンコと青いチャンチャンコのどっちがいいか』なんて不気味な声がする。赤を選べば全身を切り刻まれ真っ赤な血を流し、青を選べば逆に血を絞りとられ真っ青になる。ぞっとしない話だ。「……トイレの花子さん、か……」「でも、あたし、そういうこと言うのやめなさい、って女子に注意して、もう解決したのよ。それに今日の『水かけ事件』とはなんの関係もないでしょ?」 おれは沈黙を返事とする。 亜波根小鳥は、水をかけられた。 亜波根小鳥は、花子と呼ばれていた。 その二つは見えない鎖で複雑に絡み合っているような気がしてならない。 そもそも彼女に水をかけた、拓也の動機はなんだろう。 もし今回の犯人が女子だったというのなら、水が高いところから低いところを目指すように、しごく当然で結論も早い。 いじめだ。 だが、水をかけたのは拓也だ。宮野拓也という少年――彼までもが、いじめに参加していたというのか。妹の話をきくかぎり、なんとなくしっくりこない。 ではなぜ罪のない小鳥に、拓也は水なんてかけたんだろう?「やっぱり、いじめだったのかな。あたし、解決できてなかったのかな……」 おれが黙り込んだせいか、妹が不安そうに問いかけてきた。「大切なことはそんなに急いで答えるもんじゃない」 おれは近くを通りかかったウェイトレスに、ウーロン茶を頼む。ついでとばかりに妹も注文する。ブラッディ・マリだ。 すぐに黄金色の液体と、血のように赤い液体が運ばれてきた。 その二つをぼんやりと見つめながら、おれは問う。「つかぬことを聞くけどな」 妹の口調を真似てみた。「小鳥はふつうより背が高くて、大人びた、かわいい女の子だろ。もしかしたら拓也は小鳥に気がある素振りだろう」「うん、そうね。小鳥ちゃん、発育はいい方よ。それに拓也くんが小鳥ちゃんに気があるって、あたし言ったっけ? お兄ちゃん、どうして解ったの?」 こんな推理なら誰にでも出来る。問題はこれからだ。この不可解な事件を整理してみようと思い、おれはウーロン茶で喉を潤す。 太陽が雲間から顔を出し霧が晴れていくように、謎がその輪郭を現した。「……なるほど。気付いてしまえば簡単な結論だな」 妹は大きく目を見開いて、テーブルを叩いて立ち上がる。「お兄ちゃん、解ったの!」「まぁ、一応な」「ねぇ、どういうこと? どうして、拓也くんは小鳥ちゃんに水をかけたりしたの?」「それはだな――」 言いかけて、小説の中の名探偵は真相をすぐに語ったりしないことを思い出した。それによく考えれば慎重に話さなければいけないデリケートな問題でもある。 おれは痒くもない頭を掻いた。「……熱いお茶が飲みたい。ひとまず家へ帰ろう」●○●○●○(その6に続く)
2007年05月05日
コメント(0)
-
小説『エンドレスディスピュート』 その4 【はぴぶら☆幸せ探し♪】
こんばんは、あやまです。ちょっと、趣を変えて、短編小説を書いております。今回分は続きなので、こちらから読み始めていただけると嬉しいです。エンドレスディスピュート その1●○●○●○●○●○●○●○●○小説『エンドレス・ディスピュート』 4、 どうして洒落が解らないのか。 妹は真面目にきいてくれないと拗ねてしまい、アルコールの注文も激しくなった。 この頃になるとウェイトレスも、注文の消化される肝臓を把握したらしい。おれの前にカクテルを置くことはなくなった。ただウェイトレスは、おれのグラスの水を足しながら、「一時間カクテル飲み放題二千円也とはいえ、相棒さんは飲み過ぎじゃない。大丈夫?」と不安げな瞳を向けてくるばかりだ。 妹は青い(ブル-)珊瑚礁(ラグーン)カクテルを、両手で大事そうに包み込み、そっぽを向いている。 何を言っても口を利いてくれなくなった妹の横顔を見ながら、アライグマはあの愛らしい風貌とは裏腹に、実は凶暴で怒らせると手に負えないというイヤな事実を思い出した。 やはり、ここは兄のおれが折れるしかないか。「解ったよ。それじゃあ、拓也はなにか根拠があってやったとしよう」 待ってました、とばかりに妹は瞳を輝かせた。「そう! 拓也くんには、やんごとなき理由があったのよ!」「ああ、そうだ。きっと、拓也には、わけがあったんだ」 そうは言ったもののやっぱり、悪戯で水をかけた、それだけのことだとおれは思う。 だが、真実は小説より奇なり、なんて手垢にまみれた言葉もある。 想像を巡らせば何か予想もつかない真相が、恥ずかしがりやの子供のように、顔を覗かせることもあるかもしれない。それにもしも最後に残った可能性が、やはり悪戯だったというなら、頑固で強情っ張りで天の邪鬼な妹もさすがに真実を受け止めるだろう。 ……とにもかくにも。問題は原点に戻そう。「どうして、拓也は小鳥に、バケツの水をかけたのか?」 誰にともなく、そう問いかけた。 おれは灰色に染まった脳細胞を活性化させて、唇を開く。「つまり、拓也は真犯人をかばったんだ。蹴躓(けつまず)いてバケツの水をかけてしまった真犯人が先生に叱られるのを防ぐため空のバケツ奪い、犯人を買って出た」「あたしが振り向いたの、水音がしてすぐよ。でも蹲って泣いてた小鳥ちゃんの近くには拓也くん以外、誰もいなかったもん。そこから立ち去る時間はないわ」 あっさりと却下される。なにを負けるものか。おれは次の推理を吐きだした。「犯人は何かの騒ぎが必要だったんだ。この後のドッチボールを阻止したかったからな」「草むしりの後のドッチボール、生徒達には言ってなかったんですけど」 はい、次。「じゃあ、小鳥を着替えさせたかったんだ。実は、洋服のプレゼントするつもりで、その口実づくりのために……」「服のプレゼント? 拓也くん、小学生よ。非常識だわ」 しばしの沈黙。おれの灰色の脳細胞が、少しずつ白くなっていく。「そう、このごろの陽気は暑かろうと、小鳥に水浴びをさせたかった」「まだ五月よ。水浴びするほど暑くないでしょ」「……そうそう。ニキビ面の小鳥を干からびたジャガ芋と間違えて、思わず、バケツの水をかけてしまった」「もぉ、失礼ね。小鳥ちゃんは色白でかわいい娘なのよ、『人魚姫(リトルマーメイド)』みたいにね」「あ、そうか。小鳥は人魚で、水をかけられると魔法が解けて、正体を現すんだ。それで、正体を暴くために……あれ、そんな映画があったぞ。『スプラッシュ』だったかな?」 縄張り荒らしの不心得ものを威嚇するように、妹が睨み付けてきた。「もぉ、お兄ちゃん、ちゃんと真面目に考えてくれてるっ?!」 その実は小学生の『帰りの会』レベルの些細な問題である。にもかかわらず、それらしい真実を無理やり捏造している兄に、なんて理不尽な台詞だろう。「ええい、事実は、ただの悪戯だよ!」 そう叫んでしまいたい気持ちを冷めきったカプチーノと一緒に流し込み、おれはひとまず正論を宣った。「あのな、お前のクラスの問題だぞ。お前も少しは考えろよ」「…………」 妹は初めて、そう、水でもかけられたように我に返った。気まずそうにおれの顔色を窺ってから、食べ物を抱えて水場を探すアライグマのように神妙な顔で、唸り始める。 その唸りはしばらく続き、唸り疲れたように妹はテーブルに突っ伏した。 それから、何か大切なことに気付いたようだ。 妹は空のグラスを握りしめ、誰かに手を上げる。「あの、すみません。青紫のお酒(バイオレット・フィゼ)くださーい」●○●○●○(その5に続く)
2007年05月04日
コメント(0)
-
小説『エンドレスディスピュート』 その3 【はぴぶら☆しあわせ探し♪】
こんばんは、あやまです。ちょっと、趣を変えて、短編小説を書いております。今回分は続きなので、こちらから読み始めていただけると嬉しいです。エンドレスディスピュート その1●○●○●○●○●○●○●○●○小説『エンドレスディスピュート』 その3 3、「………………」 四分休符が九つ打てるくらいの沈黙が訪れる。 おれは意味もなく屋根裏天井を仰いだ。たった今、気付いたことなのだが、店内にはE(エリック)・サティの『三つのジムノペディ』のピアノが静かに流れていた。あまりにも場違いな会話を申し訳なく思ったのはきっとおれだけだろう。 このサティの切ないピアノの旋律に耳を傾ける気も、訪れた沈黙の意味を悟る気もない妹は、新しいカクテルを頼むためメニューに手を伸ばす。 まだ酔った兆候も見せていない妹に、おれは問い正す必要はありそうだ。「重ねて聞くが、どこが不可解なんだ?」 妹はメニューの上から、驚いた顔を半分だけ覗かせた。「なに、お兄ちゃん」「いいか、妹よ」おれは声を抑える。「今の話に不可解なんてどこにも存在しないだろう。事件と言ってもどっかのワルガキが芸能人みたいな名前の女の子に水をかけただけだ。水をかけるなんて典型的な悪戯だし、犯人も小学生だ。四年っていったら、九つか十だろ」「さっき、満十歳って教えた」 不機嫌そうに妹が答えた。「……と、とにかく。十歳なんて、まだ産毛も生え変らない子供だし、物心も自覚なんかもほとんどないだろう。どんな間違いでもありえる年ごろだぜ。大体、些細なことだ。水をかけるくらい……水をかける?」 ――水をかける……。 いやなことを思い出してしまった。 今日の昼休みのこと。おれは、ある女性と喫茶店で落ち合った。 ある女性とはいうまでもない、妹が『未来のお義姉さま』と慕っていた女性で、今日の午前中まではおれの恋人だった。 こう言うと負け惜しみみたいに聞こえてしまうかもしれないが、三日前までは二人の間には何もなかった。おれは彼女の長所も欠点も残らずに愛していたし、向こうもそうだと信じ込んでいた。喧嘩の原因だって、じっくりと話し合えばいずれは解決する問題だった。 ところが話し合いすら成立しなかった。百歩譲った俺に対しても彼女は一歩すらも譲ろうともしない。彼女は街中の人間が振り向きそうな大声でさんざんなじったあげく、いきなりコップの水を浴びせてきた。 それは不幸にも恋の破局のしるしであった。さらに不幸なことにコップの中の硬い氷を顔で受けて、当たりどころが悪かったのか、殴られたように目の下が腫れてしまったのだ。「……人に水をかける奴なんて……」思わず力も入ろう。「ロクな奴じゃない!」「それがね。お兄ちゃん、ロクな奴なのよ。だから、不可解なの」 妹は空のグラスを握りしめたまま、グラス一杯分くらいの溜め息をついた。「空のバケツをもっていた男の子――宮野(みやの)拓也(たくや)くんっていうんだけど、クラスの人気者で女子からきゃーきゃー言われてるの。……確かに、うちのクラスには、お兄ちゃんいう通り、そういう信じられないような悪戯する子もいるけど、拓也くんは絶対にそういう子じゃないの。女子には、ちょっとぶっきらぼうなとこもあるけど、優しくていい子なのよ。今日だって、バケツの水汲みなんて、みんなが面倒に思う仕事もやってたわ」「……ちょっとおれのイメージとは違うな」「うん、そうでしょ。だから、水浸しの小鳥ちゃんを見たとき、あたし、拓也くんが何かの拍子に転んじゃったんだと思ったの。そこに、たまたま小鳥ちゃんがいて被害にあってしまっただけ――それは事故なんだって……」 妹はまた溜め息をつく。今度は、ボトル三本分くらいの盛大な溜め息だ。「でも、違ったの。故意にやったらしいの。今日の拓也くん、別人みたいだったわ。一応、小鳥ちゃんには謝りはしたけど、全然反省もしてなかったし、どうしてそんなことしたのかって理由を聞いたら、あたしのこと怖い顔で睨み返してきさえしたのよ」「お前は拓也を怒らなかったのか?」「そりゃあ、普段は温厚で思慮深いあたしだって、もう湯気がでるくらいに怒ったわよ!『ねぇ、拓也くん、そういうことしちゃだめでしょ』ってね」 ねぇ、そういうことしちゃだめでしょ、ときたか。なんて迫力のない奴だ。これで小学校の先生なんて勤まるんだろうか――いや、きっとなんとかなるんだろうなぁ。「そう、強く叱ったあとも大変だったのよ」 妹は小さな握り拳を振った。「拓也くん、そんな反省のない態度だから『帰りの会』じゃあ、小鳥ちゃんがかわいそうだってクラスの子に非難されるし、『拓也くん命』の女子は言い過ぎだって泣くし、保健室で着替えてる小鳥ちゃんは『恥ずかしくて、拓也くんには会えません』って教室に帰らず泣くし……もう、あたしも泣きたかったわよ」 妹の睫の奥が潤み始めた。こいつにまで泣き出されてはかなわない。こういう時は話を促して、妹の気をそらせるに限る。「で、結局、お前はどうしたんだ?」「……ああ、うん。クラスのみんなは下校させて、拓也くんだけ残したの。本当の理由を聞きたかったからね。でも拓也くんは相変わらず、黙秘権。あたし、生まれて初めて生徒に説教ってもんをしたわ。職員会議を遅刻してまでもよ。……でも馬耳東風ってやつ。いい加減、怒る気力もなくしちゃって、もう帰そうと思ったの。そうしたら拓也くん、最後にぺっちゃんこのランドセル背負って、ものすごくショックなこと言ったの」「ショックなこと?」 妹は口紅の塗られていない唇を尖らせて言う。「『小鳥に、二つの霊が憑いてて、追い払っただけだ』」 妹はテーブルに顔を突っ伏す。目に見えて落ち込んでいる。「あたしは彼のことを心から信頼していたのに……それなのに……」 さて。どうやらここで、妹の話は一段落したらしい。 おれはかねてから決めていたように、同情したふりをして慰める作戦行動を始めた。「まぁ、そんなこと言われればショックだよな。もっとまともな言い訳だってあるだろうに。所詮、小学生の浅知恵か。水をかけたのも出来心ってやつだな。そう落ち込むな」 すると妹が外国語でも聞いたように驚いて、顔をあげた。「お兄ちゃん、違う。あたしのショックは生徒を信じ切れなかったことよ」 今度は、おれが驚いた顔をする番だ。「……おい、正気か。どう考えたって、下手な――それもとびきり下手な言い逃れだぞ」「違うわ、お兄ちゃん。たった今、気付いたの」「……たった今って? 一体、何を?」「へんな言い訳だからこそ、なにか訳があるってもんよ。拓也くんの言葉には、きっと隠された真実があるのよ。あれは彼のメッセージだったの……あたしだけへのね」 きっぱりと妹が言い切った。その熱い瞳に紙でも近付けようものなら、ボッ、と音を立てて燃え上がることだろう。妹は熱血教師よろしく情熱をめらめらと燃やしている。 おれは頭痛がしてきた。「……お前の思考は飛躍し過ぎてる」「なによ、お兄ちゃん! もしかして、あたしの生徒のこと悪く言うつもりぃ?」 今度は居直りだ。こうやって頑なに唇を結んだら、考えを曲げないのは解っている。 ――なんで女ってやつは、ひとりよがりで、わがままばかりなんだろう。 きっと占い師なら、今日のおれの運勢を『女難の相』とでも告げてくれるだろう。いや『水難の相』というべきか。今日が水曜日であることも、この場所が『水鳥の楽園』であることも、昼間に彼女に水をかけられたことも、そして妹に『水掛け事件』の話を聞かされていることも、全てが不吉で不幸の前兆のようだ。 溜め息も出やしないが、おれは自分の心を騙す。この重苦しい空気を変えることにした。「もう、この話はやめよう。このままじゃ、エンドレス・ディスピュートだ」「……えんどれす……? えっ、なに、お兄ちゃん」 妹が目を丸くするのを見計らって、おれは言った。「水掛け論(エンドレス・ディスピュート)になっちまう」●○●○●○(その4に続く)
2007年05月03日
コメント(0)
-
小説『エンドレス・ディスピュート』その2 【はぴぶら☆幸せ探し♪】
こんばんは、あやまです。ちょっと、趣を変えて、短編小説を書いております。今回分は続きなので、こちらから読み始めていただけると嬉しいです。エンドレスディスピュート その1●○●○●○●○●○●○●○●○小説『エンドレス・ディスピュート』 2、 カフェバー『水鳥の楽園』(ウォーターバードパラダイス)は、その名に相応しく、造り物のカルガモたちで溢れていた。 屋根裏天井にも、カウンターにも、ステンド窓の脇にも、丸い瞳のカルガモたちが群れをなし「ぐわぁーぐわぁー」と童謡でも歌い出さんばかりにクチバシを開いている。 底抜けに明るい店内は、大人の集う酒場とはとても思えない。もちろん、こんなヘンテコな店を選んだのは、変わりものをこよなく愛する妹だ。 当の妹は長椅子に身を預けながら、新緑色の液体の揺れるグラスを指先で摘んでいた。 メニューと照らし合わせたところによると、このカクテルはカルーソーというらしい。 妹はカルーソーで口を湿らせてから、語り始める。「今日のホームルームの授業は、園芸にしたの」「園芸? ずいぶん、じじむさいな」 せっかく始まった話の腰を折ってしまった。妹は頬を膨らす。「……じゃあ、ガーデニングよ。学年ごと、クラスごとの花壇があってね。今日は、伸びかけた雑草をむしって、水をあげたの。そういうことって情操教育には大切でしょ」「お花は大切に育てましょう、ってことか」「ううん、お花じゃないの。うちのクラスが植えたのは……えーと――馬鈴薯(ばれいしょ)」「馬鈴薯――ジャガ芋か? 素直に、ジャガ芋って言えよ」 少し呆れて言うと、妹は何が恥ずかしいのか顔を真っ赤にした。「だって、またじじむさいっていうじゃないよぉ。もう、いいのっ。他の先生たちみたいにヒマワリやらコスモスやらを植えたって、蜂や蝶のエサになるだけよ。それよりは、みんなで食べれるジャガ芋、植えた方がいいでしょっ。いいったら、いいの!」 なるほど。ムキになるところをみると、先輩の教師たちにも笑われたらしい。 それにしてもこいつは、情操教育の意味を理解しているのだろうか。そもそも、こんな頼りない妹が本当に教職免許なんて資格を取得できたのだろうか。 様々な謎を残しつつも、おれは話を促した。「……で、続きはいつ聞けるんだ?」「あー、うん。クラスのみんなはね。『えーっ、草取りぃ?』って、不満そうだったの。でも、草むしりを終えたら残りの時間で、みんなの大好きなドッヂボールをしてあげようって考えてたのよ」 明るい口調もそこまでだった。その表情の雲行きは怪しくなった。「……けど。ドッヂボールは結局できなかったわ。……授業の途中で起きたのよ。あたしの教師生活一年と一ケ月の間でも、想像を絶する不可解な大事件が」 おれの好奇心がぴくりと耳を立てた。 想像を絶する不可解な大事件。なんて響きのいい言葉だろう。「最初はあたし何が起こったのか解らなかったのよ、お兄ちゃん」 妹は頼るような瞳で、おれを見つめた。「いきなり、ざっばーん、って音がして、あたしが振り返ると、水浸しの小鳥(ことり)ちゃん――あ、これ、生徒の名前ね――亜(あ)波根(はね)小鳥(ことり)ちゃんが蹲って泣いていたの。ねぇ、お兄ちゃん。こんなことって信じられる? 小鳥ちゃんは頭からバケツの水をかけられたのよ!」 妹がふいに話を断ち切ったものだから、おれは妹の瞳に問う。「……それで?」「それでって、終りだけど」「おい、どこが『想像を絶する不可解な大事件』だっていうんだよ!」「なによ、不可解な大事件じゃない!」 負けじと妹が怒鳴り返してくる。そこでおれは、ぽんと膝を打った。「ああ、そうか。彼女の半径十メートル以内には何人も存在しておらず、何人が水をかけたのか、その犯人がまるっきり解らないっていうんだな?」「ううん。近くに空のバケツを持っている男の子がいたわ。きっと彼が犯人よ」○●○●○●○(その3に続く)
2007年05月02日
コメント(0)
-
小説『エンドレスディスピュート』 【はぴぶら☆しあわせ探し♪】
こんばんは、あやまです。どうやら今回の日記で200個目のようです。何か記念企画を……と思ったのですが、思いつかず、結局、24歳のときに書いた短編小説を載せることにしました。なんかちっとも記念になってないような(^_^;)ちょっと長いものなので、お暇な方がいたら読んでやってください♪○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●小説『エンドレス・ディスピュート』 1、グラスの中の氷を噛み砕きながら、妹がボヤいた。「男って、信用できるもんなの?」 おれは怪訝に思って店内を見渡してみる。妹の前にはおれしかいない。それでやっとこの兄に恋愛相談を持ち掛けているのだと気付いて、おれは居住まいを正す。「……いいか、妹よ」 おれは食べ終えたばかりのパスタ皿を通路側に寄せた。「男はもちろん、女だって信用ならんぞ。だが恋愛なんて遠距離ドライブみたいなもんだ。交通渋滞にあい、赤信号で止められ、途中、道にも迷うだろう。だしぬけに猫が飛び出して急ブレーキを踏んだり、卑怯な検問に嵌まってキップを切られたり、想像もしない巻き添え事故にあうことだってあるし、目的地に着く直前に助手席の相手をインターに置き忘れていることも……あ、すみません」 大事な話の途中で食後の飲み物がやってきてしまい、おれは口を噤んだ。 ウェイトレスは兄妹の顔を見比べて、ブランデースマッシュをおれの前に、カプチーノは妹の前に置く。ミートソースで汚れたパスタ皿を重ねて銀色の盆に載せると、「どうぞ、ごゆっくり」と満面の愛想笑いを見せてから、カウンターの向こうに消えた。 それを確認してから、おれは鹿爪顔で続ける。「つまりだなぁ、おれの言いたいことは――」「つかぬことを聞くけど」 妹はさっきのボヤきはどうでもよくなってしまったようで、つぶらな瞳を輝かせた。「未来のお義姉さまと、喧嘩でもしたの?」 おれは平静を保てない。「な、なんで、それを……」「だって、今日のお兄ちゃん、そこはかとなく暗いもん。それに目の下のとこ赤く腫れてる。まるで殴られたあとみたい」「な、殴られてなんか――」おれは無意識に頬の痛みに触れ、溜め息をついた。「――ああ、そうさ。あいつに殴られたようなもんだ。どうせ、おれはフラれちまったさ」「えー、まさか! 本当に、お義姉(ねえ)さまと破局をむかえたの?」 自分で言ったくせに妹は、いささか驚いているようだった。「なんで愛想尽かされたの? お兄ちゃんが安月給だから? 甲斐性なしの根性なしだから? 童顔で二十五にはとても見えないから? それとも靴下の匂い嗅ぐから? あ、解った、お節介やきで、理屈っぽいからでしょ、ねぇ!」 このまま妹の悪口を放置したら、暗く冷たい日本海溝の底より深く落ち込むことになってしまいそうだ。おれは切実に叫ぶ。「うるさい。お前には関係ないんだ。頼むから、ほっといてくれよ」 妹はやれやれと大袈裟な素振りで肩を竦める。 それからテーブルに身を乗り出して、おれの前に置かれたブランデースマッシュを手元に引き寄せ、おれには手元のカプチーノのカップを寄越した。「まぁ、女なんて星の数ほどいるわよ」 そして妹は、おどけた口調でブランデースマッシュのグラスを掲げる。「――お兄ちゃんの明日の恋に乾杯」 こぼれんばかりの笑みを湛えて、グラスを傾ける妹を尻目に、おれは仏頂面を決め込んだ。カプチーノをシナモンスティックで掻き混ぜつつ、舌の上に悪態をのせる。 ――人の不幸を面白そうにしやがって、このラスカルめ。 昔から思っていたことだが、妹はどことなく懐かしのアニメ『あらいぐまラスカル』に似ている。間の抜けた無邪気な顔といい、癖毛の撥ね具合といい、本当にそっくりなのだ。 ただ、このことは本人の前で言ったことはない。アライグマに似てるなんて聞いたら……それこそ隠れた野生をムキだしにして怒りそうだったからだ。「お兄ちゃん、なんか言いたそうな顔ね」「別に、なにも」おれはカプチーノを飲んで、ごまかした。「それより。お前が信用を疑う男って、どんな男なんだ?」 妹は、やっと自分が悩んでいたことを思い出したようだ。「うちの四年二組の男子、満十歳!」 乱暴にグラスが置かれる。妹の剣幕に合わせて、テーブルの端、ガラス細工のカルガモがびっくりしたように、ぴょんと跳ねた。「なんだ、男って、お前のクラスの教え子か」 置物のずれた位置を微修正しながらおれは苦笑する。「もぉ、お兄ちゃん、笑い事じゃない。事態は深刻なの!」 妹はいつのまにか空になったグラスを振り回した。「ねぇ、聞いて。うちのクラスで前代未聞の大事件が起ったのよ!」○●○●○●○(その2に続く)
2007年05月01日
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1