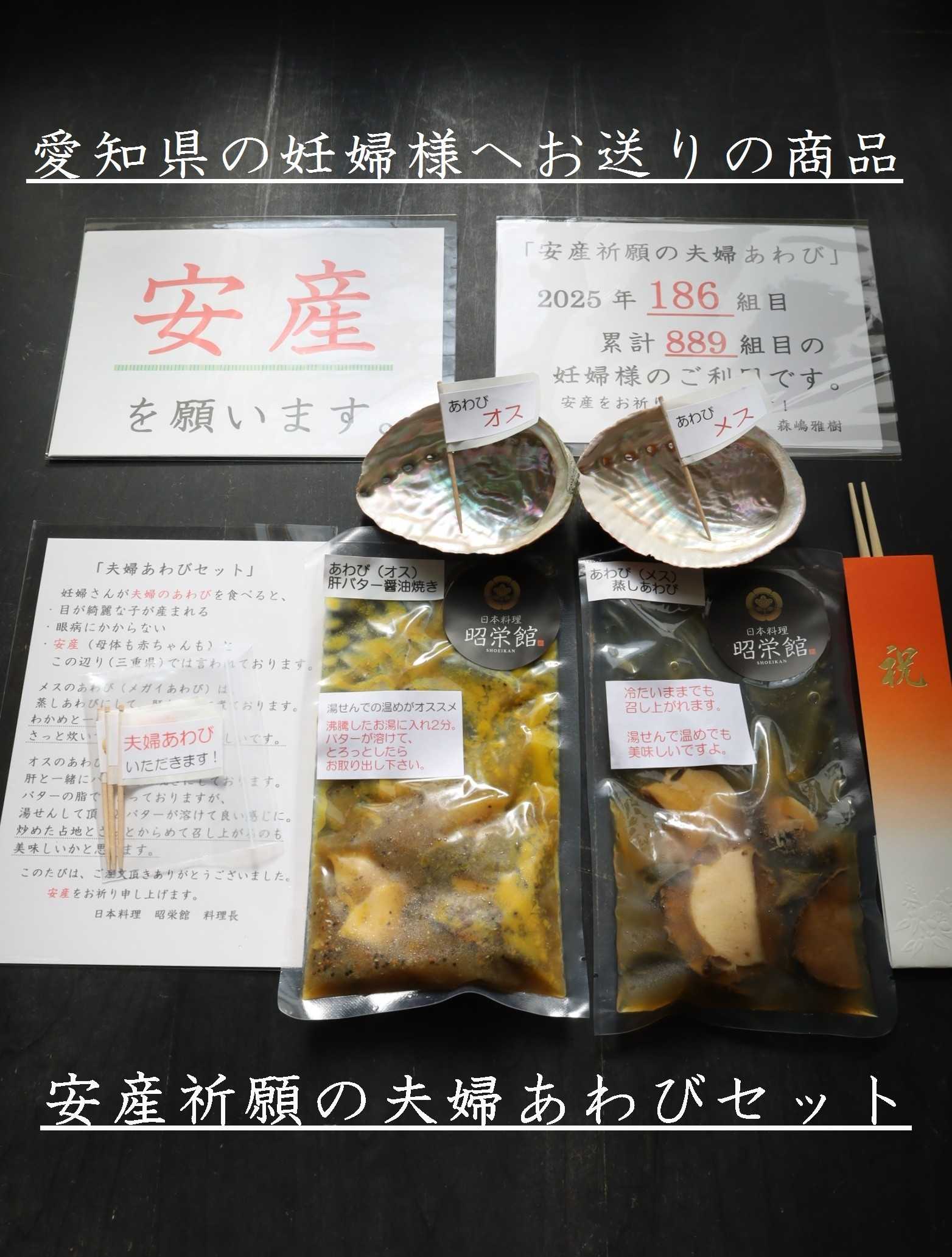2009年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
わたしの先生 2
わたしにとって先生はわたしのなぜに答えてくれる人ばかりでなく、一緒にいる時、お話をしている時、私の心の中になぜ?を落としていく人。彼らはとってもユニークわたしの普通の考えから離れたところで行動する、お話をする。ほんの10年前、いやいや5年前の私なら??それおかしいのと違う?と思って考えようともしなかった。そんなことを運んでくる人が今のわたしの大切な先生。彼らは私の持つ常識をひっくり返すし、打ち破る。時に私の心は相当やられて、へとへとになったり、ドキドキしたり・・・そうなると私の心の中でさらに大きな何で!が生まれているでも時間が経ってよくよく考えてい見ると彼らはその何で!の答えをちゃんと伝えてくれているその言葉を聞き逃しているのは私でその言葉の意味に気がついていないのも私だったそうと思ったとたん、何で!はわたしにとって当たり前のことに・・・自分の努力で学ばなければならない、とか学ぶための努力が必要とよく言われるけれども、学ぶ態勢のない日常の現場では、突然に何で!が振りかけられ、まずたじたじとなるものなんだ。誰もそれが学ぶ場なんて思いもしない。とんでもないことやんか~~どうすることもできなくて、ゲッとなった思考停止状態の真っ白こそ、新しいことを考えるにふさわしい環境なのかもしれないということで、最近無理やりっぽいけど私の常識は薄く延ばされつつあることに気がついた。そういうなぜを落としてくれる誰かさんとたまに出会えるのを楽しみにしている(たま~~でないとちょっと大変・・・)
2009.01.31
コメント(2)
-
Mも試験!
今年は卒業も入学なくて受験もなくてなんて楽なの~なんて思っていたら実は違った。ひそかに二女のMは卒業、そして国家試験があるではないか!そのMもなぜかPCの前で勉強しているあれ、その勉強方法Mが高2のSに伝授したん?M「ち、違うって!私はPCでは調べものか お絵描きか メールしかしないんだから。Sがわたしに教えてくれたんです。」その彼女も卒業を控えて、かなりの紆余曲折があった。まず、看護師にはなれない~ 一日中病院にいるなんて無理!そして学校の先生からも「あなたは看護師さんというよりは研究者向きよね」なんて言われて よ~~し、大学院にいくぞ~~ といろいろ自分に向きそうな大学院を探して受験したんだけれど、看護学じゃないから バツ!!しかも彼女ってほかの道を全部断ち切って大学院受験していたの。ふつうはだめだった時のことを考えて、第2、第3の道を用意するよね。 大学受験で何を学んだのかなぁ~ってちょっと不思議に思った。就職先や進学先の決まっていないのが実はMだって知って、先生たちはびっくり仰天「なんで、Mちゃんが??」で、彼女の志を知ってくださっているから、あっちでこんな募集があるよ、これはどう?とかみんなに応援してもらってきたこの何ヶ月間そのうち、やっぱり志のためには看護の経験は不可欠だ、と思いだしたMは病院にアタックして、とうとう今日内定の通知をいただきました。そこには 「国家試験には万全の態勢で臨み、体に気を付けて良いコンディションで病院勤務に入ってください」とのお達しが・・・ほらほら、PCの前で勉強してたらあかんで~~!
2009.01.30
コメント(10)
-
わたしの先生 (1)
久しぶりに広島のシスターからメールをいただいた。昨日私が出したメールのお返事なんだけれど、冒頭は「今日はどうしてもメールしようと思っていたところでした。先に戴いていて恐縮の限りです。」うん、彼女と私は不思議と場所は離れているけれど互いの必要はシンクロしていて、いつもこんなやり取りで始まる。本がきっかけで友人になったシスターだけれど、今は何と言ってもたびたびこのブログにも登場してもらっているSちゃんの中学高校の時の校長先生だった、ということで三人の間をメールやお手紙が行ったり来たりしている。もう退職されてお年もたぶん70前後でしょう。ある時のメールには「今から入門講座(キリスト教のことを知りたい人のための勉強会)に行ってきます。久々に緊張だわ」ておっしゃって、とても校長先生だったなんて思えない。自分を良くも悪くも装わないで、そのまんまを伝えて下さる。その素直さが大好き!入門講座に向かわれるときの緊張は手に取るようによくわかる。シスターとして皆さんの前にいる時、特にキリスト教やカトリックの信仰というものを求めてこられる方々の前にあって、自分がどんなことを伝えることができるのか?一回一回の講座を大切にされているからだ。こんな話をしよう、あんな風にすればいいそういうことではなく、自分が歩んできた人生と目の前にいる方々の毎日の中に、何か力になれる接点はないだろうか?私という人間を使って、あなたの命の糧してください。それができるかどうかはやはり彼女の態度や言葉であることをひしひしと長年の蓄積で明確に感じておられるからなんだ。彼女はSちゃんの校長先生だっただけでなく、今では私の大切な先生です。こうして私は学校に通っているわけでも、教室に行っているわけでもないけれど、実はたくさんの先生たちに見守られ教えてもらっている毎日なのです。
2009.01.29
コメント(4)
-
Sは試験!!
高2のSは先週から早く帰ってくるようになった。「どうして?」「もちろん試験やから、クラブはできないの!!」早く帰ってきては私がPCの前に座って仕事をするのを邪魔する。「お母さん、替わって、僕はここで勉強するのが一番やりやすいんやから」そう言ってコンピューターの前を陣取って好きな音楽をかけながらゲームを始める。ムッ 「ちょっと待った。勉強するとか言ってなかった?」「いやいや、このゲームの画面も僕にとったらBGMのようなものなん。お母さんは下でMちゃんのノートパソコン借りてやってね!!」そんな調子で今週に突入し、昨晩もPCの前で問題解きながらやっぱりゲーム画面が出ているから「Toさんが怒ったはったで~~ なんぼなんでも試験前にそれはないやろうって」「ハイハイ」しゃぁないなぁ~と画面を消した彼今朝、「ごめん、今日はお弁当作れなかった~~」とSに謝ったら「あぁ~ 今日は試験で午前中だけ、だからいらんの」よかった、昨日の夜だけでも彼まともに勉強したわ、とToさんの感の良さに感心していた私。試験から帰ってきたSは言った。「昨日びっちり勉強したところはばっちりできたわ!!」ほ~~ら やっぱりね、と言わんばかりの私が「良かったなぁ、ちゃんと勉強して。だからSには『勉強しなあかん』、て言わなあかんことになるねん。」「だから違うって!!僕がゲームしながら勉強したところがバッチリやったってこと!!」彼は勝ち誇ってお昼を食べに下に降りて行った。
2009.01.28
コメント(6)
-
小学校の自由参観日
1年生のクラスは「昔遊びで楽しもう」1月になってみんなが一生懸命練習してきた独楽回しやけん玉でおばあちゃんおじいちゃん、お母さんお父さん、それに小さな兄弟たちも一緒になっていろんな遊びをしました。他におじゃみ、竹べら、だるま落とし、福笑い、あやとり、かるたなんかもありました。ちょうど五女のAは友人とおじゃみをしていたので、私もちょっとやってみましたが、3,4年の時はやたらとそればっかりやっていたというのに少しも覚えていません。だけど私よりずっと年上のおばあちゃんは、おじゃみをよーく覚えていて子どもたちに上手に教えておられます。すご~い私はジャグリングを教えてあげたのですが、いや、片手2玉でもかなり難しいのですね、私も両手3玉を何回か続けるので精一杯でした。何事も練習か!!ついはまってしまいそう!!さて、4年生のWのクラスは「二分の一成人式」でした。二十歳になったときの自分に向けて、10才の自分が手紙を書き、それを発表してくれました。今の未来への希望がかなうでしょうか?どんな大きさの自分がどこに住んでいるのでしょうか?勉強しているのかなぁそれとも強豪チームに入ってラグビーしている?悲しいことや元気がなくなったときはこの手紙を思い出して読んでください。私が10才の時は、友だちいっぱいいて、一緒にきゃぁきゃぁ言いながら遊んでいたことを!目標を持って頑張っていたことを!家族と一緒におしゃべりしながら、お母さんのおいしいご飯を食べていたことを!どうしてこんなこと、10才の子どもたちが言えちゃうのか・・・Wの発表が終わったらAのところに行こうと思っていたのに、ついついみんなの言葉が聞きたくて、最後まで聞いてしまいました。皆、自分の道しっかり歩いて、友だちを大切に、20歳になったらまた会おうね、先生も!!
2009.01.27
コメント(8)
-
悲しむ人々は・・・
昨日、山上の垂訓が話題になったので、じゃぁちょっと思い出しておかなければ・・・と思いページをめくってみました。「心の貧しい人々は、幸いである、 天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は、幸いである、 その人たちは慰められる。・・・・本当に今悲しみのさなかにいる人がこの言葉を聞いたら、その人はどんな風にこの言葉を受け取るでしょう?私が悲しみの最中にあり、目の前の人がこの言葉を言ったら、ひょっとして怒り心頭に達して何をするか分からないかもしれません。あまりの無理解にシャットアウトしてしまうことでしょう。悲しみとは独特な感情のような気がします。私が普段出会う悲しみ、といっても頻繁にあるわけではないけれど、間接的な喪失や非人間的な状況を見聞きすることで私の心の中にもたらされる。それでも私が日常的に出会うその程度の悲しみは、本当の悲しみといえるようなものではないかもしれない。本当に深い悲しみの中にある時は、むしろ涙も流れず、自分が悲しみの中にあることすら分からないのではないか、と思う。でもそうやってある意味心を麻痺させてしまっていないと乗り越えられないようなところに自分がいるとき、必要なものはやっぱりそばにいてくれる誰かではないかしら・・・私と同じように悲しんでくれる人、というよりもそうなっている私に寄り添っていてくれる人、私が悲しみにあることを分かっていてそっと離れたとこから黙ってみていてくれる人、そんな人がきっと必要だと思う。それこそが、慰めを得るという事実で、そののち、悲しみから脱却した私はきっとあの時頂いた恵みに大きな感謝と支えて下さった方々との絆に大きな幸せを感じることができるでしょう。この山上の垂訓、逆説的な表現を使いながらも、最もリアルに人間の生きる姿を描写していると思う。ヤッパリ聖書、てすごいかも!!本日は一人深読会でした。
2009.01.26
コメント(6)
-
心の貧しい人は・・・
木々も、虫も、花も 時が満ちて生まれてくる私もあなたも同じように生まれてきた。木々も、虫も、花も 自然の摂理にその生きる姿を任せて一生を終える。わたしもそんな風に生きられる?いろんなところで値踏みが行われているこの人間社会私もそれに大いに惑わされているかも・・・「心の貧しい人は幸い」というタイトルが目に飛び込んできた。(「心のともしび09年2月号)『心の貧しい人』という表現は誰にでもわかる言葉ではないねといったら「空(くう)の心を持つ人」とToさんうん、それなら分かる!! 心の貧しい人は幸いである 天国はその人たちのものである (マタイ5章3節)頂いた命はすべて私自身に委ねられている
2009.01.25
コメント(6)
-
私はだ~れ?(その2)
朝はクァルテット「Il vento d’estate」の練習お迎えに来て下さったVn1のIさんの車に乗るとあぁ なんてすてきなサウンド! 今日練習予定のブラームスのクァルテットNo3の4楽章が流れている。Borodin String Quartet の演奏。やわらかでふくよか、あせらずだらけず、ブラームスの明るい日差しの中で日向ぼっこをしているような幸せ感のあるヴァリエーション「いいなぁ こんなサウンド作れたら~~このイメージを自分の中に入れておくといいんだね」I「そうそう、下手に自分の音ばっかり聞いていちゃダメ!いいイメージを自分の中に作っておけば、それが自然に本当の音になって出てくるから・・・」それで練習に入ったら、確かにちょっと自分の演奏が違ったような気がする。う~~~ん、これいいね~ これから練習前には少しでもCD聞いておこうかな? 午後からは大学に行って今度学校訪問で行うコンサート(音楽教室)の練習を現役の皆さんと一緒にしました。大学は4女のWが生まれる前にここでオペラ「ヘンデルとグレーテル」(フンパーディンク)の演奏をして以来、もう10年もご無沙汰していたのですが、あっちこっちで工事はしているけれど、それでも私が現役だったころのものもまだまだその姿をとどめていて、思わず自分が学生に戻った気分になります。大学生の皆さんと練習するのもすごく楽しいなぁ 一つ一つのことをとても新鮮に感じておられるのがすがすがしくて・・・その練習の帰りです。JRの駅で電車の到着を待っていたら「あれ、さっちゃんおばさんだ!」と声をかけてくれる学生さんが・・・ 教会のHさんのお孫さんでした。そうだった、彼女は私の後輩に去年の春なったのでした。で、ひとしきりお話をして京都駅で別れたら、その3分後に前から歩いてくる男性がニコニコ「やぁ こんなところで、今ちょうどうちの先生の結婚式があってね、素晴らしいかったんですよ。嬉しいね、あぁいう場にいさせてもらえるなんて・・・今から 出張です! じゃぁ 行ってきま~~す」幼稚園の園長先生です。「いってらっしゃい~~」 相変わらずお忙しいそう、でも本当に幸せそうな先生でした。そして嵯峨野線に乗り換えて車内で座っていると「さっちゃん? Vn持っているの誰かなぁ~て後ろから見ていたら、さっちゃんじゃない!どこ行ってたの?大学? わたしの記憶によるとさっちゃんは小学生だから、とても大学に行くあなたは想像できないわ・・・」彼女は昨年10月のコンサートでご一緒させていただいた才能教育の先輩です。 ほんとに不思議、今日は朝からすっかり楽しいことばっかりで、JRの駅を降りてからも元気一杯!!つい28分かけて楽器を持って家まで歩きました。
2009.01.24
コメント(2)
-
私はだ~れ?
演奏会明けのゆるゆるウィーク特別行事として友人の703さんとデートしちゃった~~あぁ 嬉しい! 703さんと私がとっても親しく話すようになったのは今から14年ぐらい前からだから、ちょうどバリバリ子育てに翻弄されていた私の姿を彼女はしっかり記憶に留めてくれている。そのころの私はこんなだった。(703さん語る)そのころ小学生だった長男が私(703)に質問したんです。『お母さんの夢は何?』私は、え~「夢」そんなこと突然言われてもなにも思いつかない。子どものことばかりに気を取られて自分のことがなおざりになっている自分、そしてそのことにさえ気がついていなかった自分に気付いておろおろしてしている私、そんな自分にとってもがっかりしたんです。その話をさっちゃんにしたら、「は?『夢』そんなものあるの?必要なの?」て言われちゃいました。私は子育てが終わったらこんなことしたい、あんなことがしたいって、きっとさっちゃんならロマンチックに思っているだろうと思っていたのに、そんなもの真っ向からはじかれてしまった。二人で大笑い!!よっぽど必死で子育てしていたんだね、私・・・確かにあの頃は今という時間、今日という時間に追いまくられていたわ~その時その時代の自分の姿があって、そして今がある。長いこと私を見守ってくれている友人たちがこうして時々の私のことを語ってくれることで、私は自分の過去の姿にもう一度出会える。それは自分の変化を知る瞬間でもある。とってもありがたく、そして楽しい瞬間!!今日は何度も大笑いした。 703さん ありがとうね、感謝!!どうかこれからもお付き合いください
2009.01.23
コメント(8)
-
あぁ 課題が・・・
月曜日、クァルテット(モーツアルト K464 初練習)の練習をしている間、となりの部屋からは何か厚紙をギコギコ切っているような音がしていた。何週間か前から白い大きなボードがこたつの部屋には無造作に置かれていて、「一体これ誰のん、」と私が口にする。もちろん、口では質問しているけれど、それをおいた張本人が誰かは分かっているし(そんなもの使う人、今は一人しかいないから・・・)こんなところにおいていたら汚されたり折れ曲がったりして泣くのはあなたよ!という警告の意味合いが強い。だから、おぉ 三女のKちゃん、何か作りだしたなぁ とモーツアルトのセカンドを弾きながら思った。練習を終えてこたつの部屋をのぞいてみると、何か円筒形のものを斜めに切ったようなものに三角の窓がみかんの横断面のように並べてあるものが作られていた。そのうちToさんが入ってきて「K、課題に行き詰って今にも泣きそうや」一呼吸するとまさしく困り果てた顔のKが入ってきて「おとうさん!お父さんがさっき言ってくれてた分、ちょっと描いてみてよ。もう何したらいいかわからへん ティッシュ、ティッシュは??」とこぼれおちる涙を押さえながらうろうろ・・・床に入って寝る気満々だったToさんは、布団にもぐりこみながら鉛筆と紙をとってシャッシャカシャッシャカと描き始める。Kは置いてあって自分の作品をとってぐちゃぐちゃに潰してしまった。「どうしたん?」「カフェの課題 みんな(姉や兄たち)に意見訊いたらぼろくそに言われて。だって私そんなにカフェに行ったことないし・・・私は外側やったら、手が勝手に動いてくれるねん、彫刻したり粘土したり・・・ 。 でも中身はわからへんし~~」「「今からみんなでお金出し合ってカフェでも開こうというのやったら、みんなの意見が大事やけど、今はKの学校課題やろ なんてみんなの意見を主にする必要があるの?」「だって、家族がいいと思わんもの、先生がいいって言うはずないし・・・」「先生はKたち生徒に考えてもらいたい、調べてもらいたい、体験してもらいたいことを課題にしてはるはず・・・。何が課題なのかそのことをもう一回思い出して、自分で考え・・・ 自分で良いと思える、またはこれしかできない、でもいいから 自分の中で作り出しなさい。自分の中から出てくるもの、それでいいの!!」そんな話をしているうちにToさんはせっせと自分の頭に浮かぶものを紙の上に再現して、ちゃんと三面(平面、側面、正面)の図を完成させていた。不思議なことに、課題をもった人間はああでもないこうでもないと考えあぐねて、分けが分からなくなる。意見を聴かれたものは、それこそその場の思いつきで好きなことが言える。全く素人だからこその意見を・・・。そして課題を持っていない人間は、自分の日常にはめったに転がり込んでこないこんな新鮮な作業に嬉々として取り組んでしまうのです。厳しいねえ Kちゃん一般に相当きつい場面で私の目から見ても危なっかしいと思えるような時でも、かなりの自信でやりとおしていくタイプのKの涙は印象的だった。この先もっともっときつくなるという噂のあるKの分野 どうなっていくのかな・・・?
2009.01.22
コメント(6)
-

昨日の朝も本!番!
ガチャガチャ、ざわざわ・・・さむ~~!!小学校ってこんなに寒いの?昨日の朝、まだ1時間目の授業が始まらない低学年教室の前は全く外とは変わらない寒さ。運動場で走り回っている子どもたちもいるけれど、7,8人の子どもたちは教室で懐かしおもちゃ(独楽回しやかるた)で遊んでいる。その教室も窓は全開状態で、吹きっさらし・・・キンコンカンコーン ・・・息をきらしほっぺをピンクに染めた子どもたちがどどっと教室に帰ってきてますますワイワイがやがや・・・このにぎやかさは学校ならではです。「では、お話を読むよ~~ みんな聞こえる~~?」と私が前に立って言ったとたんだった。突然あたりはシーーーーンとなって、目の前にズラリと子どもたちが並んで床に座っている。え、ほんま?オケの練習で、じゃぁ今からチューニングするよ~って私が立っても、なかなか気が付かないで個人練習している人も多いのにね~~今日の絵本はAのリクエストで にじいろのさかなまいごになる マーカス・フィスター 谷川俊太郎訳「あぁ 知ってる~」「うちにもあるわ~~」「もう いこうよ。」ちいさな しましまが せきたてた。「いわの われめの なかまの ところに かえらなきゃ だめだよ。あらしを よけるには、あそこしか ないんだから!」・・・なんて子どもたち静かなの?大変な集中力!可愛いたくさんの目が全部私の持つ絵本にそそがれているなんて・・・主人公はにじうお きらきらうおの仲間 それになかよしのしましま、 赤いしましまやきいろしましまと名前が似かよっているから結構区別しにくいはずなんだけど、子どもたち、ちゃんと分かっているんだなぁふたつの むれは、それぞれに いなく なった なかまといっしょに なった。その おいわいは よる おそくまで つづいた。」はい、お終い!!「え~~ もっともっと、もう一つ読んで!!」「まだ時間あるかなぁ もう一冊は長いよ~~じゃぁ お急ぎで!!」これは私が選んだ本。 手ぶくろを買いに 新美南吉作 黒井健絵 本当に久しぶりに読んだ。味のある物語。愛情のある物語。信頼のある物語。ところどころ混ざる古い方言の何と暖かいこと。雪の描写も子狐の言葉もなんて生き生きしているのかしら子どもたちはずっとずっとみんな 物語の世界にいた。「ご、ごめんなさい~~ また延長してしまいました」と担任の先生にごあいさつ「いいんです。子どもたちにはとってもすてきな時間なんですから・・・」あぁ 楽しい!!やっぱり、私パフォーマンスが好き~~と自分のことが少しわかった時間でした。
2009.01.21
コメント(4)
-
第8回演奏会(その4)
究極の団体競技 いやいや友人のSちゃん(元中高オケのコントラバス奏者)は団体共奏でしょ?と教えてくれました。そうそう、それは「オーケストラ」たった一本の棒一つの動きで60~100人もの人間たちが同じ音楽を作っていく。それぞれに違った役割を担いながら・・・無事に終わればホッとするけれど、ある程度なれているはずの私でさえ、本番前は何日も前から自分として意識しないまま緊張感を持って過ごしている。小学校でインフルエンザがはやってきたら、「お願い、今だけは私に移さないでよ~~」とか「ちゃんと寝とかないとなぁ」とか自分の管理も気になってくる。気になってくるということはそれだけ不安が増大しているわけだ。前日は一日中みんなことが気になっていた。団員みんなの顔を思い浮かべてみるにつけ、小さな子どもを抱えていたり、超ハードスケジュールの中でやってきてくれたり、遠くから何時間も雪道をドライブしてきてくれたり、子どもが熱を出していたり、本人もしんどくなったり・・・・ もくもくと自分の役割を果たすマエストロも本当はでっかい責任を負いながらいつもやりぬいてくれている。でも彼だってただの普通の人間で仕事の合間に時間を割いて勉強してマエストロ役を買って出てくれているわけで・・・、ふっと彼が倒れたら誰が本番の指揮をするんだろう~~という思いが心の中をよぎっていく。そんなことを考えると本番がきちんと行えるチャンスとは細い細い蜘蛛の糸で結ばれているかのようにしか思えなくなってしまう。前夜布団の中でずっと頭の中で響いている演奏会のフレーズの存在に気づいて思った。「ここまで演奏会に支配されちゃだめだろう、もうフレーズには消えてもらおう」岡田節人さんがおっしゃるように「考え方も言葉ももういらない」そう、私は昆虫のようになればいいのだ。考えも言葉もない世界でただ自分というものが生きている、それだけが自分の存在を表わしていればいい。昆虫ならてんとう虫がいいなぁ カナダに行った時寒くて昆虫のいない季節が多かったけれど、てんとう虫だけは公園で子どもたちと戯れていた・・・私はてんとう虫・・・・それですとんと寝てしまっていました。 みんなありがとう!!またまた奇跡が起こった!!演奏後打ち上げに向かう地下鉄で去年の第九で合唱指導して下さったK先生とばったり、もちろん私たちの演奏会に来てくださっていたのです。去年はハッキリ言って彼からぼろんちょんに言われてずたずたになった私たち「まぁ、ここに座りなさい」と言われて、恐る恐る座ると「今日は本当良かったよ 君たちはあれだね、ロマン派の方がいいんだね、ちゃんと自分たちの中で消化していた!!良かったよ、とてもねところで君、他にも何か活動しているの(Vnで)・・・ 小編成で「メサイア」でもやってみない?今年はヘンデルの没後250年祭なんだよね」
2009.01.20
コメント(8)
-
第8回演奏会(その3)
今回のプログラムで最初に決まったのはピアノコンチェルトで、たぶん1年ほど前にはすでにソリストの山口博明さんとお話ができていて、間もなくラフマニノフのコンチェルト2番になった思います。 本番当日においてもピアノがとても大きな存在でした。 リハーサル時にゆるゆると運ばれてきたぴかぴかのフルコンサート用のグランドピアノ、それはよく聞くスタインウェイではなくベーゼンドルファでした。 山口先生が弾かれるとまろやかでつやがあり、それでいてキラキラと音が踊り出しているかのよう。すぐに皆がわいわい集まってきて、先生とこのグランドピアノに携帯写真の砲列です。鍵盤の一番低いところには9鍵ほど表面が黒塗りにされている鍵盤が付いています。(インペリアル)先生によるとこれによってより深い音を得ることができるとのこと・・・・ラフマニノフのメロディとサウンドの世界が、どんどんあたりの空気の色を変えていきます。今考えてみると、これによってオケのみんなの耳も少し変ったかもしれません。 博明先生はオケとのリハーサル後お客さんが入ってこられるまでの時間を惜しまれるかのように、そのピアノとの対話に心を集中させておられました。本番中でさえ、先生はこの楽器とラフマニノフでデートをしておられるみたいで、優しく語りかけてはその響きを受け止め、自分の心の内から流れ出して来る全てを楽器とともに楽しんでおられるように思えました。だからこそ、その音楽はどんどんステージ上のみんなを包み込んで、すっかりオケ全体もその美しさとダイナミックスに引き込まれていきました。本番後の打ち上げで少し博明先生とお話をさせてもらったのですが、「こんな風にみんなと音楽が一緒にできるって、本当に幸せですね。普段はせいぜい2,3人と一緒にやるぐらいだから、楽しくて・・・指揮者がパンと打点を示してくれてもすぐにオケの音は出てこないでしょう。それがまた味があってね~~でも、なかなかそれに慣れることができなくて、もう少し時間があればなぁ~~ いやぁ~ 楽しかった!!」とのことです。私はいつもピアノの人は自分の楽器で弾くことができなくて、本当にかわいそうだなぁと思っていたんだけれど、こうやって素晴らしい楽器と出会うこともできるし、またオケのみんなと一緒にやることを喜んだり楽しんだりして下さるということに、またまた感激、ほんと素晴らしかった!!
2009.01.19
コメント(4)
-
第8回演奏会(その2)
1月17日 ご存じのように14年前阪神淡路大震災が起こった日でした。リハーサルがまさに始まる時、マエストロは14年前に起こったこの日の出来事について語ってくれました。京都でも大きな揺れを感じましたが、朝は何事もなかったかのように動き出しました。マエストロは3日間連続で京都会館での京都市交響楽団による中学生のための音楽教室の担当をしていて、その3日目のことす。2回同じことをした後の3回目だから何事ももう京響の方にお任せしておいたらいいなぁと思っていたら、朝一番に職場に電話がかかってきて、「すぐにホールの方に来て下さい。大変です」とのこと。取って返してすぐに京都会館に駆けつけたら、大きなガラス窓にはひびが入り、ホール天井の反響板はさかさまに歪んでいて・・・この話、お正月に偶然兄から聞かせてもらったところでした。兄は当時京響の団員だったのです。京都の中学生たちは特に変わった様子もなく、予定通り大型バスに乗って次々と会場にやってきます。ところが、演奏をする京響の団員のかなりの方々が阪神間に住んでいらっしゃって、集合時間になっても半分も集まっていませんでした。その中には指揮者の堀さんも含まれています。こりゃぁ 大変だ!!とにかく、このメンバーで何とかできる曲をまず用意しなければ・・・ライブラリヤンの方は急いで京響に戻り、楽譜探し。こんな時、彼の力量が最も問われます。いまのメンツでできる曲~~ 中学生が分かりやすく楽しめる・・・ 指揮者がいなくても練習していなくてもすぐにできる曲~~開演5分前になって玄関口にいた(うちのオケの)マエストロは、遠くから大きなカバンを持って一生懸命走ってくる一人の男性が目に入ったそうです。近づいて来られたら、その方が指揮者の堀さんで、動いては止まり止まっては動く電車の中で走りたくなるほど、自宅と京都間は遠く時間だけがどんどん過ぎて行った、とのことでした。兄「あのときは本当に大変だった。何ぼプロと言っても一人で弾くのと違ってチームでやるのだから・・・もちろん阪神で大きな被害に遭われた方々とは比べようもないものだったけれども・・・ね」と言っていた。 (私たちのリハーサルで)マエストロ「全くの偶然ではあるけれど、この日にぼくたちがこうして無事にコンサートに臨めるということは本当にありがたいことで、何もできないかもしれないけれど、このコンサートを聞いて楽しい思いや喜びが生まれ皆さんの力に少しでもなれたら、と思います。祈りをこめてやりましょう」そうです。私たちがここにいられることに感謝して・・・聴きに(見に)集まって下さる方々に感謝して・・・本番の中間休み、楽屋に大ママが跳んでやってきました。「ピアノ素晴らしい演奏やったね。管楽器の人、プロ呼んできたん?え、違うの?へ~~ ものすごく上手になったはるわぁこんな阪神淡路大震災の記念の日に美しい曲でコンサートできてよかったなぁきっとここに来はったお客さんの何人かの人は、この曲(ラフマニノフのピアノコンチェルトNo2)であのときのこと思い出して慰められたはるよ~~次の曲(メンデルスゾーンのシンフォニー「スコットランド」)知らんけどきれいな曲なん? そんなら聴いて帰るわ、明日早いんやけど・・・がんばりや~~」たくさんのたくさんの祈りが広がっていく
2009.01.18
コメント(8)
-
第8回演奏会
お陰さまで無事オーケストラの演奏会を終えることができました。あぁ 良かった!!こういうイベントは何においてもまず無事に終えることが大切。予定されたことが滞りなく終了できるって、本当に大変なことだもの。与えられたことをきちんとやるだけではない。与えられてないことも気づいてさっとやってくれる人がたくさんいてくれて・・・楽器も楽譜も、団員も・・・バックステージの人、受付チケットの人・・・お弁当屋さんも、お花屋さんも・・・そして演奏も思っていたよりも良い演奏になったみたいで、よかった。序曲のソロもリハでは落ちてしまうという、あり得ない(しかし私らしい)ミスをしていましたが、本番はちゃんとできました。たくさんの励ましとお祈りをありがとうございました。実は私はステージのことをお祈りするなんてことはめったにしたりはしないのですが、今回は思わず祈ってしまいました。とにかく無事にコンサートが終了しますようにって・・・嬉しくて、ホッとして、感謝・・・です。 本日はここまで
2009.01.17
コメント(10)
-
老化(その3)
さらに今日の新聞(読売 長寿革命)には「記憶」についての記述がありました。おじいちゃんやおばあちゃんたちに小さな頃の思い出話を語ってもらう。するとにわかに表情が生き生きとして輝きだす。「回想法」と言って長い人生の中の体験や心境を語ってもらうと幸福感を引き出すことができる。あら、それは私のカナダ滞在記や子育て記を書いている時と一緒だ。つまり私はもうしっかりそうした領域に入っているということですね。でもこの思い出が人々の幸福感を引き出す、というのにはとっても合点がいきます。だって、うちのオケだってそのものです。本番直前になってくると、久々登場の面々が練習場に集まってきて、学生時代の思い出話に花を咲かせ、一緒に美しいメロディに浸ったり、スリルを味わったり、もう一度学生時代の追体験をしているのですから・・・。これは私に言わせれば、とても大掛かりな同窓会。お手伝いで来て下さる方も、必ず誰かとつながって来て下さっているし、何度も一緒に弾いて下さっている方ばかりだから、その空気が変わることはない。そしてこの日々も遠く通り過ぎたいつかに、楽しかった幸福な記憶として、私の心の中でよみがえってほしいと思う。いよいよ、明日本番、今から練習に入ります
2009.01.16
コメント(8)
-
老化(その2)
昨日の続き「老化とは」 継続的な疲労で脳などの組織が傷つき、生命の根源である回復力が失われる現象 だから心身をリラックスさせることや力加減を知ることはとても大切なこと ・・・渡辺恭良(理化学研究所分子イメージング研究センター長)「老い」と「知的能力の衰え」は同義ではない知能は生涯を通して発達する。老いて経験を得ることでこそ磨かれ、豊かになるという力もある。 ・・・慶応義塾大 発達心理学准教授 高山緑もっとも心惹かれる言葉を述べておられたのは岡田節人(81)京大名誉教授生物から学べる最も大切なものは「蘇る力」と「しなやかさ」個々には死を迎えながらもそれらは常に全体としての再生を図っており、環境の変化に対しても個々に、または世代を越えて順応していく。この姿勢やシステムを勉強することによって、この真実を一人ひとりの人生に生かすこと、これが生物学を学ぶ意味。生物には人間のような知性はありませんが、健康に生を全うするためのすぐれた五感を備えています。ということで、人間の持つ美意識や一面的な能力の優劣、から老化(エイジング)をとらえるのではなく、生き物の大きな流れとして各年代の特徴を受け止め、未来に向かう柔軟な姿勢を常に持ちながら生きましょうということを語っておられます。おわりに「私自身はもう「考え方」とか「言葉」は忘れようと思います」だって!! つまり知識でもって語りたくないある側面から語りたくないわたし(岡田先生)の人生を見て下さい、とおっしゃっているのでしょうか、すごい言葉だなぁと思います。
2009.01.15
コメント(6)
-
老化
読売新聞に昨日から連載が始まった「長寿革命 老いの形」というのがあります。そこでご自分の作品の中に埋もれるかような写真の配置で紹介されていた方が昆虫画家の熊田千佳慕さん写真を見て、これは五女Aにぜひ見せてあげないと、と思いました。まさしく彼女の世界地べたにしゃがみ込んでは石や葉っぱや昆虫たちの姿を頭に焼き付けてそれを白い紙に再現する彼女新聞記事を読んでびっくりしました。70歳で初めて認められて(ボローニャ国際絵本原画展)有名画家の仲間入り80歳で、不安を感じる。庭に出て睡蓮の細かい毛、虫の羽の微細な模様を見て「先がないから『もっと見ろ』と神さまに言われたよう。90歳 心身の老いと疲れを感じて「二分の力を残して」作業を終えようだって!現在97歳、「僕には老後はない」とのこと!!漢字学の白川静さんもそうだった。70歳を過ぎてから有名な「字訓」「字統」を出版された。生物学的に言えば、哺乳類は15億回の心拍総数がだいたいの寿命と言われている。だから心拍の速いネズミは1~3年の寿命ゆっくりな象は60年その計算でいけば、人間は35~40歳が寿命らしい。ところがそうではない。よりよき生活環境と文化とを築いて来た人間はその目安さえも超えてしまったそうな・・・つまり私でさえも、もう寿命は越えているとのこと・・・確かに、これは感謝しないといけない。私だからではなく、本当にたまたまそうさせてもらっているのだから・・・
2009.01.14
コメント(8)
-
眠たい 眠たい
眠たい 眠たい 眠たいお昼ごはんを食べたらもうあかん!! 今日は下の二人がバレエに行くから夕飯の支度はスタートが早く2時過ぎ。3時半を過ぎると眠たい 眠たい 眠たい に再び襲われ、スープが沸いたら弱火にしておいてね、と長男に頼んで バタン!!「お母さん、Aちゃんの髪の毛してあげな(シニヨンに結ってあげて)!もう4時15分やで~~!!」「え、4時15分、半に出なあかんのに~~」必死に起きたけれどAの用意もできてなくてバタバタしているうちに30分はすみ、Wの結い終わったら、4時45分だった。「明らかに遅刻やね!!ごめん 先生にはお母さんが疲れて寝てはったから…と言っといて・・・ね」でスープはどうなったと見にいったらコンロの火は消えている。「あれ?弱火で煮てくれた?」「え、沸いたら火消すのと違うの?僕確認しなかったっけ?」「いや、弱火にしてって言ったつもりやったけど・・・」でもまぁまぁできてるわ。あと少しだけ煮ておこう~~バレエには二人でいけるけれど終わる時間が別々だからお迎えにはいかなくっちゃ!それまでの30分 何をするべきか?そうそう新しい楽譜が届いている。2チームあるクァルテットは両方とも1月から新曲にトライすることになった。 SQ135(実はまだ名無しのチーム)の方はモーツアルトのK464をするのだけれど、今回はVn1のIさんからスコア(4人のパート譜が一度に合わさって書かれている楽譜)のコピーが送られてきて、ボーイングはこんな感じ、ついでに私のパートのフィンガリングもところどころ書かれているし、イ長調の3度と6度の和音の音階も練習していといてね、とのこと。つまり彼はもうすでに全部目を通して、何度も弾いてボーイングとフィンガリングを決めたということ。今回は力入ってる~~~ オケの演奏会明け19日に練習が入っているけれど、クァルテットの方は勉強できそうにないし、もう一声いうと18日にも2月のコンサートの練習が入っている。ぶつぶつ言わずスコアからボーイングを私の楽譜に写しておこう夜ご飯を食べたらまたまた眠たい 眠たい 眠たいVnの練習をし始めると眠気は飛んでいくのだけれど、やっぱりオケの練習だけにどっぷりつかってしまう。フィンガリングやっぱり変えよかなぁ クラリネットさんが好きだったテンポは115ぐらいか?いやもう少し遅いかなぁ とテンポ設定をしながら練習・・・どこまでも続く・・・
2009.01.13
コメント(8)
-
聖書深読会1月1回「洗礼」
ちょっと前の深読会の続きです。洗礼者ヨハネからイエスがヨルダン川に入って水による洗礼を受けると、天が裂けて鳩のような感じで聖霊が下って来るのをご覧になったすると、「あなたは私の愛する子、私の心に適う者」という声が、天から聞こえた。(マルコの1章11節)実は私は小さな赤ちゃんの時に洗礼を受けたので、大きくなってから洗礼を受けられた方のように、洗礼を受ける前の自分と洗礼を受ける決心をした自分と、そして実際に洗礼を授かった後の自分と、どんな風に違っていったのか、ということをまったく意識できていません。そういう経験を持っておられる方々にはある種の憧れがあります。実際大人になってから洗礼を受けられて、すばらしい修道者になっておられる方も大勢おられます。新教では、自覚ができるまでは…ということで小さな子どもの洗礼(幼児洗礼)は行わないそうです。 ある時、まだ私が高校生ぐらいだったか、カトリックはどうして幼児洗礼があるのだろうと思って、確か下の兄に聞いたことがありました。すると「あんな、自分の子どもが生まれたら、その子にとって一番いいと思う服を着せ、いいお部屋や布団を用意するやろ。同じや、親にとって最も大切な信仰なら、まずそれを子どもに与える。」これもとっても納得のいく答えでした。 さて、このイエスの洗礼の場面でイエスが天から頂いたことば「あなたは私の愛する子、私の心に適う者」これは洗礼を受けた者はみんな、この言葉を神さまからいただいているんだ、と私は思いました。父からいただく、もっとも子どもを信用し誇りに思ってくれている言葉のように思います。実際私の父が私にこの言葉を口に出して贈ってくれたら、今生きていることを私はどんなに嬉しく喜ばしく思うでしょうか!自分の命をどんなに愛おしく思うでしょうか!そしていっぱい勇気が湧いてくるでしょう失敗なんて大丈夫、父が安心してみてくれているのだから・・・それが神さまなら、天にも昇る言葉にならない気持ちです。洗礼とはそういうものなのですね。命そのものはもともと祝福されいただいたもの。だから洗礼を受けようと受けまいと最初から誰でも「わたしの愛する子、私の心に適う者」なのです、きっと!!この日、去年私が代母をしたHちゃんが深読会に来れませんでした。わたしはそのことを本当に残念に思っていたのだけれど、でも昨日のごミサに参加した彼女は、神父さまのお説教の中でこの言葉にふれて、とても心動かされたそうです。そうなんです。洗礼ってきっと、祝福を受けている自分に気付かされるときなのですねそれはそれは幸せなことです。わたしは自分の洗礼の時には、それを知ることはできなかったけれど、でも彼女の洗礼を通して、そのことを本当によく味わうことができました。ありがとう!Hちゃん
2009.01.12
コメント(4)
-
本番まで・・・(その2)
Last Twoオケの練習は13:30~20時までやりました。なんといっても今日のメインはピアノコンチェルトです。練習会場にピアノをセットし、ティンパニー、打楽器類を入れるといつもの練習場のはずなのに、いっぱいいっぱいです。皆の荷物もあり、楽器ケースがあり・・・すべてのメンバーがほぼそろってみると、こんなにもたくさんいるんだ!!それでもVnは5プルト(譜面台1の二人組)ずつしかいないのにね。始める前に4プルト目のKさんがおっしゃいました。「ごめんなさい、ちょっとだけ前に詰めてもらえますか?もう後ろぎりぎりなんです」「はい!」と返事はしたものの、前もかなりいっぱいでピアノにぴったりひっつくような私のポジションです。 だからすごかった!!だから素敵だった!!今日のソリストの山口博明先生は合わせの時には楽譜をピアノの上に置かず、本番通り上着を着てラフマニノフの2番全楽章を通してくださいました。確かに今までもご一緒に練習していたはずなのですが、今日はすっかり彼の音楽の中に取り込まれ、指揮者は視野の片隅に何とか入ってくれていた、そんな印象です。ピアニストの息遣いと一緒に呼吸し、彼のテンポ感を示している足踏みや動きとともに弓を動かし、ピアノの音から自分の音程を拾い、フレーズにそって音を入れました。確固とした音楽がそこにある。共にいることがなんて安心なんだろう何にも、悩むことも心配することも何もない。間違いすら、すでに許されている・・・ そんな感じ!!たぶん、私は今日最高の席にいたのですそしてもちろん、本番の時も・・・ね
2009.01.11
コメント(8)
-
本番まで・・・
いよいよ、オーケストラの練習も本日を含めてあと3回となりました。今日は朝11時からVn1Vn2が集まって今までパート練習ができなかった分を取り返そうと2時間練習をしました。 気になるところを取り出して弾く、聴く、ゆっくり弾く、弾き方を変える、イメージを統一する。やりだしたらいくらでもやりたくなる。ほんの少し、こうありたいことを互いに確認するだけで、段違いに演奏には統一感が生まれていきます。Vnパートだけで練習することは全体から見れば大した部分ではないかもしれないし、実際全員での合奏においてはいろんな要素が絡み合ってくるから、パートで練習したときのように単純にはいかないけれども、それでも一人ひとりの音の調和を体験しておくと、ずいぶん合わない、合っていないということに敏感になれるように思えます。2時~6時10分まで合奏、そして1時間の夕食休憩をはさんでまた7時15分から9時まで合奏練習をしました。ところどころ弦楽器の人が休んでいますが、ほぼすべての楽器の音を聴くことができたのは今日が初めてではないでしょうか!打楽器のチンやドンもぜ~~んぶ入って、楽しいのなんのって・・・ 本番一週間前にして、ようやくオーケストラになった、わがオケです。やっぱりこれでなくっちゃ!!みんないてはじめて、もっとこうすればいいのじゃない?というところが言えるようになる。できること、できないことがわかるから、実現可能な範囲も感じられる。みんなが本気で弾いてくれるから、あっちに向かっていきたいという希望が湧いてくる。合わせようと思うより、同じ思いを持って進む方が音楽になる。なんでだろう 8時間ぐらい練習したと思うけれども、体の疲れはあってもちっとも心は疲れていない。さぁ、あすはLast Twoの練習!!
2009.01.10
コメント(4)
-
聖書深読会1月1回(その2)
さて8わたしは水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。」9そのころ、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた水と聖霊による洗礼の違いとか、とても私は聖書を研究しているわけではないから理論的なことは分からない。でもどこの世界に行っても「水」はものを清める象徴に使われているし、実際清浄にする力を持っている。ヨルダン川に入って心の穢れをとる(罪を許される)という洗礼はとてもわかりやすいし、イエスさえもヨハネからその水の洗礼を受けられたという出来事は、イエスがヨハネの今までの宣教活動に対する誠実と敬意を払っておられるような気がして、この場面は好きです。そして私はこんなことを思い出します。 兄が何年も前にマザー・テレサの「死を待つ人の家」にボランティアで滞在していた時、兄は神父なので毎朝のミサ(礼拝)の中でマザーテレサを前にお説教をしなくてはならなかった。そんなときも、マザーはこうべを垂れていつも静かに若い日本人のつたない英語の説教を聴いて下さっていた。と兄が私に話してくれたことです。どれだけの経験の差があっても、どれだけ有名無名の差があっても、互いが持っている役割をきちんと担い合って、互いに尊敬しあい、その時、その一日を生き抜くことを認め合う。そんな風に私もかかわるみんなと生きていたいと思います。
2009.01.09
コメント(2)
-
聖書深読会1月1回
聖書深読会を今年初めて行いました。まだ年始のモードから日常モードに戻るのもきつく、だからこそ時間的に忙しくて来れないメンバーもあったけれど、年の初めにふさわしい素敵な時間になりました。今日のみことばは「マルコ福音書 1章7~11節」です。12月には1章1~8節を読んでいたので、ちょうどその続きというところ。荒野で生活している洗礼者聖ヨハネが福音を述べ伝えるところから・・・7彼はこう宣べ伝えた。「わたしよりも優れた方が、後から来られる。わたしは、かがんでその方の履物のひもを解く値打もない。8わたしは水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。」9そのころ、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。10水の中から上がるとすぐ、天が裂けて"霊"が鳩のようにご自分に降って来るのを、ご覧になった。11すると、「あなたは私の愛する子、私の心に適う者」という声が、天から聞こえた。パッとひと読みして、ここはと心惹かれるのは11節の「あなたは私の愛する子、わたしの心に適う者」でもでもその前にこの7の「この宣べ伝えた」というところに目がとまります。このヨハネの呼びかけによってガリラヤ地方に住む多くのひとたちが集まってきてヨハネから洗礼を受けたのですから・・・ 相手が必要とすることあるいは自分の伝えたいことををきちんとわかるように伝えられる。 当たり前のようだけれど、とても大切な力。今や誰かに何かを伝えるにはたくさんのメディアが存在しているけれど、私はやっぱり直接会ってお話して伝えあうことほど確かなものはないと思う。この二日ほど、携帯メールのやり取りで大きな混乱に直面した。特に携帯メールは私にとっては時間のかかる歯がゆい道具。最小限の言葉でのやり取りはやっぱり危険です。これはお知らせ程度にとどめておく道具だと改めて思いました。想いを語る、想いに耳を傾ける。これはやっぱり出会いの中で大切にしていきたい。つづく
2009.01.08
コメント(6)
-
家族写真
小学校から私よりも先に家に帰っていたAとW私が帰ってくると早速話をしてくれました。A「コマな、ちっとも学校ですることができなかったし、だから代わりにかるたで遊んだん。自分たちで作ったかるたで、2回遊んだらもう終わりの時間になってしまった~~。早いな、終わるの!!」W「今度、花背山の家に2月に行くんだけど、もうお手紙くれはったよ~~楽しみやなぁ みんなと一緒にお泊まりして 持ち物もいっぱいあったわ~~」それぞれの学校生活は無事スタートしたみたい。今朝起こすのほんとに大変だった!!+自分が起きるのも!!待っていてくれていたのは子どもたちだけではなくて、メールとクリスマスカードもでした。一昨日送ったクリスマスクッキーお礼のメールのお返事でしたが、クリスマスカードに同封した我が家のメンバーの写真について書いてくださっていました。まるでご自分のご家族のように写真のわが家族みんなに毎朝「おはよう」寝る前は「今日はいい一日だった?明日はもっといい一日になりますように」て声をかけて下さっているんだって!!なんて大切にしてくださっているんだろう、とっても嬉しくなりました。実は11月12月、同じ屋根の下で暮らしているというのに本当にみんなが揃うことが難しく、写真を撮るチャンスがずっとなかったんです。せっかく日中にそろったかも、と思ったら急にToさんに呼び出しがかかったり、仕方がないから家の中で夜にでも、っと思っていても、みんなが揃う頃にはもうWもAも寝静まっているし・・・ある時夜10時過ぎに予想より早めに帰ってくることができたHの顔を見て、そうだ!今しかない~~、と思い立って、もうパジャマを着て布団に入り本を読んでいた下の二人にもう一度着替えてもらって、ようやく撮った写真なのです。まさに一瞬の時間を切り取った写真そんなことちっともメールの方には語っていないのだけれど、きっとそのことに気がついて下さっているのですね。今日カナダから届いたカードにもご一家の写真が入れてありました。私たちが滞在したころ 30代だった友人は50代に、そして子どもたちは20代、大きくなった子どもたちの顔は17年前のパパ、ママの顔にそっくりです。不思議と変わらぬ姿が受け継がれていくこのシステムにとても心動かされます。本当に家族って素晴らしい形ですね
2009.01.07
コメント(7)
-
冬休みの宿題
あぁ いよいよ明日から小学校だって!さてうちの小学生たちは明日学校に行けるのかしら・・・宿題やった?A「やった」Aの明日の持ち物にコマって書いてあるけど・・・A「あ、しまった コマ回しの練習するの忘れてた!」そんな宿題あったの~~?それからが大変。まずコマがない。「ねぇねぇ Aちゃんのこましらん?」とみんなに聞いても分からないし、ありそうなところを探しても出てこない。これはバレエに出かけているWに頼るしかない。帰ってきた彼女に聞くと「あぁ この辺にあったと思う」と言い終わる前にすでに手に持っていた。やっぱり常に一緒にいる人の情報量はすごい。今度はコマのひも巻きが難しい。だれかコマ回し上手な人、教えてあげて・・・S「懐かしいなぁ そういえば小学校の時むきになって練習してたなぁ」と熱心にやりだすし兄「お、コマか~ ちょっとやらして・・・ え~と・・・」W「私もやってみたい!! ほ~~ら 上手に回るやろ Wも去年練習したんやもん」ということでちっともAの順番は回ってこない ようやく順番は回ってきたけれど、コマ回しはとっても難しい・・・ 30分ではやはり無理か!! そうそう、この冬のWの宿題は算数が面白かった「お母さん、この問題意味わからへん。 なんなん?」どれどれ・・・問題4の数字を4回使います。× ÷ + -を何回使ってもいいので答えがそれぞれ、1,2,3,4になる式を作りましょう 4 4 4 4 = 1 4 4 4 4 = 2 4 4 4 4 = 3 4 4 4 4 = 4へぇ これ面白そう ~~ 答えが1になる式と2になる式はWもすぐ解けたんだけれど3と4はなかなか答えが出てこない私も真剣になって考えて・・・ あぁ なるほど解けたかも・・・ でも翌日には答えを忘れちゃっていて・・・ もう一回考え直し・・・Toさんや兄やMにも問題をみせて問題を解いてもらったら、それぞれ真剣になる面白さがこの問題にはあった。Wは何日も何日も抱えたままでしたが、最終的にはみんな解くことができたんだけれど、最速の人は大学1年のKでした「何々、ふむふむ」と言っているまに解き終わっていました。さすが・・・ 伊達に大学生じゃないのね!!
2009.01.06
コメント(2)
-
第2日(3)ターミナルケア
ということで思いのほかスケート場は人が少なく楽しめた2日でした。こうやって久しぶりに足の裏でエッジを感じることをすると、スケート靴もほしいし毎週?毎日のように滑りたくなる私です。でもまぁ今の私の状況だとそれは無理でしょうね。アイスアリーナも夏はプールになっていますし・・・ 昔とは環境が変わりました。でもWもAもすっかりスケートにはまって行きたい、生きたいといっています。 読書の方はようやく「看護のなかの死」寺本松野著 を読み終えました。あと10pというところでずっと止まって最後は年を越してしまったのですが、人生を考えることができる本です。昭和11年(今から73年前?)に看護師さんになられてからのさまざまな患者さんとの出会いと看取りが描かれているのですが、この長い間の医学の進歩と社会の変化の中で、一人の人の最後というものをどんなふうに見守りそこから学んでこられたのか、ということがひたひたと伝わってきます。時代が変わっても、どんな医学の進歩があったとしても、どんな状況にあったとしても、人の命は何一つ変わることがなく、いつも一人という貴重な存在であることと、苦しみや悲しみ、寂しさと共にあり、またそれを知ったからこそ喜びや希望を抱くことができるという、不思議な力を持っていることを伝えて下さっている。第一に私が感じたことは、これほどの苦しみを体験する患者さんたちのそばにいながら、どうやって自分の最後を乗り切ろうとされるのか、現実を知っておられるがゆえにものすごく大きな不安や恐れがこの寺本さんの上には在ってもおかしくないと思っていたのです。すると最後のページにこのように書かれてありました。死は他人だけのものではなく、私のためにも存在する。私が彼女(患者さん)と同じ運命になったとしたら、私はどんなことを望むであろうか? 私が悩む時、共に悩んでくれる人を!わたしの力が尽き果てたとき、私の杖となるものを準備してくれる人を!わたしの心が悲しみに震えるとき、ともに泣いてくれる人を!そして、私の孤独を見守ってくれる人を、私は待ち続けると思う。人間は弱いようで強いものを持っている。その強さを引き出し、勇気ある人間に育て、限られた命の中でなお成長し続けることができることを私に思い出させてくれる人を、私は待つだろう。 看護は、これらのことのために活動し続けなければならない。希望を持って歩み続けなければならない。それが看護の命なのだから。これは人間のあるべき姿ですねいつからか、私たちは自分の姿を見失ってしまったのかな・・・
2009.01.05
コメント(8)
-
第2日(2)
そうなんです。大ママちゃんはただ今82歳。1年前久しぶりに滑ったときはかなり怖く思えて、手すりからしばらく離れることはできなかったそうなんだけれど、この日は普通に最初からすいすいと氷の上を滑っていました。私が毎日スケートに通っていたころはバックやスリージャンプ、ターンまでこなしていましたが、さすがにそれは自粛しているようです。こういう感覚はスキーや自転車と同じですっかり忘れてしまったりはせず、しばらくすればかつての感覚が甦ってくるのですね。 そしてこれまた素晴らしいことに、広島の兄とスケートは深く大きな関わりがあります。 彼がまだ企業に務めていたころ、やっぱり休みで実家に帰ってきたときに兄と大ママと私、(それにいもうとのCちゃんもいたかもしれません)でスケートをしにリンクに行きました。しかし彼は転倒をして思いがけず足の骨折をしてしまったのでした。でもその治療のための入院中に与えられたゆっくりした時間の中で、もう一度人生を考え直し、後悔のないようにしたい、とそこで今の神父になる決心をしたのでした。 そして去年の9月に広島に引っ越すまで住んでいるところが近いからとスケートリンクに通い(1年ぐらいかな?)、自分の靴まで買ってスケートを習っていたそうなんです。しかもその先生は私がかつて東京でアイスダンスを習っていた方なのだから驚き!全くの偶然です。だからこの2日の日、WやAに一生懸命スケートの滑り方を教えたのは兄だったのです。何しろこの間までレッスンを受けていたのですから指導方法はすっかり身についているし、滑れない、ということもよく理解しているのですから・・・ WとAを連れて貸靴を借りにいき、履かしていると、あぁひもはどうやって結んでいたっけ…、余ったひもは・・・、自分の足にスケート靴をはめてみるとすぐに骨にゴツンと当たるのだけれど、それでもこの重さが・・・歩くとコツコツいう音が・・・ 懐かしいW,A手袋はめた?そうだ、帽子よりヘルメット借りておこうね!しっかりお膝曲げられる?少しリンクサイドで歩いてごらん?平気?なら氷の上に行ってみよう~~フェンスにしがみつきながら降りて、(このとき一番こけやすいね)カタカナのハの字に足先を開いて歩いてみよハッハッハ~~ で足踏みして、膝曲げてお目めはまっすぐ前だよパッとひと押しすればスーーーーと前に進むTVで見るスケートとは全くちがう現実の氷上と靴のエッジと自分の身体の関係を二人は初めて体験しました。
2009.01.04
コメント(6)
-
第2日
まったくそれは15年ぶりのことでした。元旦に大ママんちに行ってみたら、明日はスケートに行こうとみんなで相談しているではありませんか?この間からフィギュアスケートのグランプリシリーズや全日本をビデオに録画してみてるMの影響を受けて、Wや五女のAもまだ一度もしたことのないスケートに興味津々だったのです。つるつるの氷の上で、どうやってあの細いブレードを使って滑ることができるのかどうか、家族のほかのみんなはカナダで滑っていたというのに私たちだけがしたことがない、ということも納得のいかないことでした。だから、その話を小耳にはさんだAは即「私も行く~~!」と名乗り出ました。ということはもちろんWも行くわけです。大ママちゃんと妹のCちゃんは大喜び、そして広島の兄も行きます。翌朝約束の時間に二人を送って行きながらもちょっとした気がかりが心の中に残っています。このWとAにとっては全く未経験のスケートです。すっかり預けてしまうのはちょっと危険かなぁ・・・スケート場も空いていたらそう心配なことはないけれど、混んでいたらとっても危ない。氷の上という環境にどれぐらいこの子たちが順応するのか、それとも観るとは大違いですぐに嫌になってしまうかもしれない・・・などと考えて、とりあえずついて行って様子を見ることにしました。で、玄関先で「私も付いていくわ。」というと、大ママ「あぁ 良かった!内心心配やったん、大丈夫かなって!あぁ 良かった」そらそうです。大ママもCちゃんも自分自身で楽しむ時間も十分持ちたいのですから・・・。そして私は15年ぶりにリンクサイドに立ちました。この冷たい空気、ブレードが氷上を滑っていく音・・・あぁ 懐かし~~~かつては毎日、間違いなく毎日リンクに通っていたのに・・・6時からの早朝練習、一般営業後の9時からの深夜練習・・・仕方ないけど、今は自分のスケート靴さえない。貸靴で滑るか・・・・・・! 15年ぶりに氷の上に立つということよりも、貸靴で滑るということの方がよほど大きな問題なのです。何しろ私の足はとっても不思議な形をしていて内側のくるぶしのすぐ下にまたくるぶしがあるような足なんです。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・現役時代も何度もオーダーメイドで靴を注文してもきちんと自分の足に合ったスケート靴が出来上がってこなくて、足はずるずるに擦り剥けてとってもかわいそうだった。 ある日友人のお父さんが実は実際にこの注文された靴がどこで作られているのか知っているんです、とお話して下さったことで私はわざわざ作ってくださっている職人さんのおうちまで訪ねていきました。そして私の足を見ていただいたところ、「こんな足をなさっていたんですか?到底想像できていませんでした。ことばでコメントが付いていても石膏の型がついてくるわけではない、ただの足裏の型と周囲の数字だけですから・・・」そうしてじっくりご覧になってから出来上がったスケート靴はぴったりでそのフィット感は素晴らしいものでした。あぁ懐かしい あのスケート靴、ブレードは父がイギリスに行った時苦労して買ってきてくれたWilsonスケートエッジのアイスダンス用のものを付けていた。あの大事な靴もリンク移転の折にどさくさにまぎれてなくなってしまった。まぁいい、今日は取り合えずWとAの安全確保、そして15ぶりを祝って楽しく滑ろう・・・
2009.01.03
コメント(4)
-
今年第一日(2)
教会では初詣と同じように元旦のごミサがあります。「神の母聖マリア」のお祝いの日大天使ガブリエルによってもたらされた「神の子イエスを身ごもり産みますよ」、受胎告知に始まったおとめマリアから聖母マリアへの道はまだまだ続いていきますが、イエスの母としての運命を引き受けるのは並大抵のことではなかった。「今風に言えば、未婚の母であり、貧困家庭であり、さらに死刑囚の母でした」とある神父さまの言葉。確かに「母であること」「父であること」それは子どものすべてを受け入れることから始まります。そこに何があろうと、そして未来に何が待っていようとも大きな覚悟を持って生きること、それが運命づけられている。でも、一旦それを引き受けてしまえば、実はとても大きな喜びがあるのではないかな・・・。成長を目の当たりにしたり、予想もできないような楽しみがあったり、ただそばにいるだけでもありがたく思える瞬間がある。マリア様はいろんな形で親であることの素晴らしさを表して下さっていたのではないか、昔から聖マリアの姿から多くの人はそういうもの学びとっていたのではないかな、などと思いめぐらしました。ひょっとしたら今年は「聖マリア」が私のテーマになるかもしれません。 さてこの日オルガン担当であったKさんは風邪になられて急に来ることができなくなられ、あら困った~となったとき、私の幼馴染でもあるKちゃんがちょうどご実家に帰ってこられていて、ごミサに来て下さった。彼女は三条教会でオルガニストを務めておられるので、本当に急だったのだけれど、「ぜひお願いします」ということになって、彼女がこの日のミサのオルガンを担当して下さった。パイプオルガンを本格的に勉強してこられただけあって、その場の必要に応じて音色もさっと変えられ、きちんと歌をリードされて、斜め後ろからその演奏を見せていただいた私は「さすが~~Kちゃん、ステキ~~!!」 新年早々にこんな素晴らしいオルガン演奏のミサに預からせていただけるなんて、今年は素敵な年の幕開けとなりました。ミサ後、もう1人のオルガン担当のNさんや聖歌隊のメンバーはどんな時にどんな音を使ったらいいのか、そしてどんな音がこのオルガンで出せるのかをKちゃんに教えてもらって、即席のオルガン講座となりました。 Kちゃん本当にありがとう。ステキだったよ~~
2009.01.02
コメント(4)
-
今年第一日
2009年 明けましておめでとうございます新しい年を迎えて気分一新、これからの毎日に新鮮なものを感じるいいチャンスを迎えました。それはとっても嬉しいことです。それはとっても有り難いことです。いつもと違った自分になれる?お陰さまで我が家も家族みんなでこの日を迎えることができました。朝一番に起きた三女Kは急ごしらえでつくったお雑煮をおなかに流し込んで、「では行ってきま~~す」と元旦早々にバイトです。彼女の場合、普通の時は学校とクラブが忙しくてとてもバイトなんてできません。だからこの休み中にできるだけ仕事をして、クラブ活動に必要な資金や自分のお小遣いをねん出するつもりなのです。だからせっかくのお正月だけれど、今日はお昼も夜もKだけがいない形でみんなで食事をしました。8人とはいえそれぞれに大人の大きさになった子どもたち4人と小学生2人に私たち親が一つの食卓を囲むのも狭~~く、取り皿も小さめにして、お重箱4つ5つと並べてぎりぎりです。「ごめん、ごまめ(これは大ママちゃんが作ってくれました)取ってくれる?」「お餅食べる人何人?」「三色牛肉巻き、もう一つ食べても良いかな~??」食事をするにも声を掛け合って、話題もつい掻き消されてしまいそう。それでもお話ししたい人はせっせとお話をするから、それはもうにぎやかな時間ということになります。大ママの家に帰ってきていた広島の兄が手作りクッキーのお土産を持ってここにやってきたかと思うと、2分も経たないうちに今度は群馬の兄が突然「おめでとう!」てやっぱり両手にお土産を持って玄関に到着。思いがけず叔父ちゃん叔父ちゃんの勢ぞろいです。こんなに食べたらあかんやろう、と思うぐらいいっぱい食べて・・・。一年分食べたような気分みんなで祝える元旦を過ごすことができて、良かったそれぞれにお迎えになったこの新しい年が、人々のつながりや自然の中で、たくさんの恵みを生み出し、充実と喜びと感謝の泉となりますように!どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
2009.01.01
コメント(8)
全31件 (31件中 1-31件目)
1