今年になって始めたこの音楽エッセイもいつのまにか90話を迎える事になりました。読者のみなさん、本当にありがとうございました。また来年も同じようなスタイルで続けて参りますのでどうぞ宜しくお願いします。
今年最後のエッセイは、youtubeにアップしました自分自身の演奏、51曲の中から再生回数が特に多かったものの一つをご紹介します。
ラフマニノフ◇ヴォカリーズ
ラフマニノフ(1873-1943 ロシア)はロマン派、チャイコフスキー、リムスキー=コルサコフの影響を受けた作曲家であり、ピアニスト、指揮者の才能も発揮しました。
1912年に作られたこのヴォカリーズは名曲中の名曲、日本人にも人気の高い作品です。調べてみますと様々な背景とこの作品が生まれる経緯に興味が深まりました。
1895年、ラフマニノフはにシンフォニー1番を完成させましたが、2年後にグラズノフ指揮の初演では記録的な大失敗に終わったのです。その後数年間、失意の底にいたのですが、やがて1900年ごろから創作意欲を回復させます。2台ピアノ組曲第2番、ピアノコンチェルト第2番という2つの大作を完成させ、演奏会も大成功を収めます。またグリンカ賞を受賞して作曲家の名声を確立したのです。その後結婚しています。
1909年にスイスの画家ベックリンの作品「死の鳥」から着想を得た交響詩「死の鳥」を作曲、ピアノコンチェルト3番を作曲、自らピアニストとしてマーラー指揮のもと初演しました。
そして本題でもありますが、この頃女流文学者マリエッタ・シャギニャンとの文通をで意見を交わすようになります。きっかけは「Re」というペンネームで彼女がラフマニノフにファンレターを送った事だとか。そしてヴォカリーズの入った歌曲集は1912年に彼女が推薦したそれぞれの詩に作曲したもので「14のロマンス 作品34」または「14の歌曲 作品34」として生まれました。どの曲も当時活躍していたロシアの名歌手に献呈されました。終曲となるこの「ヴォカリーズ」は、ソプラノ歌手アントニーナ・ネジダーノヴァのために書かれた作品なのです。

クラムスコイ 1837-1887 ロシア◇髪をほどいた少女
クラムスコイというと「忘れえぬ女」がとても有名ですがこの作品も目にする方が多いのではないでしょうか。ロシア音楽に通じる切なさ、哀愁、そのような内面的なものがこの少女の表情にも描かれていますね。
ヴァオカリーズとは・・・・・フランス語で歌詞を伴わずに母音のみによって歌う歌唱法を指します。起源は18世紀半ばにさかのぼり、ベラールの曲集「歌の技芸」において、声楽技巧のための練習曲として当時の作曲家「リュリ」や「ラモー」の歌曲に掲載されたのが起こりでした。そのような練習曲は19世紀に飛躍を遂げて、ピアノ伴奏が付けられたりなど、その他「カプリチョ」のような機械的な練習曲にさえ演奏者の音楽をより芸術的に解釈出来るように目論まれたとの事です。
皆さんのご存知の作品ではピアノ曲になってしまいますが・・・ショパン、ラフマニノフ、リストなどの「エチュード」がありますね。エチュード=「練習曲」なのですがどれも音楽的な要素が多分に織り込まれ至難の業、演奏者泣かせです。しかしすべての音楽というものはやはり「歌」が原点ですからどんな難曲でもそこに「歌」が聞こえてこなくては面白くも何ともない、テクニックを披露するだけの無味簡素なものとなってしまうのです。そんなわけで、あ~私の修行はまだまだ続きます。
ヴォカリーズ:ソプラノ編 http://www.youtube.com/watch?v=gERptKVcxTM&feature=related
ヴォカリーズ:フルート&ピアノ編 http://www.youtube.com/watch?v=Y0vKbRVPKAk
ヴォカリーズ:チェロ&ピアノ編 http://www.youtube.com/watch?v=oQ4iVZucKFA
~~~~~~~~~~~~ アルバムご紹介 ~~~~~~~~~~~~
録音スタジオ: ソフィアザールサロン
お問合わせ: k-honma@violet.plala.or.jp
本間 まで
リサイタル・ライブアルバム~Moonlight
2010年10月2日リサイタルのライブ録音 ¥1500
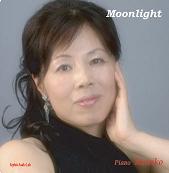
エルガー:愛の挨拶◇メンデルスゾーン:春の歌
ブラームス:間奏曲作品118-2 / カプリチオ
シューベルト:即興曲作品90-3◇バッハ:フランス組曲第6番
シューマン:夕べに / 飛翔◇ベートーベン:ソナタ「Moonlight(月光)」
アンコール
~バッハ:主よ、人の望みのびを
ボーナストラック
~ショパン:ノクターン第5番
-
101話:「ドイツ・リート誕生日」とな… June 12, 2011
-
96話:奇跡的な復活上演 March 1, 2011
-
95話:蝋燭もなく月光のもとで February 20, 2011










