部分的歯髄失活歯の歯髄保存法
nekoさんのリクエストがあったので、通常の歯科の診断では歯髄の保存は不可能とされる症例の歯髄保存を行った症例をアップしてみる。
根管を開拡した時に腐敗臭があったので歯髄壊死と診断したのだが、超音波スケーラのエンドチップを根管内に入れた時に若干の痛みと出血があったので精査してみると歯髄の30〜50%%程は生きていた。
歯髄は細菌感染していて歯髄ポリープ化が進行していたので、標準治療では歯髄は全部除去して根管拡大、根管充填、コアの作成、冠の印象、セットと進むのだが、今回は残っている歯髄(歯髄ポリープ含む)を保存してCRで歯冠をその場で再建して一回で終わることにした。直後から1日分の抗生剤を経口投与したが、これだけでなんの症状もでていない。
世界中の歯科医師は何が起こっているのか全く理解できないだろう。歯科医学の常識から完全に外れているからだが、僕に言わせれは歯科医学の常識の方が100年遅れていると思う。
この治療法が普及すればどういうことが起こるのか?、ちょっと考えるのが怖い。失業する歯医者が世界中で続出しそうだ。従来型の治療法が要らなくなるか、そこまでいかなくともそれらが必要な症例が激減するだろうからだ。
患者は喜ぶだろうが、歯医者の仕事が存続できなくなる可能性は高い。歯医者が一軒も無くなるのは患者も困るだろうから、ある程度存続可能にするにはどの程度の診療報酬に設定すべきか、考えられないことはないが、ここでは提示するのは差し控えたい。流動的な要素が大きいからだ。
安くはならないことは確かだが、インプラント等と比べると器具・材料費は極小なのでその分安くはなるだろう。
まずレントゲン写真だが、根尖の陰影は確認できないが歯根膜腔の拡大は見える。虫歯が歯髄に達しているかどうかもはっきりしない。ギリギリセーフかもしれない。

とりあえず麻酔はせず、軟化象牙質(虫歯)を除去することから始める。痛みがあれば歯髄は生きているということがわかるからだ。




歯冠内部の象牙質は70%失われている。露髄しているがこの段階では大部分は失活しているかもしれないと思われた。ここまで痛みはない。


失活している可能性が高いと考え、エンドチップが入りやすいように冠部歯髄部分を開拡した。

エンドチップを挿入して超音波洗浄してみた。

根管長16mm。通常の根管治療はしないので、根管長にこだわる必要はない。痛みや出血、根管が何本あるかに留意する。


根尖付近で若干の痛みがあり、出血したので部分的に歯髄は生きていることを確認した。ボスミン液で止血して拡大して見てみた。歯髄(ポリープ)が見える。



エアブローで水分を飛ばして、
3MIX+α-TCP精製水練りをエンドチップで1次充填。出血しているが気にしない。

余分な水分と血液は綿球で押さえる。

緊密充填されている必要性は全くない。自然にα-TCPは硬化し根管は閉塞する。
この辺りの機序はまだ分かっていないようだが、阪大の論文がある。


α-TCP50%クエン酸水練りで2次充填。これは数分で硬化するので、この上にCRで辺縁漏洩がないようにカバーする。


CR充填は収縮の影響を抑えるために数回に分けて積層法で。


CRでの歯冠再建が終わったところ


デンタルフロスが通ることを確認して終了。経過観察。
これで咬合性外傷がなければ何年も持つ。
脱離や欠けがあればその都度部分修理する。ボンディングの剥がれがあると隙間が黒色物質(FeS)で汚れるのでよくわかる。これも部分修理する。

ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ダイエット日記
- ダイエット食事日記4216日、こど…
- (2024-06-25 20:47:10)
-
-
-

- うつ病患者の復職前と復職後
- 休職中なのにストレス倍増😥
- (2023-11-14 14:02:27)
-
-
-
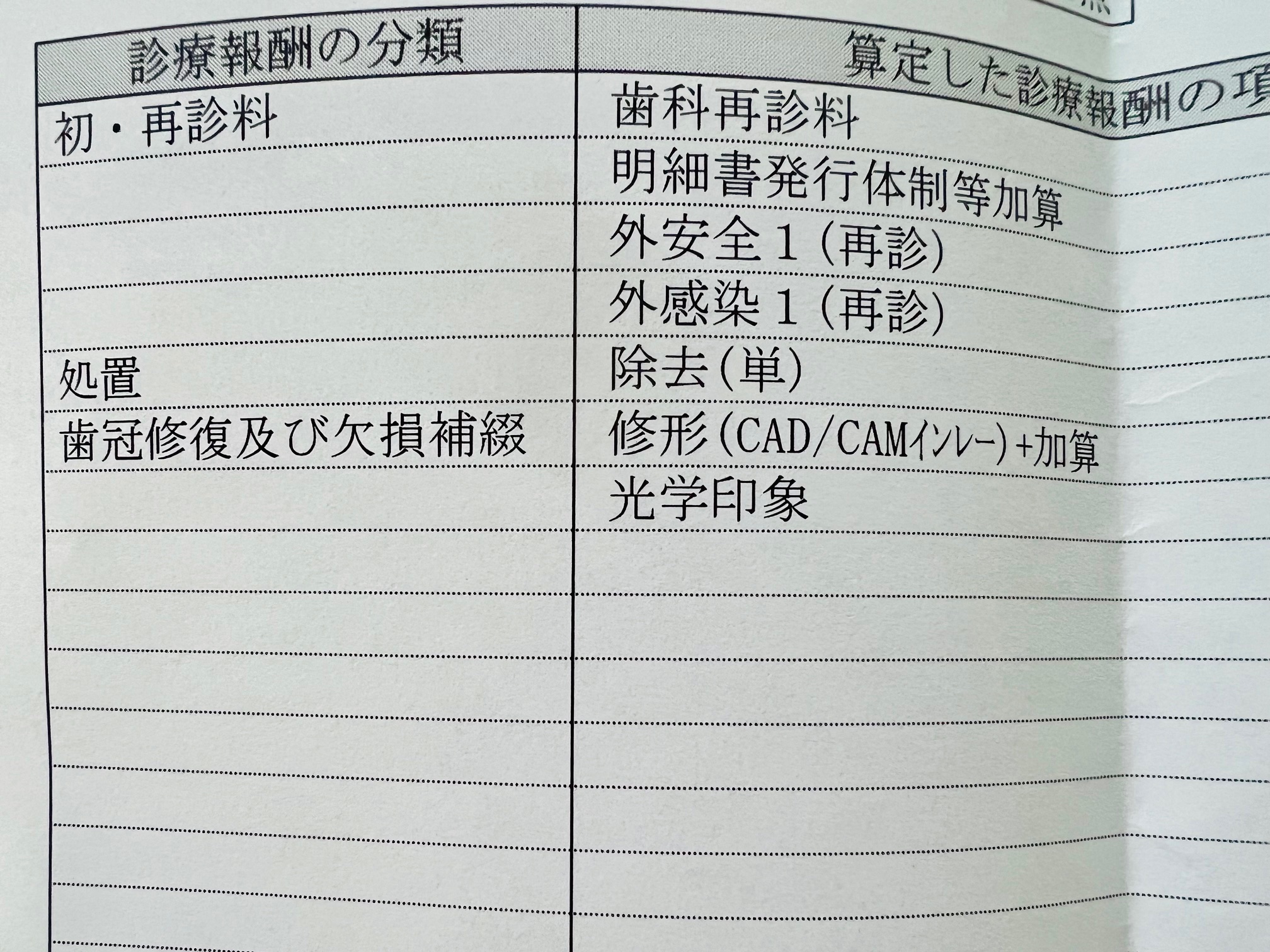
- 歯医者さんや歯について~
- 歯医者で金属のかぶせ物を外し、型を…
- (2024-06-25 20:40:40)
-
© Rakuten Group, Inc.



