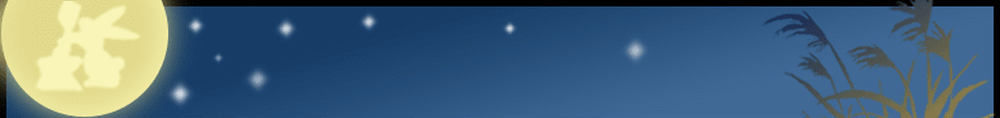PR

まもなく訪れるアミガサタケの季節を前に
きのこポエムは短歌より7音短く、俳句よりは7音多い字数で表現するプチ・ポエムである。和歌、俳句などの伝統詩とは一線を画した定型詩を想定して始めた。しかし、千数百年5・ 7調で定型詩を考えてきた日本人にとっては、口を突いて出る言葉は言うまでもなく、このリズムは言語生活のあらゆる局面に浸透しており、とりわけ和歌、俳句、川柳に馴染んできた者にとってはこの音数律を度外視して思考するのには大変な困難を伴う。
和歌の基本は上の句5・7・5で情景やものに即した描写(客観物)を記述し、下の句7・7でそれに触発された感慨や心の動きを述べる(述志)ことから成り立っている。
これを連歌(31文字を一人の作家が詠んできた詩を上、下に分けて二人の作家が詠む方法)として発展させた当初は、下の句の結論的な部分を上の句を受けて、その印象を咀嚼して、下の句の結論的な部分を上の句同様の情景描写で受けとめ、前者の詠んだ世界の情趣を損なうことなく、しかし、想定外の場の転換をもたらし、絵巻物のようにさまざまなスリリングな情景を詠み込んでいき全体として協同制作の物語を創り上げることを楽しんだのである。
しかし、次第に規則でがんじがらめになって行き形式美のほうに重きが置かれるようになっていったことから、連句・俳諧が生まれた。詩の形式は同じだが、規則を簡略化し内容も庶民レベルの哀歓を盛り込んだ世界を肩肘はらずに表現するようになって大衆的な文芸となったのである。
この俳諧の連句の完成者が松尾芭蕉で蕉風すなわち正風と言われるまでになった。彼の「俳諧は行きて還らぬ心の味わい也」という言葉はその連句の精神を言い表しており、このための俳論が『三冊子』、『去来』などの弟子たちの聞き書きの形で残されている。
短歌、俳句より7音長いか短いだけのきのこポエムは、しかし、試作してみると直ちに分かることだが、短歌の形式の述志の部分が7音と短く、俳句の言い切ることによって余韻を生じさせる効果が出せず、中途半端な感が否めないのだ。写真のワンショットのような表現でもなく、短歌の4コマ漫画のような動画的表現でもない半端な詩型なのだ。
しかし、短歌でも俳句でもないどうしようもない詩型であることは、5・7調などなんのその、全く異なる言語生活を積み上げてきた僕たちの後に続く世代ではもっと面白い展開が期待できるし、僕にとってもこれまでの人生を根こそぎひっくりかえすような事件となりつつあり、とても新鮮だ。この形式で、徐々に奴隷の韻律に馴らされた思考法を根底から変えてしまいたいという思いも加わり、しばらくはこのきのこポエムでの習作、秀作を生み出すことに精出したいと思う。
-
夜の顔不思議な俳句会 2022年05月05日
-
夜の顔不思議な俳句会も132回を迎える 2021年09月01日
-
俳句について 2021年08月01日