PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日、
「絵本」は「見える世界」と「見えない世界」、「自分」と「他の人」、「人間」と「自然」、「言葉」と「言葉が創り出す世界」、「過去」と「未来」をつないでくれます。
と書きましたが、本当はこれは「絵本の力」ではなく「言葉の力」です。
ですから、絵がなくても色々なお話しや物語を語ってあげるだけで、子どもは、五感では触れることが出来ない、繋がることが出来ないものに触れ、繋がることが出来ます。
というか、むしろ絵があることで触れにくくなったり、繋がりにくくなったりします。
耳から入った言葉はそのまま心の中に入ってきますが、絵本ではまず絵を見る事から始まるので、意識が自分の心の中ではなく、外側に向いてしまうからです。
また、絵の印象が心の状態にも大きな影響を与えてしまうので、言葉の力がダイレクトに心に響かなくなってしまいます。
さらに絵本では絵と言葉が一体化しているため、言葉的には同じことが書かれている絵本でも、絵が違っているだけで子どもは異なった物語を体験する事になってしまいます。
以下の三冊は同じ物語が書かれていますが、同じ物語の絵本のようには見えませんよね。

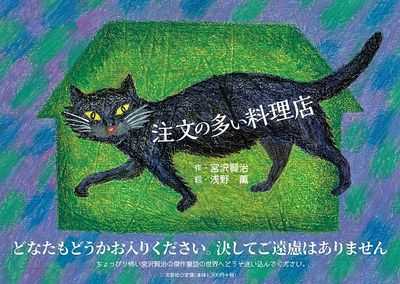
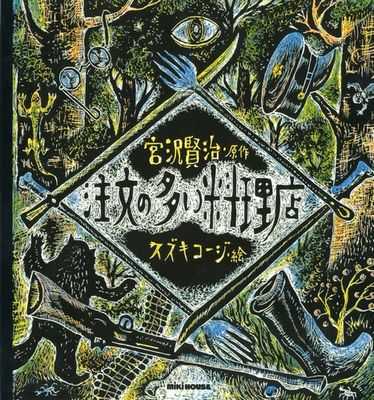
そのため、物語の力そのものを重視するシュタイナー教育では、絵本よりも素話の方を重要視するようです。
でも、絵本を読むのは文字を読める人なら誰にでも出来ます。
あと、絵本には当然のことなら「絵」があるので、同じものを見て、同じイメージを得て、同じ体験を共有しやすいです。
言葉だけの場合、人は同じ言葉を聞いても自分の経験に合わせたイメージで解釈します。「木」という言葉を聞いても、南国で育った子と、北国で育った子とでは異なったイメージで解釈します。
でも、絵本ではそれが一致するのです。
木を見たことがない子でも「木」が分かります。
そのため、絵本をきっかけにして、それを劇や造形などにつなげやすいです。
また、最近の子は色々な体験が不足しているので、言葉だけ聞いても、その言葉をイメージ化することが出来ません。「小川」という言葉を聞かされても「小川」をイメージ出来ない子も多いと思います。そんな時、「小川」が絵に描かれていると、子どもはその小川が出ているお話しに納得できます。
本来、絵本よりも言葉だけの方が子どもの心やからだに働きかける力は大きいのですが、言葉を理解し、イメージ化するだけの言語力と体験がない子にとっては、逆に、絵があることで言葉の理解が進むのです。
絵本が子どもの体験不足を補ってくれるからです。
いわむらかずおさんが書いた「14ひき」のシリーズを読むと、野原で遊んだことがない子でも、野原に興味を持つようになるでしょう。
虫が嫌いな子でも虫に興味を持つようになるかも知れません。
これは、素話にはない絵本だけの働きです。
ただし、絵本などで興味を持ったら、実際に野原に出てネズミたちが見ている世界を探してみて下さい。
絵本にはそういう楽しみ方もあるのです。

14ひきのとんぼいけ (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]

14ひきのあさごはん (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]

14ひきのぴくにっく (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]
「絵本」は「見える世界」と「見えない世界」、「自分」と「他の人」、「人間」と「自然」、「言葉」と「言葉が創り出す世界」、「過去」と「未来」をつないでくれます。
と書きましたが、本当はこれは「絵本の力」ではなく「言葉の力」です。
ですから、絵がなくても色々なお話しや物語を語ってあげるだけで、子どもは、五感では触れることが出来ない、繋がることが出来ないものに触れ、繋がることが出来ます。
というか、むしろ絵があることで触れにくくなったり、繋がりにくくなったりします。
耳から入った言葉はそのまま心の中に入ってきますが、絵本ではまず絵を見る事から始まるので、意識が自分の心の中ではなく、外側に向いてしまうからです。
また、絵の印象が心の状態にも大きな影響を与えてしまうので、言葉の力がダイレクトに心に響かなくなってしまいます。
さらに絵本では絵と言葉が一体化しているため、言葉的には同じことが書かれている絵本でも、絵が違っているだけで子どもは異なった物語を体験する事になってしまいます。
以下の三冊は同じ物語が書かれていますが、同じ物語の絵本のようには見えませんよね。

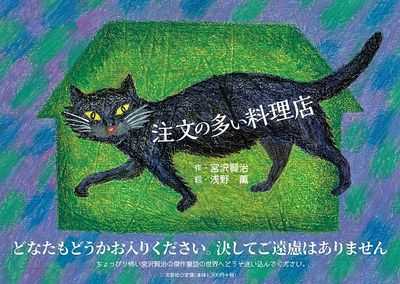
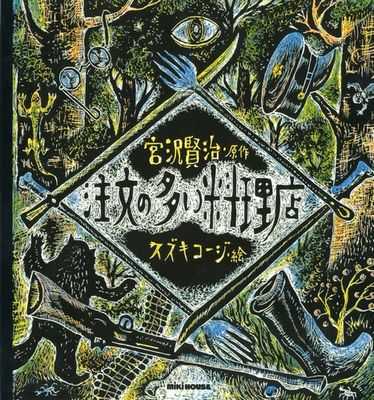
そのため、物語の力そのものを重視するシュタイナー教育では、絵本よりも素話の方を重要視するようです。
でも、絵本を読むのは文字を読める人なら誰にでも出来ます。
あと、絵本には当然のことなら「絵」があるので、同じものを見て、同じイメージを得て、同じ体験を共有しやすいです。
言葉だけの場合、人は同じ言葉を聞いても自分の経験に合わせたイメージで解釈します。「木」という言葉を聞いても、南国で育った子と、北国で育った子とでは異なったイメージで解釈します。
でも、絵本ではそれが一致するのです。
木を見たことがない子でも「木」が分かります。
そのため、絵本をきっかけにして、それを劇や造形などにつなげやすいです。
また、最近の子は色々な体験が不足しているので、言葉だけ聞いても、その言葉をイメージ化することが出来ません。「小川」という言葉を聞かされても「小川」をイメージ出来ない子も多いと思います。そんな時、「小川」が絵に描かれていると、子どもはその小川が出ているお話しに納得できます。
本来、絵本よりも言葉だけの方が子どもの心やからだに働きかける力は大きいのですが、言葉を理解し、イメージ化するだけの言語力と体験がない子にとっては、逆に、絵があることで言葉の理解が進むのです。
絵本が子どもの体験不足を補ってくれるからです。
いわむらかずおさんが書いた「14ひき」のシリーズを読むと、野原で遊んだことがない子でも、野原に興味を持つようになるでしょう。
虫が嫌いな子でも虫に興味を持つようになるかも知れません。
これは、素話にはない絵本だけの働きです。
ただし、絵本などで興味を持ったら、実際に野原に出てネズミたちが見ている世界を探してみて下さい。
絵本にはそういう楽しみ方もあるのです。

14ひきのとんぼいけ (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]

14ひきのあさごはん (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]

14ひきのぴくにっく (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.













