PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
カテゴリ: カテゴリ未分類
最近、発達障害と呼ばれるような症状の子が増えて来ています。
「診断が厳しくなったから増えて来ただけだ」と言う人もいますが、実際に、私の子どもの頃にはあまり見かねなかったような不思議な状態の子が増えて来ているのは事実です。
教室を始めた30年前頃からも確実に増えて来ています。
私の感覚では、その発達障害には二種類あるような気がしています。「先天的なもの」と「後天的なもの」の二種類です。最近急激に増えて来ているのは後天的なものの方です。
先天的なものは昔からありました。そして、先天的な発達障害を持っている子は特別な才能も持っているような気がします。私が知っている子の中にも何人かいます。そういう子は幼い時は「ただ困った子」なんですが、10才を過ぎた頃から他の子にはない才能が目覚め始めます。
ただ、幼い時にその違いを見分けるのは困難です。
今日のブログで扱っているのは後天的な発達障害の子についてです。
発達障害の子でも、いつも困ったことをするわけではありません。自由な遊びの場ではその特異性はあまり表れないからです。好きなことをやっている時にも表れません。
でも、みんなと一緒を求めるような場、ジーッとしていなければいけないような場、感じたり、考えることを求められるような場、やりたくないことをやらされるような場では、発達障害が疑われるような子は異常な行動を取り始めるのです。
私が観察した範囲での「発達障害と呼ばれる子の特徴」は、「みんなと一緒が出来ない」、「出来たとしても強い緊張を感じ苦しくなってしまう」ということです。
当然、「みんなと一緒」を楽しむことも出来ません。というか、そのような子は「みんなと一緒」という感覚自体がよく分からないのはないかと思います。
また、「見て学ぶ」ということも苦手です。「やって学ぶ」事は出来るのですが、「見て学ぶ」のが苦手なんです。だから、「みんなと一緒」が出来ないのです。
一般的な子は、他の子がやっていることを見ているだけで真似をする事が出来ます。みんなが椅子に座っていれば、自分も椅子に座るのです。
みんなが絵を描いていれば自分も絵を描こうとします。実際には描かなくても、「今は絵を描く時間だ」ぐらいは分かります。
なぜなら、それが子どもの成長を支えている基本的な模倣能力だからです。
その能力があるから、わざわざ教えなくても子どもは言葉を覚え、生活の様々な事を覚え、大人から考え方や感じ方を学ぶことが出来るのです。
でも、発達障害と呼ばれるような子は、年相応の模倣能力が育っていないのです。走り回っている子の真似はすぐするのですが、お椅子に座っている子の真似はしないのです。
どうしてそういう状態になってしまっているのかいうことですが、私は「共感能力が育っていないからだ」というように考えています。
その共感能力は3才頃までのお母さんとの関わり合いの中で育ちます。
赤ちゃんはお母さんを模倣することで言葉を覚えます。笑い方や感情表現もお母さんを模倣することで覚えます。
その赤ちゃんの頃の模倣能力は遺伝子の働きの中に組み込まれているものだろうと思います。それは赤ちゃんが持つ様々な原始的な反射能力の一つなのでしょう。ですからこれは世界共通です。
でも、その原始的な模倣能力は成長と共に次第に消えて行きます。そして、後天的な学習によって自分が生まれてきた文化に合わせた新しい模倣能力が育ち始めます。その模倣能力の育ちを支えているのがお母さんとの関わりなんです。
だから、子どもが何を感じて何を模倣するのかは、お母さんが生活している文化の違いによっても違って来ます。お母さんの気質によっても違って来ます。
その時に重要になるのが「共感能力の育ち」なんです。
(本来は)お母さんはいつも赤ちゃんの顔を見て、赤ちゃんの側にいて、赤ちゃんからのメッセージを感じ、そのメッセージに応えようとしています。
赤ちゃんが笑えばお母さんも笑い、赤ちゃんが泣けばお母さんはその泣き声によって赤ちゃんの要求や状態を感じ取り赤ちゃんの要求に応えようとします。
赤ちゃんがムニャムニャ訳の分からないことを言っても、お母さんは「ハイハイ、分かりましたよ」などと応えます。
本来、赤ちゃんとお母さんの関係はこのようなものだったのです。何十万年も昔から、お母さんは赤ちゃんに寄り添っていたのです。
そして、お母さんが赤ちゃんの気持ちにより添っているうちに、赤ちゃんの方もお母さんの共感能力を模倣するようになるのです。
言語能力も、わざわざお母さんが言葉を教えようとしなくても、ただいつも話しかけているだけで育って行きますよね。それと同じように、子どもは他の人から共感される体験を通して、共感する能力を育てているのです。
幼い子どもがお母さんのやっていることを見て模倣することが出来るようになる背景には、そのような形での共感能力の育ちがあるのです。
「一緒が楽しい、おんなじが楽しい」という感覚を支えているのが共感能力なんです。だから、日本で生まれ育った子は日本人の感性を身につけることが出来るのです。
そして今、その共感能力が育っていないと思われる子が多いのです。「お母さんがいつも赤ちゃんの側にいる」という何十万年と続いてきた子育ての根幹的な部分が崩れてきてしまっているからです。
共感能力が育っていない子は平気で他の子が嫌がるようなことをします。今どういう状況なのかを感じることも出来ないため、常に自分のやりたいことだけを優先させます。
意図的にイジワルをしているのでも悪意があるのでもないのです。ただ分からないのです。だから、叱られてもなんで叱られているのかが分かりません。
目を閉じて歩けば色々なものにぶつかりますよね。他の子にケガをさせるかも知れませんが自分自身もケガをするかも知れませんよね。でも、目を閉じているので他の子の泣き声が聞こえても何で泣いているのかが分かりません。自分がケガをしても何でケガをしたのかも分かりません。
何でみんながお椅子に座っているのか、なんでみんなが先生の話を聞いているのかも分かりません。というか、自分の周囲のそういう状態にも気付きません。目には見えていても脳や意識には見えていないのです。でも叱られます。そのため、本人も混乱して苦しんでいるのです。
周囲も大変ですが、本人も苦しんでいるのです。そのことだけは忘れないで下さい。
でも、体験を通してなら理解出来るのです。そこが糸口なんだろうと思います。
ただそれは学校という場では出来ないと思います。「学校は言葉で教える場」であって「体験する場」ではないからです。まただから発達障害の子の状態が顕著に出てしまうのです。
*******************
告知です。
2022年度もやったのですが、続けて欲しいという声もあるので2023年もZoomでの子育て講座をします。
名称は「ゆりかごオンライン」です。
内容は子どものこと、子育ての事、子どもとの遊び方や関わり方、気質のことなどをお話しします。皆さんからの質問にもドンドン答えます。
毎月第三金曜日の10:00~11:30(実際には12:00頃までになってしまいますけど)
参加費 2000円/回
録画もするので後から見ることも出来ます。
参加申し込みやお問い合わせは 「しの」 までお願いします。
以下は私が出した本です。アマゾンで買えます。
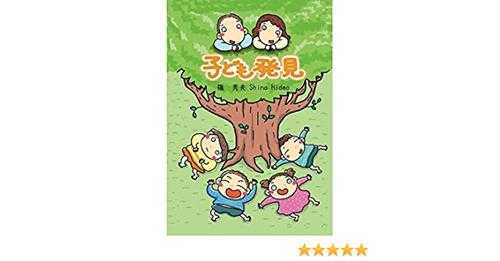
「診断が厳しくなったから増えて来ただけだ」と言う人もいますが、実際に、私の子どもの頃にはあまり見かねなかったような不思議な状態の子が増えて来ているのは事実です。
教室を始めた30年前頃からも確実に増えて来ています。
私の感覚では、その発達障害には二種類あるような気がしています。「先天的なもの」と「後天的なもの」の二種類です。最近急激に増えて来ているのは後天的なものの方です。
先天的なものは昔からありました。そして、先天的な発達障害を持っている子は特別な才能も持っているような気がします。私が知っている子の中にも何人かいます。そういう子は幼い時は「ただ困った子」なんですが、10才を過ぎた頃から他の子にはない才能が目覚め始めます。
ただ、幼い時にその違いを見分けるのは困難です。
今日のブログで扱っているのは後天的な発達障害の子についてです。
発達障害の子でも、いつも困ったことをするわけではありません。自由な遊びの場ではその特異性はあまり表れないからです。好きなことをやっている時にも表れません。
でも、みんなと一緒を求めるような場、ジーッとしていなければいけないような場、感じたり、考えることを求められるような場、やりたくないことをやらされるような場では、発達障害が疑われるような子は異常な行動を取り始めるのです。
私が観察した範囲での「発達障害と呼ばれる子の特徴」は、「みんなと一緒が出来ない」、「出来たとしても強い緊張を感じ苦しくなってしまう」ということです。
当然、「みんなと一緒」を楽しむことも出来ません。というか、そのような子は「みんなと一緒」という感覚自体がよく分からないのはないかと思います。
また、「見て学ぶ」ということも苦手です。「やって学ぶ」事は出来るのですが、「見て学ぶ」のが苦手なんです。だから、「みんなと一緒」が出来ないのです。
一般的な子は、他の子がやっていることを見ているだけで真似をする事が出来ます。みんなが椅子に座っていれば、自分も椅子に座るのです。
みんなが絵を描いていれば自分も絵を描こうとします。実際には描かなくても、「今は絵を描く時間だ」ぐらいは分かります。
なぜなら、それが子どもの成長を支えている基本的な模倣能力だからです。
その能力があるから、わざわざ教えなくても子どもは言葉を覚え、生活の様々な事を覚え、大人から考え方や感じ方を学ぶことが出来るのです。
でも、発達障害と呼ばれるような子は、年相応の模倣能力が育っていないのです。走り回っている子の真似はすぐするのですが、お椅子に座っている子の真似はしないのです。
どうしてそういう状態になってしまっているのかいうことですが、私は「共感能力が育っていないからだ」というように考えています。
その共感能力は3才頃までのお母さんとの関わり合いの中で育ちます。
赤ちゃんはお母さんを模倣することで言葉を覚えます。笑い方や感情表現もお母さんを模倣することで覚えます。
その赤ちゃんの頃の模倣能力は遺伝子の働きの中に組み込まれているものだろうと思います。それは赤ちゃんが持つ様々な原始的な反射能力の一つなのでしょう。ですからこれは世界共通です。
でも、その原始的な模倣能力は成長と共に次第に消えて行きます。そして、後天的な学習によって自分が生まれてきた文化に合わせた新しい模倣能力が育ち始めます。その模倣能力の育ちを支えているのがお母さんとの関わりなんです。
だから、子どもが何を感じて何を模倣するのかは、お母さんが生活している文化の違いによっても違って来ます。お母さんの気質によっても違って来ます。
その時に重要になるのが「共感能力の育ち」なんです。
(本来は)お母さんはいつも赤ちゃんの顔を見て、赤ちゃんの側にいて、赤ちゃんからのメッセージを感じ、そのメッセージに応えようとしています。
赤ちゃんが笑えばお母さんも笑い、赤ちゃんが泣けばお母さんはその泣き声によって赤ちゃんの要求や状態を感じ取り赤ちゃんの要求に応えようとします。
赤ちゃんがムニャムニャ訳の分からないことを言っても、お母さんは「ハイハイ、分かりましたよ」などと応えます。
本来、赤ちゃんとお母さんの関係はこのようなものだったのです。何十万年も昔から、お母さんは赤ちゃんに寄り添っていたのです。
そして、お母さんが赤ちゃんの気持ちにより添っているうちに、赤ちゃんの方もお母さんの共感能力を模倣するようになるのです。
言語能力も、わざわざお母さんが言葉を教えようとしなくても、ただいつも話しかけているだけで育って行きますよね。それと同じように、子どもは他の人から共感される体験を通して、共感する能力を育てているのです。
幼い子どもがお母さんのやっていることを見て模倣することが出来るようになる背景には、そのような形での共感能力の育ちがあるのです。
「一緒が楽しい、おんなじが楽しい」という感覚を支えているのが共感能力なんです。だから、日本で生まれ育った子は日本人の感性を身につけることが出来るのです。
そして今、その共感能力が育っていないと思われる子が多いのです。「お母さんがいつも赤ちゃんの側にいる」という何十万年と続いてきた子育ての根幹的な部分が崩れてきてしまっているからです。
共感能力が育っていない子は平気で他の子が嫌がるようなことをします。今どういう状況なのかを感じることも出来ないため、常に自分のやりたいことだけを優先させます。
意図的にイジワルをしているのでも悪意があるのでもないのです。ただ分からないのです。だから、叱られてもなんで叱られているのかが分かりません。
目を閉じて歩けば色々なものにぶつかりますよね。他の子にケガをさせるかも知れませんが自分自身もケガをするかも知れませんよね。でも、目を閉じているので他の子の泣き声が聞こえても何で泣いているのかが分かりません。自分がケガをしても何でケガをしたのかも分かりません。
何でみんながお椅子に座っているのか、なんでみんなが先生の話を聞いているのかも分かりません。というか、自分の周囲のそういう状態にも気付きません。目には見えていても脳や意識には見えていないのです。でも叱られます。そのため、本人も混乱して苦しんでいるのです。
周囲も大変ですが、本人も苦しんでいるのです。そのことだけは忘れないで下さい。
でも、体験を通してなら理解出来るのです。そこが糸口なんだろうと思います。
ただそれは学校という場では出来ないと思います。「学校は言葉で教える場」であって「体験する場」ではないからです。まただから発達障害の子の状態が顕著に出てしまうのです。
*******************
告知です。
2022年度もやったのですが、続けて欲しいという声もあるので2023年もZoomでの子育て講座をします。
名称は「ゆりかごオンライン」です。
内容は子どものこと、子育ての事、子どもとの遊び方や関わり方、気質のことなどをお話しします。皆さんからの質問にもドンドン答えます。
毎月第三金曜日の10:00~11:30(実際には12:00頃までになってしまいますけど)
参加費 2000円/回
録画もするので後から見ることも出来ます。
参加申し込みやお問い合わせは 「しの」 までお願いします。
以下は私が出した本です。アマゾンで買えます。
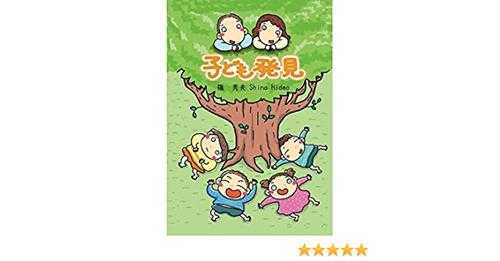
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.













