PR
Freepage List
 New!
SEAL OF CAINさん
New!
SEAL OF CAINさんザ・ノンフィクショ…
 New!
nontitle08さん
New!
nontitle08さん廣田美乃 個展「無…
 ギャラリーMorningさん
ギャラリーMorningさんじゆうたく考【壁】
 シェフ・オオシマさん
シェフ・オオシマさん遍路と農業とFXの… おばか社長さん
Comments
Keyword Search
久しぶりに知的好奇心を刺激された。
書店で手に取ったのは、腰巻の 【いまの若い人たちの詩は、「無」だ。】
白状すれれば、初めに手に取ったときは買わず、それから数日後に買った。吉本隆明ということで、ややこしい本だと読みきれないかも知れないと思い、買う決心にやや時間がかかった。だが、期待を裏切る読み易さであった。それは、東工大での集中講義であり、今の大学生のレベルを考えれば、読み易くて当たり前か・・・?。
しかし、この本は実に面白く、色々気づくことが沢山あった。それらを、少しずつ解き明かしていく。
•第一章 言語芸術論の入口
から、
日本の近代詩はいろいろ詩を書く言葉をつくってきましたが、共通点は何かといえば、比喩というかメタファーです。
比喩(名喩・暗喩)というようなことを考えれば、小説でも詩でも技術的な問題はクリアできるのではないかと、『言語にとって美とはなにか』では書いたように記憶しています。
(だが、) もうひとつ加えなければいけないのではないかと思ったことがあります。それは、日本の詩のかたちが現代あるいは近代の西欧の詩の模倣ないし後追いからはじまったのではないかということです。言い換えれば、日本の詩人たちは頭のどこかで、意識的にか無意識的にか、西欧の詩をモデルにして、それと等価な詩をつくろうとしてきたのではないか。
そこで、「喩」の次にくる技術的な問題は「等価」ということになります。
そして、吉田一穂(よしだいっすい)の「母」を引用しています。
母
あゝ麗はしい距離(ディスタンス)
常に遠のいてゆく風景・・・・・・・
悲しみの彼方、母への
捜り打つ夜半の最弱音(ピアニッシモ)
これが、西欧的という詩、
もうひとつの例として。三好達治の「乳母車」のはじめ
母よ-------
淡くかなしきもののふるなり
私には、三好達治のほうに理解も感情も近い。
色字・太字
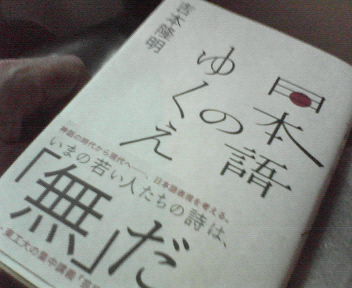
日本語のゆくえ
吉本隆明
光文社
2008年1月30日 初版1刷発行
-
『手仕事の日本』 2015.10.16
-
『ひらがなだいぼうけん』 2015.09.26
-
新折々のうた2 2015.09.25










