PR
Freepage List
 New!
SEAL OF CAINさん
New!
SEAL OF CAINさんザ・ノンフィクショ…
 New!
nontitle08さん
New!
nontitle08さん廣田美乃 個展「無…
 ギャラリーMorningさん
ギャラリーMorningさんじゆうたく考【壁】
 シェフ・オオシマさん
シェフ・オオシマさん遍路と農業とFXの… おばか社長さん
Comments
Keyword Search
ここのところ、ず~っと藤沢周平です。
前回に続き、佐高信の藤沢周平。これも、前の『山本周五郎と藤沢周平』同様に、ある一面で、司馬遼太郎攻撃の本です。
私は、『燃えよ剣』や『歳月』くらいしか司馬遼太郎を読んでおらず、『項羽と劉邦』を上巻の途中で放り投げたのですが、その時は、『項羽と劉邦』を、あまり面白く思わなかったのです。その後、司馬は経済畑の人々にアイドルのように読まれ、それが気に入らず、それ以来、司馬は読んでいません。それに、司馬遼太郎は自分にはあわなかったようです。
さて、『司馬遼太郎と藤沢周平』です。
藤沢は、「信長ぎらい」というエッセイで、《(信長の)こうした殺戮を、戦国という時代のせいにすることは出来ないだろう。信長にしろ、ヒットラーにしろ、ポル・ポトの政府にしろ、無力な者を殺す行為をささえる思想、あるいは使命感といったものを持っていたと思われるところが厄介なところである。権力者にこういう出方をされては、庶民はたまったものではない。》
司馬にはこういう視点はない。「信長と独裁」では、逆に、「信長は、すべてが独創的だった」と礼賛している。
ところが、日本の政財界の将たちは、あたかも自分たちに能力があったからのように錯覚してきた。彼らをその気にさせたのは司馬遼太郎である。 p19.20
元世界銀行副総裁・服部正也は、「戦に勝つのは兵の強さであり、戦に負けるのは将の弱さ」なのに、司馬の作品は「戦に勝つのは将の強さ」と錯覚させると、批判した。p77
司馬(遼太郎)と城山(三郎)はこの松下幸之助観において決定的に違う。司馬は松下を「非常にすぐれた合理主義者」と見ているが、毎朝社歌を歌わせ、伊勢神宮を流れる五十鈴川にフンドシ一つで入らせる「みそぎ研修」をやらせている松下幸之助がどうして合理主義者か。
城山は、本田宗一郎と松下を対比させながら、「本田さんにとっての生涯の悔いは会社に本だと名前をつけたことだ。・・・(松下は)松下と名前がついていることを誇りに思っている」 p78
《私は性格に片ムチョ(意固地)なところがあり、また作家という商売柄、人間の美しさを追いもとめる半面、汚なさも見落とすまいとするので、世間でえらいという人をも簡単には信用しない。それでも時どきえらいな、と思う人に出会うことがある。その人は、冷害の田んぼに立ちつくす老いた農民だったり、子供のときから桶つくりひと筋に生きて来た老職人だったりする。出会う場所は、テレビの場合もあり、新聞記事の場合もある。
彼らは、別格自分や自分の仕事を誇ることもなく、えらんだ仕事を大事にして、黙々と生きてきただけである。だが、それだからといって、そういう生き方が決して容易であったわけでなく、六十年、七十年と生きる間には、山もあり、谷もあったはずである。しかし彼らはその生き方を貫き、貫いたことで何かを得たのだと、私は皺深い農民の顔を写した写真を、つくづくと眺めるのである。
人生を肯定的に受け入れ、それと向き合って時に妥協し、時に真向から対決しながら、その厳しさをしのいで来たから、こういういい顔が出来上がったのである。えらいということはこういうことで、そういう人間こそ、人に尊敬される立場にあるのではないかと、私は思ったりする。実際人が生きる上で肝要なのは、そういうことなのである。こういう質朴で力強い生き方にくらべると、世にえらいと言われる人のえらさは、夾雑物が多すぎるように見える。》 p142これは、『周平独語』の孫引きである。
佐高信と宮部みゆきの対談から、
(宮部)ごく普通の人間がごく普通に生きていても、たとえば世間さまに顔向けできないようなことや、もう自分でも思い出したくないようなことの一つや二つ、ありますよね。それこそがやっぱり人間の傷なんだし、それを大げさに見せはしないけど、生身の人間として、その傷をいっしょに生きてゆく人間を、きちっと書いていくことが大切なんだろうなって、思っているんです。
(宮部)今イヤだなあと思うのは、わりとお手軽に癒やしの小説という言葉が使われていることです。藤沢先生の小説では、人間はそう簡単に癒やされるものではないし、簡単に癒やされるようではいけないんだと。 p252.253
青・太字は引用です。
巾櫛(きんしつ)の妾=執巾櫛(きんしつをとる)というのがある。人の妻となること。
清河八郎の詩にある。これも学んだこと。
この本の底に流れる思想は、派手なものではなく、地味だが確実なもの、そういう人間を認めようというものだ。しかし、それはとても難しい。自分でも、もてはやされたりすれば、それに逆らうだけの勇気が果たしてあるのか自信はない。
だから、藤沢周平に惹かれるのかもしれない。
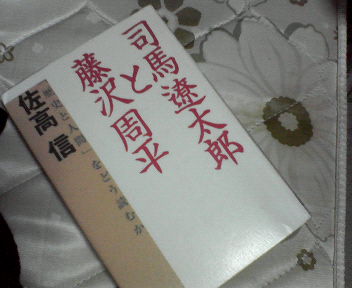
司馬遼太郎と藤沢周平
「歴史と人間」をどう読むか
佐高信
光文社
1999年6月30日 初版1刷発行
1999年7月20日 3刷発行
-
『手仕事の日本』 2015.10.16
-
『ひらがなだいぼうけん』 2015.09.26
-
新折々のうた2 2015.09.25










