PR
Freepage List
 New!
SEAL OF CAINさん
New!
SEAL OF CAINさんザ・ノンフィクショ…
 New!
nontitle08さん
New!
nontitle08さん廣田美乃 個展「無…
 ギャラリーMorningさん
ギャラリーMorningさんじゆうたく考【壁】
 シェフ・オオシマさん
シェフ・オオシマさん遍路と農業とFXの… おばか社長さん
Comments
Keyword Search
落語会の異端児、三遊亭円丈である。
前の『御乱心』以来。
円丈は新作、新作で落語界を生き抜いてきた人。その意気込みや凄まじい。そして、今の落語ブームが円丈の落語とリンクし始めた。もはや、単なる古典落語は受け入れられないようだ。古い言葉遣いや風習、風俗が伝わらないからだ。円丈曰く、昭和50年以降そうなった。江戸の面影が日本全国から消えたと、円丈は言う。
そして、新作への想い・・・、
いつも「次に作る一作こそ、未だかって見たことがないほど、おもしろい新作になるはず・・・」と作り続けている。
これは、チャップリンがネクスト・ワンといっていたことと同じ。
風習・習慣としてあった「江戸」 それから春歌は昭和五十年代まであったが、カラオケが登場して春歌を唄う者はいなくなった。やがて生活習慣の中からも「江戸」が知らない間に消えていった。
「芸は砂の山」 円丈の師匠、六代目三遊亭円生のことば、
「師匠、どうも落語ってネタおろしのときはウケて、二回目のときはあまりウケなかったというのがよくあるんですが、どうしてなんでしょう?」
「そりゃ、芸は砂の山だ!芸というのは砂の山。いつも少しずつ崩れている。私の芸はここまで上がったと思っても、なにもしないとずるずる、ずるずると落ちてくる。(略)ネタおろしのときは緊張して全力でその落語をやっているが、二回目になると、前にやったから少し安心して手を抜く。しかもそれから稽古もしてなきゃ、ウケなくて当然なのだ。芸は砂の山だ。何もしないと芸は下がる」
最後に・・・、
客として見るときのチェックポイント
(1)芸人の目が生きていたか?
(2)持った湯飲み丼の大きさはいつも一定か?
(3)モノの重さや大きさが伝わるか?
の、三項目。
これは、基本ができている噺家かどうかということ。
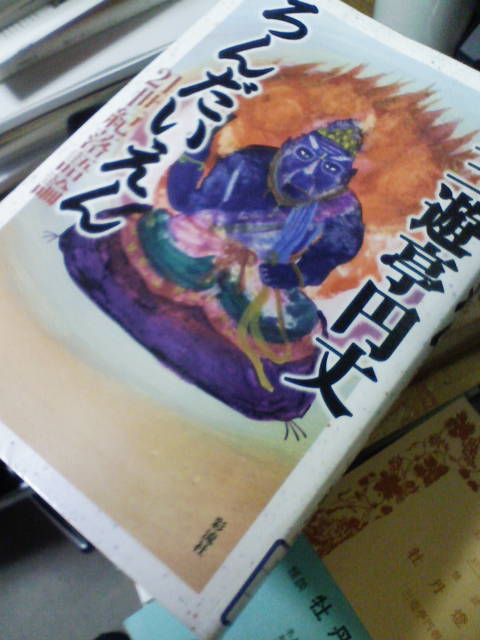
ろんだいえん 21世紀落語論
三遊亭円丈
2009年6月10日 初版第1刷
彩流社
-
『手仕事の日本』 2015.10.16
-
『ひらがなだいぼうけん』 2015.09.26
-
新折々のうた2 2015.09.25










