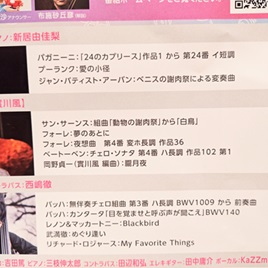3.みどり亀
3.みどり亀子供達との生活は、何時でも何処でも心理劇の場面になった。私は、時々、ストップを掛けたり、子供達が気が付かなかったことを、ほんのちょっと知らせたりするだけで、劇は、子供達の自発性によってどんどん展開していった。時には、私が息を切らすほどのスピードで進んでいくこともある。子供達も私も、毎日新しい体験を増やしていった。
しかし、何時も何時も良い事ばかりと言うわけではない。時に、自分のちょっとした不注意から、子どもを深く傷つけてしまうようなこともある。でも、そういう時、後悔したり、悔やんだり、自信を無くしたりしている私を、子供達が救ってくれるのだ。
私が、一年生を受け持った時驚いた事は、子供達がよく泣くと言う事だった。はじめはびっくりして、「どうしたの、どうしたの。」と一々訳を聞いたり、何処か具合でも悪いんじゃないかと心配したりしていた。でも、大した理由が無くても直ぐ泣くらしいと言う事が分かて来た。「まだ小さいんだな。」子供が泣いても余り関心を示していない振りをしていた。
ところが、つとむ君は、これに輪を掛けた泣き虫なのだ。華奢な体に女の子のように優しい顔をして、大きな目からぽろぽろ涙を流して泣くのだ。見ていると、つとむ君の場合も、大した理由も無しに、何時もめそめそしているようだった。
ある日、私が傍を通りかかると急に泣き始めた。はっきり見ていた訳ではないけれど、どうも、Y君がつとむ君と机の間を通りぬけようとして、ちょっとつとむ君に触ったようだった。押したとか、ぶったとかそう言う感じではなかった。本当に、ちょっとご免という感じで触っただけのように見えた。
私は、「全くこんなことで泣くんだからな・・・」と思いながら、
「どうしたの? どっか痛いの?」
と聞くと、つとむ君は、涙をいっぱい溜めた目で私を見ながら、黙って首を振った。私は、それが余りに可愛かったのでちょっとからかいたくなって、
「どっか、かゆいの?」
と聞いた。つとむ君は、真面目な顔をして、また首を横に振った。何か可笑しくなって、私は、
「へー、痛くもかゆくも無いのに泣いてるの?」
と、びっくりしたように言った。すると、つとむ君は、「??。そう言えば何で泣いてるのかな?ぼく。」と言うようなきょとんとした顔になって、突然涙が止まってしまった。頬っぺたに大きな何だの粒をくっつけたまま、びっくりしたように私を見つめていた。それが余りに純粋な目だったので、「繊細な子なのにからかっちゃいけないな」と思って、
「でも、痛くもかゆくも無くっても、心がさ、何か、こう悲しい時ってあるよね。そう言えば先生もそうくとき、痛くもかゆくも無くても泣くことあるよ。泣くことは悪いことじゃないね。泣いていいんだよ。悲しかったら泣きな。」
と言うと、
「ううん、もういいの。」
と小さな声で言いながら、首を横に振った。
「ああ、もういいの?」
と聞くと、
「うん。」
と小さく言って、大きなコックりをした。
「もういいんじゃあ、涙を拭いて遊んどいで。」
と言って、ティシュペーパ-を差し出した。つとむ君は、じっと私を見つめながら、涙を拭くと、
「じゃあ、ぼく、遊んでくる。」
と言って教室から飛び出していった。
それからと言うもの、私は、つとむ君が泣いているのを見たことが無かった。
私の赴任した小学校は、小規模校だったので、だれかれとなく重要な役が回ってくる。その年、私はまだ教師歴2~3年目、やっと学校にもなれてきたばかりと言うところだった。まだまだ、自分のクラス以外のことに目が届くような余裕も無かったのに、全校の給食費の徴収係と言う恐ろしい役が回って来た。
何時もは、朝教室に行くと子供達に「おはよう!」とか「もう、風邪はいいの?」とか言いながら、子供達の様子を見ながら、その日の教材などに目を通たりする。
でも、その日は、給食費の徴収日だったので、
「はい、お金出して! ○○君、ほらほら、外に出る前に給食費の袋出して!」
と、期限切れの借金を取れたてる高利貸しのお婆さんのように、髪の毛を逆立てて叫んでいた。
私が、事務机の上に徴収名簿を出して集まった袋をチェックしていると、つとむ君が来て、
「先生、おはよう。あっ、お金、ぼく持ってきたよ。」
と言って、袋を机の上に出した。私は、つとむ君の顔も見ないで、
「有り難う。まだの人、出して。出して。」
と繰り返していた。それからまた、
「カズ姫せんせえ・・・。」
と、つとむ君が珍しく私のところに来た。私は、チラッとつとむ君を見ただけで、直ぐに袋と名簿に目を落として、
「なあに?」
と聞いた。つとむ君は、今日は先生高利貸しのお婆さんに変身しているなんてことは少しも知らないで、
「先生、これ可愛いでしょう。」
と言う。私は、また、チラッとつとむ君の方に目をやると、机の上に小さな箱が置いてあって、中で何かがごそごそ動いていた。
「先生これね、みどり亀って言うんだよ。可愛いでしょう。」
「ああ、可愛いね。でも先生、今、ほらお金集めてるでしょ、忙しいから後でゆっくり見せてもらうからさ、さあ早く外に出て遊んでらっしゃい。」
百円玉よりちょっと大き目の小っちゃな濃いグリーンの亀が目に入ったが、私は、今それどころじゃあないと思いながら、つとむ君にはそんな気の無い返事をしていた。
「うん、じゃ、ぼくそうする。」
と言って外に遊びに行ったようだった。
自分のクラスのお金だけでも、集金は嫌だった。それに、子供達の前では金勘定はしたくなかった。だから、子供が帰ってからしたいのだけれど、それでは遅すぎるのだ。銀行は、きっかり三時に閉まるので、各クラスの担任はなるべく早く自分の組の集金を済ませて、係りの先生に持っていかないと、係りの先生は銀行が閉まる前に全校の集計が出来ないのだ。その係りの先生というのが、この新米の私なのだ。
少なくとも、私は授業中だけは金勘定をしたくないと思っていたので、休み時間を待ち構えて、十円玉やら百円玉やらジャラジャラやり始める。でも、1時間目の授業の終りのチャイムと供に、もう集計を終えたお金が届き始めるのだ。
ベテランの先生方にして見れば、どうと言うことは無い至って短時間で済ませられる単なる事務に過ぎないのかもしれないと思いながら、私はと言えば、まだ自分のクラスのお金をジャラジャラ。でも、他のクラスから続々と集計されたお金が届けられるので、休み時間などはそれを受けとって、チェックするだけでまたたく間に過ぎてしまう。また、遅くなると係りの先生に迷惑が掛かるかもしれないという心使いなのだろうか、授業中にもちらほらとお金が届けられる。
結局は、「今日は、帰りの話し合いなんてぐずぐずしていられない、さっさと子供を帰して集計しなければ・・・・。」と、一日中、と言っても、一年生は午前中で授業は終るのだが、お金のことが頭から離れない。いい迷惑なのは子供達だと思ってもどうすることも出来ない。
「そのうちに慣れて、手際よく出来るようになるわよ。」と、先輩の先生は言ってくれる。でも、どんなに手際よくやったって、例え自分のクラスだけだって、一時間目の終わりまでに集金と集計を済まることは不可能だ!つまり、手際よくと言うことは、子供には適当に自習でもさせておいて・・・、と言うことなのか!!!
兎に角、一年生を帰して、もう全校のお金は集まっているのに、自分のクラスの分をやっと終えて全校集計にかかる。上級生がお掃除に来てくれても、
「先生の周りはいいから、後ろの方だけはやくやって帰りなさい・・・。
と、お金お金で、ご苦労様とも言ってやれない。それでも、やっと三時前には集計が終り、急いで銀行に持って行く。全校から集まった十円玉とか百円玉とかがいっぱいあるのだから、結構ながさになる。
銀行から帰ってくると、学年主任の先生が、
「まあ、まあ、ご苦労様。お茶でもどう。大変よね、慣れないと。でも小規模校だから、こう言う役も早くまわって来て、仕事を早く覚えて一人前に成れるのよ。大きな学校なら、何年やってもこう言う役は廻って来ないでしょ。だから、仕事何時になっても余り出来ない先生もいるのよ。」
先輩の先生が労って、振る舞ってくれたお茶とお菓子は美味しかったけれど、私は、
「そうですねぇ。ここで早く仕事が覚えられる私は、幸運ですね。」
と言う気持ちには成れなかった。
「先生の仕事って何かな-。」と思いながら、次ぎの日の準備をして帰った。
そして、翌日。昨日のことなどすっかり忘れて、清々しい気分で子供達に、
「おはよう!」
と声を掛けながら、子供達の様子を見ていた。すると、つとむ君が何時になくニコニコしながら、近づいて来て言った。
「せんせぇ、おはよう。」
「おはよう。つとむ君、赤ちゃん、どう、大きくなった?」
「うん、大きくなったよ。でも、よく泣くんだよ。」
「ふーん。」
自分が、この間まで、めそめそしてた癖になんて思いながら答える。すると、
「せんせぇ、亀は?」
とつとむ君。
「えーっ? 亀?」
「ほら、きのう、ぼくさ、貸してあげたでしょ。せんせぃが亀好きかとお思って、一日貸してあげたでしょう。家に持ってたの?」
私は、目の前が真っ暗になった。
「ああ、そう言えば・・・。つとむ君、朝、亀を見せてくれたっけ・・・。」
私は、しばらく言葉も出なかった。やっとの思いで、
「つとむ君、亀、つとむ君が家に持って帰ったんじゃないの?」
と言うと、
「ううん、だって、ぼく、小っちゃい箱に入れてさ、先生に貸して上げたんだもの。」
と、つとむ君。二人で、集金した事務机の方に行ってみた。空っぽの箱があるだけだった・・・。私は、その空っぽの箱を呆然と眺めているだけだった。やっとの思いで我に返って、
「先生、亀のこと忘れてお金集めてたの。つとむ君が持って帰ったとばかり思って・・・。ごめんなさい・・・。」
私は、深く深く頭を下げて謝った。どんなに謝っても、つとむ君が大切宝物としている亀を、先生に見せて上げようと持って来てくれたのに、お金のことに心を奪われてなくしてしまった。そんなことは許されない。すっかり平静さを失い、おろおろしている私を見て、つとむ君は、冷静に、
「先生がさ、家に持って行かなかったら、亀はどっかにいるかもしれないよ。」
と言って、机の下とか探し始めた。
「そ、その通りだ。何処かにいるかもしれない。いて欲しい!!!!。」
と思って、机の上のノーとや紙の間などを探した。机の引出しも全部見た。まさか、お金と一緒に包んじゃったんじゃないだろうし・・・・。
「いなかったらどうしよう。」
と思うともう居ても立っても居られなかった。血の気が引くのが分かった。そんな思いで探していると、
「あっ!! いた、いた。先生、亀いたよ。」
とつとむ君の声。
「え、ほんと?!」
すぐに、つとむ君の近くに行ってみる。小さな亀が、一匹、入り口のガラス戸の所をのろのろと這っていた。私は、フーと自分から空気が抜けていくような感じがしながら、
「よかったね。よかったね。ほんとによかった。」
と繰り返していた。それ以外に言葉が見つからなかった。つとむ君は、弱々しく歩いている亀を、大切そうに手のひらに乗せて、
「先生、よかったね。」
と言ってくれた。それから、亀を箱の中に入れて机の中にしまった。
その日一日、つとむ君は、亀のことばかり考えていただろう。でも、私には、亀のことはもう言わなかった。
帰りに、箱を大事そうに手のひらに載せて教室を出て行った。
私は、亀のことは、もう何も言わなかったつとむ君に感謝しながら、でもやっぱり心が重かった。いくら亀が見つかったとは言え、つとむ君のあの好意を無残にも踏みにじってしまった自分が情けなかった。いくら、給食費の集金があったとはいえ、教師として許されることではない。私は、自分を責めながら、しょんぼり家に帰って行った。
「私って、だめだな-。でも、今頃、おなかをすかせた亀は、優しいつとむ君から餌を貰って、お中いっぱい食べたかなー。」
と、自己嫌悪に陥る自分を励ましながら・・・・。
次ぎの日の朝、他の子供達とは何事もなかったように、「おはよう。」と挨拶を交わしながら、つとむ君の来るのを待っていた。
元気のない顔で、つとむ君が入ってきた。あんまり寂しそうな様子だったので、私は声を掛けるのをためらった。つとむ君はカバンも置かないで、私の傍に来た。
大きな目を見開いて私を見つめた。それから、
「先生、亀ね、死んだの。ぼくがね、餌をね、やろうとしてものろのろしてて食べなくて、夜になったら動かなかったの。」
と静かに言った。何時も涙をいっぱい溜めていたあの大きなめは、今にも涙がこぼれそうにキラキラしていた。でも、つとむ君は一粒の涙もこぼさなかった。
私は、言葉をなくした。涙がこぼれそうになって、ただ、つとむ君の悲しみにじっと耐えている目を見つめるばかりだった。やっとの思いで、
「ごめんね。つとむ君。」
とぽつんと言った。つとむ君は、
「先生、ぼく、いいの。」
と、小さい声だったけれどはっきり言ってくれた。それから、
「じゃ、ぼく、遊んでくるからね。」
と言って、カバンを置くと、外に走ってい行った。
私は、窓際に行って、雲を見たり空を眺めたりして、こぼれそうになる涙をこらえた。つとむ君だって泣かなかったんだもの・・・。
「痛くもかゆくもないのに泣くの?」なんて偉そうなことを言ってつとむ君をからかった私を、大切な宝物を殺してしまった私を、涙一つ見せないで許してくれたつとむ君。
その日は、一日中、私とつとむ君はそれいじょぷ言葉を交わさなかった。何か言えば、もう、お互いに涙をこらえられないと言うことを知っていたからだ。
そんなに自分を責めても責めきれない思いだったけれど、あのつとむ君が、あの泣き虫のつとむ君が、泣きもしないで「先生、ぼく、いいの。」と言って許してくれたのが、本当に嬉しかった。
次ぎの日、つとむ君は、いつものように元気な声で、
「せんせぇ、おはよう。」
と言って、事務机の椅子に座っていた私に所に来てくれた。そして、
「先生ね、ぼくね、亀のお墓作ってあげたんだよ。ちょっとさ、土をこんな風にね、高くして、木にね『かめのおはか』って書いて立ててあげたの。だからね、先生、亀ももういいんだよ。」
涼しい目で私を見ながらいった。
「有り難う。ここまで言ってもらったら、もう、自信をなくした沈んだ気持ちでいたのでは、つとむ君に済まない。」と思うと、自然に心が晴れてきた。
「そう、亀のお墓作って上げたの。亀喜んだろうね。」
「うん、だから、亀も、もういいんだよ。帰ったらまたお墓を見てみるからね。じゃあ、ぼく、遊んでくる。」
と言って、元気良く教室を飛び出して行った。
これほど、人に許されたことはなかった。
「つとむ君、ありがとう。」
つとむ君は、弱虫で泣いていたんじゃないね。こんなに人を許す事って、強くなければ出来ないものね。
あの時、今にも涙の零れそうな、大きな目でじっとこらえてくれたつとむ君は、もう、優しくたくましい若者になっているだろうな・・・。
完
© Rakuten Group, Inc.