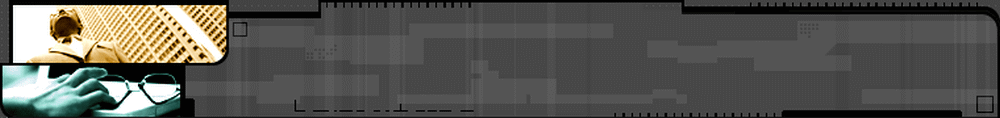PR
X
カレンダー
コメント新着
カテゴリ: カテゴリ未分類
どもー、お久しぶりです(゚ω゚)ノ
死んでたわけじゃありませんよ
ネタのないgdgdした日々を送っていたわけであります
さて…書き出したのはいいものの、何を書いたものか。
随筆についてアツく語っても面白いことは何もないし…
というわけで(どういうわけか)いつもとはちょっと趣向を変えて本業的なことでも書いてみます。
いろいろ間違えてるかも知れませんがそこのところは御愛嬌で。
デンキのはなし ―デンキとヒカリ―
そもそもデンキとは何かといえば、多くの人は直感的に雷や蛍光灯を思い浮かべるかもしれません。しかし厳密にはそれらはデンキと呼ばれるものの引き起こす現象であって、決してデンキそのものが何であるかについて言及できるわけではないのです。
そこで今回は、デンキというエネルギーが「光」という我々にもっとも身近なものに如何にして変わっているかを書いてみようと思います。
デンキが人類によって使われ始めたのはこの一世紀とちょっとの間です。そのデンキが始めて人の手によって光を発したのは白熱電球でした。
電球を発明した(実はアイデアはパクリだそうですが)エジソンはこれで図に乗り、自身の会社を立ち上げデンキをニューヨークの一角で売り始めました。日本で言うところの東京電力みたいなものですが、当時エジソンは直流で配電を行っていたため、配電地域を広げることができませんでした。彼自身交流のほうが有益であることには気づいていたそうですが、自身の発明より優れたものがあることを認めたくなかったのか、発明王の名の下に直流でゴリ押しして直流を売り込んでいたのでしょう。ちなみに交流100Vくらいなら触っても痺れるくらいでたいしたことはないそうですが、直流100Vは冗談抜きで人が死にます。
話がそれましたが、白熱電球について書くと、電球の中身が真空であることが必須条件であること、フィラメントと呼ばれるところで発光していることは割とよく知られていることでしょう。しかしそのフィラメント、なんという金属で作られているか御存知ですか?
フィラメントの多くはタングステンと呼ばれる金属で作られています。タングステンは金属でも比重の大きい金属で、とにかく重いことが特徴とも言えるでしょう。特に重さを生かした部分では、対艦弾や対艦クラスター弾、F1におけるバラストなどに使われています。
金属萌えが分かるようになると非常に愛おしい金属のひとつなのですが、マニアックなところはさておき…
白熱電球の発明は革新的なものだったといわれています。しかしあまりにも光への変換効率が悪く、寿命も短かったためエジソンの後進たちが発明した蛍光灯に取って代わられることになったのです。
蛍光灯は紫外線を蛍光物質に当てて光を得ているので完全な白い色を出すのに相応の時間がかかったそうです。厳密に言うと完全な白ではないのですが。対して白熱電球はスペクトルを見ても、綺麗に可視光線全ての波長が出ています。
正直な話、蛍光灯の原理やどのような電気特性があるかはなんとなくかけそうなのですが、その中身蛍光物質に関しては完全に専門の範囲外なので僕自身よく分かっていません。ただ、水銀を用いて紫外線を出しています。
またしてもムダ知識ですが、切れた蛍光管を見ると、たいていの場合蛍光管の両端が黒く変色しているのが分かるでしょう。これは蛍光管内の水銀がナトリウムと反応することに拠るそうです。
それから年月がたち、科学は進歩しました。その中で生まれてきたものが発光ダイオードです。発光ダイオード、通称LEDはダイオードの一種で、アノードとカソード(簡単に言うと+と-)の間の材料を変えることにより光の色を調節できます。
発光ダイオードといえば、青色発光ダイオードに関する裁判は有名ですよね。でも、なんで発光ダイオードの中で、青色をつくるのが困難だったか。それについてちょっと述べてみます。
さっき、テレビのリモコンもLEDだと書きましたが、テレビのLEDは赤外線です。対して青色の発光ダイオード…。
もうお気づきでしょうか。波長が問題になっていたのです。
前述の通り、アノードとカソードの間の材料を調節することにより、ダイオードの色は変わります。赤外線の波長は長く、可視光線でも赤色から黄色、緑、青を経て紫、そして紫外線とだんだん波長は短くなっていきます。つまり波長が長い材料はわりと早い段階で作れていたのですが、波長を短くして行くにつれて開発に時間がかかってしまいました。
結局日亜化学に対してアノ博士が勝ちましたが、青色発光ダイオードは徳島大学の研究室が長い年月をかけて作ってきた基礎研究があるそうです。アノ博士の功績も重要ですが、長い研究の中で生まれてきたものであることを忘れてはいけないと考えるべきでしょう。
十年前一昔というように、十年前とは驚くほど技術的にかけ離れました。コンピュータが普及し、誰もが多くの情報に触れることができるようになりました。それらの革新を影ながらに支えてきた「光」の存在。今、あなたの頭上を照らしている明かりは、何でしょうか?そして十年後、我々の頭の上を照らしている明かりは同じ技術でしょうか?それは誰にも知りえませんが、未来の技術にワクワクしながら明日を迎えるというのも、なかなかオツなものだと思います。
支離滅裂な文章でしたが、ネットの片隅でデンキと光について考えてみました。ご清聴ありがとうございました。暇だったら続きみたいなのを書くかもしれませんのでそのときはよろしくお願いします。
死んでたわけじゃありませんよ
ネタのないgdgdした日々を送っていたわけであります
さて…書き出したのはいいものの、何を書いたものか。
随筆についてアツく語っても面白いことは何もないし…
というわけで(どういうわけか)いつもとはちょっと趣向を変えて本業的なことでも書いてみます。
いろいろ間違えてるかも知れませんがそこのところは御愛嬌で。
デンキのはなし ―デンキとヒカリ―
そもそもデンキとは何かといえば、多くの人は直感的に雷や蛍光灯を思い浮かべるかもしれません。しかし厳密にはそれらはデンキと呼ばれるものの引き起こす現象であって、決してデンキそのものが何であるかについて言及できるわけではないのです。
そこで今回は、デンキというエネルギーが「光」という我々にもっとも身近なものに如何にして変わっているかを書いてみようと思います。
デンキが人類によって使われ始めたのはこの一世紀とちょっとの間です。そのデンキが始めて人の手によって光を発したのは白熱電球でした。
電球を発明した(実はアイデアはパクリだそうですが)エジソンはこれで図に乗り、自身の会社を立ち上げデンキをニューヨークの一角で売り始めました。日本で言うところの東京電力みたいなものですが、当時エジソンは直流で配電を行っていたため、配電地域を広げることができませんでした。彼自身交流のほうが有益であることには気づいていたそうですが、自身の発明より優れたものがあることを認めたくなかったのか、発明王の名の下に直流でゴリ押しして直流を売り込んでいたのでしょう。ちなみに交流100Vくらいなら触っても痺れるくらいでたいしたことはないそうですが、直流100Vは冗談抜きで人が死にます。
話がそれましたが、白熱電球について書くと、電球の中身が真空であることが必須条件であること、フィラメントと呼ばれるところで発光していることは割とよく知られていることでしょう。しかしそのフィラメント、なんという金属で作られているか御存知ですか?
フィラメントの多くはタングステンと呼ばれる金属で作られています。タングステンは金属でも比重の大きい金属で、とにかく重いことが特徴とも言えるでしょう。特に重さを生かした部分では、対艦弾や対艦クラスター弾、F1におけるバラストなどに使われています。
金属萌えが分かるようになると非常に愛おしい金属のひとつなのですが、マニアックなところはさておき…
白熱電球の発明は革新的なものだったといわれています。しかしあまりにも光への変換効率が悪く、寿命も短かったためエジソンの後進たちが発明した蛍光灯に取って代わられることになったのです。
蛍光灯は紫外線を蛍光物質に当てて光を得ているので完全な白い色を出すのに相応の時間がかかったそうです。厳密に言うと完全な白ではないのですが。対して白熱電球はスペクトルを見ても、綺麗に可視光線全ての波長が出ています。
正直な話、蛍光灯の原理やどのような電気特性があるかはなんとなくかけそうなのですが、その中身蛍光物質に関しては完全に専門の範囲外なので僕自身よく分かっていません。ただ、水銀を用いて紫外線を出しています。
またしてもムダ知識ですが、切れた蛍光管を見ると、たいていの場合蛍光管の両端が黒く変色しているのが分かるでしょう。これは蛍光管内の水銀がナトリウムと反応することに拠るそうです。
それから年月がたち、科学は進歩しました。その中で生まれてきたものが発光ダイオードです。発光ダイオード、通称LEDはダイオードの一種で、アノードとカソード(簡単に言うと+と-)の間の材料を変えることにより光の色を調節できます。
発光ダイオードといえば、青色発光ダイオードに関する裁判は有名ですよね。でも、なんで発光ダイオードの中で、青色をつくるのが困難だったか。それについてちょっと述べてみます。
さっき、テレビのリモコンもLEDだと書きましたが、テレビのLEDは赤外線です。対して青色の発光ダイオード…。
もうお気づきでしょうか。波長が問題になっていたのです。
前述の通り、アノードとカソードの間の材料を調節することにより、ダイオードの色は変わります。赤外線の波長は長く、可視光線でも赤色から黄色、緑、青を経て紫、そして紫外線とだんだん波長は短くなっていきます。つまり波長が長い材料はわりと早い段階で作れていたのですが、波長を短くして行くにつれて開発に時間がかかってしまいました。
結局日亜化学に対してアノ博士が勝ちましたが、青色発光ダイオードは徳島大学の研究室が長い年月をかけて作ってきた基礎研究があるそうです。アノ博士の功績も重要ですが、長い研究の中で生まれてきたものであることを忘れてはいけないと考えるべきでしょう。
十年前一昔というように、十年前とは驚くほど技術的にかけ離れました。コンピュータが普及し、誰もが多くの情報に触れることができるようになりました。それらの革新を影ながらに支えてきた「光」の存在。今、あなたの頭上を照らしている明かりは、何でしょうか?そして十年後、我々の頭の上を照らしている明かりは同じ技術でしょうか?それは誰にも知りえませんが、未来の技術にワクワクしながら明日を迎えるというのも、なかなかオツなものだと思います。
支離滅裂な文章でしたが、ネットの片隅でデンキと光について考えてみました。ご清聴ありがとうございました。暇だったら続きみたいなのを書くかもしれませんのでそのときはよろしくお願いします。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.