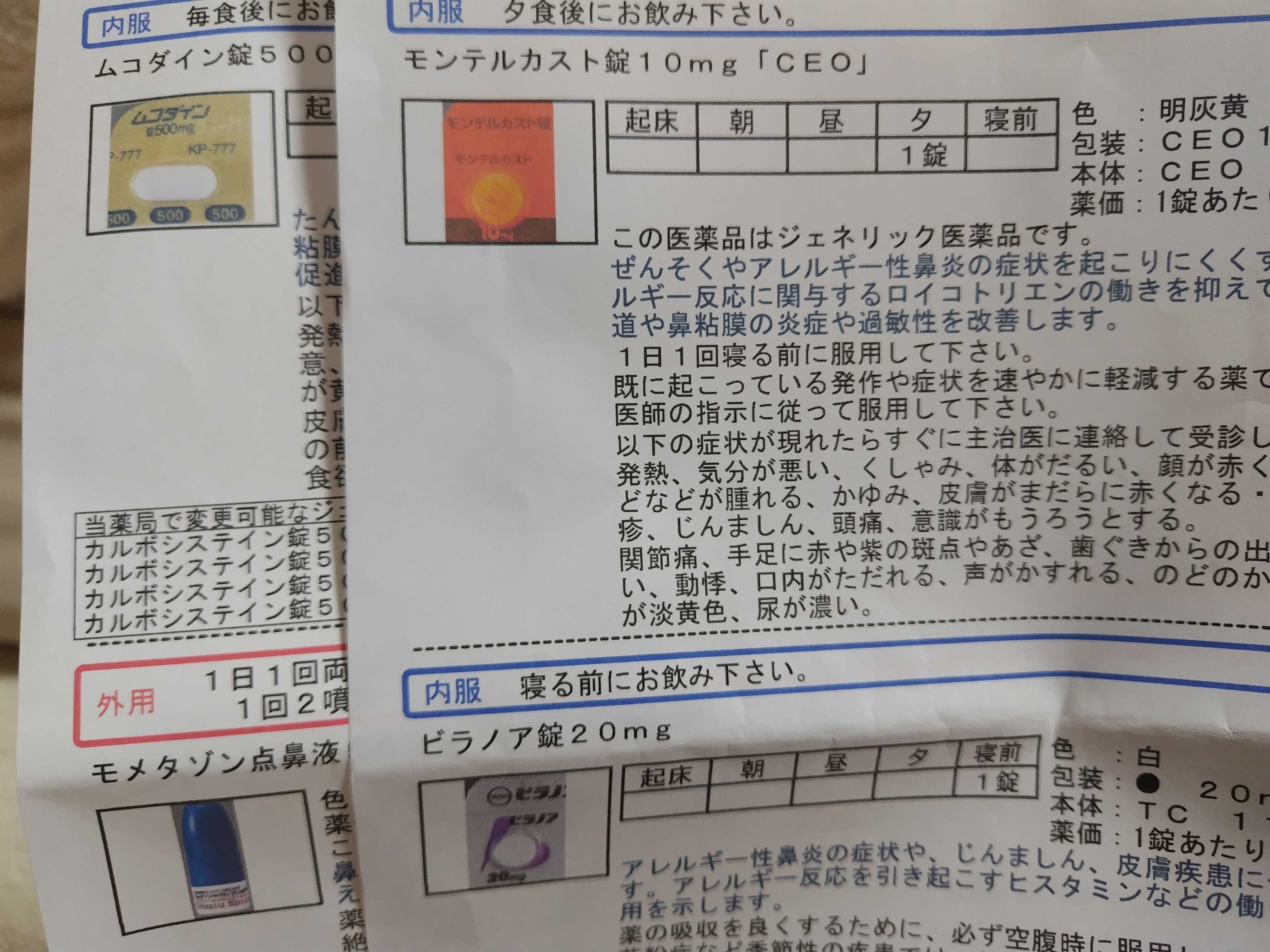2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年01月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
大人だって叫びたい!(笑)
昨日の日記に、感情を思い切り表現するのは気持ちいいよ、という話を書きました。自分でその気持ちよさを体感すると、子供のギャースカも微笑をもって受け止められるようになるわけですが、それはあくまでも結果の話で、子供を受け止めることが目的ではありません。 極論すると、子供のことなんか受け止めなくてもいいというか、自分の内側にたまってる感情と同種の感情を(子供に限らず)相手が表現した場合、それを心の底から気持ちよく受け止めることはまず不可能です。自分が空っぽになってないと、同じ感情が共鳴して心がざわめくからです。 だから、自分のたまってる感情を吐き出すのが先決です。そして親がそれをするためのサポートとして、子供はギャースカわめきたてるんだと思います。親が、自分の内側にどんな感情がたまってるのかが、子供の様子を見ている自分の心の動きでわかるんですから、これはありがたいです。 考えてみてください。 子供の様子になにかプチッと切れることは、普通の親ならよくあることだと思いますが(もちろん我が家も例外ではありません!)、そのときに、子供を受け止めなくちゃ!という理屈が先にたってしまうと、そのプチッときた自分はどうなるんでしょう? 地下のくらーい穴倉に閉じ込められて、折に触れては「外に出せ~」と雄たけびを上げる様子が、なんか目に浮かびますよね(^^; そして地上にいる自分は、地下から微かにもれてくる叫び声が気になって、結局イライラして怒鳴ったり、耳をふさぐためになにか刺激を求めたり。 この状況を変える一番の方策は、やはりその穴倉に閉じ込められた自分を、地上のお日様の下に引っ張り出してやることでしょう。お日様の下で解放感に浸りながら「「腹が立ったぞ~」と叫べばそれでスッキリなんです。それを「怒ったり泣いたりするのは悪いことだ」という“理屈鍵”のついた牢屋に閉じ込めておくもんだから、いつまでもうめき声が聞こえるという次第・・・。 子供の頃からずーっと、こんな自分を心の地下牢にたくさん飼ってませんか? そろそろ解放してあげましょうよ。怒っても泣いても叫んでもいいんです。僕が許します(笑) まあ、大人ですから、子供と違ってTPOを考える必要はあるかもしれませんが、自分が思い切り素の自分でいられる場を作って、ぜひトライしてみてください。枕に怒りをぶつけてもいいし、僕みたいに専用のワークを受けてもいいし、誰かに聞き役になってもらってもいいし。 そうやって理屈抜きで自分の感情を味わうようにしてると、気が付いたら、ごく自然に子供を受け止められるようになってると思います(^o^)b
January 24, 2005
コメント(12)
-
ぜいたくな子供たち ~親もぜいたくしましょう(笑)~
うちの子供たちを見るたびに、ぜいたくなガキどもやのう、と思います。 なにがぜいたくかといって、あやつらは外では極めてまともにしてますが、家では怒りも悲しみもぜーんぶ出したいだけ出していることです(^^; とてもじゃないけど、そんなのは僕が子供の頃には許されなかったな~。こちらが泣いたり喚いたりすると親が不機嫌になるので、これはいけないことなんだとあるとき気づいて、自分の感情にフタをし理屈で自分をなだめすかして、ネガティブな感情に陥らないよう気をつけながら大きくなりました。 だからこそ、自分が親になって子供がかつての自分と同じように、ネガティブな感情を表現しはじめると、なーんかイライラしてそれをやめさせたくなってました。多分、親とおんなじ感情パターンが身に付いてしまってるというのと、子供時代に表現させてもらえなかったつらさがこみあげてきそうでこわいんだと思います(折角フタをして見ないようにしてたのに!)。 これまでいろんなことやって、親との関係がスムーズにいくようになったり、自分が楽になるにつれ、子供の泣いたり喚いたりもだいぶ許せるようになってたんですが、極めつけは11月に広島でやったサムスカラシュッディ。 思いっきり怒ったり泣いたり恐がったりするのがこんなに気持ちいいなんて!というのが、骨身にしみてよくわかったので、目の前で子供がギャースカ言ってもほとんど平気になりました。 ※100%でない部分は、まだ僕の中に出し切れてない何かがあるということです むしろ、子供がそうした感情をどんどん出してくれるのが嬉しくて、気持ちいいだろうなあ~と思いながら、できるだけそれをやめさせないように心を配るようになりました。そうした意味で、子供がギャースカやってる最中に理屈で納得させるのは明らかに逆効果で、そういうのは、子供が落ち着いてて、親と一体感を持って話ができるときにした方が効果的ですね。 少年の凶悪犯罪というのが年々増えてるそうですが、そういう犯罪を犯す少年というのは、いわゆる“いい子”が多いというのはよく聞く話です。親の前ですら感情を上手に表現できないとすれば、他人に心を開くのはなかなか難しいでしょう。逆に、“どんな自分でも親には認めてもらえてる”という感覚を心の深いところで持っていれば、子供はどんどん輝いていくと思ってます。 もし自分の子供や家族、身の回りの人のネガティブな感情が気になって、それをやめさせたいと思う気持ちが出てくるのなら、それは相手の問題ではなくて自分の問題です。まず自分がどこかでそれをやって、例えば怒るってこんなに気持ちいいんだ~っての味わってみることをおすすめします。自分でそれがわかれば、ぜひ相手にも徹底的に怒ってもらって、この気持ちよさを体験させてあげようって思いますって!(笑) それにしてもうちのガキどもは。。。。 息子の方は、小さい頃に親がまだ甚だしく未熟だったせいもあり、つい“いい子”をしてしまって自分の感情を理屈で押さえ込もうとする場合が散見されますが、娘にいたってはもうなんと申しましょうか、親の前では何でもありです(苦笑) イヤなものはイヤ!と言うし、「お父さんもお母さんも嫌い!みんな出てって!」とか、親に取っ組み合いをしかけてくることもしばしばです(^^; それらを、こちらがニコニコしながら見守ってると、子供もやがてスッキリするようで、ぱっとスイッチが切り替わって、いきいきとした表情に変わります。この辺は子育ての醍醐味であるとともに、見守るといういい練習にもなりますね~。また、見守れない自分はどんな自分なのかに気づくチャンスでもあります(^o^)b
January 23, 2005
コメント(7)
-
命とお金・どちらが大事ですか?
[ニュース斜め読み]というカテゴリーを作りました。 最近のニュースについて、気付いたこと・感じたことを書いてみようと思うんですが、どうせ僕のことだからニュースと関係なく脱線していくような気がする、、、(^^; 今日は、サリドマイド薬の復活というニュースについて。 何を隠そう僕も関係者の一人ですが、よくもまあ飽きもせずという気がします。それだけ特殊用途には効能があって、なおかつ副作用の点も解決されてるんでしょう。 このサリドマイドという薬は、日本では僕が生まれてすぐに禁止になったんですが、海外ではもっと前からその危険性が指摘されていた薬です。アメリカでは厳しい審査官がいたおかげで、ついに認可されなかったくらいです(その結果、被害者は0) 日本の場合は、危険だとわかっていながらついついやめられず(金儲けのためばかりではないでしょうが)被害を拡大させてしまったわけで、その点はエイズと同じく薬害に共通のものだと思います。 1986年のチェルノブイリ事故のときも、汚染の可能性のある食物は、各国で輸入禁止措置が取られたわけですが、これだけ食料を輸入している日本の輸入基準は、実に大甘でした。シンガポールなんか100%輸入禁止措置が取られてましたが、日本では当時危ないと言われてたイタリア産デュラム・セモリナ小麦やトルコ産ヘーゼルナッツなどが、平気で店頭にならんでいたのを憶えてます。むしろ引き取り手がなくて国際的に暴落している食べ物を、じゃんじゃん安く輸入してたという話も聞いたことがあります。すごいっすね~。 要は、「これを食べたからガンになった」といった明確な因果関係が証明出来なけりゃこっちのもん♪とばかりに、金儲けのためには些細な危険なんかに構ってられないという社会構造になってるのではないかと思います。 身近なところでは、ちょいと近くのスーパーに行って、安いハムやソーセージやカニかまの裏側を見てみるといいです。発色剤:亜硝酸Na 保存料:ソルビットと書いてあると思います。最近は、どぎつい色の食品は敬遠されるので、発色剤の使用は減ってきましたが、それでも安いものにはよくこの両方入ってます。 これら2つは、単体だと無害なんですが合わさると発ガン性を示すんですね。僕がそういうことに関心を持ち始めて20年以上経ちますが、いまだにやってることに驚きます(^^; たとえこのハムを食べてガンになったとしても、ハムのせいだ!と証明するのは不可能だ、というのおわかりでしょうか。。。 食品添加物なんて、明らかに売る側の都合に過ぎないわけで、買う側としてはそんなもん入ってない方がいいわけです。ちゃんとしたものを作るとどうしても高くなるので、添加物入れて安く作るというのは、メーカーとしては仕方ないことなのかもしれませんが、それで消費者を危険にさらすとすれば本末転倒です。何のための誰のための食品なのか、と思ってしまいます。 ちなみに、日本は世界で最も多くの食品添加物が認可されてる国だそうです・・・・賢くなろう、消費者!(笑) 個人個人に聞けば、100人が100人、全員がお金より命が大事と答えるのに、どうして社会あるいは企業としてみると、命よりお金になってしまうんでしょうね。。。 それはおそらく、一部の企業幹部や政治家のせいにしてしまえば済む問題ではなくて、僕らが何に喜びを見出し、何を求め、どう行動しているかという僕らの価値観やライフスタイル全般を見直す話になると思ってます。 本当に、僕らはお金より命が大事と思ってるんでしょうか? お金については、営利文化と非営利文化と題して考察したことがありますが、またもうちょっと突っ込んで考えてみようかと思いました。なんかまとまったら書きますね。
January 21, 2005
コメント(0)
-
風邪の季節に、ある漫画の大胆な試み(解熱剤とインフルエンザの関係)
かつて僕の少年時代に「巨人の星」「タイガーマスク」「あしたのジョー」などがキラ星のごとく連載されてた少年マガジンという雑誌があります。 コンビニで手にとった少年マガジンの、たまたま見た「クニミツの政(まつり)」という漫画が、大胆にも薬害を取り上げてました。先週号が解熱剤の話で、今週号がそれから発展してインフルエンザの予防接種の話。 我が家はどちらも全く無縁で、予防接種は全く受けさせてないし、子供に解熱剤なんか飲ませたことないので気楽に読めましたが、ごく普通に子育てしてる家庭は、結構ショックかもしれないですね~。 多分、子供が熱を出す-->結構高く上がる-->ヘレン・ケラーという印象を持ってる人が多くって、脳に異常をきたさないようにと、早目に解熱剤を飲ませてる家庭が多いのではないかと思います。 僕も知りませんでしたが、41度以下の熱で脳症を引き起こすことはないそうです。たったこれだけの情報でも、かなり気楽に子育てできると思うんですが、それが一般化してないところを見ると、何かしら隠された意図があるのではと思いたくなりますね。 そもそも熱というのは、ウィルスを殺したり体内にたまった毒素を燃やすために、自然治癒力が働いた結果として起きてる現象ですので、それを抑える行為というのは、病気を長引かせるだけです。 だから、我が家では熱の時は自然治癒力を高めるために体を暖めてやるし、ホメオパシー治療でも熱を出しきるための薬(レメディ)なんかが用意されてます。それが普通のお医者さんに行くと、「暖めると熱があがるので気をつけてください」なんていう人もいるみたいでビックリです(^^; 繰り返しますが、「熱があがること=悪いこと」ではありません。むしろ体のエネルギーが強い人ほど(例えば子供)高い熱が出ます。 その漫画の方では、解熱剤の副作用の問題が大きく取り上げられてました。本当は解熱剤の副作用によるものなのに、「インフルエンザ脳症」という名前をつけることにより、その責任の所在を曖昧にしてるという話です。 こんな名前をつけてるのは日本だけで、しかも解熱剤の副作用として重い脳症になる可能性があることをこっそり書いておきながら、解熱剤とインフルエンザ脳症の因果関係は否定するという、まるで初期の薬害エイズのような状況になってるのがよくわかりました。 しかもこのインフルエンザ脳症というネーミングには、もうひとつ意味があって、このネーミングによりインフルエンザの恐怖を煽り立てるのに大成功したんですね。その結果、予防接種の接種数が飛躍的に伸びてる様子がグラフで示されてました。 このネーミングが登場するまでは、インフルエンザの予防接種には効果がないということが、あちこちの疫学的調査で明らかにされたり、副作用の被害が相次いだりして、1994年には30万人まで落ち込んでいたのに、今や2000万人を目指そうかという勢いなんだそうです(現在750万人)。 最近、研修でビジネスモデルの勉強をしていますが、このビジネスモデルは見事ですね~(^^; 解熱剤の問題を隠蔽できる上に、インフルエンザのワクチンも爆発的に売り出せるわけですから。 結局のところ、医療も産業なんだなあと思いますね。 産業となればお金を儲けないと成り立たないわけで、そうすると必ずどこかで「命とお金どちらを取りますか?」というボーダーラインが出てきます。そして、日本の場合は基本的にエコノミック・アニマルで、残念ながらお金の方を選択している場合が多いと感じてます(エイズを思い出してみましょう)。 ある力のある産業の発展を阻害するような問題は、よほど社会的に大きな問題にならない限り、黙殺されるんですね。それもたいてい官民一体となって、陰湿なまでの隠蔽工作が行われます。この辺は、農業問題でも環境問題でも何でもいいから突っ込んで勉強してみるとすぐにわかります。 この漫画は、ある医師にインタビューした内容を、編集部が大胆にもそのまま載せているわけですが、そんな勇気のある“危ない”医者は誰だろうと思ったら、慶応の近藤誠氏でした。 覚えてますか?『患者よ、ガンと闘うな』の著者です。 あの本も、ガン治療の実態を描いていてなかなか興味深く読みましたが、抗がん剤の認定プロセスって何ていい加減なんだろうと思いました。だって、ちょっとでもガン細胞が小さくなったら、もう効果あり!として認定されるんですよ。それが一時しのぎなのにも関わらず。 それにしてもこの近藤先生、こんなことしゃべって、医局の中で村八分にされるんじゃなかろうかと、他人事ながら心配してしまいました。もう慣れっこなのかもしれませんが(^^; まあ、興味がある人は、話の種に漫画でも読んでもみてくださいな。 別に、解熱剤の副作用に怯えなさいといってるわけではなくて、むしろそんなもんは、まず大丈夫だと思ってて、それよりも、僕らが当たり前と思わされている事柄が、実は誰かの利益のために作られたものだというケースがよくあることを知ることの方が大事だと思ってます。 どこかの新興宗教やカルト教団の話を聞いて、なんでこんな妙な教組の言うことを信じてるんだろう、ばっかじゃないの、と思うことがよくあると思いますが、実は僕らも実態はあまり変わらないという冴えないお話のひとつです(笑) 子供なんて39度の熱があっても、どうかすると真っ赤な顔してはしゃぎまわって遊んでます。自分の感性の声をちゃんと聞いていれば、「おいおい、おとなしゅう寝とかんかい!」と言いながらも、まあこれだけ遊べりゃ大丈夫やろ、と安心して見守れるだろうと思うんですね。解熱剤も抗生剤も必要のないときはいっぱいあります。 試されてるのは、ぼくらの感性であり、直感であり、そして日頃の生活習慣だと思います。
January 20, 2005
コメント(7)
-
やられました・・・
今までさんざん心のゴミ掃除をしてきましたが、そのゴミ掃除をしようと思ってる自分自身がゴミだったとは、、、。ある程度までは自力でもゴミが減らせるんですが、「自分で何とかしよう」「自分でなんとかできる」と思ってる自分がいる限り、永久にゴミは0にはならないことをあらためて思い知りました。それにしても、いい感じ・・・v(^o^)v
January 16, 2005
コメント(10)
-
苦楽を分けないで
この前の『古武術からの発想』(甲野善紀著)にこういうことが書いてありました。少々長いですが引用します。 とにかく子供のときに、「遊びは遊び、勉強は勉強でケジメをつけよう」なんてつまらないことを言うから、勉強が苦役になってしまうのだと思います。 体育をやり音楽をやり、そのなかで生活に密着した算数や社会を教えてゆけば、「僕は算数が苦手だ」という子もずっと減ると思いますし、体育を通して楽しさや苦しさを体感すれば人への思いやりが芽生え、哲学や倫理の基礎となるものの見方、考え方も養われると思います。 子供に苦手意識を植えつけてしまうというのは、早くから専門分化させてしまうからで、全体のなかで他との関連性をもたせ“たとえ”を数多く駆使して教えれば、今よりもずっと子供たちは積極的に喜んで学ぶようになると思います。 シュタイナー教育では、踊りと詩と音楽と算数を混ぜ合わせたようなオイリュトミーという不思議な科目がありますが、↑こういう考えを読むと、なるほどなあと思いますね。 良い・悪いもそうですが、僕らは何かにつけ苦と楽を分けてしまう傾向にあるようです。 家庭生活は楽、会社生活は苦(逆もあり!)、ママさんテニスは楽・家事は苦、DINKSは楽・子育ては苦、フリーターは楽・正社員は苦、○○さんとつのきあうのは楽・××さんとは苦、おもちゃを広げるのは楽・片付けるのは苦、時間とお金がたくさんあるのは楽・少ないのは苦・・・・例を挙げればそれこそ無数にあるでしょう。僕らは特に意識はしなくとも、一瞬一瞬そうやって、苦と楽を判断しながら日々過ごしてると思いませんか? ぜーんぶ楽なことばっかりにならないかなと思いつつも、そうは問屋が卸さないのが人生さ♪などとうそぶいて、苦の多さにグチをこぼしてるのが、我らが庶民の姿です。(それはそれで人間くさくって僕は好きですが、、、笑) では、苦はどこから来るのかと考えたら、苦と楽を分けた時点で苦が発生しているというのがわかりますか? つまり苦と楽を分けているうちは、永久に「楽100%・苦0%」という状態はやってきません。 しかも、楽を味わってるときは、そのうち苦がやってくるんじゃないかと不安におびえてるし、苦を味わってるときは、なんとかそれから逃れようとして、実は苦そのものを味わっていません。これはとても勿体無いことです。 そこで、苦と楽を分けずに目の前の出来事を素直に受け止めてみてはと思うのです。 例えば「手間がかかる」ということと「それは苦である」ということは別の次元の話なんです。事実と評価(印象)といってもいいでしょう。 「手間がかかるなあ」という事実の確認だけでとどめておいて、それが苦か楽かという評価を保留するんです。そうすることで、「○○は苦である」という自分の思い込みやこびりついた印象に支配されるのをある程度防ぐことができます。 そしてその目で、あらためて目の前の現実を見たときに、今までは苦とばかり思ってたのに実はこんな面白さがあったなんて、という発見がひとつでもあればしめたもんです。 持っていてもちっとも楽しくない印象は、なにかにつけさっさと捨てたほうが人生楽しくなります。僕らは、印象の集大成を現実だと思ってるわけですから。
January 11, 2005
コメント(0)
-
冬の風物詩の異変
この3連休はいかがお過ごしだったでしょうか? 僕は土曜日が会社の研修&夜はかみさんとデート、昨日が実家、そして今日は家族4人で、寒風吹きすさぶ中を福岡市中心部の大濠公園までサイクリングしました。 大人でも往復1時間かかる道のりを、6歳の娘もたくましく自転車をこいでました。この季節の大濠公園は、ユリカモメ(都鳥)が渡ってきてて、彼らと遊ぶのが我が家の冬の風物詩なんです。 あのユリカモメという鳥は、目と飛行性能が抜群で、えびせんやらポンポン菓子を放り投げてやると、素晴らしいタイミングでキャッチします。急上昇、急降下は元よりホバリングまでやります。その様子が見事で、子供たちも毎年楽しみにしてるんです。 ところが、今年は異変がありました。 これまでは決して人の手の届くところまでは近寄ってこなかったのに、そんなことお構いなしに人に近づいてきて、とにかく先を争ってエサを奪おうとします。僕の手からでも直接食べるし、なんと僕の頭にも止まりました(^^; 単に人に慣れてるとかそんな感じではなくて、ユリカモメ(そしてハトも)が切羽詰って殺気立ってるんです。 昨年はクマもエサがなくて暴れたりしてましたが、ユリカモメのエサも少なくなってるのかなあと思いました。こうした生き物たちが、なんだか人類に警告してくれてるように感じるのは、僕だけでしょうか、、、。
January 10, 2005
コメント(2)
-
『古武術からの発想』
武術とは全く縁のない卓球部出身の僕にしては珍しい本を読みました。 『古武術からの発想』(甲野善紀/PHP文庫) 高校の卓球部の先輩が、OB会の度にこの甲野義紀さんの話をされるので、気になってはいたんですが、先日宴会の時間にまだ間があった時にふと入った小さな本屋さんで、偶然見つけたのがこの本です。こうのよしのり、ってこういう字だったのか、とそのとき初めて知りました。 この高校の先輩は福岡近郊の某市役所に勤めてますが、その同僚の方で、10何代目かの宮本武蔵という方がおられたそうです。もちろん本名は別で、直系の子孫というわけでもありませんが、その剣法の型を継承してた方です。その方があるとき「こんな型だけ習得しても実戦では使い物にならない」と、仕事もやめて飛び込んだのが、この甲野さんの武術稽古研究会。 それ以来、僕の先輩もこの甲野さんのことに関心を持ち、自分の卓球の腕を上げるためにも、また後進の育成のためにも、甲野さんが研究している古武術の動きを取り入れているといった次第です。 実は、巨人の桑田投手が何年か前にもうダメかと言われたときに再起した背景に、この甲野さんのところで学んだ古武術の動きがあったそうです。最近では、アテネオリンピック陸上代表の末続選手なんかも“ナンバ走法”を取り入れてるといって有名になったとか(テレビと縁の薄い僕は知りませんでしたが)。ひょっとしたらスポーツ界では、今やメジャーな人なんじゃないかと思います。 それで、今回はじめて僕はこの本を読んで甲野さんの考え方に触れ、「きたきたーっ」という感じがしております。共感する部分、目からウロコの部分が満載です。 とにもかくにも、現代人と古人とは、体の動きの“質”が違うんだそうです。 どこかを支点にしてワイパーのように動かしたり、体のどこかをひねるというのは、野球でもサッカーでもテニスでも(武道も含めて)現代スポーツ共通のものですが、実はそういう動きは、とても脆くて無駄が多く、しかも体のどこかに負担をかけやすいというのが、甲野さんの大きな発見です。過去の武術の達人というのは、決してそういう体の使い方をしてなくて、体のどこにも支点を作らず、力をいれて踏ん張るというより体を浮かす感じで、静かに優雅に動いてるようで、それでいて速く力強い、どうもそんな感じのようです。 この甲野さんは、当然ながらサッカーもバスケもド素人ですが、この甲野さんがボールを持つと、プロの選手でもやすやすと抜かれるんだそうです。それぐらい常識を超えた動きになるらしいです。かっこいいなあと思いますね(笑) 一番驚いたのは、江戸時代までの日本人は、現代人のように手と足を互い違いに(右手-左足という具合)動かすような歩き方はしていなかったということ。僕は初めて聞いた言葉でしたが、ナンバ歩きといって右手と右足が同時に出る歩き方で、腰をひねらないようにしてたそうです。実はこの方が無駄がなく疲れにくいので、例えば飛脚なんかは、ナンバ走りで1日200kmを走りぬいたらしい。 立つこと、歩くこと・・・僕らが当たり前のようにやってる作業も、実は当たり前ではなくて、見直す余地は十分にあって、それによっていくらでも自分を変えることができるんだというのが、一番の収穫でした。とりあえず昨日から、歩くときに気をつけてナンバ歩きをやってますが、まだ慣れませんね(^^; その他にも、この本からお伝えしたい話はたくさんあるんですが、明日からの会社の研修のために、今日はもう寝ます。また今度書きますね。
January 6, 2005
コメント(8)
-
神聖にして新生なる初詣
さて、朝から飲んだくれていられるのも、いよいよ今日まで。名残惜しいですな~(笑) 昨日は、家族で初詣に出かけました。 うちはいつも、広々としていてハトと遊べる護国神社と、筑前一の宮・住吉神社に行くことにしています。さらに今年は、割と近所の高宮八幡にもお参りしたので、無事に三社参りとなりました。昨日は珍しく住吉さんがいっぱいで、お参りするのに行列ができてましたね~。 神社の参道というのは、実は産道と同じで、お宮さんが子宮で、鳥居は女性器を象徴してるんだそうです。つまり僕らは、神社にお参りするたびに、新たな誕生の瞬間を再体験していることになります。そう考えると、もっと丁寧に心を込めてお参りしようと思いますね。 今年初詣に行かれた方々は、今年はどんな人間に生まれ変わりますか? 古い自分を持ち続けるのも構いませんが、新しい自分にチャレンジするのも一興です。新しく生まれ変わったんですから、どんな自分になるのも全くの自由です(^^)v ※先月行った味噌作りの記事をUPしました。
January 3, 2005
コメント(6)
-
おめでとうございます
けんパパ@着物で酔っ払いです。 あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いします。 今日も雪が降るかと思いきや、なんだか陽がさしてきました。 いや~、のんびりといい正月ですね~。 何の心配も何の不安もなく、ただ喜びの中でお節の味に舌鼓を打ち、きゅーっと飲んだお酒がしみわたる感じに浸っております。ありがたいことです。 毎年正月には、米鶴酒蔵から純米大吟醸を2升取るんですが、今年の酒は絶品でした。毎年微妙に味が違うところがなんかいいですよね。実は大学の卓球部の後輩(♀)の実家で300年続く酒蔵なんですが、米作りからやってるちゃんとした酒蔵で、いい仕事をしてます。皆様ご贔屓の程よろしく(^o^)丿 では今から子供たちと凧揚げに行ってきます。ヒック(*^o^*)
January 1, 2005
コメント(2)
全10件 (10件中 1-10件目)
1